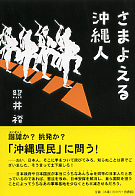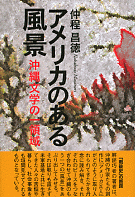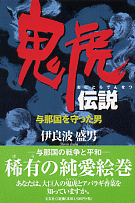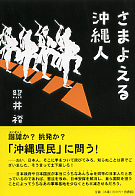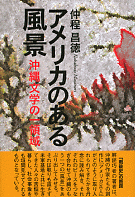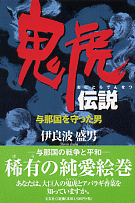|
「うりずん戦記」 上江洲安克 著 琉球新報社 1,200円+税
2008年12月26日 第1刷発行
戦後60年以上もすぎて、生活の場から沖縄戦が年々消えて無くなってゆくような気がする。外見上、沖縄は豊かになり、発展していく中で戦争の爪跡が消えていくのは当然のことだが、何故か、寂しいような、空しいような気がする。――そんな想いを持って書かれた詩集。
著者は昭和33年生まれ。なので、著者の知っている沖縄戦は、大人たちから聞いた話や、テレビで見た話、本や新聞で読んだ追体験でしかありません。
そうは言っても、彼が子供の頃は、生活の場に沖縄戦の残骸が生々しく溢れていたことでしょう。
軍靴やガスマスクや医療器具の散乱した防空壕。巨大で不気味なトーチカ。石垣やコンクリート塀に残る生々しい弾痕。家の周りや畑からは不発弾や弾片がごろごろ出てきて、子どもだった彼らはそれをオモチャにして遊び、小遣い稼ぎの材料にしたことでしょう。
しかし、詩というものはむずかしい。鑑賞力が必要です。
文章ならば、文章力で説明すればいいし、短歌ならば、心境を言葉の持つ力強さに乗せて絵を描くように表現すればいい。ですが、詩は、そのどっちつかずのようなところがあって、作者によって表現形態に幅があるような気がします。それをどう理解するか。そのあたりが難しいと思う。
自分にはこれらの詩を解説する能力がないので、掲載されたものの中から一例を示して皆さんの判断に委ねることにしましょう。いずれの作品にも、最後に一句、入ります。
藷 (いも)
悲しき背中のPW
勝者の令に起されて
勝者の令に働きて
掘る藷すべて超え太り
満々まんと地を充たす
収穫すくなき痩せた地の
めずらしき一時の大盤振る舞い
白骨の うえに肥えたり 太き藷 注:PW = Prisoner of War。戦争捕虜。
(2009. 7.20 読)

|
 |
「珊瑚礁に風光る」 太田良博 著 ボーダーインク 2,500円+税
2008年10月10日 第1刷発行
7月18〜20日は3連休。この休みにじっくり読みました。
戦後の復興間もない1956年4月から翌年1月まで、247回にわたって「沖縄タイムス」夕刊に連載された新聞小説を復刻したもの。うむ、なかなかやるじゃん、ボーダーインク。
著者は1918年、那覇市生まれで、沖縄民政府、沖縄タイムス、琉球放送、琉大付属図書館、琉球新報社などに勤務。その間、詩、小説、随筆、評論などを発表し続けた文化人です。2002年死去。
2003年から08年にわたって、その細君が尽力し、「太田良博著作集」(第1〜5巻)を発刊。その際に収録できなかった著作の一つが、この「珊瑚礁に風光る」で、それをボーダーインク社が単行発刊したのがコレというわけです。
興味は、半世紀以上前の沖縄がどうだったのかということ。まだ浮島としての名残が残る那覇の町の様子や、当時の若者の恋愛観、男女の会話の粋のあり方などを垣間見せてくれ、なかなか参考になりました。
2段組350ページ超の大作ですが、文学書としては全体のまとまり感が少し足りないなという印象。そういうことは新聞小説にはありがちですが、作品を通じて一貫して流れてくる通奏低音のようなものは、あまりありません。なので、少し間をおいて途中から読み始めたりすると前後がつながらず、再度前に戻って読まなければならないということがしばしばありました。まぁ、そのあたりは50年前の作品ということで、ご愛嬌。
その特徴的な書き出しの記述部分を掲げると、こんな感じです。時代を感じるし、那覇はまだ王国のテイストを色濃く残していたのだなぁと思います。
『土曜の午後である。
崇元寺の琉米文化会館では、西洋音楽のレコード鑑賞会が開かれていた。単純で重厚な線をもつ、そこの石門は、もと鬱蒼たる亜熱帯樹でおおわれ、門前は、尚清王時代の建立と言われる石造の下馬碑が建っていた。舜天以下時代の霊位を祀った尚氏家廟で、戦前は国宝指定物だった。
あの戦争で、跡形なく吹飛ばされた、そのあとに、かなり宏壮な構えで、文化センターの建物が建ち、あたりに、モダンな開放的な空気をただよわせている。――』
琉米文化会館ですよ。レコード鑑賞会ですよ。(笑)
そうそう、この文章、やたらと読点が多いです。その反面あちこちで句点が抜けていたりするので、ときどき考えさせられながら読むことになりました。(笑)
(2009. 7.20 読)

|
 |
「カフーを待ちわびて」 原田マハ 著 宝島社文庫 457円+税
2008年 5月26日 第1刷 2009年 3月 4日 第2刷発行
今年の春、この映画を観に行かないかと次男に誘われていたのですが、結局行かずじまいに。
で、GWに沖縄の書店でこの本を見つけたので、買って読んでみました。ラブストーリーなんて苦手なのだけれど・・・。
ロケーションは、沖縄本島周辺の離島、与那喜島。主人公の明青(あきお)は家族がなく、犬のカフーとともに島の雑貨屋を営んでいます。そしてうりずんの季節、彼に1通の手紙が届きます。
「もし絵馬の言葉が本当なら、私をあなたのお嫁さんにしてください――。」
そのきっかけは、明青が本土を旅行した際に絵馬に書いた「嫁に来ないか。」という願い事でした。
そんなことって現実には考えられないことだよな・・・と思いながらも、構成力、文章力がすばらしいので、次の展開に期待してどんどん引き込まれて読んでしまいました。
そして結末は。
手紙の差出人の幸(さち)が明青のもとに嫁に来ようとした必然性が劇的な形で明らかとなります。
ラブストーリーに特化した文学賞「第1回 日本ラブストーリー大賞」が2005年に創設され、その大賞受賞作がコレ。作者は、小説家でエッセイストの原田宗典の実妹なのだそうです。
映画のロケ地は今帰仁村。でも、実在する島に照らすと、イメージは伊是名島か、または伊江島に近いような気がします。
ひっそりと佇む家々の様子や、裏に住むユタのあばぁの表情や言動(映画ではあの瀬名波孝子が演じたらしい)、いつもカフーと散歩に出かける夕暮れの南浜の情景、小学校のグランド脇にある大きなデイゴの木のがっしりとした枝ぶりなどなど、沖縄の離島のことを思い出し、想像しながら、眠ることを忘れて耽読しました。
この本、なかなかのグッドジョブです。
どうやら映画も原作に忠実なよう。ロードショーは終わってしまいましたが、機会があればぜひ観てみたいものです。
(2009. 7.11 読)

|
 |
「しまうたGTS」 山田あかね 著 小学館 1,500円+税
2007年 7月30日 第1刷発行
20歳にして人生最悪のときを迎えた主人公・犬彦。大学2浪の身のうえに、絶好調だったバンドのほうも、まもなくメジャーデビューというときに仲間の城司とぶつかってご破算に。その上、脳腫瘍であることを宣告され、さらに恋人ナナナはなぜか城司とともに南へと失踪してしまいます。
犬彦は、途方に暮れながらも、残された時間、失踪した二人を追って東京〜沖縄〜石垣〜波照間とめぐっていきます。その途中、拳銃を持ったまま逃走する警察官スズキと、城司を探す旅をしている女子中学生の理沙が彼の道づれとなりますが、この2人が追跡行にいい彩りを添えています。
城司は沖縄・コザの出身。父親は米兵で、母親は行方不明。石垣島に住む祖母に引き取られて子ども時代を過ごしたという設定です。
そして祖母は、波照間島生まれで、ケーキ時代といわれた戦後の数年間、与那国島での密貿易で財をなした人物。城司は、その祖母から教わったしまうたの歌詞に財宝の隠し場所が秘められていることに気づき、財宝を掘り当てるべく波照間島に向かったのでした。さてさて、その結末やいかに。
疾走感たっぷりに繰り広げられるロードノベル。しまうたや与那国島の密貿易に関することが巧みに文中に練りこまれているのが、沖縄ファンにはたまりません。
巻末の「謝辞」によれば、しまうたについては仲宗根幸市氏がその基礎から指南したそう。ナルホドなあ。物語の鍵となっている城司がうたっていたしまうたは、それがとぅばらーまに乗せてうたわれるというのは語呂が合わないにしろ、見事なヤイマ口(八重山語)でした。
また、与那国の密貿易に関しては、やはり、「ナツコ 沖縄密貿易の女王」(奥野修司著)がベースになっていたようです。
なお、GTSとは、ゴーイングトゥサウスの意。GTSなんて、かつての名車スカイラインみたいでカッコイイな。(笑)
(2009. 6. 6 読)

|
 |
「海の階調」 水無月慧子 著 沖縄タイムス社 552円+税
2008年 9月27日 第1刷発行
水無月慧子「琉球処分」三部作――と副題がつく、沖縄タイムス社刊の文庫本です。
表題作「海の階調」では、首里の下級侍である区場朝伸が、琉球処分前後の琉球・沖縄にあって、世の中を少しでもよくしていこうと日本政府の探訪人(密偵)となる決意をします。
首里城明け渡しとそれに続く廃藩置県、本土から送られた官僚や警官の画策、対して権勢復活を目論む頑固党の暗躍などを背景として、激動の時代に生きる志し高い若者たちの生きざまがみずみずしく描かれています。
表題作のほか、「闇のかなたは」、「密告の構図」。
著者は、1962年北海道生まれ。中学時代、父の転勤に伴い沖縄に移り住み、以降23年間沖縄で生活したとのこと。もともと明治ものを読むのが好きで、大城立裕の長編「琉球処分」などを読んで沖縄の歴史小説に耽溺していったそうです。
そして2作目の「出航前夜祭」で新沖縄文学賞の佳作を受賞。その後20年間にわたり「沖縄とヤマト」の物語をライフワークとして書き続けてきた中から3編を選んで、このたび全面改稿して出版したのがこの本なのだそうです。
小説なので、楽しみながら読めるようさまざまな虚構や誇張などが含まれているのでしょうが、凡人(ワタシですね)がフムフムと読み進めていくにはちょうどよい柔らかさの文章です。
そして、その中には当時の琉球が偲ばれる情景描写や人々の生活の様子などが描かれていて面白い。先ごろ読んだ「誰も見たことのない琉球」(上里隆史著)で知った、一般的な琉球王国のイメージと違う、ぐっとヤマト風の琉球をイメージしながら読みました。
また、認識を新たにしたのが、頑固党。そういう勢力もあった、程度にしか考えていなかったのですが、当書には、頑固党の暗躍を恐れ、なるべく改革は控え急速に旧慣温存政策に傾いていく沖縄県庁の様子が描かれていました。
久々の沖縄への旅のさなか、渡名喜島の空き家を改造した赤瓦の一戸建ての民宿で。帰りのフェリーの中で読了しました。
(2009. 5. 4 読)

|
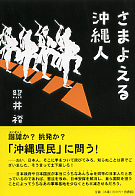 |
「さまよえる沖縄人」 照井 裕 著 文進印刷 1,000円+税
2008年 8月20日 第1刷発行
主人公・金子達也は横浜の戸塚駅周辺で働く40歳のタクシー運転手。不況下で収入減にあえぎ、運転手仲間2人とともに人生の一発逆転をかけて身代金目的の誘拐を計画します。
狙うのは、バブル期の土地ころがしによって成金丸出しの豪邸を建て、そこに住む喜屋武朝光という人物。
計画は順調に実行され、ついに完結すると思われた最後の段階で、ストーリーは思わぬ方向に急展開します。
姓が物語るとおり喜屋武はウチナーンチュで、計画の完遂を阻止したのは、南米ボロビア国にある「ボロビアうちなあんちゅ会」なる組織。金子はこの組織によって一人ボロビアに連れ去られ、各国のうちなあんちゅによって開催される水泳大会でボロビア代表を3位以内に導くことを条件に我が身の解放を約束されます。
弱小チームのボロビアは、やたらと泳ぎが得意でアマゾンの森林地帯にひっそりと住んでいるというウチナーンチュの末裔をチームに引き入れて・・・。
う〜む、なんか、展開がハチャメチャだなぁ。読んでいて楽しめこそするが、導入部と結末を並べて考えると、なんかこう、まとまりというものが感じられない。ま、沖縄に関することだから、おれはいいのだけど。
著者は、1964年横浜市生まれ。非沖縄人ですが、沖縄国際大学で学び、在学中に沖縄タイムスの「新沖縄文学賞」を最年少受賞し、30歳のときに沖縄村の広報紙記者として南米ボリビアにも赴いた経験があり、現在は横浜でタクシー運転手の傍ら小説を書いているとのことです。
ナルホドね、著者の経験や日常がそのまま作品のモチーフになっているのですね。
新沖縄文学賞受賞から21年。河野多恵子をして「尋常ならぬ才能」と言わしめた青年が分別ざかりとなり、いまここに「尋常ならぬエンターテインメント小説」を世に送り出した――ということなのですね。
コシマキには本書のクライマックスが書かれていますので、引用しておきましょう。
諧謔(かいぎゃく)か? 挑発か? 『沖縄県民に問う!』
―― おい、日本人。そこに手をついて詫びてみろ。知らぬことは罪でございました、そう
言って土下座しろ!
―― 日本政府や日本国民が本当にうちなあんちゅを同等の日本人と思っているのであ
れば憲法を改め、日米安保を解消し、自ら国防を担うことによってうちなあの軍事
基地を少なくとも半減させるだろう。
(2009. 3.22 読)

|
 |
「琉歌・恋歌の情景」 船越義彰 著 ニライ社
1,600円+税 2007年 5月15日 第1刷発行
「歌は理屈ではありません。心の波動を感性が言葉にし、声に乗せて伝えるもの、それが歌(詩)です」――
このような立場から琉歌中の恋歌が取り上げられ、一首一首について船越義彰ならではの熱く深い解説が施されている良書。
それは、たとえば次のようなものです。
『 干瀬にをる鳥や 満潮恨みゆり 我身や暁の 鳥ど恨む
(ふぃしにをぅるとぅいや みちしゅうらみゆい
わみやあかつぃちぬ とぅいどぅうらむ)
干潟に翼を休めている鳥は、満ち潮を恨む。飛び立たなければならないから…。
私は夜明けを告げる鶏が恨めしい。恋人との語らいをやめて別れなければならないから…。
恋愛は秘めごと、それゆえに、会って語らう時間は寸刻でも惜しい。この大事な時間と空間が、暁を告げる鶏の声で断ち切られる。満ち潮の干潟から飛び立つ鳥の羽ばたき、鶏鳴で彼女と別れゆく男のこころ、ため息、それが行間からあふれ、聞こえてくるようである。簡潔なだけに切なく、また恋人たちの「時間」の密度の濃さを歌いあげた一首である。
この歌は「干瀬節」の名曲に乗る。私は、この曲を小夜曲、あるいは夜想曲としても名曲であると思う。』
読んでいてつくづく思ったのですが、琉歌とはスバラシイ!
8・8・8・6の句形に乗せた言葉のリズムがよい。余計な言葉がなく、読み返すたびに深い感慨が見えてくる。また、沖縄語が耳や心にやさしい。
もっと評価されてもいい表現形だと思うが、いかがでしょうか。
船越義彰といえば、詩人、作家として活躍した沖縄を代表する文化人。しかし、2007年3月に、81歳で逝去。
当書の「あとがき」で、琉歌・恋歌と対面することは天体観測をするようなものだったが、80年という人生が自分を「眺望の場」に置いてくれた、と書いていますが、それが2007年2月。
当書が、著者の生前最後の出版物となったのではないでしょうか。
(2009. 1.12 読)

|
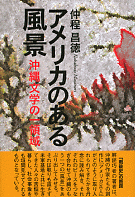 |
「アメリカのある風景 沖縄文学の一領域」 仲程昌徳 著 ニライ社
1,800円+税 2008年 9月20日 第1刷発行
「沖縄のアメリカ人(兵)は、どのように描かれたか。」
――これが本書のテーマであり、それぞれの読者に投げかけられたある種のテーゼでもあります。
著者は、琉球大学法文学部の教授。読書巧者である著者は、沖縄の作家たちの創作に「アメリカ人(兵)」がどのように取り入れられてきたかを丹念に読み解き、それぞれのピースをつなぎ合わせて沖縄のもう一つの「風景」をあぶりだして見せます。
それは取りも直さず、米軍基地と共に生きてきたウチナーンチュの苦悩や暮らし、社会現象などをも垣間見せてくれるものになっています。
沖縄における、ペリーの来航の時代から現代までの「アメリカ」を扱っていますが、中でも最もインパクトを伴って描かれているのは、やはり「復帰後の文学」の章。
『戦後の沖縄がアメリカとの関係を抜きにしては語れないように、戦後の沖縄の文学も、またアメリカ人(兵)の影を抜きにしては語れない。そしてその影は、占領下にあった27年間だけでなく、施政権が返還されたあとも、消えることなく揺曳している。占領の終焉が、基地の撤去に繋がらなかったばかりか、ほとんど返還されることもなく、多くのアメリカ人(兵)たちがそのまま居残った以上、それは、当然のことであった。――』
後半では、アメリカ人(兵)が登場する多くの沖縄の戦後小説の一部が紹介されています。
これらは、ざっと読み流しただけでもけっこう読み応えがあり、何十冊もの沖縄文学をまとめ読みしたような気分になれますから、音楽で言えばオムニバスを聴いているような感じで、おトク。(笑) 沖縄文学の入門書としても存在意義があるのではないかと思われます。
読後感としては、沖縄の戦後文学というのは、突き詰めれば「アメリカ」との格闘であったのだなぁということ。
なかなかユニークな視点に立った面白い評論書でした。
(2009. 1. 8 読)

|
 |
「琉球吟遊詩人 アカインコが行く」 与並岳生 著 琉球新報社
1,429円+税 2008年 1月25日 第1刷発行
「歌と三味線の むかし始まりや 犬子音東(いんこねあがり)の 神の御作 ・・・」
とうたわれる、琉球の吟遊詩人との誉れが高く、また、歌三線の始祖とされる、「赤犬子」の波乱万丈の人生を、新解釈で描く力作。
読谷村の楚辺地域はかつて阿嘉・饒波という隣り合った二つの村だったそうで、その浜辺でモーアシビをしている若い赤(阿嘉)犬子たちの様子から物語は始まります。
うた上手の赤犬子に思いを寄せていた村長の娘・チル小と結ばれはしたものの、そのチルに村掟の後添として白羽の矢が当たり・・・という不幸が。
村掟の嫉妬深い策謀にはまって村にいられなくなってしまった赤犬子は、首里の王朝から許しを得て、鼓を携え歌をうたいながら歩く「お祝付き(おえつき)」として島内の各地を歩くことになります。
打ちひしがれて放浪を始めたものの、旅回りして歩くうちにいつの間にか水戸黄門のような強い正義の味方となって、たちの悪い村掟や山で盗みを働くフェーレー(山賊)などを次々と退治していきます。
これって、あまりにできすぎていて、ほとんどが創作だろ?と思えてしまうほど。
まぁ、どこまでが史実でどこからが創作なのかよくわかりませんが、少なくとも物語として読むならば、なかなか痛快で面白い。
表題作のほか、琉球版水滸伝のような「日照雨(そばえ)」も収録。読みやすい全287ページ。
著者は、元琉球新報記者。これまでにも「琉球王女・百十踏揚(ももとふみあがり)」や「思五郎が行く―琉球劇聖・玉城朝薫」などの沖縄に関する歴史・時代小説を著しているそうです。
それらにも食指が動いてしまうのですが、しかし、ここまでフィクションが強いと、読むのはどうなのだろうなぁとも考えてしまいますね。(笑)
(2008.11. 3 読)

|
 |
「十津川警部「オキナワ」」 西村京太郎 著 光文社文庫 571円+税
2008年 5月20日 第1刷発行
この週末に、ちゃちゃ〜っと読みました。“オキナワ”と名のつくものはなんでも読むのだ、おれは。
2004年12月に発刊されたカッパ・ノベルズを文庫化したもので、当時運行しはじめたばかりのゆいレールが頻繁に登場したり、基地の街をことさらに強調したりしていて、まぁ、沖縄らしいといえばそう言えなくもない。
しかし、こういう類いの本って、読んでいるときはよいとしても、読んだ後の充実感が乏しい。
テンポのよすぎる展開、刑事たちの推測どおりの成り行き、なんで警視庁の刑事がこんなに頻繁に沖縄に出張してくるのかと思わざるを得ない機動的すぎる刑事の行動・・・。
こういうことがらがあいまって、そう感じてしまうのだろうな。
つまるところ、心理描写や情景描写などがほとんどないから、登場人物への感情移入ができず、結果として事務的な報告書でも読むかのような姿勢になってしまい、中身はわかったとしても、感動が生まれてこないのだろう。
振り返れば、主人公の比嘉みどりや十津川警部ってどんな人だった?と訊かれても、うまく説明することができないものな。
文学にはこういうジャンルもある、ということだけど、言い過ぎかもしれないが、こういう類いの本をたくさん読んでシアワセを感じている人がいるのだということに、多少の驚きを覚えてしまったのだった。
(2008.10. 5 読)

|
 |
「月よ、あなたに」 大城亜子 著 ボーダーインク 1,000円+税
2007年10月 1日 第1刷発行
戦後混乱期の沖縄で、幼くして体を売って生きてきた金城ユサ。そのあまりにも壮絶な生き方を嫌い、彼女に背を向けて生きてきた二人の娘たちのもとに、“ユサ自殺”の報が届きます。
ユサの亡骸を引き取るために久々に沖縄へと戻ってきた二人は、近親者からユサの過去の真実を聞かされて、彼女の一途な愛、性愛、そして別れなどに触れ、娘としての母に対する思いが揺れ動きます。
そして娘は、深い愛に胸を焦がして生きてきたユサを理解できるようになり、「いつか月の光が私を導くときには、私も愛する人のそばにいたい。」と願うようになって・・・。
暗い過去を隠しきれず、それが日々ににじみ出てしまう女性の劣情。そしてその劣情を打ち消すかのように全身全霊を傾けて注いできたユサの愛は、男性の裏切りによって否定されます。
しかし、ユサはその男性への愛情や官能の想い出を打ち消すことはできず、愛されたという矜持は自身を精神の迷路へ追い込んで行きます。
そんな女性の想い、執念、美意識といったものが、爪を彩る真っ赤なマニキュアの色に象徴化されて、深い感動となって読む者の心に残ります。
「あなたにも愛する人はいますか」
一途な愛を貫き通したユサの一生。愛に感謝できる、涙が止まらないストーリー。
1980年沖縄生まれの気鋭作家のデビュー作。次も期待しましょう。
(2008. 5.20 読)

|
 |
「となりのウチナーンチュ」 早見裕司 著 理論社 1,500円+税
2007年12月 第1刷発行
ところは浦添の牧港あたり。1階にスーパーマーケットが入っている鉄筋アパートの4階に住む新垣彩華は、ビンボーなために高校にも通えない15歳。快活で他人に頼らないところがあり、多少サーダカ(霊感が強い)のようで、聴こえないものが聴こえたり、見えないものが見えたりします。
父の勇は、直木賞作家を夢見て毎日泡盛を飲みながら役に立たない原稿を書いているフリーライター。故あって妻と別れ、実家からも縁を切られてしまっています。
そんな父娘のとなりに東京から引っ越してきたのが、鈴木父娘。我がままな母親への恐れと難しい友達づきあいのためにすっかり学校が嫌いになり、友達なんかいらないと思っている夏海と、沖縄大好きの和則です。
夏海は、あっけらかんとした彩華の行動や、同じアパートに住むというだけで分け隔てない付き合いがはじまっていく沖縄の不思議な雰囲気に触れ、徐々に心を開いていきます。
その途上には、恐い母の生き霊を彩華とともに追い払ったり、夏海を東京に連れ帰ろうと台風のさなかにやってきた本物の母をアパートの住人たちが結束して本土へ追い返したりと、さまざまな山場があります。
ラストシーンは、宜野湾のトロピカルビーチ。
「沖縄そばってどんな感じ?」と、夏海が問えば、
「食べやすいよ。見てからのお楽しみ」と、彩華が答えます。
「そばを食べなければウチナーンチュとは言えないさ」
「もう勇よー。夏海はウチナーンチュではないってば」
「うん。でも、ウチナーンチュがやるようなことは、だいたいやってみたいの。できることだったら」
「じゃ、まずは、そばさーね」
「でもさ、夏海」
「何?」
「いいんだよ。自分がウチナーンチュだ、って思っても」
―――そのとき夏海は、心の底からうれしそうな顔をしたのでした。
ウチナーグチのイントネーションまでが読み手に伝わってきそうな、不思議と温かさがいっぱい詰まった「ゆるみ系ホラー」小説。サイコーです。
(2008. 5. 4 読)

|
 |
「豚と真珠湾 幻の八重山共和国」 斎藤 憐 著 而立書房
1,500円+税 2007年10月25日 第1刷発行
昭和20年8月15日、琉球列島の最西端、台湾がすぐ隣の八重山諸島の中心である石垣島には、米も芋も豚も、マラリアの薬もなかった。日本軍によってすべて食べられたか独占されていたのだった。八重山の人たちは助け合いながら、自分たちの生きる方向を模索するのだった――。
・・・というので、面白そうだからさっそくネットで購入しましたが、これ、小説ではなく、戯曲の台本だったのですね、届くまで知りませんでした。(笑)
我が人生において、戯曲を台本で読むなどという機会はこれまでまったくと言っていいほどなかったものだから、少々面食らってしまいました。
でも、音や絵、小道具などの舞台装置と共に人間が身体全体で表現する演劇というのは、数ある芸術の中でも最高峰のものだとおれは思っているし、本書の内容が当時の世相や島人の様子などがよく表現されているので、とても興味深く読ませていただきましたよ。
作者は、俳優座養成所を卒業後、劇団自由劇場結成に参加し、1980年には「上海バンスキング」で岸田國士戯曲賞受賞したというお方。沖縄関係では当作のほかに「アーニー・パイル」なども。
先に読んだ奥野修司の著「ナツコ 沖縄密貿易の女王」がベースのひとつになっているので、読んでいて共感するところ多し。
また、著者によれば、我が「積ん読ストック」にある石原昌家の「空白の沖縄社会史
戦果と密貿易の時代」も大いに参考にしたというから、こちらのほうを読むのもまた楽しみになってきました。
このように、読んだり読もうとしたりしている書物が相互に関係し合ってくることが、読書の楽しみであり醍醐味なのですね。
でもまあ、戯曲はやはり、実際の舞台を観ないことにはホントではないような気がします。
全3時間の芝居。2007年10月4〜14日、俳優座劇場で上演されたとのこと。
これをぜひ、沖縄の演劇集団によって、沖縄の地で、上演してもらいたいものです。
(2008. 1. 5 読)

|
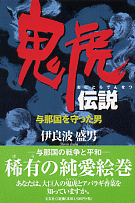 |
「鬼虎伝説 与那国を守った男」 伊良波盛男 著 文芸社
1,500円+税 2004年 2月15日 第1刷発行
宮古島生まれの鬼虎は、幼少時、守姉(むらに)の香奈に見守られながら巨漢児に成長。その後与那国の長者にもらわれ、豊かな人間性と深い洞察力を兼ね備えた指導者へと成長していきます。
やがて与那国の統治を任された彼は、底知れぬ叡智で人々を指導していきますが、やがて琉球国との戦いが始まり・・・。
沖縄方言や、彩り豊かな地方色を添えて、与那国滅亡の歴史的悲劇を描く、哀愁漂う英雄伝説として仕上がっています。
与那国の当時の歴史を概括すると、まず15世紀末には、女傑サンアイ・イソバが首長となり、祖納の集落を見下ろすティンダバナ(天座鼻)に座していたといいます。
そして1500年のオヤケアカハチの乱の後、八重山は沖縄本島の中山王国の支配下に置かれることとなりますが、与那国島では鬼虎が首長となり、中山支配に抵抗をはじめます。
これに対し中山は、アカハチ討伐に功績のあった宮古島の首長、仲宗根豊見親(なかそねとぅゆみやー)に与那国島を討たせ、与那国島は完全に中山の支配下に置かれることとなります。
このような時代背景をもとにしながら、著者は周辺事情をかなり大胆に脚色して物語を進めていきます。
サンアイ・イソバ(当書では榕樹磯波と字を当てていました。)が若い鬼虎と語り合う場面などは、現代のウチナーヤマト口で表現されていたりして、なかなかユニーク。
また、与那国の戦争と平和を表現しながらも、実は一貫して底流を流れているのは鬼虎と香奈の純愛だったりして、読む者を飽きさせません。
与那国の歴史を知る上で、難解な専門書よりも数段わかりやすく、いにしえのどなん(渡難=与那国)の国へのイマジネーションをぐいぐいとかきたててくれる良書です。
蛇足ですが、言い伝えによると、イソバは女ながらも8尺(2.4m)、鬼虎は1丈5寸(3m余)の背丈があったそう。彼らが現代に生きていたなら、さしずめプロレスラーにでもなっていたでしょうか。(笑)
(2007. 9.16 読)

|
 |
「石垣島事件帖」 坂本成穂 著 彩図社ぶんりき文庫 550円+税
2003年12月 1日 第1刷発行
彩図社のぶんりき文庫刊。ぶんりき文庫って、詳しくはわからないのですが、企画原稿を募集し、著者自身がカネを出して出版するというスタイルのものらしく、私がこの著者の本を読んだのは、やはりぶんりき文庫の「リストラマン放浪記」以来2冊目。ネットショッピングで「石垣島」の検索に引っかかってきたものです。
「リストラマン・・・」のときも感じたのですが、内容は、プロというにはもう一息といった感じ。著者は、1938年生まれ、定年と同時に執筆活動に入ったという人。好きなことをとことん突き詰める人生、それもいいのでしょうね。少し羨ましいですね。
「ヤング・ラブ・ストーリー」、「Eメール・バスター」、「アダンの木」の3篇。登場人物やストーリーのところどころにやや説明不足があったり、できすぎや偶然によってコトが進んだりと、読者側の寛容性に頼る部分がいくつかあります。
しかし、「キミ食堂」、「産業道路」、「石垣島まつり」、「のーでんショップ」、「ダイブショップ・トムソーヤー」などなど、石垣島の場所や固有名詞が随所に出てくるので、島を知っている人ならあぁ、アソコね、などと思い出しながら読むことができます。
はじめは石垣島とあまり関係ないのではと思われるストーリーであっても、最後までには必ず石垣島が登場します。(笑) このあたりをみると、著者はよっぽど島が好きなのだということがよ〜くわかります。
石垣島マニアの方は読んでみましょうね。
(2007. 8. 8 読)

|
 |
「石垣島物語」 石垣用喜 著 文藝書房 1,500円+税
2006年 1月25日 第1刷発行
表題作のほか、「遅れてきた男」、「最期に笑う女」、「孤独と闘う」、「定時制高校生」の全5篇からなる、石垣島をテーマにした文芸作品。
著者は、昭和7年、石垣島登野城生まれ。国民学校を卒業後、親の反対で進学することができず、10年ほど石垣島内で働いた後、30歳で大阪の定時制高校を卒業し、NHK沖縄放送局に勤務したという経歴を持っています。
そのような人生遍歴については、「遅れてきた男」に詳しく書かれています。もうこれは、文学作品というよりは“自分史”と言ってしまっていいようなデキですね。(笑)
「遅れてきた男」の内容から推すと、「石垣島物語」は、著者の兄である六男の松男を主人公にした、太平洋戦争中の物語ですね。
全体として、文学的価値らしきものはあまり感じられませんが、石垣島で生まれ、育ち、老いてきた一人の人間のモノローグとして捉えてみれば、それなりに楽しめます。
また、島唄をこよなく愛するワタシとしては、いろいろと興味をそそられるところがありました。
八重山民謡界の重鎮である宮良高林は、農業連合会の運転手として勤務していた頃、著者らが経営する自転車店にパンクしたトラックを持ち込んで修理したのを契機に、よく帰宅途中に茶碗酒を飲んでいった――とか、兄である三男益三の孫は、石垣島デュオとして現在活躍中の“やなわらばー”の一人、石垣優である――とか。
これらが実名で書かれてあり、なかなか面白かったですよ。
(2006. 7.31 読)

|
 |
「でいごの花の下に」 池永 陽 著 集英社 1,600円+税
2005年 8月30日 第1刷発行
『プロのカメラマンだった男は姿を消した。死をほのめかすメモと、使いきりカメラを残して。フリーライターの耀子は、恋人の故郷である沖縄へ。どこまでも青い空と、太陽と風につつまれて、愛した男を追い、その過去を知ってしまう…。戦後60年、消し難い記憶、揺れる想い…。まっすぐな愛を描く書下ろし。』
久々に読んだ沖縄にまつわる文学作品は、大きな感動を呼ぶ秀作でした。
沖縄戦、ガマでの出来事、日本兵幹部の醜悪な振舞いと人間性を失っていない負傷兵、米兵との間に生まれたハーフ、ラビリンスなマチグヮーの様子、マフックヮな太陽、美しい海、狂い咲きの白いでいごの花、沖縄ならどこにでもありそうな民宿、台風、御嶽(ウタキ)、拝所(ウガンジュ)、性高(サーダカー)生まり、キジムナー、古酒(クース)、オバァ、廃村…などなど、沖縄ならではの周辺事情をうまく使い、登場するウチナーンチュにはやさしげなウチナーグチを使わせて、雰囲気は満点です。
そしてストーリーはというと、単にそれらが散りばめられて“らしさ”があるだけではなく、沖縄の精神性がしっかりした背骨を形成していて、最後のクライマックスは2つの「骨」をめぐって大きな感動が…。ちょっとうまくいきすぎだよなと感じてしまう結末ではあるけれど、おれは泣けたゾ。いいんだもん。こーゆー場合、感動しちゃったほうが勝ちなんだもんね。(笑)
「骨」がテーマだというのは、どーゆーことなのか? それは読んでのお楽しみだよね。
表紙の風景画と題字のとおりの、汗ばむ額に爽やかな真南風を浴びたような、すばらしい作品でした。
作者はウチナーンチュではなく、1950年、愛知県の生まれ。98年「走るジイサン」で小説すばる新人賞を受賞して作家デビュー。48歳でとはまた晩成型ですね。02年「コンビニララバイ」で「本の雑誌」上半期ベスト1を獲得。初めて読んだけど、彼はなぜ“沖縄”なのだろう。
あと、作中、民宿ちゅらうみに宿泊していた謎めいた老年の「中井夫婦」の存在は、ホントは何だったのかが知りたいところです。
日曜日1日で280ページを一気に読んじゃいました〜。
(2006. 3.12 読)

|
|

|
「アクシデントの沖縄勤務」 末吉節子 著 文芸社 1,500円+税
2005年 3月15日 第1刷発行
表題を見て、これはきっとヤマトの人間が急な沖縄勤務を命ぜられて何もわからずに赴任したところ――とのイントロで始まる移住モノなのだろうな…との独断と邪推で読み始めたのですが。…Ummm、まったく違いましたね。(笑) これは小説です。
アメリカから赴任してきた海兵隊の少佐が婦女暴行未遂で起訴される。彼は20年前、父親の軍務の関係で沖縄で少年時代を送っていたことがあり、その時の学校の先生が偶然にも裁判の際の法廷通訳として彼の裁判に立ち会う――というストーリー。
著者は、2002年末、沖縄の地元紙が一面トップで報道した「米少佐が女性暴行未遂」の記事に接し、その記事を読んでいるうちに違和感を覚え、この事件をもとに小説を書いて基地の実態を多くの人たちに知ってもらいたいと思った、ということです。
この著者、那覇市立の小学校教諭を振り出しに、30年余にわたって沖縄県在米国国防省立学校で日本文化について教鞭をとってきた経歴を持っており、「これは私がしなければならないこと」と思ったそうです。この意志たるや、スゴイですねぇ。
前半は、被告人となるジム・スミス少佐を主人公に小説仕立てで進んでいきますが、後半は、通訳である比嘉みきからみた法廷でのつぶさな審理状況の描写を軸に記述されていきます。全体としては、実話に基づく「法廷小説」といったところでしょうか。
女性らしいやわらかい筆致で、私は好ましく思いながら読みましたが、もしかしたら人によって好き嫌いがあるかもしれません。
(2005. 7.24 読)

|

|
「骨は珊瑚、眼は真珠」 池澤夏樹 著 文春文庫 419円+税
1998年 4月10日 第1刷発行
ずいぶん前に発行されたものですが、沖縄在住の池澤夏樹の、しかもステキな表題の本を見つけたので、買って読んでみました。
表題のほか、「眠る女」「アステロイド観測隊」「パーティー」「最後の一羽」「贈り物」「鮎」「北への旅」「眠る人々」の9編からなる短編集で、うち沖縄関連と思われるものは2編。
「眠る女」は、もう、かつて――と言っていいと思うが、12年に1度行われていた久高島のイザイホーに、夢の中で巫女として参加している自分を見つける――というストーリー。「エーファイ、エーファイ…」という女たちの掛け声や、随所に登場する神歌のティルルなどによって、祭りの様子がある意味写実的に、そしてある意味幻想的に表現されています。
「骨は珊瑚、眼は真珠」は、死して骨となった男が、空中にさまよう魂の目を通して見ていることをモノローグする――という設定で、死んだ男の生前の強い希望により、その妻が夫の骨を沖縄の海にそっとたゆたわせる…というもの。この一種宗教的な描写は池澤夏樹らしいなぁと感じさせる見事な筆致。沖縄に惚れ込んでいる著者自身こそが、自分の骨をこのようにしてほしいと思っているに違いない。おれなんかも死んだならそうしてほしいと思うなぁ…。じめじめした狭苦しい墓に入り、山寺の深い雪に半年間も埋もれているのなんて、ヤだもんナ。
(2004.12.11 読)

|

|
「小説 遊女(ジュリ)たちの戦争」 船越義彰 著
ニライ社 1,600円+税
2001年2月10日第1刷発行
コザの古本屋で、新古書を1300円でゲット。
先の大戦の頃、辻の遊郭で遊女(ジュリ)をしていた志堅原トミ(仮名)の証言を中心に、小説仕立てで綴ったものです。
沖縄の島唄を聴いたりすると、遊女と殿方にまつわる恋のうたなどが優雅にうたわれていたりするし、沖縄の花街のあり方は本土とはまた違う性格をもっていた…などという話を聞きかじって、戦前の那覇の遊郭については決して悪いイメージは抱いていませんでした。そんなことで、ジュリというものがどういうものだったのかをもう少し追求してみたいと思って手にしたのがこの本でした。
結果としては、特に戦時中には日本兵の慰安婦として働かざるを得なかった事情などが述べられているのを読み、彼女達にとってはやはり現実は厳しかったのだな、彼女達のもつ矜持、誇りとは裏腹に、結局のところこれは女性虐待以外の何ものでもなかったのだな――ということを改めて感じました。
辻遊郭は宴会場、社交場としての役割をもっているため、ジュリたちは宴席での接待に必要な歌舞音曲の稽古を積んだといいます。これを貧乏や身売りと結びつけて、薄幸な女の孝養とするという社会通念もあり、私もこれまではそのような考え方にロマンチックなものをプラスして考えていました。だが、現実は違っていたようです。読後感は、えらく苦いコーヒーを飲んだ後のような感じかなぁ…。ちょっと目が冴えてしまったりして。
昭和初期の辻遊郭の見取り図や当時の写真が載っており、資料的価値もあります。中頭方面から那覇に突入しようとしている米軍の写真では、破壊された泊高橋とその周辺の、今のたたずまいとはまったく違う様子がわかったりします。
(2002. 5. 3 読)

|