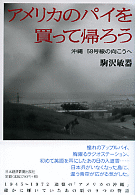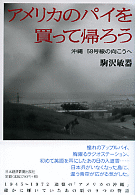|
�u���ɕ������I�i���@�q���������r����E�O�o�� �Ƒ��Ɨ��̕���v�@�@�@�c�����G�@��
�@�@�@�M���Ё@�@�@�P,�W�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�P�P�N �P���R�P���@��P�����s
�@�����푈�̎���ɂ��̐��ɐ����A���ꏉ�̊O�����ƂȂ����c�ꐷ�`�B�ނɂ́A�ÁA�߁A�p�Ƃ����O�l�̖������܂����B�O�o���́A�Z�E���`�������A�Z�̎u���x���Ȃ���A����ɐ����Â������A����Ƃ����t���ɉʊ��ɗ����������Đ��������܂����B
�@����ȉ���̈�Ƒ��̓��X���A���̎���̗l�q�ƂƂ��ɕ����������Ă܂Ƃ߂��̂����̋I�s���|�m���t�B�N�V�����ł��B
�@�P�X�Q�W�N�����A�ߔe�̑��O�d�Ԓʂ�ɂ������Ƃ������g��@�B���̉@��̖���������l���ł��B
�@���҂����̖��̈�l�Əo������̂͂Q�O�O�R�N�H�A�����̓��k���𑖂�D�Ԃ̒��ł����B
�@���҂̓��V�A��̐�U�ŁA�u�������k���̗��v�c�A�[�ɎQ�����ċ��R�A�q���̍��A�Ƒ��Ɩ��B�ŕ邵�����Ƃ����肻�̎v���o����J�낤�Ɠ����c�A�[�ɎQ�����Ă������g�߂Əo������̂ł��B
�@���ꂪ���ƂŁA�߂��������̂�S�ɍ��݁A�����̐��������Ǝ���̋L�������ǂ钘�҂̒��������n�܂����̂ł��B
�@����ɂ͂��Ȃ�_�M�����ł��F�Z���c���Ă��܂��B
�@���Ȃ�_�Ƃ́A���i���Ȃ�j���Z�i������j���I�Ɏ�삷��ƍl���A���̗�͂�M���问���̐M�ŁA�Z�i�j���j�̎��҂Ƃ��Ă̖��i�j���̌����̏����j��_�i�����Čď̂�����̂ł��B�����w��A�ɔg���Q�����\���A���c���j�A�܌��M�v�炪���{�ɏЉ�܂����B
�@�Ƃ肽�ĂĒ����ł��Ȃ��A���ʂȐl������킯�ł��Ȃ��s��̐l�X�ɒ��ڂ��āA���̐l���ɐ[�����荞��ł݂�A�Ƃ����ނ̃��|���^�[�W������D���ŁA�����������͈̂������Ȃ��ǂ݂����B
�@���̏ꍇ�A��l������芪���l�X�⎞����Ȃǂɒm�����Ȃ������肷��ꍇ�������̂ŁA���̂�������܂��I�m�ɓǂ݉����Ă������Ƃ��̗v�������肵�܂��B
�@���̖{�̏ꍇ�����l�ŁA�����o�ꂷ��l�ԊW�̈���ǂ݉����܂ł͑�ςł������A������N���A����Δ��ɋ����[���ǂݐi�߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���Ȃ����猩�����̍���҂́A�����̂����тꂽ�A�����}���ɗ���̂������ԋ߂̂悤�Ȑl��������܂���B�ł��A���̐l�ɂ́A����A���̐l�ɂ��A���\�N�Ɛςݏd�˂Ă������̐l�̐l���Ƃ����A���ɂ��ウ���������̂�����͂��ł��B
�@�Ⴂ���Ȃ��ł����A�����������Ƃɂ������ł����ł�����z���͂����Ă݂Ă͂������ł��傤�B
�@�������邱�Ƃɂ���āA���܂܂Ō����Ȃ��������̂������Ă��邩������܂��A�l�ɑ���ڂ������ς���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�i�Q�O�P�P. �X. �R�@�ǁj

|
 |
�u�C�̂��Ȃ��̍b�q���@����E�{�y���A�ւ̋F��ƂT�Q�N�ڂ̑S�����e�v
�@�@�@�s�c ���@���@�@�@�o�t�Ё@�@�@�P,�U�O�O�~�{��
�@�@�@�Q�O�P�O�N�P�Q���Q�U���@��P�����s
�@��X�Q��S�����Z�싅�I�茠�����B�X�^���h�Ŗ苿���u�n�C�T�C��������v�̃����f�B�Ǝw�J�̉��B�P�R�|�P�Ƌ���̑�ʃ��[�h�Ō}�����X��B�G�[�X�E���ܗm������͍Ō�̑Ŏ҂�Ӑg�̃X�g���[�g�ŋ�U��O�U�ɐ��ĂƂ����B����́A���Ɩ싅�������������j�����̒��N�̖������Ȃ����u�Ԃ������\�\�B
�@�E�E�E�Ƃ����A���Z�싅���m�B�����Ă̐^������ɍ��Z�싅���̂�ǂނƂ����̂��܂��I�c�Ȃ��̂ł��B
�@�Q�O�P�O�N�͉��ꋻ�썂�Z���t�ĘA�e�𐬂������܂������A����܂ł̉��ꍂ�Z�싅�E�ɂ͋��̓��̂肪����܂����B���Z���P�X�T�W�N�̉Ă̑�S�O��L�O���ɏo�ꂵ�Ă���T�Q�N�ڂ̉Ăł����B
�@���̊ԁA����싅�̋����̂��߂ɐs�͂����̂��A����싅�̕��Ƃ����鍑��K�P�B���̏Ă��쌴�̒��ŃL���b�`�{�[�����n�߁A��̌R�ɓ��������Č𗬎������Z�b�g���A���{�̍��Z�싅�E�̏d���ɖ싅�̎w���������肵�Ȃ���A���Ɏ��Z���L�O���ɏo�ꂷ��`�����X������܂����B
�@���o��́A����̖{�y���A�ɐ旧���ƂP�S�N�B����A�������������싅���u�{�y���A�v�����킯�ŁA���������̐s�͂ɂ����̂������Ƃ����킯�ł��B
�@���̖{�́A����ȍ���𒆐S�ɁA���Ď��Z����b�q���o����ʂ����������̑I��₻�̌�̍��Z�Ŋē߂��l�����Ȃǂ���ނ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł��B
�@�����������|���^�[�W���Ƃ����̂͂���܂łȂ����������ɁA�����[���ǂނ��Ƃ��ł��܂����B
�@���Ȃ݂ɁA���N�Q�O�P�P�N�̉Ă̑��ɏo�ꂵ���������Z�͏��o��ł������A���Z�����o����ʂ������������A�������Z�����͗D�����̈�p���������ƂȂǂ̋L�q�������āA��������߉��\�N�ł��b�q���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂��B
�i�Q�O�P�P. �V.�Q�V�@�ǁj

|
 |
�u�ČR�����̉���@�A�����J���i��[�j�̋L���v�@�@�@�X�� 歁@���@�@�@������
�@�@�@�P,�U�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�P�O�N�P�O���P�O���@��P�����s
�@�P�X�T�O�N�ォ��V�O�N��ɂ����āA���{�{�y�����x�o�ϐ��������đ���n�߂Ă������A����͂܂��A�A�����J�̎x�z���ɂ���܂����B
�@����Ζ{�y�ɂƂ��ĉ���́A���{�̗��j�N�\��̋ɂȂ��Ă���킯�ł����A���̂��Ƃ߂�悤�ɁA���X�̋M�d�Ȏʐ^�ƁA�P�X�T�U�N�ȍ~�����Ɖ����������Ă������҂̏������͂��D��d�Ȃ�A���̐Â��ȓ{�肪���܂��\������Ă��܂��B
�@�T���́u�ʐ^�����ČR��̉��̉���v�B
�@�Î�[��n�̃Q�[�g�t�߂��Ԃ���X�q��U��Ȃ�����������ɍs���A�C�[���n���[�A�u���B�͓��{�l�ł��v�̉��f���ƂƂ��ɓߔe�̖��g�ʂ���s�i���钆���������A�|�n�ŊC��n���Ēʊw���鉜�����̒j�q���w���ȂǁA���Ă��Ă��̎�������݂��݂Ɗ����邱�Ƃ̂ł���ʐ^�������B
�@�Ƃ�킯�Ռ��I���Ɗ������̂́A�n���Z���a�䂦�ɑ��͂���łQ�V�N����l�ŕ�炷�V���Ƃ��̑e���Ȋ����̏������B�����ʐ^�B�����疳�m��Ό��ɂ����̂������Ƃ͂����A����͂Ȃ����낤�Ƃ�����܂ł��₵���v�������܂��B
�@�U���́u�Ȃ��Ƃ߂�L���̂��߂Ɂv�́A���҂̎�ɂ��܁X�̋L�����S�B
�@��ې[�������̂́A�u�L���̒��ɐ�����l�X�v�Ƃ��ď����ꂽ�A���炩�̌`�Œm�ȂȂ�������łɖS���Ȃ��Ă��܂����l�����ւ̒Ǒz�B
�@�ߓc�m��A��ÍN�Y�A����N�v�A�����ɓs�q�A���`����P�O�l���f�ڂ���Ă��܂��B
�@�ߓc���̍��ł́A�F�l�̒ʋΓr��ɂ����ƕt���܂Ƃ����������Ƃɂ��Ă����������̘b����B���҂���u����ł͎��҂͒��ɂȂ��Ă��̐��ɂ�݂�����v�Ƃ����b������Ă������̗F�l�́A���̒��������͖S���W���[�i���X�g�ߓc�m��̉��g���Ɗm�M�����\�\�Ƃ����b����A����͎n�܂�܂��B
�@���҂������鉫����߂����Ă̍l���́A���N�̎�ތo���Ƃ������肵����ӎv�z�Ɏx�����Ă��邽�߂��A�ꌾ�ꌾ�����ɏd���A��邬������܂���B�ŋߓǂ�ł������̂Ƃ͂��łɎ������Ⴄ����������̂ł��ˁB
�@�_�]�Ƃ������̂͂������肽�����́B�܂��͏����҂̐S�̖{���Ƃ������̂��悭�����Ȃ���˂��B
�@������t�����˂���܂킵�āA�����ǂ����I�Ɛ������ďo�����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��ȁB
�i�Q�O�P�P. �T. �V�@�ǁj

|
 |
�u�u���d�R���O���v�̌n���v�@�@�@�O�� ���@���@�@�@��R�ɂ₢�ܕ���
�@�@�@�P,�X�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�P�O�N �U�� �P���@��P�����s
�@���d�R�n���͐̂���A���Ƃ��ƏZ��ł����l�����ȊO�̐l�X������A���d�R�炵���Ȃ����ƂȂ����܂����a�������ĎЉ�����肠���Ă������j������A�����������Ƃ���悭�u���d�R�͍��O�����v�Ƃ����邻���ł��B
�@���̐̂ɂ́A�u�������v�Ƃ����āA�Ŏ��̊m�ۂ�l�������̂��߂ɉ����̈ꑶ�ɂ�鋭���ڏZ���s���A�u����߁v��u�܂������߁v�Ȃǂ̔߂������w�▯�b�����܂�܂����B
�@�܂��A�����̔p�˒u���Ȍ�ɂ͑�a���Ƃ�����l�X�������Ă��āA�����Ƃ⏤�ƁA�J�c�I���ƂȂǂ������A����{��������A�p�˂Ř\����������ߔe�̎m��������Ă��āA�A�������ƂȂǂ̏��Ƃ������炵�܂����B
�@��������������́A�����𒆐S�Ƃ��鋙��������Ă��āA���̉��Z�܂����玟��ɒ�Z����悤�ɂȂ�A����ɏ��a�ɓ���ƁA��p�����{�̐A���n�ɂȂ������Ƃ���A��p�l���p�C���␅���ɂ��_�@�����������Ĕ_�ƈږ��Ƃ��ē��A���Ă��܂����B
�@�펞���ɂ́A���ꌧ�̐U���v��Ɋ�Â��{������J��ږ����s���A���ɂ����Ă��H�Ɠ��ČR��n���݂ȂǂƊ֘A���ĊJ��ږ��������������Ă��܂����B
�@�����́A���̂悤�ȁu���d�R���O���v�ɂ��āA���I�ȗ̈�ƁA���҂̎��I�ȗ̈�̂Q��������܂Ƃ߂��Ă��܂��B
�@���I�̈�Ƃ��Ă̑�P���́A�ߐ��ȗ��̓`���I���d�R�Љ�A���̊O������ǂ̂悤�ȃC���p�N�g���A�����Ɏ������̂��ɂ��āA���d�R�ږ��̗��j�����������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@�܂��A��Q���ł́A���҂̑c���ł��莩�g�����ł������O�ؐꑾ�Y�𒆐S�ɁA�l���Ő��܂ꂽ�ꑾ�Y����p���o�R���Ĕ��d�R�ɒ蒅���Ă����O�Ղ�`���Ă��܂��B
�@�P���A�Q���Ƃ��ɓǂ݉��������Ղ�ŁA�����ɋL����Ă����l�ЂƂ�̂��܂��܂ȕ����w�͂́A���d�R�̐��j�ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��ɂ���A���j�̍r�g�ɂ��܂�Ȃ���e���̐���t�����Ă���p���_�Ԍ����A�������܂����B
�@��͂���j�Ƃ������̂́A�~�N���̗��ꂩ�猩���ق������͂����邵�A�g�ɂ��݂���̂Ƃ��ė����ł�����̂Ȃ̂ł��ˁB
�@�������E�ł���P���ł��B
�i�Q�O�P�P. �S.�Q�S�@�ǁj

|
 |
�u����̐V���Đ� �����f�B�A����̐����c��������āv�@�@�@��ÒC���@��
�@�@�@�V���o�Ł@�@�@�X�T�Q�~�{�Ł@�@�@�Q�O�P�O�N �P�� �X���@��P�����s
�@�����V��Ђ̂͂��ʂ��Ј��ŁA��\������В����Ō�ɑޔC�����o�������������҂ł��B
�@������̉��ꌧ���V���E�����[�h���Ă�������^�C���X�Ɨ����V��̂Q�Ђɂ��āA�S�O���N�̐V���А����Ō��������Ă����̌������ƂɁA���̌���Ɖۑ��T��\�\�Ƃ����̂��{���̂˂炢�ł��B
�@��P�͂́u���^�u���ƕs���v�v�́A�Q�Ђɂ܂�邢�����b�B�P�X�X�W�N����ɍs��ꂽ�A���ЊԂŋɔ闡�ɐi�߂�ꂽ�V������̋��Ɖ��ɂ��Ẵh�L�������g�ł��B
�@����^�C���X�̃��C���o���N�ł��问����s���A���z�̔�p�����������H��������o�����Č��݂��Ă͂ǂ����A�Ƃ����Ă������������̂�[���ɁA���ꂼ��̉�Ђ����ɐ����c�邽�߂̑Ë��_�����o���ׂ��A���ʉ��Ō����̒������s��ꂽ�l�q�����X�����`����Ă��܂��B
�@���ǂ͎������Ȃ������킯�ł����A���̌㗼���͗[���̔��s��f�O����ȂǁA�ꂵ���������Ă���悤�ł��B
�@�����ɂ́A���R�ȗ���ŋ������Č����A�ǎ҂ɂ��ǎ��ȋL����͂��邽�߁A�ߓ������ɂȂ�悤�Ȗ��ʂȏo������߁A���Ёu���ʂŏ����v���Ăق����Ɗ肤����ł��B
�@��Q�͂͂����Ƃ��炩���Ȃ�A���҂ɂ��u��z�u�킪�l���v�v�B�S�S�N�Ԃɂ킽���ċȐ܂����ǂ����g�Ԃ��ҋƁh�̒��ł̎v���o�̂��ꂱ��ɂ��āA�����V�̑��Ɍf�ڂ������̎��X�̃��|���������Ắu���炭����z�L�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���a�V�c�u����v�̕���u�������v�̌��o���ɂ������ƂŎ�N�����^�ۗ��_�̓^����A����C�m���J��i�P�X�V�T�j�̍c���q�v�ȖK���̍ۂɔ��������Ђ߂��̓��Ή��r�����̎�ދL�ɉ����A�k���N��A�����J�̖K��L�A�ސE��̃I�[�X�g�����A�V�w�̂Ƃ��̂��ƂȂǂɂ��Ă��L����Ă��܂��B
�@�V���Ђ́A����������̓������ȂǂƂ������̂͂��������o�ł���Ă��Ȃ��̂ŁA�����[���ǂ܂��Ă��������܂����B
�i�Q�O�P�P. �S.�P�W�@�ǁj

|
 |
�u�q�ߑ㉫��r�̒m���l�@���ܑS���̋O�Ձv�@�@�@���Ô� ���@���@�@�@�g��O����
�@�@�@�P,�V�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�P�O�N �R�� �P���@��P�����s
�@���ܑS���́A���������ȍ~�A�����A�ČR��̊��܂ł̉ߍ��Ȏ�������������y�j�ƁB�ɔg���Q�Ⓦ���[���Ղ�ƌ𗬂��A�鍑��`��i�V���i���Y���Ɛ킢�Ȃ���A����̋ߑ�v�z�����[�h�����l���ł��B
�@����w�̌n����T��ƁA�ߑ㉫�ꏉ���̑��c���~�A�Ӊԏ��ɑ����Ĉɔg�Ⓦ���[�A�^���������炪�o�ꂵ�A����������w�̑�ꐢ��Ƃ���A���̉e�����đ��Ƃ��Č����ɓ��������̂��A��Ït���A���钩�i��A���ܑS�������������Ƃ������Ƃł��B
�@���̂Ȃ��ł̓��܂̈ʒu���́A��Â���邪�ɔg����c���j�̈��|�I�ȉe���̂��Ɠ����Ō����ɓ��������̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA����̒��Ő������Ȃ���A����ŋN���錻���ɑΏ����Ȃ��猤���������y�����҂������A�Ƃ����Ƃ���ɂ���̂������B
�@�{���ł͂���ȑS���̋O�Ղ�ǂ��A�ނ̋Ɛт�v�z�̕ϑJ�𖾂炩�ɂ��܂��B
�@���M���ׂ��Ȃ̂́A�ނ�ǂ��Ȃ�����A�����̏₻��ɔ�������Љ�S�̂̎v�z�I�ȗh�ꓮ���A�ނ̎��ӂ̉���v�z�����҂̓����Ȃǂ܂ł��������ɋL�q����Ă���A���ꂪ���e��[�������[�����̂ɂ��Ă��邱�Ƃł��B
�@�S���́A����̔g�ɂ��܂�A��w���ƌ�ɉ��ꖈ���V���L�ҁA�ߔe�摍���ے��A�ߔe�s���������w�Z�Z���A�ɔg�A�^�����Ɍp����R�㉫�ꌧ���}���ْ����C�B
�@�����_���̗]�g�������ނ�}���ْ������C������́A�����J�쒆�w�Z���@�A�ߔe�s��c���A�I���̎��e���������o�ĉ��ꖯ���{���[���A�����V��ҏW�ǒ��A�����������ی��ȂǂɏA���A�P�X�T�R�N�Ɏ����B
�@�܂��A�S���́A���K�v�̖��ʼn��ꕶ�|�E�ł������l���ł���A�����̂Ȃ��ł��S������̒Z�̂����������ň��p����Ă��܂��B�ނ̑��ʂ������̂��ƂƂ��ɁA�_�l���Ƃ��Ă̈��̌��ꂵ�����a�炰���Ă��܂��B
�@�l��ǂ��A���̎��オ�ɂ��ݏo�Ă�����̂��\�\�Ƃ����l���̂��Ƃɖ{��ǂ�ł���䂪�g���炷��A����Ȃ������낢�{�ɂ͂Ȃ��Ȃ��o�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA���߂��߃��J�b�^�I�ƈ�l�ق�����ł���Ƃ���ł��B
�i�Q�O�P�O.�P�P.�Q�R�@�ǁj

|
 |
�u�K���I�A���w���̑��Ձv�@�@�@�K���I�A�E�t���u���C�g���ꓯ����@�ҁ@�@�@�ߔe�o�Ŏ�
�@�@�@�Q,�O�X�T�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�W�N �X�� �V���@��P�����s
�@����E����Ԃ��Ȃ��P�X�S�X�N����A����̓��{���A��ڑO�ɍT�����P�X�V�O�N�܂ł̂Q�P�N�ԂɁA�č����R�Ȃ̏��w�����ŃA�����J�̑�w�ɔh�����ꂽ���ꗯ�w�������̑��Ղł��B
�@���v��X�O�O�l�����̐��x�ɂ���ė��w���������ŁA���̖{�͂��̂����T�T�l���A�����̎v���o��A���w��̕��݁A�����Ă��̕č����w���x���̂��̂ɑ���]����l�I�E�Љ�I�C���p�N�g�Ȃǂ�Ԃ����G�b�Z�[�W�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�ǂ�ł��Ĉ�ې[���̂́A�Ƃ�킯�����̗��w�������̃A�����J�ɑ������ہB�ނ�͂�������ČR�̌R�͂ł̒����D���ɂ���ăT���t�����V�X�R�ɓ��`���܂����A���̂Ƃ��Ɍ����S�[���f���Q�[�g�u���b�W�i���勴�j���ƂĂ���ې[�������悤�ŁA�W�O�ΑO��̔N��ɂȂ������ł������̐l�����̂��Ƃ��L���Ă��܂����B
�@����ŃK���I�A���w���x���ʂ����������ɂ͂��낢��Ȍ������������āA���R�Ȃ��痯�w�������͉���̌��㉻�ɑ傫�Ȗ������ʂ������Ƃ������̂�����ق��A�ނ�͂���A�����J�̌����Ȃ�ɂȂ��Đ��̉�����������Ă����Ƃ����ᔻ�I�Ȍ�����������悤�ł��B
�@�������A�ނ�͂���Ȃ��Ƃ͂ނ���l�����A����̏����ɂƂ��Ď����͂ǂ̂悤�ȍv�����o���邩���l���A�_�̎u�������Ė����̒n�ɓ��ݏo���Ă������̂ł��B
�@�����͂��̂悤�ȁA��҂̃t�����e�B�A���_��A���Ƃ��Č��t���ʂ����s���ł����ς��̏ő��A�܂��A�����A�����J�̐����ɂȂ���ňӋC�g�X�Ƃ��ē��X���߂������l�q�Ȃǂ���Ɏ��悤�ɂ悭�킩��A���̂�������̎Ⴂ�Ƃ��͂����������̂��Ȃ��ƁA���ƂȂ��Ă͔��܂�����������܂��B
�@���w�������̏��炵���S�҉������ŁA���ꂪ�т�����ƂR�P�T�y�[�W�B�Ȃ��Ȃ��ǂ݉���������܂����B
�@�o�ꂷ�钘���l�́A�����ꌧ�m���E��c���G�A�����ꌧ���m���E��Ê��Y�A���O�q�A�q��_���A������w���E���율�L�A�W�����J�r���Ɛ약���p�̕��E�약�����ȂǁB��ɑ�w�W�ɐi�҂����ɑ������Ƃ��킩��܂��B
�@�����������j�I�������āA����������p���ł����Ȃ��ƖY�ꋎ����̂ŁA���̈Ӗ������������M�d�ȏ��ЂƂȂ��Ă����͂��B
�@���ɂ͎��Ȗ����I�ȋL�q���Ȃ��킯�ł͂���܂��A�S�̂Ƃ��Ă����h�L�������g���Ȃ���Ă��܂��B�����Ƃ��ẮA�����{�ɂ߂������Ƒf���Ɏv���܂��B
�i�Q�O�P�O.�P�O.�P�P�@�ǁj

|
 |
�u���啨�� 1947-1972�v�@�@�@�R�����ȁ@���@�@�@�����V��Ё@�@�@�P,�V�P�S�~�{��
�@�@�@�Q�O�P�O�N �Q���P�W���@��P�����s
�@�ȑO���甃�����Ǝv���ă}�[�N���Ă����̂ł����A�l�b�g�V���b�v�łQ�x�̕i��L�����Z���B�x������v���ł����Ƃ���A����K�⎞�ɏ��X�Ŕ����I�@����K���Ƃ���ɔ����Ă��܂����B
�@������w�́A�قȂ����`�������̍����ɂ��g�n�C�u���b�h�ȁh��������@�ւƂ��ĂP�X�T�O�N�Ɏ�Ւn�ŎY���������Ĉȗ��A�l�Ԃł����u�җ�v���}����킯�ł����A���̐ݗ��o�܂�w�i�̏ڍׂɂ��ẮA����܂łقƂ�ǂƌ����Ă����قǏ�����Ă��܂���ł����B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃɂ��ď������Ƃ́A�����㕶���j�𗝉����邽�߂ɂ��s���ł���B�\�\����ȋ����[���e�[�}�������ď����ꂽ�̂��A�{���ł��B
�@��w�a���̍ۂ̗��O���w�̍\���Ȃǂ��A�����Ȃ�ΐ����̐��Q�i�t�����e�B�A�j�^����A�����J�̊g���v�z�ɕ����������ƁA�����āA��w�ݗ��v��ɂ̓n���C�̉���n�Љ�̎w���҂������[���֗^�������ƁA�܂��A��w�̉^�c���A�~�V�K���E�~�b�V�����ƌĂ��~�V�K���B����w�̋����c�̋��͂ɂ���čs���Ă������ƂȂǁA����܂ł��܂蕷�������Ƃ̂Ȃ����������[�������������L�ڂ���Ă��܂��B
�@�����V��̕����ʂŁA�Q�O�O�W�N�P������P�P���܂łS�O��ɂ킽���ĘA�ڂ��ꂽ���͂����M�A�C�����ď㈲�����Ƃ����Ȃ��Ȃ��̗Ǐ��B
�@���Ƃ����ɂ͎��̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B
�u����̗��j�́A����̐��Љ�̗��j��F�Z�����f����B���̂悤�ȗ��j��m��A���̒a���Ɛ����̕������邱�Ƃ́A����ɏZ�ގ��������g�̗��j��m�邱�ƂƏd�Ȃ�B
�@����́A���܂������̕���ł���B���ꂩ����⊮����A����������A�f�B�e�[���߂Ă����d�����������Ƃ��낤�B
�@�{�����A���̂悤�Ȗ����Ɍp�������d���ɍv��������̂ɂȂ�̂ł���A����͖]�O�̊�тł���B�v
�@�\�\���j�̋����Ƃ́A������������܂ʓw�͂������Ă̂��́B���ЁA���������Ăق������̂ł��B
�i�Q�O�P�O. �U. �T�@�ǁj

|
 |
�u��̓��̍b�q���@���d�R���H�̉āv�@�@�@����T���@���@�@�@�o�t����
�@�@�@�T�X�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�X�N �U���P�S���@��P�����s
�@����̗������Ƃ��ď��߂āA�Q�O�O�U�N�t�ĘA���ōb�q���ɏo�ꂵ�����{�œ�[�̍��Z�E���d�R���H�B�D����E���S�����͂��߂Ƃ����I�肽���͑S�����d�R�Ő��܂��������̎q�ŁA���w���̍�����Ɏu��g���ē̌������w�����Ă��܂����B
�@�u���d�R����b�q���ցv�Ƃ��������̖��ƁA�ǂ�����������ʂ̉Ƒ��łł����邩�̂悤�Ȕ��d�R���H�싅���̕����Ԃ����m���t�B�N�V�����ł��B
�@����܂Ń^�C�̈��h�����A����a�ɜ늳���ĉ���Ɂg�ʂ����h������l�q�Ȃǂ�Ԃ��Ă������҂ł����A����ǂ͂��̐��_�I�ɂɂ���悤�ȍ��Z�싅�������Ƃ����̂ŁA���͂��̖{���̂��S�O���Ă�������������܂����B
�@�������A�ǂ�ł݂ăi���z�h�Ɣ[���B�����ɗ���Ă����C���̓J���y�L�ɂ��`������ł����B
�@�����Ă��Ȃ��Ȃ����̋C�ɂȂ�Ȃ����̍��Z���̗l�q�B
�@�~�X�����镔���Ɂu���ˁI�v�Ɠ{�����ēƁA�u���O����Ɏ��ˁv�Ƃ��Ԃ����̕����Ƃ̊Ԃɗ����u���ˁv�̈Ӗ��ƉƑ��I�e�����B
�@��Ђ����߂Ă��܂��Ăł��b�q���ɉ����ɍs���Ă��܂����l�B
�@�ƋƂ𓊂��ł��A�ȂƗ��������Ăł����z�W���~�Ŋē������Ă��܂����K���o�B
�@�A���v�X�X�^���h���u�n�C�T�C��������v�����n�߂�ƁA�s�v�c�Ɛ������o�Ă��܂��I�肽���B
�@�E�E�E����܂ŁA���̂悤�ȒE�͓I�ȃA�v���[�`����X�|�[�c���������m���t�B�N�V�����Ȃ�āA�Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA���̂悤�ȏ������́A����T���ɂ����ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�ނ���A���Z�싅���Ƃ����Ĕ��d�R�̌�����s���D�������Č������A�ƌ������ق����K��������܂���B
�@�~�Y�m�X�|�[�c���C�^�[�܍ŗD�G��܍�i�B
�@�y���߂��P���B�o�t�Ђ��當�ɂŏo�Ă��܂��̂ŁA�C�y�ɓǂ�ł݂Ă͂������ł��傤�H
�i�Q�O�P�O. �S.�Q�P�@�ǁj

|
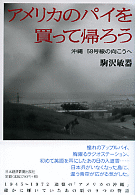 |
�u�A�����J�̃p�C���ċA�낤�v�@�@�@���q��@���@�@�@���{�o�ϐV���o�Ŏ�
�@�@�@�P,�V�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�X�N �T���Q�T���@��P�����s
�@�Q�O�O�X�N������P�O�N�����ɂ����ēǂ݂܂����B����A�����{�ł����B
�@�܂��̉���A�t�F���X�z���ɒ��߂���n���̎Ő���O�l�Z��̗l�q�B���������m�N���Ő蔲�����\���ʐ^���A���̖{�̓��e��I�m�ɕ\�����Ă���悤�ł��B
�@����́A��������{�����������Ȃ��Ȃ�A���̑���ɔ������������ٖ����������ɂ���ė������̉���B�A�����J�̕��������ꂪ�~�߂���ǂ��Ȃ邩��ǂ����߂������[�����|���^�[�W���ł��B
�@���ł͂����킸�������c����Ă��Ȃ����Ղ�[���ɏ����ꂽ�A���{�ɕ��A����ȑO�̉���̎p����������o�ꂵ�܂��B����ōŏ��ɃA�b�v���p�C���Ă����̂͒N�������̂��B�A�����J�O�`�ƌĂꂽ���ꕗ�̉p����A�ނ�ޏ������͂ǂ̂悤�Ɏg�����Ȃ��Ă����̂��B�������~�������̃z�[�N�ʋl�́A���̌ア���ɂ��Ă��ٓ��̎���̍���D���܂łɂȂ����̂��B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ̎��ӂɂ������ߊ���X�̃G�s�\�[�h���ЂƂ��d�˂Ă����ƁA����ƃA�����J���݂��Ɏ����荇���Đ������ꎞ�����A�₪�Ĉ�b�̒n������ɕ����オ���Ă����A�ƁA���҂͏q�ׂĂ��܂��B
�@�S�X�́B��P�͂ɒu���ꂽ�u�A�����J�̃p�C���ċA�낤�v�͏G��B��`�̔��X�ŃA�b�v���p�C���܂Ƃߔ�������E�`�i�[���`���Ǝv����j�B���̂i���������f���̃A�b�v���p�C�́A������������Ă��Ȃ����̂́A�A�����J��������̖��������̂ł����B
�@�ŏI�͂́u���̃��W�I�X�e�[�V�����j�r�a�j�v���܂��G��B�q�a�b�̎Љ����ɂ������p������ǂŁA�ČR�̂Ɠ��������b�N�����[���o���o���̕����ǂ��x�����j�ƁA���̂��Ƃ����݃E�F�u��ŏڍׂɏЉ�Ă���j�̘b�ł��B
�@�ق��ɁA�A�����J�O�`�ɂ��ď����ꂽ�u���݂͏������̂ŃV���[���[�ƌĂꂽ��v�A�ČR�ɂȂ����l�C�̂b��������ԉ��ɂ��Ắu�Î�[�R�l�̃\�E���t�[�h�v�A�X���u���[�ɂ��Ắu�̔��ł�����������v�A�u�����̓|�[�N�ʋl�̃o���b�h�v�A�u�Ō�̋��s�z�e���v�A�ČR�̃L���X�g����Ɛ�����q�t�̘b�́u������̂ĂĐ푈�ɂm�n�Ɖ]���v�A�u�Ő��̂���O�l�Z��v�B
�@�R�U�̋��s�ό��z�e�����āA�Q�O�O�V�N�P�O���������Ĕp�Ƃ��Ă����̂ł��ˁB������ƃV���b�N�ł��B
�@�A�����J�Ƌ��ɂ��������̂ЂƂƂ��A�m���ɋP���Ă����ƁA��ނ����l�����͌��𑵂��������ł��B����܂ł͎��ɂ��Ȃ��������y��A���߂ĐH�ׂĂ݂����B����ƕ|��ƁA�G�ӂƍD��S���Ȃ��܂��ɂȂ����𗬂̂Ȃ�����A��ՂƂ����v���Ȃ��悤�ȕ�����l�Ԃ̊W�����܂ꂽ���Ƃł��傤�B
�@����ȁA�A�����J��ɕK���Ő���������́A���̎������߂������E�`�i�[���`���ɂƂ��āA���������̂Ȃ��L���ƂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�R���N���[�g�E�u���b�N�̌����A��n�̘e�ɗ��z�e���A�h���C�u�C���̂悤�ȍ\�����c���n���o�[�K�[�̓X�E�E�E�B�T�W���������ɕ��ԓX�܂�Ɖ��͖����ɃA�����J����̋�C���c���Ă��܂����A���̑����͘V�������B���Ȃ��Ȃ��Ă���A�₪�ď����䂭�^���ɎN����Ă��܂��B
�@���������A����������ɂ͂܂荞�P�T�N�قǑO���v���N�����ƁA���ł͂������莸���Ă��܂������̂�����ɂ͂����ɑ������Ƃ��B���ƂP�O�N�����Ȃ������ɁA����炪�V�������̂ɕς���Ă����Ă��܂��̂��Ǝv���ƁA�Ȃ�Ƃ���肫��Ȃ��A�m�X�^���W�b�N�ȋC���ɂȂ�܂��ˁB
�i�Q�O�P�O. �P. �P�@�ǁj

|
 |
�u���ҁ@����n�E����̐����ؐl60�N�̋L�^�v�@�@�@�㍪�ہ@���@�@�@���~�Ƀ��l�b�T���X
�@�@�@�P,�U�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�W�N �V���Q�X���@��P�����s
�@���҂́A�����v�ƊE�̗Y�Ƃ��Ē����ŁA���O�W���A���[�r�W�l�X�ł͍��ێЉ�̑����Ŋ������Ă����Ёu�J�~�l�v�̉����B�������A��������܂ŗ���ɂ́A�����̎����ɂāu�����ĕK���̋��A��v�̂��Ƃ����������ӂ������o�����������̂ł��B
�@�����m�푈���A���\��s��ɔh�����ꂽ�q��ǐE���E�㍪�́A�ߔe�̏\�E�\��P��ɂ͖{�ƂƂ͂��������̌@���Ƃɏ]������Ȃǂ��Ȃ���A�C�R�i�ߕ����Ɉڂ��Ďd�������Ă��܂����B
�@���̌�͑��̕��m�A�R���A���ꌧ���Ɠ��l�̌o�܂����ǂ�E�E�E�B�W�c������ڂ̓�����ɂ��A���{�R�̑g�D�I��R������Ƃ��g�̂ɏ����Ȃ���{������H����H�킸�ŕ��Q���A�P�N�ȏ�ɂ��y�Ԏ��e���ł̐����������Ƃ������Ƃł��B
�@���̗l�q�́A��P�́u��ꂩ��̋A�ҁv�Ƃ��āA�S�̂̔����ȏ�̃y�[�W�������āA�����̎v���ƂƂ��ɍ����ɋL���Ă��܂��B�����ɂƂ��Ă͂��̏͂�������̓ǂ݂ǂ���ł����B
�@�Ă��쌴�ƂȂ����̋��_�ˁE�O�{�ɖ߂�A�ƋƂ̎��v�����p���Ō��݂̊�b��z���������Ԃ�����Q�́u�o�ϕ����ƂƂ��Ɉ�����v�A��_��k�Ђɂ���đ�_���[�W���A���̋���K���ɗ����オ���R�́u���ő�̍ЊQ����̕����v�Ƒ����āA���̌�͎��ƊE�Ŋ������Ɍ����芴�����肵�����Ƃ��L������S�́u���Ƃ̕i�i�͗��j����ށv�A��T�́u�푈�́A�����ǂ����ő����Ă���v�Ŋ����B
�@���������̒��ҁA�ؗ�Ȃ̂��オ��Ԃ�̉A�ŁA�l�X�ȍГ�ɑ����Ă���悤�ł��B��ΓD�_�ɍ�_��k�ЁB�k�Е�����P������A����Ɗ��������V�X�܂Ƀg���b�N���˂����݁E�E�E�B�C�̓łƂ��������悤������܂��A�Ȃɂ����I�Ƃ����A�{�Ó��Ō����Ƃ���̃A�����K�}���_���A���̓s�x�A�����J�������悤�ł��B
�@�푈�Ƃ����n�[�h�Ȏ���������Ă����q�g���āA����ς苭���̂ł��ˁB����Ȃ烁�Q�Ă��܂����������Ȃ��B
�@������ɂ���A���̐l�Ɍ��炸�A����l�Ԃ̈ꐶ�Ƃ������̂͂������낢�B��⏑����̎�O���X�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ��������̂ł��傤���A����͍�������������{�͍D��œǂ�ł��������Ǝv���܂��B
�i�Q�O�O�X.�P�Q.�Q�X�@�ǁj

|
 |
�u���� ����ɂ������ꂽ���Ȃ��������j�v�@�@�@��������@��
�@�@�@�W�p�ЃC���^�[�i�V���i���@�@�@�P,�X�O�O�~�{��
�@�@�@�Q�O�O�W�N �X���R�O���@��P�����s�@�@�@�Q�O�O�W�N�P�P�� �X���@��Q�����s
�@�i���f�X�J�A���̃C���p�N�g�̂���\���ʐ^�́H�I�@�����Ă��́A�U�T�O�y�[�W���̕������̍فI�@ ���̘J���Ҍn�̈��D����[��̓���ٓ����A�������͖����ȃ����K�u���b�N���̂��̂̂悤�ȏd�����ł���I
�@�\�\�Ƃ������ƂŁA��ʓI�ȏ��Ђ̗D�ɂQ�{���镶�͗ʂ̂���R�C�c�A�ǂނ̂ɂ����\���Ԃ��������Ă��܂��܂����B
�@�ł��A������ƌ����ē��e�͂܂�Ȃ��������Ƃ����Ƃ܂����������ł͂Ȃ��A������x����̍ו��ɂ��Ă������������Ă���Ǝv���Ă��鎩���ɂƂ��Ă��V�N�Șb�肪�����A�Ӂ`�ށA�i���z�h�i���z�h�Ǝv���Ȃ���ǂ܂��Ă��炢�܂����B����͂�A�ǂ݉����\���B
�w���͂��̎�ނŁA����܂ł܂��������ɂ��Ȃ������b�����т��������������B�ƂĂ��M���Ă��炦�����ɂȂ����i���e���Ŗڌ������B�{���ł͂��������S�[���`�����v���[���̂������Ϗ�Ԃ̂܂ܕ��Ă��������B�x�i�{�����j
�@��L���p�ɂ��ẮA��i�����͂܂��ɂ��̂Ƃ���ŁA���܂蓝�ꊴ�Ȃ����҂̋����A�����A�ؗ��ĂɊ�Â��ēW�J����Ă����܂��B���̂�����͏d���ŁA�ƂĂ��]���ł���B����A�ƂĂ��X�o���V�C�B
�@�������܂��A�O�i�́u���܂莨�ɂ��Ȃ������b�v��u�M�����Ȃ����i���e���Ŗڌ������v���Ƃɂ��ẮA���X��U���ł��傤���ˁB�i�j�@����ɏZ��ł���l�X�ɂƂ��Ă͂����炭�A�u�����A���̂��Ƃˁc�v�Ɗ���������̂������̂ł͂Ȃ����ȁB
�@���҂̗����ʒu�������A���O���I�ŁA����̖\�͒c��x�@����A�����E�̗��b�Ȃǂ�����̂��ƂɃA�v���[�`���Ă���̂ŁA�������ۂ�����ɂ��Ă��A�ǂ����Ă��A�e�̔Z����������������Ă��܂��Ă���Ƃ�����ہB
�@���̂��Ƃɂ͗��ƕ\������A������ł͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ�F�����ēǂޕK�v������̂ł��傤�B�łȂ��ƁA�����������Ƃ��肪����̐^�����ƍl���Ă��܂����˂Ȃ��̂Łc�B
�@�͗��ẮA�O�͓I�ʒu�Â��́u�V�c�E�ČR�E���ꌧ�x�v�A���ꃄ�N�U�푈���������u����A���_�[�O���E���h�v�A������E�̎l�V���ƌ�����l���Ȃǂ�ǂ����u����̉��l�E�ҏ��E�p���[�G���[�g�v�A����|�\�Ƒ��̃E�`�i�[���`���Ȃǂɂ��Ẵ��|�u�x�问���A�̂�����v�A�����̑����Ƃ��Ắu�����̉���E�����̉���v�̂T�́B
�@���Ƃ��A����^�E�����ꌧ�m���ɂ܂���b��m���I�̕��䗠�Ȃǂ荞�u����m���I�R���t�B�f���V�����v�Ȃǂ́A�ƂĂ������[���ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�@�Ƃ���ŁA���҂́u���Ƃ����v�ŁA�{���̕\���J�o�[���̎ʐ^�͚삵�����̒����猵�I���A���C�A�����ČR��n�Ƃ��������p�^�[�����������̂͂��ׂĔr�������A�����ēǎ҂ɂ́A�����̎ʐ^����A���҂��`��������������̑�������������Ăق����A�Əq�ׂĂ��܂��B
�@�������A�\���̃C���p�N�g����ʐ^�́A�P�X�V�T�N�ɖ{�����牓�����NJԓ��ŎB�e���ꂽ���̂ŁA�{���Ƃ͉��̊W���Ȃ����̂ł����B����A�C���[�W�B���|���^�[�W���Ȃ̂ɃC���[�W�𑽗p����Ƃ������̂悤�Ȗ{�̂��肩���́A�͂����Đ��������|�{�̂�����ƌ�������̂Ȃ̂ł��傤���B
�@�u����܂ł܂������Ƃ����Ă����قǏ�����Ă��Ȃ���������v�@����\�\�Ƃ������҂̈Ӑ}��ے肷����̂ł͂܂���������܂��A���̂��߂ɖ����̂Ȃ����̂�����g�ݍ��킹�ĕʂ̔��I�ȃC���[�W��ǎ҂ɗ^����A�Ƃ����悤�ȋ��́A�������Ė`���Ȃ��łق����Ǝv���܂��B
�@�E�E�E�Ȃ���āB�ƂĂ��~�[�n�[����i��I�ȗ��ꂩ�犴�z���m�x�Ă݂܂����B
�i�Q�O�O�X. �P.�R�P�@�ǁj

|
 |
�u��Ղ̃J�t�F ����u�l�ӂ̒����v����v�@�@�@���т䂤���@���@�@�@�͏o���[�V��
�@�@�@�P,�T�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�W�N �V���R�O���@��P�����s
�@�ߔN����ł́A�����̃J�t�F���嗬�s�B�����^�J�[�œ����߂���A������ꂽ�獑�����炿����҂�O��ĂЂ�����Ƃ������ރJ�t�F�ň�x�݂���E�E�E�Ƃ������X�^�C�����A����ό��̂������̂ЂƂƂ��Ē蒅������܂��B
�@����ȃ��P�[�V�����E�J�t�F�̉Εt�����ɂȂ����̂��A���K�̓��s�ʏ�́g������h�ɂ���u�l�ӂ̒����v�B�����m�̕��������Ǝv���܂��B
�@�킴�킴�{�y����K���q�����₽���A�܂��A���́g�l���h�̎��ӂɂ͓��|�ƁA�~���[�W�V�����A���o�ƁA��ƂȂǂ̌|�p�Ƃ��ڂ�Z��ł��Ă���悤�ł��B�����āA����͂Ȃ��Ȃ̂��H�Ƃ����̂����̖{�̃e�[�}�̂悤�ł��B
�@�ǂ�ł��Ċ�����̂́A�C�̂������Ŋό��q�����t���Ȃ��悤�Ȃ��̂悤�ȏꏊ�ɂ悭���������̂��Ȃ��Ƃ������ƂƁA�i���X�ɂƂǂ܂炸�Ɂu�̂�т葺�v���\�z������C��R���T�[�g����悵���肷�邱�̃I�[�i�[�̓^�_���m�ł͂Ȃ��ȁA�Ƃ������ƁB
�@�����A���̒��x�̊��z����ƌ���ꂻ���ł����A�߂������ȁA�܂��A�����Ȃ̂ł���B
�@�܂��A���́u�l�ӂ̒����v�ɍs�������Ƃ��Ȃ��A�Ƃ����̂��v���I�B�l���̐l�X�₻���ŋN����ӊO�ȏo�����ȂǂɁA����A���������E�E�E�Ɠ����ł��Ȃ��̂ł��ˁB
�@�����̗��̃X�^�C���́A���X�Ń\�t�g�h�����N�����ނ����R���r�j�Ń{�g���W���[�X����ق����S�n�悢���A����悩�r�[���̂ق��������Ƃ悢�B
�@����Ȃ��ꂪ��x�����A�u�J�t�F�E���邭�܁v�Ƃ����L���X�Ɋ�������Ƃ��������̂����ǁA���̎��͓X�̃}�j���A���`�b�N�ȃo�C�g����u�Q���ԑ҂��ł����E�E�E�v�ƌ����ĕ@���o�������Ă���B�Ȃ̂ŁB
�@���ꂩ��A����܂�����̏���Ȋ��z�Ȃ̂ł����A���̖{�̕\���X�^�C���Ɂg�N���h�̂悤�Ȃ��̂����܂芴�����Ȃ��Ƃ������E�E�E�B���|���^�[�W�����ɒW�X�ƕ\������Ȃ炻����悢�̂ł����A�����ł��Ȃ��B
�@���̂��߂ɂȂ̂��ǂ����A�����{��ǂݏI���Ċ�����A�u�����A���̖{�͂����������Ƃ��A���̂悤�ɁA�\�������������̂��낤�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ����܂��]���������Ȃ������̂ł��ˁB
�@�܂��A�S�̂Ƃ��āA���܂��܂���ɂ͂������肱�Ȃ������A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�������Ĉ��{�ł͂���܂���A�O�̂��߁B
�@������ɂ��Ă��A��x�͕l���̃����N�[�[�V������̌����Ă�����̂������ׂ��Ȃ̂ł��傤�ˁB
�i�Q�O�O�W.�P�P.�P�W�@�ǁj

|
 |
�u����Ɨ������`���̏��� �Ɖ��q�q�v�@�@�@���� �z�@���@�@�@���w��
�@�@�@�P,�T�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�V�N�P�Q���P�V���@��P�����s
�u����̓��͂��A�����܂ŗ����l�̂��̂ł���B���Ă͗��������������B�������{���ꍑ�̂悤�ɂ����B���܂���ȂB�v
�u�����͂��̉���̊C�ɖ{�i�I�ȗ{�B�{�݂����A�N�ԂT�O���h���ȏ�̎������グ��̂��킽���̖��ł���v
�@�������ԁA��㉫��̏������A�܂���l�B
�@���Ȃ���ɁA���s������āu����ɒj����v�ƌ��킵�߂��Ɖ��q�q�i�P�X�P�T�|�W�S�j�̔g���̐��U��`�����{�i�]�`�ł��B
�@���t�������Ő��܂������q�q�́A�c�����Čǎ��ɂȂ�A�X�����l�Ɍ������ċ��̍s���ɕ����A�P�U�ŃZ���x�X���i���X���E�F�V���j�ɋ삯����������A�P�X�ł̌������@�ɉ���ɖ߂�܂��B�����Đ��̍������A�a�J��̕����Ō����������ƒc�̏����̂Ƃ��Ė��������A��ɕČR��̉��̉���ɋA��A���d�Ƃ��v����V�K���Ƃ����X�Ɨ����グ�Ă����܂��B
�@���ےʂ�ł̔�v�E��ΓX�A�������͔̍|�A�{����̑����E�E�E�B
�@���āA�����}���ŁA���C�Ɠ����͂�����E�E�E�Ƃ����悤�ȃ��[�_�[�́A���Ƃ������Ȃ����͂����̂ł����A�E����������n�߂�ƐÂ��ɕ\���䂩�狎���Ă����P�[�X�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�ޏ������̂悤�ȃ��[�_�[�̈�l�������悤�ŁA�������ɂ͖Ŗ@�͂����邯��ǂ��A�����ɂ͉�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B
�@���Ƃ����������ɂ��������āA��������߂鑤�߂͈�l�A�܂���l�Ƌ����Ă����A���S�͂��ێ����邽�߂Ƀ��[�_�[�͂���Ɏ��Ƃ��g�����Ă����\�\�Ƃ��������z�B�ޏ������̂悤�ȏz�̒��ʼnh�͐����𖡂���Ă����܂��B
�@���Â��A�u����v�Ƃ������̂́A�l���������A�E��������̂��ȂƒɊ����܂��B����͍��̎���ł����Ă������ŁA�����̑O�܂ňꗬ��Ƃ̃G���[�g�������l���ˑR���X�g���ɂ�������A�ڋ߂ȗ�ł͏�i�Ƃ̐܂荇�������܂������Ȃ������ŗD�G�Ȑl�ނ�������Ă��C���Ȃ����Ă��܂�����A�Ƃ������Ƃ����������ŋN�������肵�܂��B
�@����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���ǂ��߂��A�Ō�܂Ŕ��R�Ƃ��Ȃ������̂��A���҂͏Ɖ��q�q�̐��U��ʂ��Ă�����������i�����������̂��H�Ƃ������ƁB
�@�q�q�̈̑�ȋƐтł��Ȃ����A����̔w�i�ł��Ȃ��B���̉���ł��Ȃ��B�����čő�́u�H�v�́A�\��ɂ���u����Ɨ��v�ɂ��ē��@����L�q���قƂ�ǂȂ����ƁB
�@�u�q�q�v�Ƃ����g���̐l�������������Ƃ͂悭�킩��������ǂ��A���āu�i�c�R�@���ꖧ�f�Ղ̏����v��ǂ�Ŋ������悤�ȁA�������炮�������ƍL�����Ă���������������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂́A���X�c�O�ł��B
�i�Q�O�O�W. �T. �V�@�ǁj

|
 |
�u�̉���Љ�j�@��ʂƖ��f�Ղ̎���v�@�@�@�Ό����Ɓ@���@�@�@���ߎ�
�@�@�@�Q,�W�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�O�N �P���Q�T���@��P�����s
�@���҂́A�P�X�S�P�N��p���܂�A���ꍑ�ۑ�w�̎Љ�w�̃Z���Z�C�ł��B
�@���҂́A���e����p�ɏo�҂��ɍs���A�Ζ���Ō��n���W����A���s�����Ƒ��͏I�헂�N�ɉ���Ɉ����g���Ă����Ƃ����ߋ��������Ă���A�������������߂�_�@�̈�͂��̂�����ɂ������̂�������܂���B
�@���A�^�ߍ����𒆐S�Ƃ������d�R�ƁA��p�Ƃ̊Ԃōs��ꂽ�Ƃ������f�Ղɂ��āA���ۂɖ��f�ՂɊւ���������̐l�X����،����W�߁A���̎��Ԃ��e�ׂɉ����������Ă��܂��B����͂�A�W�҂̏،��́A���X�������ɉ��ł��ȁB
�@�b�́A���d�R�E����ł̖��f�Ղ݂̂Ȃ炸�A�g�J���̌��V�������[�g�Ƃ��čs��ꂽ���{�{�y�Ƃ̖��f�Ղ�A����{���Ő���ɍs��ꂽ�Ƃ����ČR�����̂����ς炢�s�ׁi������u��ʂ��グ��v�Ƃ����j�ɂ��Ă����y����Ă��܂�����A��㉫��̍������̗l�q���ڂ����m�肽���Ƃ������͂��Ј�ǂ��邱�Ƃ������߂��܂��B
�@����l�́A�Ƃ�����Ƃ��l�D���A�̂�т�Ƃ����C���Ō���邱�Ƃ������ł����A��ʂƖ��f�Ղ̎���ɐ���������l�́A�˒m�ɒ����A�@�q�ŗE�����̂��́B�E�`�i�[���`���̂�����������������Ȃ��������ꂽ���ゾ�����悤�ł��B
�@�E�~���`���Ƃ��Ă̌o���̂Ȃ��l�܂ł��A�{���D�ɐg������A�ꝺ������Đ���オ�������̎���́A���钆�ł͂����Ă��A�E�`�i�[���`�����ł����������Ƃ��ċP���Ă������ゾ�����̂�������܂���B
�@�}������Ă���ʐ^���܂��A���ړx�����B�����̎������[�^���[�t�߂̎ʐ^��A�Ԃ�V��w��������ɔz���������ڂ��ĉƘH���}�����������̎ʐ^�ȂǁB�Ƃ�킯��҂́A�g�Ȃ�͂��ꂢ�łȂ��Ƃ��\������B
�@�^�ߍ����̖��f�Վ����m�邽�߂̕K�Ǐ��A�Ƃ����ʒu�Â��B
�@���f�ՂɊւ��Ă͂��̂ق��ɁA�u���퓇�܂Łv�i�^�ߌ��b�j�A�u���f�Փ��v�i��Y���Y�j�A�u�^�ߍ������̕Y���v�i�ɗNJF���g�j�A�u�i�c�R�@���ꖧ�f�Ղ̏����v�i����C�i�j�Ȃǂ�����܂��B�����Ԃ�ǂȂ��A���f�Պ֘A�{�B
�i�Q�O�O�W. �R.�Q�V�@�ǁj

|
 |
�u�O�����������v�@�@�@���Øa�q�@���@�@�@����^�C���X�Ё@�@�@�P,�P�S�R�~�{��
�@�@�@�Q�O�O�V�N �T���Q�S���@��P�����s
�@�܂��܂������Ȃ�����l�̃h�L�������g���́B�D���Ȃ�ł���ˁA���������́B
�@���Ï@�Ƃ́A�P�W�U�U�N���܂�łP�X�T�W�N�ɖv�����O���t�́B�Ί_���ɓn��A���d�R�ʼn���ÓT���y���L�߂������̗����҂Ȃ̂������B
�@�����t�͂ŌZ�̏@���ɂ��Ă͌����肪���������Ȃǂ��̑��Ղ��]������Ă���̂ɁA�@�Ƃɂ��Ă͂����������̂��Ȃ��B�Ȃ̂Œ��҂́A�@�Ƃ̐����l���L�^���邽�߂Q�O�N�����Ă��̖{���������̂��Ƃ̂��Ƃł��B
�@���̒��҂́A�@�Ƃ̑��̈�l�B�@�Ƃ��|�x���ɂ��������̎q�ŁA�@�Ƃ̑��Ƃ��ĔF�m����ď�������������Ί_���ɏZ�݂܂��B
�@���҂̗��e����p�ŋ��������Ă��āA�`�ꂪ�g�̂������Ȃ��������Ƃ���A�@�Ƃ���������Ĉ�Ă��̂ŁA�������肨���������q�ɂȂ����悤�B�܁A���̎q�Ȃ̂ł�����ǂˁB
�@���N���O�̏��Ȃ��L���������ɁA�����@�ƂƐe�����������l�X�̊W�҂ɓ������Ă悤�₭�ނ̃A�E�g���C�����яオ�点���Ƃ�������̖{�ł����B
�@�o�ꂷ�邽������̏@�Ƃ䂩��̐l���́A�����炭���n�ł͒����Ȗ��w�t�͂����Ȃ̂ł��傤���A�����m���Ă����͎̂c�O�Ȃ����l�ØC���炢�B�ق��ɂ́A�e���Ƃ��ēo�ꂷ�閯���w�҈ɔg��N�����ł����B�����Ɠo��l���ɐe�ߊ������Ă��炳��Ɋy�����ǂ߂��̂ɂƁA���X�c�O�B
�@���h�ȑ����A�P�V�O�y�[�W�łP�Q�O�O�~�B�̎Z����Ȃ��̂��낤�Ȃ��ƐS�z���Ă��܂��܂��B
�i�Q�O�O�W. �P. �Q�@�ǁj

|
 |
�u�^�ߍ����T�g�E�L�r���艇�_�� �|���I��z�̂R�O�N�|�v�@�@�@�����V�@��
�@�@�@�@�j���C�Ё@�@�@�P,�W�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�S�N�P�O���Q�T���@��P�����s
�@�P�X�V�U�N����n�߂�ꂽ���_�ɂɂ��^�ߍ����̃T�g�E�L�r����ɂ��ẮA�O�X���痧���a���̒��q�Ȃǂɂ���Ēm���Ă͂��܂������A���̔w�i����j�A�o�ܓ��ɂ��đ̌n�I�ɒm�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��ł��܂����B
�@�ŁA���̖{�B���݂�m���đ��Q�b�g�B
�@���҂͋����ʐM�Ђ̋L�҂ŁA���_�ɂ𗧂��グ�����S�l���I�ȕ��B�Ȃ̂ŁA���������Ȃ����̂悤�ȑg�D���������̂��A�^�ߍ����������u����Ă����͂ǂ��������̂��Ȃǂ����ɍł��ӂ��킵���l�̂悤�ł��B
�@���_���̎n�܂��A���̔w�i�ƂȂ������������Ƒ�p�Ƃ̒f���A�����̍ő���ł������^�ߍ����_���̔j�Y�A���̌�̑�����W�̋��A���O�ő������W�ł���܂łɗ͂����Ă����_���̗l�q�Ȃǂ��A�P�P�̏͗��Ăɂ���ăh�L�������g���Ă��܂��B
�@���̊Ԃɂ͒��Ԃ̗���⒩�ߕ���̂悤�ȍ��⒬�̐���A�����ȑ��������Ƃ��a瀂Ȃǐ��X�̋��������悤�ł��B���������҂����́A���̓s�x���Ȃ��A���ӂƓ��O�ȃ^�N�e�B�N�X�ʼnۑ���������Ă����܂��B
�@���҂́u���Ƃ����v�ŁA���̂悤�ɋL���Ă��܂��B
�w�^�ߍ����T�g�E�L�r���艇�_���͂Q�O�O�T�N�ɂR�O�N���}����B���̊ԁA�P�X�W�U�N�������Ė��N�����������_���𑗂葱���Ă����B���̔w��ɂǂ�Ȃ��Ƃ��������̂��A���̐l�����ɋꂵ�݁A���_�������ǂ�Ȏv��������Ă����̂��A���̈�[�ł��L�^�Ɏc�����Ƃɂ���āA���̐l�����Ƃ킽�������̑��Ղ𖾂炩�ɂ��A���A��̉���́A�Ƃ�킯�����̗��j�̂ЂƂ��܂�ǎ҂ɒm���Ă�����������肪�����ƍl�����B�\�\�x
�@�͂��A���̈Ӑ}�́A�\���ɓ`����Ă����Ǝv���܂��B
�@���_����g�D���鑤�̐l�Ԃ����������̂Ȃ̂ŁA������l�ЂƂ肪��Ƃ̒��Ŋ����A�l���Ă�����{���y�܂ł͏\���ɕ\�������Ɏ����Ă��Ȃ����݂�����܂����A�R�O�N�ԁA�������߂����đs��ȃX�g���b�O�����J��L�����ЂƂ̃h�L�������^���[�Ƃ��āA�ǂ݉����\���̂P���ł����B
�i�Q�O�O�V.�P�Q.�Q�Q�@�ǁj

|
 |
�u�哌���̕��݂ƕ�炵�@�k�哌���𒆐S�Ɂv�@�@�@�����@��@���@�@�@�j���C��
�@�@�@�@�P,�W�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�R�N �W���P�T���@��P�����s
�@����P�Q���A�}�C���[�W�����܂����̂ʼn���ɍs���܂����A���ɁI�Ƃ��Ƃ��I�@��哌���ɑ��ݓ���邱�ƂɂȂ肻���B
�@����̂��낢��ȓ��X�������Ă�������ǁA�ւ̈�����l�i�̍����Ȃǂ���A�哌���������͈ꐶ�s���Ȃ��ŏI���̂�������Ȃ��ȂƗ\�����Ă��������ɁA���������ЂƂ����B�D�͏T�P�ւ����Ȃ����A��s�@�����ĂP���킸���P�ւŕГ��Q���~�ȏシ��̂ŁA�Ȃ��Ȃ�����肪���Ȃ������̂ł��B����s����̂��A���������牫��܂ł̉������^�_������B�}�C���[�W���܂��܂ł��ȁB
�@�ŁA���̑哌���ɂ��ď����\���m���Ă������Ǝv���A�ς�ǂ����������o���Ă����̂����̖{�B����s���͓̂�哌�Ȃ̂ŁA�k�哌���Ɋւ���L�q�����S�Ȃ̂��`�g�ɂ����̂ł����A�\���ɎQ�l�ɂȂ�܂����B
�@�u�܂������v�̈ꕔ���T�����悭�\���Ă���̂ň��p����Ɓ\�\
�w���̓��X�ɂ́A�J��ȗ������m�푈�I���܂ŁA���Ƃ������̐l�������Ƃ��Ƃ������߂������j������B�����͂������������ɂق�낤����A�E�]�ƍ���ɖ�����������������ꂽ�B���ɂȂ��Ă��A�P�R�N�Ԃɂ���ԁu�y�n���L���v�l���̂��߂̐h�_�̓��̂����B����瑩���̍���f����A�l�Ƃ��Ă̎��R�����������̂́A�����炨�悻�S�O�N�O�̂��Ƃł���B�l�X�͂Ƃ��Ɏ����荇���Đl�Ԃ��Z�ނɂӂ��킵�����������ЂƂЂƂz�������Ă����B�\�\�x
�@�P�X�O�O�N���̊J��҂����̏㗤�̏���n�܂�A�����̉����A����D�̏A�q�A�d�C�̓_���A��s�@�̏A�q�A�e���r�����̊J�n�A�哌���̈�Â̏Ȃǂ����グ�āA���ڂ��Ƃɉ�����Ă��܂��B���̋�J�͕��X�Ȃ�ʂ��̂����������Ƃł��傤�B
�@�܂��A���҂͖k�哌���̒��w�Z�ɕ��C�����o���������ꌧ�̋��@�ł��邱�Ƃ���A���̋�����J�����w�Z�̕��݂ɂ��Ă��ڏq���Ă��܂��B
�@���̂ق��A�哌�����L�̓y�n���̉����̌o�܂�A�k�哌�����̈ӎ������̕��͂Ȃǂ��B
�@���Ƃ��ẮA�{�y����傫���x����Ƃ�Ȃ���������ɎЉ��Ղ���������Ă������o�܂ɂ��āA�ƂĂ��������ēǂ܂��Ă��������܂����B
�@����͓�哌�������̖K��ɂȂ�܂����A�������芴������Ă��܂��A���̂܂ɂ��A�����Ɩk�哌�ɂ��s����������̂��낤�ȁA�Ȃ�Ďv���Ă��܂��Ă��܂��B�i�j
�i�Q�O�O�V.�P�P.�P�T�@�ǁj

|
 |
�u�A�ē� �i���V�[�Ďq�̐t�v�@�@�@�_�J�Ǐ��@���@�@�@�����V���
�@�@�@�@�P,�X�O�T�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�U�N�P�O�� �X���@��P�����s
�@�u�l�v�̔����L�A���L��ǂނ̂��D�����B�Ƃ�킯����䂩��̐l�́A����ȉ^�������ǂ�l���Ƃ��Ȃ�A�����ÁX�ł���B
�@��l���̒��J�i���V�[�Ďq����́A�P�X�Q�P�N�n���C���܂�B��J���t�H���j�A�Œ��N�ɂ킽���ĉ���̓`���|�\�̌p���ƌ㐢��琬�ɐs�͂��Ă������B
�@�R�V�N�ɉƑ��ʼn���ֈڏZ������A�S�P�N�Ɍ����̂��߃��T���[���X�ֈڏZ���A�펞���̓��{�l���e���Œ������o�Y�B�Ō�w�ɂȂ肽���Ƃ����������Ȃ��邽�߃��T���[���X�̖�ԑ�w�Ŋw�сA�U�R�N�ɐ��Ō�w�����ɍ��i�B�Ȍ�A���Ō�w�Ƃ��ċΖ�����T��A�V�Q�N�ɒ��J�Ďq�����|�\�������J�݁B�J���t�H���j�A��n���C�A����ԂŌ|�\�����𗬂̉˂������߂����т��]������A�X�S�N�ɌM�Z������͂���͂����Ƃ������Ƃł��B
�@���҂́A���ꌧ�ݏZ�Ŏ����s�����E���B�ߔe�s���������̋{���痢���͂��߁A����͌��E��l�̕��|�l�������̂ł��ˁB
�@�ނ́A����ƃA�����J�̕����𗬎��Ƃ���`���Ȃ��Œ��J����ƒm�荇���A���邳�����킸�Ɍ�������������������J����̔�������҂����ɓ`�������Ǝv���A��Q�N�Ԃ����ē��Ă��������Ȃ����ފ����𑱂��������ł��B
�@�ǂ�ł��āA�S���傫���h���Ԃ���悤�Ȉ��|���Ƃ܂ł͂����Ȃ����̂́A��l�̐l���Ȃ�đ�ǓI�Ɍ���Ώ��������̂Ȃ̂ɁA���̐l�ɂ��Ă݂�����ɑ�ςŁA���X�̎�����njR�����ɖ������Ă�����̂ł��邩�����킶��ƁA���݂��݂ƁA�`����Ă��܂��B
�@�����i�������ꕔ�ł͗L���j�̐l�̗��j��ǂ��Ƃ��ɓ�����A������̂łȂ����̂��݂��݊��B���ꂪ�A�ƂĂ������̂ł��Ȃ��B
�@��l���̏���������n�܂�e����̎ʐ^���ǎ҂̃C���[�W���h�����āA�ǂ݉����ɉԂ�Y���܂��B
�i�Q�O�O�V. �S.�Q�W�@�ǁj

|
 |
�u�Y�꓾�ʐl�X�@�u���W������ږ��̔�b�v�@�@�@�{�鏼���@���@�@�@����^�C���X��
�@�@�@�@�P,�Q�O�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�U�N �S�� �P���@��P�����s
�@�u���W���͓��{����̍ő�̈ږ����ŁA�P�X�O�W�N�ɍŏ��̈ږ����T���g�X�`�ɑ����݂��߂Ĉȗ����悻�P���I���o���܂��B�����Č��݁A�u���W���ݏZ�̓��n�l�͖�P�T�O���l�B���̂����̖�P�������ꌧ�n�l�Ƃ����A��吨�͂��Ȃ��Ă��邻���ł��B
�@���҂̋{�鏼�����́A�P�X�P�T�N�A�{����������܂�ŁA�P�X�R�V�N�Ƀu���W���ڏZ�B���X�A������A�u��ă^�C���X�v�o�c�ȂǂɌg���A�P�X�V�S�N����R�O�]�N�A����^�C���X�̃T���p�E���ʐM���Ƃ��Č̋��ɋL���𑗂葱���Ă���X�P�i�I�j�̋C��������ł��B
�@����^�C���X�̌��ҏW�����A���n�R���j�A�̐��������Ő����ؐl�ł���{�鎁�Ɂu���`�v�̎��M���˗������Ƃ���A��ނŏ������߂��������@��N�����A���҂����m�蓾�Ȃ��u�B�ꂽ�j���v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�ƂɂȂ����\�\�Ƃ����̂����̖{�̗R���Ȃ̂������B
�@�R�S�́u��b�v�ō\�������A�P���I�ɋy�ԉ���ږ��̊��Ɨ܂̑��Ղ������ɁB�o�ꂷ��l���͊e�E�̒����l�������ł����A�P�Ȃ鐬�����k�ɂ͂Ƃǂ܂��Ă����A�����ɋ��ɂ��Ȑ܂�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B����A����䂭����Ɛl�X�ւ̐ɕʂ̏��B
�@�S�P�V�S�y�[�W�B�P�S�|�C���g�͂��낤���Ƃ����傫�ȕ����ŁA�N�ɂł��ǂ݂₷�����̂ƂȂ��Ă��܂��B
�i�Q�O�O�V. �P. �W�@�ǁj

|