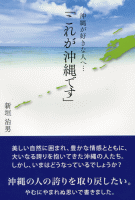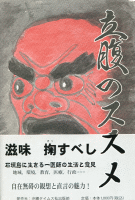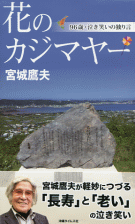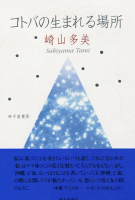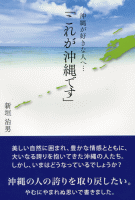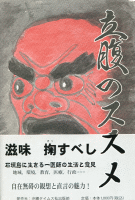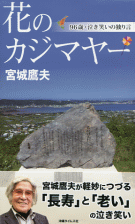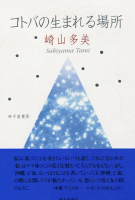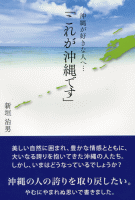 |
「沖縄が好きな人へ…「これが沖縄です」」 新垣治男 著
フーガブックス 1,200円+税 2017年3月8日 第1刷発行
2020年、1月3日から3月4日まで、沖縄本島でのロングステイを体験し、その間20冊ほどの本を読みましたが、その直前に山形で1冊読み上げてから出発した本があったのを忘れていました。
忘れてしまったのは、その内容があまりにもつまらなかったから。というか、くだらなかったというほうが正しい。格別難しい内容でもなく、読みにくい装丁でもないのですが、途中から読み続けるのが苦痛に感じるようになりました。薄い本だったので、早く読み終えて次に進もうというモチベーションだけでなんとか読み切りました。
著者の言いたいことは、武器や軍隊を持たない空想的な平和主義は真の平和をもたらすものではなく、武器を持たなかった琉球王国や湾岸戦争時のクウェートをみればそのような平和主義の末路は見えている、もっと現実に目を向けよう――ということのようです。しかしなのだなぁ……。
小見出しを拾っていくと、「日本と沖縄は、根は同じなんです」「うちなーんちゅは誇りある日本人なんです」――まあこのあたりは本土側からの視点というか一方的な思い込みがあるものの、わからないでもありません。しかし、「沖縄のマスコミにあなたもきっと騙されていますよ」「沖縄って中国に狙われているんですよ」「沖縄を中国に売ろうとしている人たちがいるんですよ」「沖縄県民よ、被害者意識を捨てようではないか」「反日年寄りの青春に付き合っている場合じゃないんですけどね」「オール沖縄よ、悪はあなたたちです」とくると、このヒトはまったくもって何を言いたいのだろうという思いに、徐々にかられていくことになります。
大きく譲ってみても、世の中右か左かしかないわけではなく、時勢や情勢としてそういう一面があることは否定できないと思いますが、それが沖縄やウチナーンチュの全体像としてそうなっているのだと言われても、まったくピンときません。ああ、ここにもまた独りよがりの大言壮語を吐く世間知らずがいるなぁと思う程度のこと。ミクロはマクロで語るものではないのですよ、わかりますか。
ふざけるなよと思わせる気持ちを増幅させるのは、そんなただの一人合点の思い込みを、厚顔無恥にも赤の他人に本を売って金を払わせるということまでして押し付けること。つまり言いたいのは、好きなことを言うのは勝手だけれども、あまりに一方的で賛同できるようなシロモノではないので、本代を返せ!ということなのですな。まあ、古書を送料込み408円で買ったものだから損害は少ないけれども。
著者は、1951年沖縄県本部町生まれの沖縄大学法学部卒業。警察官として18年間勤務した後、各種コンサルタント業をなさっているのだそうです。
著者の、周囲の人々に対する構えなり考え方がわかるところがありました。
たとえば「辺野古に基地反対運動をしに行くと1日6千円もらえて弁当もあるそうだよ」(つまりは伝聞)と言うと、「翁長知事及び共犯者を擁護する人たち」は、「証拠があるか」「あなたは実際にそれを経験しているのか」(事実の確認)と反論してくるが、こういうときの対処は、「相手の質問には直接答えず、その反対の質問を相手にして答える」「相手が質問ではない何かを言ってきても答えない」――のだそうです。
もう鼻で嗤えてしまいますが、つまりは、自分の言いたいことは伝聞であっても一方的に言うけれども、人の意見にはつゆほども耳を貸さないということを、あたかも宣言しているようではありませぬか。こういう人に対する処方箋はないと言っていいでしょう。
人間たるもの、もっと真摯でなければいけません。どこで誰が撮ったものか、巻頭、巻末の写真は今の沖縄をよく表している美しいもので、ここにばかりはホッとするものがありました。
(2020.1.3 読)

|
 |
「市場のことば、本の声」 宇田智子 著
晶文社 1,600円+税 2018年6月10日 第1刷発行
ここは沖縄・那覇の市場通り。今日も私はかわらず店を開ける。
店に立ち、市場のことばに耳を傾ければ、今日も人と本が豊かに、楽しげに行き交う──。
沖縄の本を地元で売ることにあこがれて、那覇に移住して9年。店先から見えてきた、そして店先で考えてきた、本のこと、人のこと、沖縄のこと……。古本屋の店主にして気鋭のエッセイストが新たな視点で綴る、珠玉のエッセイ集。(カバーのそでから引用)
著者は、1980年神奈川県生まれ。東京大学文学部卒業後の2002年にジュンク堂書店に入社し、池袋本店で人文書を担当していましたが09年、那覇店開店にともなって志願異動し、11年7月に退職します。そして同年11月、那覇市の第一牧志公設市場の向かいに「市場の古本屋ウララ」を開店。
2019年末現在も、古本屋店主として働きながら、さまざまな新聞、雑誌に執筆活動を行っている方です。
「ウララ」は、牧志で親しまれてきた「とくふく堂」が閉店するのを引き継いだもの。著者は本当に本屋稼業が大好きのようで、「さびしいときもお金のないときも、本屋に行けばなにかを受けとれる」と言い、「引用でも立ち読みでも、読んだ人にはいつでもいくらでも与えてくれる、言葉の気前のよさ。似合わないとも高いとも言わずに、誰にでも惜しみなくさし出されている」と、本の魅力を綴っています。
沖縄タイムスに作家・中沢けいの書評が載っていたので、以下に引用しておきます。
・宇田智子著「市場のことば、本の声」 スモール・トークの魅力 2018年9月9日
那覇へ行くと必ず牧志の市場をのぞく。公設市場の八百屋さんが並ぶあたりにある小さなコーヒー屋さんでコーヒーを飲み、それから古本屋さんの「ウララ」で本を選んで宅配便で自宅へ送ってもらう。沖縄の地域出版物の豊かさに目を見張るのもいつものことだ。
送り状を書きながら、一言二言、言葉を交わすのが楽しい。宇田智子「市場のことば、本の声」は小さな古本屋さん「ウララ」で宇田さんとお話をしている時のことがよみがえってくる。
著者の耳に聞こえてくる市場の声もこの本にスケッチされている。市場のざわめきを手に取り、目で見るかのようだ。
雑談のことを英語でスモール・トークと言うのだそうだ。「市場のことば、本の声」には市場を行き交う人のたくさんのスモール・トークが詰まっている。
「本屋と映画館の話にはとくに思いいれを感じる。あの本屋でこの本を買った、あの映画館でこの映画を観たという記憶がみんなはっきりしていて、そこに通って長い時間をすごし、大事なものにたくさん出会ったことがよくわかる。その場所がなくなっても、ずっと覚えている」
「地元の人」の一節だ。とても残念なことだが、本屋さんも映画館も現在では閉店、閉館が記憶の中にしか存在しなくなった地域も多い。市場もまた大型のショッピングモールなどに建て替えられて消えて行くものの一つなのかもしれない。公設市場建て替えの話も「ウララ」で送り状を書きながら聞いた。本の表紙に蛇が描かれているのを見て、エラブ海蛇が市場に並んでいた時代を思い出した。その頃は薫製の香りが市場にあふれていた。スモール・トークは歴史書に書かれることはめったにない。が、スモール・トークの波が大きな流れとなって歴史を作って行く。
この本はスモール・トークの魅力にあふれた本だ。ざわめきの中から生まれてくるものに触れているような感じが心地よい。
自分にとっては、2019年に読んだ沖縄本の50冊目となりました。毎年最低50冊は読むという目標を定めていて、これで11年連続の達成と相成りました。自分に拍手〜♪
(2019.12.3 読)

|
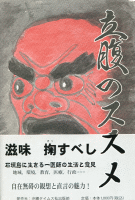 |
「立腹のススメ」 宮良長和 著 沖縄タイムス出版部 952円+税
2006年10月1日 第1刷 2007年1月30日 第2刷発行
日本全国にその名が轟いていない市井の人の生き方や考え方、これまでたどってきた人生などを垣間見ることもそれなりに楽しいもの。そこには自分に備わっていないものや経験したことのないようなことなどがたくさん詰まっていて、大いに参考にもなるものです。
そういうもののひとつとして、10年以上前に書かれたものを古書店から求めてみました。
著者は、1926年生まれで九州大医学部卒の「邂逅」同人。石垣市大川で眼科医院を開業し、息子とともに親子2代で診療を行っている人です。
表題だけ見れば、貴方ももっと腹を立てよという内容かと思われますがそうではなく、この本を発行した「宮良長和著作集刊行委員会」の中心人物がつけたものだとのこと。何人に対しても遠慮無用の自由業医師という身分に恵まれて、無気力者を奮起させるような筆勢で「公憤」について奔放に書いているから、ということのようです。
昭和40年代から現在までの間、折に触れて書いてきたものをまとめたもののようで、重複を避け、書いた年代が記されず、内容順にまとめられているものとなっています。そのためもあってか、全体として身近というよりも社会的にみて重めのテーマについて、年長者、社会的成功者という立場から長年の想いを多少上から目線で述べているような印象がありました。平たく言うと、そんなことは重々わかっているけれども、普通の人はなかなか言えないよ――といったことが長々と書かれているような感じ。まあそれが、人によっては「古武士の風格を彷彿させる奔放で爽やかな筆致」と受け取れなくもないのでしょうけれど。
個人的な評価はこのぐらいにして、2006年12月03日付け八重山毎日新聞(不連続線)に書かれていたことを以下に引用しておきます。
滋味掬すべし、なんという修辞。いやはやなんとも参りました。一読三嘆とは、こんな本のための形容ではないか。
このほど島の目医者宮良長和氏の著作が刊行委員会の編集で沖縄タイムス社から上梓された。「立腹のススメ」という穏やかならざるタイトルもいい。テーマは、旅、美、老、病、死、欲、躾など何でもあり。論旨のあまりの潔さに読んだこちらがついブレーキをかけたくなる。
行き着く所までいかないと人間は、我に返らぬとの冷徹な達観に裏打ちされた文章は、再読に耐え古びず、それ観光、開発と時流で右顧左眄する行政幹部や為にする賛成・反対運動のリーダーたちの言とは、一線を画している。
それと人は、往々にして文中のある言葉に引っかかると逡巡しそれ以上は、読み進めなくなる性向にあるが、氏は、意に介せず散りばめ、良薬口に苦しと平気の平左。
農業に帰れ、天久返還地を杜に、墓不要などの下りは、固くなった頭を刺激、柔軟にしてくれる。後書きにこんなに本があふれている時代に自著が末席を汚してもいいのかと殊勝に述べておられるがどうしてどうして。
氏の新聞投稿「石垣市民の墓」以来愛読、頭の体操をさせてもらっているファンの1人として「立腹のススメ」1冊では、物足りぬ。
(2019.8.7 読)

|
 |
「帰る家もなく」 与那原恵 著
ボーダーインク 1,800円+税 2018年3月30日 第1刷発行
発行元の編集者である新城和博は、この本の帯に次のように記しています。
「ノンフィクション作家・与那原恵さんとは古い友達で、彼女の両親の故郷である沖縄・那覇で何度も会っている。旅をしない日々を送るぼくは、与那原さんの話を聞いているうちに、気がつけばずいぶん遠くまで歩いてきたような気持ちになっていた。
たぶんほとんどの人生は、忘れ去られる。たとえそれが家族の思い出であっても。そして夜空に拡がる星々のように、誰かが見上げてくれるそのときまで沈黙している。 旅する人は、その声をきっと拾い集めることができるのだろう。
そんなことを考えているうちに、この本ができた。与那原恵のごく私的な旅の記憶と、とても大切な歴史の断片を切り取ったエッセイ、ノンフィクションたちは、彼女の旅するときの高揚感、出会いと別れの切なさが詰まっている。」――と。
文中の表現を借りれば、「帰る家はないけれど、これから旅する場所はいくらでもある。海風が吹いても消えない足跡が、遠くまでづいているはずだ」という想いで描かれた、与那原恵のエッセー集。
沖縄、台湾、韓国、日本、欧米…。自分自身のルーツでもある沖縄の近・現代史を描き、また国内外の様々な旅を続けるなかで出会ったひと、歴史、友人たちの思い出と、忘れてはいけない歴史の記憶を拾い集めてきた著者が、個人史として、ルポルタージュとして、そしてなにより楽しい旅の日々としてまとめたものになっています。
作家で詩人の山原みどり氏による、琉球新報に掲載された書評を見つけたので、ここに移記しておきます。
・『帰る家もなく』 心の眼で見続ける
「足跡はどこへ続いているんだろう」 私達はいつでも、この問いに戻って来る気がする―。
与那原恵著「帰る家もなく」を読み終えて、一番に持った思いだ。
四部構成のこのエッセー集には、どこの、どの時代においても、ままならないものの中に懸命に生きてきた人々が居、その営みが今の私達に繋がっているという当たり前の事の驚きと尊さが、丁寧に、記されている。
著名人や旅先で出会った人々の話も多いけれど、一番胸打たれたのはやはり著者自身と、その家族にまつわる物語だ。スリーイー(EEE)という幅広の靴を履き、自らも病弱ながら病身の妻と5人の子を養った父の生き様。戦争前夜の父と母を結んだ手紙。絵描きである大叔父と彼をとりまく芸術家達の苦悩と奔放……。読み進めるにつれ、歴史というものは一人ひとりの記憶の連なりで、歴史は記憶を生き直すことで物語となる、という思いを強くする。そこには与那原さんの心の眼が見た風景が映し出されているのだ。
彼女が7、8歳頃に持ったという感情―「じぶんという存在の不思議さに気付くと同時に、さみしさを知った……胸の底で、ずん、というこわい音が聞こえだした……」。全ては変わってゆくし、私達はしっかりと地面から生え出たような絶対の支えなど持ち得ないという事実を少女の直感が捉えていたのだろう。その不安が記憶という物語を通じた人間の繋がりを求めさせるのは自然な事だ。しかし心の眼でものを見続けるというのは容易な事ではない。怠惰ではなく、眼差しはともすれば溶け出す氷のように表面を滑りながら消えてしまう。まるで何事もなかったかのように。けれど確かな支えを持たない私達は、それでも何かを留めておきたいと願うものではないか。
与那原さんがここに紡いで見せた物語一つひとつが私達に思い出させてくれるものは大きいはずだ。スリーイーの足跡が「遠くまでつづいている」砂浜で、私達の後ろに今この瞬間にも生まれ続けている足跡がどこに続いているかは誰も知る事が出来ないのだし、その意味では誰にとっても帰る家はどこにもないのだから。
(2019.5.4 読)

|
 |
「あの瞬間、ぼくは振り子の季節に入った」 荷川取雅樹 著
ボーダーインク 1,700円+税 2018年2月16日 第1刷発行
世界がどんなに複雑でも、バカなぼくたちにかかればどうってことない、はずだった。
懐かしくて、悲しくて、間抜けで、切ない、青春小説の傑作が誕生!
1970年代から80年代初頭にかけての宮古島。おバカでナイーブな少年は、南の街を自由に飛び回り、やがて島から羽ばたくはずだった。目眩を起こしそうなほど素晴らしくて、迂闊な時代。でも(振り子の季節)から思春期の扉の向こうに待っていたのは、失われた明日だった……。
遠く離れた宮古島の小さな風景、出来事があなたの心を静かに揺さぶる。(コシマキから)
著者は1966年生まれなので、物心ついた頃からティーンエイジャーまでぐらいの時期の宮古島のことを、当時の思いと目線で描いている秀作です。
当時の平良は人口密度が異常に高く、昼は自動車や簡易な荷馬車がガンガン行き交い、夜は酔っ払いが奇声をあげながらフラフラ歩き回っている、空が狭く青い海も見えない猥雑な町だったと著者はいいます。
そして、そこを小汚い子供が自由に飛び回って、こっぴどく怒られたりドヤされたりしながら、少年から少し大人の少年になっていくのでした。
こういう記憶は昭和40年前後ぐらいまでに生まれた人間ならば誰もが経験してきていて、それぞれの心の中でほろ苦い思い出になっているのではないでしょうか。
著者は、このようなつまらなくて古い記憶が感情のどこか端のほうに引っかかり、振り払っても振り払ってもしぶとく食い下がって消えようとしないことに困り果てていることを告白し、そのひとつひとつを書き綴っていきます。
著者は、小・中・高と平良市内で過ごすが、高校3年生の夏、大きな交通事故に遭い半身不随となってしまいます。長期の入院、東京でのリハビリのあと宮古島に戻り、生活のほとんどをベッドで過ごすなか、読書に目覚めてやがて小説、エッセイなど文章を書いて友人らに発表するようになります。
そして2005年、「前、あり」で琉球新報短編小説賞。14年には「病院鬼ごっこ」で琉球放送RBCiラジオのファンタジー大賞。
その後もフェイスブックなどで小説や小・中・高校時代の様々な記憶をエッセイと小説の間のような作品を書き綴ってきました。それらは「マクラム通りから下地線へとぐるりと」「パイナガマヒーローズ」という私家版でまとめられています。
今回、失われた記憶を求めるかのように書き綴られた作品を加筆し、さらに書き下ろし加えて連作短編集としてまとめたのが、当書。現在も半身不随のまま、宮古島にて執筆活動や地元宮古エフエムでのパーソナリティを行っているとのこと。
(2019. 3.20 読)

|
 |
「本日の栄町市場と、旅する小書店」 宮里綾羽 著
ボーダーインク 1,600円+税 2017年11月15日 第1刷発行
栄町市場を舞台とした小さな古書店の副店長(店長は著者の父)の若い女性が綴った本が出たので、面白そうだと思って手にしたもの。
なのですが、著者の父であり店長という人物が宮里千里だとは知らずに買いました。
宮里千里と言えば、大好きな沖縄エッセーの名手で、「島軸紀行 シマサバはいて -異風南島唄共同体-」「アコークロー〜我ら偉大なるアジアの小さな民」「ウーマク! オキナワ的わんぱく時代」「シマ豆腐紀行 遥かなる<おきなわ豆腐>ロード」などの著作があります。彼は那覇市役所の総務部長までいったはず。ははあ、「アコークロー」に登場していた小学生だった娘が大きくなったんだなぁ。
市場で出会ったひと、旅で出会った本。
二度見してしまう風景、うたた寝する市場、旅の余韻、何度も読み返す本。
世界はこんなにも愛おしい。
沖縄那覇市の栄町市場にある小さな本屋さん「宮里小書店」の副店長がつづるカウンター越しのエッセイ。(コシマキから)
沖縄タイムスの書評が適切だったので、以下に引用。
・宮里綾羽著「本日の栄町市場と、旅する小書店」 市場の魔力、出会いの魅力 2018年1月28日
那覇の栄町市場に「宮里小書店」という小さな本屋がある。2013年、エッセイストで琉球弧の祭祀の録音などでも知られる宮里千里さんが店を始めた。1年後、その娘である著者が副店長として店に座るようになった。
本書の主役は栄町市場で働く人たちである。市場がにぎやかだった時代も、復帰後の静かな時代も経験してきた彼女たちは毎日店を開け、おしゃべりをして、つらそうな人が来れば気のきいた冗談で笑わせる。「明日も市場に来なさいよー」と言いながら。
著者は隣の洋服屋さんと店先で鍋をしたり、閉店する化粧品屋さんの思い出話に胸をうたれたりしながら、どんどん市場に魅せられていった。毎日の新鮮な驚きが、飾らない言葉で綴られている。
タイトルの通り、本書のもうひとつの核は旅の話だ。旅の記憶の中心にはいつも人がいる。そこで出会った人のつぶやきやちょっとしたしぐさが、その国を忘れられない場所にすることがわかる。
それから本の話。登場人物に感情移入し、作者本人と顔をつき合わせるかのような熱っぽい読書ぶりが伝わってくる。旅と読書は人に出会うという点では同じなんだと気づかされた。
そして家族の話。幼いころにふたりでアジアを旅した父と、大切な本を分かちあってきた母。旅や本の喜びを教えてくれたのは両親だった。
やがて旅先の市場から地元の市場に戻って店番を始めた著者は、たくさんの出会いに恵まれる。お客さんと本の話をし、市場の店でおいしいものを食べては喜ぶ。まるで旅人のように目を輝かせて。
著者は「いつもここではないどこかに行きたがる」子どもで、家出をくり返していたらしい。なのに栄町市場には3年半座り、いまも座っている。すごいことだ。旅するように日々を暮らせる幸せが、この本には満ちている。
いつも旅先みたいに新鮮で、何度も読める本のような市場の魔力に、読者もとりつかれるだろう。
(宇田智子・古本屋店主)
なお初出は、沖縄タイムスに2014年に掲載されたコラム、ボーダーインクのHPの「ガラガラ石畳」、池澤夏樹の公式サイト「cafe impara」に掲載された「宮里小書店便り」「本日の栄町市場」ほか。
「アコークローの娘」では、宮里家内での娘と父との関係性や家族愛などが読み取れて、興味深いものがありました。
また、ボーダーインクの編集者新城和博は自身のコラムの中で、まだ20代だった彼が役所でミニコミ誌をつくっていた宮里千里を知り、あまりの面白さに驚愕し、「アコークロー」の発刊にこぎつけたことを回想し、その娘が書いたものを親子2代にわたって編集できることに喜びを感じていました。長く編集していてこそ体験できることなのでしょう。
(2019. 2.20 読)

|
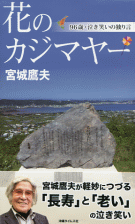 |
「花のカジマヤー 96歳・泣き笑いの独り言」 宮城鷹夫 著
沖縄タイムス社 970円+税 2018年7月7日 第1刷発行
「あ、そうだ、ぼくは来年97歳のカジマヤー。超老人の思いを書こう、若者たちには“あれ?老人ってそんなものか”と思わそう。老人たちは“そうだった、そうだった”と思うだろう・・・」
ぼくが96歳まで生きた時代、そして父や母たちの古い時代を含めて、聞いたまま、思ったまま、感じたままを書き並べただけであるから、たわごとでよいと思っている。
老いてカジマヤー、泣いて笑って独り言、命の終止符を打つその日まで、晩年の向かい風のなかを、自分の歩幅で歩き続けよう。そして書き続けよう。男のロマン「カジマヤー人生」を。
(「「まえがき」……のつもりで」から)
戦後沖縄を見続けてきた96歳のジャーナリストが、老いや人生、民俗などについて軽妙に綴ります。
著者は、佐敷生まれで、沖縄タイムスの主筆や代表取締役専務を経て、沖縄県文化協会の顧問。また、全沖縄空手古武道連合会最高顧問という文武両道を地で行く方。久高島や久米島などについての著書がいくつかあるようです。
さすがジャーナリスト上がりで、96歳にもなってから一般人が読める程度の文章をよくぞまあ書けるものだと感心します。自分には無理だろうな。その前にその御年まで生きられないと思うけれども。
カバー写真は、南城市佐敷手登根区の「アカバンタ」に建立された民謡「あかばんた」の歌碑。実はここ、2018年2月に現地に行って見てきたばかりの場所です。
この歌詞は著者が作詞したもので、上原正吉がうたってラジオ沖縄の第1回「新唄大賞」(1990年)に選ばれたことも書かれています。そうだったのか。知らなかったなぁ。
(2019. 1.23 読)

|
 |
「多良間島幻視行」 波田野直樹 著 連合出版
1,800円+税 2018年2月15日 第1刷発行
先に読んだ「沖縄幻視行」(連合出版、2012)に続く沖縄モノで、今回は多良間島。著者は、前著執筆時に知った「淡水レンズ」という言葉をきっかけに多良間島に興味を抱き、5年以上かけて島を取材したそうで、その成果としてまとめられたのがこの本です。
多良間島の特徴であるトゥブリが、澄みきった青空とともに表紙を飾っています。
多良間島というひとつの島をここまでじっくりと見詰めて詳述した本はほかに知りません。おそらく採算度外視で出版に踏み切った関係者には深甚なる敬意と大きな拍手を送りたい。
島の人々や雰囲気、祭祀スツウプナカと八月踊りなどについて、内面的な想いを含めて記されており、多良間独特の選挙の様子やタラマフツ(多良間方言)などについての記載も。
多良間島を知るのにとても参考になるとともに、読み応えや読後感もしっかりたものがありました。
沖縄文化の原型を保存する島――。
琉球弧の西の端、多良間島。東西6km、南北4km、人口1,185人。この小さな島には、神と交わる壮大な祭祀が受け継がれてきた。それを絶やさないで継承して行こうとする島の人々の意志には確かなものがある。
しかし、急速に進む人口減少と高齢化および周辺海域の緊張の高まりは、この島に深刻な問題を投げかけている。
著者は、島の最大の神事に参加し人々の思いを受け止め、文化継承の道を提言する。(連合出版ホームページから)
章立ては、前後に「プロローグ」と「旅のあとで」を配し、その間に「島の散歩」、「スツウプナカの祭祀」、「八月踊り」、「多良間の生と死」、「歴史の中の多良間」の5章。
「宮古新報」のホームページに、著作の紹介が載っていたので、以下に紹介しておきます。
・波田野直樹さんが「多良間島幻視行」を発行 2018/03/10 配信
【多良間】 波田野直樹さんがこのほど「多良間島幻視行」を発行した。波田野さんにとっては前作「沖縄幻視行」に続いて沖縄をテーマとした2冊目の著書。
波田野さんと多良間島との出会いは2011年で、「沖縄幻視行」の執筆中に淡水レンズのある島、風水集落の残る島として訪れ、以来6年間にわたって多良間の風土や住民たちと付き合ってきた。
波田野さんは「観光的にそれほど知られてなく、どちらかと言えば地味な土地柄だが、そこに生きる歴史、文化、そして共同体の姿は鮮烈な印象を残した。その体験を余すところなく描いたのが本書」と述べている。
波田野直樹(はたのなおき) 1948年東京生まれ。ウェブサイト「アンコール遺跡群フォトギャラリー」主宰。主な著書は「アンコール遺跡を楽しむ」(03年)、「アンコール文明への旅、キリング・フィールドへの旅」(07年)、「沖縄幻視行」(12年)、「多良間幻視行」(18年)。
(2019. 1.5 読)

|
 |
「沖縄、シマで音楽映画「島々清しゃ」ができるまで」 磯田健一郎 著
編集室屋上 1,600円+税 2017年1月20日 第1刷発行
一人の「音楽監督」が映画の企画を持ち込んだら、脚本まで書くことになってしまった!
これは、沖縄の離島を舞台にした映画「島々清しゃ」の始めから終わりまでを描いた制作の記録で、映画への、沖縄への愛に溢れたエッセーとなっています。
著者の磯田は、1962年大阪生まれで、音楽プロデューサー。90年代から沖縄音楽のアルバム制作に携わり、映画「ナビィの恋」や「ホテル・ハイビスカス」の音楽監督を担当した人です。
嘉手苅林昌と普久原恒勇のCD「The LAST SESSION」(1996)のプロデュースも手掛けています。
ボーダーインクの新城和博とも懇意のようで、新城とともに普久原恒男のインタビュー本「芭蕉布 普久原恒男が語る沖縄・島の音と光」(ボーダーインク、2009)をつくってもいたようです。この本、読んだな。
さらには、唄者金城盛長とも仕事をしています。
文中、映画「ナビィの恋」があらゆる面で彼の人生の転換点となり、撮影終了後に登川誠仁から工工四を贈ってもらったり、夜を明かして飲み歩いたりしたことを打ち明けています。
新城和博が2017年2月18日付けの沖縄タイムスに寄せた書評がありましたので、ここにも残しておきます。
・「沖縄、シマで音楽映画 『島々清しゃ』ができるまで」 音楽監督が撮った「遺作」
今年は沖縄映画の当たり年かもしれない。年明けからぞくぞくと封切られている。もちろん何の先入観なしに観た方がいいに決まっているのだが、本書は読むと確実に映画「島々清しゃ」が観たくなるであろう。原作本ではない。〈音楽監督兼脚本家が書いた〉、映画への夢から始まり、沖縄への愛で終わる、私的なエッセーであり、制作の記録である(巻末には出演者・安藤サクラとの対談もある)。
著者の専門は音楽制作。沖縄との付き合いは長く、沖縄音楽への造詣も深い。映画の音楽監督としてもいくつかの作品に関わっている。例えば「ナビィの恋」。
その彼が大病を患い「そうだ、遺作をつくろう」と、思い描いたシーンは、沖縄の島で鳴り響く金管楽器群。夢のシーンを撮りたいがために、著者は企画の立ち上げのみならず、初めて脚本まで書いてしまう。
映画は監督、役者はもちろん、多くのスタッフが関わる表現である。そこには秘められた物語があり、撮影され、封切られるまでの過程そのものがドラマである。ロケ地となる慶留間島との出会い(実は僕の父の出身地の島なのだけど)、現場で実際演奏した音楽を録ることへのこだわりなど、実に細部にわたって記されている。
音楽監督の仕事の幅の広さは、僕の想像を超えていた。作曲はもとより、選曲に編曲、楽器の手配に、演技する子どもたちへの演奏指導(初めてさわる楽器を本番でちゃんと響かせるための努力たるや!)。さらに天気に左右される島の空気感、波の音、鳥のさえずり、そしてさりげなくシーンの背後に流れる島唄の微かな響き。それら全てが映画の音楽なのだ。
足かけ6年にわたる映画の日々で、著者は少しでも映画「島々清しゃ」に関わった人の名前を実に細やかに記している。そうか、映画制作というのは、こんなふうに人との出会いの積み重ねかもしれない。本書を読んだ後にふたたび映画を観たのだが、感動がぐっと深まった。
(2018. 8.14 読)

|
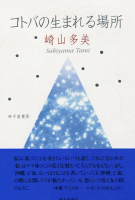 |
「コトバの生まれる場所」 崎山多美 著 砂子屋書房
2,000円+税 2004年 2月 1日 第1刷発行
私は「私」のことを書きたいといつも思う。けれど書かれた「私」はナマ身のこの私とは別モノにならざるを得ない。また、「沖縄」と「私」というようなことを書いていっても「沖縄」と「私」の間には深いミゾが横たわっている。俗にいう男と女の間のように。――という、崎山多美の第二エッセイ集。
砂子屋書房からの発行。砂子屋書房は歌集・詩集を中心に出版・販売している東京都千代田区内神田の出版社。かつてとある短歌文学賞の事務局をしていたときに、多くの歌集の発売元としてよく耳にしたものです。
読んでいて、著者の本業が予備校教師であること、中学の頃はコザでやんちゃしていたこと、一度コザを離れたものの著作当時にはコザ界隈に住んでいること、沖縄の芸能に造詣が深いこと、などがわかります。
組踊に関して、著名な立方である瀬底正憲や宮城能鳳に対する批判は強烈で、慣れから驕りがきていると一刀両断にしています。
ちょっと深呼吸、コトバの小箱、コトバ・言葉・ことば、シマ・生活・老人・子供、ブック・レビューの5章立て。
ブック・レビューでは、既読の大城立裕「水の盛装」、目取真俊「魂込め」のほか、目取真俊の「盆帰り」その他の短編、岩森道子「石の里」、小浜清志作「後生橋」なども。
ここで、先に読んだ「沖縄への短い帰還」(池澤夏樹著、ボーダーインク、2016)に崎山著「ゆらてぃく ゆりてぃく」の書評が載っていたので、その一部を以下に抜粋しておきます。
小説は書かれるものと語られるものから成る。書かれるものは史ないし誌である。語られるのは話。書かれる方はどこか公式で、作者がことのすべてを知っているという前提の上に立っている。語られる方は一人の語り手を想定する。
沖縄の作家崎山多美の「ゆらてぃく ゆりてぃく」を読むとこの二つの関係がよくわかる。一方ではこれは保多良島という架空の、しかし沖縄のどの離島でもありうる島の、島史ないし島誌となっている。作者は相当にファンタスティックな島の歴史や民俗誌をしたり顔で書き連ねる。他方には、島に住む者たちの独り語りによって主観的に提示される話がある。独り語りではあるが、合いの手を入れる聞き手はいる。
どちらの記述も現在については薄く、過去が圧倒的に濃い。現在にはただ過去を整理し展示する場としての意味しかない。すべてはすでに終わっている。
沖縄という土地の精神性を最も正確に小説の形で表現しようという意図が、こういう作品を生む。ヤマト(日本本土)の読者にわかりやすいようにという配慮を捨てて、沖縄の本性を歪めることなく書く。わかりやすいストーリーを望むことはできない。なぜならば、それよりもずっと大事なものがあるから。
この小説で沖縄の言葉が多用されるのは当然で、それが読者を限定するのはしかたのないことだ。
話は「ありんかん、くりんかい」(あちらへこちらへ)ふらふらと揺れながら進み、やがて物語ぜんたいが見えてくる。・・・
濃厚な過去がかつてあった。今はない。この島ではしばらく前から子供が生まれず、島社会の消滅は目に見えている。この話ぜんたいが強い喪失感に包まれ、哀切の情が漂っている。そういう沖縄が小説として表現される。
「後(ヌチ)ぬ事や、ヌーん心配(シワ)しみそーらんぐと、彼方(アマ)かいや、心安(ククルやし)やしーと行ちみそーリヨー」(後のことは何も心配しないで、あちらに心安らかに行ってくだされよ)という葬式の挨拶は、沖縄の精神性そのものに捧げられた弔辞のように思われる。
(2018. 3.17 読)

|
 |
「沖縄への短い帰還」 池澤夏樹 著 ボーダーインク
2,400円+税 2016年 5月25日 第1刷発行
1994年から2004年まで沖縄で暮らした作家・池澤夏樹が記した、沖縄をめぐるエッセイ、書評、インタビュー、講演、掌編小説を、新城和博らボーダーインクの編集者が厳選をして1冊にまとめたもの。
「沖縄式風力発言」(1997年)以来19年ぶりとなる池澤夏樹の沖縄県産本。沖縄で暮らした10年と、そこで得た様々な思いが書き記されています。
単行本初収録されるものも多いようです。「コラムマガジンWander」でのインタビューや、「島立まぶい図書館から眺め」に収録していた書評など、ボーダーインクならでのものも多数。
解説が宮里千里だというのもファンを喜ばせます。
この本の刊行にあたり新城和博は、「版元ドットコム」というウェブページで次のように書いています。
「・・・池澤さんと那覇で飲む機会があったので、沖縄に住んでいたころの文章をいろいろ集めて、あらためて本にできないかと話した。文章のセレクトは僕がおおよそ行い、単行本未収録の文章もできるだけ載せる。池澤さんも、沖縄の10年、そしてこの先を考えるにあたって、あらためてまとめることに興味をしめした。
結局、沖縄に来る前から去った後まで、およそ25年にわたる期間の中から、エッセイ、書評、インタビュー、講演、掌編小説など、さまざまな沖縄に関する文章を収録した「沖縄への短い帰還」は、話を持ちかけてから2年ほどたち、ようやく刊行することになった。
・・・沖縄に来た人も、去って行った人も、沖縄に住んでいる人も、それぞれ時間が過ぎ去った。この本を製作しながら、沖縄で生まれ育ち、ずっとこの島にいる僕も、あの“沖縄”としか名づけようのない季節にいたのだと、なんだかずいぶん感慨深い一冊になった。」
こうしてみると、本というものもまた、人と人とのつながりの中で生まれ、育っていくものなのだなと思う。そして、そういうストーリーこそが、書き綴られた中身をぐっと味わい深いものにするのでしょう。
内容の一部を紹介すると、次のとおり。
エッセイなどは、「今なら間に合うヤンバル探検隊」「沖縄人のための越境のすすめ」「おろかな魔物は直進する」「泡盛にあって他にないもの」「四軍調整官による講演の計画に抗議する」など。
沖縄に関する本の書評・解説で取り上げているのは、「南島文学発生論」(谷川健一)、「八重山生活誌」(宮城文)、「山原バンバン」(大城ゆか)、「高等学校 琉球・沖縄史」(沖縄県歴史教育研究会)、「アコークロー」(宮里千里)、「琉球王国」(高良倉吉)、「料理沖縄物語」(古波蔵保好)、「水滴」(目取真俊)、「恋を売る家」(大城立裕)、「てるりん自伝」(照屋林助)、「ゆらてぃく ゆりてぃく」(崎山多美)、「沖縄おじぃおばぁの極楽音楽人生」(中江裕司)、「街道をゆく 沖縄・先島への道」(司馬遼太郎)、「新南島風土記」(新川明)、「沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史」(佐野眞一)など。
講演は「太平洋に属する自分」。
ボーダーインクにしては少し値の張る本ですが、いい読み応えがありました。
(2018. 3.13 読)

|
 |
「沖縄からの出発 わが心をみつめて」 岡部伊都子 著
講談社現代新書 583円+税 1992年10月20日 第1刷発行
「沖縄戦に斃れた婚約者の足跡を追って訪れた沖縄の島々。その旅を通じて知った沖縄の苦難に満ちた歴史と現実、人々のまごころ。時の風化のなかで忘れがちな沖縄の心を切々と語り継ぐ、感動の記録」――という本。
古書店から1円+送料で手に入れたのは、1992年発行の新書。この原著は1972年の「沖縄からの出発――わがこころをみつめて」ですから、書かれてから45年後に読んだことになります。
収録は「「ヤマト世」二十年」、「二十七度線」、「土着のこころ」、「沖縄に照らされて」、「消えゆく戦の傷跡」、「沖縄人(うちなんちゅ)と共に」6篇です。
著者は、1923年生まれの随筆家。大阪市出身で、婚約者が沖縄戦で戦死。戦後すぐに結婚するも7年後に離婚。2008年に85歳で逝去しています。
文章としてはやや難解なほうかもしれません。しょうがないことですが、読んでいて文章表現や内容に古さを感じざるを得ないところがあります。
「敗戦後、半年たって彼(婚約者)の母にもたらされた公報には、「陸軍少尉木村邦夫様には20年5月31日沖縄本島島尻郡津嘉山に於て戦死。」と記されていた。」
著者は、25歳で散った婚約者がどういう土地で、どのようにして死んでいったのかを知るために、死後23年を過ぎた1968年になってから、初めて沖縄に渡ります。「二十七度線」ではそのときのことが克明に語られています。
そしてその際に見聞きした沖縄に惹かれ、著者は何度か沖縄を訪れるようになります。
ところで、自分が初めて八重山の竹富島を訪れたのは1998年のこと。その際に、新田観光の水牛車に揺られながら、あれが日本の女流作家のナントカという人が島に建てた家だ、という説明を受け、その建物を見た記憶があります。平屋で赤瓦屋根の小さな家でした。そのときは、なんとまあ、またずいぶん遠くに別荘を建てたものだ、酔狂な金持ちのすることは理解できんな・・・ぐらいにしか受け止めていませんでした。
しかし、今思えばそれが、岡部伊都子が島の子どもたちにたくさんの本に触れてもらいたいとの思いでつくった「こぼし文庫」だったのかもしれません。
調べてみると、「こぼし文庫」は今もなお新田観光の近くに存在しているようです。
蛇足ですがこの本を、2017年10月1日に開かれる「琉球フェスティバル2017東京」を見るべく上京したホテルの部屋にて読了しました。
(2017. 9.30 読)

|
 |
「南の島の便り やぶれナイチャーの西表島生活誌」 岩崎魚介 著
沖縄出版 1,600円+税 1997年 6月15日 第1刷発行
1997年発行の本で、副題に誘われて中古市場から購入し、その20年後の2017年に読みました。
著者が約5年にわたる西表島での暮らしを、主に本土に住む友人・知人に宛てて送った「南の島通信(ぱいぬしまつうしん)」というミニコミ誌を下敷きにした、等身大の生活レポートです。
著者は、1960年東京生まれで横浜育ち。専門学校卒業後、出版・編集の中小どころを転々としながら沖縄の政治・経済・自然などの問題に傾倒、83年ごろから在ヤマトの沖縄出身者らと交流、84年に念願の八重山行きを実現し、その後「八重山病」の重症患者となって、90年に西表移住を達成。諸般の事情により95年には石垣島へ「撤退」したという経歴を持つ人物です。
著者は「はじめに」で、次のように綴っています。
「デジャ・ビュ(既視感)という言葉があります。・・・初めて触れた西表島に感じたのが、まさにそれなのです。古い家並みのたたずまい、それを囲む石垣、熱帯植物の防風林、白砂を敷き詰めた道、リーフに打ちつける白波、眩しいほど白い砂浜、緑深く連なる山、山。それに加えて純朴な笑顔のファーナー、オジィ・オバァの真っ黒に日焼けした顔などなど。これらすべてに圧倒され、次に魅了されてしまったのでした。・・・頭の中が真っ白になるほどの衝撃でした。」
「そんな暮らし(八重山通い)を6年あまりも続けるうち、島での暮らしと、都会であくせく働き時には愛想笑いを浮かべ、人混みに翻弄されるギャップに悩むようになったのです。・・・ああ、と嘆息してふと目を上げれば、そこには西表島の島影が陽炎のように浮かんでいたのです。当時、私には最愛のパートナーがおり、彼女(徳之島出身)とともに「西表入植隊」を結成し、春まだ浅い横浜を出立したのでした。」
6つの章立てとなっており、「島の暮らしはエキサイティング」、「島の裏側を覗いてみれば」、「南風に吹かれながら」、「美味なヤツは喰うに限る」、「神々のすがた」、「島の歴史(体温)に触れる」。
単に「訪れる」のと実際に「住む」ことはベツモノのようで、島で仕事をし、島ならではの様々なことに仰天し、同僚とともにビーチャー(酔っ払い)生活をして、「訪れる」だけでは得られない島や島人との絆を深めていきます。その過程が、筆者の性格や表現力が反映されて、随所に挿入されるウチナーヤマトゥグチと相俟って、とてもおもしろい読み物になっています。
また、西表島とはどういうところか、ということについても、よーくわかりました。台風あり、仕事なしで、家族みんなが暮らしていくにはなかなか大変そうです。
(2017. 8. 8 読)

|
 |
「消えゆく沖縄 移住生活20年の光と影」 仲村清司 著 光文社新書
780円+税 2016年11月20日 第1刷発行
自分が沖縄を初めて訪れたのは1993年。それ以来50回近く沖縄に通い続けてきましたが、率直な感想を言うと、沖縄はすっかり変わりました。
初訪時の沖縄は、国際通りには米軍払下げ品の店や貴金属店などがたくさんあり、普通のお土産店一色の今とは違ってアメリカ世の名残りが感じられました。
旧国道329号線沿いの古波蔵あたりの道路は狭く、両側には古い建物が水タンクを備えた姿でびっしりと立ち並び、異国の風情があったものです。
那覇空港は新しくなる前の黄緑色の小さな建物だったし、首里城は復元公開されたばかりでした。
そして内地の者から見て圧倒的だったのは、沖縄の文化です。当時は沖縄ポップカルチャーが波に乗っていた頃で、りんけんバンドやネーネーズなどが大活躍。それらの背景を探ってみると、奥の深い琉球民謡の系譜があり、琉球舞踊や歌劇・芝居があり、夜ともなればあちこちで琉球舞踊が見られる店や民謡酒場が店を開き・・・という具合なものでした。
いまよりもずっとウチナーグチを話す人が多く、那覇を少し離れれば赤瓦屋根の建物が目立つような時代でした。
1998年の秋に目の当たりにした大田昌秀と稲嶺恵一が戦った知事選などは、振り返ってみればあれが大事なターニングポイントだったのかもしれません。
ところが今の沖縄は、ほかの地方都市と同じような表情を持つ町並みへと変わってきました。女性たちのスタイルや顔立ちも西洋化してすらりとしており、話す言葉も、立ち居振る舞いも、都会的です。
毎日といっていいほどどこかで開かれていた芸能公演は激減し、てびちや汁物が食べられる大盛り激安の大衆食堂もあまり見かけなくなったような気がします。
これから沖縄は、どこに向かって進んでいくのだろうなぁ。
そういう憂いにも似た気持ちをずっと抱えていましたが、同じようなことを思っている移住者がいました。大ファンである仲村清司です。
大阪生まれの沖縄人二世である著者は、1996年に那覇に移住します。当時は「沖縄ブーム」の走りの頃であり、その後NHKの連続テレビ小説「ちゅらさん」の影響もあり2000〜05年頃をピークに、沖縄は「有史以来」といわれる空前のブームを巻き起こしました。
一方、その裏側では、95年に起きた米兵による少女暴行事件をきっかけに、日米地位協定の見直しを含めて反基地運動が高まりをみせます。そして96年、普天間基地の返還が発表され、辺野古移設へと基地問題が動いていきます。
そしてその後の20年の間に、沖縄で何が起きたのか――。
「沖縄ブーム」「沖縄問題」と軌を一にし、変質していく文化や風土などに触れ続けてきた著者が、<遺言>として「中期決算的な自分の心情と素顔の沖縄」を綴ります。
プロローグに「1996年の沖縄、2016年の沖縄」を前置し、「戸惑い―観光立県・沖縄の現在」、「失われゆく風景―故郷、那覇、農連市場」、「溝―移住者の揺らぎ」、「葛藤―まとまる沖縄とまとまらない沖縄」、「民意―沖縄の真価が問われる時代」、「信仰―消える聖域と畏れ」の6章立て。最後に「エピローグ―私たちは<矛盾>とどう向き合うのか」。
沖縄を愛する著者は、米軍基地問題をめぐって沖縄と本土の関係が悪化していく中で、著者が探し求めてきた沖縄社会の基層がほかならない沖縄人の手によって切り崩されていく様に、「疲れてしまった」といいます。現実の沖縄社会の急激な変質に失意を覚えているのでしょう。それは沖縄への報われなかった「片想い」、でしょうか。
すっかり変わり果てた沖縄に残す「遺言」だと著者は言いますが、著者の変わらぬ沖縄への愛情がそこまで言わしめていることは論を待ちません。
(2017. 3.14 読)

|
 |
「島猫と歩く那覇スージぐゎー」 仲村清司 著 双葉社
1,600円+税 2013年 9月25日 第1刷発行
ひょんなきっかけで、「僕」は一匹の捨て猫と出会った。出生地、那覇市桜坂社交街。性別メス、容姿端麗――。
「向田さん」と名付けて暮らし始めたその猫と一緒に、那覇の町に出た。デイパックに向田さんを入れて、気ままに昼の路地裏をぶらついてみる。日が暮れると酔客が行き交う街路で、見過ごしていた風景に出くわした。路傍を彩る原色の花々、光るような海風、季節が立つ気配、そして、向田さんの血族とおぼしき野良猫たち……。
吹き上げる緑も、古径に乱舞する蛍も、これまで以上に新鮮に映った――。
という、表題どおり猫とともに暮らす那覇めぐり本といったところ。
仲村清司は好きで、彼の著作はだいぶ読んできていますが、今回は自分の範疇外の「猫」本ということで、2013年の発売当時は買い求めませんでした。しかしその後2年以上が経過し、古書市場に送料込み1,128円で出ていたので買ってみたものです。
仲村清司の「沖縄愛」に満ちた独特の筆致です。その文章に登場する那覇のまちの描写と、そこから感じ取ることができる那覇の色や匂いが見事。そしてまた、その中に時として顔を出す筆者のナイーヴな思いや精神状態が効果的なスパイスとなって綴られていきます。
近時劇的な変貌を遂げつつある桜坂界隈のほか、自分にとっても愛着の深いニューパラダイス通りや壺屋界隈とてんぷら坂などが舞台。ほかにも崇元寺通りの一本北の通りとなる泊地区や、栄町市場、首里の綾門大道などが登場するので、那覇・首里タウンウォーカーにとってはかなり興味深い内容になっています。
久々に前へ、次へと読み進めることができた沖縄本。
自分の場合、猫に対する格別の思いは持ち合わせていませんが、スージぐゎーでひっそりと生きている野良猫たちの様子を知ることができたのも一興でした。
(2016. 7.31 読)

|
 |
「夕凪の島 八重山歴史文化誌」 大田静男 著 みすず書房
3,600円+税 2013年 8月15日 第1刷発行
沖縄地方では「夕凪」を「ゆうどぅり」といい、特に離島に住む人々は、日が暮れる前に風が止まる静かなひとときに深い愛着を持っているように思います。また同時に、このもう少し後に訪れるたそがれどきを「逢魔(おうま)が時」といって畏れるなど、昔から独特の時間の感じ方を持っているようです。
それらは、たとえば八重山の御嶽(オン、うたき)あたりに佇んで島時間に身を委ねて実際に体験してみれば、なるほどなと実感できるもの。とても心地よいのですよ、八重山は。ああ、行きたいなぁ。
そんな感覚を本でも味わいたくて、古書にて購入。2013年の発売当時は3,600円+税の高価格に躊躇して買えなかったものを、15年の秋に送料込み1,636円で手に入れることができ、一人ご満悦状態です。
『八重山を「日本」や「沖縄」と安易に一体視はできない。凪(平和)が危機の今、本土中心の日本史に収まらない時空世界を独創的発想と緻密な研究で掘り起こす。』(コシマキから)――といった内容のものです。
著者は、石垣島きっての文化人のよう。1948年石垣島生まれ。地元紙記者等を経て、石垣市立図書館開館準備室で郷土資料を担当。石垣市立八重山博物館勤務ののち石垣市教育委員会文化課長。(2008年退職)
八重山諸島の戦史・戦後史・芸能史・ハンセン病史を調べ、『八重山の芸能』(ひるぎ社)で沖縄タイムス出版文化賞、『八重山の戦争』(南山舎)で同賞と日本地名研究所風土研究賞を受賞し、2012年、八重山毎日新聞社の八重山毎日文化賞を受賞。
石垣市文化財審議委員、とぅばらーま大会作詞の部審査委員、「沖縄県立図書館八重山分館廃止に反対し、存続を求める会」共同代表。1992年の創刊以来、月刊誌『やいま』(南山舎)で「壺中天地」を連載中。
本書は、その「壺中天地」に連載したものを中心に加筆し、数編を書き下ろしたもので構成されています。論調は、たとえば「まえがき」の一部を引用すれば、次のとおり。
『私たちは北に向かうと、なぜか心が寒くなる。支配者、暴虐者のイメージしかない。逆に、南へ向かうと世果報(五穀豊穣、幸いなる世)がもたらされ、柔和で悠久に身をゆだねる南東人を見ると心が安らぐのである。
事が起きれば、母なるニライカナイと侵略者ヤマトの相違が心の中で鎌首のように持ち上げてくるのである。これは沖縄人にとってどうしようもない心境であろう。
海風を浴び、神々と生きた時代に戻ることはできない。しかし掌の平和を日本国家によって壊されることには抵抗する以外にない。ひとりの人間として。』
どうです。穏やかな表現の中にもしっかりとした思想がありますよね。
(2016. 7.14 読)

|
 |
「哀愁のB級ホテル あなたに伝えたいデイゴホテルの物語」 宮城 悟 著
燦葉出版社 1,500円+税 2014年 8月30日 第1刷発行
『UG(好ましくない客)情報おそるべし?! スキッパー(逃亡者)に呆れ、No
Show(予約したまま解約も利用もしない客)に泣く。
アメリカ人向けホテルの歴史とホテルマンならではの裏話が満載。ペーソス漂う自虐ネタの中に基地の街「コザ」への限りない愛情があふれている。』 (コシマキから)
デイゴホテルにはもう何泊したでしょうか。コザに出向いたときの常宿として頻繁に利用しており、現在の増築前の、玄関前が駐車場だった時代からお世話になっています。格安で居心地がいいのに加え、ここには古き良きオキナワの残影が染みついていますから。
他のシティホテル、ビジネスホテルにないまったりとした時間が流れていて、1階のレストラン「うりずん」はその極致。がらんとしたところに適度な照明が施され、フロア担当は呼び鈴を何度も鳴らさない限り出て来ないといった按配で、ビールのアテに軽くつまもうと春巻を頼めば、ポークランチョンミートが入ったぶっといものが5本も運ばれてきて、もうそれだけで満腹になる上に、「おいしいから食べてね」と島らっきょうを無料サービスしてくれるようなところなのです。
そしてここは、あの嘉手苅林昌などもよく利用したという並々ならぬ歴史、逸話も満載なのですから、沖縄民謡フリークとしてはたまりまへんがな。いやぁ、大好きだな、デイゴホテル。
で、そのデイゴホテルのひょうきんな若社長だった宮城悟氏が書き綴ったのがこの本。2014年1月から琉球新報のコラム「南風」を担当し、コザをテーマにした軽妙なエッセーが人気を博し、それが本書の刊行のきっかけとなりました。
刊行されたことを知らなかったのだけど、古書で見つけたので即買いしました。
若社長「だった」というのは、氏は本書執筆中の2014年6月8日に急逝したから。「みんな、ありがとう」と病床にて乱れ字ながらも書き残した一言が、最後の原稿だったそうです。
そんなわけで、鈴木雅子氏(元カフェバー「コザクラ」店主)が編集人となって、同年8月30日に発刊されました。
以下に、2014年6月11日付の琉球新報「金口木舌」の一部を引用しておきます。
コザのホテルマンの心意気を「哀愁のB級ホテル」に込めた。経営するデイゴホテルを「B級」と称したのは大型リゾートホテルにはない独自性の証。「哀愁」は、街の歩みに根差している。
米兵相手のホテル稼業の興隆と辛苦を見てきた。ドルで潤い、基地内のホテル建設を促す「思いやり予算」に泣いた。戦場に赴く米兵の横暴と苦悩に接した。ホテルの歩みはコザの戦後史に重なる。
病と闘い余命を見詰めコラムを編んだ。息を引き取る間際、病室で紙片にメッセージを残した。「みんな、ありがとう!」と。ホテルマンを愛したコザの仲間たちは、これからも街の物語を紡いでいく。悟さんの心を胸に。
(2016. 5.21 読)

|
 |
「沖縄時間 本物のスローライフの見つけ方」 岸 朝子 著 大和出版
1,400円+税 2004年 8月 3日 第1刷発行
2004年発行のものを古書市場から購入し、2016年に読みました。
「沖縄の時間はゆったりと流れる。沖縄の食文化に詳しい著者が、せかせか生きる現代人に、沖縄流のスローライフを提案する。」という趣旨の、ゆるゆる、テーゲーな雰囲気たっぷりのやわらかいエッセーです。「人生の深呼吸、しよう」、かぁ。
著者は、1923年生まれの食生活ジャーナリスト。ということは、この本が出版された時にはすでに81歳?!
フジテレビ系「料理の鉄人」に審査委員として出演し、「おいしゅうございます」の言葉が話題となった人、と言えば思い出す人もいるでしょうか。
「はじめに」で、作品の意図を次のように記しています。
『21世紀は「心の時代」だといわれます。・・・これまでの忙しい暮らしを、ほんの少しスローダウンしてみませんか。「あれをしなければならない」「これもするべき」とがんばり過ぎるのをやめてみませんか。
のんびりと、ゆったりと。「沖縄時間」で生きてみると、これまで忙しさに紛れて気づかなかった、本当に自分がやりたかったことと出会えるかもしれません。
がんばり過ぎたり、人と比較したりしなくても「今の自分が好き」と誇れる人になれるかもしれません。
この本では、私が大好きな沖縄の人々の暮らしぶりを、独特の食文化や沖縄人気質、元気で長生きしているお年寄りが多い秘密など、様々な角度からご紹介していきたいと思っております。
皆さんにとって、今よりもっと自分らしく人間らしい、新しい生き方を探すヒントとなれば幸いです。』
年齢のわりには洒脱な文章を書く人だなという印象。(失礼)
文中には、たとえばこんな逸話なども紹介されています。
『あるオジィが病に倒れ、いよいよもう危ないということになりました。家族や親戚が枕元に集まる中、オジィは最後の力をふりしぼって息子に封筒を手渡しました。
「この手紙は、おまえが仕事に失敗してにっちもさっちもいかなくなった時に開けなさい」
オジィはそれだけいうと、安心したようにそのまま静かに息を引き取りました。
数年後、息子は本当に仕事に行き詰ってしまいます。そして、思い悩んだ挙げ句にオジィの手紙を開いてみることにしたのです
白い便せんをそっと開いてみると、そこには一言こう書かれてありました。
「ナンクルナイサァ」』
――サイコー! 沖縄らしいよねぇ。
序章から第5章までの章立ては、次のとおりです。
「東京生まれの東京育ち。でも故郷は沖縄です」「ゆるゆる沖縄―南の島の時間はゆっくり流れるのです」「テーゲー主義でいこう!―沖縄人はみんな楽天家なのです」「ごはん食べてくさぁ―沖縄のスローフードを訪ねる」「理想のスローエイジング―沖縄じゃ、オジィオバァが一番元気」「岸流「ナンクル暮らし」―わたくしのとっておき健康法」。
(2016. 4.10 読)

|
 |
「沖縄 若夏の記憶」 大石芳野 著 岩波書店 1,900円+税
1997年 6月16日 第1刷発行
著者は、1944年東京生まれで、日本大学芸術学部写真学科を卒業後、ドキュメンタリー写真に携わり、ベトナム戦争、カンボジアの虐殺、スーダンのダルフールの難民、原爆の広島の人々などを取材して、平和と人間の尊厳を見つめる著書を残した人。
この本は1997年の発刊で、それを古書店から購入して2015年に読みました。コシマキのキャッチには、「アジアの臍の沖縄にて。復帰以来25年、撮り続けてきた沖縄。豊かな風土に寄り添いながら生きる沖縄人への熱い想いを綴った最新フォト・エッセイ」とあります。
写真家による書籍なので、ページを彩る写真は沖縄の風景に加えてウチナーンチュの内面まで浮かび上がらせる陰影の深いスナップなども織り込まれており、秀逸。
しかしこの本の優れているのはその文章で、女性的な感受性で切り取った沖縄らしい断片が随所できらきらと輝いている感じがします。書かれた時代がまだ沖縄が輝きを放っていたからだとも言えるかもしれませんが、やはりこれは、書いた人が優れているからなのでしょう。
読んでいて最も気に入った部分を以下に抜き出しておきます。
他人(ちゅ)に殺(くる)さってん寝(に)んだりーしが
他人殺(ちゅくる)ちぇ寝(に)んだらん
これは、他人に痛めつけられても眠ることができるが、他人を痛めつけたら眠れない、という意味の言葉だ。
たしかに、相手を一方的になじっている言葉を沖縄では聞いたことがない。私たちヤマトンチューだったら怒鳴るだろうにというときでも、だ。
その度に、考え込んでしまう。
ウチナーンチュの優しさや懐の深さには敵わない。それにしても、このことわざのような優しさを、人びとはどのようにして、慌ただしく騒然とした現代にまで持ち続けてこられたのだろう。もっとも、狭い島の中でいちいち怒ったり喧嘩をしていたのでは、息苦しくなってお互いに暮らしてはいけない。そうした理由も一方にはあるかもしれない。
でもこの深い優しさは、何よりも海を介して付き合ってきた他民族との、平和な共存を願う思想に他ならないのではないだろうか。「平和な島」とは、先祖代々の「往(い)にし方(え)」から脈々と体の中で繋がってきた祈りのような言葉だ。
「平和な島」であり続けるには、相手もまた、平和でなければならない。ごく当たり前の個人の気持ちが広がって、大勢の願いになり、沖縄の歴史として培われてきたように思う。
これを書いていて、上原知子(りんけんバンド)のうたう「にんだらん」(作詞・照屋林助、作曲・照屋林賢)が、わが脳内を流れました。このうたの歌詞も併せて記しておきましょう。
旅宿に浜千鳥ぬ 泣ち声聞きばよ 生まり島まさてぃ 眠んだらん
チュイチュイナ チュイチュイナ
旅や浜宿い 草ぬ葉どぅ枕 寝てぃん忘ららぬ 我やぬ御側
旅宿に照月ぬ 涙に曇てぃよ 思び出すさ島ぬ同志辺 肝情
チュイチュイナ チュイチュイナ
渡海や隔みてぃん 照る月や一つぃ ありん眺みゆら 今日ぬ空や
旅宿や窓る見ば 夢のしじさよ 浮かび見る海とぅ山ぬ 懐かさよ
チュイチュイナ チュイチュイナ
旅宿ぬ寝覚み 枕すば立てぃてぃ 思び出すさ昔 夜半ぬ辛さ
うーむ・・・、琉歌はいいですねぇ。りんけんの奏でる三線の音色がビシビシ聴こえてきますねぇ。
(2015.12.12 読)

|
 |
「りゅうきゅうねしあ―沖縄・こころの旅」 辰濃和男 著 朝日新聞社
650円 1973年 2月28日 第1刷発行
1973年に刊行された古い本。これを古書店から2012年6月に入手し、2015年の秋にようやく読みました。
40年以上も前に書かれたもので、その当時は沖縄が日本に復帰したての頃、ということになります。
琉球の島々を「リュウキュウネシア」と呼び、著者がかつて訪れたことのあるポリネシアの島々と比較しながら、やふぁやふぁとした感じのエッセーに仕立てています。
珊瑚礁の海はいつも懶(ものう)い風と光の中にあり、その雰囲気を、タヒチやサモアや沖縄の人々の柔和な目の中にも見ることができた――と著者はいいます。
著者の辰濃和男は、1930年東京生まれ。東京商科大学(一橋大学)卒業。大学では新聞部に所属。卒業後朝日新聞社入社し、浦和支局、社会部、ニューヨーク特派員、社会部次長、編集委員、論説委員、編集局顧問を歴任。この間1975年から88年まで「天声人語」を担当。退社後は、朝日カルチャーセンター社長、日本エッセイスト・クラブ理事長も務めました。
「リュウキュウネシアの島々の中に、ぼくは海のすばらしさを見、懶(らん)の思想を見、「てえげえ」の神々を見、反文明の世界のゆたかさを見、「戦さよりも恋を」と考える非暴力主義を見、自然と神にとけこんだ生活を見、ともにうたい、踊る人々の歓びを見、手づくりや「分身」の美しさを見、祖国を拒む人々を見、そして愚直なまでにきびしい自己への問いかけの姿勢を見てきました。
そしてその多くは、かつてポリネシアの島々を旅した時に感じ得たものと、びっくりするほどよく似ていました。
ぼくが見た、と思ったものの中には、あるいは幻想にすぎぬものもあるでしょうし、日々、変りゆく沖縄の島々では、明日はもう崩れさって、近代に吸収されていくはかない幻影もあるかもしれない。しかし沖縄に吹く異化の風がエネルギーをたくわえつつ熱帯低気圧のように成長してゆく限り、数多くのリュウキュウネシア的な神話はさらに生き続け、人間らしさとはなにかをたえずぼくたちに問いかけてくれるに違いない。」
「ごくおおざっぱに本土と沖縄とを図式的に対峙させれば「競争社会」対「共同社会」ということになるでしょう。そして沖縄の共同社会の中に、ぼくは懶のさまざまな姿を見つけることができる。その中には老子のいう「無為」の哲学も含まれていますし、ソローの「瞑想」の精神も含まれている、と思います。
競争社会の中にあるのは、根性・効率・スピード・学歴尊重・大量生産・成功・管理・豊かさ・流行・力・早いもの勝ち・点数主義・コンピューター・合理性・人間疎外。
懶の社会の中で、その一つ一つに対峙するものはなにか。それぞれ次のようなものを考えたい。
瞑想・てえげえ・漫歩・仲間・手づくり・創造・無為・はだし・やさしさ・ものぐさ・愛情・自然・神秘・人間らしさ。」
競争社会のキーワードには、昭和40年代の高度経済成長のイケイケ時代を思い出させるものもあって思わず苦笑してしまいますが、沖縄の真髄をとてもよく捉えている内容だし、それらの多くは40年後の現在にもあてはまるなあと思いつつ、読みました。
(2015.10.17 読)

|