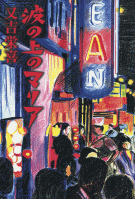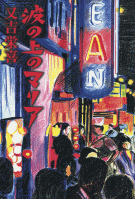|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
「時空超えた沖縄」 又吉栄喜 著 燦葉出版社 1,800円+税
2015年 2月20日 第1刷発行
沖縄在住の芥川賞作家・又吉栄喜の初のエッセイ集。
「昭和50年頃、少年時代、一心不乱に遊んだ「原風景」が現在にもつうじる普遍性を帯びている、人間の問題にも通底すると考えるようになり、エッセイを基に小説を書き始めました。
小説を書いている途中、登場人物も原風景の中の人物をモデルにしている、と気づきました。」(「前書き」から)
その原風景とは、家の半径2キロ内にあった、琉球王国発祥のグスク、戦時中の防空壕、沖縄有数の闘牛場、広大な珊瑚礁の海、東洋一の米軍補給基地、Aサインバー街、戦争の痕跡をカムフラージュするために米軍機が種をまいたというギンネムの林、地元の人がカーミジ(亀岩)と呼ぶ海岸に突き出た大きな岩、戦死者の白骨や遺品など。
「沖縄という固有の精神風土と人々の営みを見つめ、すべてエッセイに込めてきました。いつのまにか膨大な量になり、私の人生の軌跡にもなっています。」(コシマキから)
琉球新報(2015年4月12日)に掲載されていた詩人・高良勉の書評が的確だったので、以下に引用します。
作家の又吉栄喜が、40年間も注文を受け書きためてきたエッセーを、初めて単行本に編集して出版した。膨大な作品群から選抜し、「第一章 原風景1」「第二章 原風景2」「第三章 自然1」「第四章 自然2」「第五章 戦争」「第六章 米軍基地」「第七章 祈り1」「第八章 祈り2」と構成してある。
その一篇一篇が独立した作品であると同時に、全体を通して「作家にとってエッセーとは何か」という問い掛けが貫かれている。数多くの作品が読みやすいが、その中でも「木登りサール」「放射能雨」「想像の浦添」「闘牛賛歌」「沖縄の楽天性」などが特に印象に残っている。
それにしても、「原風景」の章のエッセー群は又吉文学・芸術の源泉を描き出している。「少年時代の「原風景」が現在にもつうじる普遍性を帯び、人間の問題にも通底すると考えるようになり、エッセーを基に小説を書き始めました」と述べている通りである。
私は、又吉とほぼ同世代なので少年時代に「放射能雨」などの似たような体験をしている。従って、それらの体験の中から何が「現在にもつうじる普遍性」として選ばれ「小説化」されたかもよく分かる。又吉の体験は、単に「自叙伝的記録」に止まらず、文学・芸術として描き込まれているのである。
又吉は「田宮虎彦の「足摺岬」とか、太宰治の「津軽」とかのように浦添を想像で形象して、後世に残したいという見果てぬ夢を見ている」(「想像の浦添」59ページ)とも述べている。
ぜひ挑戦し実現してほしいものだ。浦添の原風景から書き込んでいって「時空超えた沖縄」のかなたに「津軽」のような言語空間の名作が生まれてほしい。
すでに、作品「沖縄の楽天性」で時空超えた沖縄について書いた又吉には、決して不可能な要望ではないと思う。本エッセイ集はその文学・芸術の豊かな源泉を指し示している。
(2018.5.5 読)

|
 |
「呼び寄せる島」 又吉栄喜 著 光文社 2,500円+税
2008年 2月25日 第1刷発行
琉球新報に2005年4月から1年半にわたって連載されたもののよう。
単行化された著者作品のなかでは13本目のものです。
沖縄本島で脚本家を目指すものの何度も賞に落選した諒太郎は、心機一転を図ろうと故郷の離島・湧田島で民宿をはじめようとします。宿泊客から奇人を探して脚本のモデルにしようとの企みです。
又吉作品に登場する他の主人公男性と同様に、いつも優柔不断で、自分の言いたいことを心でぐっと止めるような性格の持ち主です。
その諒太郎の周りを、幼馴染である修徳や、猛雄、秀敏、安七、徹などの村役場関係者が脇を固めています。しかし彼らはいずれも考えに芯がなく、前言を簡単に翻すような軽い男たちです。
そこに、本島から島にやってきた周子、周子と入れ替わるようにやってきたその娘のクミ、これも本島から来て役場で短期就労する文学少女の千穂子などの女性が絡んで、つかみどころのないナンクルナイサ的な又吉ワールドへ。(笑)
そしてさらに、戦争体験者の長老、千穂子の文学パートナーの夢遊病者、霊能者のナベおばあ、魚の眼を好んで食べるキジムナー男、毒のような薬をつくる秘薬老女、島のあちこちに落とし穴を掘る自然保護運動家の与儀、全身皮膚病のミイラ少女、CM制作会社の伊波などが次から次へと登場し、小さな離島を舞台に様々なことが起こります。
それらはいずれも一般的に見れば奇異なことばかりで、普通の離島でよく起こるようなこととは到底思えません。
もしかしたらそれらは、作家の脳内をシュールな形で表現しているのかもしれないとは思ってはみるものの、パーツパーツはそれぞれがつくり話の喜劇でしかなく、読者にとって脈絡のない喜劇はダジャレの連発を聞かされているのと同様にあまり楽しいものではありません。
著者本人はこの作品について、「登場人物に自分が歩んできた軌跡を分け与え、60年の人生すべてを島という器に込めた作品です。今の都会の人は感情を抑え、自分を偽っている。でも、物語の人物はみんな赤裸々で言いたい放題、やりたい放題。自分をさらけ出せば相手だって自分を出す。それが調和した共同体を作るのではないでしょうか」と語っています。
そうかもしれません。
しかし、このような島は、現実としてはどこにもないことは確かでしょう。
心境を包み隠さずに言えば、「結局この小説で何が言いたかったの?」。
池上永一の描くようなエンターテインメント小説にはなりきれていないし、いちおう純文学なのだろうとの想定で読んでいる身にとっては中途半端であり、あまりぱっとしない読後感が残りました。
氏の6年ぶりとなる15冊目「時空超えた沖縄」(燦葉出版社、2015)がすでに手元にあるので、近々それも読みたいと思います。
(2017.12.24 読)

|
 |
「巡査の首」 又吉栄喜 著 講談社 1,800円+税
2003年 2月24日 第1刷発行
単行又吉本の11冊目として2003年に発刊されたもの。
沖縄の「巡査」モノといえば池宮城積宝の「奥間巡査」が随一ですが、これはどうなのだろうなと思って購入しました。
2015年3月に買い求め、2017年3月に読み終え、同年9月になってからそのインプレッションをまとめようとしているわけです。
しかし、読んでから半年も経ってしまうと、読後の印象なんてすっかり失われてしまい、どーゆーあらすじなんだっけ?というところから振り返らなければならなくなります。
うーむ、かといってもう1回はじめから読むというのもなんだし。こういうときはふつうネットを漁ってみるのが効果的なのですが、困ったことにあまりいい内容のものがヒットしないんだよなあ。
――という状態で書いています。嗤ってくださって結構ですよ。
でまあ、ネット通販によく出ているこの本の紹介を引用。
「巧一郎は、なぜ「首」を無くしたのか。本当に同僚を殺したのだろうか。
克馬と早紀の兄妹は祖父の真実を求め小舟(サバニ)で謝名元島から垂下国へと漕ぎだした。
〈首狩りの風習〉を追究する芥川賞作家の力作。
四国の半分ほどの大きさの垂下(すいか)国は、謝名元(しゃなもと)島の西南160キロにある。
元々の名称はジャガル島だが、阿族が両手に下げていた生首を戦前日本人が西瓜と見間違え、「西瓜島」と名付けたのが、いつのまにか「垂下島」に転じたと言われている。――(本文より)」
・・・。つまりは、沖縄をモチーフにして書き続けてきたこの芥川賞作家は、ミステリーやはたまたファンタジーの分野に自らの新天地を求めたのでしょうか?!
少しシェイクダウンすると、沖縄の謝名元島から160km離れたところに垂下国という国があり、そこには首狩りの習慣がある阿族が治めていた。そこで以前巡査をしていた功一朗おじいは同僚を殺害し、阿族に首を切られて死んだのだといいます。
そこで、孫である克馬と早紀は、滝おばあの骨を功一朗おじいのもとへ埋めてあげようと考え、あわせておじいが同僚を殺したという真相を確かめるために、垂下国に向かって舟を漕ぎ出す、というもの。
そのような非現実的なほうに話が行ってしまうと、ハマれば面白いのだけれども、そうならない場合はすんなりと物語にのめり込んでいけず、読後にストレスが残るということになります。
モデルは台湾なのかな。しかし沖縄の周辺にはそんな国はなく、ましてや首狩りなんて。
ありえないことをさも事実らしく話されると、自分の場合、冗談だろと思った瞬間にはその先の興味は失うことがあります。なんだかこの作品もそういうカテゴリーに入っちゃうのかなぁ。
又吉作品の非現実性は、沖縄の風習や豚などの動物ぐらいに留めておいたほうが、神秘性も感じられていいんじゃないのかな。
(2017. 3.17 読)

|
 |
「夏休みの狩り」 又吉栄喜 著 光文社 1,600円+税
2007年 3月25日 第1刷発行
相変わらず奔放な「又吉ワールド」が繰り広げられています。
舞台は沖縄の島「仲里島」の夏。主人公の小学5年生の寛は夏休みを迎えており、浜で会った隣りの組の鈴子と、宿題の標本にするチョウセンサザエを獲るために珊瑚礁へと分け入っていくところから始まります。
その後の展開は又吉にしか書けない奔放さ。寛は中学3年生の誠太郎の率いる理不尽な上下関係に疑問を感じつつも、無理強いされる仲間同士の決闘や、罰としての逆モヒカン刈りの「インディアン刈り」、向かいにある半島の子どもたちとの抗争、半島で高く売れるというマングースの捕獲などを体験していきます。
その一方で、島の大人たちは、島の長老が私的な禁酒令を出し、その実現のために女性や青年たちが「監視隊」を結成して取り締まりにあたります。という具合に、なんだかもう、わけわからずの展開になっていきます。
それらとは別に、恋の予感ともとれる鈴子に対する少年のざわざわとした感情や、年老いていくエミばあちゃんへの想い、エミばあちゃんのもとにやってくる宗教関係の人などがからんで、混沌さを増していきます。
そして、又吉作品にいつものように登場する動物。今作は「巨牛」で、島の闘牛大会で圧倒的に強かった闘牛が人知れず海を渡って仲里島にやってきたという設定です。島民が総出で探すものの誰からも発見されず、その後寛たち少年5人だけがそれを発見し、洞窟の穴の中で衰弱して死んだ巨牛を彼らだけの秘密にし、穴を「巨牛の顔」と名付けて彼らの聖域にします。
このようなさまざまな夏休みの体験を通して、少年たちは半島側の少年たちとの抗争に興味を失い、年上の悪ガキの支配から脱して、大人になる道を少しずつ歩んでいくという筋立てになっています。
それにしても、純文学にしてはあまりにも自由闊達過ぎるストーリー。次の展開が全く読めない奇抜さがあり、それを馬鹿馬鹿しいと思ってしまえば、又吉作品は読めないでしょう。逆に、次はどんな脈絡不明の展開がやってくるのかと期待して読めるようになれば、彼の世界に浸ることができるのでしょう。
一気に読んだ自分は、ここにきてようやく後者の仲間入りができたのではないかと思っています。
(2016.11. 4 読)

|
 |
「人骨展示館」 又吉栄喜 著 文藝春秋 1,667円+税
2002年 6月30日 第1刷発行
「真栄城グスク跡から12世紀の若い女性の人骨が出土した」――。
1年前の新聞を処分しようとしていた主人公明哲(めいてつ)は、その記事に引きつけられます。
明哲は、人骨の出土はそれほど珍しいことではないものの、若い女の人骨は初めてのように思い、グスクのあるG村役場で発掘調査の指揮をとる琴乃に人骨の見学を申し込みます。
その人骨は、推定26歳の未婚女性で、神への生贄だった可能性があるといい、人骨への興味が増してきた明哲は、役場に臨時職員として採用してもらい発掘調査に加わります。
人骨はヤマトの海賊の娘だと言い放つ琴乃に対し、地元の人々は、彼らの祖先であり高貴な琉球の女性だと信じて疑いません。
明哲は、地元の人々の親睦会に招かれ酒を酌み交わすうちに、「琉球の神女」説に傾きます。そして、離婚をして村に戻ってきた地元の民宿の娘、小夜子と恋仲になり、彼女の夢だった展示館をつくり、人骨を神女のものとして陳列する計画を立てることに。
好きな女の夢のために役場を退職し、財産をもつぎこむ明哲の運命やいかに……。
――といったつくりの、現代の沖縄を舞台に風刺とユーモアをこめて描かれた人間喜劇です。
この作品が一種典型的だけど、又吉作品にはいつも芯のない他律的「テーゲー」感覚の若い男性が登場し、時には活発な、そして時にはアンニュイな感じの女性たちに翻弄されて、南国的なゆるりとした空気の中をふらりふらりと生きていく情景が描かれます。
ストーリー的にも独特なものがあり、現実を描いていると思えばいつの間にかそれが一線を越えて、奇抜で非日常的な、つまりは小説的な出来事が進行する「ふんにゃりとした」空間に導かれていきます。
これらをファンタジックでほどよい脱力感を得られる好小説と思えるかどうかで、読者側の小説家・又吉栄喜に対する価値判断は変わってくるのだろうなあ。
自分としては、はじめのうちはあまりなじめなかったものの、いくつかの作品を読んでいるうちに徐々にその作風にハマってしまいつつあるようで、心地よく感じています。(笑)
(2016. 5.28 読)

|
 |
「陸蟹たちの行進」 又吉栄喜 著 新潮社 1,500円+税
2000年 6月30日 第1刷発行
2000年3月に「新潮」に掲載され、同年6月に単行化された、又吉単行本としては第8作目となる作品。約200ページ、表題作1本の長編の収録です。
沖縄本島北部のひなびた漁村に、ある時“火葬場建設”という名目で海岸埋め立て計画が持ち込まれました。小さな集落は賛成・反対に分かれてさまざまな軋轢が発生し、その解決のためついには住民投票で計画の是非が問われることになります。
主人公は30歳の独身男性の「自治会長」。本人は、集落にとって経済効果があるとの立場で賛成派。しかし彼の父親は強い反対派で、家屋を反対派の選挙事務所として貸す構えを見せるなど、かなり入れ上げています。
“基地の島”沖縄のリアリティを、痛みと哀しみ、そして独特のユーモア感覚に包み込んで描いている人間喜劇。――とのふれこみです。
沖縄のあれやこれやが端々から感じられて楽しく読むことができました。しかし、又吉栄喜の作品は、会話の部分が多いにもかかわらず、それらが平易な標準語での会話になっていて、ウチナーグチが出てきません。
日本人にとって理解するのが難しい真正のウチナーグチは無理だとしても、せめてウチナーヤマトグチにするか、もしくは間投詞などのとっさに発せられる言葉ぐらいはウチナーグチでいくかしてもらえれば、もっと沖縄らしさが不自然なく出せるのになと思いながら読みました。
ここまでで、2000年までの又吉単行本はあらかた読み終えた形。それ以降の作品はすべて買いそろえてあり、それらのうち「巡査の首」、「夏休みの狩り」、「呼び寄せる島」、そして2015年刊の「時空超えた沖縄」が未読となっています。
もうしばらくの間は又吉作品で楽しむことができそうです。
(2016. 3. 6 読)

|
 |
「別冊カルチュア 木登り豚 又吉栄喜」 カルチュア出版 1,455円+税
1996年 6月25日 第1刷 1996年 9月 8日 第2冊発行
又吉栄喜が「豚の報い」で芥川賞を受賞したのが1996年。受賞直後に「文藝春秋」を買ってそれを読んだときには、沖縄の街場にあるスナックに豚が闖入するなんて、いくら場末とはいってもこれまた妙な場面設定だなあと思ったものです。
その芥川賞作品が書かれる前、すでにその著者が豚をモチーフにした「木登り豚」を書いていたと知り、どうしても読んでみたくなったので、古書店から購入してみました。
正子は父と二人で豚を飼い、豚料理の食堂をやって生計をたてています。そこに絡んでくるのが、80歳を過ぎて一人暮らしをしているカマドおばあ。彼らの間に様々な事件が起き、ガジュマル信仰や御嶽信仰など沖縄独特の文化がからみながら、物語は進行していきます。
その中の記述を一部抜粋すると、たとえばこんな感じ。
「ガジュマルを抱きかかえるようにひれふしている十数頭の豚がいる。ガジュマルの上に栗鼠のように巧みに登っていく豚がいる。姿は豚なのだが、人間のように立っている豚が増えだした。」
「体はまちがいなく豚なのだが、蝉の羽根のような半透明な服を着ている。背広を着た区長がいる。ワンピースを着た雑貨店のおばさんもいる。ステテコを着た素潜り漁のおじいもいる。豚の顔が笑う。大きな、つぶれた鼻の下に、小奇麗に並んだ小さい白い歯がうきでる。何十もの豚が笑っている。だが、目は正子を睨んでいる。」
さて、「木登り豚」を読み終えてから半年ほどたってしまうと、読後感というほどのものはすっかり頭の中から欠落しており、覚えているのはこの本のつくりが変わっていたことぐらいです。
文学としての単行本ではなく、出版界の「沖縄発全国行き」を目指す「カルチュア」という季刊誌の別冊としてつくられたものです。内容としては、作品「木登り豚」のほか、又吉栄喜インタビュー、又吉栄喜秘蔵アルバムのほかに、作品とはおよそ関連のない「沖縄霊験万物コピー曼荼羅」とか、「豚さんを探して」というフォトエッセイなどが掲載されています。
そのうちのインタビューで又吉は、「木登り豚」について次のように述べています。
『「木登り豚」には、何かが成長していく芽生えみたいな、種子のような、爆発寸前の塊があります。塊がはじけて、あの作品を書き上げました。自然描写や人物のやりとり、会話、発想の原点のすべてがこの作品に込められている。種子のほうが花や木よりも栄養価値が高いとも言えますね。
つまり「木登り豚」の「豚の報い」を触発した作品、根底になっている重要な作品なんです。』
(2016. 2.29 読)

|
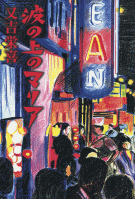 |
「波の上のマリア」 又吉栄喜 著 角川書店 1,600円+税
1998年 8月31日 第1刷発行
2015年3月、古書市場から369円+送料で入手した、1998年に角川書店から発行されたものです。
1960年代、米軍統治下の沖縄。黒人兵にレイプされ子供を身ごもり、心に傷を負いながらも、その子を育て強く生きようと決意するホステス・ミチ。その現実と向かい合えず惰性の日々を送りながら、灯火管制訓練で自作の照明弾を打ち上げ、支配からの憂さを晴らす青年タケシ。
かつて恋人同士だった二人は、対照的な生き方を選んだ。ベトナム戦争が激化し沖縄にも戦場の狂気が波及するなか、再び悲しい事件が二人を襲う…。
沖縄の歴史とともに生活を続ける芥川賞作家が、琉球の土着文化と彩り鮮やかな自然を背景に綴った、アメリカだったころの沖縄の現実。待望の書き下ろし処女長編小説。
読み終えたのが2016年1月で、これを書いているのが16年8月になってしまっているので、今となっては明確な読後感というものはなくなってしまっているというのが本当のところなのだけど、米国占領下の沖縄のどろどろとした部分が表現されていた記憶があります。
幸いこの本は単行本としては珍しく、著者の「あとがき」がありましたので、その中からこの本のポイントと思われる部分を以下に抜粋して、感想に代えることにします。
1960年代の沖縄は現代の最先端と前近代が混ぜ合わせになっていた。Aサインバーの立ち並ぶ大通りを一歩路地に入ると方々の民家に飼われている家畜が餌を求め、鳴き騒いでいた。Aサインバーの中ではニューヨークや東京の銀座に劣らないファッショナブルな装いの沖縄の女性たちが、世界最強の力を誇示する米兵を相手に嬌声をあげていた。
私の家の近くには米軍の広大な補給基地があり、ベトナム戦争の頃には血糊のついたジープや、ボディーや窓ガラスに弾の痕のあるトラックが並べられていた。戦車にはベトナムの泥がくっついていた。
基地からは米兵が鳥籠からいっせいに鳥が解き放たれたように私たちの集落に出てきた。酔っ払った米兵が真っ昼間、電信柱にしがみつき、「帰りたくない」と泣き叫び、同僚になだめられていた。米兵の青い目が何を見ているのか、言葉は何を言っているのか、よくわからなかったが、私はあの頃、タケシやミチのような人物と何度も出会ったような気がする。――
(2016. 1.11 読)

|
 |
「果報は海から」 又吉栄喜 著 文藝春秋 1,333円+税
1998年 2月20日 第1刷発行
又吉栄喜の作品を古書店から買い集め、できるだけ年代順に読んでいこうとしているところです。
この作品は、「ギンネム屋敷」(1981)、「パラシュ−ト兵のプレゼント 短篇小説集」(1988)、「豚の報い」(1996)、「木登り豚」(1996)に次いで1998年に世に出されたものです。
コシマキには、「南風(ふぇーぬかじ)に吹かれて忘れていたことを思い出す」という文字とともに、「芥川賞作家が描く、沖縄の元気2篇」とも記されています。
「木登り豚」は、芥川賞受賞作の「豚の報い」の2年前に書かれたものとされているので、この「果報は海から」が受賞後に書かれたはじめのものになるのではないかと思います。
収録作品は、「果報は海から」と「士族の集落」。
「果報は海から」は、離島のT島が舞台。漁師の家に入婿した男は、妻と姑にかまわれない退屈な日常を送っています。しかし男はそれ打破すべく、山羊を盗み、サバニに乗って対岸の本部半島で店を出しているホステスに会いに行くという冒険を試みます。前作は豚で、今作は山羊。大芥川賞受賞作家がこういうモチーフ専門でいいのかという疑問もありますが、どうなのでしょう。
併録されている「士族の集落」は、那覇に住む青年が祖母に会いに山原(ヤンバル)の奥地に行き、そこで昔ながらの琉球士族の暮らしを体験します。
(2015.12.24 読)

|
 |
「ギンネム屋敷」 又吉栄喜 著 集英社 780円+税
1981年 1月11日 第1刷発行
1981年に発行された、又吉栄喜の初期作品集。
「ジョージが射殺した猪」(「文学界」1978)、「窓に黒い虫が」(「文学界」1978)、「ギンネム屋敷」(「すばる」1980)の3編が収録されています。(カッコ内は初出誌とその年)
又吉は、1978年に「ジョージが射殺した猪」で第8回九州芸術祭文学賞を受賞。また、1980年に「ギンネム屋敷」で第4回すばる文学賞を受賞しています。「豚の報い」で第114回芥川賞を受賞したのは1996年なので、その10数年前の作品群です。
「ギンネム屋敷」は、沖縄戦から8年後の、米軍占領期の浦添市が舞台です。ギンネムの生い茂る屋敷に住む米軍エンジニアの朝鮮人男性に女性暴行の疑いが持ち上がり、沖縄の男たちが慰謝料を要求しに屋敷へ乗り込んでいくところから物語は始まります。
その朝鮮人男性は、沖縄戦直前に飛行場建設のため徴用されてきた人物で、建設当時の過去が語られる後半からは、現実と幻想の境界が徐々に曖昧になっていき、沖縄人の朝鮮人に対する加害と差別、人身や社会を狂わせた戦争の暴力性などが、文章の合間から浮かび上がってきます。
浦添市城間で生まれ育った著者によれば、この作品は家から半径2キロの世界の体験を基に物語を構築したもので、ギンネム屋敷は著者の少年期の原風景なのだとか。
「今の浦添工業の辺りだと思うが、谷底の道が曲がった辺りにギンネムに囲まれた屋敷が実際にあった。外国人が暮らしているとの噂で、僕らは幽霊屋敷として扱っていた」と振り返っています。
著者の少年時代、キャンプ・キンザーの門前町だった屋富祖・城間一帯では、Aサインバーや映画館、食堂などの基地従業員相手の店が並び、商売をしに沖縄中から人が集まり糸満や宮古の言葉が飛び交っていたといいます。
「当時はフィリピンや台湾、朝鮮などの外国人が近所にいてインターナショナルなところがあった。人骨や不発弾もごろごろしていて、スクラップ拾いで小遣いを稼ぎ、Aサインバーで米兵が暴れる。沖縄を象徴するいろいろなものが半径2キロに集積していた」と創作の原点を語っています。
(「琉球新報」のHPを一部引用させていただいています。)
自分が読んだ限りではありますが、こちらの3作品のほうが、先に読んだ「漁師と歌姫」(2009年)よりも数段文章に力があり、魂がこもっているように思えました。
(2015.10.31 読)

|
 |
「漁師と歌姫」 又吉栄喜 著 潮出版社 2,000円+税
2009年 3月 5日 第1刷発行
「ギンネム屋敷」(1981)、「パラシュ−ト兵のプレゼント 短篇小説集」(1988)、芥川賞受賞作の「豚の報い」(1996)、「木登り豚」(1996)、「果報は海から」(1998)、「波の上のマリア」(1998)、「海の微睡み」(2000)、「陸蟹たちの行進」(2000)、「人骨展示館」(2002)、「鯨岩」(2002)、「巡査の首」(2003)、「夏休みの狩り」(2007)、「呼び寄せる島」(2008)などに続いて、2009年に発刊された単行本です。
「パラシュートの…」と「木登り豚」以外はすでに入手しており、このうち「豚の報い」、「海の微睡み」、「鯨岩」は読み終えています。
小説の舞台は、昭和36年の沖縄本島の最北端にあるK村の諸見集落。20歳の漁師である正雄は、一人小舟に乗って漁をし、収穫物を隣の集落に卸しており、高校の後輩で、共同売店で働いている和子に思いを寄せています。
和子がひょんなことから集落の世話役に選ばれたことによって、物語は進んでいきます。
正雄を慕って弟子のように寄り添う五郎や、隣の集落から勝手に正雄に惚れこんで押しかけてくる行商の娘などのエピソードがからみあって進んでいきますが、最後には、漁師であることに誇りを持ち、生まれた集落に愛着を持つ正雄が、和子に翻弄されながらも、自分のアイデンティティをたしかめるために旅に出ていくという成長物語でしょうか。
「じゃあ、これから詩を詠むわね」
「俺はどうしたら?」
「このまま座っていて」
和子は波打ち際に進み、東の方角を見つめ、麦藁帽子をとり、背筋を伸ばした。
しばらくじっとしていたが、タイミングをはかり、口を開いた。朗々と古謡のような詩を詠んだ。妙な節回しがある上、細く高い声は海風に飛ばされ、よく聞き取れなかった。俺がこの夫婦岩に存在していないかのように和子は没入していると正雄は思った。
(本文より)
「俺は、どこに行くのだろうか。一体、どんな力が俺の中に眠っているのだろうか―。
鮮やかな自然と濃密な人間模様の中で流れるゆったりとした時間が、若者たちを大人へと誘う。」
とは、コシマキのフレーズです。
(2015. 9.18 読)

|
 |
「鯨岩」 又吉栄喜 著 光文社文庫 457円+税
2005年 8月20日 第1刷発行
『沖縄の「軍用地主」には、年間数千万もの地代が転がり込んでくる。祖父と二人で暮らす邦博の周囲にも、あり余る金を巡り、怪しげな人物たちの出入りが耐えなかった。そんな彼の前に、訳ありらしい若い女が東京からふらりとやって来る。彼女が言うままに、邦博はある事業を興そうとするのだったが……。』 ――という設定。
又吉栄喜は96年、「豚の報い」で芥川賞を受賞。それを読んだときも少なからず思ったのですが、純文学としては筋書きが突飛というか、次に起こることの脈絡の必然性が薄いというか。印象派の絵画をたくさん見たあと、抽象画を唐突に見せられたような感じ、でしょうか。
巻末の解説で、解説者(湯川豊)はそれを、「人物各自が大マジメに話している会話の滑稽さがある」、「それでも言いっぱなし、聞きっぱなしというものではない会話のズレは登場人物ひとりひとりがもっている時間のズレがにじみ出てくるからである」、「豚とか馬とかハブとか、生き物を描くときの又吉氏の筆致はじつに光彩陸離」などと評しています。
ふむ。言い得て妙と思う反面、ものは言いようだなぁとも。(笑)
年間何千万ももらっている軍用地主なんてほんの一握りしかいないので、主人公のような人は極めて珍しいのでしょう。それから、東京からやってきた美佐子のものの考え方は、常人には理解できないようなレベルのものだと思うし、それに唯々諾々とする邦博の行動も、おれには共感できるところがない。
ということで、理屈の世界に埋没してしまっているツマラナイ常識人には、この本を読むことで精神の安寧や知的好奇心の充足を得ることはやや困難と思われます。
反面、沖縄のものの考え方のまったり感、不可思議感は十分に得られることと思います。
その他。
会話の部分が多いのに、ウチナーグチは出てきません。
表題の鯨岩は、海の岩ではありません。軍用地の中にある洞窟を伴った岩です。
黙認耕作地の中にハブ・パークをつくって観光客を誘致し、米軍を困らせてやろうとの発想は、今の日米関係にあっては奇天烈としか言いようがないとオモイマス。
03年2月単行、05年8月文庫化。
(2009. 9.12 読)

|
 |
「海の微睡み」 又吉栄喜 著
光文社 1,700円+税
2000年6月25日 第1刷発行
1996年の芥川賞作家、又吉栄喜氏の書き下ろしです。氏は芥川賞受賞後、勤務していた浦添市美術館を退職して(1999年)執筆活動に専念したということです。
この作品、池澤夏樹氏が推薦していて、コシマキにはそのコメントが次のように記されています。
『こんなおかしな話はない。会話の細部がいちいちおかしいのだ。宮崎生まれの若い男が沖縄の離島で女に惚れる。その先の展開は、読者の予想を小気味よく裏切り、ひっくりかえし、まぜっ返す。そうか、これが沖縄の女なんだと納得するけれども、惚れたら大変さ。』
うーむ、読む人が読めば、こういう感想になるのかな〜。
というのはですね―。生意気を言わせていただければ、ワタシとしての感想は、「『豚の報い』と何がちがうの?」というものなんですね。主人公の若い男、まわりでその人物をいろどる複数のウチナーイナグ(沖縄の女性)、それらの登場人物の間に漂う男と女の機微、オキナワを連想するゆるやかな時間の流れ…、これらのモチーフは『豚の報い』と同じではないですかね…。それから、会話の細部がいちいちおかしいと言うけれど、主人公の受け答えは杓子定規のようなものが多くて、自分はそう感じなかったし…。
仕事柄、常々第三者を説得させるために書かれたような文章ばかり読まされているものだから、小説というものはどうも、読んでいる最中はそれなりに楽しいんだけれど、読み終わってしまえば「結局何が言いたかったの?」という疑念が湧いてくるのですネ。読解力がないだけじゃん―とも思うけれど、この作品、もしも…ですよ、大多数の人が自分と同じようなことを感じているとしたならば、それは単なるエンターテイメント小説にすぎないことになり、芥川賞を獲得するようないわゆる「純文学」ではないのではないか…とも思うのですが、いかがでしょうか。
まあね。小説というものは、結論や論点といったものを追い求める性質のものではないので、読んで面白ければいいのかもしれません。しかし、社会人として長年理屈や筋道の世界で生きてくると、正直言ってな〜んかモノタリナイ…という印象はぬぐいきれないのですナ。
むむ〜、またクダを巻いてしまった。スマンスマン…。しかし、ワタシ、沖縄、好き。アイシテル。ということで、又吉サン、次作にも大いに期待していまっせ〜。
(2002. 1.27 読)

|
 |
「豚の報い」 又吉栄喜 著
文春文庫 429円+税
1999年2月10日 第1刷発行
沖縄に関心のある方なら言わずと知れた芥川賞受賞作ですね。崔洋一監督の手により映画化されたので、それをご覧になった方も多いことでしょう。
私もさっそく受賞直後の文藝春秋を買って読んだのですが、その読後感は正直言って「いまいち」だったのを覚えています。今回再び文庫本でじっくり読んだのですが、なにかこう、やはり文芸書だというか、何回か訪れて体験してきたオキナワとはどうも少しへだたりがあるような気がしています。芥川賞の選考の祭、「豚」という題材の必然性だったかについて疑問を呈した委員がいた…というような話を聞いたような気がしたのですが、私としては、スナックに豚が闖入してくるということからしてどうも腑に落ちない気がするのですね。池上永一のようなファンタジーと割り切るならそれもまたいいのでしょうが…。そんなことで、2度目の読後感も、あまりかんばしくはありませんでした。
表題作のほか「背中の夾竹桃」が併録されています。
(1999.10.19 読)

|