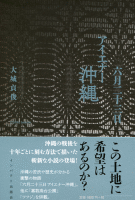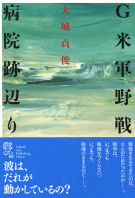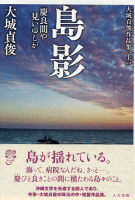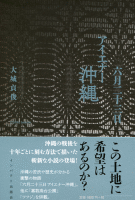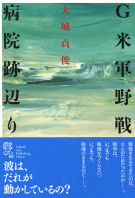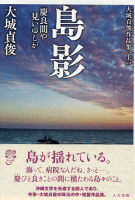|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
「沖縄の祈り」 大城貞俊 著
インパクト出版会 1,800円+税 2020年4月15日 第1刷発行
沖縄戦から戦後、生き継がれた命のことばが、今沖縄の闘いの現場にある。
沖縄、抗う心の記録を創作!
「戦争は、被害者にも加害者にも地獄ですよ。」(喜屋武幸清) (コシマキから)
まえがきも解説も、何の説明もなくいきなり本文だけというようなつくりで、上記だけでは内容が判然としませんが、著者は公職を辞したのを機に多くの著作物を世に問うており、このあたりにやや粗製乱造の傾向を見てとることができます。
2020年6月28日付け琉球新報に、仲程昌徳(琉球大学元教授)による書評が掲載されていたので、以下に引用します。
・「沖縄の祈り」 「沖縄文学」の特異性鳥瞰
日本文学という範疇に収まらない特異な文学として沖縄の文学はある。それゆえ「沖縄文学」という概念は成立する、といった考えを確固たるものにしたいと考える上原、そして、沖縄の文学を「植民地文学」だとして韓国の文学と比較してみたいと考えているジジュン、この2人を中心に、歴史学徒、方言学徒、沖縄芝居の役者として舞台に立つ院生、さらには他大学の大学院に在籍し組踊と沖縄芝居を研究しようとしている米国人、絵本研究家といった大学院生たち、いわゆる若手の研究者たちを配置し、沖縄の表現にかかわる研究の最前線を鳥瞰しようと試みた野心的な作品である。
上原は、教育家、詩人、沖縄文学研究者として、勤務している学校を休職して大学院で学んでいる。ジジュンは、韓国の大学の准教授で、サバティカルを利用して上原と同じくA大学の大学院に在籍している。2人はともに1984年生まれ、35歳である、という設定から分かる通り、作品は2019年現在を背景としていた。
2人は、主任教授に、研究室から外に出てアンケートおよびインタビューを行うことを勧められ、高校生や大学生、そして高齢者たちからアンケートを取り、沖縄戦を研究している公務員、沖縄戦体験者、演出家、新聞記者、元ハンセン病患者、元県教育長、画家そして作家を訪問し話を聞く。
アンケートおよびインタビューを通し、沖縄の状況、沖縄の苦悩が浮かび上ってくる。それはまた「沖縄文学」の特異性、「植民地文学」という視点の有効性を確認させるものともなっていく。
作品は、沖縄の複雑に絡み合う論点を切り開いていく視点の一つとして「祈り」を導きの糸にする。その方法として選ばれたのが、フィクションとドキュメンタリーの合成であった。作品は四つのサプライズで終わるが、その一つに、新しい生命の誕生を伝える電話があった。そこには沖縄研究者たちに、希望の灯をともしたいという意が込められていた。大城貞俊の文学に一貫してみられる鉱脈ともいえるものである。
この書評を読んでも明確なイメージは結像しにくいかもしれません。でもそれは、書評がよくないのではなく、むしろ著作そのもののほうに原因があるのではないかと思われます。
大学院というお堅い場を舞台にして、沖縄文学という専門的な分野を研究する人々を扱っている上に、それらの登場人物が多く、小説らしい抒情性はかなり抑制されています。会話においても沖縄らしいところが削ぎ落とされているので、自分とっては盛り上がりに欠けるなぁ、これは著者本人の研究分野が前に出過ぎていて小説っぽくないなぁと思えてしまったところです。
(2021.5.14 読)

|
 |
「抗いと創造―沖縄文学の内部風景」 大城貞俊 著
コールサック社 1,800円+税
2019年5月18日 第1刷発行
沖縄の詩に関する文芸論。
沖縄は、「詩の島、歌の島」と称され、詩歌を中心に文学活動が盛んな土地柄です。詩人で作家、評論家、研究者の著者は、本書では平成期の詩歌を中心に沖縄文学の歴史と特質を論じています。
沖縄文学のテーマや作品には、独特の言語の問題、ウチナーンチュとしてのアイデンティティー、差別や偏見との闘い――などの特徴があるとして、「本土の他地域にみられない特異な作品世界をつくっている」としています。さらに、「死者の視点を忘れるなと呼びかける戦争体験」が、常に表現する意味を沖縄文学に問いかけていると指摘しています。
巻末の「解説」で鈴木比佐雄(詩人、評論家、編集者で、コールサック社の創業者)は、「本書は「沖縄文学」と「沖縄戦後詩」の重層的な関係を考える際に最も相応しい論考集として読み継がれていくに違いない。また新たな「沖縄文学」を「しまくとぅば」を駆使して創造しようとしている若き表現者たちにも大きな示唆を与えるだろう。」と締めくくっています。
第1章では、「沖縄文学の特質と可能性」として、沖縄現代詩の軌跡、沖縄戦争詩の系譜と現在、沖縄文学の特異性と可能性、機関誌「愛楽」にみる「沖縄ハンセン病文学」、山之口貘の詩から見えるグローバル社会における詩教材の可能性、近・現代の文芸と韻律などを明らかにしています。
第2章では、平成期を1990〜99年、2000〜09年、2010〜17年に区分して、沖縄平成詩の軌跡と表現について、第3章では、詩人論として、市原千佳子、佐々木薫、網谷厚子、沖野裕美、宮城松隆、中里友豪、牧港篤三、知念榮喜、船越義彰、清田政信をピックアップして詳説しています。ほかに「沖縄平成期の詩集出版状況(1989〜2017年)」なども。
琉球新報に2019年5月26日付けで書評が載っていたので、以下に引用しておきます。
・「抗いと創造―沖縄文学の内部風景」 10人の詩人への鋭い批評
「文学の不毛の地」と言われることもあった沖縄では、しかし優れた小説や詩が脈々と書かれ続けてきた。本書は、1989年から2018年までの沖縄で生まれた、あるいは沖縄に関わる詩について文学史的に紹介、批評したものである。これまで著者・大城貞俊は「沖縄戦後詩史」「沖縄戦後詩人論」などの文学史や詩人論を公刊してきたが、本書はその姉妹編にあたる。とりわけ白眉は第3章に収められた詩人論であろう。10人の詩人に対する躍動感あふれる、そして鋭い批評を読むことができる。なかでも牧港篤三論と清田政信論が目を引く。詩に関わり続けた著者ならではの円熟の批評であろう。
書籍タイトルに使われている「抗(あらが)い」と「創造」は、一方で「これまでの書き手」と「新しい書き手」のことである。とはいえ注意が必要である。なるほど新しい書き手の表現には新味がある。しかし大城はそれを受け入れつつも、状況や生活世界から離れてしまうこと、沖縄戦というテーマが薄れること、そして難解な内面表現に傾倒しすぎることへの違和感を――表立ってではないものの――投げかけているからだ。そのため「創造」には不透明感がつきまとっているようにも見える。
他方で「抗い」のなかの「創造」も本書から読み取ることができる。例えば芝憲子「海岸線」には、買った大根が気づくと人の足になり、それを市場のおばさんに見せたところ「うちの人の左足」と答える場面がある。ここで読まれるのは、人々に沖縄戦を幻視させていく詩語である。つまりそれは戦争そのものへの「抗い」であり、そのために「創造」された言葉である。したがって「抗い」と「創造」は多面的に絡み合う必要がある、というのが本書のメッセージの一つであろう。現状に抗いつつ内面を注視したとされる清田政信論が本書の最後に置かれているのも、この絡み合いこそが沖縄の現代詩の課題だと大城が考えているからだと思われる。豊かな詩の歴史とその困難を知る上で、本書の果たす役割は大きい。(呉世宗・琉球大学教員)
(2021.1.14 読)

|
 |
「海の太陽」 大城貞俊 著 インパクト出版会
1,800円+税 2019年5月28日 第1刷発行
先の大戦中、灼熱の砂漠インドのデオリ収容所で、日本の敗戦も知らずに絶望的な日々を送っていた多くの日本人がいた。この中には運命に翻弄されながらも、ひたむきに生きた多くの愛の形があった…。戦後73年余、人間を信じることの素晴らしさと勇気を問いかける感動作、誕生!(コシマキから)
沖縄出身の漁師・与那嶺亮太は、父親と兄が海で行方不明になり、一家を支えることになる。糸満漁師の下での厳しい漁師の修業を終え、漁業が盛んなシンガポールへ渡る。だが、第二次大戦が始まり、拘束された彼はインドの収容所に移送される。そこでは思いも寄らぬ出会いと別れが待っていて……。
このところ次々に刊行されている大城貞俊作品の一つ。物語の舞台は、始まりこそやんばるや糸満ですが、その後はシンガポール、さらにはインドへと移っていきます。
終戦後、フィリピン経由で沖縄へと戻るが、家族は殆んど残っていません。しかし、苦難を共に乗り越えた悲しい人たちは翻弄され続けた人生からまたも立ち上がっていきます。「海の太陽があれば、生きていけるな」と。
(2020.8.24 読)

|
 |
「運転代行人」 大城貞俊 著 新風舎
1,500円+税 2006年2月28日 第1刷発行
2006年に発刊されたものを、WEB古書店から送料込み655円で入手した良書。
「第24回新風舎出版賞フィクション部門」の優秀賞受賞作品。新風舎出版賞は、1996年から年2回行われており、フィクション、ノンフィクション、ビジュアルなどの部門でそれぞれ最優秀賞が、そして全ジャンルから最高賞の「出版大賞」が1点選ばれるものになっています。
2005年の第24回で大城貞俊が受賞した時のフィクション部門の応募作品数は4部門合計でなんと5,894点でした。まあ、選考委員には著名な作家などは入っていず、大部分は新風舎の編集者たちで選んでいるのですが。優秀賞以上は新風舎から出版化されるというメリットがあるようです。(それ以外の作品は著者が自費で出版化)
酔っ払い救出に向かう代行車。ライトに鮮やかに照らしだされる累々たる人の生老病死。いつしか代行車は闇の中の光明になり、主人公の玉手箱に変貌する。(芥川賞作家 又吉栄喜)
舞台は那覇、繁華街の松山や桜坂あたり。20年余り勤めた学習塾を辞め、運転代行社に転職した主人公の紀夫。さまざまな人と接する中で思い至ったこととは……? 人生中盤を過ぎたともいえる年代を迎え、あらためて自己に問いかける人間ドラマが叙情たっぷりに描かれています。せわしない世の中、心の一服に最適の作品とも言えるでしょう。気取りのない平易な文章が、気持ちにすんなりと入ってきます。
以下に、新風舎の選評を引用しておきます。
大城貞俊「運転代行人」は、沖縄を舞台に耳慣れぬ職業の主人公を通して描かれる人間模様。沖縄市戯曲大賞や具志川市文学賞受賞歴のある作家ならではの鋭い観察眼で多様な人間性を描ききっている。
酔客の車を代行運転して家まで送り届けるという特殊な職業に就く主人公・紀夫の視点を通して、夜の代行車で出会ったお客たちや家族、同僚らの多様な人間性を描いた秀作。沖縄という特色ある舞台設定も、沖縄出身の著者の手により作品のユニークさを増している。端正な文章で描写される情景は十人十色の生き様をよく伝え、時に感覚的な文章表現を効果的に織り交ぜて完成度を高めている。
さまざまな人生と出逢うことで、紀夫が自分の人生を誰かの「代行」に終わらせまいと心に誓うラストはさわやかな感動を呼ぶ。
(2020.4.24 読)

|
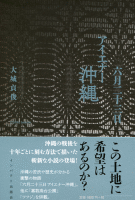 |
「六月二十三日 アイエナー沖縄」 大城貞俊 著
インパクト出版会 1800円+税 2018年8月6日 第1刷発行
秋田魁新報社 800円+税 2017年12月25日 第1刷発行
2つの書評、とりわけ1本目が全体として適切と思われるので、それらを掲載してインプレッションに代えます。
・自分たちの「生」を踏みにじり振り回してきたものへの「怒り」 黒古一夫(文芸評論家・筑波大学名誉教授) 週刊読書人 2018年9月29日
戦後文学史を通覧して、その特殊な地理的条件や歴史、文化の在り方を踏まえた上で、もし仮に「沖縄文学」という呼称が可能だとすれば、沖縄におけるハンセン病に対する「差別」と、住民や徴用されていた朝鮮人および日本軍将兵併せて約24万人が犠牲となった沖縄戦(太平洋戦争)における「沖縄人差別」の問題を主題とした「椎の川」(具志川市文学賞、1993年、朝日新聞社刊)でデビューし、本書に至る大城貞俊の文学的営為は、紛れもなく「沖縄文学」の本道(王道)を歩むもの、と言っていいだろう。
本書は、沖縄戦における組織的な戦闘が終結した「1945年6月23日」に最期を迎えた、沖縄現地で動員された16、7歳の若者たちの生き様を描いた「護郷隊」、アメリカによる占領後、住民の土地を理不尽に奪って各地に作られた基地が、沖縄人に「基地依存」の心を生み出している現実を描いた「ダミン」(「堕民」の意)、沖縄の本土復帰(1972年)から3年、激しさを増すベトナム戦争の補給基地・休養基地と化していた沖縄の歓楽街で働く女性の恋と哀しみを描いた「パラダイス」、念願かなって沖縄県警の機動隊に勤務するようになった青年のデモ隊の足を攻撃することに快感を覚える倒錯した心理に迫る「足」、友人がアメリカ兵に強姦されることを目撃した少女の苦悩と未婚を決意する複雑な心境を描いた「砂」、戦争における「加害」と「被害」の錯綜した関係を老婆の口を借りて語る「カマー」、戦後70年目の「2015年6月23日」に那覇市で起こった「テロ」を見たと主張する新聞記者の、「この地の未来の物語は、まだ紡がれていない。友よ、希望は確かにある」との思いで終わる「夢」。
これら8話から成る表題作『六月二十三日 アイエナー沖縄』の全編を覆っているのは、自分たちの「生」を理不尽に踏みにじった沖縄戦と、日米の権力によって振り回されてきた「戦後」への「嘆き」と「恨み」、及びそれらの感情の底流に渦巻いている強い「怒り」の気持ちである。そして、その著者の「怒り」は、本書の各所に見える「沖縄は日本ではない」という言葉に象徴されている、と言っても過言ではない。
この作者の「怒り」は、本書所収の、未だ「魂の救済」がなされないままに放置され続けてきた旧日本軍兵士(沖縄県人を含む)の「遺骨」が、更に沖縄を窮地に追いやる普天間基地に配備されたオスプレイを撃ち落とす「夢=願望」を描いた『嘉数高台公園』にも、また退職後の仕事として沖縄北部(ヤンバル地区)における沖縄戦について「聞き書き」する男の語りで展開する『ツツジ』にも通底している。
なお、言わずもがなのことを付記しておけば、本書に通奏低音のように鳴り響いている「嘆き」や「恨み」を装った「怒り」は、占領時代と変わらず米軍基地を沖縄に置き続けてきた日米両政府(と日本人)にも向けられたものであることを、改めて私たちに知らしめるものだということである。
・戦争矮小化の機運懸念 楜沢健・文芸評論家 沖縄タイムス 2018年10月6日
「戦争」を「戦略」に矮小化する機運が高まっている。アジア太平洋戦争への反省が「戦争」ではなく「戦略」に向けられる。失敗は「戦争」ではなく、愚かな支配層による「戦略」にあった。「戦略」を誤らなければ、「戦争」に勝てた。もう一度「戦争」をすれば勝てる。百田尚樹『永遠のゼロ』をはじめ、ちまたにはそうした機運をあおる物語が氾濫している。
本書は、沖縄の戦後を、成仏できない死者の視点から浮かび上がらせた『六月二十三日 アイエナー沖縄』『嘉数高台公園』『ツツジ』の3編からなる。「戦争」を矮小化し、その修正やねつ造がまかり通る現在の好戦的な機運と対峙する作品集といってよい。
『嘉数高台公園』には、嘉数高地の激戦で戦死し、マブイ(霊魂)となってさまよい続ける4人の死者が登場する。普天間基地を俯瞰できる公園には観光客をはじめ人が絶えない。4人は、戦後67年間、来訪者の語らいに耳を傾けてきた。そして「生者たちは戦争体験をどのように語っているのだろうか」と不安になる。公園にきた自衛官の会話に、4人は驚愕する。「戦争をしてみたいな」「もう一度戦えば、絶対に勝つ自信がある」。米軍の将校が言い放つ。「沖縄の人々はみんな優しい」「日本政府が金を出す。沖縄県民は心を差し出す」。聞き捨てならない暴言が幅を利かせている。
死者たちも一枚岩ではない。4人は壕内で「自決」した。比嘉2等兵と平良上等兵は、鈴木軍曹(島根出身)の「一緒に死のう」という呼び掛けに逆らうことができなかった。しかし鈴木軍曹は、上官の加藤大尉(京都出身)に「自決」ではなく、みな戦闘による「名誉」の戦死を遂げたとうその報告を伝える。「死者である俺たちの語りの中にもすでに嘘がある」。その「嘘」に比嘉と平良は、いまなお逆らい、抗議することができないでいる。
死者を縛り続ける「戦争」から、死者を解放しなければならない。私たちが死者を必要としているように、死者もまた私たちを必要としている。
(2020.2.10 読)

|
 |
「カミちゃん、起きなさい!生きるんだよ。」 大城貞俊 著
インパクト出版会 1,800円+税 2018年4月28日 第1刷発行
琉球王朝時代の士族の一家は、「琉球処分」で沖縄島北部のヤンバルの地で生きることになった。沖縄戦と戦後の米軍基地拡張による八重山移民と歴史に翻弄されながらも希望を失わなかったカミちゃんの人生を、新鮮な手法で鮮やかに描いた画期的な作品登場!(コシマキから)
表題は、子どもたちのマラリアを看病するうちに母親のカミちゃんまでもが高熱を発し、疲れと苦痛で絶望的な気分に侵されたときに聞こえてきた、天国にいる母ウシの声。
「ヌチヤ ティンカイニ アインドー。ヤーガドゥ、ナラーチェーサニ。アリ、ヌチカジリイキレー。」(命の定めは天にあるんだよ、勝手に命を捨ててはいけないよ。あんたが、私に教えたんじゃないか。今ここで死んだら、一番の親不孝者になるよ。命の燃え尽きるまで生きるんだよ)
沖縄タイムスの書評を以下に引用して紹介に代えます。
・近代沖縄、庶民女性の姿 2018年6月30日
琉球国の終焉から説き起こされる一家の物語である。主人公は一人の女性。激しい波に翻弄されて生きた沖縄の庶民女性の姿がここにある。作者はその庶民の人生を温かいまなざしで見つめ、豊かな物語を紡ぎ出した。沖縄文学の特徴の一つに「時代状況に倫理的である」ことを挙げる作者が、時代の大波にもみしだかれながらも希望を失うことなく、野の花のように力強く、そしてまっとうに生きた人々への共感をもとに生み出した一作である。
屋取(ヤードゥイ)人となってヤンバルに下った首里士族の4代目の子孫として、主人公は大正5年に生まれた。沖縄の娘として普通に育ち、戦争時代の女として軍人に嫁ぐ。しかし、戦争の時代は彼女の生活を巻き込みさいなんでいく。一家の希望でもあり柱とも頼んだ兄一家の台中丸沈没による遭難死。この悲劇によって主人公の母は発狂寸前に追い込まれる。そして沖縄戦。しかし、主人公の苦難の歩みはこれで終わりではなかった。人にだまされ有り金を失い、石垣島明石での開拓生活に入っていく。その苦難はマラリアのために死境をさまよう子供たちと主人公の姿に極まる。その苦難を乗り越えての再生。
琉球国の消滅・十五年戦争・沖縄戦という琉球・沖縄の近代の歴史が、主人公の家とその身体の上を音を立てて流れていく。作者の眼はその強暴な歴史の奔流を見逃さない。それがいかにして人々の生活を狂わせ、破壊するかを描き出している。主人公カミちゃんの人生は、近代沖縄の歴史がもたらした婦人の人生の一つの典型であった。
作者は前著「奪われた物語−大兼久の戦争犠牲者たち」の縁によって、この作品の主人公と出会い、その人生に引き込まれた。そこから作者が描き出そうとしたのは、歴史に翻弄されながらも力強く生きた近代沖縄の庶民の物語に他ならない。そしてこれを未来の沖縄を背負う世代に伝えようとしている。少年・少女にこそ手渡したい1冊である。
(波照間永吉・沖縄県立芸術大学名誉教授)
(2020.1.1 読)

|
 |
「一九四五年 チムグリサ沖縄」 大城貞俊 著
秋田魁新報社 800円+税 2017年12月25日 第1刷発行
第34回さきがけ文学賞で、応募総数271編の中から選ばれた入選(最高賞)作品。
さきがけ文学賞とは、秋田県北秋田市出身の直木賞作家の故渡辺喜恵子と秋田魁新報社からの寄付金をもとに1984年に創設されたものだとのこと。歴代の受賞者を調べてみましたが、残念ながらその後に大きな名を成した作家は見当たらず、名のある大城貞俊がなぜ今頃この賞の受賞者になるのかと不思議に思います。
選考委員の西木正明、高橋千劔破、森絵都の3氏からは「語り継ぐべきテーマに果敢に挑んだ」と高い評価を得たそうです。
「チムグリサ」は直訳すれば「肝が苦しい」で、沖縄の言葉で相手の身になって悲嘆に暮れる意。一人称の短編6話で構成。生者と死者それぞれの視点から沖縄戦の悲惨さと平和の尊さを強く訴えています。
沖縄タイムスに文芸評論家・平敷武蕉による書評が載っていましたので、以下に移記しておきます。
・「一九四五年 チムグリサ沖縄」 死者の声を掘り起こす 2018年2月10日
昨年、「さきがけ文学賞」を受賞した本書には、沖縄戦の種々の体験を語る短編小説6篇が収録されている。単なる証言集ではない。本書に登場する証言者は1人を除いて、みな死者である。作者は、それら死者たちの声を掘り起こし、想像し、種々の手法で描き出している。その都度文体も違えている。ここにこの作品の斬新さがある。
「『肝苦りさ』―闘いの原点はここにしかない」と述べたのは辺見庸であるが、本書のタイトル「一九四五年 チムグリサ沖縄」のチムグリサとは、「相手の苦難を見て、身がちぎれるほどに心が痛む」という意味である。身体的痛みをもって相手の不幸を受け止めることである。単に同情的・傍観者的な標準語の「かわいそうに思う」とはそこが違う。沖縄戦の体験談を聞いて「退屈」だとする本土教師がいたが、どんな悲惨な体験も聞く側に「チムグリサ」の心がなければ、体験は伝わらない。作者はそのチムグリサの話を伝えるために言葉を紡ぐ。沖縄戦では20万余が死没した。ということは、20万余の体験があるということだ。記録されたものもあるが、多くは今なお、埋もれたままである。まして、死者たちの声は――。
登場する証言者は、樹上での逃避生活の果てに自決する若い兵隊であり、隔離され、差別されて死んでいったハンセン病の患者である。第6話「道」の語り手は、臨時の看護婦として駆り出されたあげく、泣き叫びながら米兵らに凌辱される女子学徒たちである。1人は首を括って自害し、「私」は「米兵の子供を妊娠する不安に苛まれる」。終戦になっても、「私と同じようなことが再び起こらないとは限らない」という少女の怯えは、73年後の今も、現実の事件となって沖縄を脅かし続けている。
チビチリガマを荒らした犯人が沖縄の少年たちであったと言う。事件の政治性への疑念が払拭されたわけではないが、少年たちの心の荒みが心に刺さる。死者たちは2度、いや、何度も殺された。少年たちが死者の眠るガマを荒らす前に、この島の死者たちは、戦争のための軍事基地建設を進める日米両政府によって今も荒らされ、凌辱され続けている。本書は、読む読者も試されている。
(2019.2.27 読)

|
 |
「樹響 でいご村から―大城貞俊作品集〈下〉」 大城貞俊 著
人文書館 2,650円+税 2014年4月10日 第1刷発行
発売時には価格の関係から即買いを躊躇し、2017年に古書で購入し、それから1年以上たってから読むという経過をたどりました。
時代の波に翻弄された村人の生と死を描いた、これまでに未収録となっていたもの4篇が収録されています。代表作「椎の川」に低通しているところがあり、「でいご」は戦争の死者たちを蘇らせる記憶の花として象徴的に扱われています。
2014年5月、琉球新報に掲載された、詩人・松原敏夫の書評があったので、それを以下に移記しておきます。
・無名の民の多様な「生」照らす
全共闘世代の雰囲気を、青春時代に体験した人が、生活や社会や個に帰って、例えば、村上春樹を始めとする作家たちが、時代の感性を取り込みながら書いている。春樹の作品世界は時に社会や現実にある奇妙でねじれた関係を生きる人物が色濃く出たりする。大城貞俊もその世代であるが、人間の描き方がやはり違う。
作者が「椎の川」以来、詩から小説へ傾注して書き続け、沖縄を書く作家としての位置を確立しているのは周知のことだ。今回の作品集ではさらに多彩に描いている。
父を戦争で、母を病気で亡くし、上の姉は蒸発、下の姉は米兵と結婚、妻にも病気で去られ自らも心臓の病を持つ火葬場の男を描いた「鎮魂別れてぃどいちゅる」。
知的障がいのある、村の娘加世子や学生運動家で自殺する文学好きな涼子との付き合いを描いた自伝的な「加世子の村」。
ホステス同僚で堕胎経験をもつサユリとミキと脱走米兵との同棲生活を描いた「ハンバーガーボブ」。
沖縄の、無名の民の、様々な生を照らすのが、この作家の文学なのだ。戦争の記憶者、自殺者、障がい者など沖縄的現実の生の痛みを描いた作品に「生きる切なさ」や「人の生は哀しくて美しい」慈しみの感情がある。それは詩的で抒情的な情景にも表れる。
例えば「加世子の村」の結末。農道で夕日に向かうように老婆を運ぶリヤカーを押す加世子が〈ぼく〉を見つけて手を振る。〈ぼく〉も何度も手を振る。夕日を背景に加世子は影となって、〈ぼく〉は淡く照らされて浮かぶ。うまいなと思う。描写のほろ苦さが何ともいえない。いい小説だ。
「でいご村から」も、〈戦争の残した傷跡〉という作者がこだわるテーマを訴える作品である。沖縄戦で愛する家族や恋人を失った一家の悲哀の物語だが、首里士族の末裔、村人との距離という構図は古くさくないかと思った。あとがきの「沖縄を描くことで普遍的な世界に到達する」に呼応して〈沖縄文学〉に文体表現の新しさと多様描写を求めたくなった。
(2019.1.2 読)

|
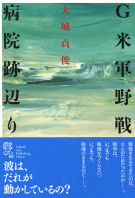 |
「G米軍野戦病院辺り」 大城貞俊 著 人文書館
1,900円+税 2008年4月25日 第1刷発行
大城貞俊の作品を買い集めて読んでいて、今回は2008年の著作を10年後に読んでみたところ。
あらすじはこんな感じ。
沖縄戦も終わりに近い頃、米軍は沖縄本島北部のG村に野戦病院を設営した。
ここには、重傷の患者が集められたが、多くはテントの中で次々と死んでいった…。
戦後60余年、あの戦争は、どのように人々に刻まれているのだろうか。
G米軍野戦病院跡辺りを背景に、今なお戦争に翻弄されて生きる島人の姿を描く。
表題作のほか、「ヌジファ」、「サナカ・カサナ・サカナ」、「K共同墓地死亡者名簿」の4篇を所収。
著者はあとがきにかえて、沖縄から書くことの意義を記しています。抜粋して次に移記しておきます。
沖縄の地は、去る大戦で地上戦が行われ、兵士だけでなく、県民の三分の一ほどが犠牲になった。戦後も、米軍政府の統治下に置かれ、様々な辛酸を嘗めてきた。戦争という体験は、土地の精霊をも巻き込み、今日までも、人々の生き方を規制している大きな要因の一つになっている。
沖縄の現在を考えれば考えるほど、この戦争体験を抜きにすることは出来ない。沖縄の人々の生き方を凝視すればするほど、死者を忘れない土地の特質に出会う。虐げられ、苦しめられ、悲しみの極致にいてもなお、死者との再生とも喩えるべき優しさを有している。私は私が生まれ育ったこの土地に、畏敬の念を感じると同時に大きな魅力を感じている。
考えてみると、このことは、私が、生き続けることの要因の一つにもなっている。私は団塊の世代と呼ばれ、全共闘世代とも呼ばれ、学園民主化闘争と、政治闘争を、二十歳前後に体験した。さらに沖縄の地であるがゆえに、復帰・反復帰闘争や、反安保闘争のラジカルな洗礼を受け、生きることの意味を鋭く問いつめられた。
私は、そんな中で、目の前に露見した状況に戸惑うばかりで、詩の表現を免罪符のように獲得して悩んでいた。自らの卑小な存在に、生き続けることさえ疑うようになっていた。「ぼくは二十歳だった。それが人の一生で一番美しい年齢だなどとだれにも言わせない…」と、ポール・ニザンの「アデン・アラビア」の一節を口ずさみながら。……
私は、沖縄の地で生まれ、沖縄の地で育ったことを、表現者としては僥倖のように思っている。死者をいたわるように優しく葬送する一連の法事や、また沖縄戦をも含めて、死者を忘れない共同体の祭事やユイマール(相互扶助)の精神に守られて、私もまた、生かされているように思う。
もちろん、それゆえに、抑圧的な権力や戦争に無頓着ではいられない。それは過去だけでなく、現在や未来にまでも繋がっていく視点だ。
私は今、沖縄の地で生きる時間と空間の偶然性を宿命のように感じている。この地にまつわる矛盾や課題は、それぞれの方法で担う以外にない。この地で生きる人々の苦悩や喜びは、普遍的な苦悩や喜びである。戦争を描くこともまた、人類の普遍的な課題である。 平成二十年 春
(2018.5.12 読)

|
 |
「奪われた物語 大兼久の戦争犠牲者たち」
大城貞俊 著 沖縄タイムス社 1,500円+税
2016年6月17日 第1刷発行
沖縄屈指の作家である著者が生まれ育ったのは、大宜味村大兼久。戦前は漁業の町で、南洋諸島のパラオやペリリューで戦死した人々が多くいる土地柄なのだそうです。
団塊の世代に生まれた著者は、戦後70年を過ぎて、やっと戦争と向き合える時間を手にすることができたといいます。定年退職を迎え、父や兄が死亡した年齢を過ぎると、父が召集されたパラオのことが気になり、生まれ育った大兼久の戦死者のことが気になり始めたと、プロローグに書いています。
「戦死者たちにとって、織り成されるはずであった人生の物語はどのようなものであったのだろうか。個々人にとってかけがえのない一つきりのその物語が奪われたのだ。(略) 戦後70年間、郷里のこの土地は、無念の思いで斃れていった人々の血と物語を吸い込んで、空を見上げ、雨に打たれ、風に曝されてきたのだ。運命と呼ぶにはあまりにも悲しいこの想定内の愕然とした事実が、私にこの本を書かせる動機になったと言っていい。」
大兼久の戦死者一人ひとりに関することについて、著者は上記のような思いで丹念に聞き書きをしています。
「沖縄タイムス」のページから、2016年8月に書かれた南風原文化センター学芸員の平良次子氏の書評を以下に引用しておきます。
最近、戦災調査についていろいろ考えることがあった。体験者が話さずにはいられない、あるいは話したくない心境は、聞いている私の人生に大きな影響を及ぼすような気がしてきた。非体験者の私たちがその体験を知るか知らないかで、記憶や記録に残るか否かということだからである。本書を手にして、なんだか胸騒ぎがした。
この本は沖縄に生きる私たちにとっての沖縄戦という歴史が、「あってほしい未来」に託す大切な人とのつながりや人と地域の歴史物語から教わることの重要さを刻んでいる。
これまで私がとらえていた沖縄戦の記録や記憶の継承などというカテゴリーを超えていた。戦死者や戦死者とともに生きてきた人たちの記録であるとともに、その「戦争体験者」と現在を生きてきた戦後生まれの人たちを重ね合わせた「物語」であるのだ。
また著者が地元の戦争体験記録を「私をも変革してくれた」と記されたように、あらためて親しい人たちの戦争の記憶に向き合った日記のようでもあった。
私がこれまで読んだ戦争体験証言や記録と明らかに違うのは、語り手の言葉がカギかっこで書かれていること。それに聞き書きをする自分自身の感情、同行した人たちの様子をも含めて文章化されている点だ。それは戦争体験者の話をどのように受け入れているか、という記録でもある。
戦争犠牲者(あえて本書はそう書かれている)の話を非体験者がどんな気持ちで受け入れたのかは、これまで読んできた戦争体験記録からはなかなか見えない事であった。主人公が体験者そのものだからだ。なるほど、聞き手、書き手の様子も同時に記録表現する、そういうやり方もあるのかと新鮮であった。体験者の声を常に聞き取る自分の生き方に反映させることを意識している、と思った。
また沖縄国際大の田場裕規先生の解説は今後の沖縄戦の記録や伝える作業で意識したい重要なことを示唆してくれた。
(2018.2.18 読)

|
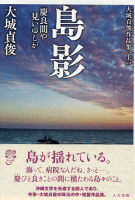 |
「島影 慶良間や見いゆしが」 大城貞俊 著 人文書館
2,600円+税 2013年12月10日 第1刷発行
人文書館から発売された、大城貞俊の上下2巻の作品集のうちの上巻。収載されるのは各4作品で、上巻はいずれも未発表のものです。
「島が揺れている。海って、病院なんだね、きっと…。慶びと良きことの間に横たわる島々のこと。沖縄文学を先導する詩人であり、作家・大城貞俊の珠玉の中・短篇作品集」――というのが作品紹介文です。
表題作の「慶良間や見いゆしが」は、祖父の唐突な自殺という衝撃的な出来事から語り出されます。
「祖父はなぜ、トーカチ(米寿)を前に自殺したのか?」。国語教師として中学校に勤める孫息子の清志は、その謎を追いながら、祖父清治郎の心を支配していた戦時中の真実の悲しい闇に迫っていきます。
「彼岸からの声」は、「あの世」と「この世」、そして「古い記憶」と「新しい記憶」という2組の対立項を鍵として、奥間キヨの彼岸からの語りと、此岸で見る夢に彼女の声を聴く主人公敬治の日々とを交錯させる物語。
「パラオの青い空」は、人生の最末期を迎えつつある老女が、老衰と痴呆による思考の衰えを自覚しながらも、20年前に自分と子供たちを遺して自殺した夫の心の真実を探り当てようと、過去の記憶と格闘する物語。
「ペットの葬儀屋」は、軍用地主で羽振りのよい叔父洋蔵が出資するペットの葬儀屋に勤める主人公の隆太は、洋蔵の愛人である社長の和代と、和代の片腕で離婚歴のある7歳年上の恋人とともに働いているが、そこに新採用されたカスミが加わることによって、奇妙に安定していた職場の人間関係ば崩れ始め・・・といった内容。
巻末の萩野敦子(琉球大学教授)による解説がよく、それによれば、この4作では、沖縄戦の記憶を抱えながら、いまだに米国、そして残念ながら日本という「他者」との関係に苦しむ現在の「沖縄」が、比喩的に表現されているのだと説明しています。
このような解釈には感服するとともに、自分にも同様の読後感があったことを付け加えておきます。
この上巻については、古書店から格安に入手することができましたが、下巻の「樹響 でいご村から」のほうはむしろ古書市場のほうが高く、まだ入手していません。
こうなれば、2,862円の定価で買うしかないのかな。早く買わないとそれも売切れてしまうだろうしなぁ。
(2017. 9.27 読)

|
 |
「アトムたちの空」 大城貞俊 著 講談社 1,500円+税
2005年10月25日 第1刷発行
沖縄文学を渉猟するうえで、大城貞俊という作家にも注目しているところ。
1949年、大宜味村生まれで、琉球大学法文学部国語国文学科を卒業。県立高校教諭、県教育庁指導主事等を経て、琉球大学教育学部教授。作家であるほかに、定年後は沖縄国際大学・沖縄女子短期大学非常勤講師。
詩誌「EKE」同人、個人詩誌「詩と試論・貘」主宰、現代文学・思想を読む会「グループZO」同人です。
1993年、小説「椎の川」で具志川市文学賞受賞。この「アトムたちの空」は、2005年、東京都文京区が主催する第2回文の京文芸賞を受賞しています。(同賞は第4回で休止。)
大城貞俊の作品を読むのは「椎の川」、「ウマーク日記」に次いで、「アトムたちの空」が3冊目。古書市場で1円+送料で入手しました。
ほかにも「G米軍野戦病院跡辺り」、「島影 慶良間や見いゆしが―大城貞俊作品集〈上〉」、「奪われた物語 大兼久の戦争犠牲者たち」を手元にスタンバイさせています。
昭和30年代への郷愁も豊かに、沖縄の少年たちの成長をみずみずしく描いています。
「みんながアトムになった。一平たちも、アトムを真似た。好んでゴム長靴を履いた。両手を頭上にあげ、拝むような仕草で地を蹴り空を飛ぶ。そんな仕草が学校中で流行った。風呂敷のマントを首にかけて走り回る生徒たちもいた。」(本文より)
沖縄の少年、一平とその仲間たちの、小学4年から中学2年までの物語。一平の家族がS村に引っ越してくるプロローグに続き、その後に「カミースー」「愛犬メリ」「鉄腕アトム」「アー・ユー・レディ?」の4つの章が展開されます。
その舞台となるS村は、国頭村の楚洲でしょうか。
「カミースー」は、一平たちが恐れていた近所に住んでいるおじいさん。少年たちは一平の父から聞いた戦争の話がきっかけとして、彼を少しずつ理解していきます。
「愛犬メリ」は、友人の克夫が一平に譲った犬。それを機に、一平は勇気を出して克夫と近づいていきます。
「鉄腕アトム」は、村に一台だけ来たテレビを見て少年たちが夢中になったヒーロー。あの当時の様々な事象が登場し、おじさんたちにはとても懐かしいです。
「アー・ユー・レディ?」は、憧れの英語教師である初子先生の口ぐせ。一平は、先生に褒めてもらうために必死に英語を勉強し、ちょっぴり性への目覚めとともに、アメリカ世にも溶け込んでいきます。
(2017. 1.15 読)

|
 |
「ウマーク日記」 大城貞俊 著 琉球新報社 1,905円+税
2011年 6月26日 第1刷発行
大城貞俊の作品を読むのは「椎の川」以来2作目。それを読んだのは1999年だから、14年ぶりにこの作者と再び巡り会ったことになります。
『具志川市文学賞「椎の川」で、読者を感動の渦に巻き込んだ作者大城貞俊が、再び生きることの尊さを問い掛ける。戦後、米軍基地の兵士とウチナー娘との間に生まれた双子の兄弟、マークとジョージ……。二人のウマーク(悪童)ぶりを描いた少年期から、物語は「世界のウチナーンチュ大会」へのクライマックスに向かって突き進んでいく……。沖縄の戦後半世紀余を小説で描いた作者渾身の意欲作』 ――とのこと。(コシマキから引用)
琉球新報夕刊に、2006年11月から07年11月にかけて連載されたものを一部改稿して単行化。
終戦から1990年代まで、時代を反映するさまざまな話題をも織り込みながら、3部構成で展開されます。
400ページ超の長編で読み応えがありますが、プロットにやや甘さがあるような感じがしたのと、先に読んだ馳星周の「弥勒世」とモチーフがよく似ていると感じました。
沖縄を題材にした小説は、どうしても沖縄戦や米軍支配下の沖縄などを扱ったものが多く、そこにはハーフの子、米軍兵士の横暴、それに抵抗する純粋なウチナーニーセー、麻薬やロック、性犯罪などがよく登場しますが、この作品もその例に漏れません。
しかし幸いなるかな、いろいろと辛いことはあったけど最後はハッピーエンドというのが救われます。
(2013. 1.19 読)

|
 |
「椎の川」 大城貞俊 著
朝日文芸文庫 540円+税
1996年8月1日 第1刷発行
日本中が太平洋戦争一色に塗りつぶされていく頃、松堂家の人々は戸数40戸ほどの村で仲むつまじく暮らしていたが…という設定で、沖縄北部「やんばる」の美しい自然の中、病に、戦争に、命を脅かされながらも、素朴な愛情を失わずにしっかりと生きる人々を詩情豊かに描いているいい作品です。
戦争のためにやむなくやんばるに疎開。それでも空からは容赦のない米軍の機銃掃射が行われます。そのうちに伝染病が、そして当時はおそろしい不治の病とされた「らい病」が家族を襲います。
沖縄戦といえば、連想するのは南部の激戦地、塹壕から両手を上げて這い出てくる島の人々や、収容所に集められた着の身着のままの粗末な生活…という印象ばかりが強かったのですが、北部ではこんなこともあったのかと驚くと同時に、あまりの悲しさに、読んでいて涙を禁じ得ませんでした。
(1999. 3.23 読)

|