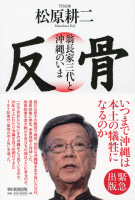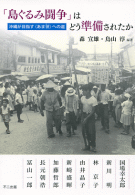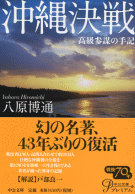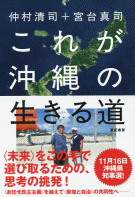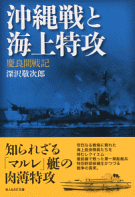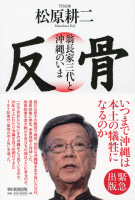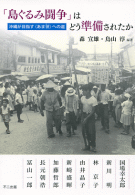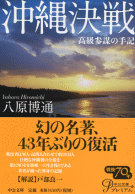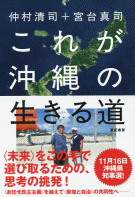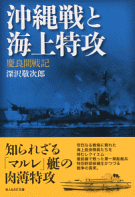|
「「強欲チャンプル」沖縄の真実 すべては“軍命による集団自決”から始まった」
大高未貴 著 飛鳥新社 1,111円+税
2015年 3月 1日 第1刷発行
曽野綾子の「ある神話の背景」が刊行されてから40年後の顛末記といった位置づけの書です。
「はじめは傷を癒そうとする小さな「方便」だった。やがて「暴走する正義」として、異論を許さない全体主義圧力に転化していく。
既得権を守るはずの歴史見直し拒否は、「独立を問う住民投票」という情念に姿を変えた。
前任者を追い落とす政局のために、排日気運を利用した政治家。それに煽られて、引き返せない一線をこえてしまった沖縄政治。
激化する国際紛争の中で、島は新たな悲劇に向かう――」
――との説明がなされています。でもこれでは、なんだか正直言ってよくワカラナイですよね。
そもそも表題の「強欲チャンプル」ってどういうことを表しているのだろう。ここだけで使われる造語ではないかと思いますが、かなり胡散臭いアジテーションが潜んでいるように感じられます。
表題というのはそれだけで全体を端的に表現する大事なパーツなのだから、意味の説明が文章のどこかでなされないのなら入れないほうがいいと思います。
ところで、著者の大高未貴はウィキペディアによれば、1969年東京都生まれ、フェリス女学院大卒のフリージャーナリスト。海外旅行会社に就職し、入社半年後にトルコ、イスラエル研修旅行でパレスチナ問題に遭遇し、ジャーナリストを志し退社。転職した大手広告会社系列シンクタンク勤務時代にミス日本に応募し、1993年度ミス日本に。同年イスラエル、トルコの国際親善の仕事をこなし、その後自費でパレスチナガザ地区を取材。その後、インドでダライ・ラマ14世などへのインタビューが成功したことがキッカケとなり、95年にジャーナリストデビュー。
2004年の日本文化チャンネル桜開局以降、番組のキャスターを務める。慰安婦問題では国内外で取材を行い、現在に至る――という方です。
個人的な感想を言えば、美人は嫌いじゃないけれども、美を利用して世渡りをしているような印象があり、あまりまっとうな経歴とは言えないような気がします。(言い方キツイかな)
その論調は、「序章」で述べている次のような文章に、方向性が示唆的に表現されています。
・・・沖縄を守りたかった戦没者たちは、その思いが正当に理解、評価されず、暗黒の闇に沈んでいるとはいえまいか。さらに今、戦没者たちを冒涜するような「沖縄独立」などという、どこかの国の工作にのせられたかのような動きが加速している。
私はかつて、沖縄集団自決の軍命令問題で、「死ぬな!生きろ!」と軍人さんに命令されたと証言する、数人の人達に現地で会ったことがある。
一方的に旧軍を指弾する沖縄の異様な同調圧力の中で、「命がけで島を守ってくれた軍人さんに、濡れ衣を着せたままでは死ぬに死ねない」と、批判や嫌がらせを覚悟でカミングアウトしてくれた人もいた。援護金を貰うために村ぐるみ、県ぐるみで集団自決の軍命令をでっち上げたのではないか、さらにそれを正当化するため、「日本軍が沖縄にいたから悲劇が起こった」という「広義の強制」説が、あたかも正論であるかのように島の言論空間を支配しているのではないか、という疑問を多くの歴史家や研究者が指摘している。そうだとしても、当初は許容される程度の詐術だったかもしれないが、ある国の工作に利用されるままの現状を知るにつけ、あの沖縄戦で亡くなった人達の怨嗟の声が聞こえてくる気がするのは私だけではあるまい。
この文章の中には引っかかるところが多くあります。
多数の軍人が、沖縄県民に「死ぬな!生きろ!」と言ってくれたなら、あのような悲劇は起こらなかったわけだし、集団自決の軍命令がでっち上げられたものだとの考えについてはまだ我慢できるとしても、それが「ある国の工作」によるものだというに及べば、そこにはあまりにも論理の飛躍があるとしか言わざるを得ないと思います。
沖縄をめぐる事象を寄せ集めて強引につなげてみたら、もしかしたらこんなことも成り立つのではないですか?という無脈絡さを感じます。もしかしたら、それが「強欲チャンプル」(強引なまぜこぜ)なのでしょうか。
そのあたりは、さまざまな考え方があろうと思いますので、読まれた方々それぞれの立場で判断すればいいのではないでしょうか。
(2017. 3.24 読)

|
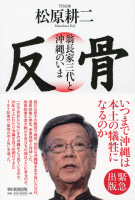 |
「反骨 翁長家三代と沖縄のいま」 松原耕二 著 朝日新聞出版
1,500円+税 2016年 7月30日 第1刷発行
自民党一筋で来た男・翁長雄志(現沖縄県知事)はなぜ、ここに来て自民党政権と激しく対立するようになったのか。彼を突き動かすものは何か。
思えば翁長ほど顔つきが変わった男もいないのではないだろうか。
私たち本土の人間は、カチャーシーを沖縄の人々と同じように踊ることはできない。しかし両手を左右に揺らして舞う人々の姿から、目を離さないでいることはできるはずだ。 (まえがきより)
翁長知事の父・祖父と沖縄戦の関わりを中心に、本土・沖縄・米軍それぞれの肉声に深く迫りながら、問題を浮き彫りにし、未来を探る。――という、翁長一族と沖縄の物語です。
祖父は息子の眼前で戦死。苛烈な沖縄戦を生き抜いた父は、遺骨収集に奔走し、米軍政府と対峙しました。翁長知事を突き動かす苛立ちの根はどこにあるのか。一方で、米兵たちはいまの沖縄をどう見ているのか。このあたりが論点となります。
著者は、1960年生まれ。84年にTBSに入社し、2014年「フェンス〜分断される島・沖縄」で第40回放送文化基金賞テレビドキュメンタリー番組優秀賞している方です。15年から「週刊報道LIFE」のメインキャスターを務めているとのこと。
沖縄タイムスの書評(一部)を以下に引用。
沖縄で起きている問題の本質を「本土」に伝えるのは容易ではない。在京メディアの一線で長年、悪戦苦闘してきた著者であればなおさら、そのハードルの高さを身に浸してきたはずだ。
「本土」の空気も、大手メディアの組織の論理も熟知している著者は、「定型化している沖縄報道を何とかできないものか」という、「自分も含めた本土メディアへの強烈な不満」を抱いていた。
翁長雄志知事が本書の主人公だ。
「辺野古」を巡って政府と対峙する翁長知事は、著者にも容赦ない言葉を浴びせる。「あなたたち本土の人間は」。インタビューの折に触れて翁長からこう言われ、その都度、著者はたじろぐ。
「翁長と話していると、自分が本土の人間であることを否応なく思い知らされる」。著者は内面を率直に吐露しながら、翁長の言葉の裏や内奥に何があるのか自問自答を繰り返す。そして、こんな心域に達する。
「私を含め、本土の人間に、沖縄県民の心の襞がわかるとは思われない。しかしわかろうとすることなしに、どうして基地問題を解決することができるだろうか」
本書は、翁長知事を生んだ翁長家三代の軌跡を追いつつ、沖縄の戦後を浮き彫りにしていく。筆圧の強さを感じるのは沖縄戦に関する記述だ。現在に連なる基地問題と沖縄の人々の精神性を考える上で、「沖縄戦」は避けて通れない。そう確信した著者はこう記す。
「翁長家三代の歩みは、まさに沖縄の戦後そのものと言ってもいいだろう。そしてその戦後はまだ終わってはいない」
強く印象に残った一文がある。
「本土の人間はいつまで沈黙を続けるのか」
本土の人間でありながら本土の人間の「醜さ」「狡(ずる)さ」に辟易する。評者が沖縄にいた17年間、そして東京で暮らす今も感じ続けている、己と周囲へのいら立ちを、本書の著者とならば共有できそうな気がしている。
(渡辺豪・元沖縄タイムス記者)
これを読んで、翁長知事の過激とも映る様々な行動に秘められた核心部分がようやくつかめたような気がしました。
(2016.11.27 読)

|
 |
「沖縄―戦争と平和」 大田昌秀 著 朝日文庫 621円+税
1996年 9月 1日 第1刷発行
著者の大田昌秀は1925年久米島生まれ。沖縄師範学校在学中に鉄血勤皇隊の一員として沖縄戦に動員され、九死に一生を得ますが、多くの学友を失います。戦後、早稲田大学を卒業し、琉球大学法文学部教授、同学部長を歴任。
沖縄戦の教訓が、沖縄の伝統的な平和思想とともに日本国民の共有財産になってほしいと切実に望む著者が、30年以上前の1982年に書き下ろしたものを、知事在任中の96年に文庫化されたものがこの本。その古書を2015年にわずか1円(+送料257円)でゲットしたものです。
著者が沖縄県知事になったのは1990年(〜98年)。95年、米兵の少女暴行事件が発生したことなどを背景として軍用地の代理署名を拒否し、大きな注目を浴びました。
その頃はちょうど自分がいちばん沖縄に熱かった時期で、社会的、政治的に沖縄はどう変わっていくのだろうかと、不安を上回る期待を持って見つめていたのでした。
序章から第6章まで。それらは「現在の軍拡状況」、「沖縄の平和思想」、「戦場への道のり」、「沖縄戦と住民の記録」、「沖縄戦の教訓」、「復帰後の基地と平和への希求」。
このうち第3章にある「住民の証言」の5つの挿話の凄まじさは、圧巻、驚愕、ただ呆然。ウチナーンチュたちが体験したこのような修羅場は、戦場にならなかった本土の人間にはなかなか理解できないのかもしれません。
そうであるならば政府は、沖縄戦の教訓を日本国民の共有財産にするために適切な対応策を講じなければなりません。しかし著者は「あとがき」で、次のように嘆いています。
『――小・中・高校の教科書で「沖縄」がどのように扱われているかを調べてみると、愕然とせざるを得ません。・・・戦後になっても1960年頃までの教科書には「沖縄」は欠落したままなのがほとんどです。では現行の教科書では、「沖縄」がどのように記述されているかといえば、大いに問題があります。』
――というありさまで、沖縄戦の教訓と沖縄の平和思想とを全国民の共有財産にしたいとの著者の願いは到底かなえられそうにはありません。
(2016.11. 9 読)

|
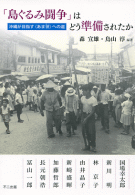 |
「「島ぐるみ闘争」はどう準備されたか ―沖縄が目指す“あま世(ゆー)”への道」
森宣雄・鳥山淳 編著 不二出版 1,800円+税
2013年10月10日 第1刷発行
沖縄を占領した米軍は、サンフランシスコ講和条約が締結され「戦時」から「平時」体制へと移行したため、民地を軍用地として使用するためには何らかの法的処置が必要になりました。また、これまで占有していなかった土地についても大規模な土地収用を開始して軍用地を拡張していったため、地主を中心に反対運動が激化していきました。
沖縄民政府側はこれらに強く抗議。しかしアメリカ側は「プライス勧告」を発し、タダ同然かつ十数年分を一括払いで支払う提案を押し付けようとしたため、保革の枠を越えた全住民を巻き込んだ「島ぐるみ闘争」と呼ばれる反対運動が起き、沖縄各地で「四原則貫徹」を求める集会やデモが行われました。
この「島ぐるみ闘争」がどのような形で準備されていったかを明らかにしようというのがこの本のテーマです。
3部構成となっており、第1部は編者が当時の歴史的諸相を概観し、第2部では国場幸太郎に着眼し、国場の自分史的な構成をとりながら時代を描写、第3部では沖縄史の論客たちが同時代の群像の交流の記憶などを記録しています。
とりわけ第2部は印象的。当時共産党員だった国場幸太郎が生前書き残した遺稿を編者たちが読みやすく手を加えたもので、米CIC本部で受けた不当な手ひどい拷問の様子を記した部分は圧巻です。
また、第3部では、50年代と現代の落差を結ぶ心情の中に国場を位置付けて記述がなされますが、その試みは当時の精神と論理を現代から未来へと橋渡しする効果がありそうです。
はじめのうちは展開が今一つ難解でなかなか読み進められずにいましたが、後半になるにしたがって円滑にかつ興味深く読むことができるようになりました。
(2016.10.27 読)

|
 |
「だれが沖縄を殺すのか 県民こそが“かわいそう”な奇妙な構造」
ロバート・D・エルドリッヂ 著 PHP新書 800円+税
2016年 4月28日 第1刷発行
『いまの沖縄は、あまりにおかしい。このままでは、日本の民主主義は沖縄から破壊されかねない。こんなに酷い、無責任なメディア、不透明な県政、説明責任を果たしていない不透明な県政、革新系がつくった偏った教育、狭小な言論空間などといった環境のもとに置かれている沖縄県民こそが本当に“かわいそう”な存在だ。
そしてこの奇妙な構造の背後には中国の影が―。
神戸大学大学院で博士号を取得し、大阪大学准教授を経て、在沖米海兵隊の政務外交部次長を務めた著者が、日本を愛するアメリカ人として沖縄と日本の危機を鋭く告発。民主主義、メディア、基地問題、日米関係などについて、「沖縄問題」という切り口を通して問題提起する。』
・・・という視点から書かれたもの。
近時、沖縄のメディアは偏重しており、沖縄問題がいつまでも解決しないのは彼らこそが諸悪の根源だからだ――的な論調をよく見聞きするのですが、それは本当なのでしょうか。
現代においては、マスコミが全体的な世論形成の主導権を握っており、時としてその論調が偏重していると感じることはよくあることです。しかし、そんな中でとりわけ沖縄のマスコミが世論を大きくミスリードしているとは思えないのですが、どうでしょう。
一般的に物の考え方というのは、考える人や、場合によっては法人や団体などが、これまでに経験してきた事実やそれらに基づく思いが積み重なって発露されるものだと思います。つまりは、その人なり組織体がどういう経験をし、どういう思いでこれまでの時代を生きてきたかをしっかり慮らないと、考え方を理解することはできません。
そのような立場に立てば、沖縄のリーダーやマスコミが、第三者にとって耳の痛いことを繰り返し、場合によっては執拗と思えるほどに強烈な発言をすることがあるかもしれません。
ですが、それらをひとつひとつ上げ足を取るように、今の発言はおかしい、偏重していると決めつけるのはいかがなものなのでしょうか。
筆者は「はじめに」で、『沖縄県知事が国際社会に向かって、「沖縄の人びとは自己決定権(=民族自決権)をないがしろにされていて、日本は自国民の自由、平等、人権、民主主義を守っていない」と声高に叫んでいると知ったら、あなたはどう思うだろうか。』と問いかけています。
しかし、これを読んだ自分は、べつに異常とも不思議とも感じず、沖縄の思いとしては極めてまっとうではないか、というのが本音です。
沖縄は、17世紀初頭から王国を否定され、明治の琉球処分を経験し、先の戦争で島全体を焦土にされ、ようやく母国と感じることができるようになった日本へと復帰しようとしていたのにサンフランシスコ講和条約で裏切られ、今もなお多くの米軍施設を背負わされて不自由な思いをしているのです。そのような苦渋の歴史の一部始終について、著者の考えを読めば読むほど、深く理解しているとは思えないのです。
また、この引用がはじめから胡散臭いのは、著者が「自己決定権」を勝手に「民族自決権」と読み替えていることです。ここでいう自己決定権は、憲法上何人にも保障された基本的人権の一部や、地方自治法上の地方自治体としての権能についてそう表現していると捉えるのが素直であり、前時代的な植民地的支配はやめてほしいということを言いたいのであって、沖縄の独立とか「沖縄民族」の高揚を表現したものではないことは一目瞭然だと思うのです。
そう思わせられていること自体が、おかしな沖縄からだまされているのだと著者は言うでしょう。でもそれって、つまるところ意見の衝突だということだけであり、単なる水かけ論なのではないか。
私としては著者に対して、沖縄側の主張をもっと真摯な気持ちで受け止める度量を持ったらどうですかとしか言いようがありません。
賛成の人、静かに拍手をお願いします。
(2016. 9. 7 読)

|
 |
「いくさ世を生きて 沖縄戦の女たち 真尾悦子 著 ちくま文庫
380円 1986年 7月29日 第1刷発行
文庫本の233ページもの。初出は1981年といいますから、今から35年前に筑摩書房から発刊され、その5年後の1986年に文庫化されたものを、このたび古書市場から入手したものとなります。
戦後36年、基地と観光の島と化してしまった沖縄で、女であるがゆえに負わなければならなかった過去に口を固く閉ざし、沖縄戦の深い傷痕をかかえて生きてきた女たちが、ひとりひとりの命こそが宝である世の中を願って、いまその胸のうちを語る。――といった内容のもの。これは読まなければならないでしょう。
著者の真尾悦子(ましおえつこ)は、1919年東京生まれ。主な著書に「たった二人の工場から」「土と女」「地底の青春」「海恋い」「沖縄祝い唄」など。夫の倍弘は詩人。90を過ぎ、眼が見えなくなって介護老人ホームに入っていたようですが、2013年に亡くなられたようです。
『3年余のあいだ、私は沖縄戦に遭った女の人をしつこく訪ねて、つらい体験を思い出させてしまった。いっそ、狂ってしまいたかった、と述懐した人もあった。いまでも、当時の恐怖から抜けられないでいる人たちなのである。
何という罪ぶかい所業か、と己れを責める一方で、私はどうしても聞きたいという心の昂りを抑えられなかった。人間が殺し合う、愚かな戦争を、二度としてはならぬ、と痛いほど歯を噛み合わせてあるいた。
沖縄の人は口が重い。しかし、何べんも会っているうちに、まるで門中の一人ででもあるかのように、家庭料理を振るまい、打ちとけてくれるのであった。』(「あとがき」より引用。)
戦争体験をした一人の女性は語ります。
「いまごろになって、ヤマトの人に戦争の話をしてみても仕方ない、と思って、ずいぶん考えたんですけどねえ。・・・これはもう、実際に遭った者でないと無理なんです。わたしが、戦争の夢を見てよくうなされるもんですからね、主人が、キミ、いつになったら忘れられるのかって可哀そうがりますけどね。生きているかぎり、あの恐ろしさはどこへも消えません。死ぬまで、わたしにとっての戦争は終らないんだ、とそう思っています。」(本文より)
ヤマトンチュに戦争の話をしても仕方ないと思うのは、距離が離れていて理解できないということではなく、ほかならぬ「加害者」に対して話すことになるからであり、そういう思いは沖縄戦を体験した大多数のウチナーンチュが抱いていたのではないでしょうか。
戦争の犠牲者になるのは、いつも弱い立場にある人たちなのです。
(2016. 8.29 読)

|
 |
「オキナワ論 在沖縄海兵隊元幹部の告白」 ロバート・D・エルドリッヂ 著
新潮新書 700円+税 2016年 1月20日 第1刷
2016年 2月25日 第4刷発行
「NO」しか言わない沖縄(=NOKINAWA)のままでいいのか?!
著者は、政治的思惑と感情論ばかりが支配する空気に抗い、20年にわたって情熱を傾け、事実に基づいた日・米・沖のあるべき姿を探求し続けてきました。
歴史研究者として、また海兵隊の政治顧問としての立場から、誤解だらけの基地問題、政権交代とトモダチ作戦の裏側、偏向するメディア――といった沖縄問題の虚実を解き明かしていきます。
沖縄の人々も日米両政府も米軍も、傾聴すべき直言が満載の刺激的な論考である――ということなのでしょう。
論調は冷静であり、一見彼の主張はすべて正しいように思えるかもしれません。しかし、憲法第9条の条文と、日本や自衛隊の現実とが乖離していることをもって、そのことが世界の信用を失うことにつながるから現実に合わせて改正したほうがよいとの単純な結論を導き出しています。そんなに簡単なことなら、あまりお利巧とは言えない日本の国会だってそうしています。
また、基地が存在したからこそ今の沖縄は復興が速く進んだと言いますが、そこには沖縄を立ち直れないほどに戦闘で破壊し尽してきた自国に対する反省は微塵もありません。
そんなことなので、個人的には沖縄が「NOKINAWA」になっているとの著者の論調には素直に同意することはできません。
著者の一方的な論理が巧みな表現等によって押し付けられる構図が新書などにはよく見られますが、この本もその類の一つのような気がします。
その証左として、彼は私のような日本人の多くからおそらく理解が得られないうえに、ある意味唯我独尊的な考え方からか、米軍側からもはじき出されてしまっています。
仮に彼の考え方が後になってみれば正しかったのだなとわかったとしましょう。しかし、政治や社会問題は、その問題に関わる人々の世論やその時代の時代性によって大きく結論が変わるものであり、正しい答えは1つだけではないはずです。
つまり著者は、正しい答えなどない物事に対して自分の主張を強く出し過ぎたために、外からも内からも相手にされなくなったと考えればわかりやすい構図のように思えるのですが、いかがなものでしょうか。いや、こういう人って、ある程度大きい組織の中にはたいていいるものなんですよね。
それでは沖縄問題について、オマエは自分なりの考えがあるのかとツッコミを入れられれば、それはかなり困った事態に陥ってしまいます。玉石混交の広い砂漠の中から宝石だけを拾ってこいと言われても、それは無理な話。沖縄問題はそれほどにこんがらがっていて、一介の沖縄フリーク風情が簡単に論破するようなマターではない、というのが結論です。
皮肉を言うつもりは全くありませんが、ここまで書いていて思い出したのは、新日本プロレスの内藤哲也が言う「トランキーロ!」というセリフ。
著者には、物事の解決や今後の身の振り方なども含めて、「トランキーロ」(焦るな、落ち着いて)の言葉を捧げたいと思います。
(2016. 7. 8 読)

|
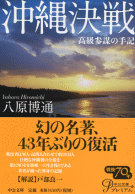 |
「沖縄決戦−高級参謀の手記」 八原博通 著 中公文庫
1,450円+税 2015年 5月25日 第1刷発行
日本陸軍大佐・八原博通。1902年、鳥取県米子市生まれ。アメリカへの留学経験に基づきアメリカの軍事状況を熟知し、第32軍の高級参謀として沖縄戦での戦略持久作戦を指揮。巧みな作戦指導によって圧倒的に優勢な米軍に多大な犠牲を与え、米軍からは「優れた戦術家としての名声を欲しいままにし、その判断には計画性があった」と高く評されています。
しかしその一方で、持久戦を展開したことが沖縄県民に悲惨な犠牲を強いることになり、後世その戦術に強い批判が集中することにもなりました。
その八原が自ら筆を執って書き記したのがこの「沖縄決戦 高級参謀の手記」で、戦後27年を経た1972年に読売新聞社から発刊されました。
そして、それからさらに43年を過ぎた2015年に、中央公論から文庫本で復刊されたので、待ってましたとばかりにすぐに買ったものです。
著者はその「序」で、「作戦参謀として、この戦いの企画指導に直接携わった私は、自らの立場に省み、また敗者兵を語らずの精神に従い、正面切って多くを語るのを今日まで拒んできた。だが作戦こそわが命と思っていた私には、作戦の巧拙善悪はいざ知らず、そうではない、実はこうであったのだと、叫びたいものがある。
戦後もすでに27年、沖縄も本土復帰した今日である。私の記憶も薄らいでいるが、幸い戦時中ならびに戦争直後にかけて書き留めておいた記録がある。これを根拠とし、現在まで多く世に出た沖縄戦の史書で問題になった諸点も考慮し、敢えて沖縄戦の実相をここに訴えんとするものである」――と記しています。
1945年6月23日、牛島満司令官と長勇参謀長が自決して第32軍は組織的な抵抗を終了しますが、八原はその直後に戦訓伝達のため民間人になりすまして脱出を図り、米軍の捕虜となります。
軍の先陣に立って指揮にあたった高級参謀のこの行動が、陸軍内部での八原の評価を最悪なものとしてしまい、戦後は陸士同期会にも呼ばれることもなかったそうです。
その後は生活に困窮し、故郷で夫婦で洋服生地の行商をしていたといいます。1981年没。
戦場での領袖間の戦術面での対立はとてもリアル。一般論として著者が自身の立場を美化する傾向があることは否めませんが、自信を持って己が思い描いている戦術を、様々な横槍や対立などに阻害されて縦横に展開できなかった悔しさはひしひしと伝わってるものがありました。
520ページ余りの厚手のものですが、それにしても文庫本で1,450円+税というのは、ちょっぴりエクスペンシヴでないかい?
(2016. 1. 3 読)

|
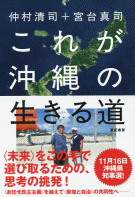 |
「これが沖縄の生きる道」 仲村清司・宮台真司 著 亜紀書房
1,500円+税 2014年10月 8日 第1刷発行
仲村清司の本はかなりの数を読んできていて、仲村氏はその間、沖縄に移住し、夫婦の凸凹ぶりでおちゃらけてみせ、沖縄のポップカルチャーを発信し、うつ病で悩み、スージグヮーの猫を愛でるなど、様々な変遷を経て、今彼は沖縄大学の客員教授をしています。そんなわけで、沖縄問題を取り上げたこの本も即買いして楽しみにしていました。しかし・・・。
「社会の空洞化が押し進み、“恨み”と“不安”のマッチポンプにより民主主義が空転し続ける本土。沖縄は本土がたどった悪しき道を追いかけるのか? それともあり得べき共同体自治へと歩み出すのか?
フラットな「本土並み化」の追求でも、構造的差別の固定化でもない、“希望”にみちた島づくりのための鮮烈な提言の書。」
――というのがこの本の紹介文です。なんとなくこれだけで、全体的に漂う著者側の自己陶酔というか利己的というか、読者に対して内容をわかりやすく伝えようという姿勢がほとんど感じられない本だということがわかってしまいます。
事実読んでみて、その印象をさらに強く持ったところ。本音を言うと、ナニコレ的で、読んでいて疲れました。
藤井誠二というノンフィクション作家が企画・司会を担当し、終始、仲村清司と宮台真司が対論形式で話を進めていくという構成。
そもそも書いた文章ではなく、それぞれが時には噛み合わない形で好き勝手に話しているのをそのまままとめたものなので、論旨を読み取るのが容易ではありませんでした。はい、読者の能力の問題だと言われればそれまでなのですけどね。
でも、この本を読んで、その内容がすっきりと理解できたという人がいたなら手を挙げてほしい。主張が強くて、小難しい用語を使い、脈絡がはっきりしない文章って、ホント、読むのが辛いものですよ。
その原因となっているのが、はっきり言いましょう、宮台真司というヒトの論理展開です。対談しているのに、話の多くが彼の発言部分になってしまっていて、話は飛ぶし、たとえ話している内容が飛躍的だし、仲村にももっとしゃべらせろよという感じ。
こういう人っているでしょう、酒の席などで空気が読めなくて一人でしゃべっている人とか。同席者が欠伸をしたってお構いなし、みたいな。
1959年生まれ、東大大学院出の社会学者だそうですが、ボクは仲村清司のファンなのです。どうかそのレベルに合わせて話してください。世の中の人間の多くというかほとんどは、アナタのように頭がよくないのですから。
というわけで、買って損したと思わせられた本。
わからないながら、放り投げもせずに330ページもよく我慢して読んだものだと、自分を褒めてあげたい。
スマン、久々にコキオロシてしまったな。
(2015.12. 9 読)

|
 |
「沖縄の不都合な真実」 大久保潤、篠原章 著 新潮新書
740円+税
2015年 1月20日 第1刷 2015年 3月 5日 第5刷発行
こじれにこじれる沖縄の基地問題の本質はどこにあるのか。
見据えるべきは「カネと権利」の構造である。巨額の振興予算を巡り、繰り返される日本政府と県の茶番劇。この構図が変わらない限り、問題は解決できない。
公務員が君臨する階級社会、全国ワーストの暮らしに喘ぐ人々、異論を封じ込める言論空間等々、隠された現実を炙り出す。党派を問わず、沖縄問題の「解」を考えていく上で必読の書。
――とは、カバーのそでに書かれた紹介文です。
沖縄は離婚率、待機児童比率、DV発生比率、非正規雇用率などが全国一、学力水準、1人当たり納税額、国民年金納付率は全国最低です。
本書では、このような状況下で人々は極端な格差社会にあえいでいる、という捉え方をしており、「沖縄の革新政党には「沖縄を差別するな」という「反日思想」はあっても、シングルマザーや失業者の暮らしを楽にさせる弱者救済の左翼思想がない」と訴え、憂いています。
また、地元にはマスコミや学識者、労組などが一体化した支配構造が存在し、それを支えているのが振興予算による利権であると訴えています。
そのあたりを端的に表す文章が「序章」にあるので、引用。
「沖縄のナショナリズムと、そのナショナリズムの発信元である、保革同舟の支配階層の存在を明らかにすることこそ、実は本書の最大のテーマとなっています。私たちは沖縄をある種の身分制社会と捉え、基地問題そのものよりも、沖縄のこうした現実を自覚し、そこから脱却する道を探ることこそ、沖縄の未来を、ひいては日本全体の未来を、明るく照らし出すことになると考えています。基地問題は沖縄の抱える問題を象徴はしていますが、問題の根っ子はそこにありません。」
まあ、ある意味真実を衝いていて、同意できるところが多数ある一方で、それは深読みし過ぎだろうと思われる部分もあり、センセーショナルとも言えるのでしょうが、きっと社会全体にはより強い賛否両論があるのだろうな。
章立ては9つで、「普天間問題の何が問題なのか」、「高まる基地への依存」、「「基地がなくなれば豊かになる」という神話」、「広がる格差、深まる分断」、「「公」による「民」の支配」、「本土がつくったオキナワイメージ」、「「沖縄平和運動」の実態と本質」、「異論を封殺する沖縄のジャーナリズム」、「「構造的沖縄差別論」の危うさ」。
共著者の一人の大久保潤は、日本経済新聞の那覇支局長として沖縄等向き合ってきた人物で、1、2、4、6章を執筆しています。
そしてそれ以外の5つの章を、大学研究者・評論家として沖縄に関わってきた篠原章が執筆しています。篠原氏はかつて「熱烈!沖縄ガイド」や「沖縄ナンクル読本」などの沖縄紹介本に本土側から携わってきた過去がありますが、そのスタンスは真逆と言ってもいいぐらいの位置取りへと変容してきているようです。
(2015.10.24 読)

|
 |
「ガマ 遺品たちが物語る沖縄戦」 豊田正義 著 講談社
1,300円+税 2014年 6月17日 第1刷発行
「ガマ」とは、このページにお越しの方はよくわかっていると思いますが、沖縄の方言で、自然にできた洞窟のこと。沖縄本島に約2千か所あると言われ、主に南部に密集しています
沖縄戦では、そのガマに隠れていた多くの住民や兵士がその中で亡くなりましたが、ガマのほとんどがジャングルの茂みの中にあり、また地盤が緩んで危険な状態になっていたりしたために、遺骨や遺品が手つかずの状態で放置されてきているところが多数あります。
あの戦争から70年。この本に掲げられた3つの話は、ガマから掘り出された遺品たちとその持ち主、そして家族にまつわる人生の物語です。
第1章は「哲也の硯」。
国民学校の卒業祝いに母から新品の硯をもらった哲也でしたが、その日の夜から長期間にわたるガマでの避難生活が始まりました。米軍に囲まれ、住民たちは投稿を考えましたが…。
第2章は「新太の目覚まし時計」。
遺骨のそばにあった、開けられた缶詰と使われていない手榴弾、そして目覚まし時計。遺品から、最期まで人間らしくあろうとした少年兵の姿が浮かび上がってきました。
第3章は「夏子のアルバム」。
60年前に民家から略奪したアルバムを返したいと、元米兵が沖縄を訪れます。写真に写った美しい女性の妹は、避難先の密林で命がけで娘を産んだ姉の最期を語り始めます。
登場人物の一人ひとりに実在するモデルがいるわけで、読んでいて、命の尊さを思い、気が遠くなるような感覚さえ覚えます。
あの戦争から70年という長い歳月が経ちましたが、それでもまだ、ガマのなかから声が聞こえてくるような気がします。沖縄戦は、まだ終わっていないのです。
(2015. 9.26 読)

|
 |
「10万人を超す命を救った沖縄県知事・島田叡」
TBSテレビ報道局「生きろ」取材班 著 ポプラ新書
780円+税 2014年 8月 1日 第1刷発行
「こんな日本人がいた! 命がけで人を守り、戦いぬいた男。
島田叡という人物をご存知だろうか――? 1945年1月太平洋戦争の最中、米軍が迫る沖縄に戦中最後の知事として赴任。5カ月の間だが、県民保護の立場を貫き通し、沖縄県民と最後まで行動をともにした。玉砕が叫ばれる中で「生きろ」と言い続けた島田の生き方を通して、沖縄戦とはどのようなものだったかを伝え、命の重みを問う。」 ――という新書。
島田叡の足跡をまとめた名著として、「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」(田村洋三著、中央公論新社、2003)がありますが、それ以来のしっかりとした島田モノでしょうか。
TBSテレビ報道局の30代から50代の記者やディレクター6人で構成する取材チームによるもので、彼らは岩城浩幸、藤原康延、黒岩亜純、佐古忠彦、片山薫、岩波孝祥。
全6章。赴任直後から決戦が迫ってきた沖縄での島田の行動をまとめた第1章「赴任直後に県政を再生」、首里から島尻へと進んだ逃避行の様子がわかる第2章「移動を続ける県庁を指揮」、野球選手として活躍した学生時代の島田を追った第3章「島田という人間をつくったもの」、中央勤務経験のない異色の官僚時代を記した第4章「名選手から異色の官僚へ」、最期の秋を迎えた第5章「今をもって県庁を解散する」、戦後に島田の歩いた道をたどる第6章「島田叡の目指した道」。
この取材班の成果は、「報道ドラマ「生きろ」〜戦場に残した伝言〜10万人の命を救った沖縄県知事・島田叡」という2時間超の特番として、2013年8月7日に地上波TBS系で放映されました。
自分は、2015年の終戦記念の日の8月15日にBS−TBSで再放送されたものを録画保存しています。
(2015. 8.12 読)

|
 |
「われ、沖縄の架け橋たらん」 國場幸之助 著 K&Kプレス
1,300円+税 2014年 7月 8日 第1刷発行
沖縄はしばしば中国寄りと言われ、時には「沖縄は中国の手先だ」と批判される。そんな人々に問いたい。「あなたは沖縄を、本当に日本だと思っていますか?」
本土と沖縄の対立をもたらしたのは、中国でもアメリカでもなく日本人自身なのだ。
今、本土と沖縄の距離を縮めるために、私たちに何ができるのか。
保守政治家として唯一人「普天間基地の県外移設」を訴え続ける著者の、渾身の提言だ!
――とは、古賀誠センセイがこの本の発刊に寄せた推薦文です。
一方、代議士である著者は「はじめに」で、次のように書いています。
「沖縄の尊厳と日本の国益の狭間で悩み苦しみ、挫折と失敗ばかりの私自身の半生をさらすことにより、沖縄と本土の相互理解に資することにならないか。そんな使命めいたものを感じながら、本書を書きました。」
うむ、カッコイイよなあ。「使命」などと感じて自分に酔っている、政治家らしい言葉だよなと思ったり。
著者は、自由民主党の衆院議員。父方の大叔父は元衆議院議員の國場幸昌、祖父は國場組創業者の國場幸太郎、義父は元沖縄県議会議員の西田健次郎というサラブレッドです。ちなみに國場組といえば、沖縄では知らない人はいない県下最大のゼネコンで、父はその「國場組」の元代表取締役社長です。
高卒後1浪して日大文理学部哲学科に入学するも、古代ギリシャ語で挫折し中退。その後、早大雄弁会に憧れ、夜間の社会科学部に入学。比較政治学を専攻し、雄弁会では幹事長を務める。
卒業後は米コロンビア大に語学留学し、帰国後、沖縄県知事稲嶺惠一の秘書。2000年には沖縄県議選に那覇市選挙区から出馬しトップ当選。20代での同議会議員誕生は史上初。当選後、自民党に入党。
03年、県議を辞して衆院選挙に出馬するも落選。04年の県議選では自民党の公認を受けられず、無所属での出馬となったが、再びトップ当選。
その後紆余曲折を経て、12年の衆院選に再出馬し、「沖縄復帰日の5月15日を主権回復記念日にする」「日米地位協定の改定」「米軍普天間基地の県外移設」等を公約に掲げ、国民新党の下地幹郎を破り当選。
15年には、戦後70年の日本の歩みを検証する勉強会「過去を学び“分厚い保守政治”を目指す若手議員の会」の立ち上げに参加し、共同代表世話人の一人となる。
当書では、「普天間基地を県外へ」、「沖縄で、保守であること」、「「復帰っ子」として生まれて」、「強大化する中国にどう立ち向かうか」、「李登輝総統の教え」、「沖縄と本土の距離を縮めるために」など、著者の政治的スタンスや基本思考を明らかにする内容の章立てが続き、最期にインタビュー形式の「「慰霊の日」に沖縄を問い直す」のインタビューが付録的についています。
政治家の記す本というのはいつもその後ろに集票的な背景がちらつき、ノンポリティークな者にとっては多少胡散臭くて、読んでいて少々辛くなることがあるものです。
この本もそういう一面がないとは言えませんが、高邁なことを書こうとせず、また、国会議員の中ではまだ一兵卒だという低姿勢が感じられるので、途中で打ち捨てることなく最後まで読めた次第です。
こんな感想しか持てなくて相済みませんが、自分は沖縄のブルジョアを代表する國場組の御曹司がこれからどう生きていくのかを見ていく上で、彼のよって立つところを今のうちに押さえておいたほうがいいのかなあという考えでこの本を手にしたところですので、悪しからず。
(2015. 3. 9 読)

|
 |
「琉球独立論」 松島泰勝 著 バジリコ 1,800円+税
2014年 7月20日 第1刷発行
「なぜ今、独立なのか! 琉球人教授が書き下ろした植民地琉球の歴史と現状、そして独立への道」
――ということで、沖縄関連書の中では物議を醸した本として2014年のある意味代表作と言えるかもしれません。
強い信念のもと、専らある1つの観点から内容が構成されているので、まずこのことを十分許容して文章になじんでいかないと、読み進めることがつらくなる場合があると思います。自分はそれにはまってしまい、残念ながら最後まで納得しながら読むことができませんでした。
それはたとえば、
「現在の日本は、琉球人が責任ある個人として主体的に国家意思の形成に参加できる国ではありません。それは、戦後史を俯瞰しただけでもわかります。およそ国家というものは、全国民に対して平等に、福利の源泉として存在していなければならないはずです。しかしながら、日本という国においては、この全国民の中に琉球人は含まれていない。
琉球人が日本国の一部であることによって多くの犠牲を背負わされるのならば、自らの国家をつくるという選択肢を琉球人が真剣に考えても当然なのではないでしょうか。」
――という一部をとってみてもわかっていただけるのではないか。
論理的には大きな過ちはないと思われますが、ここまで断言調で構成されると、そう考える理由なり背景を読む者に対してもっと明らかにしてから展開するべきではないかという疑問がふつふつと湧きあがってくるのです。
その説明は要しないと考えるのであれば、この論説はその道の熟達者によってのみ読まれるべきであって、訴えたいことの大部分は一般庶民には伝わらず、今後の思想的広がりは期待できないことになります。平たく言えば、そういうのを唯我独尊と言うのでしょう。
琉球独立というひとつの方法論であり考え方が日本国民にも十分に浸透するには、万人に「そうだな」と思ってもらえるような論述技術が必要でしょう。
生意気言ってスミマセン。かなり期待していたものですから。
(2014.11.30 読)

|
 |
「魂還り魂還り皇国護らん ―沖縄に散った最後の陸軍大将牛島満の生涯」
将口泰浩 著 海竜社 1,600円+税
2012年 7月30日 第1刷発行
「沖縄に散った最後の陸軍大将牛島満の生涯」とサブタイトルがついた、牛島満の一代記です。
表題は、1945年6月18日、牛島が第十方面軍司令官に宛てて発した訣別電にある「矢弾尽き 天地(あめつち)染めて 散るとても 魂還り魂還り 皇国(みくに)護らん」という、辞世の句から引用したものとなっています。
牛島の人物像を、外見は茫洋として中身のある薩摩隼人の典型で、幼少期から陸軍エリートとして純粋培養された、繊細と厳格、情味がほどよく調和した人柄――として描いています。
そして、陸軍士官学校を20期の三羽ガラスと称されて卒業し、陸軍の教育部門や北満で活躍し、1944年に第32軍の司令官として沖縄に赴任するまでの経過についてを、4つの章を立てて論述されています。
その後は「沖縄決戦前夜」「日本軍の迷走」「死闘」「特攻」「撤退」と章が続き、終章の「玉砕」で終焉を迎えます。
牛島について、沖縄県民は、親兄弟たちを死に導き不幸のどん底に引きずり込んだ張本人として最も罪深い軍人と位置付けていると思われます。そのような世論が根強くある中で、このように純粋に「人物」そのものに着眼して比較的冷静に論述していることには一面、敬意を表してもいいのかもしれません。
しかし一方で、勧善懲悪的な日本人の「心」の面を強調すれば、少し美化し過ぎてはいないかと皮肉の一つぐらいは言いたくなるというのが正直なところ。
でもまあ、戦記物にありがちな立て板に水の戦況陳述のようなものは後ろに引いており、大きい文字での平易な表現で220ページほどと、ちょい読みには手頃なつくりになっていますから、沖縄戦へのアプローチの一手段としても有用かもしれません。
(2014.10.17 読)

|
 |
「沖縄の自立と日本 ―「復帰」40年の問いかけ」
大田昌秀、新川 明、稲嶺惠一、新崎盛暉 著 岩波書店
2,100円+税
2013年 8月 9日 第1刷 2013年10月25日 第2刷発行
沖縄の「復帰」とは何だったのか。
人びとの切実な願いである「平和憲法の下への復帰」となるはずであった施政権返還から40年が過ぎた今、変わらない米軍基地の重圧と構造的差別の現実を前にして、「復帰」の意味を根底から問い直し、真の自立を模索する議論が高まっている。
沖縄を代表する4人の論客が、沖縄の自立への展望とアジアの中での未来像を熱く語る。
――という趣向で、2013年8月に発刊されたものです。
2012年秋に、法政大学沖縄文化研究所の主催で、大田昌秀、新川明、稲嶺惠一、新崎盛暉の4人により、「「復帰」40年、これからの40年」というテーマでシンポジウムが行われ、その後沖縄大学で同メンバーによる座談会が開かれるなどの経過ののちに新たな論稿としてまとめられたのがこの本です。
登場する4人は、元知事二人に、大学にマスコミ。それぞれ、首魁として沖縄を統率してきた人物であり、沖縄に関する現役としてはトップと言っていい論客です。
これだけの顔ぶれになると、それぞれが張る論陣がうまく噛み合わずに空回りしたり論理がぶつかり合ったりするもので、そういうところを読み取ることも一興。しかし、この本の場合そういう面がうまく処理されていて、まあ、小難しく考えないで読めるものになっているようです。
4人の論客の基本的考え方を知る上でも役に立つかもしれません。
(2014.10. 5 読)

|
 |
「新装版 民族の悲劇 ―沖縄県民の抵抗」 瀬長亀次郎 著 新日本出版社
1,200円+税
1971年 8月10日 第1刷 2013年 5月20日 第2刷発行
50年以上前の1959年に三一書房から刊行されたものが、1971年に新日本出版社から新書として再刊され、2013年に新装されて出回ったものがコレ。
2013年5月、新装再発とほぼ同時に入手していましたが、この夏、昨年3月に那覇市内に開設された瀬長亀次郎の「不屈館」を訪れたときにこの本が山積みされていたのを見て、思わず買ってしまいそうに。ん、待てよ、これはもう買ってあったかどうか・・・と一人黙考したところ。
このような一風変わった来館者の一見悩んでいるかのような姿を憐れんでかどうか、事務室の女性はレモンケーキとお茶を出してもてなしてくれたのでした。「不屈館」、いいところです。
さて、1971年の再刊当時は、佐藤栄作首相が米国との沖縄返還協定に調印はしたものの、「核ぬき・本土なみ」については沖縄県民の切なる要望にはほど遠く、腹の底から首相に唱和して万歳を叫ぶ者は一人もいなかった状況でした。
再刊に当たって瀬長の書いた「まえがき」にはそのような状況が当時そのままにびっしりと書かれており、再刊の理由を次のように書いて締めくくっています。
「本書再刊の理由は、この統一闘争と統一戦線を発展・前進させるために、アメリカの軍事的植民地的支配に抗してたたかいぬいた県民の島ぐるみの土地闘争、自由と人権、民主主義をかちとる苦難にみちた統一のたたかいをふりかえり、これに学んで、たたかいへの新たな自信とエネルギーを汲みとることができるのではないかと信じたからです。」――と。
「基地権力者の意志は法なり」、「講和条約第3条のからくり」、「スキャップ指令と占領政策」、「ふきすさぶ反共政策」、「略奪はこうしてやる」、「島ぐるみのたたかい」、「「赤い市長」の出現」、「新しい情勢」の8章。
鋭い舌鋒でありながらも、その奥にあるまっすぐな信念と人々への博愛精神がしっかりと見える、熱い政治の実践書です。
(2014. 9. 7 読)

|
 |
「沖縄戦跡・慰霊碑を巡る」 三荻 祥 著 明成社 1,200円+税
2014年 3月 7日 第1刷発行
この本の「はじめに 本書を利用されるみなさんへ」には、次のように書かれています。
「本ガイドブックは、沖縄を訪れる皆さんが、なぜ沖縄で戦争が起こったのか、沖縄県民や県外の人はどのような気持ちであの戦争を戦ったのかを考えていただくきっかけとなるよう編纂しました。県内各地に建立されている代表的な慰霊塔や塔にゆかりのある人物をわかりやすく紹介していますので、修学旅行や調べ学習等にもぜひご活用いただけたらと思います。」
ということで、南部戦跡を中心に、中部、北部の慰霊碑を合わせて全80塔が紹介されています。
このごろ沖縄の歌碑や慰霊碑を好んで見ている自分としては、今後の沖縄訪問時に見ておくべき慰霊碑を確認するために、この本を入手しました。
この本に掲載されている慰霊碑のうち、すでに現場に立っているのは、読む前はまだ10数箇所に過ぎませんでした。
そしてこの夏、摩文仁の丘に足を踏み入れ各県の塔を参拝してきたので、その数は激増。とりわけ見たかったのは、島田叡知事をはじめ沖縄県職員を慰霊する「島守の塔」で、この本で場所を確認してじっくりと見てきたところ。
そのほか今回の旅では、糸満市の真栄里地区にある「山形の塔」、「バックナー中将碑」、「白梅之塔」も巡ってきました。
このようにたいへん有用なものとして使わせてもらいましたが、まだ30歳になったかならないかという年代の女性著者の略歴がよくわかりません。
平成19年に長崎大学を卒業後、全日本学生文化会議で「大学の使命」編集長を務め、平成25年より日本青年協議会「祖国と青年」編集部――と奥付にあるのですが、ナニコレ??
主な著書は「脅かされる国境の島・与那国 ―尖閣だけが危機ではない!」、「天皇陛下がわが町に」。・・・ひょっとして右翼系なのかな。
(2014. 7.28 読)

|
 |
「沖縄・阿嘉島の戦闘 沖縄戦で最初に米軍が上陸した島の戦記」 中村仁勇 著
元就出版社 2,000円+税 2013年 2月14日 第1刷発行
沖縄戦関連で、慶良間諸島の阿嘉島を取り上げたものとしては、「海上挺身隊」に組み込まれて阿嘉島に駐屯した元兵士が記した「沖縄戦と海上特攻」(深沢敬次郎著、光人社NF文庫)があり、それを先に読んだばかりですが、こちらのほうは、阿嘉島生まれの著者が記したズバリ「阿嘉島の戦闘」です。
「軍人、民間人たちは飢餓の中で米軍とどう対峙したのか。また「集団自決」の危機をいかに回避しえたのか。少年義勇隊員として戦い続けた自らの体験を礎に証言・資料を駆使して書き上げた渾身の労作」(コシマキより)。
そう、渡嘉敷島や座間味島では集団自決がありましたが、この島ではそれがなかったのです。
戦時中の阿嘉島で起きた出来事について、日米軍の記録、著作物、手記、日米の新聞・雑誌、聞き取り、それに少年義勇隊員の一人として直接阿嘉島の戦闘に参加した著者自身の体験などによりまとめています。
自然科学系でもない本としてはめずらしく左開きの横書きの体裁で、当時の阿嘉島の様子がいくつかの写真や図とともにかなり詳しく記されています。
その中で特に優れているのは、著者の実体験に基づく記述と、戦後になって著者が直接関係者のもとを訪れて確認した証言の部分。やはりこのあたりは、郷里を愛する者が行っているところが素晴しいと思う。記者やルポライターでは出せない味ではないか。
そんな阿嘉島本を続けて読んだため、その現場にぜひとも実際に立ってみたくなり、当書を読んだ2ヶ月後の夏に阿嘉島行きを敢行してしまいました。
現地の地理や地形などはやはりその場に立たなければわからないもの。
で、行った後に検証のためもう一度本に戻って改めて読んでみればなお理解が進むのでしょうが、まだそこまではやっていません。
そうすべきなのだろうなあ。でもなあ、新しい別の本も読みたいしなあ・・・。
(2014. 6. 8 読)

|
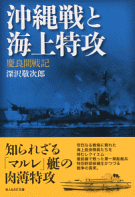 |
「沖縄戦と海上特攻」 深沢敬次郎 著 光人社NF文庫 790円+税
2013年 5月23日 第1刷発行
著者は、1925年生まれ。商業学校卒業後、特攻隊員として沖縄戦に参加し、アメリカ軍の捕虜になります。その苛酷な経験を、一人の兵士の目線で戦争体験記としてまとめています。
18歳で軍人を志願して陸軍船舶兵特別幹部候補生となり、「海上挺身隊」に組み込まれて慶良間列島の阿嘉島に駐屯、アメリカ軍の上陸を受けて逃げ惑い、飢えと闘ったのちにはPW(戦争捕虜)になって、座間味収容所、屋嘉収容所で生活します。そして1946年11月に復員。その2年7カ月の物語です。
渡嘉敷島や座間味島の集団自決について書かれたものはあるが、米軍が最初に上陸した阿嘉島については、そこで戦闘があったことを知っている者はいたって少ないと、著者は嘆いています。
そして、第一期船舶兵特幹候生1,890名中1,815名が戦病死したと言われており、生き残った者が船舶特攻を語り伝えていく義務があるような気がしてならない――と述べています。
まさに、苛烈な戦場に斃れた海上挺身隊員たちを悼むレクイエムと言えるでしょう。
沖縄へと向かう輸送船内の状況や、朝鮮から連れてこられた慰安婦たちの様子、何回かの切り込み、休戦協定の締結場面、収容所内での巧みなサボタージュの様子など、体験者しか書けないさまざまなことが描写されていて、興味深く読みました。
阿嘉島の戦闘の詳細についてはこの本で初めて触れることができましたが、奇遇なものでその1か月ほど後に、これとは別の「沖縄・阿嘉島の戦闘 沖縄戦で最初に米軍が上陸した島の戦記」(中村仁勇著、元就出版社刊、2013年)を入手して読むこととなり、さらに理解を深めることができました。
(2014. 5. 5 読)

|