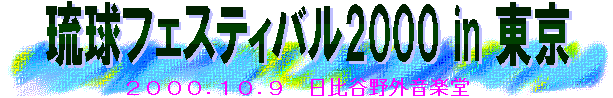
(その3)
|
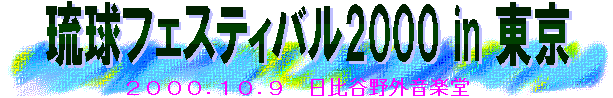
(その3)
○古謝美佐子
次は、古謝美佐子。
琉球の組踊りなどで8・8・8・6の琉歌をうたう際に用いられるあの節回しをうたいながら入場。
「みーこネーネー!」、「みさちゃーん!」などの声援が飛んでいるところをみると、一部に熱烈なファンを持っているのかもしれない。
ネーネーズ時代に第1回目の琉フェスに参加して以来、2回目だという。
公式プログラムを見ると、今回同じ追加出演者の大工哲弘は出演者欄にもちゃんと名を連ねており、そのうえ喜納昌吉・昌永の次に1ページを割いて写真入りで紹介されているのに、古謝についてはなにひとつ載っていない。
よほど直前に参加が決定したのだろう。
黒づくめのロングドレスを身にまとい、チリチリのロングヘアー姿で登場した恰幅のいい古謝は貫禄十分。
もうネーネーというようなイメージから完全に脱皮して、ソウルシンガーの雰囲気を漂わせている。
そしてそのことを増長するように、1曲目は、なんという曲なのだろう、よく聴くアメリカあたりのスタンダード民謡にウチナーグチの歌詞をつけて歌っていた。
彼女のステージではこの後が、個人的には圧巻だった。
「今日は嘉手苅のおとうの命日なので、おとうのよく唄っていたうたをうたってみます。」ということを言って、おとうの十八番を続けて歌ってくれたのだ。
まずは「ナークニー」。
沖縄本島を代表する遊び唄で、さまざまな唄者によって即興の歌詞で唄われるが、おとうがうたうと「嘉手苅ナークニー」といわれる独特のものになったものだった。
おとう得意のひと節で、多くのCDにも収録されている。
これを古謝が、自分流ではなく、嘉手苅琉でうたおうとしているのだから意義があるのだ。
次はそのチラシとしてよくうたわれた「かいされー」。
きれいだねという意味で、女郎との恋が歌いこまれている、しんみりとした唄だ。
そして「ヒンスー尾類小(じゅりぐゎー)」(「かまやしな」ともいう)。
那覇は辻(花街)の芸妓(ジュリ)との遊びや風俗が織り込まれている。
いったいこれらのうたは、21世紀になっても誰かがうたっていけるのであろうか。
ジュリなんていったって、もうそれ自体を連想できなくなっているわけで、きっと息子の嘉手苅林次の代が過ぎるとこの世から消えていってしまうのではなかろうか。
ちょっと感傷的になってしまうが、そういう側面からも、琉フェスの歴史として語り草になるワンシーンであったろうと、私は思っている。
3曲立て続けにやって一息入れた古謝は、今日の午前中の雨はきっと、参加できなかったおとうの涙雨で、今は月が見えてくるほどにその雨があがったのもおとうのおかげだろう、みたいなことをしゃべっていた。
ただの天候の変化もそう考えると意味ありげで、靴の中まで水浸しになったことも、もう許せてしまうからおもしろい。
厚い雲に切れ目ができて、空には本当に月が輝いている。
古謝は、最後にオリジナルをということでスローなララバイを1曲うたって、小走りに楽屋へと戻っていった。
○またまた藤木が、語る語る
幕間となって、またまた藤木が登場。
さきほど中断してしまった、なぜ粟国島か、という話の続き(答えは、ミュージシャンの多いわがままキャストがどこかへ逃げ出さないため、だそうだ。竹富島でロケをとの計画もあったが、高速船が頻繁に出ているので却下されたらしい。)をして、そこからいろいろと派生した話をする。
なにせ次はいよいよチャンプルーズの番だから、やや多めの準備時間が必要なのだ。
まずは、ナビィの恋で恵達オジィを演じた登川誠仁。
映画登場以来、誠グヮーの演技はうまかったという人がいるが、実はうまいのではなく、あれがあの人の「地」なのだということ。
そして、登川や嘉手苅林昌のようなサムライはもう不世出だろうが、喜納昌吉、大工哲弘、照屋林賢などこれに続く団塊の世代もまた違ったすさまじさがある、という。
その一例として、像のオリの軍用地返還問題でクローズアップされた知花昌一(ちばなしょういち)を挙げ、彼は戦争を憎んでいるだけであって、夜は仲のよい米兵とともにライブハウスでぎんぎんのロックを聴くのが大好きなおじさんなのだという話をする。ほう、そうなのですか。
次は嘉手苅林昌の逸話。
日本橋の三越を見て「那覇の三越もたいしたものだ、東京に支店を出している」と言ったという話。
初めて飛行機に乗ったときに、太陽をさがして窓から下をのぞいていたという話。
「先生と呼ぶのはやめろ」とおとうが言うから、ではどう呼べばよいかと訪ねると「"サキウマリ"と呼びなさい」と言ったとか(サキは先、ウマリは生まれですよね)。
そして、レコーディングでは絶対に1回しかテイクしなかったため、レコーダーを複数セットしなければならなかったことなどを披露した。
○喜納昌永登場!白雲節を唄う
さて、準備も整って、照明がステージ全体を照らし出されると、すでに81歳の喜納昌永が舞台中央やや左手に、椅子に着座してスタンバっている。
水色の着物がよく似合い、いくつになっても沖縄芸能界のスターであることを感じさせる。
そして喜納昌吉が登場。場内またまた騒然となってきた。
藤木が、「それでは、おとうを偲んで、「白雲節」から…」と言いつつそでに下がる。
私もこれは見ものとばかりに身を乗り出したが、一人で来ていた隣のおじさんもやおら立ち上がって拍手をしはじめた。
そうだったのか。
泡盛を飲みつつわりと静かに観ていたおじさんだったが、彼もおとうが好きだったのだ。
さっきの嘉手苅3連発のときも何かそわそわしていたものなあ。
きっと私と同様、「嘉手苅林昌一周忌・追悼」という新聞広告につられて、当日券でやってきた人なのだろう。連帯感が湧くなあ。
白雲節は、大工哲弘も入って、大工、昌吉、昌永の順で1番ずつ、5番までうたう。
唄に関して言えば、声量やアピールの度合いからいって昌永は目立たないものの、三線の弾きぶりという点では大工にも決して引けを取らない流暢さがあって、なかなかよろしい。
また、昌吉が白雲節をうたえるなどとは思ってもみなかった(あとで確かめると、この唄はなんと彼のCDにも入っていたりする)ことなので、この唄は沖縄ではメジャーなのだなと改めて思うとともに、ちょっと風変わりな昌吉であっても(?)やはり民謡の大家の子供なのだということがよくわかった。
白雲節が拍手とともに終わると、大工、昌吉が退いて、太鼓担当の男と、サンバ(三板)・お囃子・踊りを一括して担当する女性が登場し、昌永が三線を早弾きして1曲うたう。
目の輝きなどはどうしても薄らいでしまっているのは否めないが、唄い、弾く姿勢などはさすがとしか言い様がない。
81にしてこれだけやれるというのは、本物なのだろう。
去年10月、大琉球まつり王国のメインイベントとして、那覇の奥武山公園でチャンプルーズが公演した(なんと、入場料タダです!)のを観たときも昌永が出てきたので、そのときはホントかよとびっくりしたものだが、こうやって見慣れてくると、親子それぞれがやっている異なるジャンルの音楽を同じ皿に乗せて食べくらべてみるというのも、案外いいのかもしれない。
昌永は本流の沽券といったものをどう昇華して舞台に上がったのかはわからないが、昌吉の考えからすれば音楽のジャンルなどは関係ないのだろう。
○喜納昌吉&チャンプルーズ
そしていよいよチャンプルーズだ。
昌吉は上下とも白のトレーナーとスラックスというシンプルな出で立ちで登場。
背中には「すべての武器を楽器に」とロゴが入っている。
最初はインストゥルメンタル。
昌吉のほかに6人の奏者が一糸乱れぬ演奏を繰り広げる。
ギター、ベース、ドラムス、キーボード、パーカッションの女性、そして電子ドラムのようなものを扱っている男もいる。
これはもうただの観客であっても一目瞭然なのだが、女性の一人を除き、演奏者はものすごく張りつめているようで、何かの合図があれば絶対に見逃さないぞというように昌吉を見つめている。
きっとバンドの中は規律正しい専制君主制がしかれているのでしょう、よくも悪くも。
演奏が終わったときには大きな歓声や拍手が沸く。
前席の女性二人連れが「すごい!」と驚嘆の声をあげていたくらい、本格的で迫力のあるものだった。
このような世界はこれまでの琉フェスにはなかったなあ。
2曲目はエイサーソング「久高まんじゅう主」のロックバージョンだ。
チャンプルーズ得意の曲とみえて、よく耳にするものだ。
昌吉が吼える。
赤・黄の衣装のパーランク隊がステージ上に踊り出て、一気に盛り上がる。
そして3曲目は、スローバラード「愛は私の胸の中」。
「愛をさがして船に乗った 道に迷って風に聞いた…」という歌で、The Boom の宮沢和史の作品だという。
人差し指を立ててその太い腕を突き上げるという、喜納昌吉特有のアクションが出始めている。いいぞいいぞ。
4曲目は、沖縄サミットを皮肉った「サミットばんざい」というもの。
「サミット オミット デメリット…」などとはしゃぎながらうたう、おちゃらけ音頭でありました。
喜納流の(?)結論がよくわからないままのような(?)MCがあって、次は「森の人よ」。
にぎやかで、迫力があってとてもいいが、女性ボーカル(喜納幸子)の、どこから出てきたのかわからないような声(失礼)には十分な納得ができない。
私が沖縄ミュージックに傾倒し始めたのは、今を去ること20数年前の昭和52年、喜納昌吉とチャンプルーズのデビューアルバムを購入したことがそもそもであるといっても過言ではない。
今思えばまさに鮮烈の本土デビューだった。
「ハイサイおじさん」や「島グヮーソング」、「東崎(あがりざち)」、「レッドおじさん」などはどれも新鮮で、受験勉強そっちのけで何度も聴いたものだった。
おかげで今でも、カラオケは「ハイサイおじさん」でがんばっている(って、関係ないでしょ)。
その頃から思うと、喜納はずいぶんと歩を進めてきたのだなと感慨が深い。
しかし、ひとつだけ言わせてもらうと、女性のボーカルがちょっと…ということなのだ。
はっきり言って聞き取れないし、りんけんバンドにおける上原知子のようないわば「気品」のようなものが乏しい。
あくまでも個人的見解なので聞き流していただきたいのだけれど。
○喜納のステージを観て感じたこと
激しい曲が終わると、「ありがとう!」そして、「りんけんやネーネーズがいればもっとありがとう!」などと喜納が叫ぶ。
本当にそうなってほしいものだが、一度退いた知名軍団や照屋林助大統領を戴いた照屋ファミリーは、来年以降再度結集できるのだろうか。
また、嘉手苅林昌亡き後の民謡界は、今後も本土の音楽シーンに大きな影響力を持ち続けることができるのだろうか。
そして最も大きな心配は、21世紀の沖縄ミュージック界を束ねていく、いわば総帥的存在は誰になるのかということだ。
これまでは、沖縄の音楽界は言うなれば二極化構造だったのだろうと分析している。
ひとつは従来から存在していた民謡中心のグループであり、あくまでも地元や伝統を意識して活動しているもので、もうひとつは、地元オンリーの世界とは一線を画して、島の伝統音楽を取り入れつつ独自の境地を開拓し、コマーシャリズムに乗ってどんどん外へと出て行こうとするグループである。
前者は、嘉手苅林昌や登川誠仁、大工哲弘のような琉球民謡協会関係者、地元の民謡酒場でがんばっている人たち、あるいは前川守賢のような路線を歩む者などであり、後者は、チャンプルーズやかつての紫などのロックグループ、新良幸人とパーシャクラブなど、ライブハウス的なところで他のジャンルと融合して登場してきたものや、BEGINのように「イカ天」からはい上がってきたものなどである。
そして、20世紀末、これらの狭間に谷間の百合のように繚乱の花を咲かせたのが、知名定男という男であったのだと思う。
言うまでもなく花とは、ネーネーズであり、りんけんバンドであり、琉球フェスティバルというお花畑に咲くたくさんのアーチストだったわけだ。
しかし、こうやって今回の琉フェスをみてみると、まず、知名がいない。
別に知名でなければならないというものではなく、その立場の人間がいない、ということだ。
そして、花々の象徴であったネーネーズはすでに解散しており、その後継者が育ってきていない。
それは多分、新生ネーネーズが担うべきなのだろうが、仮に今回彼女たちが出演してメインを張ったりなどしようものなら、力量というかネームバリューの面で弱すぎることが暴露してしまい、ひいては琉フェスの存続自体に影響を与えてしまうことになっただろう。
さらには、琉フェスの象徴、カディカルのおとうの死である。
このようにみると、どうやら新世紀の谷間の花園はちょっと期待できそうもない、というのが正直な感想だ。
然れば、2つのグループがそれぞれの道を歩むか、あるいは強烈なリーダーシップを持った者、たとえば喜納昌吉が、自己のジャンルのほうに他を強く引きつけていくか、といった二者択一の道筋しか考えられない、ということになってしまう。
個人的な意見を述べさせてもらうと、そうなってしまえば琉フェスの存在意義も薄れてしまうわけで、やはり願わくは、人気、実力ともに申し分なく、お山の大将になりたいという喜納の気持ちはよくわかるけれども、ここは知名をたてて、知名が中心となって、21世紀最初の琉フェスを開催できるようにしてほしいと願っている。
○ハイサイおじさんと唐船ドーイ
話がそれてしまった。
チャンプルーズとしてのラストの曲は、おなじみ「ハイサイおじさん」だ。
喜納が「はじめはゆっくり、あとは早く!」と一声叫んで、さあ、はじまった。
もはや観客で座っている者は一人もいない。
ステージ側から観客席に向けてオレンジ色のライトが照射され、われわれ観客は、そのあたかも日が沈む直前の夕焼けの逆光ような中で、海岸に打ち寄せる波のようにわずかな揺らめきとなって動く。
ほぼ最後列なので、会場全体がそのように見えるのだ。
ステージには、先に登場したパーランクー隊、さらには東京沖縄県人会青年部の人々などが再び登場し、踊りながら演奏する。
最高潮だ。
だんだんテンポが速くなってきて、ステージには最後に混沌の世界が訪れたところで曲は終わったが、場内騒然とする中、今度は再び喜納昌永と大工哲弘がやってきて、「唐船ドーイ」でカチャーシーとなる。
昌吉、大工はもちろんだが、何と昌永までがこのめちゃくちゃに速いテンポに乗ってガンガン早弾きし、「アイヤセンスル ユイヤナー!」と唄っているのにはほとほと感心する。
そうこうするうち、喜納は観客に向かって、ステージに上がって来いという仕草を繰り返す。
そして、一部のトランス状態に陥った人々が上がって踊り始めるや、それに聴衆が陸続としてステージに登りはじめた。
いったい何人の観客が上がっただろうか。
200人以上はいただろうか。
もうステージ上はまさに立錐の余地もないような状態になっており、われわれのいる客席からは、昌永や大工はもちろん、さっきまで最前列で吼えまくっていた昌吉すらその姿を確認することができなくなってしまった。
歌声や音楽は聞こえるので、ステージ上では妨害行為などはなく、演奏可能な状態はなんとか維持されているのだろう。
去年大琉球まつり王国で観たときも最後は客をステージに上げていたから、これはまあ、いつもの演出ということなのだろうが、それにしてもなかなかやるものだなと思う。
ふつうのミュージシャンにはちょっとまねできないかも。
○フィナーレへ
そしていよいよフィナーレ。
藤木が登場し、押されて舞台から落ちそうになりながら「はいはい!琉球フェスティバル2000 in 東京、いかがでしたでしょうか。ステージにいる皆さんは、降りるか下がるかしてくださーい!」てなことを叫んで、いったん場内の沈静化を図る。
そして、最後に出演者全員で「花」をうたおうと呼びかけ、すべての出演者が勢ぞろいするや、イントロが流れ出した。
再びオレンジ色の逆光線。
たくさんの観客の手がウージのそよぎのように右に左になびく。
「花は流れて どこどこ行くの 人も流れて どこどこ行くの…」
「泣きなさい 笑いなさい いつの日か いつの日か 花を咲かそうよ」
まったく、今やカラオケなどでも歌われてすっかり聴きなれた唄だが、どうしてこうもじんじんとくるのか。
時間は8時を回ってしまった。
喜納をはじめとして出演者でうたう「花」のリフレインはまだまだ続いているが、私は帰りの最終の新幹線に乗らなければならない。
発時刻は20:28なので、いつまでも感動に浸っているわけにもいかない。
もうそろそろ夢から覚める時間だ。
始まった時間が遅かったので、もしかしたら最後まではみられないかもしれないなと心配していたが、何とかほぼ最後まで楽しむことができた。
雨に降られ、1時間近く待たされと、いろいろ予期せぬ出来事もあったが、思った以上に楽しむことができたし、考えさせられるものもあった。
また、おとうのことにしろ、20世紀のしめくくりということにしても、自分としての区切りがつけられたような気がする。
遠くから時間とカネをかけてわざわざやってきた甲斐があったというものだ。
さあ、帰ろう。
この日比谷野音を去るに当たって、なぜか、今日ここに参加したという、自分にとって記念となるようなものが無性に欲しくなってきた。
そうだ、Tシャツを買おう。
自分らしくない考えだと思いつつ、場内にしつらえてある売店に寄って、ステージを食い入るように見つめている売り子のおねえさんの肩をつついて、鳥と花がデザインされた白いTシャツを2,500円で購入する。
「なぜか」と書いたが、記念のものが欲しくなる理由を、実は自分は気づいている。
デジャヴのような直感を恐れずに言ってしまうと、琉球フェスティバルが、20世紀の終焉とともに消滅してしまいそうな気がするから、なのだ。
もちろん、そうなってしまうことは、断じて私の意図するところではない。
来年も再来年もやってほしいのだ。
いつまでもやってほしいのだ。
ぜひ、つまらない事情で開催を断念することのないように、切に願うものである。