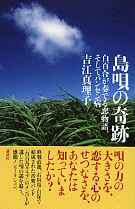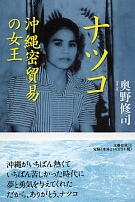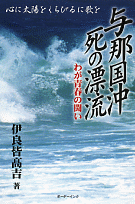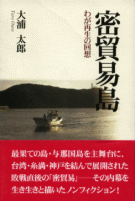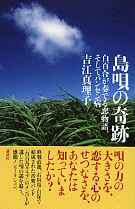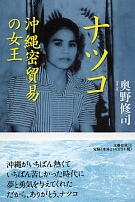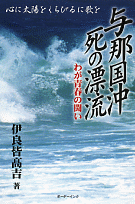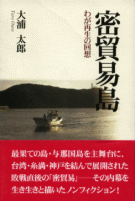|
「沖縄ストーリーズ」 砂守勝巳 著 ソニーマガジンズ
630円+税 2006年 1月20日 第1刷発行
窓越しに見える海の風景。外の強い日射しのコントラストが心の影を映しているかのようで、印象的な表紙ですね。(眺め自体は沖縄のものではないような気がするけど…)
“オキナワ”に心惹き寄せられて住み着いた6組の男と女の物語。
彼らには、世代や、移り住んだ事情についての共通性はなく、彼らがなぜこの島を第二の故郷としたのだろうか?!――というのが、この本のテーマです。ま、その答えは、読み手の感じ方によって決まるのですが。
沖縄で活躍するミュージシャン「やちむん」の奈須重樹と山里満寿代。
北谷で黒人のタトゥーアーチストと暮らすマコ。
キャンプシュワブで出会い、恋をし、親の猛反対を押し切ってアメリカーと結婚した志喜屋勝子。
中国の国営放送を聞いて育ち、台湾大学で学び、那覇の牧志で中国茶の販売をして暮らす、沖永良部島出身の川畑勝。
島々を放浪し、コザで写真を撮って暮らしていた福井出身の女性“いっちゃん”。
青年時代、大阪での3P体験がトラウマとなり、沖縄でゲイとなって生活していた“たぼ美”――。
著者は、沖縄で生まれ、幼い頃に父は一人故郷のフィリピンへと戻り、母の実家のある奄美大島で長く暮らしてきたという生い立ちの写真家です。
そんな著者が、自分の出自にも思いを馳せながらやさしいまなざしで淡々と綴る文章には、じっとしていてさえ汗がにじんでくるような今夏の読書環境を忘れさせてくれるくらいの強い磁力、というか、説得力を感じました。
単なる移住モノというより、人間のドキュメントという印象。人々の人生をファインダー越しに切り取っていくような迫力があります。
「オキナワ紀聞」(1988年、双葉社刊)を加筆・修正し、さらに新たに2005年現在の彼らの様子を付記したものとなっています。
(2006. 8. 4 読)

|
 |
「オキナワ・海を渡った米兵花嫁たち」 澤岻悦子 著 高文研
1,600円+税 2000年 6月15日 第1刷発行
一般的に言って、人間は大人になると“結婚”し、夫婦の絆を人生のひとつの生きがいとしながら、年老いて死んでゆく…。多くの人間がたどる普通の人生と言ってもいいと思いますが、これが国際結婚となれば、まだ簡単に“普通”としてひとくくりにするまでには至っていないのではないでしょうか。
そして、沖縄にあっては、その歴史の特殊性から、米兵と結婚して海を渡って行った花嫁が多くいると言います。
その花嫁たちが異国の地でどのような状況で、また、どのような境遇や心境で日々を送ってきたのか――ということについて、ある日ナゼかトートツに知りたくなってしまったので、ネット通販なら1,500円以上は送料無料だし(笑)、さっそくこの本を入手して読んでみることにしました。
当然ながら、米兵花嫁たちにはそれぞれの人生があって、多種多様な道のりを歩んでいますが、言葉のカベや出産・子育ての苦労、そして故郷への深い郷愁の念などについて彼女たちが語る様々なエピソードは、その一言一句に妙に重々しいものがあります。
しかし、それでいてその多くが、今となっては幸せであると結論付けられていることには、大きく感動するのを禁じ得ません。
あれほどの苦労があったというのに、どうして今はそのように満足げに語ることができるのでしょう。それは一種の諦観? それとも、すべてを自分の幸せに結び付けてしまうウチナーンチュの幅の広い肝心(チムグクル)のなせる業なのか?!
著者の意図は、沖縄ではめずらしくないこのような結婚についての実態を明らかにするため、極端に悲惨な事例はできるだけ避け、当事者の女性達のたんたんとした生き様を描くことにあったようで、この本はその意図がうまく結実していたなぁ、というのが読後感。
とりわけ第2章の「国際結婚にみる人生模様」は、多くの具体事例がいい語り口で掲載されていて、なかなか圧巻でした。
(2006. 2.25 読)

|
 |
「だれも沖縄を知らない ―27の島の物語」 森口 豁 著 筑摩書房
1,900円+税 2005年 7月15日 第1刷発行
沖縄に深い造詣をもつフリージャーナリスト森口豁(かつ)による渾身のルポルタージュです。
著者は都合3回、集中的に沖縄の島々を歩いたといいます。
1回目は1960年前後に琉球新報の記者として、2回目は沖縄が日本に復帰する1972年前後に日本テレビの特派員として、そして3回目が、2000年代初頭のこのたび、今度はフリーのライターとして――。
そんなことをベースに、過去40年にわたって著者が見てきた27の島々の“今”を描いた――というのがこの本。
かつて取材した島人を20数年ぶりに訪れるなどして、日本という“大国”の影響を受けながら変わっていく離島の様子を、ジャーナリストらしい鋭い観察眼で報告しています。
多くの体験を元にかつての沖縄と比較する目を持っている、という著者の優位性がいかんなく発揮されていて、また、それぞれの島当たりたっぷり10ページ余りとなっているレポートは読み応え十分。
若い人が島を離れて行き、かつて盛んだった芸能が衰退していくなどの姿が書かれていて、読んでいて、日没を前にしたきれいな夕焼けを眺めているひとときのような心境になりました。
蛇足ですが、なんと、筆者は1966年のイザイホーを取材しているんですね〜! びっくり。(12年に1度行われる久高島の秘祭イザイホーは、1978年を最後に、その後は後継者不足等から行われていないのです。)
また、筆致についても、元記者らしく、客観的な事実を連ねて問題点を浮き彫りにしていくという進め方を採っていて、なかなかヨイです。
ただ、少し気になったのは、新聞記者の取材にままあるような、結論を決めつけてかかる類いの表現が一部に見受けられたこと。人それぞれがいろいろなことを考えているのに、そのうちの一人が言っていること、主張していることが100パーセント正義であるかのような表現は、読者にとって不必要な誤解を招く種となりますので、要注意ですかね。
ひとつのコミュニティとして完成している小さな離島に一人の記者が現れる。その記者の取材姿勢によって島人が動揺し、コミュニティがぎくしゃくし始める――。取材の際にそんなことはなかったのかとやや心配になってしまうような部分もあったりしました。
さて、ところで、この表題。どーゆー意味やねん?
センセーショナルな響きがあっていいのですが、まさか、“観光で何度か沖縄を訪れた程度では、沖縄のことなんてだ〜れもワカルはずないんだもんね。少なくとも40年は見つめなきゃだめなんだもんね、ケッ!” …ということではないよね。(笑) ――あ、読み込みが浅くて、どーもスンマヘン。
(2005.12.11 読)

|
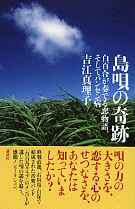 |
「島唄の奇跡 白百合が奏でる恋物語、そしてハンセン病」 吉江真理子 著
講談社 1,700円+税 2005年 4月14日 第1刷発行
芸能の盛んな石垣島の白保で50数年前に結成されたという音楽バンド「白百合クラブ」が、全国展開してもてはやされたのは、2003年頃からだったでしょうか。
この「白百合クラブ」、新良幸人や大島保克の父たちがメンバーになっていることなどから、私も一瞬興味を抱いたのですが、すでにメンバーの大半が70代後半になっているということもあって、歴史的意義はあっても音楽的にはまぁ、それなりのものなのかなと理解してしまいました。
で、この本。したがって、それなりの期待感を持って読み始めたのですが…。これは驚くべき深みをもった感動ノンフィクションでアリマシタ!
主人公は、白百合クラブ結成当時の主要メンバーである多宇郊(たう こう)という人物。彼はクラブの天才的音楽プレイヤーとして活躍し、生涯独身のまま1993年、他界します。彼はメンバーだった頃、隣村の大浜で結成された「オリオンクラブ」のマドンナと相思相愛となり、一時同居したものの、しばらくして結婚せずに別れてしまいます。
成就しなかった恋愛などはどこにでもありますが、この二人がなぜ別れなければならなかったのかを著者が追求していくにつれ、その先には、相手を想うからこそ別れなければならない壮絶なドラマがあったのでした。
当時は、ハンセン病が遺伝病であるとの蒙昧な理解のもと、感染者は隔離され、身元を隠しながら親族とも離れ離れの生活をしなければならなかったそうです。そして人々は、身内に感染者がいることを隠し通さなければなりませんでした。
感染者は、なにかの自由を失うなどという生易しいものでなく、一度の人生そのもの奪い取られていたと言っても過言ではない日々を送っていた、とのことです。
著者が足かけ11年をかけて取材し、執筆したという物語の経緯はみなさんで読んでいただくこととして、私が思ったのは、①ノンフィクションってサイコーだな〜! デキのよいノンフィクションは映画なんかよりもずっと感動的だよな〜、ということ、②ヨシエさんの文体は女性特有のウエットな感じがあって、このようなテーマを扱うことによってそれがいいほうに作用しているなということ、そして、③愛は、一時のものではなく、永遠のものこそが美しいのだなということ、などでした。
ちょっと早いけど、今年の輝け!マイ・ノンフィクション大賞は、この作品で決まりですね。
(2005.10.10 読)

|
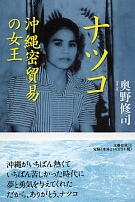 |
「ナツコ 沖縄密貿易の女王」 奥野修司 著 文藝春秋社
2,143円+税 2005年 4月10日 第1刷発行
「密貿易島」、「与那国沖死の漂流」に続いての与那国島密貿易関連本です。
戦後の密貿易について、このところいろいろと出版が続いているのも、当時から50年以上が経過して、いわば時効もいいトコロになっているということ、そしてまた、関係者が生存しているうちにドキュメントしておかねばということが、ダブルで影響しているのだろうと推測するのですが、いかがでしょうか。
当書は、コシマキから引用すると、
『 彼らが懐かしんで「ケーキ(景気)時代」と呼ぶその時代は、1946(昭和21)年から51年までの6年間ほどだが、沖縄中がヒステリー状態になったように、子どもから老人までこぞって密貿易にかかわるという異様な時代であった。混乱、騒擾、欺瞞、陰謀に明け暮れながら、しかし冒険の時代でもあった。誰にも拘束されないかわりに、才覚と度胸ひとつで大金をつかむことができた時代でもあった。彼らが「女親分」という夏子は、しかし彼らの上に君臨したわけではなかった。「貧しかったが、夢があった」時代の、いわば象徴的な存在だったという。』
という内容の本。
著者はこの時代を「あれは「ウチナー世」ではなかったか」と言います。
沖縄は、「唐世」があり、琉球処分以降の「ヤマト世」があり、敗戦後の「アメリカ世」から復帰後の「ヤマト世」へと移り変わりますが、あの時代こそ沖縄が、誰の支配も受けず、誰の手も借りず、占領軍に対抗して自分たちの持てるエネルギーを存分に発揮できた「ウチナー世」だったのではなかったかと――。
そんな中で金字塔のように輝いていたのが夏子だったというわけ。
カバーにあるとおりの彫りの深いチャーミングな表情に、背丈わずか150センチほどの彼女が、巨漢の荒くれ男たちを従え、手腕と度胸と情報収集力によって密貿易の頭目として活躍したというから、なんとも痛快ではありませんか。
夏子は、与那国だけでなく石垣島、台湾、本島の糸満や本部などに居を移しながら、神戸や和歌山などとのルートをつくって、多量の物資を動かしていたとのこと。なかなかスケールも大きかったようです。
夏子がこれほどの大立者だったにもかかわらず、著者はこの物語を上梓するのに12年もかかったそうです。沖縄県公文書館に琉球政府以前の資料がほとんどなかったり、証言者が若くても70代後半で記憶が薄れていたりと、苦難の連続だったようです。
しかし、歴史は記録されてこそ存在するわけで、記録されなかったら夏子は沖縄の歴史から抹殺されてしまったことでしょう。そういうことからも、著者の努力は大きな意味があったと思いマスね。
いちばん熱かった時代の沖縄の一端を知ることができたし、なにか充実したすがすがしい読後感が得られたし、読んでよかったなと思える1冊でした。
それにしても、蜜貿易関係の連続出版、これ、それぞれの著述が互いに連関しあっていて、続けて読んだらかなかな面白かった。多面的に考察できて興味深かったですよ、えぇ。
(2005. 9.25 読)

|
 |
「琉球弧からの飛翔」 山口栄鉄 著 榕樹書林 1,800円+税
2001年11月20日 第1刷発行
著者の山口栄鉄という人、かつて印象深く読ませていただいた「琉球と琉球の人々
琉球王国訪問記」(沖縄タイムス社刊)の共訳者の一人で、なかなか文芸調のいい訳し方をしている方でした。
たしか、長い間アメリカの有名大学で教鞭をとり、最近本島の大学に戻ってきていたはずとの記憶があったので、この本の表題を見て、専門分野からのアプローチによりなにか「沖縄」や「琉球」の根深いところから鋭い論評でもしているのだろうと思って、購入しました。
しかし、いざ読んでみると、私の推測は見事に覆されてしまいました。内容は、著者自身の自伝的エッセーなのでした。
でも、私にとってはむしろ、こういうものこそおもしろい。己の視点から眺めた「外の世界」を表現しているわけで、その時代の諸相や、一個人としての素朴な感動といったものが、端的に表現されていて、わかりやすいうえにある意味新鮮な一面もあります。
第1章の「那覇炎上〜対馬丸を追うように」では、戦争によって失われた様々なことを、学者としての衣を脱ぎ捨て、その無念さなどを感傷的なまでに表現しています。(著者は1938年那覇生まれ)
また、第6章「「エール」学派との出会い」や第7章「「英文日本学」構想」では、専門分野における課題や独自の構想について熱く語る場面もありました。
この人の半生は、こういうことで感動し、悩み、決断をしたのだなということがわかり、一読者としては、自分の才能や能力が及ばない世界において、あたかも自分がそこを冒険しているような錯覚に陥ります。
前出のイラミナセンセイの「与那国沖 死の漂流」も然りですが、ありえない創作話よりも、多少なりとも知っている人のこういう自伝的エッセーを、もっともっと読みたいと思うこの頃のワタシなのでした。
あっ! そうそう、この本の第14章には、前出「密貿易島」の著者・大浦太郎氏が登場します。二人の出会いもまた、なかなか数奇なものです。こういう連鎖が味わえるのも、読書の楽しみですなぁ。…えっと、その出会いがどんなものだったかは、読まれる方のお楽しみにとっておきましょうね。
(2005. 9.18 読)

|
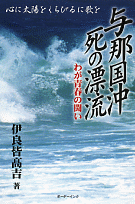 |
「与那国沖 死の漂流 わが青春の戦い」 伊良皆高吉 著 ボーダーインク
1,500円+税 2004年 3月10日 第1刷発行
私が著者に初めてお目にかかったのは、仕事の場。全国都道府県議会議長会という組織があって、その総会に出席するために、山形県議会の議長に同行して上京したときでした。
出席者名簿の「山形県」の欄の次に見るのは、沖縄マニアとしてはトーゼン「沖縄県」のところ。ほほ〜、議長は伊良皆高吉というのね。これ、「イラミナ」って読むんだよナ、きっと。読谷村にもこういう地名があったからナ…なんて。なんと著者は、平成15年当時、沖縄県議会の議長だったのです。
そしてまたこの人、著名な沖縄・八重山民謡の師範でもあったりすることがわかり、唄って踊れる県議会議長である彼の生き様というものに私は強い興味を覚え、いつか機会があれば身分の違いもわきまえず話かけてみようかとも思っていたのでした。(ウチナーンチュならきっと許してくれるはず、との甘えあり)
しかしその後、伊良皆議長は、平成16年の参議院議員選挙(喜納昌吉が比例民主で当選した、あの選挙)に県議の職をなげうって出馬し、落選。ダメな時はとことんダメなもののようで、この選挙にからんだ選挙違反が発覚し、公民権停止の憂き目をみたのでした。
その人の、若い頃から壮年時までの活躍ぶりが本になったわけで、私としても他人事とは思えず興味津々。ただちに入手しようと思っていたのですが、全国販売はされなかったようで、あちこち探してこの6月、沖縄旅の際にパレット久茂地の書店でようやく手に入れたのでした。
イラミナ先生が二十歳の中学教員だった頃、生徒たちの待つ与那国島へと石垣島から渡る際、乗った船が転覆。同僚をはじめとして多くの犠牲者が出た中で九死に一生を得たところから物語は始まります。そしてこのことが、一代記の伏線としてストーリーの底流を形成しています。
読んでみるとイラミナ氏は、与那国の教員を振り出しに、その後上京して法政大学に籍を置いて苦学。明星食品勤務を経て、沖縄に戻り独立。即席ラーメンの販売やいくつかの農林水産物の加工・販売業などをしていたようです。
しかし、残念ながらこの本、もともとは1980年に発刊されたものを、24年後の2004年に、完全復刻したものとして発売されたようで(県議会議長就任に合わせて一儲けを狙ったか、ボーダーインク?!)、1980年以降の人生遍歴や議長となるまでの紆余曲折についてはすべて欠落しており、これを読んだだけではわかりません。
私としてはむしろ直近のそのあたりを知りたかったので、読後感としてはやや喰い足りないようなところがありました。ぜひ、天国から地獄(スマヌ)、波乱万丈の続刊を書いてほしいと思いマス。
さて、郵政解散に基づく今回の衆院選、本日8月30日公示。9月11日はどういう結果になるのでしょうねぇ…。
(2005. 8.29 読)

|
 |
「沖縄ヤクザ50年戦争」 洋泉社MOOK 1,400円+税
2004年 7月 7日 発行
沖縄のいろんなことを知りたい一心で、おれもとうとうこのような本まで手にすることになってしまいました。(笑)
沖縄の地ではかつて、暴力団が、血で血を洗う戦争さながらの抗争を繰り広げていた――ということについて、その当時新聞紙上を大いに賑わせていたことをぼんやりと覚えています。沖縄が本土復帰したのを機に、本土から大手の広域暴力団が陸続として進出する動きがあり、地元組織がそれをくい止めるために見境なく戦っている――との総括のしかただったように思いますが、この本を読んで、どうやらそれは抗争の段階でいうとかなり後半のほうの話のようでアッタ。
そもそも沖縄のヤクザというのは、本土のそれとは成り立ちが違い、住民の必要物資を占領軍の倉庫などからくすねてくるという戦後の“戦果アギャー”や、沖縄で発達した“ティー”、つまり空手の使い手たちの集団から生まれたものであるとのこと。主としてコザを中心とした中部は戦果アギャーが、那覇は空手組織が、それぞれベースとなっていて、このような成り立ちの違いが本島内部における対立軸となっていたようです。
抗争の歴史や大物ヤクザの人物伝、さらには現幹部へのインタビューや映像で見る沖縄ヤクザ史、年表などなど、沖縄を愛しかつ任侠道に興味をお持ちの貴兄には(そんな人っているのか?!)ぴったりの1冊です。
私としても、現在の沖縄空手道の隆盛や、闘牛大会に集う血の気の多そうなウチナーイキガなどにつながっていく命脈というのはこのあたりにあるのかなと考えながら、思いのほか楽しく読ませてもらいました。
(2005. 8. 5 読)

|
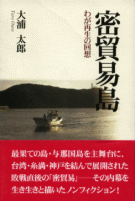 |
「密貿易島 −わが再生の回想−」 大浦太郎 著 沖縄タイムス社
1,800円+税 2002年 6月 7日 第1刷発行
与那国島は、戦後の混乱期、密貿易で大いに栄えた時期があった――との話を何度か聞いていました。しかし、その詳しいことについてはなかなか知りうるところにならず、手頃な本がないかなと思っていたところ、ネットでつらつら検索してみると、おお、いい本があるではないか!
『最果ての島・与那国島を主舞台に、台湾・糸満・神戸を結んで展開された敗戦直後の「密貿易」――その内幕を生き生きと描いたノンフィクション!』
との扇動的なコシマキのキャッチが、なんともそそりますね〜。
密貿易に中心的人物の一人として関わった当事者の回顧録は、読んでいてとてもスリリングでした。荷揚げ先の神戸では同僚が官憲によって拘束され、著者も追手から逃れるため、変装しながら投宿先を転々とするところなどは圧巻。
ほかにも、船で物資を運搬中に台風に翻弄されて食料も燃料も尽きたところで久高島に流れ着いたり、石垣島では敵対する勢力の船長一味からあわや袋叩きにされそうになったりと、山場は数多いです。
著者はそんな、小説にでもなりそうな波乱万丈の人生を歩んできた人なのに、晩年には自分の経営するプロパンガス事業が評価されて黄綬褒章なんかもらったりするのですから、日本という国はおもしろい国だと思うねぇ…。
与那国島が殷賑を極めたのは、終戦の1945年から1950年まで。この年の5月、久部良(くぶら)集落の密貿易現場を急襲した米CIC指揮官オール大尉の一隊が約20日間で、密貿易関係者、物資、船舶、組織を根こそぎ壊滅させたことで終焉した――ということです。
密貿易の話のほかにも、与那国生まれの著者が語る古きよき与那国の話も貴重。また、与那国を語る際にあの「与那国の歴史」の著者としてよく登場する池間栄三医師も著者の密貿易時代の仲間だったようで、折々に登場します。
自著による一代記なので、不都合な部分はおそらく大幅にカットされているのでしょうが、ここまであからさまに書いてくれれば、それも許せてしまいます。最後に近づいてくるにしたがってどんどん盛り上がりました!
(2005. 6. 5 読)

|
|

|
「八重山の台湾人」 松田良孝 著 南山舎やいま文庫 1,800円+税
2004年 7月12日 第1刷発行
石垣島の名蔵地区には台湾からの移民が多く住んでいると聞いており、このあたりについてできれば少し詳しく知りたいと思い、読んでみました。今の世の中、知りたいことについてはだいたい本が出ているのですよね。これって、案外スゴイこと。
著者については、参加しているとあるメーリングリストによく投稿なさっていたので、親近感を持ちながら読むことができました。八重山毎日新聞の現役記者の方です。
八重山地方で生活する台湾人たちが、どのような歩みを経て現在に至ったかを、いかにも新聞記者らしい筆致で記録しています。戦前、なぜ多くの台湾人が八重山に移り住んできたのか、そして、彼らがどんなに苦労を重ねて日本人としての国籍を取得したのかなどを知り、彼らに対する認識を新たにしたところ。
わかりうる先祖は数世代先からずっと現在の地に土着している――という我が身に照らしてみると、まったく違った人生や生活が、そこにはありました。人種や民族、国籍といったことも含めて、「自分とは何か!?」などと考えることなど、少なくとも30代までは、おれの場合なかったものなぁ…。
ところで、松田さんに限らず記者の書く文章というのは、限られた字数の中、極めて的確な表現で事実を中心にたたみかけてくるところがある、と思う。それは、「合理的」という印象を受ける反面、文章内での遊びが少ないため、読み解くのに多少頭を早く回転させなければならないときがあるのですね。
おれの場合、実はコレが、強烈な眠気を惹起したりするのね。てなことで、ゆったいくわったいと、間に何回かのうたた寝を織りこみながら、よく言えば「オレ流」にて楽しませていただきました。
スミマセヌ…批判めいたこと言ってますけど、どうしてどうして、1,800円の価値は十分にあったと思いますよ。
(2005. 5.29 読)

|
 |
「八重山人の肖像」 写真・今村光男、文・石盛こずえ 南山舎
2,800円+税 2004年 5月15日 第1刷発行
南山舎が発行している月刊「情報やいま」の1994年3月号から2003年12月号に掲載された表題と同名のコラムを加筆修正し、再構成した1冊なのだそう。
八重山にルーツをもつ、なんと105人(組)もの人たちについて、写真入り記事で構成されています。私はそれらの名前のうち、数えてみるとわずか22人(組)しか知らなかったのです。しかし、それぞれの文章を読んでいくと、ははぁ、かつて本を読んだりネットで見たりして知った八重山のあの人って、この人だったんだなーという御仁が続出。そんなことで、これはけっこうおもしろかったし、ためになりました。
トップバッターは星美里。そう、夏川りみちゃんですよ。1994年当時の夏川りみが、まだあどけなさが漂う1枚の写真とともに掲載されていました。
このほか著名なところでは、平田大一、BEGIN、安里勇、白百合クラブ、日出克、鳩間可奈子、池間苗、具志堅用高、新良幸人、池上永一、ミヤギマモル、宮良忍、大工哲弘などなど。…おい、これってほとんどミュージシャン系ではないかい? えへへ…、“著名”っていうのは、おれの場合そういうことなんですね、勘弁勘弁。各界でもっと有名な方々も掲載されていますからご安心を。
読み進めていくと、明治生まれで掲載後すでに没している方も多く、月日だけは無常に過ぎていくんだなぁ…なんて、おれも思うような歳になってシマッタ…。写真に写った年配の方たちの表情や姿勢はいずれも毅然としており、そのことひとつをとってみても、ひとつの「八重山人像」が浮かび上がってくるような気がします。
ところで、私の本を買うときの基準のひとつに「価格」がありますが、基本的には2000円までなら、興味の赴くままに即買いすることにしています。てなことで今回、この本を買うにあたって逡巡すること2回。3回目にして清水の舞台から飛び降りるつもりで(大げさ!)、なかばヤケクソで(笑)買うことにしました。でもま、この本を読んだことで、なんかこう、ヤイマピトゥのみなさんに少〜しだけ近づくことができたかな〜なんて思えたりして、読んでみてよかったかも知れないなと感じているところ。
1人当たりのテキストがわずか1ページ分と少ないのがチト残念ですが、多少八重山の事情なりこれまでの歴史などを知っていれば、書かれている人が具体的なだけに、絶対におもしろく読めると思います。八重山の事情にあまり詳しくないんだよねという人は、別の本を読んで基礎知識を身につけてから読みましょうね。
(2005. 1.22 読)

|
 |
「美麗島まで」 与那原恵 著 文藝春秋社 1,600円+税
2002年11月30日 第1刷発行
表紙は、著者・与那原恵の実の母親里々(りり)。著者がまだ小学6年生のときにこの母親は亡くなったのですが、その母親から聞いていた話と、幸いにも「唯一の財産」として残っていたアルバムを頼りに、著者は里々の一生と、その父・南風原朝保の生涯をたどります。
朝保は、東京に進学して医師になる勉強をし、その後ロシアのニコリスク(現ウリースク。ウラジオストクの北)で知人の病院を手伝った後、台湾の台北で開業医を始めた―という波乱万丈の人生を送った男。
その子の里々は、朝保の再婚などもあって、親元を離れがちな少女時代を送り、首里生まれの与那原良規と結婚し、東京で結婚生活をしたといいます。
著者は残された写真をもとに、現地に赴いて様々な人たちから話を聞きながら、自分のルーツとなった人々の人生を綴っていきます。
人生ある程度まで歩を進めると、「自分とは何か」という問いはみんな持つものだと思います。しかし、現況はなかなか厳しく、過去を掘り下げることはだんだん難しくなってきているのではないでしょうか。
我が家にあっても、子供たちと常日頃家族や「家」について話す機会などそう多くなく、きっと詳しいことなど受け継がれることなくどんどん忘却のかなたへと流されていってしまうのでしょう。子は親の話を聞かず、親はそんな子をあきらめの境地で眺め、社会はそれすらもとがめない構造になっていく…。
そんなことを嘆きつつ、人と人との織りなす奇跡のようなつながりがあった彼らの時代をとてもうらやましく思いながら、読ませてもらいました。
文章の中には当時の台北とそこに住む沖縄人の様子、石垣島に移住してきた台湾人の生活、密貿易で栄えた与那国島の様子などが登場し、興味深いその時代がどんなものであったかを知ることができます。
また、家族の周囲にいた数々の著名人も登場します。古波蔵保好、山之口貘、比嘉春潮、藤田嗣治、火野葦平などなど。
美麗島とは台湾の別称ですが、著者にとっては、苦難の時代に生きた母・里々の人生そのものが「美麗」に映った――ということなのでしょう。
圧巻の家族史。オススメの1冊です。
(2005. 1. 9 読)

|
 |
「楽園をつくった男
〜沖縄・由布島に生きて」 森本和子 著
(有)アースメディア 1,500円+税
2002年10月15日 改定版第1刷発行
由布(ゆぶ)島って、ご存知ですか? 西表島の東海岸にあって、500メートルほどの干潟を水牛車で渡っていくという小さな島なのですが、八重山の風情の代表として必ずと言っていいほど観光パンフレットに登場するこの島には、ある人物の、現在に至るまでの気の遠くなるような努力があった――ということが、しみじみわかる著作です。
由布島は、その小さな島がそっくり動・植物の楽園のようになっているのですが、この本は、この楽園をつくった男・西表正治さんの苦闘の物語です。
太平洋戦争が終わり、台湾から家族とともに故郷の竹富島に帰ってきた西表さんを待っていたのは、10倍に膨らんでしまった島の人口と、それに伴う生活の糧をどうやって得るか、ということでした。そのため家族や仲間たちとともに新天地の無人島・由布島に移住し、開拓をし、新生活を始めたのです。
その後、台風によって、海抜わずか1.5メートルの島すべてが海水に洗われてしまうという、山間部に住んでいる自分などには想像を絶する被害があり、それを契機に島から多くの中間たちが去って行きましたが、彼とその家族は誰も見向きもしなくなったこの島に1日に1本ずつココヤシを植えて、現在の由布島の原型をつくっていったというのです。
著者は、永年児童文学に携わっている方であり、文章は至って平易。あっという間に読めます(1500円が惜しい?!)。
西表さんのように、そんなに有名ではないけど一生懸命に生きた人の人生にスポットを当てて、別に大袈裟でもなく、ひけらかすでもなく、淡々とその人の生涯を描いていく――という作品群にはなかなか好感が持てるし、心の底から感動できるものですよね。
由布島に渡ったことのある中高生にはゼッタイ読ませてみるべきでしょう。感銘を受けること間違いなしです。
(2004. 1.12 読)

|
 |
「沖縄ソウル」 石川真生 著
太田出版
2,000円+税 2002年10月 8日 第1刷発行
沖縄にこだわり、沖縄人の「人間ドラマ」を撮り続けている写真家・石川真生の自叙伝的エッセー。
彼女は1953年、大宜味村生まれ。アメリカ統治下時代に青春期を迎え、二十歳前には沖縄が本土復帰するという激動期を強く、そして闊達に生き抜いています。49歳で、二度目のがん手術を受けて人工肛門を付けることになってしまった彼女。5年以内の生存率は6割という診断を受けても、抗がん剤治療を断って、今も取材に駆け回り、新たな恋を求めています。すごいですね〜。まえがきでは『体はババーでも(認めましょ)やる気と生きざまは20歳の若者にも負けない自信があるってこと。私は死ぬまでバリバリ青春するし、写真を撮り続けたいといつも思っている』とアネゴ的に発言してオリマス。
内容は、これまで彼女が撮ってきた作品をアンソロジー的に語りながら、合わせて親との確執や恋、セックス、自分の結婚歴、早婚の娘のことなどについて、自分のいつもの語り口なのでしょう、“女”の口語体で書き綴られています。
70年代後半、米兵と同棲しながら金武の外人バーで働いていた頃のこと。80年代、那覇の港町で自ら始めた飲み屋「あーまん」(やどかりのウチナーグチ)に集まる海の男たちとのこと。90年代前半、地元「沖縄芝居」の喜劇の女王・仲田幸子率いる『劇団でいご座』を追いかけていた頃のことなど、いずれも読んでいて、また、モノクロ一点張りの写真を見て、その「時代」を痛切に感じることができます。
一番のインパクトはやはり、最後の写真、人工肛門をつけたおなかを“サラシサラシ”して快活に笑顔を見せている著者の写真でしょう。オンナは強いんだな〜と、思わずたじろいでしまいます。また、それと並んで、懸命にリハビリ中のやせ細った老婆の写真は彼女の母。幾度もの確執があって、ここにきてようやく理解し合えた二人――というエピローグはなかなか感動しますネ。
というワケで、圧倒的な内容のため、ついついいつもの就寝時間を大きく越えて読みふけってしまいましたよ。Ummm…充実の1冊ですかね。
(2004. 1. 5 読)

|
 |
「インタビュー 東京の沖縄人」 新垣 譲 著
ボーダーインク
1,600円+税 2003年 3月10日 第1刷発行
この本って、東京で、しかもその第一線で活躍している、成功者としての沖縄人をインタビューしているのかと思って、最初に見たときは買わなかったのね。でもって、再度目撃したときによ〜く眺めてみると、どうやらそうではないらしい。東京でごくフツーに暮らしている若い年代のウチナーンチュたちを対象としたものだったのですね。それじゃ、買お、買お…。
東京生まれの沖縄二世のフリーライターである著者が、ボーダーインクの発行するシマーコラムマガジン「woder」に掲載するため、1993年から2000年までの間、東京に住むウチナーンチュがどのような思いで生活しているのかをインタビューしたそうな。
それだけでも興味深いのですが、今度は2001年から2002年にかけて、それらの人たちのその後を追跡して再度インタビューを試み、過去と現在の様子を2つ並べてルポってみた――というのが、この本の真骨頂なのですね。
読んでみて、とてもよかったですよ。本書に登場する16人は、はじめにインタビューを受けた当時の年齢で20代の人が多く、それぞれがさまざまな思惑で上京し、精一杯生きている様子が伝わってきます。いろんな人生があるんだな〜というのが素朴な印象。
東京でずっと生活し続ける人もいれば、沖縄に戻って新たなスタートをきる人もいますが、それぞれがふるさと沖縄を愛し、懐かしんでいる様子がいとおしく思えたりする場面もありました。
別にためになったりはしないけど、心のビタミン剤として読むのにふさわしい一冊だと思います。宮国優子さん、病気に負けないでヨ。さいが族・「読めば宮古」のブレイク、オメデトウ。「書けば宮古」も買ったよっ。
(2003.11. 2 読)

|
 |
「子乞い 沖縄 孤島の歳月」 森口 豁 著
凱風社
1,800円+税 2000年1月20日 第1刷発行
発売年次こそ新しいですが、実はこの本、1985年にマルジュ社というところから発刊された「子乞い
八重山・鳩間島生活誌」を補筆・修正して、一部書下ろしを加えたものです。したがって、ここに書かれている世界は基本的にかなり前のことで、当時小学生のいなくなってしまった鳩間島にピカピカの1年生としてやってきた通事勇生(とうじはやお)君(本の表紙に載っている男の子)は、1999年現在、23歳になっています。
当時は、水も電気もままならないような生活があったようで、かつては何百人といた島の人口は41人。いよいよもって島から学校がなくなろうとしている時でした。そしてそこには、島の存亡を賭して学校が廃校になることをくい止めようとした人々がいたのですね。
今となっては、鳩間島の人々が公的な里子の受け入れをすることによって島が生き返ったことは広く知られるところとなっていますが、当時は手探りの状態だったでしょうし、そのうえ明日明日小学生が一人もいなくなってしまうという苛酷な状況の中で、皆さんはよくがんばったものです。
鳩間島に行ったとき、この学校のグランドで昼寝をしていて、先生に注意されてしまったことがあります。校門には右と左に「鳩間小学校」「鳩間中学校」と記されていました。中学校も1984年に復活したのですね〜。
島の里子受け入れの中心人物として登場する通事力(つとむ)さんは、当時は60歳前後。中学校の開校式でカチャーシーを踊っている若々しい力さんの写真も載っています。実はこの人、鳩間島の簡易郵便局長で、「ペンション・マイトウゼ」を経営する健次さん(羽根田治著の「パイヌカジ」では「建次」と表記されている)のお父さんなんですね。私もマイトウゼに泊ったときにお会いしましたが、80近くとは思えない、かくしゃくとした方でした。当時健次さんはまだ、神奈川県で働いていたようです。
「パイヌカジ」では、島全体が共同体として仲良くやっているような、いわば「いいところ」を中心に紹介しているのに対して、「子乞い」のほうはさすがに新聞記者出身のジャーナリストが手がけたものとあって、平和一辺倒では進みません。島の実力者と若手との対立、役職者への住民の突き上げ、新参者と土着の人間との齟齬などについても、名前を挙げて冷徹に記述しています。好き嫌いもあるでしょうが、私としては、書き方が、米ホワイトハウス内で起こった事件、はたまた日本政界を揺るがすスキャンダル等々を取り扱っているような趣きがあり、この文体で鳩間島を取り上げている…っていうのがなんかとてもオモシロオカシくって、楽しみながら読みました。
本論からずれますが、この本を通してわかったことがいくつかあります。民宿「まるだい」は「大工」という名字のおばあが経営していて(当時)、大工哲弘はその親戚筋に当たること、また、宮古の唄者仲宗根豊は、このおばあの娘婿に当たること、「青空荘」の主の鳩間昭一は案外ケチであること(?!)…などです。ちなみに、鳩間可奈子は、青空荘と関係があるらしいです。
ああ…また行きたくなってきたなあ、鳩間島…。
でも、あんなにステキに見える鳩間島も、当たり前だけど、いろいろあるんだよね。ヨカヨカとばかり言っているのではなく、そんな歴史があってこそ、あの集落が息づいているのだということを十分認識しておく必要があるよなあ…。
(2002. 2. 3 読)

|
 |
「沖縄シャウト」 砂守勝巳 著
講談社文庫 571円+税
2000年2月15日 第1刷発行
なかなか刺激的な表紙なので、沖縄とは名がついているものの、ドラッグだとかセックスだとか、そういったものを扱ったものなのかなと思って、あまり期待せずに購入したのですが、読んでみてびっくり! 著者は沖縄の母と、米軍の仕事で沖縄にきていたフィリピン人の父との間に生まれたハーフで、父との再会を夢見て、ボクサーになればフィリピンに行って試合ができる日が来るだろうと考え、なんとホントにプロボクサーになってしまった人なのです。
結局ボクサーとしては大成しなかったようですが、その後写真家となり、さらにはこうやって文筆活動などをやっている…という文武両道的、志さえあればなんだってできるんだかんねっ!的なヒトなのですね。うーん、すばらしい…。
そしてついに離れ離れになって30年後、彼は父親と劇的な再会を果たします。人間というものは一人一人が過去という十字架を背負って、それぞれ懸命に生きているのだなということ、さらには、戦争、鉄の暴風、征服、統治、移住、混乱、再編、復興などなど、わずかの期間に起こった想像を絶するような世の中の変化が、一人一人の人生に実に様々な、そして数奇な人生を与えてきたのだなということが、目の前の現実のケースとして実感できるものとなっています。
何といってもこれは、人から聞いたものをまとめたのではなく、著者本人が実感して、自分の言葉で書いているのですから迫力がありますよね。
そのほかにもいろいろあります。第一章「沖縄の混血ロックンローラー」では、伝説のハードロックグループ「紫」で活躍していた、これもまたフィリピン人を父親に持つ城間俊雄・正男兄弟を取り上げ、彼らの生きてきた道をたどりながら、沖縄におけるいわゆるオキナワン・ロックンロールの繁栄から現在にいたるまでを紹介しています。
また、第二章「沖縄へ、Aサインのコザへ」では、米兵相手にするためにできた夜の街を舞台に、かつて大繁栄を誇った頃と現在とを比較しながら、その盛衰のコントラストを切ないぐらいに見事に描いています。
読後感は、「しみじみ」でしょうか。
(2001. 2.24 読)

|
 |
「闘牛の島」 小林照幸 著
新潮社 1,400円+税
1997年12月20日 第1刷発行
徳之島の闘牛ファンならこの牛を知らない人はいない、知らないとわかった時点でもうもぐりであることがばれてしまう…という、今も語り継がれている歴史に残る名牛「実熊牛」の一生を追った名作です。
実熊牛の徳之島における戦績はなんと「44戦42勝1敗1分け、勝率9割5分5厘」。そして自らが初代となった優勝旗の通産獲得回数は16。昭和20〜30年代にかけてつくられた記録だが、これらはどちらも現在まで破られていない大記録となっているという。
牛主の実熊実一さんがこの牛に注いだ愛情や期待は並々ならぬものがあったようで、その様子などが最近人気のノンフィクション作家、小林照幸の取材とたくみな筆さばきにより描かれています。
闘牛は、徳之島では一時の慰めとして「牛ナグサミ」と呼ばれ、また沖縄の各地では「ウシオーラセー」と呼ばれて実に盛んですが、闘牛がいままで続いてきたのにも、戦争をはじめとして幾多の危機があったのだということもこの本を読むとよくわかります。また、徳之島のこの牛や、沖縄の「ゆかり号」のように強い牛が登場するたびに闘牛ブームが巻き起こっていたようです。
とにかく南の島で行われている闘牛はすごいです。興味がない方も一度見てみればそのすごさ、奥の深さに驚くのではないかと思いますよ。スペインのそれのようなカッコつけなどやっているひまはありませんからね。
わたしはまだ徳之島の闘牛を見たことがないので、いつかは全島一大会に的を絞って訪問してみたいものだと考えています。あの「ワイド節」を本場で聴くために。そしてそれに合わせて牛主が勝利牛の上の飛び乗って踊りだすという情熱的なシーンをこの目で見るために…。
(2000. 7. 6 読)

|
 |
「沖縄・国際通り物語―「奇跡と呼ばれた1マイル―」 大濱 聡 著
ゆい出版 1,800円+税 1998年1月20日 第1刷発行
これもまた、読んでよかったと思えた本でした。
大正時代に県庁や警察署が泉崎に移転して、それまで東町や西本町だった那覇の中心地が東北方(現在の県庁周辺)に移動してきましたが、旧都首里と那覇を結ぶ交通は崇元寺から久茂地、美栄橋を通るか泊高橋を経由する道しかありませんでした。そこで、県庁前から安里に伸びる牧志の中央部を貫通する道路が建設されたのが、現在の国際通りのルーツなのだそうです。
沖縄を訪れれば必ずといっていいほどに誰もが歩くであろうこの通りですが、現在は通りの中心地になっている牧志や松尾は、戦前は那覇の郊外に過ぎず、墓地と芋畑が目立つだけの湿地帯だったのだそうです。
それではなぜこの通りが「国際通り」と呼ばれるようになったのでしょうか?
このほかにも、国際通りがどのようにして現在のような繁栄を得ることになったのかとか、その前はどこが商業や経済の中心だったのかなどの疑問について、明快な回答を与えてくれます。現在の地図と見比べると、なるほどと思うことがたくさんあるはずですよ。
さらに、現在はすっかり見えなくなってしまったガーブ川の話や、戦後の映画館の果たした役割、貿易業者たちの大移動、国際通りをめぐるデパート出店戦争の舞台裏、大拡幅計画の顛末などについて、いろいろなエピソードや関係者の証言などをまじえながら精緻に編集されていますので、何度か那覇を訪れたことのある人なら絶対に楽しめます。
(1999. 9.30 読)

|
 |
「奇抜の人と呼ばれて〜沖縄・石垣島断面史」 崎原當弘 著
自分流選書 1,619円+税 1998年8月15日 第1刷発行
1998年11月3日、石垣島を訪れた際に、アンガマのお面の飾り物を手に入れたくて「南嶋民芸館」に寄りました。品定めをして宅配の手続きを済ませたあと、この民芸館の店主が管理している「南嶋民俗資料館」をみせてもらいたいと申し出たところ、懇切にも民芸店の店番を放り投げて、資料館をマンツーマンで案内してくれたのです。
先代が管理していたものを引き継いだばかりでなかなか手が回らないけれども、ちょうどこの日がその先代の一周忌なのだという。先代は米軍占領時代に石垣市議会議長をしていたということで、資料館内には当時の珍しい写真や品物なども展示されており、興味深く見せていただきました。
資料館になっているカーラヤー(沖縄独特の赤瓦家)の居間でお茶をごちそうになりながら、ずいぶん長い間いろいろな話をうかがった後にいとまごいをすると、「これを読んでみませんか?」と差し出されたのがこの本だったのでした。
このような経緯で手に入れ、主人公の人となりもその息子からある程度聞いているので、実に印象深い1冊となっています。
先代が書き綴っていた「自分史」をまとめたもので、長男が校正・編集を手がけ、次男(民芸館の店主)が資料収集をして出版のはこびに至ったようです。
主人公ははっきりとものをいうタイプで行動力もあったようで、表題が示すように普通の人の何人分かの経験や実績を重ねて、風のように八重山の激動期を駆け抜けていった…といった感じの一生だったようです。
また、主人公が関わったさまざまな事件を通して、当時の八重山の世相や置かれていた状況がよく見えてきて、とてもおもしろかったです。
内容は、①崎原家のルーツから母系の石垣島・名蔵への移住とそのころの開拓状況、②著者の台湾時代のくらしと戦後の引き揚げ状況、③石垣島製糖会社ができるまでの交錯する世相と裏面史、④パイナップルブームの様相や、石垣港の着工から完成までの歴史、⑤石垣市と大浜町合併当時の議会の状況と議長時代の裏面史、⑥議員引退後のブタ会社経営など、⑦琉球政府中央教育委員時代、⑧祖国復帰時の世相と人心の不安等々…となっており、一人の社会的リーダーの目からみた戦後八重山の裏面史という性格の構成になっています。
私にとって、読んでよかったと実感できた本のひとつです。
(1998.11.15 読)

|