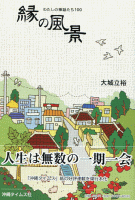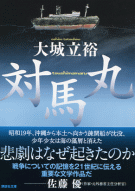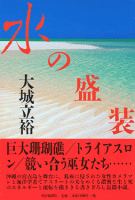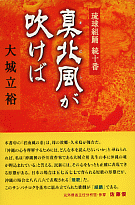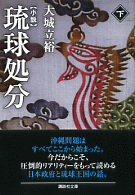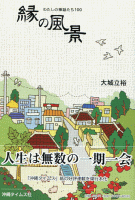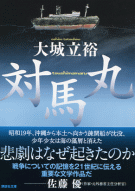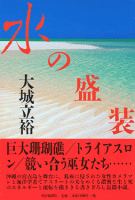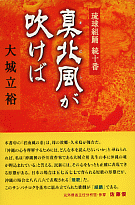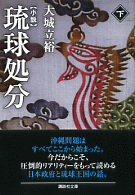|
|
|
|
 |
「焼け跡の高校教師」 大城立裕 著 集英社文庫
500円+税 2020年5月25日 第1刷発行
戦後占領下の沖縄。大学を中退し米軍諜報機関の翻訳作業についた私は、仕事に倦んで教師へと職を変えた。赴任先は、校舎も教科書もない高校。だが、日本の影響を受けないここで、国語ではなく“文学”を教えたい。自分の創作戯曲を生徒達に演じさせようと考える。物はないが、もう戦争はないという開放感に満ち溢れた時代の少年少女と教師を描く。著者が自分の一番輝いていた時と回想する自伝的小説。(カバー背表紙から)
ウェブ上に森本浩平氏(ジュンク堂書店那覇店店長)による書評があったので、以下に引用させていただきます。
・沖縄初の芥川賞作家・大城立裕の青春私小説を読む
森本浩平(ジュンク堂書店那覇店店長)
戦前から独自の出版文化が根付き、多くの県産の書籍が発行され続ける出版王国・沖縄。その沖縄出版界を半世紀以上ものあいだ、常に先頭で牽引してきた作家・大城立裕。沖縄では知らない人はいない、沖縄初の芥川賞作家である。御年94歳になるが、今なお精力的に書き続けている。
本作は大城氏自身がこれまでの人生の中でもっとも輝いていたと語る、1948年、22歳に宜野湾村野嵩(のだけ)高校の国語教師となってからの2年間を綴った青春自伝小説。のちに「カクテル・パーティー」で芥川賞を受賞する大城氏の、作家人生の礎ともなったのであろう、文学を通じて心を通わせた生徒たちとの交流が描かれる。
多くの生徒たちに思いを馳せ、個々の人物像も交えながら、授業、家庭訪問、学芸会などの学校生活が回想されていく。
実際の授業の中で使われた教え子たちのいくつかの作文が、そのまま文中にちりばめられた場面もある。それは県立図書館に大城氏より寄贈され、現在も「大城立裕文庫」として残されている貴重なもので、当時の情景をリアルに映し出す。
学芸会では生徒たちと演劇に取り組み、自らが文芸作品を戯曲にする。その作品は石坂洋次郎の当時のベストセラー「青い山脈」。この戯曲がのちに新聞社主催のコンクールに出品され一等にもなる。またもう一つの作品、大城氏が半年間暮らした熊本市の闇市場が舞台の「望郷」は、疎開者たちの沖縄が描かれる。遠い故郷沖縄を思い暮らす沖縄人同士の絆。それは現在も変わらない。
敗戦直後の焼け跡に建つ校舎を舞台にした物語だが、そこには暗然たるものはない。生徒たちは実に朗らかで、快活とした様子が伝わってくる。そこには大城氏が戦中派の一人として、若者には悔しい思いをさせまいとの情念が強くあったに違いない。
70年以上前の終戦直後の沖縄が、大城氏の記憶から見事に精細に描かれた本作は、当時の沖縄を知ることができる貴重な作品とされるであろう。文学離れが進んでいく昨今、文学こそが人間教育として大事なものだという大城氏のメッセージを読み取り、本作から多くを学ぶほかない。
その大城立裕は、2020年10月27日に逝去しました。ここに琉球新報の訃報(一部)を引用しておきます。
・大城立裕氏が死去 沖縄初の芥川賞作家 95歳
戦後史を体現、沖縄問題の根源問い続ける 2020年10月28日
沖縄初の芥川賞作家で長年、沖縄文学をけん引し、沖縄とは何かを問い続けた大城立裕氏が27日、老衰のため北中城村内の病院で死去した。95歳。中城村出身。大城氏は3月に体調を崩し、入退院を繰り返していた。小説、戯曲、評論、エッセーまでさまざまな分野で琉球・沖縄の通史を独自の歴史観で書き続け、沖縄の戦後史を体現した。
今年5月に出版され、米統治下の沖縄で高校教師をした経験を基にした自伝的小説「焼け跡の高校教師」(集英社文庫)が最後の出版物となった。
大城氏は1925年生まれ。県立二中を卒業後、中国・上海にあった東亜同文書院大学に入学した。敗戦で大学が閉鎖され同大学を中退し沖縄に帰る。
戦後は米施政下の琉球政府職員、日本復帰後は県職員を務めた。青春の挫折と沖縄の運命とをつなげる思想的な動機で文学に関わり、職員の傍ら執筆を続けた。日本復帰前の67年、米兵による暴行事件を通して、米琉親善の欺瞞を暴いた「カクテル・パーティー」で芥川賞を受賞した。68年には沖縄問題の根源に迫った「小説琉球処分」を出版した。復帰後は県立博物館長も務めた。
戯曲「世替りや世替りや」で紀伊國屋演劇賞特別賞。93年には戦時中の沖縄の刑務所を取り上げた小説「日の果てから」で平林たい子賞。90年に紫綬褒章、96年に勲四等旭日小綬章、98年に琉球新報賞、2000年に県功労賞を受賞した。創作意欲は衰えず、15年「レールの向こう」で川端康成文学賞。19年に井上靖記念文化賞を受賞した。
近年は沖縄の基地問題に関し、積極的に発言した。2005年、米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古への新基地建設問題について、本紙のインタビューに答え、「第二の琉球処分だ」とし、「県民に与えられたテーマは辺野古に基地を造らせないこと」と述べた。
11年には同問題をテーマにした短編集「普天間よ」を刊行。伝統芸能の継承発展にも取り組み、組踊の新作も執筆した。
(2020.12.12 読)

|
 |
「あなた」 大城立裕 著 新潮社 1,750円+税
2018年8月30日 第1刷発行
共に生きた60余年あなたは何を思っていたのだろうか……。あなたを見守り、また見送るなかで、二人ともに過ごした夫婦の時間は、行きつ戻りつしながら、記憶にさらに深く刻まれ、やがて新たに繋がり始める。沖縄に暮らし続けてきた作家の日々。92歳の「いま」が、静かに、豊かに、語り出される。歳月という釉薬に、独特の色合いを増しながら。
伴侶の死と夫婦の歴史を、沖縄を背景に綴る表題作「あなた」、そして、生き抜いてきた時代を書き留める「御嶽の少年」のほか、「辺野古遠望」「B組会始末」「拈華微笑(ねんげみしょう)」「消息たち」の滋味あふれる私小説6篇が収録されています。
著者はあとがきで、前著の「レールの向こう」(2015年)から「あなた」(2018年)まで、妻のことを私小説として一気に書いたという思いがあると述べてます。この時点で92歳。文章には一抹の老害もなく、鮮明です。
今年1月19日、琉球新報ホールで行われた大城立裕作の新作組踊「対馬丸」を観に行った時には、95歳に近くなった本人がその場に来ていたのと出くわしましたが、車椅子に乗ってはいるものの矍鑠とした姿には驚かされました。
ウェブ上にあった発行元の新潮社の書評(「波」2018年9月号より)を1本、以下に掲載しておきます。
・沖縄に生きる92歳の現在 川本三郎(評論家)
沖縄に生まれ育ち、この9月に93歳になる作家が、辿ってきた道を振り返る。個人史であり、市井の人から見た沖縄現代史にもなっている。
長く一緒に暮し、先に逝った妻のこと。辺野古のこと。旧友たちのこと。女を作って家を出たことのある父のこと。田舎で過ごした子供時代のこと。そして次々に先立ってゆく友人たちのこと。
老いの身には、過去が鮮明になってくる。生きるとは思い出を重ねてゆくことだ。そこには悲しみがあり、悔いがあり、感謝がある。まして高齢になってからは、妻が、兄が、身近の友人たちが亡くなってゆく。もう思い出のなかにしか生きていない。
表題作「あなた」は、60年以上連れ添った亡き妻へ捧げられている。1954年に見合いで結婚した。戦後のまだ貧しい時代。公園らしい公園もなく、記念運動場と呼ばれたところで初夏の夜、「デート」をした。その時「あなた」が言った言葉を「私」はいまも憶えているという。「わたし、一所懸命やるわ」。戦後のつましい青春が泣かせる。
奥さんはいまふうにいえば専業主婦としてよく働いた。二人の子供(男の子)を育て、公務員と作家の二足わらじで苦労する夫を支えた。「あなた」は、その奥さんが亡くなったあとに書かれた思い出の記だが、ひとりよがりの感傷はない。淡々と事実だけを書き込んでゆく。それだけに、老いた夫婦に必ず訪れる別れ、どちらかが先に逝く終末の悲しみが迫ってくる。奥さんは脳梗塞で倒れ、やがて肺癌にもなる。その頃から、記憶も薄れてゆく。
だから、死に接して「私」は思う。「あらためて有難く思うのは、病気の発症から終末にいたるまで、あなたがまったく痛みを訴えることがなかったことだ。自分が肺癌の終末を看取ってもらっているのだということさえ、意識していないことを、私は感謝したい」
認知症が進んだためだろうか。奥さんの意識がないことを幸いにする。
感謝ではあるが、それがつらいことであるのは言うまでもない。死を見送る側には、自分だけが生き残っていることへの罪の意識がある。その生存罪責感が「あなた」の文章を引締めている。
収録作の「御嶽の少年」では昭和のはじめ、中城村という田舎の祖父母の家で過ごした夏休みの日々が牧歌的に描かれる。集落どうしの大綱引き、パッカラーという粘土の遊び(めんこを思わせる)、村にいたフラーと呼ばれる狂女、朝鮮飴売り。田舎の子供時代が豊かに思い出されてゆく。とりわけ、牝山羊を牡山羊のところに「つけ」に行く話はおおらかで面白い。大城立裕はよく沖縄の民俗を主題にした小説を書いたが、こういう野育ちの影響もあったかもしれない。
「拈華微笑」は父親の思い出。この父親は「私」も含め、三人の子供がいながら、遊女あがりの女と一緒になって家を出た。富裕な家の生まれだが、遊び好きで財産を蕩尽した。
どうしようもない父親だが、作者はそれなりに面白い人物だったと、愛情をこめて描いている。思い出のなかで父親は許されている。
老いてゆくと現在が遠ざかり、過去が近づいてくるという。しかし、「辺野古遠望」を読むと決してそうではない。大城立裕は、沖縄の厳しい現在、とりわけ辺野古基地建設問題に関心を持たざるを得ない。
大城立裕は、政治問題を生の言葉で小説のなかで語るのを避けてきた。日常を生きる生活者の落着いた言葉で小説を書いてきた。しかし、「辺野古遠望」には、随所に熱い言葉が出てくる。沖縄の現状への怒り、憂い、不安が表現される。
「普天間あたりも基地を造る前はのどかな村落と田園であったが、あの辺野古に同じものを造るというのか」
「(以前は)アメリカだけを相手にした時代であったが、いまは日本政府をあらたな相手として加えなければならなくなった」
そして、老作家はこう呟かざるを得ない。
「私が年来考えてきたのが、生きているうちに沖縄の問題は片付くだろうか、ということである。思いついたときにはいくらか期待感もあったが、このごろではほとんど絶望している」
この原稿を書いているさなか、翁長知事死去の報を聞いた。
(2020.3.20 読)

|
 |
「花の幻―琉球組踊十番」 大城立裕 著 カモミール社
3,333円+税 2007年11月6日 第1刷発行
2007年11月発行の、創作組踊十番。
著者・大城立裕は「あとがき」で、次のように記しています。
20世紀末期、琉球伝統芸能・組踊の殿堂としての国立劇場おきなわの創建をひかえて、組踊の創作をしようと志したのは、伝統の継承のためには創作が必要であり、琉球語のネイティヴ・スピーカーとしておそらく最後の世代ではないか、という責任感のようなものに突き動かされたからであった。それを組踊の創始者・玉城朝薫の顰にならって5本書き、「新五番」だと少々きざな吹聴をして「琉球楽劇集 真珠道」と題して上梓したのが、2001年のことである。
先人の衣鉢を継ぐとしても、現代は現代なりのあたらしい方法を持たなければなるまいと、私なりに思索をしたつもりである。その思索のひとつに、5つの作品を琉球歴史の5つの時代を配するということがあって、当然現代劇をふくんだが、喜劇を配したのはわれながら思いつきの冒険であった。書いた順序は時代順で、「海の天境」(古琉球)、「真珠道」(近世)、「山原船」(近代の夜明け)、「花の幻」(沖縄戦)、「遁ぎれ、結婚」(戦後)となる。
五番で終わるはずであったが、かるい思いつきで六番目を書いたところで、勢いに乗るように十番まで書いてしまった。
書いた順にいえば、
「さかさま「執心鐘入」」は時代喜劇である。「執心鐘入」の道具の鐘のもうひとつの使い道を作ろうというだけが動機である。十番まで書こうと思いつく、きっかけになった。
古典組踊はすべて王府を擁する首里中央の立場や美学を描いたが、辺境を舞台にする組踊もあってよいではないかと、「悲愁トゥバラーマ」(八重山)、「サシバの契り」(宮古)を書いた。
古典に数多くある按司ものを一つは、と思って「今帰仁落城」を書いた。唯一の荒事といえようか。
最後の十番目に何を書こうかと思案して、恩納ナベと吉屋ツルに歌合戦をさせてみようかと思いついた。多少ふざけているが、ふざけをドラマに転化すれば、真面目である。
「琉球楽劇集 真珠道」と異なる最大の点は、本文の下段に日本語訳をつけ、本文を現代読みの表記にしたことである。歴史的仮名遣いの表記は、現代の役者にとっても読者にとっても無理な面がある、との配慮からである。
「琉球楽劇集 真珠道」では「梗概」をつけたが、今回はそのかわりに作品ごとに、作にかかわるエッセイを入れた。作の意図などを書いた。
古典の時代にくらべて印刷の便にめぐまれたために、後世に残る可能性が大きくなっている。ひとりの書き手で十番の達成というのは、けだし組踊の創始以来初のことだが、それも印刷、発表の可能性を得て、なかばはそれをたのしみに牽引されてのことであり、その面では有難い時代にめぐりあわせたと思っている。あと2年、数え年85歳の干支までに十五番達成をめざし、いま十三番を書きあげたところである。
――と、厚顔にも公言するのは、もっぱら己れの退路を断つためである。時あたかもしかし、琉球語の衰えゆく時代のさなかにあるというのは、まことに皮肉なことで、この十番が無益な抗いに終わらないことを願っている。
この文章で、著者の思いや作意については十分に理解してもらえることと思います。
組踊十番+エッセイのほかに、歌劇「月夜の人生」と「泊阿嘉(補綴)」、随筆「私のなかの琉球芸能−伝統と創造のはざまで」。
付け加えておくと、これらの新作は2010年段階で、「サシバの契り」を除く9作品が舞台化されているとのこと。作品は上演してこそ価値があるということからすれば、舞台化された数もすごいです。
一時期沖縄で「遁ぎれ、結婚」がけっこうな話題になっていたことを思い出しました。2005年の国立おきなわでの上演では、玉城満の演出により、地方として徳原清文、長嶺ルーシー、與那覇徹が参加していたようです。立ち方では瀬名波孝子のほか、当時若手と言われていた小嶺和佳子、高宮城実人、呉屋かなめ、新垣江里子・麻里子姉妹、山城亜矢乃なども。みんな、今も元気でやっているのかな。
また、大城はこの後新作組踊を二十番まで書き上げ、2011年には「真北風が吹けば
―琉球組踊続十番」をものしています。それらは、奄美、糸満、首里、久米島、やんばるを舞台とした「風土記」もの5作と「愛のシリーズ」5作の10本になっています。
(2018.8.26 読)

|
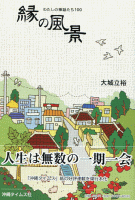 |
「縁の風景 わたしの挿話たち100」 大城立裕 著 沖縄タイムス社
1,600円+税 2007年6月11日 第1刷発行
2007年、著者が82歳のときに発刊されたもの。
「沖縄タイムス」夕刊紙上で連載された「縁の風景―私の挿話集」(2006年1月6日〜7月15日、45回)とその続編(06年10月6日〜07年3月31日、42回)の一部を割愛し、それらに著者による書き下ろしを加えて構成したもの。
人生80年のうちに五体に貼りついたさまざまな記憶の映像を、グソーまで持っていくのは勿体ない。生きた証と言っては大げさだが、ここらで読者に申し送ってもよいか、と考えてみた。(「あとがき」から)
おかしな話、若き日の追想、海外での出来事、ウチナーグチをめぐって、折々の思い、私的・沖縄戦越し、創作の余白、忘れ得ぬ人々の8つのテーマに分けて配列されています。ほとんどの挿話は2ページ分の見開き600字で編集されていて、どこからでも読めるようになっています。
肩の凝らない簡潔かつ面白みのある文章ですが、さすが大城立裕で、随所に見られる含蓄や鋭く温かい人間観察などがあり、読み応えも十分です。
「忘れ得ぬ人々」では、人間国宝・島袋光史、民俗学者・仲松弥秀、元沖縄県知事・平良幸市、文人・池宮城積宝、音楽家・宮良長包、音楽家・渡久地政一、思想家・新垣弓太郎、役者・間好子、戯曲家・木下順二、芸術家・岡本太郎、作家・中上健次、洋画家・安谷屋正義、作家・石野径一郎、俳優・宇野重吉などが登場します。
(2018.7.24 読)

|
 |
「さらば福州琉球館」 大城立裕 著 朝日新聞社 1,400円+税
1994年 3月 1日 第1刷発行
1994年3月発行のものを2015年1月に入手し、18年まで書棚に積ん読として温存していたものを、引っ張り出して読みました。初出は1980年の「別冊文藝春秋」なので、この作品が世に出て40年近く経ってからようやくにして読んだことになります。
福州琉球館とは、琉球専用の滞在施設として中国側の手で設置されたもので、はじめは泉州にあって来遠駅といったものが、1469年に福州に移転し、名も柔遠駅(じゅうえんえき)といわれるようになります。設置の年代は不明ですが、15世紀後半にはすでに存在し、1879年の琉球処分により王国が廃されるまで活用されました。
琉球使臣の宿泊所、交易連絡所として用いられ、明・清2代にわたる琉球と中国の交流の主要舞台となりました。
その琉球館は、琉球王国崩壊後、沖縄県設置に反対する旧臣たち(脱清人)の拠点となります。
日本の琉球処分に反発し憂国の思いに燃える男たちは清国に支援を求めて海を渡りますが、彼らを待っていたのは…。
――という、歴史の波に翻弄されながらも、時代に立ち向かう琉球人の群像を描いたものが本書となっています。
漢字の名前のたくさんの登場人物同士が会話をしている記述が多く、その部分はついついすーっと読んでしまうのですが、小説全体の筋立てがよく見えなくなってしまいがちなのはそのあたりに原因があるのかもしれません。つまり、各登場人物のイメージが脳内で結像しないというか。
また、ある程度琉球王国のたどった経緯なり歴史を踏まえていないと難解なところもあったような気がします。
それらはつまるところ、読み手の能力と集中力の問題でしかないのでしょうが。
うーむ、いつか読み直しをするべきなのだろうな。
(2018. 4. 4 読)

|
 |
「レールの向こう」 大城立裕 著 新潮社 1,600円+税
2015年 8月30日 第1刷発行
このところ大城立裕については旧著作を古書店から買い漁って読んでいましたが、当人にとって初めてという私小説で、しかも川端康成文学賞を獲ったという「レールの向こう」が新たに刊行された(2015)ので、ありがたくゲットしたところ。
当書の紹介文をウェブから拾うと、次のとおり。
「川端康成文学賞受賞記念の短篇集。「沖縄の私小説を書いてきた」作家の新境地。沖縄に生きて、その風土を呼吸しながら創作を続けてきた89歳の作家の、初の私小説。時の移ろいを生き抜く老年の日常。妻の入院をきっかけに、出会ってきた人々の面影とともに、遠い記憶が鮮明に蘇り、いまを生きる私を、強く激しく揺り動かす――川端康成文学賞を受賞した表題作と新作「病棟の窓」を収録する、最新作品集。」
「レールの向こう」、「病棟の窓」、「まだか」、「四十九日のアカバナー」、「エントゥリアム」、「天女の幽霊」の6篇。
「レールの向こう」は、脳梗塞で倒れて入院した妻に付き添う日々。作中では妻を、長年連れ添った思いを込めて「お前」と呼び、旧知の作家への追悼文を依頼されても即座に断り、「お前への思いを薄めることを、いまの私は拒否したい」と。まっすぐな知性と意志とが文章に張りを持たせ、老いを感じさせません。
「病棟の窓」は、今度は自分が左大腿骨を骨折して妻と同じ病院に入院することになり、院内でやはり高齢となった旧知の人々と思いがけない再会をすることに――。
「まだか」は、95歳の父親の遺産相続をめぐる兄と弟の心理的確執を。
「四十九日のアカバナー」は、墓をめぐる本家と分家の葛藤を分家の側から描いています。
「エントゥリアム」は、移民したまま音沙汰のなかった祖父をハワイの病院に見舞う話。
「天女の幽霊」は、戦後60年を前に急速に都市化する那覇新都心に幽霊が出るという噂が。ヒロインの巫女が、噂の背後に何らかの陰謀があるのではないかと疑って調べ始めてみると、案の定いかがわしい巫女が介在していることに気づく、というストーリー。沖縄における古いものと新しいものとの相克を描いています。
90歳になんなんとしてなお、これだけの筆力があることには、ただただ感服するしかありません。
なお、川端康成文学賞は、年度中最も完成度の高い短篇小説に贈られる、作家の川端康成を記念して作られた文学賞です。1974年からの歴史があり、過去に佐多稲子、水上勉、開高健、島尾敏雄、大江健三郎、高橋たか子、安岡章太郎、目取真俊らが受賞しています。
(2017. 2.17 読)

|
 |
「琉球の季節に」 大城立裕 著 読売新聞社 1,359円+税
1993年 8月11日 第1刷発行
2016年の沖縄本50冊目として、年の最後に読んだ1冊です。
「カクテル・パーティー」(1967)で沖縄発の芥川賞作家となった大城立裕が、1993年に発表したエッセー集です。それを古書市場から手に入れて読んだもの。沖縄の最大の論客と言っていい大城センセイですから、読まなければなりません。
「復帰後20余年、いま独自の文化と歴史を見直し、新しい時代を切り開く沖縄からのメッセージ」(コシマキ)というキャッチが付いており、著者曰く、
「いつのまにか、沖縄が同情の対象どころか、日本の中のゲンキ印として、羨望の対象にもなりかねない風潮が生じてきました。沖縄のなかでも、近代史で予想できなかったほどの自信が芽生えています。
この季節に、沖縄から日本の文化に寄与することを、考えております。そして、沖縄で普遍的な問題を考えるようになりました。すくなくとも、問題意識だけはしっかり持ちたい、という願いから書いた文章……。
そういう文章を前面に出して、この本を編んでみました。」(「あとがき」から)――とのこと。
確かに、かつてはマイノリティと見られていたウチナーンチュの置かれている日本における位置取りというか、相対的な地位(?)は、客観的に見て本土復帰が達成された(1972年)頃とは大きく様変わりし、実に堂々としたものになっていると思います。
推察するにそれは、ウチナーンチュの持つ「文化力」が牽引したものではないでしょうか。
ウチナーポップがワールドミュージック界の旗頭となり、その後それを凌駕する形でアクターズスクール出身の歌手やMONGOL800などの気鋭が日本のミュージックシーンの中央に躍り出たことはその代表例と言えるでしょう。
身辺雑記、新聞コラム、文化論などを1冊にまとめたもので、早いものでは1968年のものから最後は92年までと、著作年代的にも幅広いものとなっています。
「「だからよ」文化の明暗」、「ヤポネシア論の宿題」、「沖縄復帰10年の文化状況」、「アルゼンチン・タンゴ」、「南米移民のいま」、「祖父母のこと」、「学童疎開のこと」、「沖縄方言の落とし穴」、「地名のあて字」、「姓と屋号」など、取り扱われる事象もまた幅広く、興味深いものが並んでいます。
さすがにやや古さを感じるのは否めないところですが、失われつつある沖縄の地域性に思いを馳せながら、感慨深く読むことができました。
(2016.12.31 読)

|
 |
「普天間よ」 大城立裕 著 新潮社 1,600円+税
2015年 3月13日 第1刷発行
私は戦争体験はないが、よくある「悲惨な戦場」を書くのは他に任せて、自分は違う戦争を書こう、と考えた。
このたび基地「普天間」を書いたら、これこそがまさに、沖縄の戦争そのもの、なのだった。
沖縄の宿命というものか。
――と、大城立裕の思いがコシマキに記されています。
『在日米軍基地の約75%が集中する沖縄。轟音のなかで暮らす祖母、父、娘の三世代それぞれの「普天間」。「沖縄の魂」を織り込んで問う、日本の未来。「沖縄と戦争」をあぶりだす7篇。』
こちらはショッピングサイトでの、この本の紹介文です。
その7篇は、「夏草」「幻影のゆくえ」「あれが久米大通りか」「窓」「荒磯」「首里城下町線」「普天間よ」。
勝方=稲福恵子・早稲田大学教授は2011年7月31日付けの琉球新報の書評で、「島が耐える現実を凝縮」と題して次のように述べています。
物語の力に突き動かされて、那覇空港からモノレールに乗り継ぎ、終点の首里駅から「首里城下町線」のバスに乗った。このバス路線の名前がそのまま作品の題名になって、この短編集『普天間よ』に収められている。かつて戦場だった丘陵の淵を巡る路線。語り手が車窓から手繰り寄せる情景を、私も巡礼のようになぞってみたくなったのだ。
語り手の小橋川英介は、少年兵として徴集された戦場でのおぼろげな記憶を、62年後の今、訳あって東江清昌に確認しなければならない。しかし戦友はすでに恍惚の人となり、記憶を共有するすべは失われた。それでも、清昌の傍らで控えめな応答をする「奥さん」の存在が、取り返しようもなく失われた記憶の淵を照らしてくれる。「戦争の記憶」は、「東江のなかで立派に凍結されているのを見届ける思いがした」。会いに来たことは無駄ではなかった。
「…彼の脳裏に戦争の記憶がすべて消え去ったもののように見えながら、真実はむしろ、この機会により確実に定着したのに違いないと思った。もう滅びまい。ただそれが表白されないだけだ。生きている者が認識できるかできないかは、それはごく些細(ささい)なことではないか」
物語の時代設定も、作者が実際に執筆したのも、2007年。「集団自決」の軍関与問題をめぐって「記憶・証言」の有無が問われ、沖縄中が哀しみをこらえて忘却の蓋を外し始めた時だった。
およそ作家というものは、リアルタイムな出来事をモチーフにしようとはしないもの。とりわけ政治的に過ぎる2007年や、「普天間」の現実は、小説にせよといわれても、そう簡単に書けるものではない。作品化するためには、事件の背後にある現実の襞を幾重にも掘り下げてテーマを発酵・醸成させるだけの時間が要るからだ。
しかし文学の常識をひょいと超えて、この作品は、この小さな島が耐えている現実の重みを、崇高なまでに凝縮して見せている。この夏は、この一冊を携えて、普天間から中城への巡礼に立とうと思う。
さらに、大城立裕は、あるインタビューに答えて次のように述べています。
「短編集を出そうとなったとき、出版社から普天間をテーマに書いてくれと頼まれました。びっくりしましてね、あんな大きな問題をと。一瞬思案したものの、逃げてはいけない、受けて立とうと考えた」
「私は小説に政治問題を取り入れるのは好きではありません。政治的に描くのではなく、沖縄人のアイデンティティを奪還できるかどうかというテーマで象徴的に描けないかと考えた。基地問題の本質は、奪われた土地を取り戻したいという沖縄人のアイデンティティです。基地にされた土地には、もともと人間がいた。人が生き、生活を営み、歴史を紡いできた。土地にはその記憶が染みついている。我々沖縄人はそこに生きているというアイデンティティを奪還するのだ、という思いを書いたつもりです」
「琉球舞踊は沖縄の代表的な文化、いわば魂です。ヘリの爆音に伴奏の音曲はかき消されてしまうが、それでも主人公は踊り続ける。そしてヘリが飛び去り、再び音曲が聞こえてくると、踊りはぴったりと音曲に合って終わる。基地の重圧に琉球文化は負けない、との思いを込めました。沖縄人の基地への抵抗、闘いは粘り強く続く、との希望の表明でもあります」
このような小説集ですが、自分はそこまで内容を理解して読めたのかどうか、はなはだ疑問です。
改めてもう一度読んでみる必要がありそうです。
(2016. 4.25 読)

|
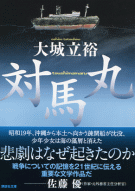 |
「対馬丸」 大城立裕 著 講談社文庫 730円+税
2015年 3月13日 第1刷発行
1944年8月、沖縄から本土に向かった学童疎開船・対馬丸は、アメリカ潜水艦・ポーフィン号の魚雷を受け、夜の海に沈みました。
乗船者1,661名、このうち学童は800余名。生き残った学童はわずか50余名だったそうです。
戦争完遂という大義名分のもとに実施された疎開事業における最大の悲劇がどうして起きたのか、また、生き残った学童たちは数日間の漂流をどのようにして生き残ったのかを伝える内容となっています。
無邪気な沖縄の学童たちは、本土に行けば雪が見られる、鉄道に乗れるなどと、なかば修学旅行気分で沖縄を発ったことでしょう。
そして、彼らを送り出して離ればなれになってしまう親たちの心情はいかばかりだったでしょうか。
さらには、無垢な子供たちを危険な水域に敢えて送り出そうとする教育者たちの葛藤は…。
著者は、元沖縄県立博物館長で、沖縄芝居の脚本なども手掛ける沖縄文化人の第一人者、大城立裕ですから、ノンフィクションに作家らしい脚色を施しており、読みやすいものになっています。
対馬丸の遭難については、当時は箝口令が敷かれ、社会も混乱していたので、知る人は少なかったようです。著者本人も、戦後ながく対馬丸の遭難のことは知らなかったそうで、1960年に遭難学童遺族会から執筆依頼を受けたのを契機に取材を始めたのが事件を知るきっかけとなったようです。
事件発生から71年、沖縄戦の終結から70年が経過し、当時の事実を語ることができる人々が少なくなっています。
戦争を知らない世代ばかりになった現代においてこそ、我々はこういう文献をとおして、戦争という悲しい出来事の実態をしっかりと受け止める必要があるのではないでしょうか。
(2015.10. 2 読)

|
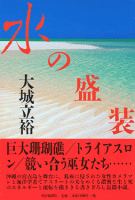 |
「水の盛装」 大城立裕 著 朝日新聞社 1,900円+税
2000年 8月 1日 第1刷発行
2013年の夏に、大城立裕の本を古書市場からまとめ買いしたもののひとつ。2000年に発行されたもので、それを2015年の5月に読み、9月になった今、その読後インプレを書いています。
沖縄の宮古島を舞台に、乳ガンに侵されたカンカカリヤ(神がかり)の素質を持つ女性カメラマン「千寿」と、海洋学者でトライアスリートの夫「鳴海」をめぐる、濃密な生と死のエネルギーと流転を描ききる書き下ろし長篇小説です。
巨大珊瑚礁、トライアスロン、競い合う巫女たち…などが登場して宮古島の風情、風景等が描かれていますが、それは観光名所紹介といった感じもないではありません。
〈私といっしょに消えて……〉
ついに思う。あなたは十分に走り、生ききったのだから、もう私といっしょに消えてもいいのではない? それから、生きなおそう。私はもう、それに賭けるほかはない。あなたも一緒……。海だっていま干潮に向かっているのよ。あらためて満潮を迎えるために……。
八重干瀬では確実に干潮に近づきつつあって、珊瑚礁が大潮にふさわしく広大に浮き上がってくる。それを千寿は、自分と夫の命として見はるかし、あのなかへ二人で溶けこんでいけばよい、と願った。(本文より)
うむ。こうしてコシマキあたりに書かれているキャッチを引用しているのはほかでもありません。数カ月前に読んだ内容をうっすらとは思い出せても、もはやポイントを押さえて記述することができなくなっているのですな。
とりわけ単行本の小説ってのは「まえがき」や「あとがき」、「解説」といったものがないことが多いので、過去の記憶を手繰り寄せる端緒となるものが足りないのです。
というわけで、こんな感想でゴメンナサイ。
(2015. 5.31 読)

|
 |
「恋を売る家」 大城立裕 著 新潮社 1,700円+税
1998年 4月15日 第1刷発行
イザイホーで有名な宗教の島・久高島で生まれた朝子は、本島中城の青年英男のもとへと嫁ぎます。
嫁ぎ先は誇り高い神女殿内で、母はその神女。また、接収された軍用地からは莫大な使用料が入る家でもあり、英男は働くことをせずウシオーラセー(闘牛)に心血を注ぎます。
英男のアイデアで、御嶽の隣に連れ込みホテルを建設し、朝子はその管理人として働くことになります。
一見幸福を約束されたかに思えた結婚でしたが、その後、家の資産を狙うヤクザ者が夫に近づき、朝子の心は次第に“濁った闇”に包まれていきます。
戦争は、終わったように見えて実は、慢性的な占領体制という形で影を引きずります。そしてその体制は、人間を変え、文化を変えてしまう――ということが、家庭での出来事や日々の生活を通して滲み出てくるようです。
「日の果てから」、「かがやける荒野」に続き、沖縄を代表する作家が、激しく揺れ動く現在の島を舞台に“沖縄の魂”の変貌を描き切った一作となっており、これらは著者をして「戦争と文化」の三部作と言わしめています。
(2014. 6.29 読)

|
 |
「かがやける荒野」 大城立裕 著 新潮社 1,500円+税
1995年12月10日 第1刷発行
1995年の作品。著者自らが「戦争と文化」の三部作と名づけている「日の果てから」、「かがやける荒野」、「恋を売る家」の真ん中に位置するもので、著者は当書の「あとがき」で次のように記しています。
『敗戦直後の民衆のバイタリティを描き出してみたいと、かねてから考えていました。・・・沖縄の戦争については私なりの解釈があって、それはたんに物理的な破壊にとどまらず、社会の体制のすべてを滅ぼしたのだ、ということです。ただ、文化を滅ぼすことはできず、それが蘇りのエネルギーになったと思われます。これらのことを「日の果てから」で書きましたが、その先を見ることが、この作品に課されました。』
そして、過去の既成の形が戦によっていったんカオスに戻ったとき、そこで蘇るものはどういう形をとるのか、蘇る、あるいは生きなおすとはどういうことなのか、それは選択が可能なのか――などについて、米軍に見合うように生み出されたコザの町を物語の舞台にして表現していきます。
コシマキのキャッチは次のようなもので、なかなかに味があり、全体をうまく表現していると思われます。
『捨てられない記憶がある。見えない記憶がある…。敗戦から2年。沖縄の“荒野”で、人々はそれぞれに“蘇り”を試みる。戦場で記憶を喪った少女を中心に、占領下の基地の町で繰り広げられる叙事詩的長編小説。』
(2014. 3.22 読)

|
 |
「ハーフタイム沖縄」 大城立裕 著 ニライ社 1,800円+税
1994年 9月 1日 第1刷発行
芥川賞受賞作家の大城立裕によるオキナワン・エッセー。古書店から400円で入手して読んでみました。
1968年から1993年まで、主に80年代に沖縄の新聞や各種出版物などに掲載された文作をまとめて、1994年9月に発行されたものです。
著者は「あとがき」で、「まとめてみたら、戦後の思いを総括したような気配をも帯びているようです。あるいは沖縄近代史への思いのすべてをも。」と書いています。
そして、「スポーツの球技にハーフタイムというものがあります。一応の区切りをつけ、採点を得ながら、まだ先がある、ということです。沖縄の現段階のことを、文化史のハーフタイムのようなものではないか、と解釈してみたのが、題名の由来です。」とも述べています。
筆の及ぶ先は沖縄の歴史、芸能、人、暮らしなど広範囲にわたっており、興味深いものが豊富。それらは、「沖縄方言論争」を総括する、伊波普猷が生きていたら、「琉球の風」雑感、沖縄県民と芸能、創作舞踊管見、笑築過激団、金城哲夫の帰郷、比嘉康雄の世界、東恩納寛惇と中国語、琉球士族の名前、「クラシン」連想、二足草鞋の40年・・・などなど。
1925年生まれの大城がもっとも脂ののってきた頃の著作であり、透徹した眼差しで跡づけられた沖縄の精神史論にもなっていると思います。
(2014. 2.23 読)

|
 |
「日の果てから」 大城立裕 著 新潮社 1,400円+税
1993年 3月20日 第1刷発行
だいぶ前になってしまいましたが昨年7月、大城立裕の著書(いずれも古書)を6冊まとめ買いしました。
その直前に読んだ「真北風が吹けば ―琉球組踊続十番」(2011年刊)がなかなかよく、その先駆けとなった「花の幻―琉球組踊十番」が欲しくなったので、そのついでということで。
しかし、買ったものは作品が出来上がった年代順に読みたいもの。
購入した6冊は、「日の果てから」(1993年)、「ハーフタイム沖縄」(94年)、「かがやける荒野」(95年)、「恋を売る家」(98年)、「水の盛装」(2000年)、「花の幻―琉球組踊十番」(07年)。
ということで、この本から読み始めました。
1945年4月、アメリカ軍が沖縄本島に上陸。凄絶な地上戦の“地獄絵”の中、逃げ惑う住民。刑務所も、遊廓も、そこに縛られる人々も何もかも、沖縄は死の渦のなかで回転し、やがて敗戦とともに浄化される――。
神女殿内(のろどんち)の家柄である神屋家を絡め、文化、歴史、風土を背景に太平洋戦争末期の沖縄戦を神話的世界にまで昇華させた傑作長篇。――という作品です。
ある対談で大城は、「自分の作品の中で「日の果てから」が、今でも印象に残っている作品だそうだが…」と問われ、「そうね、「日の果てから」はかなり小説の構造としてもよくできていると思う。素朴さが抜けたところがあったな」と語っています。
また、「日の果てから」、「かがやける荒野」、「恋を売る家」は、著者自ら「戦争と文化」の三部作と名づけているのだそうです。
著者は、20年以上前、芥川賞を受賞した頃から一度は沖縄戦を書きたいと念じていたとのこと。そして、書くならば、あらためて自分が書くだけの意味がなければならず、それは沖縄戦も沖縄の過去と未来をつなぐ長い歴史のなかの一区切りだという意味を加えたいと考えていたようです。
沖縄の文化にとって、戦争とは何であったか。戦争で何が変わり、また変わらなかったか。人々は戦の最中または前後に、何を願ったか。それはどう報いられたか。――などについても表現されており、新しい普遍性の発見もそこにはあったと思います。
(2014. 1. 3 読)

|
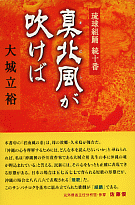 |
「真北風が吹けば ―琉球組踊続十番」 大城立裕 著 K&Kプレス
2,000円+税 2011年 6月28日 第1刷発行
沖縄文学界の重鎮が創作した琉球組踊の台本10本。先に「花の幻―琉球組踊十番」が刊行され、これの続編という形で2011年6月に発売されたものです。
奄美、糸満、首里、久米島、やんばるを舞台とした「風土記」ものに加え、「愛のシリーズ」5作の10本により構成。それらは、「いとしや、ケンムン(奄美)」、「羅針盤(からはーい)由来記(糸満)」、「龍潭伝(首里)」、「君南風(ちんぺー)の恋(久米島)」、「ハブの祝祭(やんばる)」、「異本
銘苅子」、「愛よ、海を渡れ」、「真北風(まにし)が吹けば」、「対馬丸」、「名護情話―外伝
白い煙と黒い煙」。
題材を奄美や中国にとってみたり、戦時中の対馬丸に焦点を当てたりと、大胆な題材で組踊を創作しています。しかし、登場するセリフは大部分がウチナーグチで、それがサンパチロクのリズムに乗ってやさしく語られていきます。もちろんその合い間には地方が謡う沖縄古典民謡が入り、登場する役者による「つらね」が入りますから、気分はすっかり組踊を観ているようなものです。
ああ、いいなあ、組踊。国立劇場おきなわに行って組踊公演が観たくなったなぁ。
ウチナーグチがよくわからなくてもご安心。すべてに日本語訳が付いていますから。
この台本を、ほとんど日本語訳を読まずにある程度理解できるようになったなら、アナタはもう立派な沖縄理解者だと言っていいでしょう。
まあ、読んでいるうちにだいたいはわかってくるものですし、何よりもウチナーグチのリズムで読んだほうが、身体に、ハートに、心地よいですからね。
原価3,500円の「花の幻―琉球組踊十番」を中古で1,500円売っているのを見つけてしまった。どうしようかな、買っちゃおうかな。・・・と考えて、大城立裕の「ハーフタイム沖縄」、「恋を売る家」、「日の果てから」、「かがやける荒野」、「水の盛装」、「花の幻―琉球組踊十番」の6作品をアマゾンで買っちゃいました。
(2013. 7. 4 読)

|
 |
「カクテル・パーティー」 大城立裕 著 岩波現代文庫 1,040円+税
2011年 9月16日 第1冊発行
読みたいなと思い始めてから長い間手に入らなかった芥川賞受賞作であるこの作品ですが、このたび復刻されて文庫本として発売されたのを知り、沖縄美栄橋近くのジュンク堂書店で入手。
1967年に文藝春秋社から発売されて以降、1975年、1982年にも他の出版社から発行された経緯があるそうですが、それから約30年を経過しての再発となります。
発行部数が少ないこともあるのでしょうが、解説を含めて320ページに満たない文庫なのに税込みで1,092円もする。高いよなぁ。でも、読めるのだからシアワセか。
沖縄初となった芥川賞受賞作の表題作のほか、「亀甲墓」、「棒兵隊」、「ニライカナイの街」。そして最後には、日本語版未発表の「戯曲 カクテル・パーティー」と、全5編が収録されています。
このうち「カクテル・パーティー」は、米軍統治下の沖縄で、日本人、沖縄人、中国人、米国人の4人が繰り広げる親善パーティー。そのとき米兵による高校生レイプ事件が起こり、国際親善の欺瞞が暴露されていく――という筋書き。
米軍属に暴行を受けた娘を持つ主人公が、不利だとわかっている裁判に事件を訴えることを決意するまでの展開を描いた物語になっています。
1995年に起きた少女暴行事件をはじめとした数々の基地被害を思い出させるだけでなく、依然として基地の重圧が押し付けられている沖縄をめぐる複雑な政治状況をも浮かび上がらせ、この小説がけっして古典になることはなく、同時代的な緊張を読む側に提起する力を持っていることがわかります。
長く全集や文学選などのアンソロジーでしか読めなかったこの作品が、今では文庫で読める、という意味は非常に大きいと思います。
沖縄で買って、山形に連れてこられ、読み終えたのは三重県に出かけての帰りの新幹線の中。自分に買われたばかりにずいぶんと旅をさせられた本となりました。
(2012. 7.18 読)

|
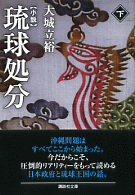 |
「小説琉球処分(下)」 大城立裕 著 講談社文庫 762円+税
2010年 8月12日 第1刷発行
処分官として派遣されてきた松田道之が琉球に突きつけたのは、尚泰王の上京、清国への朝貢の禁止、明治年号使用の強制など、独立どころか藩としての体裁をも奪おうとするものでした。
このことによって琉球は、内部でも意見が分かれ、頑固党と開化党の戦いは骨肉化していきます。
世界で軍隊を最も嫌う国といわれた琉球がどうこれに対処していくのか――。
物語は佳境に入ってきますが、その中で露わになるのは、琉球側の煮え切らない態度。なんとかして結論を先延ばしにしようとして三司官やそれに次ぐ親方たちが鳩首会議を開きますが、ラチが開きません。
彼らが考えていることは、対外的にどうかということよりもむしろ、琉球内部の統制の問題であったり、自分たち特権階級の保身であったりするところであり、読んでいて歯痒さがつのります。
そこで立ち上がるのが、大和や外国を経験して見聞を広めてきた若いサムレーたち。彼らが古い体制の中で徐々に発言力を増していき、苦悩しながらも、松田や伊地知といった明治政府側の役人たちと肩を並べるようにして未来の琉球を考えていく姿には、感慨深いものがあります。
巻末には、元外務省職員で、母が久米島の出身という佐藤優が重厚な解説をしています。
彼は、琉球処分の後に発生した八重山・宮古分島問題(1880年)を分析すれば、日本人である沖縄の同胞を守るという中央政府の主張が欺瞞であったことがわかるとし、この構造的差別のかたちは琉球処分のときに組み込まれたと書いています。
そしてこれと構造的に同じ現象が、21世紀になった今でも、普天間飛行場の移設問題などで繰り返されていると嘆いています。
そして、次のように現状を憂えています。まったく同感です。
――沖縄の人々の間に、かつて自らの国家であった琉球王国が存在し、それがヤマトによって、力によって滅ぼされたという記憶がよみがえってくる。
そうなると日本の国家統合が内側から崩れだす。
この過程が始まっていることに気づいている東京の政治エリートがほとんどいないことが、現下日本の悲劇である。
いまわれわれが直面している危機を認識するために、本書がひとりでも多くの人の手に取られることを望む。
(2011. 7. 2 読)

|
 |
「小説琉球処分(上)」 大城立裕 著 講談社文庫 762円+税
2010年 8月12日 第1刷発行
清国と薩摩藩に両属していた琉球。日本が明治の世となったことにともない琉球は、薩摩藩の圧制から逃れられるのではないかとの希望を抱いていました。
ところが、明治政府の大久保利通内務卿らが断行した台湾出兵など数々の施策は、琉球を清国から完全に切り離し、日本に組み入れようとするための布石なのでした。
ここに、琉球と日本との不可思議な交渉が始まることになります。
その経過を物語調に仕立てたのがこの本。ウチナー切っての知識人であり、ウチナーの“良心”の体現者でもある大城立裕が長年かけてまとめた作品です。
この本、文庫版の発売(2010年)から38年も前の1972年に初版が刊行されているらしい。では、なぜ今文庫化なのかというと――。
なんでも、2010年6月、菅直人が、衆参両院で首相指名されたあとの記者会見で、「数日前から「琉球処分」という本を読んでいるが、沖縄の歴史を私なりに理解を深めていこうとも思っている」と述べたことを受けて、出版社への問い合わせが殺到したため、なのだそうです。
まぁ、こちらとしてもこういう本が容易に手に入れられることはとても好都合ではあるのですが、世の中ってそんな程度のもんなのだなぁとの思いも。
上巻だけで520ページ余り、下巻と合わせて千ページ超の大作です。読み応え十分、というか、語り口調が淡々としていて、どちらかというとあまりエンターテインメント的であるとは言えません。
しかし、バックデータはしっかりしているとみえて、論調に破綻はなく、事実に忠実なのだろうなと思わせるところが多いです。
したがって、歴史的に読めばおもしろく、古い資料を読むよりもずっと楽だし、加えて当時の沖縄の人々の心情まで理解することができるというのはスゴイ!という立場で読むのがいいのではないかと思います。
(2011. 6.22 読)

|