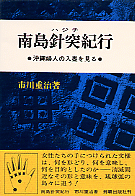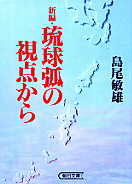|
�u�l���Ŕp�~�S�N�L�O�� �����ςȁv �@
�@�@�@���d�R�l���Ŕp�~�S�N�L�O���Ɗ�����L�O������@�ҁ@�@�@��R��
�@�@�@�P,�T�O�O�~�@�@�@�Q�O�O�R�N �X���P�Q���@��P�����s
�@���̍��́A�{�͂����ς�l�b�g�ʔ̂ōw�����Ă��܂��B����𗷂����Ƃ��ɂ͏��X�ŗ~��������{���`�F�b�N���邾���Ȃ̂ŁA���Ă̂悤�ɖ{��������������ė�����A���Ă���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�������A���̖{���p���b�g�v�Βn�̏��X�Ō������Ƃ��́A���n�ł͂܂��[�b�^�C�ɔ����Ă��Ȃ����낤���Ƃ��\�z�ł������߁A�������ɍw�����܂����B���̔��f�͐����������i�c�B
�@���ċ{�ÁE���d�R�ɂ́A�e�l�ɓ�����ɉۂ����l���Łi�ɂ�Ƃ������j������A�����͂��̕s�����ʼnՍ��ȐŐ��̂��Ƃŋꋫ�ɂ������ł����Ƃ����܂��B
�@�V�Ŗ@���{�s����A�������悤����Ƃ��̑O����I�Ȑ��x���������ꂽ�̂́A�P�X�O�R�i�����R�U�j�N�B�����̌㔼�ł���B�ق�̏��������̂̂��ƂȂ̂ł��B
�@���ꂩ��P�O�O�N�B���d�R�ł͐l���Ŕp�~�P�O�O�N�L�O���Ƃ��s���A���̕�̂ƂȂ�����������s�����̂����̋L�O���Ƃ����킯�ł��B
�@���e�͑傫���Q�ɕ�����Ă��āA��P�͂ł́A�S�N��̍��A�l���ł��l����\�\�Ƃ�������ŁA���̎����l���ł��߂��鏔���ɂ��Ă̊�e���f�ڂ��A��Q�͂ł́A�L�O���ƂƂ��čs��ꂽ�e��s�������h�L�������g����Ă��܂��B
�@��e����́A�l���ł����d�R�̐l�X�̐����Ɍ��t�ł͕\���Ȃ����炢�ɏd���̂��������Ă����l�q���A�f�ГI�ł͂���ɂ���A���ɂ悭�`����Ă��܂��B
�@���ɃW���Ƃ����̂́A�u�d���i�܂��Ȃ�����ȁj�Ɋւ����l�@�v�ɂ������L�q�ł����B
�@�����Ŗڍ���l�̘d���ƂȂ��������̐l�����Љ�A���̏����͊�e�Ҏ��g�̕���̑\�c��ł��������Ƃ������B�����āA�������������l�̌n�}�ׂĂ�������e�҂́A���̖�l�̌�������q���Ƃ͂Ȃ�ƁA���݁A���g���l���̎t�Ƌ��ł���g�߂ōł���Ȑl�������\�\�Ƃ������Ƃɂ��ǂ蒅���Ă��܂��̂ł��B
�@�����͏���������B���̏Ռ��I�Ȏ�����O�ɂ��āA��e�҂͂����������h�������Ƃł��傤�B
�@�L�^���A���j�����Ƃ��Ă̐��i�������{�ł����A���悤�Ȋ��������ꂠ��A���d�R�́g���h��m�邽�߂ɂ��傢�ɎQ�l�ɂȂ���̂Ǝv���܂��B
�@��ɓ���Â炢�̂���_�ł��傤���B
�i�Q�O�O�T. �Q.�P�U�@�ǁj
 |
 |
�u����l�͂ǂ����痈�����v
�@�@���� �i�E�y�쒼���@�����@�@�{�[�_�[�C���N
�@�@�@�P,�U�O�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�X�N �W���Q�O���@��P���@�@�Q�O�O�Q�N �W���Q�O���@��R�����s
�@�����ɂ͂��A�����Ȃ�l���Z�݂������̂��H
���Đ��E�j�ŏK��������̌Ñ�l�E�`��l�͌��݂̗����E����l�̑c��Ȃ̂��H ���Ă܂��A�O�X�N����ɂ͂������������N�������̂��H �\�\���悤�ȓ�Ɋ��R�Ɨ������������̂��A�l�Êw�ҁE�����i�Ɖ�U�w�ғy�쒼���A�����ĂQ�l���R�[�f�B�l�[�g���鉫��w�ҁE���Ǒq�g�B�t���t���A�����A����l�͂ǂ����炫���̂��H
��̑S�̂ǂ��Ȃ̂��H�I
�@�c����Ȋ����ŁA���͕s�����̂܂܁A�����r���D��S��s�œǂ�ł݂܂����B
�@���ʂƂ��ẮA�܁A����ς莩���ɂ͂�����Ƃނ������������ł����ˁB�ǂނ̂ɂ����Ԃ�ƍs���߂���āA���\���Ԃ�H���Ă��܂��܂����B���y�[�W�ǂ����Ŗ���ɗ�����������������̂Ȃ��c�B
�@�l�Êw�Ƃ����̂́A�ЂƂЂƂ̔��@���̌�����ςݏd�˂邱�Ƃɂ���āA�����͂����ė��_���\�z���Ă����w��Ȃ̂ł��傤�B�ǂ����Ă����͂̒��ɂ́u������Տo�y�́~�~�v�ȂǂƂ������L�q���o�Ă��Ă��܂��܂����A�����X�ɂ��Ă̈ʒu�Â�������Ȃǂɍ��ݍ��݂Ȃ���ǂݐi�߂Ă����Ȃ��ƁA�����Â������Ă��āA�I���ɂ͉����Ȃ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��ˁA���^�V�Ȃ̏ꍇ�B
�@�ł��A���Ƃ��Ίe�n�̈�Ղ���o�y�����Ñ�l�̓��W�����r���邱�Ƃɂ���Ă��낢��Ɛ������Ă݂���Ƃ���Ȃǂ́A����Ȃ�ɁA�͂͂��A�i���z�h�c���Ċ����ŁA����Ȏ����ɂƂ��Ă���ʐV�N�ȂƂ��������܂����f�X�B
�@�������A���W���̌`���āA��ׂĂ݂�Ƃ��ꂼ�ꂪ�Ǝ��̓����������Ă��āA�����Ԃ�Ⴄ���̂Ȃ̂ł��ˁB�����ł�������ǂ݉�����悤�ȍl�Êw�ɂ��Ă̗\���m�����������Ȃ�ƁA��w��˂̂��̐g��Q������ł��i�B
�@���g�́A�\��Ɠ����̑Βk�̋L�^�����S�ɂȂ��Ă��āA�����⑫����`�łQ�l�̒��҂ɂ��T�{�̘_�l�W���ڂ��Ă��܂��B���̊w��̐��E�̂��Ƃł�����A�\��Ƃ��Čf����ꂽ�^��ɑ��錋�_����C�Ɍ���Â�����Ƃ������̂ł͂���܂��A�������������̌����͂��Ђ���ǂ��B
�i�Q�O�O�S. �V.�Q�T�@�ǁj

|
 |
�u�����Ɨ����̐l�X
���������K��L �P�W�T�O�N�P�O���v �@�@�W���[�W�E�X�~�X�@����
�@�@�@�R���h�S�E�V��E�ǁ@����@�@����^�C���X�Ё@�@�P,�R�O�O�~�{��
�@�@�@�Q�O�O�R�N �X���Q�T���@��P�����s
�@�P�W�T�O�N�P�O���A�C�M���X�̐_�w�҃W���[�W�E�X�~�X���p���C�R�̃��C�i�[�h���ɂė��������ۂ̖K��L�ł��B
�@���҃X�~�X�������ɖK���S�N�O�A�����ւ̃L���X�g���̓`����ړI�Ƃ��āA���łɃx�b�e���n�C���Ƃ����l���Ƃ��̉Ƒ����������Ă����̂ł����A���̈�t�ł�����ւ荂���鋳�t�͗������{�Ƃ͂܂��������肪���킸�A�ߔe�E�g�̏�̌썑���ɔ��ΗH��ԂŏZ�܂킳��Ă����̂ł����B����ȏ��X�~�X�́A�x�b�e���n�C���̂��Ƃŗ����Ɖp���̊Ԃɐ������a瀂ɂ��Ē��ׂ邽�߂ɁA�R�͂ɓ��悵�Ă����Ƃ������P�Ȃ̂ł��ˁB
�@�x�b�e���n�C���͕ЈӒn�������A��ؓ�ł͂����Ȃ��Ƃ��낪����A�ߔe�̒��O������u���ዾ�v�i���傤�B�ނ̓��K�l�������Ă����B���͔ڂ����҂ւ̏́̕j�ƌĂ�ċ�����Ă����悤�ł����A��ʂł͓��������Ă̒ʎ��ł���Ǖ~�i�q�u�j�����i�����炵�����傤���イ�j�Ɛ[���M���W�������Ă����Ƃ������ʂ��������肵�āA�����j�̒��ł��ِF�́A�Ȃ��Ȃ������[���l���Ȃ̂ł��B
�@�x�b�e���n�C���ɂ��Ắu�����������S�j�v���ڂ����A�����ŕ���I�ɓǂ߂܂��̂ŁA�Q�Ƃ��Ă݂�̂������ł��傤�B
�@�ŁA���̖{�ł́A�����������j���ɔ[������̂����邱�ƂȂ���A�����̓ߔe�A������̐l�X�̐����⒬���݂̗l�q�Ȃǂ����҂ɂ͈�ې[�������悤�ŁA���̗l�q�����͂̂��������œo�ꂷ�邱�Ƃɉ������������䂩��܂����B�Q�����A���̗���B
�w�����Ƃ����Ή����A�ґ�O���ɕ�炷�l�Ԃ̂�����̊��l�̎҂��A�ߒQ���Y�A�S�z��s���Ɩ����ɐ����Ă����邾�낤���B�Ƃ��낪���̗����ł́A����Ύ��R�l�Ƃ������ׂ����̐l�X�́A���C�ɐ����A�߂��݂�Y�ݎ�����������Đ����Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�܂�ނ�͔ނ�Ȃ�ɂ��̐l����搉̂��Ă��邱�Ƃ͂܂������Ȃ��̂ł���B���m�̐��E�ł����s���I���R���́A�������ꂽ��i�����́A�����ɔ�����т�߂��݂ȂǁA���̐l�X�ɂƂ��Ă͉��̖��͂��Ȃ��̂ł���B�c�x
�w�l�X�̊炪�����̖�����ɏƂ炵�o����Ă����B�����̊�A���ꂪ��������Ȃ��Ă���B�l�̔g���������ɂ��ӂ�āA����ꂪ�ʂ�߂���̂�������Ă����B�ӂ�ɂ͌u���ɔ�ь����A���͂̎���Ƃ���u�̗����ł���B�����璆���P���Ă����B����������ƁA�y�u�̌Q�ł͂Ȃ����B���ۈꕽ�Ă̒n�ʂ������Ȃ��قǂ̓y�u�Ȃ̂������B�c�x�i�ߔe�����ւƌ������ĐL�тĂ����Ƃ�������哹�̗l�q���H�j
�@���Ƃ����Ŗ�҂������Ă���悤�ɁA����Ȃɂ������낢�A�O���l�̌����P�T�O�N�O�̗��������̘b���A�ǂ����č��܂Ŗ|����o�ł����ꂸ�ɂ����̂��A�ƂĂ��s�v�c�Ɏv���܂����B�S�P�S�O�y�[�W�𑧂��ɂ��Ȃ��i��U�����ȁH�j�ǂ�ł��܂��܂����I
�i�Q�O�O�S. �Q.�Q�X�@�ǁj

|
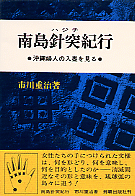 |
�u�쓇�j�ˁi�n�W�`�j�I�s�v �@�@�s��d���@���@�@�@�ߔe�o�ŎЁ@�@�@�P,�T�O�O�~
�@�@�@�P�X�W�R�N�T���P���@��P�����s
�@�Q�O�O�R�N�āA�~�n�}�̃W���X�R���̏��X�œ���B�����Ԃ�O�̔��s�ŁA����ł��Ȃ���������̖{(��)�B�ł��A�ƂĂ����i�ł��邤���ɁA�艿�̏�Ɂu�P�O�O�O�~�v�Ƃ����V�[�����\���Ă������̂ŁA���߂��߃��b�L�[�Ƃ���ɍw�����܂����B
�@�����ʂɂ͂��ď����̐��l�V��Ƃ��āA��ɓ��n�i���n�W�`�j���s�����K�������āA���ꂪ��������O�L�ɋ֎~���ꂽ���߁A����n�W�`�����������͂قƂ�ǖS���Ȃ��Ă��܂����Ƃ����܂��B���̐_��I�ȏK���̎��Ԃ�m�肽�����̂��Ƃ��˂��ˎv���Ă��������ɁA�����������������Ǝv���Ă��܂��B
�@���҂͑�w�ő��`�W�̎d�������Ă�����ŁA������̕��ʂ���n�W�`�ɋ����������A��l�̊W���������Ƃɉ��x�����n�������s���Ă��̖{�������グ���\�Ƃ�������̂悤�ł��B
�@���̖{��ǂ�ŏ��߂Ēm�����̂ł����A�n�W�`�̖͗l�ɂ͈��̃p�^�[���������āA���ꂪ�����ʂ̂ǂ̒n��ł��傫�����Ȃ��̂ł��B�����āA���܂����ʒu�Ɏ{���ꂽ���܂����͗l�ɂ́A���ꂼ��m�łƂ����Ӗ�������̂ł��ˁB
�@���āA�傢�Ɋ��������̂́A�n�W�`�̂��Ƃ������������́B�����哇�̖��w�ŁA�u�r�����ꂠ���� ����͂����q�܂� �������ꂠ���� �ʓ��i���܂��j�q�܂��v�Ƃ������̂����ɔ������B�����ɂ����Ă͓��n�́A���̒j���ɂƂ��Ă��Ȃ薣�͓I�Ȃ��̂������ł��낤���Ƃ����̂�܂��B
�@���҂̒����́A����{���͂������A���̎��ӂ̗�����{�ÁA���d�R�ɂ��y�сA����ɂ͑�p��k�C���ɂ�������n�̏K���Ƃ̔�r�܂Ŏ��݂Ă��܂��B
�@�ɂ��ނ炭�́A�e�n�̃n�W�`�̎���N�W�Ƃ��̔�r�ɏd�����u����Ă��邽�߂ɁA�ǂ�ł��ĒP���Ȋ��������邱�ƁB�����āA���̕��ʂ̌����͂��܂�i��ł��炸�A���_���e�Ղɏo�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�ǂݐi�߂�̂�e�ՂłȂ����̂ɂ��Ă���悤�ł��B
�@���Ⴊ�N�W�ł��Ȃ��Ȃ������ƂȂ��ẮA���̕���̌����̐i�W�͍�������҂ł��Ȃ��̂ł��傤�ˁA�����ƁB
�i�Q�O�O�S. �P. �S�@�ǁj

|
 |
�u������j���� ���{�̏k�}�v �@�@�ɔg���Q�@���@�@�@���}�Ѓ��C�u�����[
�@�@�@�P,�P�O�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�W�N�V���P�T���@��P���@�@�@�Q�O�O�P�N�U���Q�T���@��Q�����s
�@���̂���A����̗��j�ɂ��āA�����Ȃ�Ƃ��n���I�Ȗʂ��l�����ĒNj����Ă݂����ȁc�A�Ȃǂƕs�����Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��āA���̂ЂƂƂ��Ă���Ȗ{�����ɗ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���ǂ�ł���̂ł����A�Q��O�ɓǂނ̂͂�͂�_���̂悤�ŁA�Ȃ��Ȃ��g�ɂ��܂���ˁ`(��)�B
�@�\���́A�u����w�̕��v�ƌĂꂽ�ɔg���Q���A�s�풼��̉���ŁA���N�ɋy�ԉ���̋��̗��j��U��Ԃ�Ȃ���܂Ƃ߂����́B�ɔg�E����w�剺�̖{���ɂ���O�Ԏ�P���̉���ɂ��A�u������j����v�i�P�X�S�V.
�U�j�́A�ɔg�����a�R�N�ɃA�����J��n���C�V���āA�u����扽���ցv�Ƃ̑�ōu���������Ƃ��̍u���^���x�[�X�ɂ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂��������B
�@�O�ɓǂ�Ńq�W���[�ɋꂵ�߂�ꂽ��g���ɂ́w�×����x�Ɣ�ׂ�ƁA�������≺���Ă��邱�Ƃ������Ă��A�����͓ǂ݂₷���Ȃ��Ă��܂��B
�@���̖�ɍ����ꂽ�u���̖M�v�́A�_�̂ɂ����u����肭�Ɂv�A���Ȃ킿�u�̍��v��A�z����\�\�̂ق��A�u���A�m�v�́u���܂�����v�A���Ȃ킿�u�����Ғm��v����A�܂��A�u���K�v�́u���m��v����ȂǁA������̌��t���猻�݂̒n���╨���Ȃǂ�ސ����Ă݂���Ƃ���́A���������̓�����̂悤�ŁA���\�y�����ł��B�Ȃ��m��ɂȂ����悤�ȍ��o�����邵(��)�B
�@�S�̂̂Q�^�R�͂��̕\���ŁA�c��̂P�^�R�́u�����l�̑c��ɏA���āv�A�u�����j�̐����v�A�u�i���_��茩���鉫��̔p�˒u���v�A�u����l�̍ő匇�_�v�̂S�_�ł��B�����͖����̎���ɒ����ꂽ���̂ŁA�q�W���[�ɓǂ݂Â炢�B�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�����S�҂͂�������w�×����x�ɏ�������Ă�����̂Ɠ����Ȃ̂��B
�@��͂�A���̎l�ꔪ�ꂵ���w�×����x�͓��ʂ������̂��ȁB���̎��͕ǂ����������̂Ȃ��c�B
�@�Ƃ������P�ŁA�����j�̌n���I�c���ɂ��ẮA��������������������̉ۑ�ƂȂ��Ă����̂ŃA���}�X�ˁB
�i�Q�O�O�R.�P�P. �W�@�ǁj

|
 |
�u�V�}�̌��閲�\�����Ȃ햯���w�U���v �@�@�ԗ䐭�M�@���@�@�@�{�[�_�[�C���N
�@�@�@�P,�U�O�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�W�N�S���R�O���@��P���@�@�@�Q�O�O�Q�N�S���R�O���@��Q�����s
�@�R�V�}�L�ɂ́w�Ȗ��ȃt�B�[���h���[�N�����ƂɁu�V�}�v���l���A���炩�Ȏ����ł����Ȃ�̖�����ǂ݉����x�Ƃ̋L�ځB����A�����̂��炩���͊m���ɓǂ�ł��Ċ������܂����B
�@���҂́A�P�X�T�S�N�A�앗���͊쉮�����܂�́A�����w��U�̗�����w�̐搶�B�\���́A����̒n�����u�����V��v�ɁA�w�����Ȃ햯���w�U���x�Ƃ��ĂP�X�X�U�N�Ɍf�ڂ��ꂽ�G�b�Z�[�𒆐S�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���́B
�@�V���Ƃ�������ꂽ�����̂Ȃ��ŏ����ꂽ���̂Ƃ����̂́A�Ƃ�����ƌ��t���炸��������A��`���ǂ܂Ȃ��ƈӖ�����Ƃ��낪���ʂ��ɂ��������肷����̂Ȃ̂ł����A����͂��������Ƃ�������܂�Ȃ��A���������炩������ł��傤�A�V���L�����L�̂�����ǂ��Ȃ��A�ƂĂ��悢�܂Ƃ܂�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��f�X�B
�@�u�ᐅ�ƃX�f�B���v�A�u����̖��Ɓv�A�u���z�V��Ǝ��R�ρv�A�u�L�W���i�[�Ƃ��̎��Ӂv�A�u�̖����v�Ȃǂ́w�����ƐM�x�A�����āA�v�����E�������E�����Ȃǂ̐����≫��e�n�̍j�����E�n�[���[�Ȃǂ��������w�܂�x�����S�e�[�}�ƂȂ��Ă��܂��B
�@����̖����������ꍇ�A�{�y�̐l�ԂɂƂ��Ă͂�����Ɠ���ȃJ�^�J�i�W�L���p�ɂɏo�Ă��邱�Ƃ����蕨�ł���A�������܂��������낢�Ƃ�������̂ł����A�{���͂����̗p����ꌹ���璚�J�ɉ�����Ă���Ă��܂��B���S���S�B
�@�܂��A���̖{�̂����Ƃ���́A�����̖����w�҂̐��Ȃǂ����p���ĕ��ׂĂ݂��邾���łȂ��A������n���̌ØV���璘�Ҏ��炪�������������ƂƏƂ炵���킹�ė��҂̈Ⴂ��N���ɂ��Ă݂�����A���Ҏ��g�̈ӌ��𐏏��ʼn����邱�ƂȂ��J���Ă݂��肵�Ă���̂ł��B���̗ނ̖{�ɂ��肪���ȁA�w��̒���������t������悤�Ȉ�ۂ���Ƃ���͂Ȃ��A���Ƃ����Ę_���̂Ȃ��א�������I�ɒ����킯�ł��Ȃ��A���̂悤�ȑf�l�ł������ǂނ悤�Ɋy�����ǂނ��Ƃ̂ł���O�b�h�ȂP���ł����B
�@����̖����I�Ȑ[�݂ɂ͋C�Â��Ă͂��邯�ǁA��发��ǂނ̂͂�����Ƃˁc�Ƃ��������ɂ́A�����ƃ^���s�c�̖��i�B�]�������ł���B�\�������Ղ����A�Ȃ��Ď��������炩���ł�����B
�i�Q�O�O�R. �S.�Q�U�@�ǁj

|
 |
�u�×����v �@�@�ɔg���Q�@���@�@�O�Ԏ�P�@�Z���@
�@��g���Ɂ@�@�X�U�O�~�{��
�@�@�@�@�Q�O�O�O�N�P�Q���P�T���@��P�����s
�@����͂�A�N�x�����}���Ė{�Ƃ��Z�����A���̂Ƃ���Ȃ��Ȃ��z�[���y�[�W�̍X�V���ł��Ȃ��ł��܂������A�X�V���i�܂Ȃ����������ЂƂ̃t�@�N�^�[�Ƃ��āA����߂ē�ǂ́i�����܂Ő�w��˂Ȏ����ɂƂ��āc�Ƃ������Ƃ����ǁj�����Ƀu�`�������Ă��܂������Ƃ��������܂��B���ꂪ���̖{�B
�@�G�b�Z�[�ȂǂȂ��肩�����炷��Ɠǂݐi�ނ��Ƃ��ł���̂����ǁA�R�C�c�͏��ł���������ɏo�ł��ꂽ�Ƃ������j�I���{�ŁA���܂��W�|�C���g�قǂׂ̍��`�����łT�O�O�y�[�W�߂�������Ƃ����A���ɂɂ��Ă͕��������ނ̂��́B�ǂނ̂ɂƂĂ����Ԃ��������Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ��l�N�X�g�ɐi�߂Ȃ������̂ł��ȁB�c�ƂŋA�肪�x���Ȃ�A�A���R�[����ێ悵�����ƂȂɓǂݎn�߂���̂ł�����A�����Ƃ��͐��s���x�Ŗ���ɗ����邱�Ƃ��ł����肵�āi�j�B
�@�Ăȃ��P�ŁA�Z�����s�����O�Ԏ�P�搶���t��������ɂ��ƁA���́u�×����v�́A����w�̕��Ƃ�����ɔg�̏����o�łł���Ɠ����ɑ�\��ł�����A�����S�S�N�ɏo�ł���Ĉȗ����x���ĔŁA�������J��Ԃ��ꂽ���̂����̂��ѕ��ɉ������\�\�Ƃ������Ƃ̂悤�B�ꎞ�̉���u�[���͋������Ƃ������͂�]�_���Ƃ�킯���y�̑��ʂ���悭������邵�A���������̂��Ƃɂ��Ă͂����v���̂ł����A����Ɋւ�����j�I�����̕��ɉ���������ɍs���Ă���Ƃ����o�ŊE�̓���������ƁA�����������牫��Ɋւ�����{�����̒m�I�v����j�[�Y�́A�u�[���ȂǂƂ����ꎞ�I�ȌX���Ƃ������������Ɛ[���Ƃ���Œ����ɐ����Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����v�������Ȃ�܂��B
�@�܂��A�O�ԉ���ɂ́A�w���ꕶ���_�Ɋւ���ɔg�̈ꐶ�̖���̖G��́A�قڂ��́u�×����v�ɏo������Ă���ς�悵�Ă���x�ƋL����Ă��܂��B�쓇�̖����A�̗w���X�ɋ������������̌����͔����Ēʂ�Ȃ��P����������܂���ˁB
�@���e�́A�u�����l�̑c��ɏA���āv�A�u�Y�Y�l�v�A�u���K�Ƃ����閼�́v�A�u�����a���l�v�A�u�������y�҂̕@�c�A�J�C���R�v�A�u���̂̓��C�@�v�A�u���w�Ɍ���ꂽ�锪�d�R�̊J��v�A�u������̊|���ɏA���āv�A�u�o���l�v�ȂǁA���ꖯ���w���D�҂ɂƂ��Ă͐����̂S�R�ҁB
�@�������������̕��Ȃ炨�����낭�Ă����Ƃ����Ԃł��傤���A��b�m���̂Ȃ��܂܂ɓǂݎn�߂�ƁA��ɈȊO�̃i�j���m�ł��Ȃ��\�\�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�G�L�X�p�[�g�����̂P���ł���܂����B���^�V�͂ǂ������āH�@�����A���͎G�w�{�̂悤�Ȍy�����̂����������ł��B
�i�Q�O�O�R. �Q.�Q�W�@�ǁj

|
 |
�u����̗��j�Ɨ��v �@�@�� �w�b�@���@ �@�o�g�o�G���V���@�@�@�W�U�O�~�{��
�@�@�@�Q�O�O�Q�N �S���P�X���@��P�����s
�@�P�X�X�R�N�ɕ������ꂽ�m�g�j�̑�̓h���}�w�����̕��x�i�o���Ă��܂����H�j�̌���҂ł�������Z���Z�C�̒��ɂ��A���j�G�b�Z�[�Ƃł������̂��ȁA�����Ă����ނ̊��ɂ͋C�y�ɓǂ߂�{�ł��B
�@���e�́A�傫���R�B�w�����̗��j�x�͂Q�O�O�O�N�Ɂu�m�g�j�l�ԍu���v�Ƃ��ď����ꂽ���́A�w����ɂ������x�́A�������u���j�X���v�Ɖ���^�C���X�ւ̊�e�̂ق��P�W�{�̏������낵�A�w�Βk�E���j�����u�����̕��v�̐��E�x�́A�J��h�ꎁ�Ƃ̑Βk�\�\�ł��B
�@���҂͑�p�Ƀ��[�c�������ېl�Ƃ����āA���j�����߂鎋��͂₽��ƍL���ł��B�����̗��j�𒆍��Ɠ��{�Ƃ̊W�ɂ����đ�����Ƃ����������������ɂ����āA������̏ꍇ�͑�p�⒩�N�A��A�W�A�A����ɂ͒����̐�̃E�C�O���ȂǂƂ��Δ䂵�Ęb���W�J���Ă݂��Ă��ꂽ������Ă��܂��B�����āA�����̗��j�I�������A���܂��鉫��̊ό��n�╗�y�A�K���Ƃ��̂悤�ɂȂ����Ă���\�\�Ƃ����M�v�Ō������̂ł�����A�ǂ�ł��Ă܂������ދ����Ȃ��̂ł��ˁB������q��ƂƂ����͓̂ǎ҂�������R�c��m���Ă���c�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B
�@�Ƃ�킯�w���j�X���x�́A�ǂ����\�t�g�B���j�Ƃ������悤�Ȏ����̐ςݏd�˂ɂ����؎�`�͊������Ȃ������ɁA�l�Ԃ��{�������Ă���z���́A��z�́A�D��S�Ƃ��������̂��h�����Ă���悤�ȁA�����ǂݕ��ł����B����̗L���ǂ���̃J���[�ʐ^�������������ĂȂ��Ȃ��O�b�h�B
�@���W���[�����̐V���ł��̂ŁA�S���ǂ��̖{������ł���ɓ���Ǝv���܂��B�����m��ЂƂ̎����Ƃ��āA�A�i�^���ǂ�ł݂Ă͂������ł��傤���B
�i�Q�O�O�Q.�P�P.�P�O�@�ǁj

|
 |
�u�����������S�j�v �@�@��
�×^�u�@���@ �@���}�Ѓ��C�u�����[�@�@�X�S�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�V�N �U���P�T���@��P�����s
�@�\����悭����ƁA����́u���S�j�v�Ȃ̂ł��ˁB�܂������̊��Ⴂ�ɂ���ď���ɂ��̖{�͗������A����́u���S�j�v�Ȃ̂��낤�Ǝv���Ă����̂ŁA�܂��͓ǂ݂͂��߂Ĉ�x�т�����B
�@�����Ă����āA�ǂݐi�߂Ă����ƁA����́u���S�j�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����̖����Ɋ����u�q�u�����v�Ƃ����l���́u���L�v�ł��邱�Ƃ��������ē�x�т�����B����킵���\������Ȃ��ق���������Ȃ̂��ȁB
�@�ǂ�ł��Ďv���̂́A����͂����Ƃ��ɗ����̖��������������l�łȂ���Ώ����Ȃ��ȁ\�\�Ƃ������ƂƁA��w�̊w�҂ł͂��̂悤�Ȉ��L�I�ȃG���^�[�e�C�������g�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ����낤�ȁ\�\�Ƃ������ƁB���������N�Ȃ��A�R���������Ă���̂́I�I�@����́A���҂̗��������邱�Ƃɂ���Ĕ[���B
�@���҂́A�{�����鏫�ۂƂ����A���ꌧ���璡�̕����ے��������߂����Ƃ�����w�Z�̐搶������̕��i���ȁH�j�B��啪��͉���̋ߌ���j�A�����j�������B�Ӂ[��A�Ȃ�قǂˁB
�@�q�u�̐l�ƂȂ�������Ȃ�ɂ�������ƌ`�Â���A���j��̓�������̐��ʂƂ�����Ƃ̐����ɂ���āA���҈ꗬ�̃X�g�[���[�Ɏd���ďグ�Ă��܂��B
�@�L���ŔɖZ�ȍ�Ƃ̎�ɂ�邻�̏ꂵ�̂��̂悤�ȗ��j������āA�������������ł���ˁB�璷�ȃX�g�[���[�ƃ����p�^�[���ȓW�J���J��L������悤�ȁc�B����ȍ�ƂɁA�u���̂��炢�͕����Ă��珑����i�v�Ƃ������Ƃł��Гǂ܂��Ă݂����悤�ȁA�����̈��ł��B
�@�ł��A������āA���{�̖������A�e���J���𔗂�o��������������������ɂ́A���������L�[�ƂȂ�|�W�V�����ɂ�������ł��ˁ`�B�����̗�������{���߂���O����͊w�I�Ȋϓ_�����[���m�邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���ꂩ��A�����͓�������i���N���A�e�[�Q�[�O�����J��L���Ă����ˁ`�c�ĂȂ��Ƃ��A��[���킩��܂����B
�@����́A���̂悤�ȉ���̐��_���ɂ�������̉���a���҂Ȃ�A�u�܁`���A�I�}�G���͂܂����������c�v�ƁA���ēǂ߂鉫��ߑ�j�ł��B
�@����S���G�C�T�[�܂���ς�ׂ�����Ɍ�������s�@�̋@���œǗ��B
�i�Q�O�O�Q. �W.�R�P�@�ǁj

|
 |
�u������̂��ƂÂā|�����ʕ��������̗��v
�@�@�@���k�V�n�E���k�M�q�@���@ �@�����[�@�@�Q,�Q�O�O�~�{��
�@�@�@�Q�O�O�O�N�S���R�O���@��P�����s
�@��w�ň�l�̋����Əo��A���̋������t�Ƃ��Ċw�т�������l���A���������ɂ��邤���ɕv�w�ƂȂ��āA���\���ɑ؍݂����肵�Ȃ���t�B�[���h���[�N���s�����\�\�B���̖{�͂��̈�[���܂Ƃ߂����̂ł��B
�@�w�p�I�ɏ�����܂Ƃ߂����̂ł͂���܂���B�W�L�̂������͓��̂������A�����Ƙb���Ă���l�q�����̂܂܋L���������̂��́B���̎p���͏I�n��т��Ă��܂��B
�@���̂悤�ȓ��e�̂��̂�{�ɂ��邾���ň�ł����炦�钘�҂Ƃ����̂́A�܂������̃V�A���Z�҈ȊO�̃i�j���m�ł��Ȃ��ł��傤�B�����Ă���A���҂̑n��Ƃ��������b����̂���ׂ������Ƃ����S�Ȃ��́i�P�ɑA�܂������Ă��邾���ł��A���ӂȂ��j�B
�@�t�B�[���h���[�N�A�u���������v�Ƃ�����@�ɂ��ẮA�ŋߕp�ɂɕ������悤�ɂȂ�܂����B�����w�̐��E���͂��߂Ƃ��čŋ߂Ƃ݂Ɍ������Ă��Ă���悤�ȋC�����܂��B�����g���̗��Ƃ����[���@��A�����ɗ��j����h�Ƃ������t�Ɏh�����A���ꂾ���łȂ��n�����k�̗��j�E�����ɂ��Ă����ڂ��Ă���̂ł����A�W���鏑���͕����������Ԑ���Ƃ�������������܂��B���Ƃ̉��H���Ȃ��̂Ōn���I�łȂ��Ƃ�������݂͂�����̂́A�b�҂̎v���⊴��X�g���[�g�ɓ`����Ă���̂ŁA������x�̑O���������قǂ�����Ă���A�ǂݕ��Ƃ��Ă����ւ�y�������̂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���҂͖{���̒��ŁA���������̌����ɂ��āA�w�l�炪����Ă����̂́A�����̊w��ł����Ɖ��ɂȂ�̂��悭�킩��Ȃ�����ǁA�L���Ӗ��Œn�挤���Ƃ������̂��낤��B���͉��ł����A�Ƃ悭������邯��ǁA�Ȃ��Ȃ��ꂵ�����₾�ˁB�S����قꍞ��ł���t�B�[���h���[�N���n�挤���̊j�S���Ǝv���B�x�\�\�ƌ���Ă��܂��B
�@���҂͕��X�����ɂ��ĕ����������Ă���悤�ł����A�����������ɂƂ��Ă͂���Ȃ��Ƃ͐����̗��j�S�̂̂ق�̈ꕔ�ł����Ȃ��킯�ŁA���X�����ɂ��ǂ�����߂ɂ͕�����͂������̘b�̑S�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����A�܂��������ꂱ���n�挤���Ȃ̂ł���ˁB
�@�f�ڂ���Ă���C���^�r���[�́A���\���A���NJԓ��A���[���i���d�R�j�A�^�_���A��q���A���v���A���V���i�g�J���j�ł̂��́B�����Ȃ������A�������Ƃ������Ђ������o�Ă��Đ̌������܂����A�����ǂނ̂͂��������y�����ł��B
�@�P�X�X�O�N��̂��̂����S�ł����A�b�����Ă��ꂽ�l�̑����͎c�O�Ȃ���������̐��������Ă��܂��B���ꂼ��̌��������������Ƃ��Ă��������ɁA���̌����͎��̖���A���j�̗���A���R�̐ۗ��̈̑傳����������܂���B
�i�Q�O�O�Q. �U.�Q�U�@�ǁj

|
 |
�u�쓇�����ւ̗U���|���ꍑ�ۑ�w���J�u���V�v
�@�@�@���ꍑ�ۑ�w���J�u���ψ���@�ҏW�@ �@�ߔe�o�ŎЁ@�@�P,�T�O�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�W�N�R���R�P���@��P�����s
�@����͗��j�E�����Ƃ������A�u����w�v�Ƃ����悤�ȍL�����e�ɂȂ�̂��Ȃ��c�B
�@�e���r�Ō��J�u���Ƃ��ĕ������ꂽ���̂��A�e��̒S���u�t����M���ĂP���̖{�ɂ܂Ƃ߂��\�\�Ƃ������̂ł��B���̂悤�ȊW�ŁA���ƈ�ʐl�ł����������Ă����ȃe�[�}�ݒ�ɂȂ��Ă��܂����A���̔��ʁA�r�W���A���Ȗʂ��v�������芄������Ă��܂�����ۂ��������̂ɂȂ��Ă��܂������ȂƂ�����ۂ͔ۂ߂Ȃ������B���̌��ʂƂ��āA���X�ދ��ȓW�J�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�e�[�}�͂������ǂȂ��c�B
�@���ꂩ��A�ǂ����Ă����������u���̏ꍇ�A�ʐ���펯�̃��x������i�M�҂̃_�C�i�~�b�N�Ȑ��_��A�Ǝ��̒T���̎�@�A���j�[�N�Ȍ��_�Ȃǂ������Ă����A�ẴE�U�b�^�C�G�߂����̖{�ɏ[�ĂĂ��܂����͎̂��s�����������B���Ƃ��āA�u������ǂ��Ȃ̂�v�ƌ��������Ȃ镔�����������肵�܂����B
�@�\����������ǂȂ��c�B�u�i���g�E�u���J�w�m�C�U�i�C�v�Ƃ������t�̋����͂ǂ��ł����B�z�����܂��悤�ɗU���Ă��܂��܂��˂��B
�@���e�B�e�[�}���݂�ƁA����͂����A���L�������[���ł��B���܂��B
�@�u�͍����猩������ƃA�W�A�v�A�u���㉫��̋��F��Љ�v�A�u����̃��[�c�v�A�u���{�̒��ٍ̈��v�A�u�쓇�̑c����J�v�A�u�������痈�������v�z�v�A�u���������̒n�搫�v�A�u����̎�Ҍ��t�l�v�A�u���ꖯ�b�ւ̗U���\�L�W���i�[�ƃJ�b�p�\�v�A�u�w�����낳�����x�̖��́v�A�u�_�̂���I�L�i�����E�|�b�v�X�܂Łv�A�u�Ղ�⑺�V�тɏo������x��_�E���K�_�v�B
�@�\���ɕ��L���ł��˂��B
�@���e�̊��ɒl�i�������O�[�ł����A�����]���́u�����ꑧ�v�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B
�i�Q�O�O�P. �W.�Q�V�@�ǁj

|
 |
�u���ƍĐ��̌����M�`�C��n��_�X�v�@�@�O�Ԏ�P�@�� �@�@�p��I��
�@�@�@�P,�T�O�O�~�{�Ł@�@�@�P�X�X�X�N�T���R�P���@��P�����s
�@�\���́u�j�[�����v�i���d�R�̒|�x���ɂ���B�j���C�E�J�i�C�������Ă����D�����̐ɂȂ����Ƃ����j���Ȃ�Ƃ��_�X�����A�܂�������������A�Ǐ��ł��B
�@����ɂ́A�C�̔ޕ��ɂ����킹�̖������p���_�C�X�A�c�悽���̌���������Ƃ��鑼�E�ρA�j���C�E�J�i�C�̐M������܂����A���E�ɍL���铇�ׂ̂������ɂ͂���Ɨގ����������M�����t���Ă��āA���̌����Ɠ��Ƃ̉����ɂ́A�����ΊC�ӂ̓��A���g���Ă��邱�ƂɁA�O�ԃZ���Z�C�͋C�Â��������ł��B����Γ��A���u���̐��v�Ɓu���̐��v�́u���킢�v�̐��E�Ƃ��ċ@�\���Ă���A�Ƃ����̂ł��B
�@�{�����ȁH�Ǝv���ǂ�ł����ƁA�i���z�h�i���z�h�B���������͂������̂��ƁA���E�ɂ܂Ŕ͈͂��L���Ẵt�B�[���h���[�N�ɗ��ł����ꂽ���_�W�J�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���܂��B�����n�_�ɂ���Ă͐���̖K�₵���s���Ă��Ȃ��Ƃ��������܂����A��͂茋�ǂ̂Ƃ���A�T������Ⴊ���邩�Ȃ����̖��Ȃ̂ł��傤�B�܂˂̂ł��Ȃ����Ƃł��i�A�^���}�G�_�I�j�B
�@�͂��߂ɉ���̑��E�ς⌴���M�Ɠ��A�̊W�ɂ��Ċm�F���������ŁA�ɍ]���́u�j���[�e�B���K�}�v�Ƃ������A���ɂƂ��āA����̓��A�̂���悤�����ؓI�ɉ�����Ă��܂��B�܂������ŁA�K�}�̎��u���킢�v�Ƃ��Ă̐��i����������Ɠǎ҂ɍ��܂�郏�P�ł��ˁB
�@�����Ă�������A�Z���Z�C�̊�͐��E�ɍL�����Ă����܂��B�o�_�̍��̒��ړ��A����͂��܂��āA�A�C�k�̃|�N�i�E���V���M�Ɠ��A�A�t���E���E�p���A�j���[�W�[�����h�̃n���C�L�M�Ɠ��A�A�A�C�������h�̃e�B���E�i�E�m�O�M�Ɠ��A�A�M���V���E�N���^���̐_�X�Ɠ��A�A�G�W�v�g�̑��E�ςƑm�A�M�A�؍��ϏB���̑��E�ςƎO�����Ȃǂɂ��ĉ�����Ă��܂��B�����A�z���g�A�����Ȃc�Ɗ�����������̂�����܂��B
�@�l�I�ɂ킩��₷���Ă悩�����ȂƎv�����̂́A�ЂƂ͏��͂́u����̐_�Ƒ��E�v�ł��B����ɂ��ƁA����Ñ�̐_�ϔO�ɂ����ꂼ��ɕʂ̔��������������u�j���C�E�J�i�C�̐_�v�A�u�A�}�~���E�V�l�����̐_�v�A�u�I�{�c�E�J�O���̐_�v�Ƃ����R�̐��E�̐_�X������A����炪�������Ă��Ă��܂��Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ł����c�B�����̐��i���ɂ��Ă͂����ł͉�����܂��A�ƂĂ��t�[���I�ł��B
�@�����ЂƂ́A�u�C�̔ޕ��̊y�y�j���C�E�J�i�C�v�ŁA�j���C�ς̕ϑJ�ɂ��Ă�������Ƃ����Ӌ`�̐��������Ă��邱�Ƃł��B�Ȍ��ɐ�������ƁA�@�c�_�̂܂��܂�����A�A���҂̍��̍s���Ƃ���A�B�n��ɖL���A�K���A�����������炷��͂̌���n�A�C�C�̔ޕ��̊y�y�c�Ƃ������Ƃł����A����͂����܂ł��\�ʓI�Ȃ��Ƃł����āA���ꂼ��̎��[���Ӗ�������`���ߒ��ɂ����d�v������߂��Ă���̂ŁA�����̂�����͈�x�ǂ܂�邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�i�Q�O�O�P.�@�U. �Q�@�ǁj

|
 |
�u���ꏗ���j�v�@�@�@�ɔg���Q�@���@�@�@���}�Ѓ��C�u�����[�@�@�@�P,�Q�O�O�~�{��
�@�@�@�@�Q�O�O�O�N�P�P���P�O���@��P�����s
�@�P�X�P�X�N�ɔ������ꂽ�����̏��ɁA�ɔg���s���������Ɋւ�������^�Ȃǂ������Ăł��Ă���̂����̖{�B���쐭���炪�ҏW���Ă��܂��B
�@�\���̏������Ȃ�Ƃ����������_�X�����B
�@����̗��j�߂�̂ɂ͂��������A�v���[�`�������Ă����̂��낤�Ǝv���čw���������̂ł����A����̗�����������ɂ͂����Ȃ����̂́A�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA�ǂ�ł݂ĂƂĂ��ʔ����A���߂ɂȂ���̂ł����B
�@�Ȃ��ł��u���ށv�i�����A����j�ƌĂ��A�҂Ȃǂ̗V�s�Ŋ��Ă����A�܂��{�y�ł����Ȃ�Ώ��Y�̒��ԁi�Ƃ����̂��ȁH�����͂����Ă��j���A���X�͂܂�ňႤ���̂̂悤�Ȉ�ۂ��܂������c�j�̐l�����̐����̗l�q�Ȃǂ������āA���ɋ����������ēǂ܂��Ă��炢�܂����B
�@�����Ƃ̌Ôg���ۍD���̘b��ǂ��Ƃ�����̂ł����A�Ôg�����̕��̑�⎩���̎Ⴉ�������ɂ́A�n�ʂ����Y�������l�O�̒j�B�݂͂Ȓ҂��������͂��Ă����悤�ŁA�܂��A���{�̏��Y�ƈႤ�Ƃ���́A���ނ͎��R�������F�߂��Ă����̂������ł��B�����āA�Q�O���߂��������肩��͈��z��X�ɔ[�߂�q���Ƃ낤���Ƃ�܂����A���ɖ��͂Ȃ����������Ȃ�ł��ˁB���̂�����̘b��A���ł��������ɍs���Ă���i�ŋߕ��������Ƃ����b�������Ƃ�����܂����j�W�����n�̗l�q�Ȃǂ��ڂ��Ă��܂��B
�@���̂ق��A�Ñ�̗����ōs���Ă����Ƃ����u�����͂�̗V�сv�A�����ɂ��āA�������\���鏗�̐l���[�Ȃׂ̘b�A���^�̗��j�I�����A���ď�����������Ȃǂɂقǂ����Ă����u�n�W�`�v�Ƃ����h�Ɋւ���L�q�ȂǁA����̏����Ɋւ��镗���E���������������Ɍ����Ă��܂��B
�@�������A���������������A���̂悤�ȓ��e�̂��̂ł����ɂɂȂ��Ĕ���o����Ă��܂��Ƃ������̐��̒��́A�ƂĂ����炵���ł��ˁB
�i�Q�O�O�P.�@�R.�Q�W�@�ǁj

|
 |
�u���{�l�̍��̌��� ����v�����v�@�@�@��ÍN�Y�@�� �@�@�W�p�АV��
�@�@�@�U�U�O�~�{�Ł@�@�@�Q�O�O�O�N�T���Q�Q���@��P�����s
�@�������A���Ă͈ꕔ�̃}�j�A�b�N�Ȑl�X�̊Ԃŋ��߂��Ă������̂悤�Ȑ��E�����������̂��A�Ȃ�ƐV���ŏo�Ă��܂��̂�����I�h���L�ł��B������ς�������̂��Ƃ̊��S���o����Ɠ����ɁA�m���ɍ��A���̒��͕������\�̎��ォ��S�̎���Ƀ��o�C�o�����Ă��Ă���̂��ȂƎ����Ȃ�Ɋm�M���Ă��܂��܂��B
�@�r�V�Ď������u�ڂ��͂��̖{��S��ǂނ��낤�B����͐V���ł͂Ȃ��B�ÓT���v�Ɛ�^���Ă��܂����A�����f���ɓ����ł���P���ł��B
�@���҂́A�x�@���Ζ�����]�g���Ďʐ^�������͂��߂��Ƃ����ꕗ�ς�����o���̎�����ł��B�l�����I�ɂ킽���ē��ʂ��𑱂��Ă��āA�N���s���Ƃ��čs������J��ʂ��ē��̗��j�A���l�̉F���ρA�����ςȂǂ�̌����Ȃ���A����̐��_�����̑c�`�������邩���킩��₷���Ԃ��Ă��܂��B�w�҂̋L�q�ł͂Ȃ��̂ŁA���炷��ǂ߂܂���B
�@�v�����̍��J�ɂ��ẮA�P�Q�N�ɂP�x�s��ꂽ�Ƃ����C�U�C�z�[�́A�����I�ɂ͍Ō�̌p���҂ƂȂ����i�����s��Ȃ��Ƃ͒N������Ȃ�����ǂ��A�����I�ɂ͍���͍s���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ƃ������Ƃ��A���̖{��ǂ߂ΒN���������ł���Ǝv���j�����V�Y����i�P�X�W�X�N�����j�҂��҂�����}�[�N���ĕ��������������ƁA�܂��A���X�Ȃقǂ̉̓n���ɂ��A���ƃJ�����̓O���ނ����Ƃɍ\������Ă��܂��B
�@���S����̂́A�J�i�\�L���ꂽ�e��̌ŗL�����̈Ӗ���������Ă���Ă��邱�Ƃł��B���Ƃ��A���J���J���i��u�\�[���[�K�i�V�v�́A�\�[�͊ƁA���[�́u���v���a�������́A���������āu�Ǝ��ҁv�Ƃł������Ӗ��ł���Ƃ��A�����̂��Ƃ��u�j�[�r�`�v�ƌ����̂́u�������v�ŁA�v�����̍ŏ��̌������n�c�ł���Z���ŁA�����ɂ��܂��Č��������Ƃ���A�Z������̍��������ƈ��������čȂɂ��Ă��܂������Ƃ���R������A���X�̐��������Ă���̂ŁA�ǂ�ł��Ĕ����ɂȂ����悤�ȋC�������肵�܂��B
�@���J�̗l�q�Ȃǂ̋M�d�Ȏʐ^�i��ʐl�����Ă͂����Ȃ���ʂ��A���̐l�͎B�e������Ă����ł��ˁj�Ⓡ�̌����}�����Ă��āA�����s����ł��B
�i�Q�O�O�O.�P�P.�P�Q�@�ǁj

|
 |
�u�V�쓈�T���`���X�V���Ɖ���S�N�v�@�@�@�����V��Ё@�ҁ@�@�@�����V���
�@�@�@�Q,�T�O�O�~�{�Ł@�@�@�P�X�X�X�N�X���P�T���@��P�����s
�@���X�V���Ƃ����A��������̂P�W�X�R�N�A�����������Ƃ��问�����Ԃ��ɕ������l�ŁA���̂��Ƃ��L�^�����u�쓈�T���v�͓����̗������u����Ă�����m���ŋM�d�ȕ����ƂȂ��Ă��܂��B
�@���R�Ȃ̂ł��傤���A�����V�Y�����������̂��P�W�X�R�N�Ƃ������Ƃ������āA�����V��Ђ��n���P�O�O�N�̋L�O���ƂƂ��āA�u�쓈�T���v�ɕ`����Ă��鉫��̎p�����̌�̂P�O�O�N�łǂ��ϑJ�𐋂����̂��Ƃ������_����A�T�Q��̘A�ڂ�V���Ɍf�ڂ��܂����B���̖{�͂�����P���ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B
�@�ߔe�̏��X�ōw�������̂ł����A���������ǂ̏��X�ł����̖{�͐V���R�[�i�[�ɕ��ς݂ɂ���Ă��āA�x�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă���悤�ł����B
�@���X�̑��Ղ����ǂ�Ȃ���A�����Ƃ̗l�q���͂��߁A��ʁA�`�p�A�x�@�A����A�����A�R���Ȃǂ̍��ڂ�݂��ďq�ׂ��Ă��܂��B
�@���̂ق��A��k�哌���̓y�n���L�������g�Ɗԁi�p�C�p�e�B���[�}�j�`���̋��������A����Ɠ��̖咆�Љ�̉���A����̖����^���̐��ҎӉԏ��i����͂� �̂ڂ�j�̂��ƁA�j�����̎Ќ���Ƃ��ĉh�����ҁi�`�[�W�j�̂��ƂȂǂȂǁA�����[���b�肪�����f�ڂ���Ă��܂��B
�@�u�쓈�T���v�̕����{�����邻���ł����A��������̂܂ܓǂނɂ͂�����ƍ��C���v��܂����A������V���Ɍf�ڂ������̂Ȃ̂ŁA���l�ɗ����ł���悤�ɂ܂Ƃ߂��Ă��邵�A�ʐ^�͑������c�Ƃ������ƂŁA����t���[�N�͈�ǂ̉��l����ł���[�B
�i�Q�O�O�O. �S.�R�O�@�ǁj
�@�@�@�@
|
 |
�u����`���̊�@�Ɛ_�X�v�@�@�@�J�쌒��@���@�@�@�u�k�Њw�p����
�@�@�@�P,�O�O�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�U�N�S���P�O�����s�@�@�@�P�X�X�X�N�R���Q�Q���@��R�����s
�@���҂́A�����w�҂œ��{�n���������̏����Ƃ����������������A��g�V���́u���{�̒n���v�u���E���{�̒n���v�i��������������߁j�Ȃǂ̒��҂ł�����A�n���Ɋւ��Ă̑��l�҂ł��B
�@��P�͂ł́u���A��̉���v�ɂ��Ę_�l���A����𗝉�����̂ɂ����Ƃ���Ȃ��͉̂���ŗL�̐_�̑��݂ł���A��������������ꍇ�A����͓��{�{�y�Ƃ̉�ꉻ�Ƃ����Ռ��ɑς���Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�����ĉ���́u�쓇�����������v��ݒ肷�ׂ��ł���c�Ǝ咣���Ă��܂��B�ǂ��ł��A��������Ȃ��ł����i���̏ꍇ�A���̂悤�ɔ������͂��������Ƃ����_�]�͑�D���ł��j�B
�@��Q�͂́A���|�l�V�A�Ƃ͉����Ƃ�������N����A���M�i����Ԃˁj��ʂ��ĊC�l�i���݂�j�̓����l�����肵�āA����̎��ԂƋ�Ԃɂ��đz����y���܂��B
�@��R�͂́A�{�Â┪�d�R�̉S�A���X�V���̕Ӌ������Ȃǂ̗�������Ȃ���A�l���ł̐��E�����܂��܂Ȋp�x���番�͂��A���̎��Ԃ������Ȃ܂łɖڂ̑O�ɒ��Ă������̂ƂȂ��Ă��܂��B�����̈�ۂƂ��ẮA���̑�R�͂��i���o�[�����ł��B�l���łȂ炱�̖{�A���Ċ����B
�@�w�p�I�ŁA�ǂ݉����\���ł��B
�@�Ƃ���ō��̕\���A�ǂ������킩��܂��H��ڂł��̂ւȁ[�Ǝv�����l�́A�ʂł��B
�@�����͉���{���A�������ł��B
�i�P�X�X�X. �W.�Q�Q�@�ǁj
�@�@�@�@
|
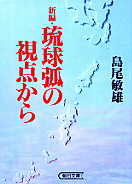 |
�u�V�ҁE�����ʂ̎��_����v�@�@�@�����q�Y�@���@�@�@�������Ɂ@�@�@�U�V�O�~�{��
�@�@�@�P�X�X�Q�N�W���P���@��P�����s
�@�Y�o�������āA���̃z�[���y�[�W�̖��O�́A���̖{��ǂ�ł������߂Ă����\�z���������������̂ł��B�����擇�n�������łȂ��A�����𒆐S�Ƃ���������̕����̔��M�n�܂��Ă����A���{�͓�ɂȂ����Ă����킯�ł�����ˁB���̖{��ǂ�ŁA�����ʂ̎��_�������Ƃ������������߂Ă������̂Ȃ̂��ȂƊm�F�ł����悤�ȋC�������킯�Ȃ̂ł��B
�@�����q�Y�Ƃ����ƁA�w������Ɂu���̞��v�Ȃǂ��������������Ȃ���ǂL��������i���e�͂�������Y��Ă��܂��Ă��邪�c�j�A�������ƂƂ��ẴC���[�W�����������̂ł����A�펞�������ɒ���������A�����̐l��������ɂ����肵�āA���ǂ����ɏZ��ł��܂����悤�ŁA�܂��ɗ����ʂ̎��_���炳�܂��܂ȓ��@���s���Ă���l�̂悤�Ȃ̂ł��B
�@���̖{�́A�u�����q�Y�S�W�v�i�S�P�V���E�����Ёj�̂Ȃ�����A�쓇�Ɋւ���G�b�Z�C��V���ɕ҂��̂ŁA��ꕔ�ł̓��|�l�V�A�Ɨ����ʂɂ��ďq�ׂ���A��ł͂P�X�T�T�N����P�X�V�W�N�ɂ킽���Ă̑����̋I�s�������ڂ����Ă��܂��B
�@�ǂ�ł݂āA�쓇�ɂ��Ă̎��삪�������ƍL�������悤�ȋC�����܂����B
�@�����ɂ���x�s���Ă݂����Ȃ��c�B
�i�P�X�X�X. �R.�Q�R�@�ǁj
�@�@�@�@
|
 |
�u�C��̓��v�@�@�@���c���j�@��
�@�@�@�@��g���� �@�@�@�@�T�U�O�{��
�@�@�@�@�P�X�V�W�N�P�O���P�U�����s�@�P�X�X�W�N�S���U���@��Q�R�����s
�@�����w�̌��ЁA���c���j�̗��j�I�����ł���܂��B
�@�u�܂������v������ƁA���t�����a�R�U�N�U���ƂȂ��Ă���̂ŁA�P�s�{�̏��ł͂��̍��Ɋ��s���ꂽ���̂Ƃ킩��̂ł����A���̒��Ɂu�R�O�N�قǑO�ɁA���{�l�͂����ɂ��ēn���Ă������Ƃ������Ƃɂ��ď����\�������Ƃ�����v�Əq�ׂĂ��邱�Ƃ��炷��ƁA���̖{�͂��̕��������a�����ɑk����̂ƌ����܂��傤�B
�@�����ׂ��������ɓ��e�����\�w�p�I�Ȃ̂ŁA�����Ƃ����ȒP�ɃR�����g���Ă͂����Ȃ��i�ȒP�ɃR�����g����\�͂��Ȃ��j�̂ŁA�\���̌��t�����p���܂��B
�@�u�����́A���{�����̑c�悽���͂����Ȃ�o�H�����ǂ��Ă��̗Ɉڂ�Z���B�ނ�͈��Z�p���g���ėy���������u�C��̓��v��k�サ�A����̓��Â����ɓn�������̂��c�B���V�̎��̕Y���E��L�̕��z�E�l�Y�~�̈ڏZ�ȂLjꌩ�����Ȏ�������|��ɁA�ŔӔN�̖��c�i1875-1962�j�����U�̒~�ς��X���č\�z�����Y��ȉ����v
�@�\�\�ǂ��ł����B��������̑�]���O�Y����ł�����˂��B
�@���̖{��ǂ�Ŗ�Q�N�������A���^�N�V�����̓������͑����͒m�����g�ɂ��Ă���i�c��������Ȃ��A�������Ƃ����i�j�̂ŁA������x�ǂݒ��������āA�����n���̂���_�]�����Ă݂����Ǝv���Ƃ�܂��A�͂��i���ȁj�B
�i�P�X�X�X. �Q.�Q�P�@�ǁj
�@�@�@�@
|
 |
�u�����I�s�v�@�@�@����@���@���@�@�@���ԕ��Ɂ@�@�@�S�S�V�~�{��
�@�@�@�P�X�X�R�N�Q���P�T���@��P�����s
�@�ǂ̂������ԑO�Ȃ̂ł͂�����Ƃ����nj㊴���Ȃ��̂ł����A�S�̂Ƃ��Ẵ��`�[�t�́A�����Ɋւ���A�ʎj�Ƃ��������O���u�I�ȗ��j�������̓ǂݕ��c�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
�@����֘A�̑����Ƃ��ẮA���Ǒq�g�̗����̗��j�Ɋւ�����发�i���̂��́j�ƂƂ��ɂ��̖{���قڑ�P���̂悤�ȋC�����܂��B
�@���炭�Ԃ�Ƀy�[�W���߂����Ă݂�ƁA���̖{�A�ڎ����Ȃ���ł��ˁB�ŁA�_�]���悤�Ƃ���Ƃ�����x�����Ɠǂ�ł݂�K�v������B
�@�ł��A�u�Y�Y�v�̌ꌹ�Ƃ��A�u���̑D������Ă����v�Ƃ��A�u�A�J�n�`�̖ŖS�v�Ƃ��A���o�����E���ǂ݂��������ł�������Ɩʔ������B���܂����͂�����Ɩʓ|�Ȃ̂ŁA���̂����ǂƂ��ɂ܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���܂��B
�i�P�X�X�R. �Q.�P�R�@�ǁj
�@�@�@�@
|
 |
�u���������v�@�@�@���Ǒq�g�@���@�@�@��g�V���@�@�@�T�U�R�~�{��
�@�@�@�P�X�X�R�N�P���Q�O���@��P�����s
�@�v���Ώ�L�́u�����I�s�v�ƂƂ��ɁA���̂P�����I�L�i�������̃X�^�[�g�ƂȂ����P���������L�O���ׂ���P���ł��邱�Ƃ��A�܂������ċL�ڂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���炭������Ȃ��ĒT���Ă����̂ł����A����ƌ����܂�����A�E�t�t�c�B
�@�������߂ĉ���̒n�̂́A�P�X�X�R�N�̂Q���ł�������A���̖{�͂����Ƃ��̎��O�����c�Ƃ������ƂŔ������߂����̂������̂ł��傤�B���̖{�����s���ꂽ�̂͂P���Q�O���A��������������s�������܂������̍��ł�������A�V���Ɍf�ڂ��ꂽ�L�������Ă������ɔ����ɑ������c�Ƃ����R�g�̌o�܁A���тɋ��̃g�L���L�Ƃ����������̏��A���ł��育�����Ƃ��ē`����Ă��܂��A�n�C�B
�@���v���A�����ȒP�Ɏ�ɓ���ł��ǂ��������Q�b�g�����c�Ƃ����R�g�Ȃ̂ł��傤�ˁB�����{�Ƃ̏o��́A���̐l�̐l����L���ɂ���\�\�Ƃ������Ƃ�n�ł������悤�Ȃ��̂ł��i�z���g����j�B
�@�Q�l��������j�N�\�����āA�킸���A���̒l�i�I���܂��ς�ς�Ƃ߂����Ă݂�ƁA�����͓ǂݎ��Ȃ��������Ƃ��Ȃ�ƂȂ������A�����������̂��c�ȂǂƊ������āA�Ȃ��������̂�����܂��B
�@�����̑O�A���ǃZ���Z�C�̐��܂��K�₵�����Ƃł����邵�i�Q�O�O�O.�P�Q�j�A���_�ɗ����A��Ƃ����Ӗ�������A�߂������ɂ�����x�ǂ�ł݂����Ǝv���܂��B
�i�P�X�X�R. �P.�Q�X�@�ǁj

|