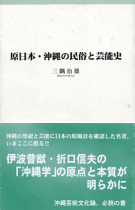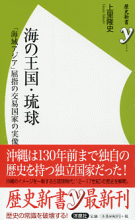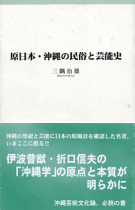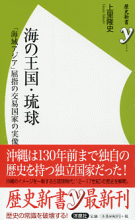|
「茶と琉球人」 武井弘一 著 岩波新書
780円+税 2018年1月19日 第1刷発行
近世琉球で、どのようなモノが、どこで生産され、誰が流通を担い、どのように消費されていたのか。
大国の狭間で翻弄されつつも、日常的に茶をたしなみ、“ゆたかに”農業型社会を築いていた人びとの暮らしぶりは?
「庶民の姿」と多様な「地域性」とに焦点を当て、「薩摩の世」時代の沖縄の自立を問う。いわばモノからみた琉球史!
著者の武井弘一は、1971年、熊本県人吉市生まれの琉球大学法文学部准教授。専門は日本近世史で、特に江戸時代の村社会と自然環境の研究している方のようです。
2016年、「江戸日本の転換点」で第4回河合隼雄学芸賞受賞。
著者は「はじめに」で、比嘉春潮の著述を引用しながら近世の沖縄人が非常によく茶を飲んでいたことを示し、「これほどまで沖縄で茶が普及していたことをふまえれば、“茶”をクローズアップしてみると、思いがけずに意外な史実、いや新たな琉球の国のカタチが見えてくるかもしれない」と記しています。
よく飲んでいた茶というのは、現在沖縄でよく目にする「サンピン茶」ではなく、球磨地方で作られてきた「球磨茶」です。
序章と第1章で近世琉球の政治や暮らしを概括し、第2章では当時の琉球で飲まれていた球磨茶がどのような道をたどって琉球と結びついたのか、そして第3章ではどのようにして琉球の社会に茶が浸透していったのかを解説しています。
終章では、近世琉球においては農業を土台とした持続可能な社会が形成されてきており、「琉球農業国家」というのが「茶と琉球人」を追い続けてきたことで見えてきた新たな琉球の国のカタチだったとし、琉球国=交易型社会という先入観をはぎとった琉球・沖縄史を研究していくべきだと結論付けています。
(2018.6.21 読)

|
 |
「沖縄伝説の歩き方」 徳元大也 著 沖縄文化社
1,650円+税 2016年9月16日 第1刷発行
「伝説を具体的な事物と関連づけること、伝説が「事実」だった時代の想いを共有すること、伝説の信憑性を少しでも回復させること、それが「伝説を歩く」ということである。」――という力強い前口上で、全36編の伝説話が写真と共に紹介されていきます。
それらは、自分の興味の赴くところとあまりにも合致しているので、ここに全部掲げておくことにしましょう。
「鬼餅の由来…内金城御嶽」、「識名坂の遺念火…識名坂」、「怪物ガーナー森…ガーナー森」、「普天満宮の由来…普天間権現発祥之地」、「黒金座主…大村御殿跡」、「真玉橋の人柱…真玉橋」、「琉球の開闢神話…ヤハラヅカサ」、「稲作発祥の伝説…受水走水」、「黄金の瓜子…イシキ浜」、「木田大時の占い…木田大時の屋敷跡」、「白銀堂の由来…白銀堂」、「奥武の観音像…奥武観音堂」、「飛び安里…飛び安里初飛翔顕彰記念碑」、「手登根大比屋…フッチャー石」、「袖離れ坂…野嵩石畳道」、「妖怪を封じた経塚の碑…経塚の碑」、「森の川と天女…森川公園」、「浜比嘉島のアマミキヨ…シルミチュー霊場」、「泡瀬ビジュル…泡瀬神社」、「屋良漏池の大蛇…屋良ムルチ」、「赤犬子の伝説…赤犬子宮」、「運玉義留…運玉森」、「多幸山のフェーレー…フェーレー岩」、「金武観音寺の由来…金武観音寺」、「夫振岩の由来…夫振岩」、「源為朝伝説…源為朝上陸記念碑」、「受剣石…テンチヂアマチジの御嶽」、「大宜味のブナガヤ…喜如嘉の七滝」、「天岩戸のクマヤ洞窟…クマヤ洞窟」、「無蔵水の由来…無蔵水の岩」、「宮古島の創世神話…漲水御嶽」、「ヨナタマと継子伝説…通り池」、「マムヤの悲恋伝説…マムヤの墓」、「野底マーペー…野底岳」、「赤口とティラ石…赤口」、「ティンダバナの伝説…ティンダバナ」。
いやはや、すごい。当方も沖縄を歩き始めてからすでに四半世紀以上が経つので、これらの大部分については聞いたことがあり、またかなりの場所を現地に赴いて見てきています。
この中で未踏なのは、ガーナー森、木田大時の屋敷跡、飛び安里初飛翔顕彰記念碑、フッチャー石、野嵩石畳道、運玉森、テンチヂアマチジの御嶽、喜如嘉の七滝、マムヤの墓、赤口の10箇所。
沖縄の「まちまーい」のガイドブックとしてなかなかのスグレモノ。沖縄に行く機会を捉えて、この本を参考に、未踏地についても見に行きたいと思います。
(2018.2.27 読)

|
 |
「新聞投稿に見る百年前の沖縄」 上里隆史 編著 原書房
2,000円+税 2016年 3月 7日 第1刷発行
おもしろい趣向の本。
戦前の「琉球新報」投書欄には、恋愛や友情、不満や悲哀、クレームや身の上相談など、多様で自由奔放な読者からの投書が掲載されていました。
この書ではそれらをジャンル別に紹介し、百年前の沖縄における人々の声と世相を浮かび上がらせています。
編著者は、当時の新聞を熟読整理して提示するわけなので、自ら思索し筆を執って書くということはあまり必要なく、こういう仕事も悪くないのではないかと思ったところです。(笑)
1912(大正元)年から1915(大正4)年までを範囲としていて、目次から内容を拾うと、恋愛・結婚、修羅場、友情、最近の若者は…、クレーム、お出かけ・旅行・異郷の地にて、質問・お願い、つぶやき、笑い話・珍事件、不満・苦悩・悲哀、わたしの主張、その他新聞記事がラインナップ。
公器といわれる新聞が、当時はここまで載せていたのか!と驚くほどの記事たち。こんな些細な、超ローカルな、こんなレベルの…。(笑) また、個人情報保護などという感覚は当時はなかっただろうからなあ。
百年前の沖縄は、明治維新からひたすら欧米列強に対するために国ぐるみで突き進んできた明治時代が終わり、大正は親たちが築き上げてきたものを相続し消費する時代とも言え、あえて言えば、昭和の高度経済成長の繁栄を享受し、消費している平成の時代と類似しているのかもしれません。
当時は大正デモクラシーが沖縄にも流入し、港湾都市だった那覇が大いに栄え、電気、鉄道、道路、娯楽施設などの社会インフラが整備され始めた頃だったでしょうか。
そのような時世を背景にした当時のリアルな人間模様を垣間見ることができ、なかなか興味深いものでした。
東京新聞に掲載された書評がありましたので、紹介しておきましょう。
・書評:新聞投稿に見る百年前の沖縄 上里隆史著 腹蔵のない庶民の声
(東京新聞2016年4月10日)
沖縄最初の新聞である琉球新報の投書欄「読者倶楽部」に掲載された投稿を、「恋愛・結婚」「つぶやき」「不満・苦悩・悲哀」など12の項目に分類して、百年前(大正元〜4年)の沖縄庶民の声を聞き取ろうとしたのが本書である。
ちなみにこの琉球新報は最後の琉球王尚泰の四男尚順を中心に、第1回の県費留学生として学習院や慶応義塾で学んだ高嶺朝教、太田朝敷ら旧琉球士族によって明治26年に創刊され、1県1紙制度により昭和15年に消滅した。現在発行されている琉球新報は、戦後に創刊された別の新聞である。
さて投稿の内容だが、「辻の遊廓」街の話は喧嘩騒動、中学生の徘徊問題なども含めて多彩。ふられた腹いせか「女郎税増税案」の意見も複数ある。巫女(ユタ)撲滅の提案もある。「国民的同化」を社是としていたからではないだろうが、投稿は沖縄語(ウチナーグチ)ではなく標準語で書かれている。
投稿男性は冷笑しているが、「男尊女卑の世をば、女尊男卑」にしたいと話す、頼もしい少女の姿もある。また、軽便鉄道の開通により「糸満婦人」の健脚や優美端正な体格が失われるとの懸念は、現在の車社会に生きる沖縄人の問題にもつながる。
当時の写真や広告・図版も豊富で、時代状況の簡潔な説明もあり、百年前の沖縄の日常が見えてきて興味深い。(与那覇恵子=東洋英和女学院大教授・近現代日本文学)
ちなみに評者の与那覇恵子は、NHKのドラマ「ちゅらさん」で沖縄風俗考証を務めた方でもあります。
(2017. 8.15 読)

|
 |
「沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで」 櫻澤 誠 著
中公新書 920円+税 2015年10月25日 第1刷発行
カバーの袖に記された概要は次のとおり。
『太平洋戦争中、地上戦で20万人強の犠牲者を出した沖縄。敗戦後、米国統治下に置かれ、1972年に本土復帰を果たすが、広大な基地は残された。
復帰後の沖縄は保革が争いながら政治を担い、「基地依存経済」の脱却を図る。だが95年の米兵少女暴行事件を契機に、2010年代には普天間基地移転・歴史認識を巡り、保革を超えた「オール沖縄」による要求が国に行われる。
本書は、政治・経済・文化と、多面的に戦後沖縄の軌跡を描く。』
全8章。1〜4章では本土復帰前における米国の統治政策を、5〜8章では本土復帰後における県政の保守と革新の交代によって、それぞれ時期区分・章立てがされています。
これは、著者が言うには、復帰前には米国の方針転換が、また、復帰後には県民による知事選択が、それぞれ政治的な変化を示しているからなのだそう。
ナルホド、読んでみると復帰後などは知事選挙や県議会議員選挙の結果等が詳細に語られ、それに合わせて時代的な出来事を整理していくというつくりになっています。誰々が知事だった時はこういう状況だったということを理解したいのであれば、ある意味わかりやすい書かもしれません。
琉球新報は2015年12月20日付けの紙面に、この本についての琉球大教授・我部政明の書評を載せています。しかし彼はこの本を、次のように消極的に評価しています。
『20世紀に沖縄に生まれた者、20世紀から沖縄に関心を持った人には、新鮮さは少ないと思う。「そうだったのか」という疑問氷解よりも、「そうだったよな」との懐古の感情を呼び起こす。』
『沖縄内部のみに焦点を当てるよりも、環境との相互作用から、沖縄の社会における政治的、経済的、文化的影響がどうように展開したのかを描くことが重要だろう。米軍基地にみる日本政府の沖縄への介入の結果、生じてきた現象が身近にあるからだ。閉じた沖縄の現状を描く本書は、より開かれた沖縄の現代史への跳躍台となっている。』
一方では、文章の書き方に問題があるのか、何度も読み直さなければならない場面が多くありました。
ふつうに書いたものをぎゅっと要約したような文章になっており、不必要な記載が一切なく、時によってはずっと前に出た主語を省略したりしているため、誰が、何を、どうした――という基本的なところが不鮮明になったりするのです。
まあ、文章は人によって合う、合わないがあるのでしょうけれど。
第7章(1990〜)あたりからは、自分が沖縄に興味を持って現実に直視してきた時代なので、とくに興味深く読むことができました。大田〜稲嶺〜仲井真〜翁長と続く各時代が概括されていてよかったと思います。
(2016.10.12 読)

|
 |
「幕末、フランス艦隊の琉球来航 −その時琉球・薩摩はどう動いたか−」
生田澄江 著 近代文藝社 1,300円+税
2014年 2月20日 第1刷発行
「薩摩の黒船」がもたらしたものとは――。ペリー来航の9年前、フランス艦隊は和好・通商・布教の目的を掲げて琉球に乗り入れた。薩摩支配の露見に怯える琉球、フランスに表だって退去を迫れない薩摩と、三者の思惑が交錯する激動の幕末を追う!(コシマキより)
著者の生田澄江は、法政大学大学院人文科学研究科日本史専攻修士課程修了で、明治維新史学会、洋学史学会会員デアルとのこと。
本書は、著者が大学院生だった1992年に書いた修士論文を、平易なドキュメント風に書き換えて20数年ぶりに世に問うたというものです。
この著作のポイントは3点。
ひとつは、外国船の来航の事態を単に「外圧」として捉えるのではなく、フランス艦隊の来琉前後のフランス側の背景に即して再検討すること。
2つめは、フランス艦隊がフランス人宣教師ほか1名を残していったことから、琉球王国が日清両属という国際的位置を隠蔽することに全力を尽くさなければならなくなっていった過程を明らかにすること。
3点目は、フランス側の通商要求に応じて琉仏貿易を開始した場合、薩摩と琉球の関係が表面化することとなり、琉球王国が実質的に日本の属国であることを明確にすることを模索し始めるが、その過程を明らかにすること。
はたして140ページの論考で、著者はその目的を達成することができたのでしょうか。
それは読んでのお楽しみということにしておきましょう。
(2016. 3.18 読)

|
 |
「雑誌とその時代 沖縄の声 戦前・戦中期編」 仲程昌徳 著
ボーダーインク 2,000円+税 2015年 4月20日 第1刷発行
仲程昌徳という人は、目の付け所がおもしろい。1943年テニアン島の生まれ、琉球大学文理学部国語国文学科を卒業し、同大学で勤めてきたという、どちらかというと学者肌の人なのだろうけれど、この本の場合、戦前及び戦中期に発刊された沖縄の雑誌に着眼し、その執筆者の想いや表現、内容などを丹念に読み込んでいき、その当時の社会的背景に迫るという作業を地道に行っているのです。
ほかにも、小説や雑誌など過去の様々な書物類の記述からその時代を明らかにしていくという手法をもとにものした著作がいくつかあり、きっとかなりこだわるタイプの人なのだろうと推測します。
取り上げているのは、雑誌「南洋情報」と「月刊文化沖縄」、そして「アララギ」や「心の花」などの各種短歌雑誌。
「南洋情報」や「月刊文化沖縄」が発刊された昭和15年には、戦中の国策により新しい刊行が一切不許可になり、これらの雑誌の発刊は「滑り込みセーフ的な事態」だったのだそうです。
創刊号の表紙を飾った金城安太郎の美人画(この本の表紙にも使われています)も、本の内容とともにそれ以降は変わっていくこととなり、雑誌を通して当時の時代性と文学活動の様子が見えてくるような内容になっています。
また、1926〜45年の約20年間に発行された本土の短歌雑誌に登場した沖縄の歌人と歌を丹念に見て行くことで、沖縄の昭和歌壇史が見えてくるようになっています。
どちらかというとマニアックで、好きでなければ読み進められないといった部類の本かもしれませんが、自分はそれなりに楽しめました。
(2016. 1.17 読)

|
 |
「沖縄の殿様 最後の米沢藩主・上杉茂憲の県令奮闘記」 高橋義夫 著
中公新書 880円+税 2015年 5月25日 第1刷発行
謙信の流れをくみ、鷹山を中興の祖と仰ぐ名門、米沢藩上杉家。その最後の藩主・茂憲(もちのり)は明治14年、琉球処分から日が浅い沖縄に県令として赴きます。沖縄本島をくまなく巡り、宮古・石垣両島まで及んだ視察で目撃したのは、困窮にあえぐ庶民の姿でした。
再三の改革意見は明治政府から黙殺され、志半ばで解任される茂憲。しかし、情熱を傾けた「人材育成」は、後年になって実を結びます。今日もなお沖縄で敬愛される上杉茂憲の2年にわたる奮闘の記録です。
数年前、沖縄陸軍病院南風原壕を訪れたときに、そこでガイドボランティアをしている方が、どこから来たのか訊いてきたので山形県だと答えると、「ああ、上杉県令の出身地ですねえ」と嬉しそうに言うのでした。そしてその後は、上杉県令の布いた善政についてひとしきり説明を受けたのでした。山形県人としてちょっぴり嬉しかったかな。
そのぐらいに沖縄県民に愛されている県令のようです。戦中の県令だった泉守紀などとは大違いです。
その奮闘の記録は、新書で手軽な本なので買って読んでいただくとして、その中の一節を読んで当時の沖縄本島の様子がよくわかったので、以下にその部分を引用して記しておきます。
「王城のあった首里、古来の商業都市の那覇を別格として、地方の各間切、離島の生活は、わずかな数の間切役人以外の住居は、細い丸木を柱とし、茅草で屋根を葺き、かろうじて雨風をしのいでいる。衣服は夏冬をわかたず一枚の粗悪な芭蕉布をまとい、食は甘薯、蘇鉄にとどまる。年中男は農耕、女は織りものに追いまくられているが、産出する米、粟、豆はすべて貢租にあてても足らず、貢糖のほかに私的に売る砂糖は、貢租の不足分の補填にあててしまい、なお余るものがあれば間切町村内の公費にあてる。「一粒の米粟自ら食するあたわず、一尺の反布自ら衣(き)るあたわず、これを要するに、一県の黎庶37万余人のうち僅々たる数百人を除くのほか、人間社会中些少の快楽あることも了解せざるものとす」――」
(2015.11.26 読)

|
 |
「壺屋焼入門」 倉成多郎 著 ボーダーインク 1,000円+税
2014年 7月30日 第1刷発行
著者は、那覇市立壺屋焼物博物館の主任学芸員で、壺屋焼の人間国宝・金城次郎が生きた明治時代以降の壺屋焼を研究テーマにしている方です。
その著者が、最近の知見を活かした手頃な壺屋焼の入門書のようなものがあればという要望を踏まえて、本書がいささかでもその役割が果たせるならば幸いだと考えて書いたものとなっています。
これまでの研究成果に基づいて、壺屋焼の歴史をたどり、その特徴、作り方、陶工たちとその作品、壺屋のまち歩きのポイントなどを紹介しています。
近世琉球陶器の黎明を告げる3人の朝鮮人陶工のこと、初期の壺屋焼に見る陶工たちの家譜、明治以降の壺屋焼の衰退と復興、民藝運動が壺屋焼にもたらしたもの、日本復帰後の現代陶芸など、壺屋焼をめぐる内外のトピックスについて多角的に詳述しています。それでいてなんなく読める、というつくりになっているこの本には敬服します。
付録(しーぶん)として書かれている、壺屋ゆかりの地を辿る、さいおんスクエアのシーサー、沖縄陶祖の墓へ、井戸・窯・工房・店めぐりなどの項は、壺屋の観光や散策の一助にもなることでしょう。
(2014.10. 1 読)

|
 |
「琉球の花街 辻と侏伶の物語」 浅香怜子 著 榕樹書林
900円+税 2014年 2月20日 第1刷発行
那覇の花街・辻に伝えられる民俗芸能ジュリ馬行列に関心を持っており、かつてホームページでそのことを調べていると、「浅香れい〜風流者たちの精神史」というページで当書の著者の論考に接することができ、当方と同じように調べていたり、その上実践までしている人がいるのだなと、その名前を認識はしていました。
その人が、女性の視点から辻とそこに住む女たちの生活の実相と社会的背景を描いた本を出したというので、すぐさま入手したものです。
著者は、群馬県伊勢崎市出身。玉川大学卒業後、日本大学大学院芸術学研究科で博士後期課程芸術専攻修了。春駒じゅり馬民俗芸能研究会、アリラン民俗芸能研究会・主宰。
琉球の花街として知られる辻は、女たちによる自治制度が確立されており、本土のものとは異なる成り立ちと性格を持っています。
辻に通う客との関係等々を歴史と伝承を踏まえて解明しながら、著者の活動のひとつである本土の門付け芸能としての「春駒」の継承、その伝播の南限としての琉球の「じゅり馬」との比較研究を通して、「辻」とは何かを明らかにしようという試みの書となっています。
「はじめに−辻の名芸妓の死」に続き、第1章の「琉球の花街」では辻地域のこと、旧廿日正月とじゅり馬、辻の戦後、現在のじゅり馬の風景を紹介し、続く第2章は女性たちの組織、もてなしと料理、盆切りと歳切りなどについて述べた「辻村女の里の暮らし」となっており、その後、「ジュリをとりまく社会的背景」、「辻村の形成とその背景を考える」、「辻とジュリがつむいだ琉球芸能」、「徐葆光が愛でた琉球の女性」と続き、「おわりに ― 本土の春駒から沖縄のじゅり馬へ」で締められています。
戦前期の辻村の詳細な略図が妓楼名入りで掲載されており、貴重。ほかに「那覇及久米村全図」や昭和初期のじゅり馬のカラー絵葉書などもあって、とても興味深く読むことができました。
全盛期の辻やそこで生活するジュリ、当時の那覇社会の様子などを知る上で、大事な資料となりました。
(2014. 9. 7 読)

|
 |
「沖縄を豊かにしたのはアメリカという真実」 惠隆之介 著 宝島社新書
762円+税 2013年 9月14日 第1刷発行
「歴史」のカテゴリーに入れてみましたが、親米的思想が強く感じられる1冊です。
沖縄県は、先の大戦で激しい地上戦が展開され、それから27年間もの間、米国の施政権下に置かれました。このことについて一般的な日本国民は慈悲のまなざしで同情の念をもっていますが、著者が言うには、実は沖縄の近代化はむしろ米国によって初めて達成されたのであって、米国統治が長かったことは沖縄にとってけっしてマイナスではなかったというのです。
それは一理あるでしょう。しかしだからといって、沖縄はアメリカに統治されていてとてもよかったですね、とはならないはずです。この右寄りの著者はさまざまなロジックを用いてそういうことを言おうとしているように思えるので、注意が必要です。
戦前の沖縄は亜熱帯特有の感染症が蔓延し、寿命も47歳と短命であったが、米国政府によるプライマリーケアの定着が奏功して、沖縄返還時には感染症は撲滅され、日本最長寿県の87歳を達成した。ところが現在は、沖縄の青壮年の死亡率は全国ワーストワンであり、これは戦後世代が米国統治時代を忘却した結果ではないか。
―――これが著者の考えのようですが、この一文だけでも極端なものの見方だということがよくわかると思いますが、いかがでしょう?
「沖縄を長寿の島にしたワニタ・ワーターワース女史」、「世界最高峰の看護制度があった沖縄」、「沖縄の教育を育てたハンナ米海軍少佐」、「沖縄産業の父・オグレスビー氏」、「沖縄の金融改革を進めた弁務官P・W・キャラウェイ」などの内容で、沖縄におけるアメリカ人指導者を礼賛しています。
彼らの功績を否定するつもりは全くありませんが、アメリカ人の彼らがいなければ今の沖縄はなかったと言いたげな一方的な論調には同調できず、むしろだからなんなのサと思いたくなります。
最終章では「沖縄県民ゆすり」発言報道で物議を醸しだしたケビン・メアと著者の対談となっています。自虐史観がお好きな方はどうぞ。
(2014. 3.14 読)

|
 |
「世界の沖縄学 沖縄研究50年の歩み」 ヨーゼフ・クライナー 著
芙蓉書房出版 1,800円+税 2012年11月 3日 第1刷発行
著者は、1940年オーストリア・ウィーン生まれの日本研究者。とりわけ琉球・沖縄や奄美の研究で国際的な評価が高く、また、国際琉球・沖縄学会(というものがあるらしい)の会長でもあるとのこと。
本書は、著者の研究成果のアウトラインを示すもので、琉球・沖縄研究を国際的視点から評価する立場で、沖縄大学地域研究所で行った講演をベースにまとめられています。
柳田國男から「君は沖縄よりも奄美大島の加計呂麻という島に行きなさい」と勧められて昭和37年に渡島したことや、外間守善からおもろの解釈を受けたこと、当時鹿児島県立図書館の奄美分館長をしていた島尾敏雄との交流などが書かれており、興味深い一面がありました。
しかしその反面、ヨーロッパ人の著者は長い間、文献学・文学の立場、いわば書物の中から日本学を追求せざるを得ない環境にあったようで、それは往来が飛躍的に発達した今となっては、残念ながら学問の手法としては古典的な雰囲気を感じさせます。
「沖縄研究の国際化」、「世界の沖縄学 ―沖縄研究50年の歩み―」、「沖縄のアイデンティティを考える」、「ヨーロッパ製地図に描かれた琉球」、「ヨーロッパの博物館・美術館保管の日本コレクションと日本研究の展開」、「ヴィーン歴史民族学派と日本民族学の形成 ―日本民族学が中欧の日本研究に及ぼした影響―」、「私の旅の日本」。
地図や美術館の日本コレクションについての部分は少々退屈というか、専門的でマニアック。しかし、クライナーという人物がどう沖縄・奄美に関わったかが垣間見える部分は面白かったと思います。
(2014. 1. 5 読)

|
 |
「古代の琉球弧と東アジア」 山里純一 著 吉川弘文館
1,700円+税 2012年 5月 1日 第1刷発行
古代の琉球弧は、これまで律令国家の版図外の異域と見られ、「日本の歴史」の埒外に置かれていました。しかし、近年は境界領域の問題として、また列島の古代史という視点から注目を集めるようになっています。
当書は、考古学の成果と文献史学のこれまでの研究の蓄積をもとに、古代の琉球弧の歴史過程を、東アジアとの関係をも視野に入れながら記述されています。
琉球弧において文字による記録が現れるのは、1650年の「中山世鑑」が最初で、それ以前の琉球弧は「日本書紀」や「続日本紀」などの正史、「延喜式」、中国の「随書」など極めて限られた史料しかなく、しかも断片的な記事が散見されるのみです。
こうした文献史料の欠を補うのが考古資料ですが、近年奄美諸島では、倉木崎海底遺跡や喜界島城久遺跡群などの発掘成果が相次いでおり、古代琉球弧の歴史的展開を理解する上で重要な史料が増えてきています。
これら近年の研究成果を取り入れ、古代日本と南島の交流を改めて見つめ直す作業をしているのが特徴となっています。
大きな章立ては、「7世紀の琉球弧と東アジア」、「8〜9世紀の「南島」と遣唐使航路」、「モノから見た琉球弧」、「10〜13世紀の琉球弧と東アジア」。
琉球弧で産するヤコウガイが「螺杯」というさかずきに加工され、日本の絵巻に描かれているのを図示するなど、わかりやすい記述で楽しめました。
城久遺跡群の発掘などによって、古代琉球弧の捉え方は大きく変化せざるを得なくなっているのですね。
(2013.10. 2 読)

|
 |
「琉球王権の源流」 谷川健一・折口信夫 著 榕樹書林
900円+税 2012年 6月21日 第1刷発行
琉球王権の成立の謎に迫る、谷川健一・折口信夫の両巨匠の揃い踏みによる論評本というので、購入。
第一尚氏王権の発祥について、折口信夫は「琉球国王の出自」という論文の中で、肥後佐敷の名和氏の残党が、沖縄本島の東南海岸の佐敷あたりに最初の根拠地を築いたとする仮説を展開しています。
谷川健一の生まれ育った郷里である熊本県水俣市は、その折口説に縁由があります。水俣市の大字浜には為朝が琉球に向けて船出したという伝説が残っており、船津という漁業集落には為朝を祀る祠もあったそうです。
水俣のすぐ北には佐敷がありその北が八代ですが、折口は、「おもろさうし」にみられる「やまと やしろ」という対句表現は、「やまと」は薩摩であり「やしろ」は肥後の八代ではないかと述べています。
収録内容は、谷川健一については「「琉球王国の出自」をめぐって」として、「日琉交易と日宋貿易」(初出「日琉交易の黎明」森話社、2008)、「英祖王と高麗・南宋」(書き下ろし)、「「琉球王国の出自」をめぐって」(同「国学院雑誌」第79巻第11号、1978)、「やまと・やしろ――薩摩と肥後八代」(同「青と白の幻想」三一書房、1979)の4編。
証明こそできませんがかなり確からしいと思える材料が提示されており、古代琉球を考える上で大いに参考になります。
折口信夫については、谷川の論考のベースとなった「琉球王国の出自――佐敷尚氏・伊平屋尚氏の関係の推測」(初出・伊波普猷還暦記念論文集「南島論叢」沖縄日報社、1937)を新字・新文体にしたものが掲載されています。
しかしこれが読みづらく、よく理解できませんでした。わずか70数年前の文章ではありますが、自分にとってはもはや古文のように感じられました。
(2013. 9.23 読)

|
 |
「知れば知るほどおもしろい 琉球王朝のすべて」 上里隆史・喜納大作 著
河出書房新社 1,400円+税 2012年 6月30日 第1刷発行
琉球王朝を舞台にしたNHK・BSドラマ「テンペスト」で時代考証を担当した上里隆史が、全国に生まれた琉球史ファンに、難解ととられがちな琉球の波乱万丈でおもしろい歴史をもっと平易に楽しんでもらおうと、若き琉球史研究家である喜納大作と共同して世に送り出した琉球史入門書です。
フィクションではない琉球史を知ろうとすれば、これまでは高価で難しい専門書を読むしかなかったのですが、そんな状況を打破るという意味ではなかなか画期的かもしれません。
第1章「王宮・首里城の秘密」では、首里城内の各場所の役割や、女官の位置取り、「京の内」の謎などについて書かれています。
第2章は、興味深い首里王府の仕組みを解説しています。それらは王府の中枢である評定所の役割、そこで働くキャリア官僚の様子、警察署と裁判所を兼ねた「平等所」の裁判と刑罰、国王一世一代の大行事である冊封など。
第3章は、「国王と士族、庶民のくらし」。歴代王のトピックス、国王の一日の生活、お妃さまの決定経緯、700以上もあった姓、命よりも大切な家譜とそれを管理する系図座のことなどを取り上げています。
第4章は、「琉球の神様と文化、風俗のふしぎ」。琉球独自の信仰と神女の組織、琉球の石造アーチ橋、琉球の海を走った馬艦船、客の選択は遊女側にある女性だけの村「辻」、琉球と日本の髪型比較など。
文章はすべて「現代語」で書かれており、極めて平易。琉球王国に関する基礎知識などは不要で、まったく気軽に読めます。というか、あまりに気軽に読めてしまい、読了するまであっという間でした。
(2013. 8. 2 読)

|
 |
「私の日本地図8 沖縄」 宮本常一 著 未來社
2,200円+税 2012年 4月25日 第1刷発行
1970年に同友館という出版社から刊行された「私の日本地図8 沖縄」を原本に、2012年に再発売されたもの。今、宮本常一はブームを迎えているようで、宮本の著作はけっこうあちこちで発売されているような気がします。
宮本が初めて沖縄の地を踏んだのは1969年のことで、わずか6日間の旅程だったようです。その6日間に本島、久米島、津堅島、浜比嘉島、伊江島などを巡っており、そのときのことを雑感や写真でまとめたのがこの本です。
その記録の、特に写真で感じるのは、アメリカ世だったあの時代の沖縄から、今に通じるものもたくさんあるとはいうものの、いかに多くのものが失われてしまったか、ということ。
それらは、車道と歩道の機能分化が進んでいない道路に沿って建つ赤瓦の家々だったり、先の戦で緑が失われまばらな建物の中で360度見通しのきく大地、琉球政府の入ったモダンな建物、琉球大学の構内にひっそりと建つ守礼門、港内に繋がれたたくさんのサバニ、豊年祭でセーラー服のまま太鼓を叩き踊る女子高生、境界のない久米島空港、頭上にバーキを載せて歩く女性、横文字オンリーの看板が並ぶゲート通り、などなど。
記録の中で宮本は、「単に沖縄の本土化をはかるだけが沖縄復帰の意義ではない。沖縄人のための沖縄をいかにして築いてゆくか」であると述べています。沖縄を語るうえで、現在に至っても最も重要な問題であると思いますが、宮本がそのように記録してから40余年が経過して、それが現実のものになっているかというと、いまだに果されていない課題であると言わざるを得ないのではないでしょうか。
1970年当時の付録地図付き。那覇、那覇から摩文仁まで、糸満、保栄茂(びん)、慶良間・粟国、久米島をまわる、基地付近の町、津堅島、浜比嘉島、伊江島へ、琉球博物館、沖縄雑感――の全12章。
伝わってくるものが多い良書でした。
(2013. 2. 2 読)

|
 |
「琉球古道 歴史と神話の島・沖縄」 上里隆史 著 富山義則 写真
河出書房新社 2,200円+税 2012年 3月30日 第1刷発行
沖縄に存する古道についてあちこち探索して歩いているところであり、この本を読んで、さらにまだ見ぬ古道の名残りを体験しようという魂胆で購入。で、読んでみて、自分の興味にドンピシャ!であることが判明。
現代の我々が毎日のように使う「道」。何気ないその風景には歴史が地層のように積み重ねられている。その成り立ちはどのようなものであったのだろう。(「はじめに」から)
上記のようなものの捉え方には強い共感を覚えます。とりわけ「何気ないその風景には歴史が地層のように積み重ねられている」というあたりにヴィヴィッドに反応してしまうし、その成り立ちについて思いが行ってしまうあたり、自分も同じなのだ。
全4章は、「琉球神話と巡礼の道」「海上の道と古琉球」「すべての道は王宮へ通ず」「沖縄県の誕生と近代の道」。
「琉球古道」という言葉は、歴史的に使われている用語ではなく、琉球王府によって築かれた「宿道」(すくみち)、明治以降の鉄道、さらには「海上の道」なども範疇に含めた造語だということです。
記述されているもののうち、すでに体験済みなのは、東御廻りの聖地群、受水走水、首里城周辺、運天港周辺、長虹堤跡、綾門大道、真珠道、経塚、安波茶橋、当山の石畳、フェーレー岩、喜納番所、玉城グスク、戻る道、パイプラインなど。
反面、未体験は、辺戸の御水取りの道、那覇の末吉宮参詣道、今帰仁のハンタ道、浦添城下の仲間集落、ペリーの旗立て岩、恩納村仲泊から真栄田にかけての国頭方西街道の遺構、新しくなった嘉手納ロータリー、平安名のワイトゥイ、うるま市の旧天願橋など。
「道」に対しては、まだまだ興味は尽きません。現場に立って考えてみる。これが大事。
この本を契機に、行ってみたいところがまた増えました。
(2013. 1.12 読)

|
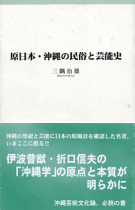 |
「原日本・沖縄の民俗と芸能史」 三隅治雄 著 沖縄タイムス社
1,524円+税 2011年10月31日 第1刷発行
2012年末の沖縄旅行のお供に連れて行った本。沖縄で、沖縄関連の本を読む、というのも悪くありません。
沖縄の祭祀と芸能に日本の原風景を確認した名著、いまここに甦る!! 伊波普猷・折口信夫の「沖縄学」の原点と本質が明らかに。沖縄芸能文化論、必読の書。――というので、これは自分にぴったりデアルと、大きな夢と期待をもって読ませてもらいました。少々難しいところもあったけれど、期待に違わぬ内容でした。
1972年というから沖縄が本土復帰した年の12月、第三文明社というところから文庫として刊行された「原日本おきなわ」に、若干の訂正を施して前篇とし、その年以降現在に至るまでの沖縄の伝統芸能の動向を追った記述を後篇として、まとめられたものです。
著者がこの本を刊行するにあたって2011年に書いた「あとがき」で言うには、1958年に初めて沖縄の土を踏み、基地化し、変質し、リトル・アメリカのような沖縄の姿を見て慨嘆したものの、それはとんだ早とちりであったと。翌日からの旅では、基地化ぐらいでもとの文化を失くすほど沖縄はヤワではなかったことを痛感したようです。
国頭の村々では、婦人たちが芭蕉布を丹念に紡ぎ、古謡をうたい、絣の着流しに白鉢巻でエイサーを踊っているのを見、ウンジャミで白衣を着た神女たちがアシャギに集まって神酒を人々に授け歌舞に興じていた様子を見て、いたく感動した――と書いています。
そして、何ゆえ、かくも沖縄人は、郷土の旧文化に執着するのか? また、何ゆえ、かくも遠い昔からの文化が沖縄人たちの心を燃え立たせるのか? その因をたずねたい!・・・と。
そういう想いで、本書は書かれたようです。スバラシイではありませんか。
前篇は、「民俗から芸能・舞台芸術へ」のサブタイトルで、古代社会と民俗〜古代の芸能〜琉球王朝の芸能〜民衆の歌と踊り〜舞台芸術の明治・大正・昭和――といった流れで解説。
後篇は、本土復帰の後に興った組踊の再生、沖縄演劇の復興、舞踊・音楽の興隆の陰にある課題、琉球芸能の他地域への広がりなどについて記述しています。
全体として、古代から現在に至るまでよく研究し、長い間見守っているという印象。
好ましいのは、文章全体に沖縄の民俗・芸能を慈しむようなやさしい眼差しが感じ取れること。ああ、この人は本当に沖縄の民俗・芸能を愛し、行く末を案じているのだなあと、実感できます。
新書としては高価な1,600円(税込)。でも、その価値はあったと思います。
(2012.12.25 読)

|
 |
「石垣島唐人墓の研究 -翻弄された琉球の人々-」 田島信洋 著
郁朋社 1,500円+税 2011年 7月18日 第1刷発行
石垣島の市街地より西へ約4キロのところに、石垣市唐人墓という観光地があります。その墓の紹介文として、「1852年、イギリス船に奴隷として乗せられた中国人が石垣島に逃げ込み、島人にかくまわれたが、イギリス兵が見つけ、128人を殺害してしまう。その霊を祀る」――と記されていますが、この記述は年代以外すべて誤りなのだそうです。
この石垣島唐人墓が誤って紹介されている現状をなんとか改めたい、また、江戸の末期、琉球国の南の島を舞台に起った、ほとんどの日本人が知らない国際的な事件を広く伝えたい、との思いで書かれたのがこの本です。
「琉球王国評定所文書」を中心に、それで欠けた部分を「島津斉彬文書」で補いながら、それらを日誌風に現代文に書き直して時系列的にまとめたもの、との体裁になっています。その意図は悪くないと思いますが、それらを解説する部分が少ないからか、読んでいるうちに著者が何を言わんとしていたのかを見失ってしまいそうになるといううらみがあり、一般人にとってはもう少しわかりやすい構成にしたほうがいいかなと思いながら読みました。
当時、琉球国の光の部分はもっぱら首里を中心にありましたが、薩摩を恐れ、中国に遠慮し、その間を巧みに渡り歩いていく上で、役人たちは卑屈になることに馴らされ、やがて自分たちの卑屈さにさえ気づけなくなってしまいます。そしてそのしわ寄せは、首里から遠く離れた八重山の島民に次第に重い負担としてのしかかっていったわけですが、その様子が随所に読み取ることができます。
章立ては、「サンビャクトゥヌピトゥヌパカ(三百唐人墓)」、「事件の発端」、「事件の急展開」、「唐人護送へ」、「事件の新展開」、「苦悩の始まり」、「唐のお指図」、「帰国の途へ」、「石垣市唐人墓―虚像の背景」。
「唐ご都合向き」を最優先させた琉球政府。白い米を食べ、薬を与えられ、医者に診てもらう唐人のかたわらに、人頭税と飢餓と疫病に苦しむ自国の民である島人がいる、という異様な風景。
琉球国の陰の部分を照射すると、卑屈な首里王府の役人と哀れな島民の姿が見えてくるという、虚しくも悲しい後味が残る作品でした。
(2012. 9.11 読)

|
 |
「琉球の時代 大いなる歴史像を求めて」 高良倉吉 著 ちくま学芸文庫
1,300円+税 2012年 3月10日 第1刷発行
現代沖縄・琉球史研究陣の旗手による「琉球史」。
琉球王国が、内側からの視点のみならず、アジアの海原に位置づけられ、さまざまなまなざしを交叉させることで、ダイナミックなドラマとして綴られています。
1980年の作品ですが、その後1989年に地元ひるぎ社から新版を出したものの絶版。そしてこのたび(2012年)、ちくま学芸文庫として再刊されたものです。志向のロングテール現象があるといわれるこの時代、いい本はこのように再版されて手に入れることができるのですね。(詠嘆)
著者は、「沖縄」ではなく「琉球」という表現を用い、「琉球」が内包するダイナミックな世界を復権させたい、今を生きる沖縄県民のために「琉球」を我々の側に取り戻したい――という強い意志を込めて、タイトルを「琉球の時代」としたといいます。そして、学術書として書くのではなく、なるべく読み物風にとりまとめてみたいと考えたとのこと。
その意図は見事に実現されており、琉球という国の全体像がつかめ、そこに生きた人の息づかい、激しい攻防、悲しみや喜びの声、危機に直面したときの苦悩のため息、それに立ち向かうための論議の場面などが、当時の琉球の風景と共に、手に取るように伝わってくるものとなっていました。
多くの資料をベースに難しいことを簡単に、しかも読者にとって興味深く読めるものにすることというのは、なかなか一般的な学者にとっては至難なことで、蓄積を噛み砕き、自分のものとして提出できる高みにたどりついた高良倉吉のならではの表現力と言っていいのではないでしょうか。
「マラッカにて」をプロローグとし、「黎明期の王統」「琉球王国への道」「大交易時代」「グスクの世界」「尚真王の登場」「琉球王国の確立」の6章。そしてエピローグに「古琉球と現代」。
与那原恵による巻末解説もなかなかいいです。
平易に読める良書。この本の位置取りとしては、1冊目は琉球史の概説(入門)書として、沖縄・琉球に関する「2冊目の入門書」といったところでしょうか。
(2012. 8.29 読)

|
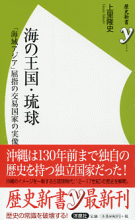 |
「海の王国・琉球 「海域アジア」屈指の交易国家の実像」 上里隆史 著
洋泉社歴史新書 890円+税 2012年 2月21日 第1刷発行
「古琉球の歴史は記録が豊富というわけではなく、その実態は謎が多い。しかし史料がまったく存在しないわけではない。残されたわずかな史料を丹念に調べ、空白地帯にパズルのピースを埋めていく作業が求められている。
古琉球の実態を明らかにする作業は、史料が存在しないことを理由に最初から「結論」を用意し、恣意的な史料解釈によって荒唐無稽な仮説を唱えるものでもなく、また史料に書いてあること以外のことはいわない、いわせないという「実証原理主義」に陥るのでもなく、実証と仮説のバランスのとれた分析がもっとも必要とされているのではないだろうか。
古琉球の全体的な状況をまず把握し、それらを残された史料と突き合わせ、蓋然性が高いかどうかという面から突破していく試みが、古琉球を解明する一つの有効な方法であるように思う。」
――「あとがき」より。
この基本姿勢にはまったくもって同感であり、その姿勢が貫かれている良書です。
琉球の歴史を語る際にはこれまで、「日本」か「中国」かという原理的オリジナリティを抽出し、起源や出自でもってその「本質」を見出そうという考え方が多く用いられてきたように思いますが、そういった考え方はもうやめにしたほうがいいのではないでしょうか。
そして、むしろその「本質」とは、どのような文化が流入し、どのような人々が入って来ようとも、南西諸島に住む人々が数百年の歴史の過程でそれらを選択的に受容し、自己流に改造し、「琉球」と呼ぶしかない主体を自らの手で作り上げてきた、ということにあるのではないでしょうか。
日本社会の中に「琉球・沖縄」という独自の歴史的経験を持つ地域があった事実を知ることは、画一的ではない、多彩でバリエーションのある豊かな日本社会の創造に大きく寄与するのではないかと考えます。
「海域史」という新しい視点を提示したうえで、全6章。「境界の喜界島・異界の琉球」、「港湾都市・那覇の誕生」、「琉球の大交易時代」、「海の王国・古琉球―この国のかたちについて」、「交易国家・古琉球のたそがれ」、「古琉球とは何か」。
新書版でありながら、読者に訴えるものは大きなものがありました。
(2012. 6.16 読)

|