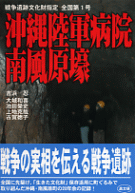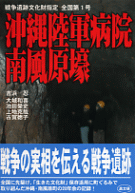|
「ひめゆり 沖縄からのメッセージ」 小林照幸 著 角川文庫
857円+税 2010年 7月25日 第1刷発行
「21世紀のひめゆり」(2002年11月、毎日新聞社刊)を再編集、加筆・修正し、改題して文庫化されたものです。
1945年3月26日からおよそ90日間、非戦闘員であるはずの「ひめゆり学園」の320余名は日米両軍が激突する戦場へと動員され、13歳から19歳までの無辜の227名が死亡しました。
ガマの内部では「学生さーん、水をくれー」と叫ぶ負傷兵を看病し、寝静まった夜のガマにはウジが患部を食う音が密かに響く。
最終局面では、降伏しようとする日本兵の背を日本兵が撃ち、美ら海が血の色に赤く染まり、ともに従軍した女学生たちが銃弾で、手榴弾で、次々に息を引き取っていく。
そんな“人間が人間でなくなっていく”戦場を体験して生き残り、戦場体験を語り継ぐ語り部となった宮城喜久子。
その先輩で、1フィートの会で記録映像を通じて沖縄戦の実相を伝える活動をつている中村文子。
本書はこの二人に焦点を当てつつ、戦後の日本と沖縄の実態に迫っていく――というつくりになっています。
戦時中の実相を詳細に記すというものではなく、二人の戦争体験の記憶やまなざしを通してその後の沖縄をめぐる情勢を追っていくものになっていて、文庫版ながら全540ページ強の重厚なもの。
活字が小さくびっしりと書かれています。文字が多く値段が安いのがコストパフォーマンスだとしたら、この本は満点以上でしょうね。(笑)
全6章で、「沖縄戦と9.11を生き抜く」、「建立「ひめゆりの塔」」、「星条旗への反乱」、「日本(本土)への愛と憎しみ」、「映像の中の沖縄戦、証言の中の沖縄戦」、「語り継ぐ戦争」。
「文庫版あとがき」で2002年以降の“それからのひめゆり”について20ページにわたって追加して記述されているほか、「解説」は外務省のラスプーチンといわれた佐藤優が12ページ書いています。
ひめゆり関連の書物を読んでいつも思うのは、幸いに命を失わずに済んだ人たちが、幾多の友人を失いながらもなお、生きていかなければならないことの重責やしんどさについて。
このたびの東日本大震災で生き残った震災地の人はもちろん、広い意味ではわれわれも同じであり、亡くなった人々のためにもわれわれは「生きること」にこれまで以上に真摯に取り組まなければならないのでしょう。
(2011. 5. 3 読)

|
 |
「激動期を走る」 仲本安一 著 琉球新報社 1,238円+税
2010年 8月 7日 第1刷発行
2009年に「人物列伝 戦後沖縄の政治家たち」を琉球新報社から上梓した沖縄の元革新政治活動家・仲本安一が、こんどは自分の半生記を綴りました。いやぁ、バイタリティにあふれていますね。(笑)
「はじめに」で氏は、「私の半生を一口で語るならば、戦前―戦中―戦後、そして復帰運動などの激動期をただひたすらに走り続けた日々であったように思う。(中略)後ろを振り向かず、前に向かって進むだけであった」と述べています。すごいすごい。拍手♪
内容を読んでみると、本当にそのとおりで、高校卒業後は弁護士を目指して上京し、そこで沖縄の軍用地強制接収問題があまりに小さい動きにしかなっていないのを目の当たりにして政治運動に参加し、それ以来、青年運動、労働運動、大衆運動などに身を捧げ、アメリカの軍事支配からの脱却と一日も早い祖国復帰を目標にして戦ってきたようで、そんな様子がよ〜くうかがわれます。
そして苦節27年、沖縄の日本への施政権返還は実現したものの、その後さらに37年たっても(2010年現在)米軍基地による被害と忍従はなおも続いており、著者は、何のための祖国復帰だったのか、自問自答が続く昨今だと嘆いています。
祖国よ、冷たい母になるなかれ!と叫ばずにはいられません。
第一部私の回顧録、第二部評論と随筆、第三部関連資料というように分類されていますが、何といっても圧巻は第一部。幼少期、小学・中学・高校・大学生の時代、青年運動時代、労働運動時代、市議会議員時代、県議会議員時代、党務活動の時代、会社役員時代の各時代を詳述。特に政治活動以降の、多くの沖縄の政治家たちとの丁々発止の交流は、みどころたっぷりです。
世の中が熱かった時代の政治は、生き生きとしていて実におもしろいですね。
(2011. 3.27 読)

|
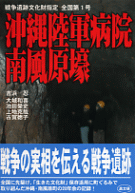 |
「沖縄陸軍病院南風原壕」 吉浜 忍 編 高文研 1,600円+税
2010年 6月23日 第1刷発行
戦争遺跡の文化財として指定された第1号である「沖縄陸軍病院南風原壕」を保存、公開、活用していくための、南風原町の関係者の平坦ではなかった取り組みについての報告書。
南風原町が沖縄陸軍病院南風原壕を全国で初めて、太平洋戦争の戦跡として町の文化財に指定したのは1990年。当時は戦跡を文化財として指定する基準がなく、県は文化財指定する法的根拠がないとして受け付けなかったそうです。
そのためまず町が町としての指定基準を改正し、その後、国の基準も1995年に改正されたとのことです。
南風原町は、字別の戦災悉皆調査、南風原壕の徹底調査などを実施し、その成果等を踏まえて壕を保存活用するという目標を掲げ、2007年6月からの公開にこぎつけました。
全7章からなっており、「沖縄戦と南風原」と「沖縄戦と沖縄陸軍病院南風原壕」を概説した後、「「記録し、伝える」取り組み」、「病院壕の文化財指定と保存活用の取り組み」で取り組み状況の詳細を述べ、とりわけ整備の進んでいる20号壕についてを、「20号壕の整備はどのように行われたのか」と「20号壕の公開、活用」で説明し、最後に「戦争遺跡の調査と保存運動の歩み」を、沖縄の状況を中心に概説します。
著者として、公開当時の町文化財保護委員会委員長の吉浜忍氏をはじめ、南風原文化センター館長(当時)、同センター学芸員、町史編集室職員など、実質的に南風原壕の文化財指定や調査に関わってきた人たちが名を連ねています。
そのためか、壕に対する熱い思い入れが感じられたりするところもあって、やはり書くべき人が書かなければいい本はできないのだなという思いを強くします。
一方、専門家が書くとどうしても枝葉末節に力が入ったりすることがあるものですが、この本はそういうことは感じられませんでした。
今度沖縄に行くときには、南風原文化センターと南風原壕にはぜひ行ってみたいと思います。
(2011. 3.21 読)

|
 |
「昭和天皇の艦長 沖縄出身提督漢那憲和の生涯」 恵 隆之介 著
産経新聞出版 1,800円+税 2009年 9月28日 第1刷発行
沖縄に関する本を読んでいると、歴史的な背景を解説する場面などでよく海軍少将漢那憲和の名が出てきます。なので、この人について詳しく知りたいなと思っていたところ、発刊されたのがこの本。ただちにゲット。
大正10年、皇太子だった昭和天皇が、皇室史上初めて欧州を訪ねたときに、その御召艦「香取」の艦長として大役を果たしたのが漢那憲和でした。それ以来、昭和天皇の覚えめでたきを得て、軍人、政治家、故郷の星として活躍します。
少年時代の彼は、学業優秀で抜群、沖縄尋常中学で学友会の会長となり、生徒たちのリーダーとして信望が非常に厚かったようです。
その彼が、ワンマン校長を排斥するために、同級生の伊波普猷らとともにストライキを指導した話は痛快で、当時の文部大臣に建白書を送りつけたり、そのことが逆に当時の県知事、奈良原繁をして彼の保証人にしてしまったりします。
退役後の晩年は、民政党から立候補して衆議院議員。軍人からの転進でしたが、シビリアン・コントロールを提唱して賛軍派とことごとく対立します。そんな漢那を昭和天皇は深い心で支援し、彼は衆議院議長に登りつめます。
そして、このような立派な人間が世に出て活躍する陰には、廃藩置県の激動の中、女手ひとつで憲和らを育て上げた母・オトのひとかたならぬ努力があった、というのが、大まかな筋書きです。
当書のオリジナルは、昭和60年というから昭和天皇が崩御する3年ほど前に、著者が自費出版したもの。これを昭和天皇が愛読していたということを平成19年にある月刊誌で紹介されたのがきっかけで、平成21年に改めてこの本が出版されたという経緯があるそうです。
どういう経緯にしろ、ひとりの人間に焦点を当てた歴史ドキュメントというのは、いいですね。人間の生き様があぶり出されて、多少のデフォルメはあるにしろ、その時代が生き生きとして甦ってきます。それを追体験できる仕合せよ。
(2010.10.22 読)

|
 |
「沖縄へ −歩く、訊く、創る−」 鈴木 耕 著 リベルタ出版
1,500円+税 2010年 8月 4日 第1刷発行
『沖縄が、ただならぬ言葉を発し始めている。「沖縄差別」、「沖縄の屈辱」―。発した沖縄にとっても、向けられた沖縄県民以外の日本人にとっても、辛く、切なく、そして厳しい言葉だ。』
そんな言葉がコシマキに書かれているので、なにか政治的でイデオロギー色の強い内容かなのかと思うと、さにあらず。
抑制の効いた文章で、押し付けがましい思想が感じられず、沖縄に想いを向けて思索をしながら読むものとして、とてもよくできている本になっていると思います。
政治を扱ったルポルタージュというよりも、むしろエッセーのようなソフトな印象を受けます。
自分としては、辺戸岬の先端にある「祖国復帰闘争碑」に関する記述と、労働歌「沖縄を返せ」の大工哲弘による歌の意味の転換、元沖縄県知事大田昌秀へのインタビュー、著者自身の考えをまとめた「沖縄医療特区」構想などについて、特に興味深く思いながら読みました。
(2010. 9.27 読)

|
 |
「幻想の島 沖縄」 大久保 潤 著 日本経済新聞出版社
1,800円+税 2009年 7月23日 第1刷発行
戦争と米国支配と基地負担の三重苦への賠償で「振興漬け」になった沖縄は今、多くの副作用に見舞われています。値上がりを続ける軍用地の借地料、様々な補助金や公共工事の高率補助、税金の優遇……。特別の配慮が日常化した沖縄には、愚直にがんばることがバカらしくなるような状況がたくさん生まれました。
――このようなモチーフで書き綴られる問題作。
著者は日本経済新聞社の記者で、2005年から08年までその那覇支局長をした、まだ40代の気鋭です。
沖縄に対する鋭い洞察力と記者らしい分析が随所に感じられて、またその表現も、「です」「ます」調の短文で平易なものながら、舌鋒鋭いとでも表現できそうなストレートさがインプレッシヴです。
たとえば沖縄振興策については、本土側の人間の心に沖縄に対する2種類のマイナス感情をもたらす、としています。
一つは、沖縄の戦中・戦後の被害に対してあまりにもたくさんの税金が支払われ、それが全く役に立っていない現実を見て、それまで沖縄に対して抱いていた同情心や後ろめたさが消えていき、むしろ嫌悪の気持ちが芽生えること。
もう一つは、もともとおっとりした気質の沖縄が、振興策によってますますおっとりし、自助努力の機運を奪い去られ、そのことが怠惰な印象を醸し出すために、一種の軽蔑の感情につながること。
これらは、著者が好意と期待を持って沖縄に赴任してそこで生活するうちにじわじわと肌身で感じたことのようであり、非常に説得力があります。
結論としては、結局は沖縄が本土に抱く不満というのは「基地を沖縄に押し付けるな」ということであり、基地が多くあることが元凶で、基地さえ大幅に削減されれば目下の沖縄の副作用は一気に解消されるのではないか、ということのようでした。
しかし著者は、単に沖縄の現状を嘆くだけではなく、全8章の最終章「自立へ」で、それまで述べてきた状況に対する著者なりの打開策を提示しています。それらは具体的で、いくつかの有益な試みや成功例などが示されており、沖縄の持つポテンシャルをうまく活用すればきっと新たな道筋が見えてくるのではないかと感じさせます。
このあたりが言いたい放題のゴーマンをかましている輩などとは峻別できるところであり、著者には沖縄に注ぐ視線に温かさがあるし、そこに暮らしてじっくり観察していた人間だけあるなと納得できました。
(2010. 4. 4 読)

|
 |
「汚名 第二十六代沖縄県知事 泉守紀」 野里 洋 著
講談社 1,748円+税 1993年12月20日 第1刷発行
沖縄戦が激化する1943年7月、新たに沖縄県の第26代知事が勅任されました。この泉知事というのがとんでもないヤツで、間もなく米軍が上陸してくるのが怖くて、退任する45年1月までずっと、こんな沖縄なんかとはおさらばだとか、はやく別の県の知事に栄転しないかとか、ぐだらぐだらと言いながらほとんど仕事をしなかったらしい。
だってサ、2年に満たない在任期間中、地方長官会議があるからとかなんとか言って長期間上京したり福岡に行ったりで、都合6ヶ月間も沖縄を不在にしていたというのですから、オドロキでしょ。今の地方自治体では到底考えられませんよね。本土出身者は沖縄を脱出すればそれですむでしょうが、沖縄県民はそうはいかないんだゾ! お前は沖縄県知事だろ。
そ奴をいつか読書で糾弾するべく(笑)、関連本を探していたのですが、あったのですよ、すげー本が。1993年発行のこの本を、古書店から買いました。
読んでみてわかるのは、まずは彼が典型的なお坊ちゃま官選知事だったこと。世間を知らず、自己中心的で、ポスト、地位が歩いているような人だなと思いましたね。日記の書きぶりなんて笑わせますよ。自分のことを「泉君」なんて書いているんだから。
着任の知事訓示では滅私奉公を職員に説いておいて、我が身かわいさに自分の人事異動を画策したり、十・十空襲にビビッて知事官舎を後にして落着いた普天間にとどまり、陣頭指揮すら放棄する始末。これってもう、弁明のしようがないと思いますよ。
さらには、転任先の香川県では、あれほど空襲に慌てふためいていた男が「空襲恐れるに足らず」などと、ラジオで語ったりしています。もう、アホやんか。
著者の論調は、泉知事が決戦直前に異動したのは、軍との折り合いが悪い知事が軍と対立を深めたため、このままでは戦争ができないと大本営や内務省が判断したとみるのが妥当で、逃げ出したのではない――というものですが、そんなことは結果であって、日頃からいやいや知事をやっていたことは明らかであり、彼としてはたまたまあった異動がいわば渡りに船だったということ。
著者も最初は、ひどい知事がいたものだと憤り、知事はなぜ沖縄から逃げ出したのかを聞き出すために、義憤に突き動かされて元知事を探したそうです。ですが、1983年、探した先で会った泉君はボケが始まった病気の老人。結局のところ、時間はすべてのことを風化させていた・・・という、肩の力が抜けるようなエピローグが待っていたのでした。
それにしても腹立つなぁ、当時の官選知事って。どっちを向いて仕事をしているのやら。偉いだけ偉くて、こういう輩ではねぇ・・・。
(2010. 1. 2 読)

|
 |
「人物列伝 戦後沖縄の政治家たち」 仲本安一 著 琉球新報社
952円+税 2009年 5月10日 第1刷発行
著者は、十代で政治家を志し、学生運動−青年運動−労働運動−政治運動とひたすら走り続け、1960年に25歳で沖縄立法院議員に立候補して落選、30歳に那覇市議会議員に当選して、40歳には沖縄県議会に当選。
しかしその後は参議院議員選挙、衆議院議員選挙にも出馬したもののそれぞれ次点で落選し、4勝5敗の負け越しとなり、61歳で政界を引退した人物。沖縄戦後政治の真っ只中で永年活躍してきた、いわばその生き字引のような人です。
登場する政治家たちはというと、理論と雄弁の安里積千代、勤勉と柔軟の大山朝常、実直と反骨の松岡政保、誠実と情熱の屋良朝苗、慎重と土着の平良幸市、理論と実行の西銘順治、理想と不屈の瀬長亀次郎、庶民と人情の平良良松、豪快とラッパの下里恵良、清楚と孤高の知念朝功、発想とホラの高良一、雄弁と行動の島清――の12人。
ニックネームがつく政治家というのがスバラシイ。プロレスが人気絶大で、キラ星のようなメインイベンターが百花繚乱だったあの時代とイメージがかぶります。古くは鉄の爪、生傷男、狂犬、人間発電所…なんていうのから、後には黒い呪術師、南海の黒豹、千の顔を持つ男などなど。(笑)
読んでみて感じるのは、戦後から施政権返還までの沖縄の政治はとても庶民に身近なもので、政治家にはさまざまな個性や魅力があったのだなということ。演説会には人々が群れをなし、県会では熱い議論が戦わされていたものな。
復帰前の政治家たちには大きな志があり、与野党を問わず、みな沖縄を思う情熱と使命感で満ち溢れていたのでしょう。
バブルがはじけて十数年間、なんの改善策も出さずに既得権益に汲々としてしがみついていた某政党や、派閥間の調整によってその場しのぎで1年ももたずにすげ替えられる政権トップの状況、そして、口先だけで国や大義を語ろうとする凡庸な職業政治家の大量発生などは、当時の沖縄と比較すると、ただただ嘆かわしく、憐れにみえるのですね。
かわいそうになぁ・・・。あ、かわいそうなのはオレたち国民なのか。
(2009.10.31 読)

|
 |
「不屈 瀬長亀次郎日記 第2部 那覇市長」 琉球新報社 編 琉球新報社
2,190円+税 2009年 4月 4日 第1刷発行
第一部の「獄中」に続く第2弾。
表紙は1958年1月4日、那覇のハーバービュー広場で開かれた那覇市長選挙の立会演説会で熱弁をふるうカメジロー。こんなにたくさんの市民が演説会に駆けつけていたのですね。当時の沖縄は政治の季節の真っ只中だったのだろうなぁ。
今回は、1956年11月から58年1月までの日記をベースに、若干の解説が加えられたものとなっています。
読んでいて印象的だった部分を抜粋してみましょう。
1957年1月7日、市長に当選して初登庁、全職員を前にしての訓示。
「私は600の市職員の団結を信ずる。打ち出された敵の砲撃の破片が彼らの砲列に飛び散り、乱れ飛ぶようにするためには、市民の利益と県民の利益を増すためには、諸君の団結の力が必要である。市長はそれを確信している。一切のデマを粉砕して、くめどもつきぬ民族愛をもって、凍結した外壁を打ち破りとかしてみましょう。雪どけはやがて現れる。だが、手をこまねいて居眠りをしていては現れない。太陽より強い愛情がいる。その愛情は知性と勇気によって支えられるであろう。祖国の同胞はわれわれを支持している。国際即ち反戦平和の勢力もこちらの味方である。前進しよう。ゆっくりと、だが断固として。」
那覇市長選挙に関する解説文の一部。
「瀬長の主張が最も効果的に語られた場は、深夜に及んだ立会演説会だ。有権者は瀬長派や反瀬長派の主張を直接聞き、投票に臨んだ。演説会会場が民主主義の実践の場であったともいえよう。瀬長派は人々の共感を集め、幅広い支持を取りつけることに成功した。」
1957年8月13日、市議会議員選挙で市政再建同盟派勝利の祝賀会における市長あいさつ。
「12(議席。市長不信任を阻止できる3分の1を上回る議席数)の、市民を嵐から守るガジマルをあなた方は植えつけた。植えつけたばっかりだ。だがその根は市民の台所にしっかりとだきついている。ガジマルのうっそうとしてしげってつくりだしている木陰は、こよなきいこいの場所である。17名の同盟議員(反瀬長派)が闘い疲れて休ましてくれと頼み込んだら、否、頼まんでも疲れているなと見てとったら、誘い入れて休養させなさい。水でも飲ませてください。そして説得するのですよ、ガジマルになれと。そうすればこれまでの非を覚り、やがて30(全議席数)のガジマルが11万市民の生活と民主主義を嵐の中で守り抜く態勢をとれるのだ。」
50年前、沖縄にはこういう気骨のあるすばらしい政治家がいたのですよ。
第1巻発売から1年半後の出版。今から第3巻の発売が待ち遠しいナイスな企画です。
(2009.10.13 読)

|
 |
「沖縄ラプソディ 〈地方自治の本旨〉を求めて」 宮城康博 著 御茶の水書房
1,600円+税 2008年10月10日 第1刷発行
著者は1959年名護生まれ。20代には東京で演劇などに関わり、冷戦が終焉する90年代初頭に名護に戻り、地域計画や市役所の広報をつくる仕事をしながら、結婚して子宝にも恵まれます。
そして、子どもたちのため、地域のために働いていた矢先、名護市への新基地建設の話が火の粉のように降りかかってきます。
「子どもたちに米軍の新しい基地をプレゼントしてはならない」
そう考えた著者は、請われるままに新基地建設の是非を問う住民投票の代表を引き受け、積極的に「政治」にコミットしていくことになります。
1997年の市民投票では建設反対が過半数を上回ったものの、その後の市長選挙では容認派の市長が誕生し、市民の本音と建前が入り混じった複雑な様相を呈していきます。そのような中で著者は、国のなりふり構わぬ権謀術数を目の当たりにし、我々は国策を前にして何をしても無力なのか、そして憲法に位置づけられた「地方自治の本旨」とは何なのかについて、悩み、反発していくことになります。
本書は、そのような10年を著者が振り返り、その経験の意味と内容を反芻しながら現在を考えるというエッセイ集です。「ラプソディ」とは、叙事的で民族的な内容を持つ自由な形式の楽曲のこと。そんな表題どおり、自由な形式で、沖縄の多様で複雑な姿が伝わってくる1冊です。
そのようなコンセプトで政治的な問題について展開していく、という取り組み姿勢は共感できるのですが、個人的な意見としては、残念ながら、背景の政治的、時事的な問題が重すぎ、それをサラリと書こうとするところにやや無理があったような印象がありました。
こういう問題は、やはり新聞記者などがやるようにまず淡々と事実を述べ、それをどういう立場からどう考えるか、というように、整頓された書棚の本を1冊1冊読み込んでいくように論じていくほうが、読者に伝わるものが多いと思います。
(2009. 6.10 読)

|
 |
「ペリリュー・沖縄戦記」 ユージン・B・スレッジ 著 伊藤 真/曽田和子 訳
講談社学術文庫 1,400円+税 2008年 8月 7日 第1刷発行
「戦記モノ」が好きなのかもしれない。
もちろん人と人との殺戮合戦のような場面に身をおいたことはありませんが、生きるか死ぬかのぎりぎりの状況で感じるであろう「生きること」の意味やすばらしさなどについては、多少は理解することができるような気がするのです。
これは、ハードボイルド小説などでの格闘場面を読んだときも同様で、相手の持つ匕首が鈍く輝く様子に身体が反応してサーッと鳥肌が立ったり、深く切創を負ったときの痺れるような感覚が蘇ってきたりします。
そういう状況を目の当たりにして感じることは、死ぬことが怖いというよりも、むしろ生きていることそのものが強く実感できて、なぜか嬉しくなってしまったりするのです。こんなおれって、変なのでしょうか?
さて、この「ペリリュー・沖縄戦記」。アメリカ第一海兵師団第五連隊第三大隊K中隊の一員として、中部太平洋にあるパラオ諸島のペリリュー島と、沖縄の攻略戦の2つに参加した著者、ニックネーム「スレッジハンマー」が、その訓練期間と戦場における体験を記したものです。
20世紀最大の殺戮戦の中で体験した凄絶な様子を読み、ただただボーゼン。前線で悩み、奮闘した一兵士の体験談なので、その生々しさがストレートに伝わってきます。
戦場にあっては、政治的な正当性とか国際法上の人道的配慮などは、あるにはあるものの取るに足らないものであることが実態のようで、腐臭ただよう泥濘の中で地を這った者でなければわからない戦場の真実ががしがしと読む者の心を掻き砕いていきます。
このうち沖縄戦では、アメリカ軍が被った人的被害のうち、神経を病んだいわゆる戦闘外の事故兵は2万6千余名に及んだということです。
沖縄戦については、これまで戦跡を歩いたりして当時の戦線展開上の地理的状況がよくわかるので、わずか数百メートルを前進するためにかくも多くの血が流されたこととか、現在平和的な都市施設が次々につくられている地がかつては目を背けたくなるような凄惨な戦場だったことなどが体感的に理解でき、身を震わせながら読みました。
こういうことは知らなければそれで済むことなのでしょうが、思うに、そういう出来事をベースにして我々は今、平和を享受しているのだということを心に刻むこともまた、生きるためには重要な作業なのではないか。
きれいごとの中だけで一生を終えたいと思っている人にはオススメできない本ですが、生きることの意義や尊さについて確実に深められる1冊であると思います。
(2009. 3.15 読)

|
 |
「沖縄 悲遇の作戦 異端の参謀八原博通」 稲垣 武 著 光人社NF文庫
857円+税 2004年 1月15日 新装版第1刷発行
沖縄戦の高級参謀として専守持久戦を主導した八原博通を中心に据えた戦記。1984年刊を文庫化したものです。
沖縄守備隊首脳部が攻勢一辺倒の戦術を唱える中で、孤立しながらも冷静かつ合理的な判断を下した作戦主任の、人となりや戦術思想を明らかにします。
陸大に最年少で入校、主に作戦畑を歩き、アメリカに留学して欧米流の戦術を学んだという経歴を持つ八原は、太平洋の離島における防衛戦の教訓から、沖縄本島上陸軍を海へ追い返せる可能性はないことを冷徹に見通します。そして、米軍の猛烈な火力優位をはね返すためには、洞窟地下陣地に拠って耐え、専守持久する作戦しかないと判断します。
その判断の根幹は、敵の撃滅が不可能ならできるだけの出血を強い、戦意をくじく、というのが目的であり、その目的を逸脱した無意味な死は結局は自己満足の弱い死にすぎないとする、合理的な価値観にありました。
しかし、その合理性こそが、結果として沖縄県民に多くの犠牲を強いることになったのは、実に皮肉な結果といわざるを得ないでしょう。
作戦的には理にかなっていても、制空権確保のために飛行場を制圧すべきとする航空関係者などからは、臆病で腰抜けの戦術であるとして最低の評価を受けていたようです。
そして、軍人として弱腰であることは、彼が沖縄戦から捕虜となりながらも生還した(!)ことで、一層強固なものとされてしまいます。
高い戦術合理性と、行動の矛盾。
著者は、このような個人の行動と内面の矛盾や、戦いの火ぶたが切って落とされてから加速度的に大きくなっていった軍内部の作戦の齟齬などは、結局のところ、われわれ日本人が伝統的に持っている行動・思考様式(エトス)に原因があるのではないかと分析しています。
いずれにしても、彼のような思考をする人間は、この戦いが最初から無謀なものであることは見通していたし、そもそも彼のような人物は、軍隊のような極めて日本的な組織とは水と油だったのではないでしょうか。
それにしても不幸なのは、そんな将来展望のない戦いの舞台となってしまった沖縄の住民です。
絶望的な状況の中で足掻く、軍と民。時代がそうだったのだとは思うものの、何とかならなかったものかと悔しくも残念に思いながら読みました。
先に「沖縄に死す 第三十二軍司令官牛島満の生涯」を読んだときには、こちらの本をあわせ読んでから自分なりの歴史観を持つことにしようと考えていましたが、なかなかどうして、そう簡単に確たる歴史観は持たせてもらえないようです。
(2008.10.18 読)

|
 |
「証言 沖縄「集団自決」 慶良間諸島で何が起きたか」 謝花直美 著 岩波新書
740円+税 2008年 2月20日 第1刷発行
1945年3月、連合軍が沖縄攻略のため最初に上陸した慶良間諸島で起きた集団自決の真相を追いかけた良書。
いったい何が約600名もの人々を死に追いやったのか――というを問いにはさまざまな証言や考え方があって、たとえば曽野綾子著の「沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実」では、軍命令による集団自決についての確かな証拠は見当たらないとしていて、読んでいるほうはナヌ、ホントかよ?!と疑心暗鬼になったものでした。
そんな折、2007年の文科省の高校歴史教科書検定では、沖縄戦の集団自決の記述に当たって「日本軍の強制」と取られかねない表現を削除されます。
この事態を受け、同年9月、宜野湾海浜公園で「教科書検定意見撤回を求める県民大会」が開かれ、実に11万人もの人々がともに立って、検定意見にノーを突きつけたのでした。
歴史を書き換えようとするこのような動きの中で、凄惨な事件の生存者たちは、60年の時空を超えてようやく、これまで黙して語ることのなかった人を含めて、当時の実相や現在の思いを証言し始めたのです。
読み進めると、真実はどうだったのかを究明しようという意図はそう強く感じられず、むしろ重い口をようやく開き始めた人々に寄り添うかのように静かに証言を聴いていく――というつくりになっており、それらは心に重低音のように響いてきます。
政治的に見てどうだとか、どんな意図を持って事実を認識しようか、などという尺度とは別の、自分だけ生き残ってしまった悔いや、死んだ人の命を悼んで苦悩する中で人間として生きていくことの残酷さのようなものが、ずっしりと伝わってきます。
写真入りで紹介されている証言者はいずれも70歳代後半以上の年齢で、人間の寿命を考えればもうすぐ事実を知る人はいなくなるのでしょう。であるとすればなおさら、これらの証言は我々が語りついでいく必要があるのでしょう。
渡嘉敷、座間味、慶留間、阿嘉の4島にわけて章立てされていますので、それぞれの島の事情により違った状況があったことがよくわかります。そして、それぞれの島の状況がわかっていくにつけ、客観的に見て集団自決に関する軍の関与はなかったというのは明らかに大ウソだということがはっきりします。
だって、軍はたとえ住民に直接死を命じなかったとしても、米軍に対する恐怖心をあおり、米軍の捕虜となることを許さないよう住民を指導した一方で、軍命を優先して住民保護を放棄し、手榴弾まで配ったのですから。これを軍の関与と言わずして、何と言うのでしょうか。
忠告。
この本は、気分の優れないときや精神的に不安定なとき、不満やストレスの多い状態のときなどには読まないようにしましょう。それらの症状がさらに悪化してしまう恐れがあります。(笑)
(2008. 9.17 読)

|
 |
「沖縄に死す 第三十二軍司令官牛島満の生涯」 小松茂朗 著 光人社NF文庫
619円+税 2001年 1月12日 第1刷発行
住民をも巻き込みながら3ヶ月に及んだ沖縄戦の死闘を指揮したのが、沖縄防衛軍司令官で陸軍中将(のち大将)の牛島満。
精鋭師団を他地に転出させられるという戦力弱体化の中で、決戦か、持久かに揺れる司令官の苦悩と、その素顔を綴る――という趣向の戦記もの。
牛島満といえば、連合軍の日本本土への襲来を少しでも遅らせるため、沖縄本島をいわば捨て石にして、沖縄諸島及びそこに住む沖縄の人々に筆舌に尽くせない甚大な被害を導き、悲劇を招来した張本人として紹介されることが多く、私もそのように理解していました。
ところが当書では、牛島は慈愛あふれる温厚な軍人で、牛島の出身地の鹿児島県で言う「ウドサア」(うどの大木のような茫洋とした性格)で、重要事項の決定はすべて参謀長の長勇に任せきりだったと書かれており、全体として牛島は悪くないようなトーンで描かれています。
さらに、大変な戦禍をこうむった沖縄の人たちは牛島を非難する人は少ないとし、軍と行動をともにしたある沖縄女性は「お父さんと学校の先生をごっちゃにしたような温かい人だった」と証言しているというのです。
率直に言って、それって、本当なのかどうか。
これまで読んできた多くの沖縄戦に関する書籍とはかなり食い違う評価であり、善玉、悪玉というステレオタイプの分類をするのはどうかとは思いつつも、司令官として全責任を負う人間を、この人のせいでこうなったのではないとでも言いたげな論調は、にわかに信用することができないなあ、というのが率直な感想です。
参謀内が、主戦派の長参謀長一派と慎重派の八原作戦参謀一派に分かれていたといい、連合軍上陸後、参謀会議で主戦派が提唱した突撃を実行して敗走。その後長参謀長は意気消沈し、参謀内は八原作戦参謀の持久戦略が支配することとなり、このことが沖縄県民に多くの犠牲を強いた喜屋武半島撤退へとつながっていった――という論調なのですが、これについてはいずれ別の角度から再考してみる必要がありそうです。
この本とは別に、八原作戦参謀を中心に書かれた「沖縄悲運の作戦 異端の参謀八原博通」という本も入手しているので、これをもあわせ読んでから、自分なりの歴史観を持つことにしましょう。
平成元(1989)年に単行本として発行された「将軍沖縄に死す」の改題版です。
(2008. 7.27 読)

|
 |
「沖縄密約 ―「情報犯罪」と日米同盟」 西山太吉 著 岩波新書
700円+税 2007年 5月22日 第1刷発行
沖縄返還は1972年に実現しましたが、返還に当たっては日米の思惑が交錯し、様々な政治的密約が存在したという事実が、近年アメリカの公文書や当事者の証言で明らかになってきました。
著者は当時、毎日新聞の首相官邸や外務省などの担当記者として取材活動を行い、沖縄の施政権返還にからむ密約の取材をめぐって、返還の年に国家公務員法違反容疑で逮捕、78年に有罪となった――という経歴を持つ人。
その後著者は、次々と明らかになってきた密約を裏付ける事実を背景に、2005年には先の判決に対する謝罪と損害賠償を求めて提訴するという行動に出ています。
政治の時代だったと言える昭和40年代、佐藤栄作、田中角栄、福田赳夫といった政治家たちが「返還」実現のためにあの手この手でアメリカと交渉するいわばフットライトの当たるステージ上の状況と、その一方で、隠密裡に活躍するネゴシエーターたちの生々しい苦悩の様子が、リアルに再現されています。
そして後半では、変質していく日米同盟の状況や、情報操作が情報犯罪にまで増長してきている現在の状況を述べ、それに対する憂いを切々と訴えています。
沖縄返還という非常に重要なテーマを扱っているものですが、この本を読んで感じたことは、この問題を自分のものとして考えるにはあまりにも関連する知識が乏しすぎるのだなということ。
言葉を変えれば、当時の政治や国際状況等に相当程度の造詣がないと、著者の論じることの全容を理解するのは困難なのではないか、と思うのです。
著者自身が敗訴した訴訟事件の当事者なわけですから、どうしても記述内容に力が入ってしまうのはわからないではないのですが、できればもう少し平易に、また、時代は40年近くも前のことなので、当時の背景などをもっと簡潔に解説するなどすれば、さらに理解が深まっただろうと、少々残念です。
(2008. 7. 4 読)

|
 |
「不屈 瀬長亀次郎日記 第1部獄中」 琉球新報社 編 琉球新報社
1,667円+税 2007年11月11日 第1刷発行
戦後の沖縄を代表する政治家で、カメさんと呼ばれて親しまれた瀬長亀次郎の、1954年から56年までの獄中・病床日記です。
2007年に琉球新報誌上に連載されたものを、新たな資料や書簡、関係者の証言や研究者の解説を加えて編集刊行したもの。
日記は、立法院議員時代、人民党事件で投獄された54年11月から、脳梗塞で倒れる直前の87年までの33年分、延べ200冊に及ぶ膨大な量だそうで、今回刊行された獄中・病床日記はその全体のわずか5冊分に当たる分量なのだそう。当書が「第1部」であるということは、今後何冊か刊行されるのかな。
カメジローは、単調な獄中生活を“独習と闘病”の場と捉え、家族に多くの本を差し入れてくれるよう手紙でリクエストし、毎日を修行者のように生活します。
病に冒された十二指腸の痛みをこらえながらの日々は痛々しいですが、それを気骨で克服している様子が伺え、政治家としての逞しさ、信念の深さが感じ取れます。
これまでに刊行されたカメさん関係書籍としては、「瀬長亀次郎回想録」(1991 新日本出版)が代表的。ぜひこれとあわせて読みましょう。
さて。知名定男が作詞作曲をした「おしえてよ亀次郎」といううたを、ネーネーズがうたっていますので、紹介しましょう。
♪ うんじゅが情きさ 命どぅ宝さ 我した思いゆ 届きてぃたぼり
それはむかしむかし その昔 えらいえらい 人がいて 島のため人のため つくした
あなたならどうする 海のむこう おしえてよ 亀次郎
それは海が赤く 泣いている 自然をこわす 人がいる 約束は守らず そっぽむく
あなたならどうする 愛と涙 おしえてよ 亀次郎
平和を愛する ウチナーと 闘う拠点の 基地がある 手を合わせる 親祖父がいるのに
あなたならどうする となりあわせを おしえてよ 亀次郎
(2008. 6. 1 読)

|
 |
「命こそ宝 沖縄反戦の心」 阿波根昌鴻 著 岩波新書 740円+税
1992年10月20日 第1刷発行 2006年 4月14日 第12刷発行
阿波根昌鴻(あはごんしょうこう)氏は1903年生まれ。敗戦後、米軍占領下の伊江島で土地闘争の先頭に立ち、復帰後も一貫して軍用地契約に応じない反戦地主として闘った人です。
1984年に反戦平和資料館「ヌチドゥタカラの家」を建設。訪れた人を案内して自らコツコツ集めてきた展示物を説明し、見てもらった後には戦争の悲惨さや島の土地闘争のことなどを自分の体験をもとに話す――というスタイルで交流しながら学び合う活動をしてきたことは、当時たびたびテレビなどでも特集されていたのを覚えています。その氏は、残念ながら2002年に逝去。
当書は、氏の語り伝えたいことが、平易な言葉で、長老らしく精神的な抑揚を抑えた形で淡々と、学び、考え、行動してきたこととともにまとめられています。
「復帰後の沖縄、そして伊江島」、「「反戦平和資料館」を創る」、「戦争の証拠が訴えるもの」、「国の不正をただす裁判」の4章と、終章として「心の勉強と真理の闘い」。
終始「わし」という一人称で思いを伝えていることに好感。
イデオロギー的な一代記というものはともすると著者自身の考えが中心に据えられるため、読者にとってはお仕着せ的なものになりがちですが、当書の場合そのようなことはまったくなく、むしろ文章の奥に潜む信念が、水がゆっくりと沁みこんでくるかのように心の中に入ってきます。そして、そのことが逆に読者の静かな憤りを醸成するという、不思議な読後感があります。
『この伊江島はね、海も動いているし、生きておる。こうして木を見ていますとね、風は三味線ですよ。静かな三味線をひくと、木の枝はみなクミウルイ(組み踊り)する。あれは王様の前で踊るおどりですね。三味線という風が力強く吹くと、沖縄のカチャーシー、庶民の元気踊り。そして、木によって、踊り方がみな違う。木の葉が大きい木の踊り、木の葉の小さい木の踊り、みな違う。それも見事。
天を見たらですね、雲がどんどん動いて、いろいろなかたちに変わる。舟になったり、ライオンになったり。それもまた見事。
何でも生かしていかなければならない。戦争がない平和な島をどうしてもつくっていかなければならない。わしはそう強く思っております。―――』(本文より引用)
とてもステキなオジィだったのでしょうね。ご存命のうちにお会いしたかったです。
(2008. 4.17 読)

|
 |
「私の沖縄戦記 前田高地・六十年目の証言」 外間守善 著
角川書店 1,500円+税 2006年 6月23日 第1刷発行
沖縄学者外間センセイの、若き日の沖縄戦体験記。
学者らしくたくさんの文献や証言を読破した上で、自分の記憶をもとに、60年以上も前のこととは思えないくらいに鮮明、詳細に記述しています。
内容の中心は、沖縄初年兵の著者がある大隊に同行して、首里の北方、現浦添市の当時前田高地と言われた戦略的高地において血で血を洗うような激戦を繰り広げ、その後敵の防衛線を突破して浦添丘陵を北東へと逃避する――というすさまじい体験の記録。
連日の集中砲火の下で蛸壺に隠れ、泥地に這いつくばって戦い抜く日本兵の様子は、まさに死線を超えていて、生き延びた人がいるなどということが不思議なほど。そんな中にあっても、砲弾飛び交う下で学校の同僚と邂逅し、抱き合いながらも傷ついた互いの身体を思いやるシーンなどがあったりして、とても感動的な面もあります。
彼らは終戦を知らずにガマや塹壕で敵の目から逃れながら抵抗し、8月29日、先に捕虜になっていた日本兵の説得を受けて武装を解除、あの屋嘉の収容所に収容されますが、その中での生活のことについても記述があり、こちらもなかなか興味深いものでした。
これまで私は、激戦が展開されたという嘉数高地やシュガーローフ、富盛の高台などを見てきましたが、この本を読んで、前田高地の今――というのもぜひ見てみたくなりました。
おそらくはすっかり宅地などに開発されてその名残など跡形もないのでしょうが、その場にたたずんで過去を回想してみるということだって、そう無意味であるばかりではないでしょう。
表紙の写真は、前田高地のシンボル、為朝岩。この岩の周辺でも大激戦があったとのこと。現場探索をする際はこれが目印となるのでしょう。
第1刷発行日は、沖縄において日本軍の組織的抵抗が終了した日から数えてちょうど61年目の日。そしてまた、読了日は、奇しくも真珠湾攻撃により太平洋戦争が開戦した12月8日。それから66年の月日が流れましたが、戦争の不幸な記憶や影響は、いまだにあちらこちらにあって、人を沈鬱にさせたり涙を流させたりしています。
(2007.12. 8 読)

|
 |
「沖縄 シュガーローフの戦い 米海兵隊地獄の7日間」
ジェームズ・H・ハラス 著 猿渡青児 訳 光人社
2,300円+税 2007年 4月 3日 第1刷発行
沖縄地上戦最大の戦い――。それは、那覇市北部、今は「那覇市おもろまち一丁目6番地」となっている小さな丘をめぐって、血で血を洗うような白兵戦が繰り広げられたという“シュガーローフの戦い”でしょう。
那覇市街への突破を試みる精鋭・米第6海兵師団と、丘に地下陣地を構築した日本軍は、1945年5月12日から一週間、激しい丘の争奪戦を繰り広げます。1日に4度その主を変えるほどの激戦に、海兵隊は2千名を超える戦死傷者を出したとのことです。
この本は、その熾烈な戦闘を、生き残った100名以上の最前線兵士へのインタビューをもとに、精密に再現したドキュメンタリーです。
沖縄戦というと、首里にあった日本軍の司令部が南の摩文仁へと撤退する1945年5月下旬以降の逃避行の際の、戦火から逃げ惑う県民と日本軍との悲惨な状況を思い浮かべます。しかし、その最前線、首里の防衛線をめぐって泥沼の戦いをしていた日本軍と米軍の様子については、比較的伝えられることが少ないようで、なかなか知ることができませんでした。
そんな折、見つけたこの本、なかなかの会心作でした。
シュガーローフをめぐって米軍は、少なくとも11回の攻撃を行ったといいます。その様子は、
『朝日がのぼると、K中隊の周囲は、海兵隊員や日本兵の死体、飛び散った肉片などで、食肉処理場のような様相を呈していた。「泥の上に散らばったり、谷間の壁の岩に張りついたり、人間の肉片は、あたり一面に散らばっていた」と海兵隊員は語った。
体が真っぷたつになった男、切断された腕や脚、取れた頭部などがゴロゴロしていた。G中隊の海兵隊員、フランク・ヘップバーンがこの場所にやってきたとき、手を伸ばせば、どこにでも砲弾の破片があり、前夜の砲撃の凄まじさに息をのんだ。「降り始めた小雨で、泥の表面が洗われ、金属片や肉片などが驚くほど鮮明に、ぼんやりとした霧の中にうかび上がっていた」と彼は当時を回想した。』――という具合。
人間たちが、こんなに簡単に、しかもこんなにたくさん、戦争のために死んでいったという事実。それがごく当たり前に、ほんのちょっとしたエピソードを紹介するかのように、360ページにわたって記述されています。これは、他の追随を許さないほどに鬼気迫るものがありました。
そんな悲しい歴史を持つシュガーローフも、今では紳士服量販店やCD・ビデオ店などが立ち並ぶ新都心おもろまちの一角に、頂上部に市の配水タンクを載せたかっこうで、何事もなかったかのように存在しています。
62回目の終戦記念の日を挟み、盆の休暇中に心静かに読了。平和のありがたさを痛感するとともに、そのような史実を絶対に風化させないことこそが何よりも大切である、ということを今一度肝に銘じさせずにはおかない1冊でした。
(2007. 8.17 読)

|
 |
「反戦平和の手帳 ―あなたしかできない新しいこと」
喜納昌吉/C・ダグラス・ラミス 著 集英社新書 700円+税
2006年 3月22日 第1刷発行
喜納昌吉とC・ダグラス・ラミスの対談集です。
喜納昌吉は、「ハイサイおじさん」や「花〜すべての人の心に花を」などをつくった沖縄ポップ史上屈指のミュージシャン。今はナント参議院議員になってしまい、特異な人生を歩んでいるおじさんですね。
ラミス氏は、元アメリカ海兵隊員の政治学者で、「世界がもし100人の村だったら」の対訳をしたヒト。沖縄の論客知念ウシの夫でもある人なのだそう。
目次を見ると、「「現実的な戦争」は存在するか?」とか、「「戦争をしません」から「戦争は禁止されています」まで」とか、「もう間にあっていない問題の解決策」などという柱立てがしてあるのだけど、これらっていったいどーゆーイミなの?? 本来目次というものは、それを見ただけでおよその内容が概括できるというものなのだろうだが、この本にあってはちょっと違うゾ。
読む前からそんなことがあったので、日本通とはいえ外国人、そして、不思議で独特な考えを持つ喜納の対話集ともなれば、きっと禅問答のような難解な内容なのだろうなと思いつつ読み始めました。
で、案の定、難解。(笑)
難解というよりは、読者のほうにかなりの空想力が必要だという感じでしょうか。一語一語をよ〜く考えながら読まないと、言わんとしていることの真髄がよく理解できなかったりして・・・。
でもまぁ、言っていることが突飛だったりするだけで、大江健三郎の「沖縄ノート」なんかよりはずっと正常。またご大層なことを語っちゃって・・・というところがある程度ですから。
いつも思うのだけど、対談集って、読み解くのが難しい。勢いでしゃべっていることを平板な文字に置き換えているため、話の力点がどこにあるのかを見失いがちになるのですね。
対談、鼎談なら、その現場で聴き入るべきなのでしょうね。
(2007. 6.19 読)

|