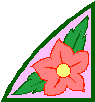○ネーネーズ 業のうた、愛のうた
(ネーネーズのCD「ユンタ」のライナーノーツ) by 上原直彦
 業(わじゃ)という言葉がある。
業(わじゃ)という言葉がある。
日本語の転語で、辞書には「行い、仕業、仕事、事業、やり方、方法」などと訳されている。
沖縄口(うちなーぐち)の"わじゃ"も大意は同様であるが、このCDに収録されているCHICKEN海ヤカラ(津堅島の海の輩者)、舟むちユンタ、国頭サバクイ、DAY−O!、汗水節、県道節は、いってみれば、その業のうたである。
漁師、船乗り、沖仲士は海業(うみわじゃ)で、農業を主とした陸地の仕事を陸業(あぎわじゃ)、そしていまひとつ、山のそれを出業(やまわじゃ)といいきって、専門職をさし、お互い敬意をはらい合っている。ほかに、芸能をよくする者を業持ち(わじゃむち)といって、一目おいたりする。
つまり、他人の業を大いに認め、敬意を表しながら、ウチナーンチュは悠久の歴史を生き抜いてきたといえよう。だからこそ島唄には業の歌が多いし、他人の業にそっぽを向いたところには、歌は生まれない。
ネーネーズは、新しい形の歌の業持ちで、古謡、新曲とりまぜて業を賛歌する訳だが、それぞれの業は、人間複数で成す場合、そこには男、女、個人的な愛の関わりが芽ばえるのもまたごく自然なことで、そこいらをふくらませるために、ウムカジ、チャッチャー、ユンタ、そして泊阿嘉伝説とウサガンナというラブソングなども組み入れて"業の歌"としたようだ。
沖縄に住み居る者にとって、ネーネーズがどの程度の歌の業持ちに位置しているか、それは判断しにくい。
なぜなら、言葉の数だけ歌のある沖縄では、上手下手は別として、ほとんどの人が歌者(うたさー)で、玄人、素人の境がないからである。
したがってこのCDの出来具合は、聴くあなたが、きっぱりと評価することになる。
それがいかような評価であっても、ネーネーズは謙虚に受け止め、次なる歌道を歩むことになろうが、願わくば「聴いていて、少なくとも耳の邪魔にならない出来」といっていただきたいのは、関係者のひとりとしての一人よがり…。
そして、県外で、この歌たちに心動かされた方がいたならば、めんどうでも一度、ネーネーズの住む、いや、彼女たちを生んだ島の地を踏んでいただきたい。風のそよぎを感じていただきたい。
さすれば、言葉のハンディを越えた島びとの心情が容易に理解できるし、そのことは即、島びとが語り合いとして持ち合わせている南の島うたとの出逢いになろう。
このCDがそのためのパスポートになれば、こんな歓びは他にない。
馬は乗って知れ!人は出逢って知れ!と諺にある。
歌はうたって知って、すべての人々との共有財産にしたい。 (1992年9月)

○ネーネーズのCD「なーらび」のライナーノーツ by 筑紫哲也
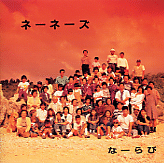 伝統に戻ると言ったのか、原点(もと)にと言ったのか、酒席のことなのではっきりしない。
伝統に戻ると言ったのか、原点(もと)にと言ったのか、酒席のことなのではっきりしない。
前作のアルバム「コザdabasa」は私の大好きな、楽しい創意に満ちた作品で、なかに収録されている「黄金の花」は私のやっている番組のテーマにも使わせてもらった。
ファンというのは欲の深い生きもので、さて次はどんなネーネーズのアルバムを作るつもりかと、わがシーサーおじさんこと知名定男に私がたずねた答がそんなことであった。
ネーネーズは活躍の幅を近年どんどんと拡げ、「寿司や納豆」だの「タクシードライバー」などの"外国語"も堂々と母音に力をこめて歌ってきたが、彼女たちが生まれ育ったのは「島唄」の世界である。ここらでそこにいったん立ち戻ってみようということで出来上がったのがこのアルバムである。
ところが沖縄の伝統、なかでもその伝承者、知名定男というのが曲者で、原点回帰と言っても単純にカビの生えた古典をなぞったりはしない。島唄というのがもともとそういうもので、古典、伝承から新作までひとつながりになっている生きものなのである。だからネーネーズのひとりひとりがソロを取っている知名・上原コンビの作品と昔からの民謡との間に全く違和感、断絶がないのである。
新しいもの、伝統をふまえたものをまぜこぜにして、それを沖縄化していく「チャンプルー性」も沖縄の伝統的得意技であるが、このアルバムに参加した内外のアーティストは多彩なチャンプルーの具である。
それにしてもネーネーズというのは力のあるグループである。そのことは「黄金の花」の後のテーマ曲を決める時、候補曲が前の曲に"力負け"してしまう過程で痛感したことだが、のびやかに郷土の自然とむつみ合うこのアルバムを聴くとますますその思いを強くする。沖縄の音楽の源はその自然に在り、そこに根を張ってこそ力があるのだとあらためて思う。
(1995年3月)

○島唄美しゃ (雑誌「うるま」2001.8 から) by 知名定男
小那覇舞天さんがプロデュースし、結成させたフォーシスターズと云う女性コーラスグループはセンセーショナルなデビューをし、ある種、伝説的な歴史を残した。それに業界は右ならえで多くの女性グループが生まれた。民謡三人娘(二代目、三代目も含め)、でいご娘、糸満ヤカラーズ、屋良ファミリーズ、等など。これらのグループはそれぞれ特長を持ち多くの民謡ファンを楽しませた答えである。
さて、ネーネーズだが、古謝美佐子、吉田康子、宮里奈美子、比屋根幸乃の4人はけっして私の弟子でもなければ、そんなに親しい間がらでもなかった。まあ古謝は、幼少の頃から顔見知りではあったが。彼女はいったん三線を持ち、歌い始めると、暗いイメージながら聴く人の心に強くイメージを与える切なさと、大城美佐子に通じる昔の匂いを持っていた。宮里は、細かい節々に色香を発する華があり、吉田は正統な歌唱法に安定感があり、比屋根は新人ではあったが、他の3人にない若さとパワーがあった。それぞれのものが合体した時にネーネーズは完成する。と私は、いや私以外の人達も期待したものである。
それが、なかなかそう簡単にはうまくいかないもので、個性の強い4人がスタジオに入ったりすると、それはもう主張の火花が飛びかい、すさまじいほどの世界が展開する。おまけに仲間意識の程でプロデュースする私の主感までが火に油をそそぎ、そこは諸君の思っている島唄の世界とはまったく別の、まるで工事現場の如き修羅場と化する。いやそれがまた、私の立場としては楽しくもあり、頼もしくもあるのだから不思議な世界でもある。
アンサンブルという音楽の意味でとらえると、ネーネーズはとてもじゃないが程遠い。だが、しかし「唄う」ということで考えると、ネーネーズは自由に、沖縄的伝統チャンプラーで、ぶつかりにぶつかりあって大きな波になり、幅になり、それが厚みになり暖かみになったりする。これを発見した時に私は大きな喜びと感動にひたることができた。無我夢中の10年間を、私はネーネーズと共に居られたことを誇らしく思うし、ネーネーズにありがとうを言いたい。心を込めて美佐子、康子、奈美子、幸乃、書き忘れたがまったく違うジャンルから入って来てとても苦労した江里子、みんな本当にありがとう。

○上原知子 ZAN (上原知子のCD「ZAN」のライナーノーツ) by 篠原章
 沖縄には伝統的に歌上手が多い。ときには素人のなかにもびっくりするほど巧みな歌い手がいる。日本広しといえどもこれほど歌上手が多い地域はないだろう。古典音楽や民謡の歌手はむろんのこと、安室奈美恵やMAXにいたるまで、こうした伝統の上にあることはまちがいない。
沖縄には伝統的に歌上手が多い。ときには素人のなかにもびっくりするほど巧みな歌い手がいる。日本広しといえどもこれほど歌上手が多い地域はないだろう。古典音楽や民謡の歌手はむろんのこと、安室奈美恵やMAXにいたるまで、こうした伝統の上にあることはまちがいない。
が、それだけ歌い手には恵まれた沖縄にあっても上原知子は別格である。天性の喉や高度な発声の技術をうんぬんしているのではない。それだけならほかにも優れた歌い手を見つけることはできるだろう。上原知子は歌に生命を吹き込むことができる、類稀な才能をもった歌い手なのだ。
上原知子の肉声を間近に聴いた人なら、誰しもがこの評価に相槌を打つはずである。彼女が目前で歌いだしたとたん、そこには磁場のようなものが生まれる。空間が独特のディストーションを示して、聴き手の五感をダイナミックに麻痺させ、歌という幻想の世界に柔らかく引きずり込んでいく。比喩としていっているのではない。事実、そうなってしまうのである。いってみればナチュラル・ハイ、ある種のトリップ体験なのだ。
同じような状況を一度だけ経験したことがある。ニューヨークで、とあるプライベートなパーティに招かれたときのこと。出席していたアリサ・フランクリンがアカペラでゴスペルを歌いだしたのだが、上原知子ほ聴いたときとまったく同じように、五感すべてがアリサの創りだした磁場に引き寄せられ、歌という神秘の虜になってしまったのである。
私たちはふだん、カラオケというノイジーかつイージーなコピー文化に首までつかっているので、歌の巧拙を根源的なレベルで判断することができなくなっている。だが、本来の歌とは、こうした磁場や神秘性のことを指すにちがいない。誤解をおそれずにいえば、上原知子やアリサ・フランクリンを聴くことは、神々に限りなく近づく瞬間を味わうということなのである。
上原知子は1958年沖縄県糸満生まれ、父・上原長幸は、腕のいい床屋として糸満いちばんの理容店を経営していたが、生来の民謡・芸能好きが高じて、知子6歳の時、「明日から店をたたんで芸能グループを旗揚げする」と宣言、安定した商売をいとも簡単に投げ捨て、知子も含む上原ファミリーをコアとした糸満ヤカラーズを結成してしまう。
折しも、後に上原知子の夫君となる照屋林賢(りんけんバンド)の父・林助が主催していた抱腹絶倒エンターテイメント"ワタブーショー"の人気凋落後で、沖縄芸能界は「ファミリーもの」に活路を見いだそうとしていた時代であった。この時期から70年代始めにかけて、糸満ヤカラーズを始め、屋良ファミリーズ、フォーシスターズなどといったファミリー芸能グループが活躍、歌・踊り・寸劇などをパッケージした芸能ショーを沖縄各所で展開し、大いに人気を得た。
糸満ヤカラーズは、知子・千佳子の幼い姉妹も人気の的だった。年端もいかない可愛らしい二人が、歌、踊り、太鼓、ときにはカマやヌンチャクを使うアクロバティックな武の舞までやってのけるのだから、評判になるのは当たり前である。米軍キャンプでも人気アーティストのひとつだったという。
他のファミリーグループが消滅してから後も、糸満ヤカラーズの人気は衰えることなく、祭りや宴席などハレの場に欠かせぬ存在として、ウチナーンチュ(沖縄人)の生活のなかに根を張っていった。彼らの名声は本土にまでおよび、千昌夫など本土のスターが巡業する際に、客演として招かれることも珍しくなかった。
東京でのバンドマン暮らしに見切りをつけて沖縄に引き上げ、知名定男などとともに民謡ニューウェイヴの時代を切り開こうとしていた照屋林賢も、糸満ヤカラーズに強く引かれたミュージシャンの一人であった。いや、ヤカラーズではなく、上原知子に引かれたといったほうがより正確かもしれない。もっとも、知子の芸にひかれたのか、知子の美しさにひかれたのかは定かでないが、80年代に入ると林賢は、ヤカラーズの楽屋に足繁く通いつめ、やがて舞台の裏方まで進んで引き受けるようになった。
林賢がりんけんバンドを結成したのは83年のことだが、最初から上原知子をシンガーとしてフィーチャーしていたわけではない。なにしろ知子はすでに糸満ヤカラーズの花形、ジーンズにTシャツという出で立ちでロック・フェスティバルに出演することもあったりんけんバンドとはまったくの格違いである。しかし、目まぐるしいメンバー・チェンジを繰り返すなかで、林賢が上原知子を密かに狙っていたことだけは確かである。
紆余曲折を経た後、上原知子はゲスト・ヴォーカリストとしてりんけんバンドのファースト・アルバム「ありがとう」(87年)に参加することになるが、これをきっかけに、林賢は上原知子を"公私ともに"引き抜くことに成功する。結婚は88年、りんけんバンドへの正式参加は89年のことであった。
以後、りんけんバンドは、急速に成長していった。祖父・林山(沖縄古典音楽の大家)と父・林助ゆずりの林賢の音楽センス・芸能センスと糸満ヤカラーズ直伝の知子の芸能精神が一体化したところに成立した新生りんけんバンドだから、後はもうこわいもの知らずである。
90年1月に六本木WAVE店頭で行われた東京初ライブを皮切りに、りんけんバンドの活動の場は沖縄を越えて、日本へ、世界へと飛躍的に広がっていった。90年5月にファースト・アルバム「ありがとう」をCD化して以来、「カラハーイ」(91年)「アジマァ」(92年)「gongon」(94年)などの名作を経て最新作「夏ぬ子」(97年)に至るまで、全部で9枚のオリジナル・アルバムをリリースしている。
年間50〜70回はこなすというりんけんバンドのステージでは、フロント三人衆のパワフルかつコミカルなパフォーマンスも評判だが、なんといっても観客は、日本の他のシンガーではけっして味わうことのできない、それこそある種の美学にまで高められた上原知子の品格の高い歌唱を心待ちにしているのである。
さて、その世紀の歌姫・上原知子による初のソロ・アルバムがこの「ZAN」である。
知子ファンにとってはむしろ遅すぎるほどのソロ・デビューとなったが、誰もが陶然とするほどの出来映えである。ただし、これまでのりんけんバンド・サウンドをイメージして聴き始めると、少しばかり裏切られることになる。そこにいるのは、りんけんバンドを支える生身の上原知子ではない。林賢の生みだした多彩で奥行きの深いサウンドにのって天女のように自在に舞い踊る"魂"こそがここでの主役なのだ。
ZAN(ざん)とはウチナーグチ(沖縄語)で人魚の意、いかにも海人の国・沖縄らしい神秘を象徴するタイトルである。プロデュースとアレンジは、もちろん照屋林賢。
一部はダブリン(アイルランド)で録音されているが、歌を含む録音のほとんどは、コザ(沖縄市)は胡屋十字路にあるマルテル・スタジオ(林賢のプライベート・スタジオ)で行われた。ゲスト・プレイヤーとして、日本よりも海外で有名な佐渡を拠点とする和太鼓グループ"鼓童"から金子竜太郎(ちゃっぱ)と内藤哲郎(太鼓)、雅楽ニュー・ウェイヴの旗手として知られる東儀秀樹(笙、ひちりき)、りんけんバンドのレコーディングではすでにお馴染みの西アフリカ・マリ共和国出身東京在住のギタリスト、ママドゥ・ドゥンビア(サリフ・ケイタの元サポート・メンバー)、やはりりんけんサウンドには欠かせない二胡(胡弓)の第一人者で中国出身東京在住の姜建華(ジャン・ジェンホァ)などが参加している。
さらに、ダブリンでのセッションには、ロナン・ブラウン(イーリン・パイプス)、ノリーン・オダナヒュー(アイリッシュ・ハーブ)、ナリグ・ケイシー(フィドル)の3人が参加している。ロナンを始め、いずれもソロ・アルバムもあるベテラン・アイリッシュ・ミュージシャンである。これら以外の音は、基本的に林賢の打ち込みとなっている。
全10曲中9曲が林賢の作品、残りの1曲が新進作曲家・照屋林山によるもの。詞のほうは、近年、林賢と不動のコンビを誇る版画家・名嘉睦稔の作品が5曲、トラディショナルを林賢がエディットしたものが4曲、林助によるものが1曲という構成になっている。
音やリズムのベースは驚くほど無国籍だが、全体としてきわめて濃密で力のこもった作品である。カチャーシー・ナンバーである1曲を除いて、すべてスローかミディアム、上原知子の歌をじゅうぶん堪能できるコンテンツとなっている。
しかし、ここで「沖縄の上原知子」を期待して聴いてはならない。それは誤った聴き方である。上原知子の歌唱は明らかに沖縄音楽をベースとしているし、名嘉睦稔の詞を始め言葉はすべてウチナーグチ、情景描写の舞台もことごとく沖縄である。それでもなお、この作品は"沖縄"を主張するものではない、と断言したい。
照屋林賢というたまたま沖縄で生を受けたプロデューサーが仕掛けた地球的な冒険の旅に、たまたま沖縄で生を受けた第一級の女性シンガーが果敢にも挑み、見事に成功したと解釈してもらいたいのである。
でなければ、二胡とイーリン・パイプスをハウス風に味つけしたゴージャスなイントロ曲「ZAN」の疾走感も、海洋文化のロッか・バラードとでもいえそうな「照る月」の誘惑も、ひちりき、イーリン・パイプス、アイリッシュ・ハーブ、ストリングスの絡みが醸し出す「天河原」の幻想美も、モンスーンをアメリカン・ポップス正系の伝統でコラージュしたかのような「降いしぐく雨」のグルーヴ感も、そしてガムラン風がせつないほどの情念を温かくデフォルメしてくれる「渡海やひじゃみてぃん」の開放感も、まるで説明できない。
音楽に本来正しい聴き方などないはずだが、香港でもニューヨークでもカルカッタでもいいから一度は旅先の雑踏のなかで、一度は月夜の海沿いを走る車のなかで、一度はウチナーグチの歌詞を一語一語味わいながら、といったように、このアルバムをさまざまな環境でじっくり聴いてみたいものだ。りんけんバンドでもお馴染みの名曲「生まれ島」を聴き終わる頃には、時代のしがらみのなかで忘れかけていた魂の輪郭を思い出せるにちがいない。
上原知子という最上質の歌手にめぐり会えた幸運に、ぼくは今、心から感謝している。 (1997年6月)

○創刊に寄せて
〜雑誌「東北学」創刊号(東北芸術工科大学東北文化研究センター発行)から〜
by 赤坂憲雄(東北芸術工科大学教授(民俗学))
汝の立つところほ深く掘れ、其処に泉あり――。
かの南の島にあって、未踏の沖縄学への道行きを辿った伊波普猷が、座右の銘とした言葉である。
ひとつの思想の流儀が、ここにはたしかに固い結晶と化して見いだされる。
みずからの拠って立つ場所をひたすらに掘ることが、やがてはもっと広やかな、普遍へと繋がる回路の発見へと導いてくれる。
東北学もまた、そうした思想の流儀をもって、いまだ知られざる歴史の獲得へと向かう。
東北ははじまりの場所である。
新たな列島の民族史的景観を拓いてゆくための、それゆえに選ばれた、ささやかな知の脈流の拠点である。
この移ろい、揺れるはじまりの地から、「いくつもの日本」を孕んだ、もうひとつの歴史への方法を鍛えてゆかねばならない。
まず、そこにある東/西の円形なす土俵を、その、あらかじめ約束された予定調和のフィールドを突き崩すことから始めたい、と思う。
西南の方位にある都にとって、東北はつねに「奥」を冠せられた、東の果ての荒涼たる辺境の地であった。
東/西の軸に沿った眼差しの地政学こそが、辺境という宿命を、宿命の装いを凝らしつつ東北に強いてきた根源である。
それは逃れがたい手かせ足かせとなって、その地にある人々の意識を呪縛してきた。
この呪縛を解きほぐすために、いま東/西の土俵の外に立つことが求められている。
それから、南/北の混沌を宿した四角いジャングルへと赴くことにしよう。
この弧状なす列島の南/北の方位には、異相の風景が豊かに埋もれている。
「ひとつの日本」の懐に抱き取られることを拒みながら、縄文へと連なる「いくつもの日本」の鉱脈が覗けている。
それをひとつひとつ掘り起こし、糧として、素材として、「いくつもの日本」を抱いた列島の民族史的景観を拓いてゆかねばならない。
東北はそのとき、縄文を底に沈めて北に深く繋がりつつ、弥生以降の歴史の中では、西の文化をくりかえし受け入れ、大きな変容の跡を刻まれてきた地域として見いだされる。
だから東北には、「ひとつの日本」に穿たれた裂け目が数も知れず存在する。
そこかしこに「いくつもの日本」の影が射している。
東/西に閉じた眼差しの地政学をカッコに括り、南/北の方位へと眼差しを開いてゆくとき、もうひとつの東北が堰を切ってあふれ出す。
そこに、東北学の拠りどころは求められるはずだ。
その向かうべき方位だけは、しかと定まった。
とはいえ、東北学がいまだ、可能性のささやかな種子にすぎないことは明らかだ。
山肌の藪を払い、木立ちを伐り枝を落とし、火入れをして、種を播く。
『東北学』はいわば、このカノ畑(焼畑)の現場である。
藪に覆われた山野に、小さな種子を播くことから始めよう。
東北はやがて、ひとつの可能性の大地として再発見される。
『東北学』はそうして、東北からのルネッサンスの拠点となる。
さて、出立のときだ。
ルネッサンスの前夜、薄明の湿りを帯びた闇の深さが、心地よい。
はじめの一歩を、怖ず怖ずと踏み出すことにしようか。
1999年9月7日 残暑の山形にて
《参考:東北文化研究センター設立の趣旨〜雑誌「東北学」の位置付け》
この春(1999年)、東北芸術工科大学の一隅に、東北文化研究センターはささやかな産声を上げました。
センター設立の宣言の冒頭には、「弥生史観の暗闇の中から、縄文の光が次第に大きく日本の魂を揺さぶりはじめている」とあります。
いま、東北の大地の底からは、もうひとつの東北を求めて足掻く、ざわめきにも似た、数も知れぬ声、声、声……が聴こえてきます。
たとえば東北の歴史とは、弥生の稲作の北上とともに始まるのか、あるいは、坂上田村麻呂の蝦夷征伐によって幕を開けるのか、それとも、はるか一万年の時間を宿した縄文を起点に語られるべきなのか。
そうした問いが、東北のいまを生きる人々のアイデンティティにかかわる問題として、静かに浮上しつつあります。
縄文の光は確実に、東北の現在を照らし出す精神の拠りどころと化しているのです。
それはしかも、たんに東北に限られたものではなく、より広やかな列島の民族史的景観それ自体を、根底から変容させてゆく起爆剤ともなる可能性を秘めています。
弥生に始まる「いくつもの日本」は、古代七世紀に「日本」という国号を戴く国家が誕生して以来、つねに「ひとつの日本」という幻想の繭に包まれ、その存在を隠蔽されてきました。
この時代は疑いもなく、新しい日本文化像の出現を待望しています。
それはおそらく、「ひとつの日本」から「いくつもの日本」へと、また東/西から南/北へと、列島の民族史的景観を拓いてゆくことによって、はじめて獲得されるものです。
東北文化研究センターは、あくまで東北に拠りながら、そうした新たな列島の民族史への道行きを辿ることを願って設立されました。
センターの機関紙として、年二回(四月・十月)刊行される雑誌『東北学』は、以上のような設立の趣旨にそって行われる活動の拠点となります。
(「東北学 vol 1」巻末のお知らせから引用)

○記憶の海へ 〜「別冊東北学」創刊に寄せて
東北芸術工科大学 東北文化研究センター所長 赤坂憲雄
やがて、近代が果てようとしている。いや、すでに近代という時間のほとんどは、命脈が尽きたのかもしれない。
形のない不安に苛まれながら、誰もが何かを探しあぐね、その何かの正体すらわからず、途方に暮れている。
たとえば、村とは何か、国家とは何か、世界とは何か、そして、いま・ここにある自分とは、いったい誰か。そんな古色蒼然とした問いの群れが浮きつ沈みつ、どこか強迫的な揺さぶりをかけてくる。
わたしたちはいま、それらの問いに応答するべき、いかなるたしかな言葉を所有しているか。
新しい言葉の群れが出現しなければならない。眼前に異形をさらし続ける現実を捕捉するための、新しい言葉と方法が欲しい。
逆説的な物言いではあるが、その、いまだ獲得されていない言葉や方法は未来にではなく過去にこそ埋もれている。
少なくとも、その種子だけは、過ぎ去った時代の体験と記憶のなかに、おそらく、すでに播かれているはずだ。
新しげな言葉や方法を密輸入して、したり顔に現実を裁く、そうして知をめぐる産みの苦しみを回避する者らの跳梁跋扈を、いつまでも許してはならない。
汝の立つところを深く掘れ、そこに泉あり―。それが依然として、方法的な起点に置かれるべき覚悟の呪文である。
いま・ここから、新しい言葉と方法を求めて戦いをはじめたい、と願う。
遠ざかりゆく体験と記憶のなかに、未来を照らしだす、たとえば知恵や技術や世界観が埋もれている。たとえ、原石のかけら程度のものであるにせよ、それはたしかに掘り起こすに値するものだ。
世界を記憶すること、そして、記録すること。
記憶はそれぞれの身体に宿りして、しかも、世界を映し、大きな歴史を孕んでいる。
それぞれの個の記憶は、他者の記憶に繋がりつつ、まるで大海に流れ込む幾筋もの河川のように、世界の記憶へと連なっている。
そこには、ひたすら茫洋と、個と世界とがからみ合う、果てしもない記憶の海が広がっている。
どんな記憶も定まった形を持たず、輪郭すら溶けやすく、儚い。
それはただ物語られる現場に、つかの間姿を現わし、ふたたび沈んでゆく。
だから、記憶をこの世に留めるためには、記録という行為による仲立ちが必要となる。
いかなる記録の手法がありうるのか。
聞き書き、ルポルタージュ、自分史、民俗誌……。その手法は多様であっていい。
それぞれの現場にあって、創意工夫が凝らされていい。そこに生きてある人々の声に、ただ謙虚に耳を傾けることだけを、ひそかなる仁義と心得ておくことにしよう。
それぞれの現場から、記憶の海の底深くへと、いくつもの記録の垂鉛を降ろさなければならない。
ここに立ち上げられる『別冊東北学』は、そうした記憶と記録をめぐる実験の場でありたい、と願う。
世界を豊かに記憶せよ、そして、したたかに記録せよ。
2000年7月22日 西蔵王の麓にて

○パナリの風 (高良倉吉著 「切ない沖縄の日々」(ボーダーインク)から)
 八重山のパナリは、昼は焼けつく太陽、夜は質量感あふれる闇となる。しかし、昼となく夜となく、島の表面をなでるように風が吹き続けている。そして、ぞくぞくするような汎神的な雰囲気が漂っていた。
八重山のパナリは、昼は焼けつく太陽、夜は質量感あふれる闇となる。しかし、昼となく夜となく、島の表面をなでるように風が吹き続けている。そして、ぞくぞくするような汎神的な雰囲気が漂っていた。
何百年、何千年にわたって島びとが暮らしてきたこの土地から、30年ほど前に生活が去っていった。今や牧場という単一の生産の場となったこの島では、30年前の生活の跡も、何千年前の暮らしの痕跡も等しく「遺跡」なのである。それらの横に居並んだ時間の上を、実に絶え間なく風が吹き渡って行く。
あの島の夜は、真に夜なのであった。重々しい暗闇が完全に支配しており、その中を酒瓶を片手にさまようぼくの姿があった。よく見ると、闇の中にほんのりと白く浮きあがるものがあった。牛どもが踏み固めた道である。空中に敷かれた獣道、それをたどる俗な人間の遊泳、パナリはやはり汎神的であった。
強い日差しを避けて木陰に寝そべっていると、向こうのほうを犬のクロがのんびり歩いて行く。やることもないので、クロの行動を眺めていた。クロはどうやら牛の後をつけているらしい。足どりも自信なげであったが、時折カラスが下りてきて、クロのまねをして、てくてく歩き、クロのおしりをつついたりする。クロは後ろを振り返り、物憂げな表情をしたかと思ったら、カラスに向かって優越感を投げ、また牛の後を追う。
隣に寝そべっていた牧童が、「あの犬はさあ、自分のことを牛だと思っているわけよ。色も牛に似ているだろ。だけど、同じ黒い色でも、カラスよりは大きいと自慢しているわけよ」、と解説している。
そうか、クロは自分が牛なんだが、みんなより体が小さいのでコンプレックスをもっているのか。しかし、カラスのいたずらに対しては悠然たる態度をとっておれるのか。
今のパナリには犬が1匹しかいない。あとは牛とカラスだらけである。クロの気分を中心とする新しい歴史が、いま始まったのかもしれないな。
そんなクロの劣等感・優越感の上を、やはりパナリの風は吹き渡って行く。 (1989年1月31日)
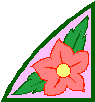

 業(わじゃ)という言葉がある。
業(わじゃ)という言葉がある。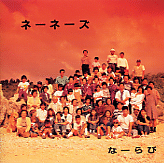 伝統に戻ると言ったのか、原点(もと)にと言ったのか、酒席のことなのではっきりしない。
伝統に戻ると言ったのか、原点(もと)にと言ったのか、酒席のことなのではっきりしない。 沖縄には伝統的に歌上手が多い。ときには素人のなかにもびっくりするほど巧みな歌い手がいる。日本広しといえどもこれほど歌上手が多い地域はないだろう。古典音楽や民謡の歌手はむろんのこと、安室奈美恵やMAXにいたるまで、こうした伝統の上にあることはまちがいない。
沖縄には伝統的に歌上手が多い。ときには素人のなかにもびっくりするほど巧みな歌い手がいる。日本広しといえどもこれほど歌上手が多い地域はないだろう。古典音楽や民謡の歌手はむろんのこと、安室奈美恵やMAXにいたるまで、こうした伝統の上にあることはまちがいない。 八重山のパナリは、昼は焼けつく太陽、夜は質量感あふれる闇となる。しかし、昼となく夜となく、島の表面をなでるように風が吹き続けている。そして、ぞくぞくするような汎神的な雰囲気が漂っていた。
八重山のパナリは、昼は焼けつく太陽、夜は質量感あふれる闇となる。しかし、昼となく夜となく、島の表面をなでるように風が吹き続けている。そして、ぞくぞくするような汎神的な雰囲気が漂っていた。