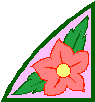○ファーストアルバム録音秘話
(嘉手苅林昌のCD「ジルー」のライナーノーツ) by ビセカツ
 鮮やかに記憶している出来事がある。
鮮やかに記憶している出来事がある。
1964年の暮れも押し迫った12月24日、嘉手苅林昌のファーストアルバムが録音された。
この日、筆者は義兄のおんぼろシボレーに嘉手苅と、これも2000年2月に亡くなった作曲家の三田信一を乗せてコザ(現沖縄市)から那覇の琉球放送ホールへと向かった。
我々を迎えてくれたのは、当時琉球放送で民謡番組のディスクジョッキーを担当していた上原直彦。この日は琉球放送の忘年会があり、本職のミキサーがセットしていったのを、筆者が操作して録音することになった。
さて、始めようとしたが何から録ったものか、嘉手苅がいっこうに曲目をあげようとしない。三絃を持たせてマイクの前に立たせれば自然にうたが出てくるから、との上原の指示で嘉手苅は準備した。そして飛び出してきたのがそれまで我々が全く聴いたことのない歌詞による「かまやしな節」、CDの5曲目に収められた「ヒンスー尾類小」である。
この時の録音ではシングル盤にも使えるように1曲3分以内に収めようという事前の打ち合わせがあったのだが、ミキサー兼タイムキーパーの筆者が目前で展開されているあまりに素晴らしいうたに聴き惚れてしまい、終了のキューを出し忘れてしまった。あの時の驚きと感激は忘れられない。
もうひとつ付け足すと、この日太鼓を叩いたのが八重山民謡の山里勇吉だった。他に人がいなかったから仕方なく呼んだ。というのは、八重山と沖縄本島ではリズムの取り方が違うものだから、普通ならとてもうたえたものではないのだ。
嘉手苅は「勇吉、人の裾を踏んづけるなよ」とボヤいていた。様々な悪条件下でのこの名唱。嘉手苅林昌はやはり、うたの神だったのかも知れない。
不思議な巡り合わせだが、沖縄本島と八重山諸島の源流を同じくすると思われる異名同曲を集めたCD「うたあわせ」(BCレコード、1998年録音、筆者制作)で嘉手苅林昌と山里勇吉は共演することになる。これは嘉手苅林昌最後のスタジオ録音となった。
今回のCDには「ヒンスー尾類小」の他にも貴重な作品が目白押し。「風狂歌人」と合わせて聴いて欲しい。なお「ジルー」とは次良、嘉手苅林昌の童名(わらびなー)である。本土で言えば次郎だ。沖縄のお年寄りたちは今でもこの童名で呼び合うことがある。

○ジルー、嘉手苅林昌とのこと
(嘉手苅林昌のCD「ジルー」のライナーノーツ) by 小浜守栄
戦後の民謡の草創期から一緒にうたって来たけれど、一番最初の出会いはハナタレ小僧の頃だな。越来尋常高等小学校へ、いつも同じ道をいっしょに通っていた。だから嘉手苅のことは小学校時代からわかるんだよ。まあ子供の頃からおおざっぱでノンカー(のんき)で、言うなれば生来の楽天家だった。
わしが三絃を弾き始めたのは小学校5年の時で「上り口説」から覚えた。嘉手苅もすでにその頃は弾いていたと思う。しかし嘉手苅が三絃を弾けると知ったのはテニアン島(南洋諸島)で。でもあそこでは一緒にうたったことはなかった。
 嘉手苅はわしより一つしか年下ではないけれども、体はとても小さい方だった。それでびっくりしたんだが、これが南洋に行ってものすごく身長が伸びた。最初に会った3ヵ月後にはもうかなり伸びていた。終戦直後わしは軍隊から復員し、彼は南洋から引き上げて来ていた。逗子の寮で出会って、久里浜の援護所で一緒に三絃を弾いたりしたな。
嘉手苅はわしより一つしか年下ではないけれども、体はとても小さい方だった。それでびっくりしたんだが、これが南洋に行ってものすごく身長が伸びた。最初に会った3ヵ月後にはもうかなり伸びていた。終戦直後わしは軍隊から復員し、彼は南洋から引き上げて来ていた。逗子の寮で出会って、久里浜の援護所で一緒に三絃を弾いたりしたな。
内地(日本本土)から沖縄に引き上げてきてしばらくしてから、嘉手苅の兄弟に叱られてね。何で手をひっ掴まえてでも連れてこなかったかと。
嘉手苅がようやく帰ってきた時、最初はみんな合点しなかったんだ。外見が変わって、身長があんなにも伸びて、違う人のようだった。
その頃の生活の苦しさは本当に例えようがなくてね、うたどころではなかった。わたしも初めは馬車むちゃー(馬車曳)して。食べ物が無い時代だったからその頃の仕事といえば軍の炊事が花形で、わしは軍作業、チャイナ(中国料理)炊事などをやった。嘉手苅も最初村の馬を借りて馬車むちゃーして、半年くらいしてから自分の馬を買って随分長い間馬車むちゃーを続けていた。
その後嘉手苅はこれでは食べていけないということで、馬を売って劇団に入りその地方(じかた)をやり始めたんだ。
嘉手苅林昌という人は本当に楽天家で、家族の者がひもじい思いをしていても何とかなるさと全然あわてないわけ。わしはその点ではとても神経質だったけれど。全然違う性格だったが、うたいにはあちこちへよく一緒に行ったものだった。
(1992年4月インタビュー。写真は昭和27年頃のおとう(CD「ジルー」から)。)

○空(くう)を旅する人
(嘉手苅林昌さんを偲んで(Okinawa Online HP)から) by 吉村喜彦
沖縄で、「お父」あるいは「おじい」と呼ばれ親しまれていた嘉手苅林昌さんが逝ってしまった。
きっと100歳まで生きてくれるだろうと思っていたので、突然の旅立ちとしか思えず、まだ実感がわかない。しかし、心の中に開いた穴は日増しに大きくなっていくし、沖縄のとても大事な宝物のような人をなくしてしまった脱力感も大きい。
林昌さんとはじめて会ったのは4年前。それまではステージで背筋をしゃんと伸ばして歌う姿を眺めるだけだった。ときどき聴衆に語るでもなくつぶやく言葉はすべてウチナーグチなので何を言っているのかさっぱりわからなかったし、演奏を終えると自ら「終わり」とつぶやいたり、なかなか一筋縄ではいかない、たぶんちょっと気むずかしいおじいだろうと思っていた。
取材の旅に出るためにコザの嘉間良(かまら)バス停で待ち合わせをしたが、三線ケースを片手に持って古い樹木のように立っていた。「バス停からお家は近いのですか?」と訊くと「歩いて5分。走って2分。這ったら10分」と何食わぬ顔で答えを返してきた。この一言が林昌さんへの距離を一気に縮めた。
続いて林昌さんは「煙草はやめたんだよ」と言いながらハイトーンを吸いだしたので、けげんな顔で見つめると、「買うのをやめたんだよ。もらうのはしようがない」と再びとぼけた。
こうしてはじまった旅の中で、いくども林昌さん独特のアフォリズムを耳にした。
海を眺めながら、 「ぼくは速くはないけど、いつまでも泳いでいられる。絶対、沈まない。焦ったら沈むよ。 ぼくの友人は泳ぎが上手でね、50年近くたっても潜ったまま、まだ帰ってこない。何でも『上手』と『好き』があるさ。ぼくは自分のうたが上手だと思ったことはないよ。ただ好きなだけさね」と語り、自らの酒の上での失敗談(酔っ払って見ず知らずの人の通夜に出て焼香していた)をした後、
「失敗がないというのが最大の失敗さね。人間であればこそ失敗もある。軽くいくことさ。突っ張ってると案山子と同じ。ああ、負けるもんかと思うことが失敗。今度の戦も負けてよかった。だいたい、ぼくはいままで勝ったことがない」と語った。
林昌さんは酒が好きだった。「飲まないときは全然飲まない。でも飲んだら止まらない。ノー・ブレーキ」と自らを評したように、はじめての旅の宿で夜を徹して泡盛を飲んだ。人を好きになると耳を噛むと聞いていたが、その夜、べろべろになった林昌さんはぼくを羽交い締めにして、耳を噛んだ。何よりもそれがうれしかった。
一般的には1920年(大正9年)生まれとなっていたが「ほんとは、大正5年生まれさ」と教えてくれた。なぜ4年さばを読んでいるのかは言わなかったが、林昌さんの周りには神話の霧が立ちこめていたような気がする。
越来村(現在の沖縄市)で生まれ、9歳の頃に母親の影響で三線を弾きはじめた。尋常小学校を3年で自ら「卒業」し、下男奉公に出る。16歳で大阪に旅立ち、製材工場で働いた後、沖縄に戻るも南洋移民となり、遠くトラック諸島まで放浪。現地で軍隊に召集され、昭和20年に復員。鶴見、大阪で沖縄芝居の地謡をつとめ、昭和24年に沖縄に戻る。
戦死したとばかり思っていた息子が帰ってきたのを喜んだ母は1週間カチャーシーを踊り続けたという。その後、沖縄の島々浦々を芝居の一座とともに旅して回り、録音したシングルレコードは100枚以上、アルバムも30枚を超える。
林昌さんは一生の間ずっと旅を続けていた。旅が好きだった。奥南洋クサイエ島(この島の女性と恋仲になったが彼女と別れて復員した)に行きませんか、と誘うと目を輝かせ、絶対行こうと約束してくれたが、それを果たせなかったことが残念だ。
旅をしながら、林昌さんの言葉はうたになっていった。行く先々の土地のうたを口ずさみながら車の振動に揺られていた。真夏の昼下がり、蝉の声をバックに宿の部屋でひとり三線を弾く姿はとても美しかった。村を歩くと「林昌さんですよね?」とよく声をかけられたが、「いや、違うさ。よく間違えられて迷惑してるんだよ。ぼくは林昌の弟だよ」と飄々とこたえ、とてもキュートな笑顔を見せていた。
ある夜、コザの民謡クラブで夜中過ぎまで酒を飲み、酔いの回った林昌さんを自宅まで送っていこうとすると「いや、送ってもらわんでもいい」と何度も言う。が、とにかく自宅前まで送り、そこで別れた。車をUターンさせて大通りに出ようとすると、煙草をふかしながら真っ暗な道を背筋を伸ばして自宅とは逆方向に歩く林昌さんが、ヘッドライトに浮かび上がった。
「男は出たら、旅だよ」と車の中でつぶやいていた枯れさびた声が忘れられない。
照れ屋でジョーク好き。言葉になる前のリズムや間を大切にし、押せば引く、引けば押すような話の呼吸をもっていた。その精神の根元には老荘に近い「大いなる虚」あるいは「空(くう)」の思想が宿っていたような気がする。器は中が空いているからこそ器の用をなす、ということを体現していた。
林昌さんが長い旅に出ていってしまった心の穴は、だから、林昌さんが開けてくれたとても大切な穴なのだ。ぼくらはこの大きな穴をしっかりと持ち続けなければならない。
今ごろ、林昌さんは、ハイトーンの白雲に包まれながら、心ゆくまで「買うのをやめた」煙草を吸い、ノー・ブレーキに酒を飲み、空の歌をうたい続けているだろうか。

○嘉手刈林昌の回り舞台
(嘉手苅林昌さんを偲んで(Okinawa Online HP)から) by 宮里千里
1994年11月、ある賞が嘉手苅林昌に授けられた。「沖縄県文化功労賞」という。沖縄では最大の名誉ある賞だといわれている。平和とか経済とか自治とか教育とかの部門もあるのだが、沖縄という地域柄を考えると文化部門というのが一番かも知れない。
で、お祝いをということになった。場所はもちろんのことコザだった。親戚縁者も多かったはずだが、圧倒的に民謡関係者が占めていた。面白いことに、会場内は早送りのビデオテープみたいにせわしかった。そこに集った琉球民謡協会の面々は、ほとんどがいわゆるプロである。民謡クラブで唄っていたり、民謡教室(民謡研究所というのが正式な名称だが)で教えていたりする。
ということで、仕事の合間に顔を出していたのだろうか、それぞれ三線ケースを抱えてきては大急ぎでお祝いの一曲を唄ってはさっさと帰っていく。それが何人もそうするものだから、妙に落ちつかないでいた。
沖縄民謡界オールスターが出演しての「祝う会」が大盛況だったのには意味があった。沖縄の音楽は大きく分けて古典音楽と沖縄民謡がある。誰がどこで決めたのか、古典音楽は「上」で沖縄民謡は「下」という悪しき風潮が長い間にわたって横たわっていた。首里という中央集権の地域と結びついて古典音楽が根付き、他の地域には庶民的な沖縄民謡が広がっていった。
ややもすると「下」に位置していたのを沖縄どころか全国に認知させたのが嘉手苅林昌であった。それゆえに本人は関知しないところで大御所と呼ばれ、あるいは神様にも祭り上げられたりしていた。
宴が終わって、参加者は三々五々会場を後にするのだが、主役は黒ずくめのスーツに渋目のネクタイだったが、客を会場出口付近で見送るではなしに何となく坐っていた。この坐り方が何とも素敵であった。ヤンキー坐りの変形で、両足底をピタッと床につけていた。つまり和式便所でのスタイルであった。後ろに回って見とれてしまった。こういうスタイルでかっこいいという人はまずいない。誰にも真似のできないほどに独特の世界を持っていた。このときほどカメラを持っていないことを悔やんだことはない。
とにかく多くの人から絶賛された。ところが不思議なことに金にはほとんど縁がなく、驚くほどのギャラで唄いまくっていたように思うのだが。
1993年9月9日、沖縄ジァンジァンが幕を降ろす直前だった。「言葉のコンサート」ということで進行役の上原直彦と組んで舞台に立っていた。おそらくは独演会という形で最後だったのではないだろうか。見事なまでに完璧であった。
「嘉手苅語録とエピソードを集めたら、一冊の本が出来上がってしまう」と新聞に追悼文を書いたのはビセカツこと備瀬善勝さんだったが、本当にそうであった。いつもレギュラー出演していた琉球放送の「芸能バラエティー ふるさとバンザイ」での上原直彦とのやりとりは、嘉手苅の飄々とした存在を存分に引き出していた。そしてそれを客席からいつも見つめていた熱狂的なファンが多くいたことを覚えている。
みんなの脳裏には、微動だにせず「きょーつけ!」の姿勢で唄っていた姿が焼き付いているはずだ。

○嘉手刈さんのこと
(嘉手苅林昌のCD「琉球情歌行」のライナーノーツから) by 大城美佐子
 今の人たちは幸せだよ、昔は師匠と向かい合って三絃習うということはなかった。皆が集まって、習いにというより、息使い、指使いを見に行きよった。私の場合は下(しも)でお茶を入れながら耳は皆の話と三絃の音を聴いていた。
今の人たちは幸せだよ、昔は師匠と向かい合って三絃習うということはなかった。皆が集まって、習いにというより、息使い、指使いを見に行きよった。私の場合は下(しも)でお茶を入れながら耳は皆の話と三絃の音を聴いていた。
この人から三絃習いたいと思ったら、この人の仕事を全部奪い取って、掃除、床拭き、鍋洗いも終わってからやっと向かい合って、それも四、五分というようなものだった。「山原汀間当」を習うために、大阪で住み込みまでやったことがある。だから嘉手苅さんの場合でも、一緒に弾いて習うことなんてとんでもなかった。どこどこに唄いに行くといったら、仕事を早く切り上げて、車代も出してお供させてもらって、袖で聴いて、節回しとか、クセとかをすべて盗もうと考えていた。そこに着くまでにいろいろな話をしてくれるわけ。唄の話。これを聴くのが本当に楽しくて。
若い頃はどんなに気が沈んでいても嘉手苅さんの唄を聴いたら気持ちが落ち着きよった。
渋谷ジァン・ジァンの頃の話? あの頃はよく食べて、私の分は嘉手苅さんが「お前は肉は好きじゃなかったよな」と、パクリ。
セイ小(登川誠仁)はカチャーシーのイメージが強かったけど、嘉手苅さんはとにかく、すべての唄においてみんなに信頼されていた。労さん(竹中)も任せっきりって感じだった。
いつだったかね、私の店で飲んでいたとき、嘉手苅さんが足腰立たないくらいしたたか酔っ払って連れの二人の男に担がれて送り返された。翌日嘉手苅さんが現れてケロッとして「ゆうべやなーやがてし酔いたっさー」(笑)(昨夜はもう少しで酔っ払うところだった)。店ではこの言葉がしばらく流行言葉になっていた。すべてにおいてこの調子だから憎めないわけ。
私にとって、知名定繁が「おやじ」なら嘉手苅さんは「あにき」かね。今ごろ天国で、二人して一緒に三絃弾いているかもね。
(1999年11月インタビュー)

○「ジァン・ジァン」での嘉手刈林昌
(嘉手苅林昌のCD「琉球情歌行」のライナーノーツから) by 上原直彦
「帰ろう!こんな防空壕みたいな所では歌にならない!」
着いたとたんにこれである。穴ぐら、暗闇、彼にとっては好ましいイメージではない。それは必ずしも‘戦争’とはつながらないが、それによる労苦に関わることだけは確かである。もちろん、方言で「帰ろう!」と言うのだから意味を知らない伊藤公一氏などはニコニコだが、小生は気が気でない。なにしろ頑固この上もない嘉手苅だから…。そこへ「お疲れさま」と声をかけ入ってきたのが雪村いづみさんで、彼女もここで毎月歌っていることを説明すると、嘉手苅曰く。
「彼女とは映画のスクリーンではあるが、子役時代からのつきあいである。彼女がここで我慢しているのなら、ボクも我慢しよう」
だからこのレコードのほんとうの制作者は雪村いづみさんである。ありがとう。
沖縄人はどう考えても日本人ではないようで(日本人です)、したがって我々の‘島うた’を充分味わっていただくまでにはいきませんが、この一枚がきっかけになれば幸い…。
音・言葉…それらを文字にするもどかしさ…。むしろ、解説的文字どもがこの一枚を聴くのに邪魔なのかも知れません。
「地方人は地方の言葉で語るときに真に自由である」と申しますが、うた・言葉でさえ接点のないニッポン国…遠いなあ。
それでいて、ニッポン国によって開発(いや破壊?)されていくオキナワ…。どうしよう。こっちからニッポンを差別してやろうかしら。ナムアミダブツ。
(1974年4月発売のLPのオリジナル解説)

○嘉手刈林昌の世界
(嘉手苅林昌のCD「琉球情歌行」のライナーノーツから) by 竹中
労
‘祖国’復帰前の1969年、はじめて沖縄を訪れたとき、コザ市の作曲家、普久原恒勇氏のお宅で、嘉手苅林昌の島唄を聴いた。いっぺんでこの風狂の謡人(うたびと)の擒になった私は、会う人ごとに、そのウタ・サンシン(歌・三絃)がどんなに素晴らしいかを説いてまわり、自分でも私家版のLPを製作するという(沖縄春歌集/海のチンボーラー、URC)、熱の入れようであった。
耳を引っ張るようにして、現地へむりやり連れていった人々もある。この盤を制作した伊藤公一君や、ディレクターの武田京子さんも、いうならば私の島唄狂いにまきこまれて、嘉手苅林昌の世界の住人となったのである。永六輔、大島渚、長部日出雄、熊井啓、平岡正明といったお歴々をふくめて、ヤマトンチュー(日本人)嘉手苅信徒の第1号であることを、私はささやかな誇りとしているのだ。
じっさい、かくも蠱惑的に吹く風の調べを、他に知らない。
「旅や浜宿り…」アカバナー咲く琉球弧の島々を漂泊しながら、私はふとおのれが嘉手苅のウタ、サンシンのリズムのままに動いている、いや動かされているのに気づくことがあった。つまり、その島唄は琉球の自然、人情そのものだった。
若かりしころ、チャーリー・パーカーよりほかに神はなしという、短絡したジャズ狂だった。美空ひばり、ザ・ビートルズ、そして 嘉手苅林昌。4番目の‘神様’である彼のうたこそ私のもとめていたもの、ビーバップ、流歌、リバプール・サウンドを止揚して、人間の始源へ回帰する、風と水のリズムであった。これからそう長くもない唄の旅路に、魔のごとく襲う一期一会の音楽的昂憤を体験することが、度々あるとは決して思えない。
‘嘉手苅学’の大家である上原直彦が、歌詞の解説で詳しく語っているので、蛇足を必要とはしないだろう。そして、与那覇朝大の描く仏桑華(アカバナー)の血の色に、すべては尽くされているのだ。単に過客にすぎぬヤマトンチューの私が、いまさら何を喋々することがあろう。このLPを聴くあなたの耳に、琉球弧を吹く潮騒のリズムが届けばと思う。
琉球放送のディレクターであり、忘れられようとしていた宮古、八重山の島唄を電波に乗せた上原直彦、いちずにアカバナーを、琉球庶民の‘県花’であるこの花を描きつづける与那覇朝大、私の敬愛する友人たちがみな、「沖縄/ニッポンではない!」という、屈折した想いを抱いていること、つまり‘祖国’復帰の欺罔に、異族の言葉と節廻しでうたわれる島唄を通じて気づいてくれたなら、さらに幸せである。
工工四(クンクンシー)という独自のペンタトニイク・サンパチロク(八八八六)の詞型でうたわれる沖縄の歌謡は、明らかに大和文化圏の埒外にある。音楽の世界に限っていえば、‘琉球共和国’はまさに日本列島から独立しているのである。それが、嘉手苅林昌の世界、私のユートピアである。
嘉手苅林昌の略歴を、かいつまんで紹介すれば、彼は大正9年(1920年)7月4日(旧暦)、現在のコザ市である沖縄県中頭郡越来村で生まれた。通称、カテイガルのジルー、尋常小学校3学年中退、10歳で年期奉公、16歳で大阪に出て製材所の職工となった。大分46連隊に入隊、特例をもって三絃の携行を許可される。除隊後は南洋諸島のテニアン、サイパンに渡り、港湾荷役、製糖工場等々を、三絃片手に流れ歩く。現地召集、25歳で復員、敗戦4年目の沖縄に帰り、馬車曳き(バサムチャー)となる。やがて世の中が落ち着いてくると、逆に流浪の生活がはじまる。琉球芝居の下座でタイコをたたき、サンシンを奏で、本島、宮古八重山の島々、その足跡のいたらぬところなし。嘉手苅島唄は漂泊の日々に、さまざまな呂律(りょりつ)を呼びこみ、増幅していく過程に円熟したのである。…以上ダイジェスト。
眼中に金銭も名聞もないこの謡人を、束縛することは不可能にちかい。この盤は、めずらしくその嘉手苅が、東京にやってきて渋谷のジァン・ジァンで開いた、リサイタルの実況録音である。司会し解説を、上原直彦と私が交互に相つとめた。
沖縄から同行した大工哲弘は、かつて私が全日本歌謡選手権(よみうりTV)の審査員をやっていたときに、島唄一本で7週を勝ちぬいた。
大城美佐子もまた、貴重な存在である。大工は市役所の職員である、アマチュアである、大城も家庭の人であるという。嘉手苅林昌の世界は、その裾野において豊饒である、ゆえに決して滅びることはない…。
(1974年4月発売のLPのオリジナル解説)

○酔どれ親父の流れ節
(嘉手苅林昌のCD「海・恋・戦」のライナーノーツから) by 上原直彦
 「ひと口、乗らないか」
「ひと口、乗らないか」
永六輔氏の勧めで始めたのが、沖縄ジァン・ジァンの柿落としシリーズの内の<言葉のコンサート>であった。
入場料をいただき2時間。それに値する内容の話題、話術を持ち合わせていない私は、嘉手苅林昌大兄との<トーク&島うた>というスタイルをとることにした。時に何を言っているのか長年付き合いの私にも判らない林昌大兄の語り口。それが、逆に客受けして<上原直彦の言葉のコンサート>は初回から大兄に乗っ取られてしまった。以来<嘉手苅林昌の言葉のコンサート=助手上原直彦>は、3ヶ月、5ヶ月越しに10回ほど開かれ、沖縄ジァン・ジァンの名物シリーズのひとつになった。
嘉手苅林昌。
「先輩。友人。知人としては最高の人だが、親兄弟、親戚には決してしたくない人」
それだけに林昌大兄と組むには気苦労があった。と言うのも、その日の大兄の精神状態によって、歌、話の内容が変わってくるからだ。もちろん、大兄相手のトークに、台本なぞいらない。ぶっつけ、アドリブの世界なのだが、例えば、大兄の懐に千円以上の現金が納まっているとか、負けなしでパチンコを楽しんできた日はよい。積極的に人生を語り、沖縄と世界平和の行き先を訥々と論じる。が、その逆の場合、あるいは、昨夜の酒が醒めるか醒めないかの間(はざま)が、開演時間の潮時と合致すると最悪。ひと言も発せず、生返事ばかり。しかも、歌ははしょるは、三絃の手は抜くはで、相方づとめはハラハラで心臓に悪影響を及ぼした。それでも客は、そうした大兄にキャラクターを楽しんで付き合っていた。嘉手苅林昌は真のエンターティナーと言い切ることができる。
何回目かの沖縄ジァン・ジァン公演、当日の出来事。
コザから早々に出てきたものの、リハーサルなど完全無視。ジァン・ジァンの楽屋の路向かい、沖映通りのパチンコ屋に直行する大兄の後ろ姿を見て、悪い予感がした。予感は良い事よりも悪い事が的中する。1時間足らずで楽屋入りした大兄の顔色が冴えない。
「那覇はダメだ。まったく出ない。5千円もつぎ込んだのに。パチンコはコザにかぎる」
相当な不満である。那覇市長のせいにしかねない。因みに、パチンコ資金5千円は、私の財布から持っていったモノなのに…。
その日の<言葉のコンサート>は大兄。<やる気なし><大いに手抜き>そのダンマリ加減が、また、客に受けるのだから不可思議以外の何ものでもない。それだけではとどまらない。大兄のノリがよくないシーンになると、客席から、歌の囃しはかかるし、ハネーチャー小(テンポが速い、賑やかな節曲)になると、太鼓、三板など、飛び入りの鳴り物担当者が参加するのだから、これまた<嘉手苅林昌の世界>としか言いようがない。
本人が勝手に「俺のフランチャイズ」としていた沖縄ジァン・ジァン<閉鎖>が報じられるや、
「ヒコ!言葉のコンサートを仕込め。散り行くものに情けをかけてやらねば、沖縄人の心情に反するゾ!」
同感。共鳴。
「さよならコンサート」をキッチリとやった。
そのステージ。開口一番、大兄は言い放った。
「世間は冷たいネ。勝手だネ。沖縄ジァン・ジァンがあるときには来ないのに、無くなると聞いたとたん<小劇場文化の火を消すな><沖縄ジァン・ジァン存続運動を起こそう>と、殊に文化人シェンシェイ方はおっしゃる。理屈に合わない。各種催し物に招待券で無料入場しているのはシェンシェイ方。無料入場者が多いと小屋は潰れる。招待されたら、入場料の十倍の御祝儀を包むのが常識。では今日は、カネを払って入場した皆さんの幸せと、沖縄ジァン・ジァンの閉鎖を知っていながら来なかった人たちの不幸を祈願して、大いに歌います」
会場の拍手鳴りやまず…。
この沖縄ジァン・ジァン・ライブのCD(注:「海・恋・戦」)が出る平成12年。奇しくも東京渋谷ジァン・ジァンが4月に閉鎖された。嘉手苅林昌も風狂の人生に幕を下ろして、10月9日、一周忌を迎える。
あくまで人間臭く、最後までニッポン人になれなかった沖縄人嘉手苅林昌と35年の歳月を共有することができた私。幸か不幸か…。いや、ありがたい時間であった。
林昌大兄は、いまでも時折り私の枕元に座って三絃を弾き歌う。そして言う。
「ヒコ。ここに沖縄ジァン・ジァンを建て直したから、お前も早く来い。<言葉のコンサート>は、続けなきゃなるまい」
私は答える。
「お断りします。まだ、この世に未練があるのです。勝手に一人で演っていて下さい。そして、暫くは夢にも出てこないでヨ。暫くは、呼ばないでヨ」
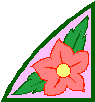

 鮮やかに記憶している出来事がある。
鮮やかに記憶している出来事がある。 嘉手苅はわしより一つしか年下ではないけれども、体はとても小さい方だった。それでびっくりしたんだが、これが南洋に行ってものすごく身長が伸びた。最初に会った3ヵ月後にはもうかなり伸びていた。終戦直後わしは軍隊から復員し、彼は南洋から引き上げて来ていた。逗子の寮で出会って、久里浜の援護所で一緒に三絃を弾いたりしたな。
嘉手苅はわしより一つしか年下ではないけれども、体はとても小さい方だった。それでびっくりしたんだが、これが南洋に行ってものすごく身長が伸びた。最初に会った3ヵ月後にはもうかなり伸びていた。終戦直後わしは軍隊から復員し、彼は南洋から引き上げて来ていた。逗子の寮で出会って、久里浜の援護所で一緒に三絃を弾いたりしたな。 今の人たちは幸せだよ、昔は師匠と向かい合って三絃習うということはなかった。皆が集まって、習いにというより、息使い、指使いを見に行きよった。私の場合は下(しも)でお茶を入れながら耳は皆の話と三絃の音を聴いていた。
今の人たちは幸せだよ、昔は師匠と向かい合って三絃習うということはなかった。皆が集まって、習いにというより、息使い、指使いを見に行きよった。私の場合は下(しも)でお茶を入れながら耳は皆の話と三絃の音を聴いていた。 「ひと口、乗らないか」
「ひと口、乗らないか」