○歌は旅人~黒潮の海を往来した歌たち by 仲宗根幸市
(嘉手苅林昌、山里勇吉のCD「うたあわせ」(1999年)のライナーノーツから)
 民謡は「漂える歌」といわれるように、よく旅をする。ある土地に発生し、ある目的を持ってうたわれた歌が他の土地へ伝播し、その地に根づくことはよくみられる。多くの民謡は流動しながら存在しているのである。
民謡は「漂える歌」といわれるように、よく旅をする。ある土地に発生し、ある目的を持ってうたわれた歌が他の土地へ伝播し、その地に根づくことはよくみられる。多くの民謡は流動しながら存在しているのである。
琉球文化圏では、各ブロックとも民謡の波及、逆流現象が多い。そのような中から派生した異名同曲を集め、八重山と沖縄の民謡の「歌あわせ」を初めて試みたのがこのCDである。これは嘉手苅林昌、山里勇吉御大の遊び心と、「民謡の移動」に着目した斬新な企画によって実現した。
複数の地に同一系譜の民謡が伝承されていることは、これらの地に人間の往来があった証である。伝播は①そっくり伝わる、②変化しながら伝わる、③原型をとどめぬほど変化する、といろいろだ。詩曲に類似性があれば系譜も分りやすいが、大変化している場合は面食らってしまう。その場合は、民謡の変わりにくい要素の囃子詞や、反復形式の類型から手繰り寄せる方法もある。
島々へと伝播した数々の民謡の生き様に触れると、まさに「歌は旅人」であることを実感する。面白いのは民謡が旅をするとき、必ず人々の好みや暖かい思いが加味されていることである。芸術的歌曲が固定化しているのに対し、民謡は時代性、社会性、即興性も反映し翼を広げる。それは南島歌謡史や日本歌謡史の上からも注目されてよい。
それでは琉球列島各地へ伝播させた大きな媒体は何者だったのだろうか。その中心には船乗りやバクロウ、漁師、地方巡業の芝居役者、門付芸人(京太郎)、巡礼者、出稼ぎ、移民、商人、出征兵士などが挙げられる。また、1672年、私娼を集めて開かれたという那覇の辻、仲島、渡地の三大遊郭(渡地遊郭の起こりは判然としない)の存在を見逃してはならない。
沖縄の本土復帰後、徳島県のある民謡・芸能研究家と知り合い、親しく交流してきた。我々には共に地域のテーマを追いかけ、その究明に悪戦苦闘中であった。その過程で、それぞれの住んでいる地のゾメキ(歌、三線で騒ぎ踊ること)の芸能を、いったん自らの地から解き放って黒潮の流れに乗せて考えてみよう、と話は発展。相互の調査の結果、共通性、ちがい、判明したもの、しないものなどが鮮明になった。
我々のテーマは、もちろん日本のゾメキの双璧たる徳島の「阿波踊り」と沖縄の「カチャーシー」が中心。関連して本土の「六調」「ハイヤ節」(ハンヤ節)「奄美六調」「八重山六調」「ガーリ」のスイング感溢れる芸能であった。これら黒潮の流れに息づく乱舞の伴う芸能を、徳島の友は「乱舞の紐」と、私は「乱舞の帯」と名付け、夢をかき立てたのである。
源流を解くことはできなかったが、潜在的に東南アジア方面の南島文化にまで辿れるだろう。黒潮のさんざめきというダイナミックな流れと地域的展開に関心を持った私は、以後、民謡・芸能の流動に海の文化の存在を強く意識するようになった。「黒潮の海」と聞くだけで心のざわめきを覚えるほどである。
周囲を海に囲まれている沖縄は、隔絶した島嶼である。だが、そのことは反対に海によって外界と結ばれていることを意味する。沖縄の民謡を考えるとき、海の役割は大きい。即ち「海が運んだ民謡」が多いのだ。
琉球列島では①沖縄⇔八重山、②沖縄⇔宮古、③沖縄⇔奄美、④日本本土⇔琉球文化圏など、いろいろな伝播のコースがある。また、民謡の移動は海路だけでなく、陸路も多い。
日本民謡の“王様”といわれる「追分」は、近世の半ば以降長野県の碓氷峠一帯でうたわれた馬子歌が源流といわれている。浅間山麓追分宿の飯盛り女の三味線唄が「追分節」となり、やがて「越後追分」「酒田追分」「本庄追分」へ。さらに北上して北海道で「江差追分」を生んだ。一方、日本海へ旅をした追分は「壱岐追分」ともなっている。
また長崎県平戸市田助漁港の色街の酒盛唄が、帆船時代全国の港へ運ばれたのが「ハイヤ節」である。熊本県の「牛深ハイヤ節」、鹿児島県の「ハンヤ節」、新潟県の「佐渡おけさ」、青森県の「津軽アイヤ節」、岩手県の「南部アイヤ節」などとなって、日本海をぐるっと廻って太平洋側へ伝播し洗練されている。
同じくゾメキの「六調」は四国、中国、九州一帯で分布する「ヨイヤナ節」から派生したとみられている。「牛深六調子」「球磨六調子」、南下して「奄美六調」となり、カチャーシー王国の沖縄本島を素通りして八重山へ伝播。少しテンポのゆるい「八重山六調」となって黒潮の海を逆流し息づいている。
ほかに、江戸時代に全国的に流行したと伝えられている「ションガイナ」「ションガ」「ションガエ」系は奄美の「シュンカネ節」、沖縄の「遊びションガネ節」、宮古の「多良間ションガネ」、八重山の「与那国ションガネ節」の名歌との脈流が考えられる。
それだけではない。明治の末、全国的に流行した「ラッパ節」は、九州の炭鉱で与論島の移住者と劇的な出会いをした。与論の人たちはラッパ節を三線にのせ、やがてこの歌は「与論ラッパ節」となり、のちに「与論小唄」へと発展。沖縄の本土復帰後さらに潤色され、「十九の春」となり大ヒットした。そして今度は沖縄から日本本土へと逆流し全国を循環したのだから、歌の持つ生命力は実に凄いものだと感嘆せざるを得ない。

○琉球古典音楽のヒーリング効果(一部) by 藤田 正
(「沖縄は歌の島―ウチナー音楽の500年」(藤田正 著、2000年8月晶文社発行)から)
 けふの ほこらしやや (読み)きゆぬ ふくらしゃや
けふの ほこらしやや (読み)きゆぬ ふくらしゃや
なほにぎやなたてる なをにじゃな たてぃる
つぼでをる花の つぃぶでぃをる はなぬ
露きやたごと つぃゆちゃ たぐとぅ
琉球古典音楽を代表する祝い歌「かぎやで風(かじゃでふう)節」である。
この歌詞に、三線とお琴による、初々しいメロディが付いている。三線と琴は寄り添う花のように、あるいは愛を成就させた若い男女のように、静かに右へ左へと揺れる。その姿がとても美しい「かぎやで風節」である。
「かきやで風」は、祝いの席に欠かすことのできない沖縄第一級の歌である。
歌の意味するところは、今日の誇らしい気持ち、嬉しさは何にたとえようか。それは、ツボミが露を受け花開かんとする時のよう、ということである。
まことにめでたい。
またそのめでたさ、美しさを、万物が完成する直前に求めているのがこの歌である。花が咲く直前に、ヒトが感じるドキドキした気持ち、華やかな瞬間を迎える期待。これを「かぎやで風」は「誇らしゃや」と、胸をたくさんの空気でふくらませたような言葉で書きあらわし、歌っている。
ぼくはこの「かぎやで風節」を手がかりに、かつて沖縄が琉球と呼ばれていた古の時代の音楽とは、どのようなものであったかを、これからしばらく語っていこうと思う。
「かぎやで風節」は、老人の舞いとセットになっている。子孫をもうけ、今や富も地位も万全という無敵状態となったお爺さんが、みんなの前でピカピカの衣装を着て踊る、という設定である。一般に「かぎやで風節」は、その踊り「かぎやで風」に多くの目が注がれるがゆえに、歌に込められた若々しさと、お爺さんのダンスがなぜ一組になっているかは語られることはない。
花のツボミに水滴がたれるという場面は、朝のみずみずしさを映し出すものであり、同時に「セックス」をも象徴している。
まぁイヤラシイ。
と思うあなたこそ、心が曲がっている。
現世でいかに名をなした人であろうとも、いずれ天は人を地上から連れ去る。神さんからお声が一番先にかかるはずのオジイチャン、オバアチャンが、時に子たちを連れて「かぎやで風節」で踊る「めでたさ」の本質は、ここにある。「かぎやで風節」には、めぐり巡って、再び元の場所に戻る、返りたいという切なる願いが込められている。人間の円環である。
めでたさ、誇らしゃとは、人の「死と再生」のもう一つのタトエである。だからこそ、「かぎやで風節」の歌詞にはフレッシュな輝きが込められ、そのメロディは若いカップルをたたえるように可憐なイメージで作られているのである。
「かぎやで風節」は、生きることの意味を問う歌である。

○平成ワタブーショー制作メモ by 藤田 正
(照屋林助のCD「沖縄チャンプラリズムの神髄1」(1996年)のライナーノーツから)
『平成ワタブーショー』は、照屋林助による、ひさしぶりのレコーディングである。
照屋林助自身が書いた略歴によれば、1981年の『沖縄、祭り、放浪芸』(CBSソニー)以来ということだから、実に15年ぶりのアルバム発売となる。
CD時代となってからはもちろん本作が最初だが、林助は「40年ぶりだ」という。つまり初レコーディングと同じ気持ちで望むという意味なのだと、ぼくは思っている。また、一本のマイクを立てて「さあ歌ってください」というフィールド・レコーディング型、あるいは民俗音楽録音型ではなく、録音当日から遡ること約1年の歳月をかけ、企画・選曲などに本人自身も加わる形でアルバム全体の構想を練るという本格的なレコーディング作業は、彼にとってこれが最初の試みである。
 プロデューサーとしてぼくが彼に依頼したのは、二つだけである。一つは、ヤマトの者にも理解できるようにウチナーグチの多用は避けてほしいこと。二つは、「普段着の林助」を録音したいということである。息子の照屋林賢は、ずっと以前から「林助の凄さをみんなに見せつける強力な作品を作るんだ」と断言しており、ぼくはそれと最終的に対をなす作品ができればと願ったのである。
プロデューサーとしてぼくが彼に依頼したのは、二つだけである。一つは、ヤマトの者にも理解できるようにウチナーグチの多用は避けてほしいこと。二つは、「普段着の林助」を録音したいということである。息子の照屋林賢は、ずっと以前から「林助の凄さをみんなに見せつける強力な作品を作るんだ」と断言しており、ぼくはそれと最終的に対をなす作品ができればと願ったのである。
照屋林助は現在、一人でステージをこなすことが多い。かつてのワタブーショウやマーニンネーラン・バンドではなく、自分で一つ一つ音を打ち込んだ伴奏をバックに、自分が弾く四線(よみせん)と歌だけで活動している。場所は、コザ独立国大統領官邸の二階にある「てるりん館」と決めた。「普段着」であるならば、この場所以外にありえない。
コザ独立国大統領とは照屋林助のことだが、彼のそばに、林助が沖縄で一番に認めるギタリスト、松田弘二(ひろじ)を呼び、二人だけでステージをつとめてもらうことにした。松田は林助の腹心であり、同国のギター大臣でもある。今回は、二人だけのステージにより、林助の「遊ぶ姿」を見せたかった。観客は、「同国閣僚」たちを中心にしたごく限られた仲間たち20人ほどである。
すでにお気づきと思うが、タイトルに「沖縄よろず漫芸」とあるように、このCDに展開される照屋林助のステージは、歌だけではない。ゆるやかにテーマを持った一つの話があり、そのあとで関連する歌がうたわれる。ぼくも少し前までカン違いしていたのだが、照屋林助はシンガーではない。歌もうたう「総合的芸能人」なのである。
録音当夜(1996年3月3日)は、前座をつとめていただいた照屋正雄、玉城満(司会も)、照屋林賢、どんとの各氏のライヴをふくめ4時間以上という豪勢なものだった。トリの照屋林助は2時間強ステージに立った。この林助が受け持った前半部が、本アルバム『平成ワタブーショー
沖縄チャンプラリズムの神髄 1』に収められ、後半部が『同2』となったと思っていただいてかまわない。
その2時間、照屋林助は少年期を語り、戦争を語り、歴史を語り、民俗を語り、三線の意味を語り、伝説の巨人・小那覇舞天を語っている。それらは多岐にわたっているようにも見えるが、根本は一つしかない。それは、時も人も物も、すべてが交流しあい、最後には「オキナワ」と呼ばれる場所へと同化させてしまうこの島国ならではの混合性「チャンプルー文化」のパワーと、それに対する限りない愛情と感謝についてである。
照屋林助はこれを、彼自身の言葉で、「チャンプラリズム」と名づけた。ぼくらはその沖縄混合文化の権化である御当人、テルリン先生の導きのもとに、本CDで南邦庶民文化の秘密を知ることになるのである。
林助がよく口にすることであるが、『平成ワタブーショー』のような舞台は、漫談とはいっても非常に特殊な唯一無二の形式を持っている。漫談は基本的にお笑いであるのに対し、照屋林助の話には笑いを呼ばない学者のような視点を随所に発見することができる。でも笑えないからといって単に研究発表かというと、そうでもない。可笑しくはないが、面白い。だが、なるほどと感心したあとに、今までの話は「ウソだ」とくる。そして、トークばかりかというと、歌もある。それもポピュラー音楽系統から沖縄民謡、沖縄演劇の抜粋まであるのだ。まさに、そのステージ構成自体からして照屋林助は「チャンプラリズム」なのである。
『平成ワタブーショー 沖縄チャンプラリズムの神髄 1』は、「伝統的」な神様への祈願から始まる。このレコーディングが、どうか成功しますように、ということである。今回のレコーディングは、先ほども書いたように日本語(共通語)を理解する方であるならば、おおよそ判る内容であるので、ここではぼくは内容の解説はしない。ただ一つだけ、テルリンの資質が知れるのに、ヤマト者にはまず理解できない箇所を説明させてもらって、この原稿を終わりにしたい。
それは「ウートートゥ、ウートートゥ、マヤーコートゥ」という最初の呪文である。日本国の言語にやたらと詳しい林助によれば、「ウートートゥ」とはオリジナルが「ああ尊や」ということ。これは真面目な言葉だ。だが、これとぴったりゴロの合う後半の「マヤーコートゥ」は、ネコが手招きしている様子を指すのである。
みゃ~みゃ~(マヤ~マヤ~)と鳴きながら頭に手をやるネコを指すこの言葉は、沖縄ではユーモラスで笑いを誘うものとして使われている。だから、「山入りの呪文」は、「ああ尊や」という真面目な言葉から、突然冗談へと移ってしまうことになる。
ゲラゲラ笑いを誘う部分ではあるのだが、実はこの「マヤーコートゥ」とは「招き猫」のこと。かつては「千客万来」という意味で使われていたのだが、それが時の経過とともに、誰も原意がわからなくなり、猫の可笑しさを形容するものに変形してしまっていたのである。つまり、めでたく、ありがたい願いである本来の「マヤーコートゥ」の意味を発掘した林助は、意図的に「ウートートゥ」のオチに、この文句を持ってきたのである。
林助による、このような発想の豊かさは、本アルバムの様々な部分に見つけることができるはずである。
(写真は、照屋林助のCD「沖縄チャンプラリズムの神髄2」のジャケットから)

○てるりん、その憎めないスマイルの中身 by 藤田 正
(照屋林助のCD「スマイル」(1998年)のライナーノーツから)
 このCDは、照屋林助にとって4枚目の作品となる。(中略)
このCDは、照屋林助にとって4枚目の作品となる。(中略)
96年の『平成ワタブーショー』が発売された頃から、照屋林助はがぜん忙しくなった。再開され大掛かりな会場に変わった「琉球フェスティバル」では(96年)、りんけんバンドと共にトリのステージに立った。この時の、りんけんバンドに併せた彼の朗読は、その声の響きにすら芸があるというほどの、極めて美しいものだった。
公演は東京はもちろんのこと、京都、大阪、富山、福岡といった場所でも行った。現代沖縄大衆芸能における最大の人気者は、大都市を除けばこれまで殆どヤマトに足を踏み入れたことはなかったが、彼はどこでも温かい歓待を受けた。ぼくの故郷である富山県の伏木という小さな町では、県下に住むウチナーンチュの方々が遠方からわざわざ集まってくださり、お父さんやお母さんはその小さな孫や子たちに挨拶をさせていた。
中の一人がいわく、
「新聞を何度見返したことか。こんな方と、自分が生きているうちにもう一度会えるなんて、会場に来るまで信じることができませんでした。孫には、林助さんという方をぜひ見せておきたかったんです」
ぼくはこの時、照屋林助という人が単なる人気者ではないことを、初めて体験的に知ったのである。このような、静かだが熱い支持を得た結果だろうか、『平成ワタブーショー』は1万枚という、この手のCDとしては異例の好セールスとなった。
97年9月、照屋林助はヤマト制作による初めての単行本を出した。筑紫哲也氏の対談本『沖縄がすべて』(河出書房新社)である。続いて本年(98年)の1月、『てるりん自伝』(みすず書房)を刊行。つまり、照屋林助のヤマトへの本格的な登場は、およそ2年間で第一段階を終了したといっていいはずである。
では第二段階。
その端緒が、『スマイル』である。
『スマイル』の基本的な構成はこれまでのオーマガトキ盤と変わらない。歌と語りによる、林助が言うところの「漫芸」である。ただ今回はライブではなく、まず音楽部を先に録音し(97年3月19日)、後から録音した(同3月22日)話の部分と編集した。観客は入れていない。音楽部の担当は彼のマーニンネーラン・バンド。「照屋林助&マーニンネーラン・バンド」名義のCDアルバムは、今回が初めてとなる。
『スマイル』における大きな変化とは、「沖縄の笑い」とテーマを絞り込んだことにあるはずだ。照屋林助のお得意であり、また沖縄文化の中心を構成する重要な要素について、彼は語り歌う。
ただし、これも林助のお得意芸であるが、話はあちゃらこちゃらへと自由に漂っていく。その漂い方がまた、林助的であり沖縄的なのである。CDの最後あたりに出てくる元コザ市長・大山朝常氏(昨年話題になった『沖縄独立宣言』を書いた人物)の話など、「スマイル」どころか「真剣勝負」の逸話だが、林助流のこのあり方がまた面白いのである。
林助流の「笑い論」において、最も重要なのが、トラック9「国頭サバクイ」に端を発する箇所である。
「国頭サバクイ」は、沖縄本島北部地方で歌い継がれる有名な木遣り歌で、種子島にも同じ系譜のものが存在するほど(「ヨンシー踊り」)伝播力がある。「川田の国頭サバクイ」「城(ぐしく)の国頭サバクイ」「伊江島の…」と、リアレンジされたサバクイが各地に存在するのだが、照屋林助の鋭いところは、この木遣り歌で重要なのは歌詞カードに載ることのない笑い声への注目である。
はたして人は、おかしいから笑うのか?
そんな笑いよりも深い、人間の営みの根底に根差す笑いが存在するのではないか?
照屋林助は「国頭サバクイ」において、このような問いかけをしているのである。彼がわざわざトラック11で同系列の「多良間ヨンシー」(実況録音、これは男ヨンシーと言われるものだろう)を紹介しているのは、そういうわけである。人の生活を脅かす「驚異」「恐れ」「魔物」を撃退するために、忘れるために、あるいは近づけないために人は笑う。芸能の本質を考え続ける照屋林助らしい指摘であろうとぼくは思う。
ただし、いくら内容が学術的ではあっても、照屋林助はそれをあくまで自分の芸の中に取り込んでしまう。時折、ほんとだろうか?と思うような話があるけれども、それは林助らしいキュートなマジックなのである。
『スマイル』には、ちょっとヘンクツに考えれば「ヤマトに対するパンチ」らしき箇所がいくつも出てくる。寒いクニと温かい沖縄との芸能のあり方の差、などという部分は、なにしろぼくが北国出身ということもあって、「うーむテルリンめ、その高笑いは何ごとか!」と思わせる。恐らく林助氏、これに関してはホンネを喋っていると思うのだが、この人の存在の仕方というかしゃべり口というものは、本当に憎めないものがあるから困っちゃうのである。童歌である「いぇー烏(がらさ)」などにしても、ヤマトの暴力的な支配と沖縄の関係を暗示させた痛烈な歌だが、こういうものを「テルリン流おもしろ文化論」の中で何気なく持ち出してくるのが照屋林助という人なのである。
このアルバムは、前の『平成ワタブーショー』に比べれば、とてものんびりしたテンポで進む。「人道とは」の話なんて、のほほんスマイルの典型であろう。だが、そういった中から、林助氏の「刃」がちらりと見え隠れする。ぜひこういった味を楽しんでいただきたいと、ぼくは願うのである。

○舞天随想 by 桜沢有理
(小那覇舞天のCD「沖縄漫談 ブーテン笑いの世界 VOL1」から)
 ここに一葉の写真がある。男の眼はどこか遠くをさまよい、この世ならぬものを見ているかのようだ。いや、この世を見過ぎたというべきか。
ここに一葉の写真がある。男の眼はどこか遠くをさまよい、この世ならぬものを見ているかのようだ。いや、この世を見過ぎたというべきか。
私がこの写真に出会ったのはかれこれ1年前のこと。来年33回忌を迎えるこの男のCDを出そうとしていた私は、雲の彼方にいる存在がもう一つつかめず、徒らに時だけを費やしていた。しかしこの写真を見た瞬間、初めて生身の人として迫る何ものかを感じた。この人はこの眼で何を見、何を考えていたのだろう。
小那覇舞天。戦後沖縄の大衆芸能の復興に奔走し、乙姫劇団の強力なアドバイザーであり、フォーシスターズの生みの親、そしてなにより自身が法外な笑いの創造者であったブーテン。だが残念なことに、この希有な人物も忘れられつつある。その存在を伝説の彼方に置くのではなく、彼の笑いの本質とは何だったのか、彼の残したものは何だったのかを、時代が大きく揺らいでいる今、もう一度考えてみたい。
舞天の芸風は一言でいうならば、徹底して上の者を笑い飛ばすこと。しかつめらしい古典も、彼にかかると即パロディである。彼自身高い学歴を持つ、いわゆるディキヤーだったが、普段もの静かでくそ真面目な人間が、面白おかしく百面相をするだけで人は腹を抱えて笑った。心に潜む欲望をシニカルに見つめる深い洞察力と社会性、教養に裏打ちされたすその広い芸、奇想天外な展開とユーモアとで人を徹底的に笑わせたのである。
そしてあの、余りにも有名なエピソード。戦争で家庭を失い、沈み切った人々の家に「命(ぬち)ぬ御祝事(ぐすーじ)さびら」と押しかけ、こんな時代だからこそ生き残った者たちは笑わなくては、と三弦をかきならした。笑いは命の祝祭しは、なんと生命力に富んだ言葉だろう。
舞天は多くの人に愛され慕われたが、彼は本心をあらわにすることはなかったに違いない。晩年、病を得て痩せたからだに密かにさらしを巻きつけ、人に気づかれぬようにしていたという。乙姫劇団の団長、間好子はいう。あの方はやるとおりに見ているだけでした、人生に対する注意は誰も受けなかった。しかしその間がいまだに忘れられない一言があるという。「好ちゃんやー、沖縄なかい、汝(いゃー)夫ないしぇー生まれてうらんさいさー。」そしてこの言葉どおりに結婚することはなかったのだから、あの方は人をよく見ていたと笑う。
 沖縄戦で嘉手納から北部まで逃げまどい、戦後石川の捕虜収容所に入れられた舞天は、文字通り地獄を見たろう。人間のはかなさ、愚かさ、無力感。戦後、駆り立てられるように活動したのは、彼自身、ポッカリと心にあいた穴を埋める必要に迫られていたのか。人々を愛し大衆のエネルギーを信じながらも、どこかその猥雑さを突き放して眺めている。もちろん自分さえも。そのことが中が見えぬ凄さ、怖さとなって表れる。
沖縄戦で嘉手納から北部まで逃げまどい、戦後石川の捕虜収容所に入れられた舞天は、文字通り地獄を見たろう。人間のはかなさ、愚かさ、無力感。戦後、駆り立てられるように活動したのは、彼自身、ポッカリと心にあいた穴を埋める必要に迫られていたのか。人々を愛し大衆のエネルギーを信じながらも、どこかその猥雑さを突き放して眺めている。もちろん自分さえも。そのことが中が見えぬ凄さ、怖さとなって表れる。
結局のところ舞天の眼が何を見ていたかなどということは分らないのだ。追っても追っても雲の彼方に逃げていくだけだ。それでも人々に強烈な印象を残し、舞天の芸は永遠でいる。
戦前戦後を通じて方言撲滅運動が続いた時代に(戦時中は方言がスパイ語とみなされ、日本兵に殺された人さえいた。)これだけ沖縄口で通したことに、やはりこの人は反骨の人だなと思う。そんなことはおくびにも出さなかったろうが。
何十回となくこの古い音源を聴いてつくづく思うのは、今ではもうこんな沖縄口を日常で聞くことはなくなった、ということだ。現在ではウチナーヤマトグチという、標準語に方言をまぜたようなものを使っているが、それは匂いはするがやはり沖縄口ではないだろう。言葉はその国の文化そのものであるだろうに、21世紀には5~7千の言語の95パーセントが失われるという。そのうち沖縄口教室でこのCDも聞かれるのだろうか。
しかしどのような時代になろうとも、人々を真に魅了する芸能を創ろうと努力していくことこそが、私達に課せられているのだ。 (2000年10月23日)

○CD「新良幸人 パーシャクラブ」から by 新城和博
 このアルバムを聴きながら、初めて八重山民謡と出会った日を思い出していた。那覇、平和通りのマチグヮー(市場)角のライブで新良幸人と太鼓の相棒仲宗根哲(愛称サンデー)が演奏していた八重山民謡は、僕の心の底の方にコツンと落ち着いた。那覇に住む僕が初めて意識した八重山民謡だけど、これは宝物になるぞという予感。民謡のほんとの出会いと言ってもいい。それから何故幸人の歌う八重山民謡に魅かれるのか考え続けた。
このアルバムを聴きながら、初めて八重山民謡と出会った日を思い出していた。那覇、平和通りのマチグヮー(市場)角のライブで新良幸人と太鼓の相棒仲宗根哲(愛称サンデー)が演奏していた八重山民謡は、僕の心の底の方にコツンと落ち着いた。那覇に住む僕が初めて意識した八重山民謡だけど、これは宝物になるぞという予感。民謡のほんとの出会いと言ってもいい。それから何故幸人の歌う八重山民謡に魅かれるのか考え続けた。
「謡の島、踊りの島」である八重山の中でも、特に芸能が盛んな村として有名な、石垣島白保村出身の幸人は、幼い頃から必然的に三弦を手にし、島の唄を歌っていた。高校時代は、八重山古典音楽コンクールで最年少で受賞したりしているが、彼の本格的な音楽活動は大学進学で沖縄島那覇に出てからと言っていいだろう。三弦を自由自在に扱い、島の民謡を歌う。民謡が伝統芸能という枠に囚われていない、ひとつの自由な音楽であることを魅力たっぷりのパフォーマンスで証明していった。
幸人を追うようにして白保からやってきた後輩であるサンデーが島太鼓でコンビを組んでからは、さらに活動が広まり、沖縄島々だけでなく日本国各地でも、独自のライブ活動を続けた。普通民謡というイメージだと民謡研究所とか民謡酒場とかになるわけだが、二人の場合ライブハウスでブルースのように、ロックのように、ポップスのように、歌い、演奏する。それを可能に出来る、幸人のボーカルと三弦プレイヤーとしての実力は、並大抵のものではない。
「こんなふうに自由にやっていいんだ、音楽だから」。そこに「民謡の可能性」を見たのが、上地正昭である。元りんけんバンドのべーシスト(このバンドではギター)の彼は、それ以前から那覇の音楽制作事務所「PAO
MUSIC COMPANY」でCM音楽制作等の活動を続けてきた。またレコーディングスタジオにいた時期もあり、琉球舞踊の音楽や民謡、古典音楽の録音も経験している。その中で沖縄音楽の魅力を知った彼は、りんけんバンドへの参加を経て、その魅力を今の時代にアピールするビジョンを持っていた。その彼が初めて幸人を見たのは、毎年りんけんバンドがトリを取っていた「オリオンビアフェスタ」のステージである。「もう感動した!すっげーことしている奴がいるなって」 民謡を新しいアレンジで聞かせるというビジョンにまさにうってつけだったのが幸人の存在なのであった。
この二人の出会いの確かさが、新しい世代の沖縄音楽を作り出すバンド「パーシャクラブ」の魅力である。バンドのメンバーは神村英世(ベース)、神村英(鍵盤)、津波古慈乃(ドラム)、金城盛長(三弦)、そして上地正昭と、那覇出身在住であり、幸人もサンデーも長年那覇に住んでいる。民謡の宝庫「白保」と沖縄一の都会「那覇」との遭遇、融合がこのバンドの音と言えるかもしれない。
アルバムに収録されている曲のほとんどが八重山民謡。幸人のレパートリーの中でもよく歌われるものばかりだけど、ソロの場合と違って、バンドならではの大胆で細心なアレンジが施されている。しかしあくまでも民謡の素晴らしいメロディーは壊していない。この絶妙なニュアンスは、やはり沖縄、島の人間の血なのだろう。民謡を核にして、いろんなテイストの音が見事に調和している新しい沖縄音楽である。
例えばよく子守歌として歌われる「月ぬ美しゃ」は幸人が歌うと見事なラブソングになるのだが、パーシャクラブバージョンではさらにムーディーに仕上がっている。普通沖縄の三弦は、伴奏楽器、バッキングとしてつかわれるものだが、幸人の場合完全にリード楽器である。三弦のソロとシンセギターなどとのからみは、このバンドならではのものだろう。
このアルバムは、レコーディングスタジオに入るのを避けて沖縄本島北部、大自然の山の中のログハウスに機材を持ち込んで録音された。アルバム全体の開放感はその環境が反映されているのかもしれない。
オリジナル曲である「風ゆイヤリ」は作詞新良幸人、作曲は上地正昭コンビのしぶいラブソングだが、新しい世代の沖縄音楽を目指すバンドの方向性が見事に示されている。新しいものを絶えず作り続けること、それが伝統を受け継ぐことなのだから。
「パーシャクラブ」は、誕生してから一年もたっていない新人バンドである。しかし、これから新しいチャレンジをしていくバンドである。このCDはそんなバンドから送られたライブへの招待状なのである。那覇のマチグヮー角で幸人とサンデーのライブを見て以来、さまざまなライブを体験したけれど、「パーシャクラブ」のライブはまた新たな八重山民謡を見せてくれた。衝撃的と言ってもいい。
僕たち世代は「島唄」ということで妙に敬遠したり、逆に過剰に誉めすぎたりするけれど、彼等のライブを聴いていると、そんなことは忘れてしまう。民謡は、何百年に渡って歌われてきたヒットソングなのだ。そしてそれは時代に応じた演奏でさらに輝くはずだ。あくまでもその時代と人に支持されるポップミュージックでなければならない。それを楽しく証明してみせたのが「パーシャクラブ」なのだ。 (1994年6月)

○カケロマの旅
by 仲宗根幸市 (「「しまうた」を追いかけて」(ボーダーインク)から)
 「佳計呂麻は東西に細長い島だ。北に瀬戸を隔て大島の多くの岬が、日を帯びて湾内の静かな水に映る景色は、南の海では見なれない趣であった」
「佳計呂麻は東西に細長い島だ。北に瀬戸を隔て大島の多くの岬が、日を帯びて湾内の静かな水に映る景色は、南の海では見なれない趣であった」
これは柳田国男の「海南小記」のひとコマの紹介であるが、加計呂麻は「大島筆記」では“慶留間”、「南島神話」では“佳奇呂麻”、「海上の道」では“佳計呂麻”――となっており、現在は記録地名で「加計呂麻」があてられている。
南の島々を跋渉して、一番忘れられないのは私の場合、波の音である。特に加計呂麻の波の音は優しいさざ波ながら、胸をかきむしるように強烈に訴えてくる。
沖縄ともゆかりの深い諸鈍部落の波の音は絶品だ。樹齢三百年のデイゴの巨木が百メートルも続く海岸に立つと、諸鈍湾に寄せては返す波音は旅人を必ずや一瞬立ち止まらせ、魅きつけよう。
特に夕方陽が落ちた後の波音は、周囲の静寂を打ち破り、優しくわれわれに迫ってくる。まさしく風と波の自然の音楽だ。あの波の音は沖縄の浜辺では経験し得ない音だ。それは加計呂麻がリアス式海岸で、岬と入江が複雑に入り込み峡湾が多いことによろう。この諸鈍の波の音は、私が逍遥した他の地域の波とは、さざ波のでき具合や音が異なっていた。
コウモリが羽をのばしているかのような加計呂麻の北側と、大島海峡に面している部落の波の音には相違が見られる。諸鈍部落が位置する徳之島側に対面している南側の峡湾の波の音は、皆独特で印象深い。
最近、加計呂麻のある部落を訪ねたことがあるというA氏と話し合う機会があった。A氏曰く「加計呂麻のある部落の浜辺の波音を聞きながら飲んだビールの味は最高であり、今でもビールを見れば加計呂麻の夜の波音を思い出す」と語っていた。私も経験者の一人として、その気持ちがよくわかり嬉しくなった。
隣の与路島・請島の並みの音も最高級であり、私は打ち寄せる波の音に魅かれて与路島ではとうとうある晩、歌の録音を中止して、炬火を遠くに見ながら波の音を録音したことがある。
権力的な匂いのする大陸系の文化に対して南島の文化は、より人間を大切にする共同精神がみなぎっている。あらためて孤島文化のよさをみなおしたい。

○登川誠仁のCD「スピリチュアル ユニティ」のライナーノーツ by 藤田 正
 登川さんを、島に住む周囲の人たちは「せいぐゎー(誠小)」と呼んでいる。
登川さんを、島に住む周囲の人たちは「せいぐゎー(誠小)」と呼んでいる。
目下の者であれぱ、本来はこんな気軽な言葉を使えないのだが、町を歩く彼のそばから、「エイ、せいぐゎー!」の掛け声やら、ささやきが、どこからか聞こえてくる。
何かいたずらでもしそうな「せいぐゎー」、今にも三線を持って歌いだしそうな「せいぐゎー」、冗談の一つや二つこちらへ投げかけてきそうな「せいぐゎー」。
登川さんは、歌の島のお偉いさんであるよりもずっと先に、島の人にとって明るい人気者であるようだ。
その誠小の「ぐゎー(小)」であるが、この沖縄特有の言い方は、人や物の語尾に張り付けて言い方を柔らかくしたり、可愛く変える効用を持っている。すなわち、「誠小」とは「せいさん」とか、もっと親しい場合は「せいちゃん」と呼ぶ感覚に近い。
「せいさん」も「せいちゃん」も、私にはとても演劇的な名前である。どこかはかなくて、はかないがゆえにエロチックで、言ってみれば心のどこかに傷と陰を隠し持った男。そんな男を、見つめる島の仲間たち。
焼けつく太陽の下でシャウトする誠小に、湿っぽい映画のラストみたいなものを重ね合わせるなと言われるかも知れない。だが登川さんの歌には、肩越しに「せいさん」と思わず声を掛けたくなる、ある種の「あやうさ」と「はかなさ」がにじんでいる。
私は、登川さんの音楽プロデューサーである以前に、彼のファンなのだが、きっと町で「せいぐゎー!」と声をかける島の人々も、私と同じように、ただ歌が上手いだけではない男が発する「誠小が心の奥底から訴えかける何か」に感応している。だからこその声援であろうと思うのだ。
沖縄の映画として歴史を塗り替える大ヒットとなった『ナビィの恋』に、中江裕司監督が実質の主役として登川さんを連れ出したという理由も、本音の部分では私の感情と一緒だったのではないか。私はこの映画のテーマ・ソング「Rafuti」を、登川さんとイギリスからやって来たマイケル・ナイマン氏と一緒に作らせてもらったが、ナイマン氏も同じような意見だった。
強さ、重厚といった鎧の下に、人の情け、センチメントが溢れかえっている。そんな歌手が登川誠仁である。
登川誠仁さんは、表向き大変にストロングなミュージシャンである。
強く、打てば、ビリリと歌が跳ねる。
野球漫画にあるように、豪腕ピッチャーが投げたボールのあたりが、いつまでもバッターのてのひらに残っているような、重いシビレ。これなくして、登川さんという歌手は語れない。語れないが、その奥に、もう一つ「隠し部屋」を持っているのがこのシンガーの希有なところである。
『Spiritual Unity』のどこでもいいから音を出してもらえば、お分りになるはずである。彼の弦は、いつ切れてもおかしくないほどに激しい音を立てている。声はどうか。全16曲、情緒に安っぽい涙をふりかけたような、うわべだけの情感を描くボーカルは、一切出てこない。
出てはこないが、その先にもう一つの部屋を、私たちは発見してしまうのである。
誠仁さんは、その部屋で泣いている。
だからこそ登川さんは、マジにかっこいいのである。ぼくはそんな彼に、ワールド・クラスのシンガーが基本的にそなえている音の深さを見る。彼は、「琉球民謡登川流宗家」なり「琉球民謡協会名誉会長」なりという、歌の島・沖縄にとっては第一級の大きな肩書きを持つ人だが、実体は、それを遥かに越えているはずである。
アルバム『Spiritual Unity』はそんな「沖縄・歌の大人(たいじん)」の魅力を、私と中川敬(SOUL FLOWER UNION)とで、出来うるかぎり引き出そうとした作品である。
70を過ぎてもなお疾走することをやめない、歌の人、登川誠仁。
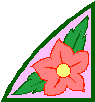 ぜひこのアルバムで、胸震わせていただけたらと願う。
ぜひこのアルバムで、胸震わせていただけたらと願う。

 民謡は「漂える歌」といわれるように、よく旅をする。ある土地に発生し、ある目的を持ってうたわれた歌が他の土地へ伝播し、その地に根づくことはよくみられる。多くの民謡は流動しながら存在しているのである。
民謡は「漂える歌」といわれるように、よく旅をする。ある土地に発生し、ある目的を持ってうたわれた歌が他の土地へ伝播し、その地に根づくことはよくみられる。多くの民謡は流動しながら存在しているのである。 けふの ほこらしやや (読み)きゆぬ ふくらしゃや
けふの ほこらしやや (読み)きゆぬ ふくらしゃや プロデューサーとしてぼくが彼に依頼したのは、二つだけである。一つは、ヤマトの者にも理解できるようにウチナーグチの多用は避けてほしいこと。二つは、「普段着の林助」を録音したいということである。息子の照屋林賢は、ずっと以前から「林助の凄さをみんなに見せつける強力な作品を作るんだ」と断言しており、ぼくはそれと最終的に対をなす作品ができればと願ったのである。
プロデューサーとしてぼくが彼に依頼したのは、二つだけである。一つは、ヤマトの者にも理解できるようにウチナーグチの多用は避けてほしいこと。二つは、「普段着の林助」を録音したいということである。息子の照屋林賢は、ずっと以前から「林助の凄さをみんなに見せつける強力な作品を作るんだ」と断言しており、ぼくはそれと最終的に対をなす作品ができればと願ったのである。 このCDは、照屋林助にとって4枚目の作品となる。(中略)
このCDは、照屋林助にとって4枚目の作品となる。(中略) ここに一葉の写真がある。男の眼はどこか遠くをさまよい、この世ならぬものを見ているかのようだ。いや、この世を見過ぎたというべきか。
ここに一葉の写真がある。男の眼はどこか遠くをさまよい、この世ならぬものを見ているかのようだ。いや、この世を見過ぎたというべきか。 沖縄戦で嘉手納から北部まで逃げまどい、戦後石川の捕虜収容所に入れられた舞天は、文字通り地獄を見たろう。人間のはかなさ、愚かさ、無力感。戦後、駆り立てられるように活動したのは、彼自身、ポッカリと心にあいた穴を埋める必要に迫られていたのか。人々を愛し大衆のエネルギーを信じながらも、どこかその猥雑さを突き放して眺めている。もちろん自分さえも。そのことが中が見えぬ凄さ、怖さとなって表れる。
沖縄戦で嘉手納から北部まで逃げまどい、戦後石川の捕虜収容所に入れられた舞天は、文字通り地獄を見たろう。人間のはかなさ、愚かさ、無力感。戦後、駆り立てられるように活動したのは、彼自身、ポッカリと心にあいた穴を埋める必要に迫られていたのか。人々を愛し大衆のエネルギーを信じながらも、どこかその猥雑さを突き放して眺めている。もちろん自分さえも。そのことが中が見えぬ凄さ、怖さとなって表れる。 このアルバムを聴きながら、初めて八重山民謡と出会った日を思い出していた。那覇、平和通りのマチグヮー(市場)角のライブで新良幸人と太鼓の相棒仲宗根哲(愛称サンデー)が演奏していた八重山民謡は、僕の心の底の方にコツンと落ち着いた。那覇に住む僕が初めて意識した八重山民謡だけど、これは宝物になるぞという予感。民謡のほんとの出会いと言ってもいい。それから何故幸人の歌う八重山民謡に魅かれるのか考え続けた。
このアルバムを聴きながら、初めて八重山民謡と出会った日を思い出していた。那覇、平和通りのマチグヮー(市場)角のライブで新良幸人と太鼓の相棒仲宗根哲(愛称サンデー)が演奏していた八重山民謡は、僕の心の底の方にコツンと落ち着いた。那覇に住む僕が初めて意識した八重山民謡だけど、これは宝物になるぞという予感。民謡のほんとの出会いと言ってもいい。それから何故幸人の歌う八重山民謡に魅かれるのか考え続けた。 「佳計呂麻は東西に細長い島だ。北に瀬戸を隔て大島の多くの岬が、日を帯びて湾内の静かな水に映る景色は、南の海では見なれない趣であった」
「佳計呂麻は東西に細長い島だ。北に瀬戸を隔て大島の多くの岬が、日を帯びて湾内の静かな水に映る景色は、南の海では見なれない趣であった」 登川さんを、島に住む周囲の人たちは「せいぐゎー(誠小)」と呼んでいる。
登川さんを、島に住む周囲の人たちは「せいぐゎー(誠小)」と呼んでいる。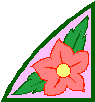 ぜひこのアルバムで、胸震わせていただけたらと願う。
ぜひこのアルバムで、胸震わせていただけたらと願う。