
| 読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と |
|
《No.5》 1 ビセカツ一代記(抜粋) 備瀬善勝 (インタビュー 神谷一義、平井玄) 2 「ヤマト嫁」のプロローグから 吉江真理子 |
「沖縄島唄紀行」(小学館)から3題 文・藤田 正 3 夏の疾風、太鼓の響き 4 本土から届いた平和の願い 5 子は神、神はいつもそこに |
|
|
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集

読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と
感じられる名文が、世の中には数多くあります。
そのようなHP管理人の心情を、お立ち寄りいただいた方々に
少しでも理解していただきたいあまり、
このページを設けてみました。
引用文については、出所等を明らかにしつつご迷惑にならない
よう心がけて掲載させていただきますので、
ご理解のほどよろしくお願いします。
《No.5》
1 ビセカツ一代記(抜粋) 備瀬善勝
(インタビュー 神谷一義、平井玄)
2 「ヤマト嫁」のプロローグから 吉江真理子
「沖縄島唄紀行」(小学館)から3題 文・藤田 正
3 夏の疾風、太鼓の響き
4 本土から届いた平和の願い
5 子は神、神はいつもそこに
○ビセカツ一代記(抜粋) 備瀬善勝 インタビュー 神谷一義・平井 玄
(「音の力・沖縄〜コザ沸騰編」(インパクト出版会)から)
神谷 今日はコザの島うた名プロデューサー、ビセカツ一代記を伺いにきました。
備瀬 僕がコザに来たのは中学二年の三期なんですよ。五歳からそのときまでは本部(もとぶ)にいました。生まれたのは那覇の西新町です。軽便鉄道があって、ちっちゃいときにおんぶしてくれたのが船越キヨ。キヨおばさんは戦後も可愛がってくれました。彼女の唄との接点は全然ないですが、赤ちゃんの僕を可愛い可愛いとよくおんぶしてくれた。もう死にましたが、彼女は戦争で家族を九名亡くしたんです。子供から全部。悲惨ですよ。料亭で三味線弾いて一生終わりました。でも、戦後再婚した旦那さんがよかった。
僕がコザにきたころはまだ一番街が解放されていなくて、基地だったんです。コザ中学にいく道があるでしょ、その左側も基地だった。いまの一番街のアベニュー、センター通りの右側が商店街で左側が基地だったんです。空港通りも含めてずっと中の町まで。中の町の市民劇場は昔、琉米親善センターって言ったんだけど、我々は皮肉を込めて植民地センターと言ってました(笑)。あの通りから全部、ここらは基地だったんです。山原(やんばる)から出て来た頃の町一番の繁華街はコザ十字路でした。
平井 戦後すぐですか。
備瀬 すぐじゃないですよ。僕は終戦のときは幼稚園生でしたから。コザの始まりは嘉間良(かまら)なんです。コザ十字路から南へ向けて坂があるんですが、あの右側一帯に警察署やら教会やら芝居小屋があった。修学旅行で通ったことがある。
僕がきて一番最初にびっくりしたのは、商店街の大売り出しのときに朝からエライおっさんが三味線弾いてるんです。お酒を前にして。たまに弁当の差し入れがあったりてんぷらの差し入れがあったり。商店街が開くのが朝の九時くらいで、閉めるのが夜の八時か九時くらいです。その間ずっと一人で三味線を弾いている。誰かなと思ったら、嘉手苅林昌さん。エライ人がいるなと思って、僕ずっと聴いてたんです。三時間くらい聴いて、同じ唄が全然出てこない。エライ化け物がコザには住んでるなと思った(笑)。
本部では昔テルリン大統領(照屋林助)が紹介した、立琴の、奄美の里国隆の追っかけをよくしました。あの辺までナフタリンを売りにきてたんです。あの人の唄は奄美の唄や当時の流行歌が主で、人を集めてやってました。あの人は流行歌が半分くらいでしたが、嘉手苅林昌はなにをうたっているかわからない。軍の払い下げのマイクに三味線を持って、蓄音機をかけないで、一人でうたってました、センター通りで。日当をもらってるわけじゃないんですよ、食事と酒だけ。
・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・
神谷 民謡に西洋楽器が入ってきたのはどういう影響なんでしょうかね。やはり戦前から(普久原)朝喜さんがやっていたからですか。
備瀬 それもあるでしょうけど、結局、マンドリンが流行ったのは三味線が高くなったからよ。マンドリンは最初は五千円以下で買えたから。それで四弦を三弦にしちゃうんですよ。三線のチンダミ(チューニング)でやるわけ。そうすると音も面白いし。バイオリンも弾いてましたが、又吉真栄さんがクウチョウ(胡弓)を普及させるために一生懸命やっていたからクウチョウに代わりました。沖縄民謡は本来ファンソウ(横笛)はないんです。八重山の人はファンソウがありますが。ほとんどないです。サンバ(三板)叩いてやるくらいで。あとでギターがそばで立ち始めたのは喜友名朝幸あたりが初めかな。徳比嘉政治あたりが、すごいんですよ、クラシックギターのボディーの割れた奴、変な音がしてね。最初聴いたとき、箱三味線があるじゃないですか、鹿児島のゴッタン。あれかなと思って(笑)。ああいう感じで伴奏して受けて、レコードでヒットしたもんだからギターを入れるようになったんですよ。民謡酒場で最初の頃はギターを三味線みたいに弾いていた人もいましたよ。
神谷 電気三味線というのもその頃ですか。
備瀬 そうですね、あれも民謡酒場のせいですね。あれは幸地ラジオが国際通りにありまして、ガイドさんが持っている感度の悪いマイクがあるじゃないですか、あれじゃないとうまくいかないんですよ。林助は自分で発明したと言っているんですが、あれはみなさん同時に発明したんじゃないかと思うけどね。あれは感度のいいマイクだとだめなんです。口をくっつけてしゃべるやつ、感度の悪いマイクだとよかったんです。
神谷 昔のシングルで登川誠仁さんのにもギターとドラムが入っているのがありましたよね。ドラムを知名定男さんがやっている。
備瀬 マルタカレコード。フォーシスターズがコンボとかいろいろやったでしょ。
神谷 ええ。パーカッション、ボンゴとかいろいろ入ってましたね。
備瀬 民謡シンカは、山内昌徳をはじめとして、けっこうバンド好きなんですよ。みなさんカラオケ作ってうたうんです。だから、山内たけしは歌謡曲で全国デビューしたのですが、もっとじっくり沖縄民謡教えとけばよかったのに。優しすぎてだめなんですよ、沖縄の子は歌謡曲の世界では、と言われたんです、武田京子(クールファイブや森進一のプロデューサー)に。山内昌徳さん、目の前で言われて、アンタ、あんな醜い世界に子供いかすのは、優しすぎる、人を押し退けることを知らないからって。これではいつまでたってもだめだって言われたけど、いかしちゃった。
神谷 山内昌徳さんも軍作業やってたんですよね。
備瀬 終戦直後の一番いい仕事ですよ、炊事だもん。終戦直後の炊事っていったら、食料入るし。米兵が残した飯は炊事の連中で分けあったんです。調理するときから持って帰る準備してる。それを持って帰って売ったりした。ものすごいいい職、憧れの職業なんです(笑)。多分、収入はあのときの村長よりもよかったでしょう。教師辞めて軍作業にいった人はいっぱいいましたよ。教師の給料でラッキーストライク一ボール買えるかどうかだもん。ラッキーストライクが基準でしたね、いくつ買えるか。なぜかキャメルのことをシカグァって言うんです、あの当時沖縄では。ラッキーストライクは赤玉。
神谷 その頃は洋モク、洋酒なんかは。
備瀬 ウイスキーはセブン、ハーラー。ベトナム戦争の頃のセンター街の裏は全部白鷺の一升瓶がありましたよ。ウイスキーに混ぜるんです。とにかく、まともなウイスキーは飲めなかったですよ。PXでも酒を持ち出すのはけっこううるさかったですよ。タバコよりもずっと。それで、いっぱい密造をやってました。自分たちで芋焼酎も作るし、その頃に眼潰れた人もいっぱいいました。
神谷 嘉手苅さんは大丈夫だったんでしょうか(笑)。
備瀬 終戦直後に沖縄にいなかったからでしょうね。直後はクサイ島から横浜にいって。一人子供がいるんです。南洋にもいる。あの話は孫の前ではしたがらないね。林昌二郎、帰るときの名前は。珍しい男だね、全然女口説かないけど、いい女が寄ってくるんだよね。いまの奥さんも前の奥さんが私子供産めないので、友達の戦争未亡人を、これは一人だけ子供産んだ経験があるから子供産めるから、あんたこれを嫁にしなさいって奥さんが言ったんです。
神谷 昔の唄者、嘉手苅さんや登川さんたちはもてたんでしょうね。
備瀬 嘉手苅さんが戦前大阪に逃げたのは、お父さんが馬か牛かを売った代金を盗んだから。帰ってくるときに五倍くらいにしてもってきたらほめられた。
神谷 知名定繁さんもそうじゃないですか。みんなけっこう不良だった。定繁さんのお父さんは自転車屋さんだったんですよね。
備瀬 定繁はけっこう戦前の古典を勉強したり、師匠についたりしてやった。それから稼ぎに大阪いきましたでしょ。でも、もてるもんだから、酒も好きだし、大阪で財をなさないで帰ってきた。だから大阪の県人会では人気ないんです。大阪に稼ぎにきたのに唄と酒と女だけで(笑)。朝喜は大阪の県人会では尊敬される。唄もうたったけど、財を残したというので。定繁が嘉手苅林昌と違うのは、ちゃんと師匠に古典を習ったおかげで、すごい仕事しているんです。例えば、沖縄の一番古い流派で湛水流の琴の工工四を作ってみたり。いま考えるとすごいですよ、文化功労賞ものです。終戦後、大阪から帰ってすぐですからね。それでいてなぜずっと貧乏だったんでしょうね(笑)。県や国がやるような仕事を一人でコツコツとして、作り上げて、世に残した。ああいう人たちがいなかったら、湛水流はなくなっているんですよ。
あの人たちの時代までは民謡も古典音楽も区別して考えてない。ただし、学校の校長先生あたりが古典をやっている人たちは、民謡はうたわさなかったんですが、馬車持ちゃーとか、普通の人たちは一緒にうたってました。学問で音楽をやった人たちは嫌ったみたいです。
民謡酒場の前は料亭ですよ、スナックがなくて。料亭と言っても四畳半から六畳くらいで、夜中でも、コンコンと叩いて、ああ、こいつは大丈夫となれば入れる。お座敷があって、誰か三味線弾く人がいて、いまのスナックみたいな感じですよ。サカナヤーと言いますがね、あの頃の料亭は。そこで三味線弾いてた女性もたくさんいますよ。
登川誠仁というのは悪い男でね、そういう歌手は料亭の後ろに自分の部屋を持ってるんですよ。あるとき、彼がある女の歌手を訪ねていったら留守だった。見たらカメラがあって、フィルムが残ってたから、イチモツ出して襖に挟んで写真撮った。その人現像して持ってったら、写したことのない写真が一枚入っている(笑)。そういういたずらをする人だった。子供みたいなもんよ、みんな。その頃の人たちはいっぱいエピソード持っていて、うらやましいですよね。
(登川)誠ぐゎーが名護の劇場で地謡していたときに、羽地(はねぢ)の劇場で嘉手苅さんがいて、そこは露天劇場で雨が降ったから中止になった。嘉手苅さんが遊びにいったら、誠ぐゎーが三味線弾いてた。そしたら、嘉手苅さんの顔見て、三味線下ろして、嘉手苅林昌が続きを弾いたって話とか。芝居の地謡やってたときも、酒飲み過ぎて、気がついたら寝てたとか。嘉手苅林昌は伊江島公演にいって、酒飲み過ぎて、気がついてみたら西表だった(笑)。
・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・
備瀬 りんけんバンドのりんけんが、これから僕らの音楽は日本に受け入れられるんでしょうかって言うから、僕の答えは、多分日本人にも縄文人が多いから、すんなり受け入れられるんじゃないの、当分大丈夫じゃないのって言ったことあるけど。世界の音楽聴いてますけど、本来人のリズムとか民族の違う音楽とか、非常に体受けつけないですよね。例えば黒人に上原正吉の音楽を聴かせると、すぐ帰ります。とくにああいうベターとしたリズムのない情歌を聴かせると。古典音楽でも帰りますけど、一番帰りが早いのが上原正吉で、レコード屋でずいぶん万引き防止で使った(笑)。ところが、嘉手苅林昌かけたら踊りだすんです。僕がこの人の歌を最初に聴いたのは、さっき話したように市場の大売出しのとき。高校卒業して四、五年くらいたってましたかね、嘉手苅さんと飲みにいったりし始めたのは。あれ癖悪いから、誰かボディーガードつけていかないと。一番最初のLP覚えてます?あのときは僕の兄貴のシボレー借りて、「ちんぬくじゅうしい」を作曲した三田新一が三味線持って。上原直彦がディレクターで、琉球放送のスタジオ借りて録音したんですが、年末でみなさん忘年会で、その日、ミキサーはセットだけして、あとよろしくって。で、僕がミキサーなんです。と言ってもスイッチ押すだけ。上原直彦は八木政男に太鼓頼んでいたつもりだったら、頼んでなかった。年末で忙しいし、いない。太鼓がない。どうしようかなと思ったら、山里勇吉がいたんです、運悪く。勇吉さん来いって呼んだんです。ところがあの人は八重山の人で、イエマデーク(八重山太鼓)さ。嘉手苅さんが、なんだこの勇吉よ、人の裾踏んで、動きもできないって怒る。八重山太鼓だから。「ヒンスー尾類小」なんか勇吉さんが全部叩いている、あの頃のLPは。
その前に何をうたうか、一応タイトル、歌詞の出だしを書いてって嘉手苅さんに言ったら、二合瓶の酒置いて、鉛筆と紙持ってずっと座っている。三十分たっても一行も出てこない。それで作戦変えて、うたい出したのをそのまま録ろうということで、始めたんです。タンメーの三味線と嘉手苅さんの三味線を持っていって。唄、「ヒンスー尾類小」うたい出したんです。初めて聴いたんです。びっくりこいた。三分すぎたら合図出して、そうしたら次のフレーズで終わりますということだったんだけど、面白いからつい乗っちゃって、あんなに長くなっちゃった。こっちが忘れてしまった、サイン出すの、聴き惚れちゃって。それであの「ヒンスー尾類小」は最初のレコードでは十七番くらいまである。なにをうたっても時計見ていて三分で終わるという約束だったんだけど、面白いもんだから忘れちゃって、永遠にうたった。あれが竹中労が東京に持っていって、それから沖縄にすごい歌手がいるというので、映画関係者に聴かせて、その後から深作欣ニは来るわ、大島渚は来るわ。
・・・・・・・・・・(続く)・・・・・・・・・・
(1996年10月25日、コザ・キャンパスレコードにて)
○「ヤマト嫁」(毎日新聞社発行)のプロローグから by 吉江真理子
デイゴの大木に赤い花が咲きのこり、集落の星砂が敷きつめられた小道では、いろとりどりの花の列が迎えてくれる。光の粒子が高密度で凝縮してつくりだす青いあおい空。ぽん、と音をたてて立ちあがる、ひとがたの雲。太陽に透かして見る芭蕉の葉。赤瓦の家から三線の眠気を誘う音色が聞こえてくる。ちょっぴり湿りけのある島の空気を、深々と吸うわたしの肺が歓びに満たされていく。
風を切って自転車を走らせれば、記憶のようにふいにやってくる亜熱帯植物の甘やかな香り。それが潮の匂いに代わり、おいしげる植物のあいだからコバルトブルーの輝きを見つけたときの驚き。くるぶしまでの浅い翡翠色の海に横たわり、波のリズムにからだをまかせたとき、細胞のひとつひとつが幸せな吐息をもらす。
うりずんと呼ばれる春の季節と若夏との、ちょうどあわいにあたるころ。
はじめて八重山の島々をまわったときの感動は、いまも忘れない。
あまりに太陽がまぶしくて、軽いめまいをおこしたのか、わたしは不思議な感覚を何度も味わったものだ。明るすぎて冥(くら)い、光が闇に反転する真昼の白昼夢のような一瞬。道を歩いていても海で波と戯れていても、突然、総天然色の世界が写真のポジからネガに変わるように、ぐるんとひっくりかえって見えるように感じることがあった。
珊瑚の粒を敷きつめた真っ白な道に落ちる自分の影。そのコントラストに驚き、光が強ければ、影もまた濃くなるのだと気がつく。
まぶしすぎてあまりにくらい、沖縄の両義性――。
それは、偶然ひきよせられるように迷い込んだ御嶽という聖域の深い森の闇にも、月のない夜の離島の漆黒の闇にも重なる、はじめての体感だった。
昼の明るさと夜の暗さ。光と闇。この相反するふたつのものが、それぞれの濃さをきわめるほど、両者は互いをひきたてあう。その振幅が大きければ大きいほど、それを包含する宇宙の器は大きくなる。
わたしが沖縄にひかれるようになったのは、その懐の深さ、そして光と闇の交錯する姿が東洋思想で言う陰陽のように感じられたからではないかと、いまでは思っている。それは宇宙のエネルギーの法則そのものを表わしているからだ。
1990年、二度目の沖縄旅行で、わたしはすっかり八重山諸島にはまってしまった。
土地の魅力もさりながら、人のあたたかさが乾いたこころにしみた。ちょうどそのころストレスから病をかかえこみそうになっていたわたしにとって、それはこころとからだを潤す癒しのひとしずくのように感じられたものだ。
光のあふれる南の島は、人々の気質も南国特有の明るさとゆるやかさ、やさしさに満ちている。台風や干ばつといった自然の脅威を受け入れてきた島人にとって、支えあって生きることはDNAに刻まれた知恵なのだろうか。かつて日本のどの土地でも感じることができただろう地域共同体の体温が、島をすっぽりと包みこんでいる。その温度がとてもここちよかった。
人は個人で存在するけれども、ひとりでは生きられない存在でもある。それを日常の一瞬一瞬に手応えとして実感できる場所、それが沖縄だと思ったものだ。
都会の追いたてられる時間のなかで縮んでしまったこころをゆったりとのばし、やわらかく揉みほぐすことのできる場所――。わたしにとって沖縄はまったく別の時間の流れる異次元の空間のように感じられた。それはどこか懐かしく、魂のふるさとのような既視感をも、ともなっていた。……
藤田正・著、大城弘明・写真による「沖縄島唄紀行」(2001年7月、小学館発行)という本があまりにもすばらしく、充実した内容だったことから、あまりの感動、ヨロコビに耐えられず、ここに全29題中3編をご紹介します。「数ある島の名歌に耳を傾けながら沖縄の旅に出る」というこの本の趣旨に共鳴する方は、残念ながら前文及び沖縄らしいカラー写真の数々までは紹介できませんので、ぜひ買って読んでみてください。(泣)
○夏の疾風、太鼓の響き 〜七月エイサー
七月遊びや 面白むん (七月の遊び 風雅の遊び)
踊たい 舞うたい 遊びみそぉり (踊り、舞い 楽しみ召され。)
「南嶽(なんだき)節」
七月、沖縄の夜は、沸騰する。
エイサー、エイサー、サーッサ
サーッサ、エイサー
広場の向こうから、通りの先から、とどろくあの声がこちらへ向かって進んでくる。
陽の落ちた町にこだまする太鼓の響き。街灯の下に勢ぞろいした青年たち。吹き出す汗が、路上に散る。待ちかねたこの祭りのために、二才達(にーせーたー、若者達)が集うその姿、この気合い。エイサーは、夏の沖縄の夜を駆け抜ける。
エイサーとは、お盆に帰ってきた先祖をあの世へ送り出す、そのフィナーレを飾る祭りのことである。
沖縄のお盆は、旧暦の7月13日から15日までの3日間、ウンケー(先祖のお迎え)、ナカヌフィー(中の日)、ウークイ(お送り)と名前がつけられているが、エイサーは、先祖を送る最終日、あるいはその翌日に行われるパレードだ。
イーヤーサーサー、ハーイーヤー
ッスリ、ッスリ、ッスリ、ッスリ
地面に叩きつけるような太鼓のビートと、それを軽妙に跳ね上げる掛け声のリズム。若者は揃いの衣装で隊列を組み、街路を練る。
片脇に抱えた大太鼓を、乱れなく打ち鳴らす沖縄市園田(そんだ)の青年会。朱や紫の頭巾が、陽に焼けた顔に凛々しく映える。紺の着物をタスキがけ、黒い帯、頭は白巾(しろさーじ)という小粋なデザインは、勝連町平敷屋(かつれんちょうへしきや)の青年会。彼らは手に持つ小さな太鼓だけで見せ場をつくる。
あちこちで指笛が鳴る。切れ目なく伝承歌が歌われる。「仲順流り」(ちゅんじゅんながり)「久高満寿主」(くーだーかーまんじゅーす)「海ヤカラー」「スーリー東(あがり)節」「南嶽節」…。浮き立つ三線の音(ね)、永遠のリズム。
「七月エイサー」とは、奇数曲で構成されたこれらのメドレーをまとめた言い方なのである。
七月(しちぐゎち)七夕 中ぬ十日(とぅーか)
二才達や揃(する)とてぃ 遊(あし)ぶさや 「仲順流り」
(七夕から、中の十日、皆で遊ぶんだ)
月(ちち)や月とぅ思(うむ)てぃ 明(あき)る夜(ゆ)や知らん
みやらび、腕(うでぃ)枕 な夜や、明かち 「海ヤカラー」
(月だ夜だと思っても、恋の相手の腕枕に夜が明けた)
エイサーは、17世紀の初めに「南無阿弥陀仏」を琉球へ広めようとした袋中(たいちゅう)上人の布教に端を発すると言われている。
死に別れた愛しい実母に会いたいと、あの世の扉が開くこの七月に…今もこんな歌(「継親(ままうや)念仏」)が伝わるように、エイサーは念仏踊りがルーツのようである。エイサーの原風景は、かつて念仏者(にんぶちゃー)や京太郎(ちょんだらー)と呼ばれた、本土から来島した流浪の僧侶、芸能者が作り出したという。
しかし、本島中部に起こったとされる仏供養のこの歌舞も、時を経て、中身は変わった。
約半世紀の歴史を持つ「沖縄全島エイサーまつり」の賑わいを見るまでもなく、現代におけるウチナーンチュ(沖縄の人)としての意識の高まりは、県の内外に数多くのエイサー団を生み出した。関西や関東だけでなく、いまや移民先の海外にも多くのチームを発生させ、その熱気がエイサーをいよいよ活気にあふれた芸能へと変貌させている。
月明かりの下、頬っかむりで家々に酒や金銭を請うて回ったかつての一群は、ウチナーンチュの心意気を示す象徴となった。
沖縄の熱き心、エイサー。今や御先祖様は、その飛び散る若い汗を眼下にまぶしく眺めながら、あの世へ駆けて行く存在なのかも知れない。
○本土から届いた平和の願い 〜さとうきび畑
ざわわ ざわわ ざわわ 広いさとうきび畑は
ざわわ ざわわ ざわわ 風が通りぬけるだけ
今日も見渡すかぎりに みどりの波がうねる
夏の日ざしのなかで (作詞作曲・寺島尚彦)
ずっと向こうまでつづく赤茶けた道の両側に、天に向かってさとうキビが伸びている。一本だとひょろ長くてどこか頼りなさそうだが、キビは畑にいつもびっしりと植えられて、ジリジリと照りつける太陽の下、無数の長い葉を風にうねらせている。
シュガー・ロード(キビの道)。あつい暑い南の島の、風物詩である。
「さとうきび畑」は、このキビの道に一人、おとうさんの面影を追う歌である。
あの日鉄の雨にうたれ 父は死んでいった
夏の日ざしのなかで
そして私の生まれた日に いくさの終わりがきた
夏の日ざしのなかで
主人公は、終戦の日に生まれた人のようである。彼女は、父を知らない。歌は父が軍人であったのかどうかも知らせない。民間人であったか、日本人であったかもわからない。沖縄戦をベースにして作られた「さとうきび畑」ではあるが、歌は特定の戦争に狙いを定めることなく、すべての戦争の悲劇とは万人が共有すべきものであると主張している。戦後に台頭したフォーク世代、寺島尚彦らしい視線である。
NHK「みんなのうた」で、森山良子がうたう「さとうきび畑」が登場したのは1997年の夏のことだった。その清廉な歌声に、たくさんの賞賛が寄せられた。しかし森山は、沖縄が日本に返還される頃(72年)から、この歌をうたってきた。
「みなんのうた」でのオリジナル・シンガーは「ちあきなおみ」だった。ちあきなおみによる初めての放送が1975年の4月。その年の7月に、沖縄本島の本部(もとぶ)で「沖縄国際海洋博覧会」が開催される。しかし復帰後の発展のためにとは名ばかりに、沖縄は「海洋博」によって深刻な経済的打撃を味わう。沖縄の基幹産業の一つである観光事業は、ここにゼロからの出発を余儀なくされる。沖縄戦集結30年目の出来事である。
その15年後の1990年、蘇った観光産業が本格的な軌道に乗った時、「さとうきび畑」の続編ともいうべきザ・ブームの「島唄」がミリオン・セラーとなった。こんもりとしたさとうキビ(ウージ)の畑に、戦争への怒りと、島唄(沖縄の伝統的大衆歌)の癒しを塗り込めたこの歌は、「さとうきび畑」と同じく本土から届けられた名歌として、当時の「沖縄ブーム」を牽引する1曲となった。
でいごの花が咲き 風を呼び 嵐が来た
でいごが咲き乱れ 風を呼び 嵐が来た
くり返す悲しみは 島渡る波のよう
ウージの森であなたと出会い ウージの森で千代にさよなら
島唄よ風に乗り 鳥とともに 海を渡れ
島唄よ風に乗り 届けておくれ 私の涙 (作詞作曲・宮沢和史)
95年の6月23日、糸満市摩文仁(まぶに)の平和祈念公園で「平和の礎(いしじ)」の除幕式が行われる。沖縄戦終焉の地、血塗られた激戦の丘、摩文仁に、判明したすべての戦没者の名を刻もうという記念碑である。
「平和の礎」の基本理念は、「戦没者の追悼と平和祈念」「戦争体験の教訓の継承」「安らぎと学び」である。考えてみれば、これは戦後における沖縄音楽がよって立つ基盤とまるで同じである。2000年の時点で24万人に届かんとする死者の名前を刻む「平和の礎」は、もう一つの「沖縄の歌」だった。
この国が平和だと 誰が決めたの? 人の涙も 渇かぬうちに
アメリカの傘の下 夢もみました 民(たみ)を見捨てた 戦争(いくさ)の果てに
蒼いお月様が 泣いております 忘れられないことも あります
愛を植えましょう この島へ 傷の癒えない 人々へ
語り継がれて いくために 「平和の琉歌」(作詞作曲・桑田佳祐)
「平和の琉歌」は、「平和の礎」除幕式から約2ヵ月後、95年9月に起きた米兵3名による少女レイプ事件に触発された桑田佳祐(サザン・オールスターズ)が書き下ろした。「さとうきび畑」と同じように反戦を掲げた名作である。しかしこのような歌ができるのは喜ぶべきことなのか、悲しむべきことなのか。
戦後の「沖縄の歌」は、未だその歴史を閉ざすことはない。
○子は神、神はいつもそこに 〜童神―天の子守り唄
天(てぃん)からの恵 受きてぃ此(く)の世界(しけ)に
生(ん)まりたる産子(なしぐゎ) 我身(わみ)ぬ守(む)い育てぃ
イラヨーへイ イラヨーホイ イラヨー 愛(かな)し思産子(うみなしぐゎ)
泣くなよーや ヘイヨー ヘイヨー 太陽(てぃだ)ぬ光 受きてぃ
ゆういりヨーや ヘイヨー ヘイヨー 勝(まさ)あてぃ給(たぼ)り
(作詞・古謝美佐子、作曲・佐原一哉)
天の恵みを受け、この世に生を受けた私の子。私が守り育てる。
イラヨー、いとおしい私の子。泣いちゃだめよ、ヘイヨー。
太陽の光を受けて、どうか良い子に育つことを。
子は宝もの。子は未来であり、すべての始まりである。沖縄であろうが本土であろうが、子どもを慈しむことに差はない。
差があるとするならば、沖縄では今も、大人向けの新作歌謡にまじって新しい子守り唄が作られていることである。古謝美佐子がうたう「童神」は、1997年の発表。親から子へ贈る沖縄の子守り唄として、最も新しく作られた名作である。
「童神(わらびがみ)」とは、幼児にあてられた雅語のような言葉である。まだ物心のつかない赤ん坊は、神にいちばん近く「ヒトと神の中間」にいる。汚れなきその姿は、同時に、現代のような医療が想像もつかなかった時代にあって、本当に生きることができるのかどうか、まるで不明の存在でもあった。「わらび・かみ」という言葉には、お腹を痛めた母親からの、計り知れない思いが込められているはずである。
「童神」の二番は、次のようにうたわれる(前半)。
夏(なち)ぬ節来(しちく)りば 涼風(しだかじ)ゆ送(うく)てぃ
冬に節来りば 懐(ふちゅく)るに抱(だ)ちょてぃ
イラヨーへイ イラヨーホイ イラヨー 愛(かな)し思産子(うみなしぐゎ)
(夏が来れば涼しい風を送り、冬になれば懐に抱く。いとおしい私の子)
沖縄の祭りで子どもと言えば、それは「弥勒(みるく)様」とのセットで語られることが多い。ミルク様とは、五穀豊穣の神。もともとは仏教の弥勒菩薩であったものが、南邦の海洋文化と交わることで、独特の存在となったのである。
鮮やかな着物に身を包んだ、布袋(ほてい)様にそっくりのミルク様は、子どもやお母さんたちを従えて、村の向こうから「やぁやぁ」とやってくる。八重山の豊年祭、種子取(たなどぅい)祭、結願(きちがん)祭、節(しちぃ)祭などに現れる、遠目にもはっきりと目立つ大柄でハデなミルク様は、めでたく「ヒト」となった子どもたちを、村の大人たちの前でお披露目する役を担っているとも見えるのである。
もちろん子の成長も、ミルク様がヒトの世に届けてくれる「豊穣」である。
赤田首里殿内(あかたすんどぅんち) 黄金燈篭(くがにどぅる)下(さ)ぎてぃ
うちが明(あか)がりば 弥勒世果報(みるくゆがふ)
シーヤープー シーヤープー ミーミンメー ミーミンメー
イーユヌミー イーユヌミー ヒージントー ヒージントー 「赤田首里殿内」
(首里の赤田の殿内に、黄金の燈篭が飾られて、煌々と灯が灯れば、
さぁミルク様のありがたい果報がやってくる)
本島南部・大里村古堅(おおざとむらふるげん)には「ミーミンメー」という子どものお祭りがある。
首里の童歌とし知られる「赤田首里殿内」の囃子言葉を、小さな子どもたちが紅白の棒(ヂンナーク)を両手に持ち、大きな声でうたい踊る。「ミーミンメー」とうたう部分では、両耳を引っ張りながらチョコっと首を傾げる姿など、その仕草も可愛い。これも豊穣と健康祈願のお祭りである。もちろんチビッ子たちの前には、オジイとオバア役の二人に手を引かれたミルク様が歩く。チビッ子たちはミルク様の子どもであるとされている。
そう言えば、沖縄各地で盛んに行われる綱引にも、その巨大な綱の上に稚児が乗る。この時、稚児は神の霊力が宿る特別な存在である。綱引きも沖縄では害虫駆除祈願、豊穣祈願のれっきとした神事なのだ。
ヒトの始まりそのものである子どもは、大人たちに見守られ祭りに参加しているようでいながら、反面、主催者たる大人たちにとってみれば、村と島の命の円環を完成させるためのまさしく「童神」なのである。
その大人からの思いは、たとえば、八重山の堂々たる儀礼歌「鷲(ばすぃ)ぬ鳥(とぅるい)節」からも、聞き取ることができるはずである。「鷲ぬ鳥節」は、子が童から「若鷹」へと成長した、その輝かしい姿を歌に込めている。
ここでは内容だけを紹介させていただく。
綾のような羽根を持つ若い雛が、虹のように美しい若鷹が生まれた。
それは正月の、元旦の、まだ朝早い時である。
若鷹は東の空へ飛び起ち、あの太陽に向かって舞う。
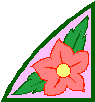
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集