
|
読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と |
|
《No.6》 1 自然を織り込む女性たち 立松和平 2 母と子の残像 森口 豁 3 漂白のマレビト・里 国隆 宮里千里 |
4 別れの歴史 森口 豁 5 珍版ウチナー・ミュージックは、なぜつくられたか (吠えてくれ、誠小先生!) 藤田 正 6 名曲選「戦後の嘆き」 藤田 正 |
|
|
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集

読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と
感じられる名文が、世の中には数多くあります。
そのようなHP管理人の心情を、お立ち寄りいただいた方々に
少しでも理解していただきたいあまり、
このページを設けてみました。
引用文については、出所等を明らかにしつつご迷惑にならない
よう心がけて掲載させていただきますので、
ご理解のほどよろしくお願いします。
《No.6》
1 自然を織り込む女性たち 立松和平
2 母と子の残像 森口 豁
3 漂白のマレビト・里 国隆 宮里千里
4 別れの歴史 森口 豁
5 珍版ウチナー・ミュージックは、なぜつくられたか
(吠えてくれ、誠小先生!) 藤田 正
6 名曲選「戦後の嘆き」 藤田 正
○自然を織り込む女性たち by 立松和平
(「沖縄ポップカルチャー」(東京書籍)に掲載されたインタビューから抜粋)
最近、僕は琉球の織物に興味を持っています。染めと織りで一番元気なのは沖縄なんですよ。沖縄は機械織りをしていないので、とても品質がいい。染めももちろん紅露(グール)とか、フクギとかの植物染料を原料に染めているのがほとんどです。この間、石垣島に行ったときに拝見したんですが、川平では蚕を育てて、繭から糸を紡ぐことからはじまるんですよね。沖縄の織物には、その土地の自然である山とか海や、その土地に根ざした精神性が布に反映されていて面白いんです。
僕は沖縄の織物が好きで、なかでも絣に興味を持っている。自然の素材を材料に群星(むりぶし)や水(みじ)、風模様などの自然を織り込むんですよね。なぜ、天体の星を織ったり、水の文様を織ったり、鳥の模様とかを織るのかというと、そこに自然に向けての祈りをこめるためです。
僕は与那国のおじいにこんな話を聞きました。お姉ちゃんが蚕を育て、糸を紡ぎ、もちろん染料となる植物を山から採取して染め上げた糸で弟の着物を一生懸命織るわけですよね。「これがお姉ちゃんに作ってもらったはじめての着物だ」と、おじいに見せてもらったんですよ。10代の頃に作ってもらった着物を70歳を過ぎたおじいが大切に持っているんです。素晴らしいですね。
沖縄にも琉球藍があるけれど、藍だて(注:藍の原料となるタデアイの葉に水をかけて醗酵させて、藍色をつくること)というのは本土のほうではすごく温度管理が難しいんですよ。温度が上がらないとうまく醗酵しないので、温度管理するのが大変らしいんです。琉球藍っていうのは、その辺のポリバケツで藍がたつんですよ。沖縄は藍染をするには、非常に恵まれた風土なんですよね。山には赤みを生み出す紅露があり、屋敷の防風林にもなるフクギは黄色が採れるよね。
昔の着物は藍が多いんだけれども、藍だてしていると蚊も寄ってこないんですよ。藍染の着物を着ていれば、荒野に入っても蚊が寄ってこない。それは防虫剤の役目にもなるんですよね。たとえば傷口にぬったりすると傷薬にもなる。たいていの植物染料には薬効があるんです。着物を着ることによって病気やケガが治るようになっているんです。それは沖縄でも大和でも同じです。例えば、茜という茜色の染料があります。茜色の着物は古くなると布団にするんです。そうすると風邪なんか治っちゃうんですよね。それは薬をまとっていることと同じなんですよね。これは非常に理に適っていることだけど、今では着物は着るだけの実用品にされてしまって、そういうことが忘れられてしまっているんですね。
日本の織物の少なくとも絣は、沖縄の文化から生まれ伝わったものです。そのもとはもっと南から伝わった。今では、織り染の分野の職人さんのなかには男性もたくさんいますが、織物になぜ星や水などの自然が織り込めたかというと、沖縄には女性が男を守るという思想<おなり信仰>があったからなんですよ。
もちろん女性は自分の着物は自分で織るんですが、沖縄ではだいたいお姉ちゃんが弟に着物を織ってあげたり、母が息子に織ってあげたりするんですよ。その一着に健康に育ちますように、人生の荒波を無事に航海できますようにとの願いが込められているんです。実際に離島では海を渡っていかなくちゃいけないことが多々あったから、星が導きますように、水の災いが無いようにという祈りを織り込んでいると僕は感じたんです。だから単に美しいからではなくて、染めと織りの中に女性たちの家族に対する思いがすごく込められているんですね。
沖縄にこれだけ深い文化がなぜ根づいたかというと、一つは自然条件が恵まれていたから、そしてもう一つは固有の着物文化や伝統工芸を大切にする基盤があったんですよ。そして僕が強く感じたのは肉親への愛情が非常に強くて、祈りが深かったからだと思うんです。今ではどの着物も素晴らしくて、それこそ専門職人の手で優れた商品を作ってますよ。でも、本来の染め織りっていうのは家族の健康を祈って作っていたんですね。
沖縄には染め織りの分野の大家がいっぱいいます。紅型、久米島紬、宮古上布、八重山上布、八重山ミンサー、与那国織、読谷花織、琉球絣、芭蕉布と沖縄にはそれぞれの地域に織物があって、それぞれに独特の風情や風合いが違うんです。そんなふうに染織物が体系的に残っているのは、沖縄だけだと思うんだ。
○母と子の残像 ―ウルトラマンの戦争― by 森口 豁
(「沖縄 近い昔の旅 非武の島の記憶」(凱風社)から)
義足のおんな
毎年六月が来ると想い出すことがある。あの沖縄戦を生きながらえた一人のおんなの突きつけた“戦傷”を前に、身の置きどころを失って戸惑った若き日のぼく自身の姿についてである。
おんなは1921(大正10)年生まれ。毎日のように顔を合わせていたその頃は、40にさしかかったばかりの女ざかりであった。ぼくはそのおんなを、お母さんと呼んでいた。沖縄の女性にはめずらしく色白で、広いおでこに、愛くるしい眼。真夏の暑い日でも和服を上手に着こなしていた。しかし、歩くとからだが左右に大きく傾いた。戦争で片方の足をそのつけ根のところからもぎとられ、義足を当てがっていたからである。
彼女は、その不自由なからだで一軒の小さな食堂をきりまわしていた。その食堂は那覇市牧志の国際通りから横町を少し入ったところにあった。当時、沖縄で新聞記者をしていた独身のぼくは、ここで日ごと1、2食の食事にあずかっていた。食事代は無料。その代わり、彼女の長男が東京・世田谷のぼくの実家で食事を摂っていた。食事の、いや息子の交換をしていたのである。
“義足のおんな”の「息子」になったぼくは、調理場に接した6畳ほどの彼女の居間に通され、いつもそこで食事をした。客の出入りの多い食堂のアンマー(おかあさん)ゆえ、席のあたたまるヒマはなく、一日中、立ったり座ったりの生活だったが、義足のまま座ることのできない彼女は、その都度、和服の裾をたくしあげ、義足のつけ外しをした。すると、太腿のあたりで無惨に断ち切られた白い足が小さな部屋の蛍光灯の明かりの下にさらされた。
そんな時、ぼくは、見ていいものか、それとも目をそらすべきか迷ったが、おんなはぼくの感情にはお構いなく、いつも大胆に裾をたくしあげ義足のつけ外しを繰り返した。1960年代初めの頃のことである。
屋嘉節
その頃、彼女の長男は東京郊外の山中に広いキャンパスを持つ私立大学に通っていた。その彼がぼくに沖縄旅行を促したのは、それより4、5年前の1956年の冬。学年が一つずれていたので当初は顔見知り程度でしかなかったが、その旅行を契機に彼とぼくのつきあいは急速に深まっていった。母親に似て、やはり額の大きな、目の輝いた青年であった。
――本土の若者たちに沖縄の実情を知ってもらおう!
二週間の沖縄親善旅行から帰ったぼくらは学校のなかに「沖縄研究会」をつくり、『見てきた沖縄』と題する10ページほどのガリ版刷りの小冊子を月々発行、全国の高校の生徒会宛てに送りつづけた。当時、学校の寮に入っていた彼は、それからまもなくして東京・世田谷のぼくの家の隣家に下宿してきた。そして双方の屋敷を仕切る生け垣に、背をかがめればどうにか通れるほどの穴をあけ、そこを二人だけの秘密の通路にした。
彼もまた、ぼくの母をお母さんと呼び、親子7人の家族のなかに南島のさわやかな風を送り込んでくれた。
沖縄戦の“鉄の暴風”が吹きすさぶなかで、家族が散り散りになるほどの体験をしていながら、彼は自らすすんで戦争を語ることはなく、いつもことさら明るく振る舞った。ぼく自身の戦争体験といえば、屋敷の一郭に掘られた防空壕のなかから、時折上空で展開される戦闘機の空中戦を親の目を盗んで楽しんだり、サーチライトの明かりで夜空に浮かび上がったB29爆撃機の編隊から投下される焼夷弾が、まるで花火のように美しく開花するのを、半ば恐ろしげに眺めたりしたぐらいであった。そんなぼくに戦争のほんとうの怖さなどわかろうはずもなかったが、戦場からやってきた彼が語りたかったのは戦争の恐ろしさではなく、むしろ戦争が人間にもたらす哀しさであったように思う。
学校に人影が絶えた放課後にはじまるぼくらの小冊子づくりは、時に深夜に及んだ。暗い蛍光灯の下で黙々とガリ版を切った。彼は、沖縄の文化や歴史、言語、芸能などについて書くことが多かった。刷り上げても郵送代が工面できるあてもないのに、それでも一途につづける…、そのようなことの繰り返しであった。
ある夜、封筒の宛て名書きをする彼の口から耳慣れない沖縄民謡の調べが流れ出た。
♪懐(なち)かしや沖縄(うちなー) 戦場(いくさば)になやい
世間御万人(しきんうまんちゅ)ぬ 袖(すでぃ)ゆ濡らち
哀り屋嘉村(やかむら)ぬ 闇ぬ夜(ゆ)ぬ烏(ガラシ)
親居(うやう)らん我身(わみ)ぬ 泣かん居(い)ちゅみ
無蔵(んぞ)や石川(いしちゃ)村 茅葺ちぬ長屋
我(わ)んや屋嘉村ぬ 砂地(しなじ)まくら
「これは《屋嘉節》といって、終戦直後に出来たうたなんですよ」
尋ねるぼくに、彼は言った。
米軍が沖縄北部の屋嘉村につくった捕虜収容所のテント小屋のなかで、誰の口からともなく歌われはじめた民謡だと言う。戦火のなかで生き別れ、死に別れていった親兄弟や愛する人への思いを切々と歌いあげ、甘世(あまゆ:平和な世の中)を願う庶民の心情を吐露したうたであった。ゆったりとした節まわしは、まるで地べたにへたり込んだ人間のため息のようで、戦火に焼き尽くされた島の時空を連想させた。ぼくが教えを請うと、彼は幾度となく反復して歌詞と旋律を教えてくれた。
あの日からもう40年の歳月が過ぎ去ったが、ぼくの脳裏にはつい昨日のことのように、あの残像があざやかだ。青年のままの彼がいまも生きつづけているのである。
“義足のおんな”もまた、ヤマトからやってきた「もう一人の息子」であるぼくに、よく沖縄戦の話を聞かせてくれた。戦争を知らず、むしろ戦争を楽しんだ体験しか持たないぼくがそれをどれだけ理解できたのか、いまなお心もとないのだが、かつてウジ虫のわいた傷口を野にさらしながら弾雨の下を地を這って逃げたという彼女がぼくの前にさらした断ち切られた白い大腿部は、何よりも戦争のおぞましさと、一人の気丈なおんなの胸の内を語っていたことだけは確かである。
母子は沖縄が日本に復帰してまもなく、まるで示し合わせたかのようにしてこの世を去っていった。57歳と38歳。母の名は金城ツル。その息子の哲夫は、ツルがまだ19歳の時に生をさずかったが、二人は、親子というよりは友達同士といったほうが似合う母子であった。
その哲夫は、大学を出たあとテレビのシナリオ作家となり、毎週日曜の夕方、全国の子供たちをテレビの前に釘付けにした<ウルトラマン>シリーズのメインのシナリオ作家として名をなした。そして、ブラウン管のなかに<チブル星人>とか<ジラース><ヤナカーギー>などという名の怪獣や異星人を登場させた。チブルは頭、ジラー(ス)は次郎、ヤナカーギーはブスの沖縄方言だが、その語呂のおもしろさと異質さも手伝って日本人には新鮮に映り、受けた。
しかし、金城哲夫のねらいは単に語呂のおもしろさではなく、そうした名を持つ怪物たちに“沖縄のこころ”を仮託、地球人が抱え込んだ<正>と<負>を人びとにさり気なく提示することにあった。
戦争のおろかさや、核や毒ガス兵器と同居するオキナワ…。
毎年6月が来るとツルと哲夫を想い出すのは、この月が“戦世(いくさゆ)”の月であるからに違いない。
○漂白のマレビト ―里 国隆・街頭ステージ録音ノート― by 宮里千里
(里 国隆のCD「路傍の芸」(JABARA)から)
まず音が消え、その後に風景が消えていく。
長年、民俗祭祀などの録音を記録してきて、ある一つの事柄に確信を持つようになった。神歌を伴う祭祀は、口承による唄を継いできたが、やがて近代という魔物の前にもろくも潰え去っていく。ところが人々の動作は割と最後まで記憶に残るらしく、内容理解はともかくとして脳裏に焼き付くものらしい。音はなくても人は動きを割と最後まで演じきれる。まず音が消える。その後に映像が消える。
那覇の町から、ある音が消え、そしてある男の姿も消えた。
土曜の昼下がり、東京の渋谷の街にいた。スタジオでのマスタリング作業があった。一本のテープが、17年ぶりに長い眠りから目を覚ます。
この街は以前にじっくり歩いたことがある。おそらくは日曜日だったのだろう、多くの大道芸人が繰り出していた。ペルーから来たというフォルクローレのメンバーもいて、ケーナを中心に賑やかな演奏をしていた。彼らは自らの演奏テープを販売していたが、かなり濃厚なレベルと見た。数学者のピーター・フランクが数個の球回しをして、その代償として自著を売っていた。渋谷の日曜日の午後は、誰もがビルの谷間を抜ける風にそよいでいた。まるで沖縄の、うりずんの季節のようであった。大道芸って、こんなにも楽しいんだ……。
那覇市の平和通り。メーンの通りである国際通りから平和通りへ人をかき分けるようにして進む。
1982年11月17日午後4時頃。平和通りのアーケードを奥へ進んだところで、一人の老人が地べたへ坐りこむようにして竪琴を弾き鳴らしていた。まぎれもなく里国隆その人。
里国隆を見たのはその日が初めてだった。いや、そうではなかったのかも知れない。幼い頃、母に手を引かれて見た光景だったような気もする。通りにはいつでも盲目の三線弾きがいたし、それは複数だったと思う。道端での空き缶を前にした路傍の芸は街の記号の記憶でもあった。
数百メートル先からアーケードの屋根を伝って竪琴や四ツ竹らしき音が、そして雑踏のノイズに混じって確かにあのしわがれた声が這うようにして届いてきた。最初は通り会のスピーカーから流れてくるレコードかとも思ったが、どうも違う。あの音は、ひょっとして。近づくうちに肝(チム)ワサワサーしてきた。<とーひゃー、でーじなとーん>すわ、一大事とばかりに通りを急いだ。
いた、いた。里国隆だ、間違いない、里国隆だ。 「しばらくはここにいらっしゃいますか。録音をお願いしてもよろしいでしょうか」と、確認をしたうえで自宅に大急ぎで走った。なんたる偶然、なんたる幸運。その後の1988年ソウルオリンピックでのベン・ジョンソンの驚異的な幻の世界記録を、おそらくは上回るスピードだったに違いない。走っている途中でも、頭はいま聞いてきた音で覚醒されていた。と同時に録音のための必要機材をシュミレーションしてみる。自宅に着くや今度は競泳のとんぼ返りターンで平和通りに戻る。オープンリールのテープレコーダー、テープ数本、バッテリー、マイク、マイクコード、マイクスタンド、肝心のヘッドホーンは忘れていたが、そんなこと構うものか。ここまでくると長距離走である。これらの録音機材を担いで、今度はローマオリンピックのアジス・アベベを上回るハイペースで疾走した。走りながら録音の手順を考え、走りながら録音のための機器をつなぐ。
手造りの竪琴と拍子の四ツ竹で演奏し、唸るように唄っている。その日、里さんは絶好調だったはずだ。とにかく、張りのある声がアーケード内に響きわたっている。本人が「あんたで交渉して下さいね、路傍ですから。食うや食わずですから」というだけあって、街頭ライブはいよいよド迫力を増してくる。
すべての好条件が揃っていた。周辺で遊ぶ子供たちのノイズ、投げ銭の音、自転車やオートバイの走り回る音、沖縄らしく米軍用機、そしてついには平和通り商店街のアナウンスまでも録音に飛び込んできての「特別出演」をしてもらった。アーケード内であったことが全てであった。録音の天敵たる風を遮り、微妙にこもる音。何度でも繰り返すが、幸運であった。
街頭にしては少々は目立つ録音風景になってしまったが、そこは里国隆。さすがに場を踏み尽くした百戦錬磨のエンターテナーであった。状況を十分に把握していた。平和通り商店街のアナウンスに同調するかのように弦が切れてしまう。このCDにはあえて、そのときの調弦シーンを入れてある。目が不自由なのだが、あっさりと弦をつないで演奏を続けていた。奄美の島々や村々、そして沖縄の道々で何十回、何百回と弦が切れたことだろうか。驚いたことに、弦が鉄弦だっただけに調弦に使う道具はペンチだった。それでガン、ガン、ガンと叩くようにして鉄線の弦をくくる。それよりも調弦の立ち上がりの速さにはさらに驚く。
このライブ、おそらくは里国隆最後の路上演奏だったような気がするのだが。この録音の1年前に、ラジオ沖縄が里国隆特集を組んでいる。インタビューをふんだんに駆使しての番組なのだが、ここで一つの才能に気付く。目が不自由であることは他の器官を発展させると言うが、驚くべき才能を発揮している。ウチナーぐち(沖縄語)を自由に操り、なんとアメリカ兵相手に英語まで披露する。生活の中で、生きていく上で身につけた沖縄の言葉や英語は半端ではない。実にそれらしく会話をしているのである。
里国隆の沖縄での動きは、沖縄のロックシーンの軌跡と符合している。彼の主なステージはコザであったし、金武であり、辺野古であった。いずれも米軍基地があって、アメリカ兵たちが朝鮮・ヴェトナムに送り込まれる「にわか景気」を臭覚で感じとっていたのだ。戦争特需であった。
文化・歴史を共有する奄美諸島と沖縄諸島との間の海上に引かれた一本の線。いわゆる二十七度線。このラインを越えるにはパスポートが必要とされる時代があった。そこを密貿易船に乗って、多くのあまみんちゅとともに沖縄に海渡(わた)ってきた国隆。
歌に関して、沖縄が奄美から輸入した言葉が少なくとも二つある。一つは「島唄」、あと一つが「唄者」という言葉。「しまうた」に関してはそれほどの説明もいらないだろうが、いろいろな呼称のあったのをひとくくりにする役割を果たした。問題は「唄者」である。
奄美で「唄者」という響きが一種の尊厳を伴う単語であると聞いたときは、ある種の感動を憶えたものである。沖縄での「唄者」という充て字はそれほど古い話ではない。歌に従事する者のことを「うたさー」と言っていた。漢字を充てれば、やはり歌(唄)者であるが、そこには一種、見下したような響きがあったことは否めない。沖縄で古典音楽と民謡という区別分化が発生した背景もここらあたりにある。唄が経済的価値を生み出したころから、その傾向は強まった。唄うこと、かつては神に代わり口をつくものであったが、何時の時代からか地位を下げてきた。それは日々の近代化の中で確実に疎外されてきた歴史がある。
里国隆の芸は、「唄者」というよりも「うたさー」としての地位を与えられていたのではないだろうか。それを誰よりも知っていたのが本人だったのでは。きれいごとだけでは飯が喰えない現実の前に、杖を頼りに漂白を続けた。
沖縄で里国隆を知る幾人かの奄美出身の人々に話を訊いてみた。路傍で投げ銭受けを前にして唄う姿を、「同じ奄美出身者として、複雑な思いであり、こうはあってもらいたくない」というようなことを感じたと話してくれた。会った人々は、いずれも年配者で、戦争前に奄美の村々を唄い歩く姿を見たことのある方々だった。複雑な思いは持ちながらも、しかしかつて聞いた音に懐かしさを憶える。
戦後すぐに聞いたという方もいた。徳之島で聞いたときは、とにかくレパートリーが多く、里国隆などの影響で青年団による劇団結成ブームがおこったほどだという。里国隆はテレビやレコードなどもない時代に、文化を運ぶ役割も担っていたことになる。
そうなのだ。文化だったのだ。文化というとなんだか急に軽々しくなるが、彼はマレビトであった。珍しきモノ(者)は稀に遠くから来たれり。奄美・沖縄の南島に近代まで存在したマレビト信仰。神は必ずしも神の格好をしてはいない。あるものはみすぼらしき姿で、あるものは異人として島を訪れた。実際のところ、マレビトは「情報」という五穀を島々、村々に伝えたのだ。その価値に対する成功報酬的、ギブアンドテイクが発生した。
1985年6月22日と翌23日、「奄美・島唄 第15回」のステージが沖縄ジァンジァンで行われた。里国隆最後の最後の舞台であった。
奄美から沖縄島に至る島々、村々、そして屋仁川、永田橋の欄干そば、コザ、金武、辺野古の米軍基地近くのバー街の路上がステージだった。そして那覇の平和通り交番向かいの、立ち飲みコーヒー屋前の電信柱を背にしてのステージがあった。
沖縄ジァンジァンがあった国際通りと平和通りで唄っていた場所までの距離は、およそ200メートル。この通りを何十回、何百回と歩いた老人の姿が静かにフェイドアウトしていった。
○別れの歴史 by 森口 豁 (「子乞い 沖縄孤島の歳月」(凱風社)から)
鳩間島の戦後史は別れの歴史であった。
台風や干ばつに追い立てられて集団で島を出ていった家族たちとの別れ、ヤマトの国の高度成長で若者や働き盛りの壮年までが、スーツケース一つを手にして勇んで出ていった別れ、息子の高校進学で家族挙げて引っ越していった親戚との別れ、がんに冒されて那覇の病院に入院するあの頑固者だった老人が、再び生きて帰ってくることのないであろう想いを寂しげな眼に表わして、じっと手を握り合って声もなく去っていった別れ……。
一人ひとりの顔が、つぎからつぎへと西原の頭に浮かんでは消えた。
出稼ぎのため島を出る人の場合、桟橋の上の空気は、それでもなごんだ。貧しい島にとってそれはお祝いのような別れだった。こんなとき島びとたちは、あの軽快で明るい船出の唄『だんじゅ嘉利』を、手拍子に乗せて歌った。船が桟橋を離れると誰ともなく、
「儲けてぃ呉(く)うよう!」
と叫んだ。
干ばつや台風に見舞われて家をたたんだ一家が島を出るときは悲愴だった。誰の目にも、もう彼らはこの島に帰ってこないであろうことがわかっていた。こんなとき、桟橋のすぐ近くに住んでいた宮良のおじいは、普段から床の間に飾ってある大きな日の丸を、長い竹ざおに結わえつけ、高々と掲げながら不自由なからだを船べりに運んだ。
子どもの進学などで石垣島や沖縄本島に渡る家族の引越しのときは、公民館長がハンドマイクを持って桟橋に立った。船の離岸が迫ると、館長はマイクを口元につけ、デッキに並ぶ一人ひとりの子どもたちの名前を呼んで励ました。小さな血縁共同体だから、どの家の子もわが子同然で、名前はいつも呼び捨てだ。元気で一所懸命勉強して、立派な大人になるように、と呼びかけた。そして館長は最後に必ず、
「……人は減っても島は減りません。島はなくなりませんから……島を忘れずに……」
と、血を吐くような声で叫んだ。
船が遠くに去り、コメつぶのようになって波間に消えるまで、誰もが桟橋の端まで身を迫(せ)りだして立ち尽くした。いつの場合もそうだが、こうした数々の別れで、誰の口からも、“さよなら”の言葉は聞かれなかった。たたずみ終わるといっせいに深い溜息がもれ、その大きな呼吸を合図に人々は丸くかがんだ背を海に向け、ながく伸びた白い桟橋の上を部落へと戻った。誰ひとり言葉をかわす人はなく、ただうつろに、うつむきかげんの姿勢で黙々と歩いた。重い足取りで。
西原章吉も、いつもその人群れのなかにいた。
部落に戻ると、人気の絶えた屋敷跡が空に向かってぱっくりと口を開けていた。西原は、そうした一つひとつの別れと、たった今、目の前でくり広げられた別れを重ね合わせた。そして、ヤマトンチュにはわしらの気持ちはわからない、わかってはもらえない、と思うのであった。………
○珍版ウチナー・ミュージックは、なぜ作られたか(吠えてくれ、誠小先生!)
by 藤田 正 (登川誠仁のCD「HOWLING WOLF」のライナーノーツ)
登川誠仁によるアルバム『ハウリング・ウルフ』は、1997年3月20日(春分の日)にレコーディングされている。
メイン・プロデューサーが照屋林助。伴奏には林助および彼のマーニンネーラン・バンドから仲本興次と松田弘二、それに登川自身というラインナップである。編成は、三線に太鼓という島唄の「標準装備」に加え、ドラム・セットとエレキ・ギターが入っている。これはずいぶんと変わった編成のアルバムのはずである。曲構成も、変わっている。
アルバムの端を切るのが軍歌「露営の歌」の替え歌であり、米兵が残していった歌があり、島唄の教則本などではあまりお目にかかったことのない大人の遊び歌もある。また、ぽくのようなヤマトの者には耳新しい「安里屋ユンタ」もある。
曲の構成だけでない。お聞きになれば分かるように、登川誠仁と照屋林助とのユンタク(おしゃべり)まで入っている。それもほとんどがウチナー口(沖縄ことば)である。
これは、珍版ウチナー・ミュージック・アルバムとでも言えばいいのか。沖縄の音楽を一つにまとめたといっても、こういうスタイルのものは、他にないのではないか。あるいは、他の演者では、ちょっとできないのでは?と、思うのである。
登川誠仁は琉球民謡協会の会長である。別の言い方をすれば、登川誠仁は沖縄・島唄界のリーダーシップを執る最高峰の一人である。企画者であるぽくは、この方に、沖縄音楽のざっくばらんな、いってみれば「ストリート・ソング」的な側面が強く出たアルバムを作れないものか?とたずねたのだった。
『ハウリング・ウルフ』の企画は、NHKのある番組がきっかけだった。登川誠仁はこの番組で長年の友人である照屋林助と一緒に、とても奇妙な歌を披露した。題名は「ペストパーキンママ」。登川が米軍キャンプで働いていた時に黒人兵から口づてに教わったものだそうで、この耳だけで覚えた「インチキ英語歌」を二人は声を張り上げ楽しそうにうたっていた。
うたう本人すらが意味不明のこの歌の本家は、当然「アメリカむん(もの)」である。だが同時に、間違いなく沖縄的でもあった(厳密に言えば、戦後コザ〜沖縄本島中部地域の文化の反映)。ぼくはこの歌のあり方、そしてこれを沖縄音楽のドンともいうべき二人が取り上げたことに、いたく感銘を受けたのである。
「ペストパーキンママ」は、もう一つの、(優れた)沖縄大衆歌である。だが、ある年代を境に忘れ去られる歌、でもある。権威のカケラもない歌、でもある。どんな経緯があったのかは知らないが、沖縄音楽の長たる御二人が、テレビ番組という公共の場で「ペスト…」を堂々とうたってみせた。これは、沖縄音楽がいかにフレキシブルである(頭が柔らかい)かの証明であり、また島唄という現代沖縄文化の根幹をなす美学が、どこにルーツの一端があるのかをも指し示す貴重な「証言」と言ってよかった。ぼくはこの「衝撃的な一曲」から想像をたくましくし、島唄あるいは現代琉球民謡のバックグラウンドを、楽しく、知りたいと考えたのである。
そして、こんな小僧の相談相手となってくれたのが、我らがコザ独立国大統領・照屋林助だった。林助は<なんともはや!>という顔をしながらも、登川誠仁へ電話連絡をとってくれたのだった。
登川誠仁(のぼりかわ・せいじん)は、昭和1930年(昭和5年)11月18日、兵庫県尼崎市に生まれている。戸籍上は「盛仁」。だが、これは登録時のミス。また生年は、一般的に32年(昭和7年)とされているけれども、これも正確ではないそうである。愛称、誠小(せいぐぁー)。石川市東恩納(ひがしおんな)に育つ。
登川誠仁が芸事に早熟であったことはつとに有名で、すでに彼は11歳の時に「カチャーシー」を弾きこなすことができた。16歳の時、当時の主要劇団の一つであった松劇団へ地謡見習いとして加わり、その後珊瑚座ほかの劇団を転々と修行に励んだ。共進座という芝居小屋では、一世代上の嘉手苅林昌と地方(じかた)仲間として初めて一緒に仕事をしている。
三線、三板(さんば)、島太鼓など、古典民謡に必要な修行は十代でマスターし、二十歳を過ぎたあたりから、のど自慢大会やカチャーシー大会で多くの賞を得た。1962年、琉球民謡協会の設立に参加。70年、民謡の工工四(くんくんしー、楽譜のこと)としては初めて声楽譜を付けた「民謡端節舞踊曲工工四」を発刊、伝統的な沖縄大衆歌の基本を書物として明示した。
現在は6期目となる民謡協会会長のほかに、琉球民謡登川流宗家、沖縄県無形文化財技能保持者の肩書を持つ。
経歴を読めば、まことにいかめしい誠小先生である。確かに自他ともに認める頑固者であり、少年時代から芸事ならば目上の年寄に対しても、おかしいと思ったものはおかしいと言い放った。チビのくせに、童(わらばー)のくせにと散々に言われても、彼は自論を覆すことはなかったという。
彼は言う、「沖縄には、くさむにー(ホラ吹き)という言葉があるが、わしは自分ができることだけを吹いているだけなんだ」
「わしのような人間がいないと。だが、わしのうたが本物というわけではない。昔からのうたは、昔のものとして習っておいて、現代は現代のものとしてやればいい。崩れたものしか知らなくて、それを自分流だとごまかすのが、我慢ならんのだ」(発言は、藤田がヤマト口に直した)
この発言に表わされた登川誠仁の考えは、純粋主義とは似たようでいながら、微妙に異なっている。沖縄音楽は常に変化し続けて良いのだという認識に立ちながら、同時に過去の遺産をしっかりと学んで欲しいということである。
かつて嘉手苅林昌(琉球民謡協会名誉会長)と登川誠仁が話をしていた席に、偶然ぼくが居合わせたことがある。二人の会話は少しづつ沖縄民謡(島唄)の将来がテーマとなり、「もう我々の世代で終わりだろうね」と静かに話していたことを思い出す。言葉(ウチナー口)も話せず、うたの背景も分からなくなった者たちに何ができるかとすら、二人は言った。ぼくは彼らの意見に何かを言えるほど沖縄音楽に詳しくはないが、二人の寂しさというか焦燥感というものは、しみじみと肌で理解できた。現代の沖縄音楽がどのようにして生まれ、変化し、発展してきたのか。
アルバム『ハウリング・ウルフ』の、下敷きにあるのは、これである。大正期から本格化した移民、移住の歴史、太平洋戦争、そしてヤマト→アメリカ→ヤマトという極端な世変わりを経て、ウチナーンチュは沖縄返還(1972年)を前後とし「島唄(我々のうた)」という言葉を手に入れる。これは、アメリカ黒人にとっての「ソウル」「ブラック・イズ・ビューティフル」といった言葉と同じ自己の積極的肯定である(島唄という言葉は、もともとが奄美地方のもの)。
この島唄という言葉に表れた島全体の意識が、沖縄音楽をより美学的に純化させてゆく。と同時に、喜納昌吉に代表される新しい世代は、今述べた沖縄の激動をそのまま反映したポップ・ミュージックを創造し始める(代表的な例が、返還直後にヒットした「ハイサイおじさん」)。
ぼくは、この二つの流れが現在の沖縄音楽の基本軸だと思っている。多少図式化過ぎることを承知で言えば、喜納世代より前の革新者たちは、この二要素を一つの身体に併せ持った人が多かったのではないかとぼくは思う。その代表的な人物とは、もちろん登川誠仁であり、今回のメイン・プロデューサーとなってくれた照屋林助である。
例えば、戦後沖縄の大衆歌謡において最も洒落たナンバーの一つ「ヒヤミカチ節」に関連した二人の話では、「ヒヤッ!」(よしっ、立て!という気分だろうか)という掛け声は、「ヒヤ〜」と伸ばしてはすべてがぶち壊しになる。この曲を闘牛場から流行らせていった二人にとって、「単なる掛け声」がどれほど重要なものであるか、ということである。これは先ほど触れた、嘉手苅と登川の会話とつながってゆく。
それにしても、闘牛場の熱狂の中で、「沖縄を世界に報せよう。私は虎、羽をつけてくだされ…波路はるかパシフィックを渡って!」と大合唱されたというこの曲のありようを想像してほしい。まるで名画を観ているようにドラマチックではないか。これぞ、うたの現場である。
誠仁&林助による「ヒヤミカチ節」一曲だけでも、これまでぼくが説明してきた沖縄大衆歌謡の二つのエッセンスが、しっかり染み込んでいるのである。山内盛彬が書いたメロディは実にモダンであり、明らかにアメリカ音楽の影響下にある。だが、アメリカむんが同時に沖縄むんでもあり、そのあり方は、「ペストパーキンママ」と比べて、いよいよ沖縄的にチャンプルーが成功しているのである。この見事なブレンド! このような歌、そして演者なくして次世代がありえなかったことが、実によくわかるのである。
さて、このアルバムのタイトルであるが、そのイメージはハウリン・ウルフ(吠える狼、本名=チェスター・アーサー・バーネット)という素晴らしいブルースマン(故人)にある。登川誠仁のヴォーカルは、以前にまして味わい深く、そのウナるヴォーカルは聞き手にさまざまな映像を熱く呼び起こさせる。ハウリン・ウルフの地鳴りのような発声と登川誠仁のそれとは、本質的には異なるのだが、両者の、「美しさ」の中身は同じであるとぼくは思ったのだ。
また、照屋林助の指示によるドラム&ギターのバッキングも、ハウリン・ウルフが数々の名作を残したメンフィス・ブルースとフィーリングが本当によく似ている。特に「なりたい節」なんて、もう涙ぽろぽろである。正装し金屏風の前で完全無比の絶品をうたい上げるのも登川誠仁であるが、もう一つの姿がこれである。そしてその姿は、沖縄音楽の決して忘れてはならないもう一つの側面であるとぼくは思うのである。
『ハウリング・ウルフ』は、照屋林助の「てるりん館」で、実に和やかな雰囲気の中で行われた。登川誠仁は、そばに島酒(泡盛)のグラスを置き、島のタバコ(バイオレット)を吸いながら、得意の六線を弾いた。六線とは、三線を改造した楽器で、もともとはマンドリンにヒントを得て作られたものである。
取り上げられた曲目は、登川誠仁の代表的一作である「戦後の嘆き」(島に帰ってきたある青年兵士の絶望をうたったもの)から、「ペスト…」、これまた彼の代表作「新デンサ節」、大人の遊び場でうたわれた「辻の六調節」、誠小先生の十八番であるラストの「アッチャメー」に至るまで、内容はバラバラである。
だが、それは誠仁&林助による一種の歴史ものがたりの中で、きっちりと融和している。島酒片手に遊び、泣き、笑ってきた二人の傍には常に「島のうた」があった。『ハウリング・ウルフ』は、この豊饒を世に伝えようとするアルバムのはずである。
○名曲選「戦後の嘆き」 (「ウチナーのうた」(音楽の友社刊)から) by 藤田 正
「戦後の嘆き」 作詞・作曲 登川誠仁
大和から 戻てぃ 沖縄 着ちみりば
元姿 ねーらん 影ん 変わてぃ
* 戦世 我ね 恨みゆさ
見りば なちかしや 戦場に なとぅてぃ
世間 うまんちゅぬ 袖ゆ 濡らち
* 繰り返し
島戻てぃ みりば 親兄弟 うらん
戦世ぬ なれや 涙 びけい
* 繰り返し
うみちらね なゆみ 泣ちくやり ちゃーすが
戦世ぬ なれや 運命 でむぬ
那覇からタクシーに乗って「コザヘ」と運転手に伝えると、「コザですか、懐かしい言葉ですね」と言われたことがある。ハンドルを握るその人によれば、ヤマトンチュが沖縄市をそのように言うのは近ごろ滅多にないそうである。
御存知のように現・沖縄市は、それ以前、コザという世にも珍しいカタカナの名前が付けられた市であった。ぼくの気持ちからすれば、沖縄に到着して再び「沖縄へ行ってくれ」というのは、何かとても奇妙な行為であって、やっぱりコザがいいと運転手氏に伝えたのだが、彼は笑っているだけだった。
ヤマトの音楽人間にとって、コザは謎の場所である。地名としての「沖縄の中の沖縄」だけでなく、むず痒い何かを発信し続ける場所である。この町を誉め殺しにしないでくれと言ったコザンチュもいたが、沖縄最大のインディーズ、マルフク〜普久原家がここにあり、嘉手苅林昌−照屋林助−登川誠仁という象徴性の高い戦後の名人が今でも目と鼻の先に住んでいて(ぼくはこれを「魔のデルタ地帯」と命名して喜んでいる)、知名、喜納の両家も、ロックの拠点も、若手のディアマンテスたちも…と指を折ってゆくと、とてもこれが偶然の所産だとは思えないのである。
ポピュラー音楽において一つの大きなジャンルが形成される時、これはほぼ決まりごとのように、一つの小さな町・地域が背負った歴史の特殊性と資本主義の軋轢が背景となる。ニューオーリンズ(ジャズ)、キングストン(レゲエ)、ニューヨーク(サルサ、ラップ)…いずれも、共通する特質を備えている。そして、エルヴィス・プレスリーを世に送ったロックンロールの町、メンフィス。コザ音楽の魅力の特色が世界のどの町に似ているかと問われた時、ぼくはこのメンフィスを挙げることにしている。条件が備われば、「チャンプルー・ミュージック」という言葉が一般名詞に変わる可能性だってあったとぼくは思う。
豊かな伝統文化を背景に、コザには戦後の混乱時に他地域からの大量の人口流入があり、米国の直接支配があり、その文化は常に揺れ常に発酵状態にあった。現代沖縄において、コザほどにめいめいが緊迫状態の中で自己なるものを自問した地域はなかったはずである。ジャンルとしての「チャンプルー」成立に欠けていた条件の一つは、メンフィスのサン・レーベルのような地場産業としてのレコード・ビジネスが、良しにつけ悪しきにつけ、ゆったりとテーゲーだったことである。エルヴィスを見出したサム・フィリップス(サンの代表)のような豪腕がいれば、照屋林助、喜納昌吉と続く「突拍子もない人々の系譜」は、大旋風を巻き起こしたはずである。
断っておくが、ぼくはそうならなくて残念だとは言っていない。なぜなら、そうならなかった所に、コザなり沖縄ならではの素晴らしさの本質が隠されているからである。
「戦後の嘆き」は、カチャーシー、早弾きの名手とヤマトで喧伝される登川誠仁の、もう一つの側面を知らせる美しいバラードである。ぼくはこれを、沖縄におけるブルースの名品として聞いている。
「戦後の嘆き」は、大戦が終了してのち、故郷へ帰ってみれば元の姿を残さないほどに変わり果てた姿であった。かててくわえて、親兄弟もいないではないか。ああ、あの戦を恨むばかり、と歌われている。
誠仁によれば、ある国頭出身の男性を思い出して書いた歌だそうである。この人は十代の時にヤマトへ行き、そこで兵隊にとられた。敗戦。そしてウチナーに帰れば、これはいったいどういうことなのだ…と、毎日のように誠仁の前で泣き崩れたのだそうである。1930年生まれの少年・誠仁とその男性とは歳は離れていたが、二人は酒を酌み交わす仲(!)となり、誠仁の歌・三線を聴いて彼はまた泣いた。「戦後の嘆き」はその出会いをきっかけとして出来上がった歌である。詞が閃いた場所は、御自宅のトイレの中。
登川誠仁のヴォーカルは、実に渋く味わい深い。ぼくがこの歌を面と向ってじっくりと聞かせてもらったのは『ハウリング・ウルフ』のレコーディングの時が初めてだが、その心、表現の核心はまるでブルースであった。適度に枯れザラついた声質の中から、くくくく〜っと伸びやかな艶が溶け出す。これはまさに、何十年もびっしりと歌い込んできた人物にしか出せない、大変な歌唱である。
登川誠仁自らの指定によるドラムと彼自身の改造六線がバック。塩辛いヴォーカル。そして人生の悲痛をうたうことでこそ浮き上がる、生きるというテーマ。エルヴィスが圧倒的に影響を受けた40〜50年代のブルースと、どうしてここまで似るのかは謎である。
しかし、一つ違うことがあるとすれば、優しさの質だろう。登川誠仁の言い方を借りれば「こういう懐かしい(哀しい)歌はあまり歌わない」。なぜなら誠小先生御自身が泣いてしまうから…。氏の、そして島の本質の一端を覗かせていただいた一言だった。
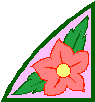
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集