
|
読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と |
|
《No.7》 1 野ざらしの人 宮川 勉 2 南島の昭和史を歩いた漂白の芸人 仲宗根幸市 |
||
|
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集

読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と
感じられる名文が、世の中には数多くあります。
そのようなHP管理人の心情を、お立ち寄りいただいた方々に
少しでも理解していただきたいあまり、
このページを設けてみました。
引用文については、出所等を明らかにしつつご迷惑にならない
よう心がけて掲載させていただきますので、
ご理解のほどよろしくお願いします。
《No.7》
1 野ざらしの人 宮川 勉
2 南島の昭和史を歩いた漂白の芸人 仲宗根幸市
○野ざらしの人 by 宮川 勉 (里 国隆のCD「黒声」のライナーノーツ、全文掲載)
里国隆、通称「乞食の国隆」は、大正8年6月10日、奄美大島笠利町崎原(さきばる)に生まれた。国隆は人から生まれを問われると、崎原と答えるよりも「あやまる」と答えるほうが多かった。そのほうが理解が早いからだ。あやまる岬とは奄美大島の東北端に位置し、大平洋に突き出すように隆起している台地である。そこに立つと、眼下に茫漠とした海が広がり、遠く水平線がゆるい弧を描いているのが望める。風が強く、近くの蘇鉄の林は、つねに目に見えぬ巨大な手でなでつけられているかのように、せわしなく葉を揺すっている。現在は「奄美十景」という景勝地に選ばれ、道路も整備された公園となっている。
崎原はその岬から歩いて5分ほどの集落だ。今でも当時とそう変わらない畑と樹木と低い軒の家が点在する、閑静な土地である。
放浪の芸人と呼ばれた国隆だが、彼は最期まで故郷を捨てることをしなかった。17歳で家を飛び出してからは、この土地に住むことはほとんどなかったが、ことあるごとに戻ってきては、つかの間親類縁者と宴を張り、去っていった。放浪生活の憩いの場として、彼にはこの土地と血を分け合った人々が必要だったのだ。そして彼が生涯歌っていた民謡の節回しもまた、この土地独特のものである。いわば崎原と国隆は「へその緒」でつながっていた。
1、樟脳売り
墓碑によると、里家は薩摩藩政時代は士族だった。萩原三四郎と乙女加那の末裔となっているので、藩の役人三四郎が赴任したときに、島の娘乙女加那と結ばれ、居着いたという物語を想像できるが、実際のところはわからない。
士族だったせいか、島の中では、わりあい裕福な層に属しており、田畑も広く所有していたという。といっても国隆が生まれる大正時代は、まだ貨幣経済が浸透しておらず、島のほとんどの家がそうであったように、里家も自給自足に近い生活をしていたようである。
父義秀、母オトミの長男として生まれた。義秀24歳、オトミ23歳の子である。
国隆が生まれた当時、里家は大家族で、義秀一家の他に、義秀の弟妹、弟の嫁、それに義秀の父赤坊、母清ヅル(キヨヅル)が同居していた。総勢4組の夫婦を含む16人家族だったという。
赤坊は近隣に名を轟かす歌者だった。歌者というのは、島にテレビもラジオもなかった時代に、宴席に呼ばれて三味線と唄を披露する「村の芸人」である。村人はその声に高揚し、三味線の響きに憂さを晴らした。赤坊はその芸の高さから、村内だけではなく、近隣の村でも評判の歌者だった。ちなみに昭和29年に、赤坊は上村藤枝らとともに東京までレコードの吹き込みに来たという話が伝わっている。しかし何かの理由でひとり一座から離脱したらしい。このとき残りのメンバーだけで録音したSP盤の存在が確認されれば、国隆以前に本土で奄美民謡を吹き込んだ唯一のレコードということになる。いずれにしても祖父と孫とが、民謡で本土デビューする機会に恵まれたという事実は興味深い。
赤坊が三味線を持って、村をまわったように、義秀もまた村をまわることが多かった。
義秀は大正時代末期というから、ちょうど国隆が失明した頃に天理教本部で神事儀式の作法を修得する。
赤坊が歌者として祝祭時や葬儀に呼ばれたのと対照的に、義秀は神事を執り行うために村内一円をまわるようになった。村では資格を持つものがいなかったために、彼はずいぶん重宝されたようだ。 「労を厭わず東奔西走、人々から感謝され尊敬の念でみられている」 『鹿児島県推薦被顕彰者選考関係資料』にはこう記されている。ここにはまた終戦後、水稲増産栽培法を開発し、その普及につとめたということで笠利町から表彰されたことも併記されている。
村人が亡くなると、葬儀は義秀が執り行い、その後の宴席では赤坊が歌ったなどということもあったかもしれない。
いずれにしても国隆が生まれたときの里家には、歌者の祖父と、のちに祭祀者で篤農家として表彰される父が同居していた。
国隆が失明したのは生まれて8ケ月のことだといわれている。同居していた叔母、里梅干代(義秀の弟国光の妻)は、80年も前のことをよく覚えている。
「あの子はかわいそうでえ。赤ん坊の頃、赤い腫れ物ができて……それを直すのに島養生いうてい、二銭銅貨を焼いて酢壷につけて……それを全身に塗ったの。それが目に入ったんじゃないかあ、とみんなが言ってましたよ」
島養生というのは、医学が普及する以前の奄美に伝わる民間療法のことだ。焼いた銅貨を酢につけて、その酢を患部に塗ると腫れ物が直るという言い伝えがあったようだ。前述したが、島には貨幣経済が十分に発達しておらず、銅銭がこういう呪術的な道具に使われていたというのが興味をひく。
銅貨に徽菌が付着していたのだろうか、幼くして国隆は視力を失うことになる。
目が見えなくなった国隆の遊びというと、びんだら(洗面器)を叩いてリズムをとり、赤坊の目を盗んでは、床の間に飾られている三味線を弾くことだった。赤坊にばれると、こっぴどく怒られたらしい。
盲学校のない島なので、就学年齢に達しても国隆は、家に居続けた。赤坊は三味線の扱い方には厳しかったが、唄と三味線の演奏は徹底的に教えた。宴席にもたびたび連れて行った。視力を失くした孫に、当時の赤坊は生きる術を教え込もうとしていたようだ。
「お前はこれで生きていかなければならない」
赤坊はそう国隆に諭したという。
このように国隆を語るとき、祖父赤坊との関係はわりあい理解しやすいが、父義秀との関係はやや複雑なようだ。
前述したように、その頃、義秀は天理教本部で神事儀式を習得している。このことと国隆の失明は関係あるのかどうかわからないが、まったく関係がないと断じるのは、むしろ不自然な気がする。息子の失明をひとつの試練として、神に救済を求めたと推測するのは、考え過ぎだろうか。
昭和6年、国隆12歳のときにひとつの転機が訪れる。それは本土からやってきた樟脳売りの老人との出会いであった。
後年自作の竪琴を弾いて、路傍で唄を歌い暮らすスタイルは、この老人から受け継いだものだ。老人は竪琴をつまびきながら、『ゴンドラの歌』や『カチューシャの唄』など当時の流行歌を歌って客寄せをしていた。しかしこれは彼特有のスタイルというよりも、当時の樟脳売りはみんな竪琴を持って村々を歩き回っていたらしい。
国隆はこの老人について行き、家出を敢行する。
この老人が村にやってきたはじめての樟脳売りではなかったはずだ。今までにも何人もの樟脳売りが訪れている。だから家出の動機は、老人に求めるよりも、むしろ国隆の精神的な成長に求めるべきだろう。赤坊から常日頃いわれた「三味線と唄で生きていくしかない」という教えを、現実的に考えられる年齢に国隆はなっていた。身過ぎ世過ぎの術を持て余し、就学年齢に達しても家にいなければならない焦りが、ふいに樟脳売りについていく気持ちになったのだろう。
国隆は旅の合間合間に、板と番線でどうやって竪琴を作るかや、その奏法を聞き出した。家人が国隆を発見したのは、旅人宿であったという。
家出から連れ戻された後の国隆を覚えているのは、いまでは弟の里治光だけだ。治光は国隆の8歳下の弟である。 「(兄は)隣の部落まで子守に出されたの。でも何回も実家に帰された。子守の仕方が悪いのなんのと言われてね。子供の首が垂れるまで、日照りのなか浜辺で唄を歌っていたんだって。また子供が泣いてもうちに連れてかないで、子供の親に怒られて。それで気も強くなったんだね」
義秀は、樟脳売りについて行くような盲目の少年を持て余していた。そこで彼が国隆に与えた労働は、子守だった。しかし国隆はわざと子供の親を怒らせ、実家に帰されるのを望むかのように、子供を放って唄の練習に励んだ。いまや国隆の望む生き方は、こういうものではなかった。樟脳売りとの旅で「自由」の味を覚えてしまった彼には、その誘惑は絶ちがたかった。
そしておのれの腑甲斐無さをなじるかのように、気を荒立てていた。
「ガキ大将に余分な口のきき方をしたんでしょう。あそこに木があるでしょう。あそこで5、6人で言い合いをやっていたんだ。ぼくが何の気なしに近付いたら、すごい剣幕で兄は連れていかれた。そのうち寄ってたかって埋められちゃったの、首まで。ぼくは木に隠れて見てた。それで埋めた人たちが浜の上に上がって姿が見えなくなった頃、シャコガイの殻を持ってってね、掘ったんだ……兄貴はもう首のまわりが紅潮して、汗だくだくで、あれ30分もしたら死んじゃったろうな。そんなことがあってから、2、3日して兄貴はそれっきり家を出てしまった」
このエピソードは国隆17歳、治光9歳のときだと推測できる。
そのとき祖父赤坊は、国隆に樟脳を買うわずかな金を与えた。盲目の少年が、行商人として長い放浪の人生を歩み始める。
昭和11年のことだ。
2、カンコのサトさん
奄美大島ではつい最近まで村のことを島と呼んでいた。それは道路が整備されていなかった昔、隣の集落へ行くにも船を使って海上を移動していたことの名残りである。
国隆が北端に近い崎原から、南端の古仁屋(こにや)へ行くのも、船を頼って海岸の集落伝いに進んで行った。
古仁屋からは瀬戸内海峡を渡って、加計呂麻島へ。さらに徳之島、沖永良部、与論、そして沖縄本島へと、渡って行った。
その頃の国隆がどこでどのくらいの期間をどのように過ごしたのかを、知る資料は乏しい。
しかしここに当時の彼の様子を伝える貴重な資料がある。昭和56年にラジオ沖縄が制作した『帰ってきた半琴(ハングトゥ)弾きの国隆』というドキュメンタリー番組のテープだ。
この番組は戦争の記憶も薄れつつあるなか、沖縄にとっての戦争とはどういうものだったのかを確認しようという意欲的な作品である。プロデューサーの松野均さんは、当時63歳の国隆を沖縄に呼び、戦前、戦後に過ごした街頭や村をまわらせている。その日はちょうど6月23日、36年前に唯一地上戦が展開された沖縄で、日本軍が組織的戦闘を断念した日にあたっていた。のちに「沖縄慰霊の日」として、沖縄の人々の胸に刻まれる特別な日となっている。
さて、その番組のなかで、国隆は沖縄の東北端にある国頭都安田(あだ)の集落を41年ぶりに訪れている。
昭和15年4月、国隆は若い女性に連れられて、道なき道をこの辺境の集落まで来ていた。 国隆は当時をこう回想する。
「自分でもいい度胸だったと思うんですよ。盲滅法で若い歳で、もしその部落で断られたら道に寝るのを覚悟のうえでの旅だったですからね」
その日、出征兵士を見送る会が学校で催された。国隆は白粉がわりにチョークを顔に塗って登湯した。娯楽が乏しかった集落の人たちは、村中総出で学校に集まっている。
はじめてみる竪琴、日の不自由な若者、彼のつむぎ出す音色は強烈な印象を、村人たちに与えたようだ。
♪ 歓呼の声や旗の波 「あとはたのむ」のあの声よ
これが最期の戦地の便り 今日も遠くでラッパの音 (作詞 深草三郎 作曲 明本京静)
竪琴でばらんばらんと弾いて歌った『皇国の母』は、その後、村の流行歌となり、国隆は「カンコのサトさん」として長く記憶されることになる。当時小学生だった人たちが、ラジオの収録日にも国隆を迎えているが、彼らは41年前のことをまるで昨日のように覚えていた。
♪ 思えばあの日は雨だった 坊やは背でスヤスヤと
旗を枕に眠っていたが 頬に涙が光ってた
彼らは2番の歌詞になると、国隆と一緒になって「思えばあの日も」と合唱している。子供たちにもわかりやすい内容だったのかもしれない。
このようにして、国隆は数人の行商仲間とともに、あるいはひとりで、島々を渡り、家の軒先、木の根元で夜を過ごし、人に手を支えられながら道なき道を歩き、たまに呼ばれれば宴席で唄を歌い、また次の集落まで人に導かれ……そんな放浪が続いた。
その頃、崎原の実家では両親が、国隆のことを心配し続けている。とくに母オトミは、目の不自由な長男を哀れに思い、何度も連れ戻そうとしたようだ。
当時小学生だった妹の福山ユウコはこう回想している。
「兄がどこそこにいたよって情報が入ると、すぐに母が行くんです。だけどそこに伝わって行くまでに何日もかかるんですね。今みたいに車もないから船で行って……。やっと着くと、たった今、兄は出て行ったよって言われるんです。母はあちこち探していましたよ。連れてこなきゃって」
ユウコが語る次のエピソードも、当時の里家が国隆をどう思っていたかがわかる印象的な話である。
「私は子供心に(放浪芸人だった)兄が笑い者になっているんじゃないかとか、恥ずかしいとか思いました。一瞬ああ、あんな兄なんかいなければいい、ほんとの話、そう思ったこともありますよ。だけど宗教家の父がね、……『物、金の貧乏は仕方ないが、人間は心まで貧乏になるんじゃない』というのが教えでした。兄がどこ行って、どういうみすぼらしい恰好をして、どういうことで人に世話かけてるかもわからないって頭がいつも(家族に)あるから、自分の家に来る人は、乞食が来たって泊まらせる家だったの。雨宿りじゃなくて、泊まらせて。いっぺんはね、泥棒を泊めたことがあったんです。雨宿りに来たから、その一派を泊めたんですって。泥棒をしてきたあとですが、そんなことは知らないで……(笑)そうしたら翌朝、『お世話になりました』ってその泥棒がお爺ちゃんに物を置いて行ったって。だけど家を出てすぐに捕まっちゃった。そんな家だったの」
しかしそんな国隆も、たまに何の前触れもなく、実家に戻ってくることがあった。そういうときは、仲間を連れてくることが多かったという。ユウコの記憶では脚の不自由な人と、猿の物真似が上手な人が一緒だったという。大道芸人たちだったのだろう。そして数日するとまた旅の空だ。来たときと同様に、国隆は突然出て行く。
そんなことの繰り返しが戦争になるまで続いた。
戦時色が強くなってくると、国隆の自由な放浪は翳りをみせるようになってきた。
前述のラジオで国隆はこう語っている。
「あちこち行って、いろんなこと訊かれたりね。どういうふうにして来たか、スパイ……今も疑いがあるんですけんども、なんかそういうところ懸念ないですか(と役人などが尋ねるが)……あるかもわからないけれども(集落から)私が帰るまでに、証拠物件ずっと取り上げてくださいって、当時やっていたんだ」
しかし、さすがに戦争中は、放浪生活がやりにくかったのだろう、国隆は奄美大島に戻ってくる。島の中の部隊駐留地へ行っては、慰問のために、竪琴や三味線で唄を歌って過ごす。
ここにラジオ・ニッポンが昭和54年に制作した番組がある。タイトルは『ラジオ・カプセル'79ドキュメンタリー奄美ホウレモン琴弾き国隆の戦後史』。ホウレモンとは、奄美言葉で放浪者という意味である。このなかで国隆は当時をこう語っている。
「戦争で商売、やりにくくなったことはない。戦(いくさ)はかえってよかったんだ、あたしには。兵隊送りやら、必勝遺家族慰安会とかね、ずっと慰問しよったから。もう品物を売らなくてもね。忙しくって戦(いくさ)どころの騒ぎじゃなかったですよ。その頃、部隊のなかを転々転々と空襲に追われながら歩きよったです。夜はずっと慰問、慰問で。兵隊なんか集めおってね、慰めて歩きよったですよ。世渡りのため、唄を歌ったのはね。これじゃなければ世渡りできないわけですよ。もちろん世渡りのためじゃなければ歌うはずないでしょ。世渡りというよりもこういうふうにして一般民の心にしみるようなことをしていかなければ私の取り分がないんですよ。すずしく渡れないというわけですね」
日の見えない国隆にとっては、たしかに村々を渡り歩いて門付するよりも、慰安会に呼ばれて唄を歌うほうが楽だったし、稼ぎも良かったのだろう。
世の中をすずしく渡るために、戦争を賛美する唄を歌い、慰問会ではあっちからもこっちからも声がかかったという。
♪ ひとつとせ いのち世界の大戦争
勝ち抜くために努力せよ ソラ努力せよ
♪ ふたつとせ ふた親離れて出てからは
御国のために尽くしましょう ソラ尽くしましょう
♪ みっつとせ 皆様これからお互いに
食糧増産つとめたり 自給自足を守りましょう
この『戦争数え唄』は国隆の作詞作曲であろう。すずしく世の中を渡るために、時局に合わせた歌詞を作って、兵士とその家族に聞かせている。この歌詞にどれだけ国隆の想いが入っているかは甚だ疑問だが。
というのは戦後、同じ曲に次のような歌詞をつけて歌っているからだ。
♪ ひとつとせ 広く知られた大東亜戦争
広めた東條は憎まれて ソラ憎まれて
♪ ふたつとせ ふたたび還らぬ人々は
大東亜戦争に身を捨てて ハレ情けない
♪ みっつとせ 皆様日本の兵隊は
死ぬのが手柄の教育で ソラ阿呆らしや
♪ よっつとせ 夜の夜中も昼の間も
空襲警報に気はとられ あわれ国民は 仕事が手に取れぬ
それでは戦後のこの歌詞が、国隆の思想を反映しているかというと、それも少し違うような気がする。もちろん自分自身も含めて、戦争に振り回された民への憐憫は深いが、ここで浮かび上がってくるのは、放浪芸人としてのしたたかな姿だ。戦争を嫌っていた国隆が、生きるためには戦争賛美の唄を歌わざるを得ない、いや積極的に歌って楽しませましょうという姿勢。
後年『黒だんどう節』に
♪ 大東亜戦争に日本が負けて 負けたんが当たり前
科学の戦(いくさ)に竹やり持ちょて 負けたんや当たり前
という自作の歌詞をつけて歌っている。
戦争協力の束縛から逃れて歌うのは、まず自分自身の感情の吐露だった。そしてそれが沖縄、奄美の人たちから賞賛されると、また処世術として歌い続ける。
それは戦前に島々を放浪し、路傍の芸人として鍛えた文字どおり「生きる術」であった。目の前の聞き手を楽しませつつ、世の中をすずしく渡ること。もし彼に戦中戦後を貫く思想と呼べるものがあるとしたら、まずまっ先にこの放浪芸人の処世術があった。
次のエピソードもまた彼の処世術の一端を物語るものだ。
連日連夜の慰問会で、戦前の放浪時代とはうって変わってお金が入ってきた国隆は、軍に大金を寄付している。その額は一説には120円というから驚く。海軍大臣名の感謝状をもらったという。
しかしこの話にも裏があって、国隆の義理の弟(妻イノの弟)である吉井信雄は、そのいきさつをこう語っている。
「ある集落で戦死した息子がいる家族と会ったわけ。親兄弟は泣けないわけよ、人前では。名誉の戦死だから。それに同情して(国隆が)戦争で人を殺してって歌ったんじゃないの。そうしたら憲兵隊に、ちょっと来いってひっぱられたんだって。そうしたらある人に知恵を授けられて、それで120円寄付して、帰って来られたって。今だから話すけどって、言ってましたよ」
国隆はその感謝状を、生涯名瀬のアパートの部屋に掲げていたという。
3、沖縄放浪
昭和20年8月15日、日本は戦争に負けた。
翌年、奄美大島を含む北緯30度線以南の南西諸島は、アメリカの統治下に置かれる。このときから8年後の昭和28年12月25日、アメリカから日本へのクリスマス・プレゼントのように復帰を果たすまで、奄美は実質的にアメリカだった。
里国隆の戦後は、眼の手術から幕が開く。
末妹の勢田秀子の証言である。
「あたしが小学校5年の夏休みに、赤木名(奄美大島・笠利町)で眠の手術をしたんですよ。国分さんという眼科の先生がいまして、兄の眼を診断したら、片っぽうだけは瞳が死んでるんだけど、もう片っぽうは生きているから、手術して、曇りを剥げば、月夜の晩ぐらいには見えるからっていうんで、私は夏休み中、病院にいたんですよ」
秀子の記憶では昭和21年の夏のことである。医療設備がまだ充分でない終戦直後の奄美で、27歳の国隆は眼の手術を受けた。水道が満足に完備されていないので、秀子は赤木名の病院に泊まり込んで、毎日、泉まで新鮮な水を汲みに行ったのだという。
妹の献身と手術の甲斐があって、国隆の視力は少し回復した。
後年彼の勘の鋭さを「まるで眼が見えるようだ」と評する人がたくさんいるが、実際には「月夜の晩」くらいには見えていたというのが真相らしい。
ここで秀子はもうひとつ興味深い話を聞かせてくれた。
ちょうど国隆が眼の手術をしている頃、国隆には嫁がいたというのだ。体が弱かったので、国隆の実家にいて、病院には来られなかったらしい。
「兄は(どこかに放浪に)行っては、お嫁さんを連れてきて、また一緒に(放浪に)出かけて、次に帰ってくると別の人を連れてくるの。もてたんだ(笑)」
これは秀子の記憶である。姉のユウコの記憶では、国隆はいつもひとりか、行商仲間と帰ってきたと語っているが、実際はこういうこともあったのだろう。
娯楽が乏しい島にやって来る芸人であれば、それだけで「もてる」要素はある。しかも20代の若き青年となれば、なおさらであろう。
国隆は生涯8人の妻をもったと語っているが、確認できる一番目の妻は、このときの女性である。秀子の話では、彼女は国隆の子を孕んだが、流産したという。それが眼の手術の前だったか後だったかは、もう記憶がないが、体が弱く家にいたきりだったということは、妊娠中あるいは流産後で体調が思わしくなかったのかも知れない。
その後の彼女がどうなったのかわからないが、戦後の沖縄行きのときには、国隆はひとりで旅立っている。
眼の手術を終え、お札の裏表を見分けられるくらいまで視力が回復した国隆は、またぞろ「放浪の虫」が痺きはじめていた。
その頃里家には、戦争で一時帰郷していた叔父(義秀の弟)がいた。戦争も終わり大阪に行こうかと思い立ったとき、彼は国隆を呼んだ。そしてB円を渡し、日本円に交換するように頼んだという。当時アメリカの統治下に置かれていた奄美は、沖縄ともども日本円ではなくB円と呼ばれた紙幣が流通していた。国隆は二つ返事で請けおって、出かけて行った。
「それから十何年も帰って来ないの。いい人にお金を渡したねって(笑)」
叔父の金を持ったまま出奔した国隆が向かった先は沖縄だった。それから昭和38年の12月に帰って来るまで、17年間国隆の舞台は沖縄になる。
戦後の沖縄行きも、戦前と同じコースを通って南下していった。徳之島、沖永良部、与論……与論からは中華貿易のポンポン船で、沖縄の平安座(へんざ)に着いた。昭和22年4月のことだ。
敗戦直後の沖縄は焦土と化した島の復興や、米軍の基地建設で混乱していた。ある日突然に町ができたと思うと、暫くして忽然と消えたりしていた。国隆は、ひしめき合う人々にくっついて、沖縄の土地を転々としていく。『半琴弾きの国隆』から彼の肉声で辿ってみよう。
「屋慶名にたどり着いたら、すぐ警察に行ったわけですね。そのときの警察に、新米の大島の警官たちが希望して沖縄に来とったわけですよ。私が行ったら、ああ、国隆うじ、国隆うじと呼んでね、所長以下、私を関係官みたいに屋慶名の旅館に迎えてくれてね。沖縄の状況を聞いたわけですよ」
国隆が最初に訪れたのは「金武湾(きんわん)」だった。ここは具志川のはずれの辺鄙な場所だった。ところが、戦後米軍の船が停泊するので、彼らを相手にテントのような店が、次々に現れ、たちまち繁華街になってしまったようだ。「金武湾」というのは、アメリカ人が名付けた地名である。あっという間に繁栄して、またまっ先に衰退したテント村のような町だったという。
ここで国隆は街角に座って、竪琴を弾き、唄を歌った。基本的に門付はしなかったらしい。しなくてもアメリカの軍人が面白がって、お金をたくさんくれるし、門付は時間をとられるので効率が悪かった。このスタイルが後に「乞食の国隆」と呼ばれる由縁である。実際、樟脳を並べるよりも缶からを置いていたほうがずっと実入りが良かったようだ。
次に行った先は石川だった。当時石川は沖縄北部の山原(やんばる)に疎開していた人たちが帰ってきて、町の人口が数倍に膨れ上がっていた。ここでも金武湾と同じように路傍で演奏をし、それがウケにウケた。当時彼は中古の米軍衣料を来ていたが、たくさんあるポケットがすぐにお札でいっぱいになったという。その町の印象を、国隆は「とにかく、石川は寂しさまぎれ、喜び……ちゅうことですね」と言っている。
石川に一時的に集まっていた人たちが各地に帰ると、国隆はコザや普天間に行く。ここは基地建設で湧き返っていた。アメリカの兵隊が闊歩し、彼らを客として次々に盛り場が生まれていた。
珍しい竪琴と、盲目の青年の唄は、アメリカ人にカルチャー・ショックを与えたようだ。国隆が店に入ると、ジュークボックスを止めて、竪琴の演奏に耳を傾けたという。ほとんど拉致されるような形で、Aサイン・バーに連れて行かれ、歌わされたことも一度や二度ではなかった。
「まあ、その頃の思い出で一番残っているということは、弾いておって歩いていると、外人に呼び止められることね。カモーンって、呼び止められてね、それはあたしを呼んでいるのかわからないでしょ。そうすると後ろから補まえられてカモーンってね。ひとりがたかるとなると、皆がそれに動員されて囲まれるってことですよ」
当時の繁華街でのウケ方は、末妹の秀子も目撃している。彼女は昭和26年頃、兄を頼って沖縄観光に来ていた。
「兄にお店に連れて行ってもらったけど、もうウケてね。すごかったよ。あちこちのお店行ったんだけど、みんな満員でさ、客は通りがかりに三味線や竪琴の音を聴いてね、入って来るの」
その頃、国隆は宜野湾市大謝名に小さな借家を借り、3人目の妻と暮らしていたという。
最後の拠点となったのは、沖縄北部の辺野古(へのこ)という町だった。ここも静かな海辺の町だったが、昭和34年からの九志の基地建設で、まるで「正月と盆が一緒になった」ように湧き返っていた。ここで国隆は1年半ほど過ごし、やはり相当稼いでいたようだ。
金武湾を皮きりに、石川、コザ、普天間、辺野古と、彼は群集を求めるように放浪をしていた。彼の商売には人がいなければならなかった。大勢の人がいればいるほど、商売はうまくいった。ポケットに札束が増え、外人は彼を取り巻き、ついに彼はアメリカ兵に連れられてハワイにまで行ったという話もある。取材では、このハワイ行きの具体的な話がとれなかったが、複数の人が彼からそう聞いたと証言している。そういうこともあったかもしれない。確証はないが、否定する根拠もない。おそらく演芸団の一員として船に乗せられ、連れて行かれたのだろう。盲目の男が三味線や竪琴を弾いて、オリエンタルな唄を歌うというだけでも、外人たちにとっては面白かったはずだ。
しかし沖縄放浪の現実は、本人が語るほど景気のいい話ばかりではなかった。
語ってくれたのは山城武次、ヤス夫婦だ。昭和33、34年頃というから国隆がコザや普天間を拠点にしていた時期の話である。当時、山城夫婦は普天間に住んでいた。
ある日、家にいたヤスは通りの向こうから子供の頃に聴き慣れた竪琴の音を耳にする。窓から覗いてみると、はたして国隆が道を歩いていた。
「はい、国隆うじ!」
「はげえ、ヤスコ!」
ヤスは徳之島出身で国隆をよく知っていた。彼は戦前、幾度となく徳之島に立ち寄っては、ヤスの実家に招かれて宴を催していたのだ。テレビもない時代には国隆のような歌者を呼び、近在の者を集めて夜の無卿を慰めるのが、何よりの楽しみだった。
再開後のヤスは、国隆の面倒をなにくれとなくみるようになる。Yシャツやズボン、パンツまで洗濯させられたと、ヤスは当時を振り返り笑っていた。その頃彼は三番日の妻とも別れてひとり身で、とくに決まった家もなく町をふらふらとしていたのだ。父親の義秀の「どこでどうやって人様の面倒になっているかもしれない」という心配は、現実のものとなっていた。
ヤスの夫、武次の記憶では、
「どっかに行って疲れたりしたら、うちに二、三日おってみたり、いなくなったかと思うとまたひょっこり現れたり」していたという。気心の知れた家ということで、ずいぶん気軽に立ち寄ったようだ。
そんな国隆を、武次は見かねて、隣の借家に住まわせるように取りはからった。
「あの人酒飲むからさ、あちこちで寝るんだよ。ある朝、国隆うじが道で寝とってさ、浮浪者みたいなのがふたりで、国隆うじの懐を探っているんだ。たまたま見かけて、こらあって怒鳴ったら逃げて行きよったけど。あの人は、ずうっとそういう生活してたんじゃないの」
こうして国隆と山城夫婦とは、隣付き合いが始まった。
彼らの印象に残っている話としては、こんな出来事がある。
ある日、国隆が突然、新居に新しい嫁を連れてきたという。それを知った山城夫婦は、近所の友人も招いて、ふたりのためにお祝いの宴を催した。国隆自ら厨房に立ち、豚の肝の味噌漬を作り、そして皆で酒を飲んだという。その場にいた誰もが今度こそ放浪人生に区切りをつけて、安定した生活に入ることを確信した瞬間だったかも知れない。
ところが三味線も入り、宴もたけなわになった頃、事故がおこった。国隆の替わりに嫁が台所に立ったのだが、どしんという大きな音がして、倒れてしまったのだ。癇癪の発作だった。
それから数日して、国隆は山城夫婦のところへやって来た。他人に相談なんかしたことがない彼としては珍しく、夫婦に相談を持ちかけたのだった。聞くと妻の症状はかなりひどく、その後も何度も発作をおこしていたという。とても目の不自由な国隆が生涯、介護し続けられるものではなかった。やはり彼女を里へ帰したほうが、お互いのためであろうという結論になったという。
翌朝、国隆はわずか数日連れ添った妻のために、浴衣の反物を買い、里までタクシーで送り届けた。
彼が借家を引き払ったのは、そんなことがあってすぐのことだった。これからどこへ行くのか、山城夫婦には告げられなかった。
昭和22年から始まる沖縄放浪は、昼間は街角で缶からを前に竪琴を弾き、夜は盛り場を流すのを日課としていた。盲目の芸人が何故かくも長き期間、沖縄で生きられたのか、不思議な気がする。もちろん景気よくドル札をばらまく米兵や、ホステスたちが彼の演奏を好んだということは確かだ。しかし生活の資を稼ぐことと、実際に生活することとは次元が違う。彼を支えてきたものは一体何だったのだろうか。
おそらくそれは、山城夫婦のような奄美出身者のネットワークだったのだろう。昭和20年代、奄美から職を求めて多くの人が沖縄にやって来ていた。本土に復帰する以前の話だから、奄美の人たちが出稼ぎに行くとしたら、米軍基地建設に湧く沖縄だった。そんな彼らが有形無形の形で国隆を支えていたのだろう。
山城夫婦のように、隣に住まわせてまで面倒をみるのは希有な例だろうが、盛り場で働く大島出身者が、たまたま道ばたで故郷の唄を聴いたとしたら、やはりお金を缶からに投げ入れただろう。あるいは自分の働く店に呼んで歌わせたかもしれない。
こんな話も聞いた。当時の沖縄に大島出身の親分が幅をきかせていたという。国隆が盛り場で排除されずに商売ができたのも、じつは彼のおかげだったという話だ。
それではどうして盲目の放浪芸人を彼らは大事にしたのか。これも推測だが、国隆が歌う大島民謡は、故郷を離れた人たちに「懐かしさ」を感じさせたからだろう。彼の歌声はけっして美しい声ではない。しわがれた野ざらしの声である。人に合わせてアレンジなんかしない古い歌い方だ。しかしそれこそが、故郷の爺さまや婆さまが歌うのと同じ旋律、同じ節回しの唄だった。だから彼らは、その「懐かしさ」ゆえに国隆が生きる余地をちゃんと残したのだろうと想像する。それはアメリカ人が受けたカルチャー・ショックとは、まったく別の種類の感動で、境涯が違う人たちとは共有できない、孤独な感動だったのではないだろうか。
異論を承知で書くと、沖縄放浪は、国隆が芸そのものだけで生きていたというよりも、奄美出身者のネットワークが彼を生かしていたのである。そして彼が生きていく唯一の武器は、祖父赤坊から徹底的に教えられた古い節回しの民謡だったのだと。
4、嵐の夏
昭和38年、国隆は沖縄での生活に見切りをつけ、故郷奄美大島に帰って来る。
沖縄は基地建設ラッシュが終わり、盛り場も昔に比べ、ずいぶんと大人しくなっていた。かわりにベトナム戦争前夜ともいうべき、不穏な空気が辺りに立ちこめ、米兵も刹那的に暴れることはあっても、以前のように陽気に騒ぐということがなくなった。
そんな町の気分についていくにも、また野宿をするにも、国隆は若くはなかった。すでに44歳になっていた。28歳で沖縄に渡ってから17年の年月が経過していた。
帰郷してすぐに、8番目の、そして最後の妻イノと所帯を持つ。女性関係に華やかだった国隆だったが、籍を入れたのは、生涯でイノだけだった。
最初に住んだのは奄美大島の中心地、名瀬の市街地だった。その翌年、ふたりは名瀬市のはずれにある公営アパートに移り住む。最上階の部屋で、そこからは永田墓地が見おろせる。「名瀬一番の天国一の玄関口」。国隆は冗談で人にこう語った。
夫婦はここでお互いの身をかばい合うようにして、国隆が死ぬまで暮らすことになる。イノもまた目が不自由だった。
彼の職業は、相変わらず路傍で三味線と竪琴を弾き、歌うことだった。沖縄放浪時代と違うのは、缶からの替わりに樟脳が並べていることだ。このスタイルは戦前にやっていたもので、じつに久しぶりの商いだった。が、ナフタリンが売れても、生活費がまかなえるわけではない。やはり沖縄時代と同様、夜になると、盛り場の屋仁川通りを流していた。「乞食の国隆」と人に蔑まれることはあっても、やはり故郷の地で缶からを前に置くのは憚られたのかもしれない。
名瀬の永田橋が彼の昼間の舞台だった。当時からその近くで洋品店を営む店主は、彼のことをよく覚えていた。民謡から昔の流行歌からなんでも歌っていたという。歌と歌の合間にはエロ話をやって、非常に面白かったという。毎日、昼頃やって来て、日が暮れるまで炎天下で演奏を続けていたそうだ。
中村八重が国隆と出会ったのも永田橋のたもとだった。彼女は国隆よりも4歳年上で、これを縁に、最晩年の国隆の会方をつとめる女性である。
「(国隆さんが)市場のそばでムシロをひいて歌っているんです。そして樟脳やあ、こんなに抱いて、声が枯れて歌が出きらんば、皆が集まっているのにひとつも買う人がいなかったんです。琴でも聴いて買ってくださればいいのになあ……琴が声よりも懐かしいのになあ、と私は思ったんです。吾(わ)が先買えば、(皆も)買わないかいち思って……それでも私が買っても皆帰ろうとするから、ちょっと待ってください、私は上手ではないけれど、少うし歌を歌う人だから、吾が歌えばその樟脳買ってくださいますかあち言ったら、ハイあんたが歌ったら買ってあげるよおと皆が言ってね。そしたら私がどんな唄、歌えばいいですかあ、くるだんどう節、ぎんどろ節なんかいっぱい言われたけど、私が言い出したんだから歌わんばち。自作の空襲の歌も歌ったんですよ。そしたら皆が喜んで、買ってくださって……」
八重は自分の住所を国隆に伝え、また必要だったらいつでも呼んでくださいと言って別れた。国隆はたいそう喜んだそうだ。彼女は若いときから声がきれいで、戦争中は兵隊送りの集会でよく歌を歌わされていたという。そのため戦後は、自分は兵隊さんのために十分歌ったからと、けっして人前で歌を歌わなかった歌者である。国隆が自作の「黒だんどう節」を歌うことによって戦争への嫌悪感を表したしたとしたら、彼女は歌わないことで、戦争への憎悪を示していたのだ。
ある人は国隆を評して「風景の一部」と呼んだ。それほど人が交錯する場所には、いつも彼の姿があった。それがあまりにも当たり前の姿であったがゆえに、誰も違和感を感じなかった。
皆が知っている、だけど誰も気にとめることがない存在。彼の人生は、「乞食の国隆」として静かに南国の風景に埋没していくものであっただろう。それは誰よりも本人が、そう思っていたはずだ。
そんな彼に転機が訪れたのは、昭和40年代後半、沖縄に遊びに行っていたときのことである。
奄美で所帯をもったところで、生来の放浪癖は直らなかったようだ。イノを部屋に残し、ふらりと旅に出ることが多かった。
行き先は沖縄だった。やはり昔の知り合いが大勢いたし、どこの辻で演奏をすれば、実入りはどうかということも知悉していた。観光旅行ではなく、芸を見せながら、お金を稼いでの旅だった。それが彼には一番気安い生き方だったし、やはり旅が好きだったのだ。
ふらりと出ていくのと同じように、ふらりと帰って来た。戦前や沖縄放浪時代と違うのは、帰ってくる場所が定まっていることと、いつもイノが迎えてくれることだ。口の悪い国隆は、イノを「留守番に置いているだけ」と周囲には語っていた。
奄美に帰ってきてから何度目かの沖縄行きのときだった。彼はコザにいた。沖縄の本土復帰前の話であることは確かだが、いま年月を確定する資料は何もない。
なんとなくその日、照屋林助は路傍の国隆が気になって、しばらく観察していたという。彼を見るのは始めてではなかったし、唄も聴いたことがあった。しかしどういうわけか、今日は奄美の三味線の撥が気になるし、竪琴が気になる。おまけに歌っている民謡も、大和風でもあるし琉球風でもある。ちゃんぷるーだな、これは。彼は思った。
意を決して、国隆に声を掛けて、自宅まで連れて行くことにした。
照屋林助とは沖縄のテレビやラジオで、歌に司会に活躍し、絶大な人気のある沖縄随一の芸人である。また民俗学にも造詣が深く、沖縄地方に残る諸芸を、音で記録することをライフワークとしていた。家に招き入れた国隆の前にさっそくマイクを立て、テープで録音を始めた。
こうして国隆の演奏は「照屋コレクション」のなかに加えられることになる。
それから数年後、膨大な「照屋コレクション」を聴き、国隆の唄に大きな衝撃を受けた人物がいた。竹中労だ。彼は長年芸能ライターとして活動していたのだが、持ち前のアナーキーな思想のために、活動の範囲は芸能評論を大きくはみだし、映画を作ったり、社会批評をしたり、文化革命を目論んだりしていた。そんな彼が昭和47年の沖縄復帰に際して、精力的に取り組んでいたのは、琉球の民謡文化と歌者(ウタサー)の探索だった。衰弱していく日本の諸芸のなかに残る、本物の芸を探し求めていた。本土の人間に理解しやすく加工されたものではない、道端の芸や街中の芸がどこかに残っているのではないか。そんな思いで復帰したばかりの沖縄を彼は精力的に歩き回っている。沖縄音楽の重要人物に次々とあたり、嘉手苅林昌や登川誠仁を見つけだした。そして昭和49年には彼らを本土に連れ出し、「琉球フェスティバル」と銘打った大コンサートを敢行し、沖縄民謡ブームを作った。そんななか、照屋林助とも接触し、照屋コレクションを聴く機会を得たのだった。
昭和50年、竹中は国隆の野ざらしの声を聴き、これが本物の道端の芸であることを確信する。林助から国隆の住所を聞き出し、すぐに名瀬に駆けつけた。
墓地の見おろせる公営アパートで、竹中労は56歳の国隆とまみえた。はじめて会ったその日、夏に催される「琉球フェスティバル'75夏」への参加を依頼し、国隆の前に金の包みを置いた。
「8月の公演まで、酒はいっさい絶ってください。酒が入ると、声が悪くなる」
国隆は承知した。それから数カ月、彼が酒を控えていたのは、複数の証言がある。
♪ 大東亜戦争に日本が負けて 負けたんや当たり前
科学の戦に竹やり持ちょて 負けたんや当たり前
その頃、国隆の「黒だんどう節」について、小沢昭一、竹中労、照屋林助の3人が鼎談している、そのなかで、小沢昭一が「はいつくばって土下座したい歌だ」と評価している。国隆の本土上陸は、いやがおうにも一部の知識人たちの間で期待が高まっていった。
その夏はまさに嵐のように、初老の国隆を襲った。
8月9日、東京杉並にあるテイチクのスタジオでレコード録音するのを皮きりに、8月12日には京都円山公園音楽堂、13日は新宿コマ劇場に出演、14日青年会館で再びスタジオ録音、15日日比谷野外音楽堂、16日大阪難波花月劇場という強行スケジュールだった。
8月6日、羽田に降り立った国隆はひとりだった。今回の「琉球フェスティバル'75夏」に同行するのは、嘉手苅林昌、登川誠仁、糸数カメ、瀬良垣苗子、知名定男、大工哲弘、饒辺愛子、照屋林助という沖縄のメンバーばかりだった。奄美からの参加者は国隆だけだった。
本来は合方が来るはずだったのだが、直前に来るのを辞退している。
理由は奄美で竹中労が起こした暴行事件だったという。7月30日、竹中は国隆のアパートを再訪している。間近に迫ったコンサートと、テイチクからのLP発売に関しての打ち合わせのためだ。アパートを出た竹中は、屋仁川にある飲み屋でひとり酒を飲み、ホステスに連れられてホテルに戻って来る。事件はそのホテルで起こった。こんな夜遅く戻ってくるのは非常識だと怒るホテルの管理人と、客に失礼だろうというホステスの言い争いから、管理人がホステスに侮辱的言辞を口にしたらしい。そこで、つい竹中が手を出してしまったようだ。
これは翌日の全国紙の夕刊に載り、ふだん事件の少ない奄美では大騒ぎになってしまった。竹中労は赤軍派ではないかというデマまで飛び交った。そんななか合方をつとめるはずだった女性は恐くなり、東京行きを断念したのだといわれている。
合方不在のまま民謡は歌えるはずがなかった。羽田に着いた国隆は、すぐに東京在住の叔母の栄タダに連絡をとる。タダは前日に入れ歯を直したばかりで、最悪の状態だったが、甥の頼みとあっては引き受けないわけにはいかなかった。
こうして9日のテイチクでの録音には、叔母が合方として参加した。タダはその日、国隆とは数十年ぶりの再会だった。
しかし録音は完璧だった。とても66歳とは思えない声、また数十年ぶりの再会とは思えないほどの絶妙な息の合い方だった。
それもそのはず、タダは奄実にいたときに、よく国隆を背中におぶって唄を歌っていたという。彼女も国隆も、赤坊が歌う節回しを体に染み付けていた。一度同じ環境で同じ節回しで体で覚えた民謡は、どんなに長い間離れていても、なんなく呼吸を合わせることができるものなのかもしれない。LP『奄美の哭き歌』はこうしてできた。叔母と甥のデュエットという、おそらく世界的にも珍しいレコードだった。
12日の京都円山劇場からは、これまた急に呼び出された萩原君江が合方をつとめた。萩原は当時尼崎に住んでいた。彼女の夫が国隆と同じ笠利町の出身であったことから、彼女もまた国隆と同じ節回しで歌うことができたのだ。こちらも十数年ぶりの再会で、いきなり舞台に立つことになる。その後、新宿コマ劇場、青年会館、日比谷野音(栄タダと一緒)、そして難波花月と、国隆のもっとも熱い夏を、ともに過ごすのである。
さて、どうにかこうにか乗り切った初めてのコンサートだったが、客の数は思ったよりも入らなかった。京都円山では150人、これは前回の約5分の1。東京公演でも、昨夏の約4分の1の1,300人しか入らなかった。これは、コンサート直前に起こした竹中労の事件が尾を引いている。沖縄、奄美関係者がコンサートは中止だと思い込んでしまったのだ。「琉球フェスティバル'75夏」は興行的には大赤字だったようだ。
しかしそれでも国隆にとっては、十分な大舞台であった。なにしろいつもは道端で観客に見下ろされながら弾いていたのが、一夜にしてステージに立ったのだから。
この夏、彼が残した音は前述の『奄美の哭き歌』(テイチク)と、『狂闘乱舞 カチャーシー大会』(大阪難波花月劇場ライブ、テイチク)、『熱狂の日比谷野音Vol1戦争の哀れ』(日比谷野外音楽堂ライブ、CBSソニー)という3枚のLP盤におさめられた。
夏のツアーの間も、国隆は好んで「黒だんどう節」を歌った。観客数はいまひとつ伸びなかったといえども、来た客はおしなべて、この敗戦の歌詞と、呻きに似た黒声にど肝を抜かれたようである。
当時27歳で「琉球フェスティバル'75夏」の専属カメラマンをつとめた井出情児は、率直な感想としてこう述べている。
「なんじゃこりゃって思いましたよ。いきなりうぇーとやり出したときは。ぼくはこれだってね。いわゆるプロの歌い手じゃないでしょ。そのぶんヒューマンな部分で感じられたから。面白いなと思ったし、絵になるなって思った。存在感があるんだもの。舞台にいても楽屋の隅にいても」
沖縄のメンバーが多いなか、井出の写真におさまっているのは、圧倒的に国隆の姿だった。楽屋の隅で番線を歯で切って、修理していたのが印象的だったという。
5、最期の放浪
「俺はレコードを出しても有頂天にならないよ」
横浜から駆けつけた妹のユウコに、日比谷野音の楽屋でそう言ったという。
その言葉どおり、国隆はこの夏を過ぎても、相変わらず永田橋のたもとで、売れないナフタリンを置いて、唄を歌っている。
行き交う人たちにとって、彼は依然「乞食の国隆」のままだった。永田墓地を見おろす公営アパートに妻イノと住み、昼間は永田橋、夜は屋仁川通りを流していた。「琉球フェスティバル'75夏」は、この島からはあまりにも遠い所で起きた事件に過ぎなかったのだ。
その頃の様子がわかるこんな話がある。
琉球フェスティバルで合方をつとめた萩原君江の話である。フェスティバルから2年後、彼女は大阪尼崎を引き上げ、奄美大島に帰ってきた。話はその直後のことだ。
「永田橋で国隆うじがナフタリンを売っていたんですよ。それで君江も歌え言うから、一生懸命歌ったんです。そしたら叔母が通りかかってね、『はげえ、懐かしい声で唄するが、名瀬にはこんな良い声の人はおらんじゃが思って近寄ってみたら、君ちゃんの馬鹿じゃないか』ち。なんで、国隆うじが歌え言うから歌ってるんだというと、『ふりむん(大馬鹿者)、昼間っからそんな歌う人ひとりもおらんよ』ち叔母にしかられてね(笑)」
弟の治光には「俺は道の上で死ぬんだ」と漏らしていた。
里国隆という男の凄みは、ここにある。奄美民謡をはじめて本土に紹介したことも、レコードを出したことも、この言葉の前では影が薄い。最後まで自分の生き方を曲げなかった男。孤独と自由。その魂が奏でる音。
しかし歌者や研究者の中には、国隆の芸を見直す気運が、盛り上がっていた。各地の郷友会に誘われたり、研究会に引っ張り出されたりするようになるのもこの頃である。
現在奄美を代表する歌者である築地俊造は国隆を早いうちから評価していたひとりだ。太鼓を叩きながら三味線を弾き、さらに四つ竹を叩くというアクロバット的な奏法と、そこから生まれる絶妙なリズムが気になって仕様がなかったという。
ある日道端の国隆にお金とカセットテープを渡し、六調(奄美の騒ぎ唄、宴会の最後は必ずこれで盛り上げ、踊る)を吹き込んでくれと頼んだ。ああ、いいよ。国隆は請け負い、翌日にテープを俊造に渡した。
自宅に戻って、再生してみてがっかりした。テープには延々と国隆の口上が入っていて、演奏は入っていなかったのだ。
そこでまたテープを渡してお願いすると、今度はきちんと六調を吹き込んでくれたという。
この頃の国隆は、徐々に歌者たちとの交流を深めていく。アパートに招いては「唄遊び」を催したりもした。こうした歌者たちの中には、築地俊造のように、彼の技を自分のものにしようとする熱心な者もいたようだ。
自宅に民謡教室の看板を掲げたこともある。しかし彼の性格が、人に芸を教えることに向かないため、すぐに外したということだが。
昭和60年6月22日、23日の沖縄ジァン・ジァンへの出演が彼の最後の旅となる。病をおしての沖縄行きだった。
そのひと月前に、国隆は名瀬中央病院を退院したばかりだった。長年の放浪生活からか、彼の体は年齢のわりには衰えていた。60歳を過ぎた頃から、胸の不調を訴え、何度か入退院を繰り返していた。
退院後、すぐに大阪尼崎に飛び、郷友会の人たちを前に演奏している。それすら、イノや親戚の反対を押し切っての出演だった。記録ビデオを見ると、往年の骨太さはまったく感じられず、ほとんど瀕死の老人の姿がそこにある。合方は中村八重だった。
そういうわけで、今回の沖縄行きは親戚には黙って、隠れるように出かけている。
旅立つ前日、不思議なことがあった。国隆はイノに「土産は何がいいか」と聞いたという。今まで一度もそんなことを言ったことがなかったのに。
「あなたの体が健康で戻っちくりばいい」
イノはそう答えた。
ジァン・ジァン公演の合方は松山美枝子だった。国際通りのホテルに隣同士の部屋をとった。松山は国隆の具合が大分悪いのを知り、もし夜中でも具合が悪くなれば、壁を叩くようにと言いおいて休んだ。
はたして22日の朝6時に壁が鳴る。急いで部屋に行くと、国隆は息苦しいと訴えた。背中をさすり、水をあげると具合が良くなったという。そしてその夜の公演は、病を押してのライブとは客が気がつかないほど、生命力が漲った声を張り上げている。唄と唄の合間にはジョークで人を笑わせるのも忘れていない。
翌日は不調を訴えることもなく昼間が過ぎ、夜の公演も無事終了した。テープを聴くかぎり、国隆をかばって松山がたくさん歌っているような気がするが、国隆の声に体調の悪さは感じさせない。口上も前日同様、しっかりとしている。
打ち上げ会は、国際通りの「波」というスナックだった。
濱田直隆はその夜、国隆を自分が経営する「特別養護老人ホーム」に招待することになっていた。彼は国隆と同じ笠利町出身で、国隆を子供の頃から知っていた。やはり戦後に沖縄にやって来て、昭和50年から宜野座で「老人ホーム」を経営している。
今回のジァン・ジァン公演の前に、国隆から一本の電話があった。話していると国隆がたいへん老人ホームに興味を抱いているのがわかった。それでは一度見てみますか、そう濱田は国隆に提案し、公演が終わったあとに連れていく約束になっていたのだ。
濱田は「波」まで車で迎えに行く。
「ビール、ウイスキーが出たが、国隆うじはいっさい飲まなくて、食べ物を少し召し上がっただけでした。私の隣に座ってもらったんですが、暫くすると私の背広の裾を引っ張るんですよ。帰ろうと。そんなら帰りましょうかと。私も車だから飲めない。それじゃ失礼します、先輩方、皆さん、私はこの方をお連れしますと言って会場を出ていったんです」
車は宜野座に向かって58号線を北上した。
「嘉手納にきたらね、この辺はどこだって、国隆うじが聞くんです。嘉手納基地ですよ。そうか、昔キャンプに出入りしていた頃はよく来たとこだよ。懐かしいなあ。ここで食べたハンバーガーの味が忘れられないんだと。ありますよ、そこにありますよ。買ってきましょうねと。あと飲み物は何を召し上がりたいのって聞くと、コーラはいいからミカンのジュースが欲しいって言うんです。それでハンバーガーとジュースを車の中で召し上がったですよ」
でいご園に着いて、濱田ははじめて国隆の体調が最悪なのに気がつく。
「園の階段を昇るとき、二三段上がって上がりきれなかったんです。それで抱っこをして階段を上げました」
夜11時過ぎ、呼吸困難になり、あわてて医者を呼んで診察をさせる。その夜は酸素吸入器をつけて休ませる。
翌日、老人ホーム内で精密検査をする。その日の医者の診立てでは、どうも心臓と肝臓が付着しているようだということだった。
当時は精密検査の結果が出るまで一週間を要した。そこでそれまで老人ホームに体験入居したらどうですか、と濱田が聞いた。国隆は願ってもないと言って喜んだという。寮母や老人たちに竪琴を弾いて楽しませるから、よろしく頼むよと。
それから3日後、国隆は検査結果を待たずに心停止する。じつにあっけない最期だった。昭和60年6月27日。享年66歳。
遺体は濱田の采配で、石川の火葬場で荼毘に付された。結婚してから23年間、旅から帰ってきた国隆をいつも迎えてきたイノだったが、最後の旅から帰って来たのは遺骨だった。
国隆の死はあっという間に伝説となった。いわく慰問先の老人ホームの舞台の上で倒れて死んだと。しかし真相はジァン・ジァン公演を無事やり遂げたあとに体験入居した老人ホームで、持病をこじらせての死だった。しかし彼のことを知っている者ほど、壮絶な死のドラマを思い描いた。
国隆が死ぬのだったら、畳の上での死であるわけがない、大道で生き、大道で死ぬ、本人もそう言い、皆もそう信じていた。しかしそう思わせることこそ「乞食の国隆」の神髄であり、彼の生き方そのものが壮大な芸だった証拠であろう。
生前の彼を知るものはナフタリンが売れている現場をほとんど見ていない。かりに売れていたとしてもその金額はわずかなものだったろう。彼が何を売っていたか、いや売らなかったかがよくわかる。
彼の墓はあやまる岬のすぐ近くにある。長い放浪のあと、ようやく故郷に帰って来た。 (敬林略)
○南島の昭和史を歩いた漂白の芸人
by 仲宗根幸市 (里 国隆のCD「黒声」のライナーノーツ)
昭和52年、わたしは名瀬市で盲目の芸人里国隆と初めて会った。早速あいさつがわりに「あさばな節」と「黒だんど節」をうたってくれた。呻くような歌声に、一瞬わたしは面食らってしまった。なぜなら、奄美の歌といえば、あの神秘な美しい裏声をイメージしていたからである。だが国隆の歌はドスのきいたダミ声で、腹の底から絞りあげるかのようであった。喉を締めつけているような発声は決して心地よいものではない。けれども、のちに放浪芸人としての国隆の芸へのイメージは変わっていった。
即興が凄いのだ。国隆のかなでる半琴(はんぐとう=短い琴のこと)と奄美三絃に乗せた歌は、あたかも山あいからひんやりとそよぐ風のような哀感と、奄美民衆の叫びが伝わってくる。そして、北大島の古い節まわし(崎原節)の伝承者としてわたしは注目していた。
沖縄戦33回忌の昭和53年、国隆はラジオ沖縄の招きで那覇空港に下り立った。国隆の足跡を追う番組に出演するためである。一連の企画には、わたしも同行した。具志川市、石川市、沖縄市、那覇市の平和通りを訪ね、市場のおばあさんたちの前で国隆は半琴を演奏した。さらにわれわれは名護市の辺野古、国頭村の安田まで北上した。安田といえば、沖縄の本土復帰前まで陸の孤島と呼ばれ、昭和の初め頃までは道らしい道のない山地である。そんな安田で、今次大戦直前国隆青年はなんと、公演をやっていたのだ。珍しい国隆の芸を見たという当時の少年らは、50代になっていた。その晩国隆は至極ご満悦で、「奄美の子守歌」を早いテンポでうたい、村人と旧交を温めたのである。国隆の沖縄へのひとり旅がまた面白い。名瀬から牛積み船に乗って航行中時化に遭い、国頭村の奥に漂着。そこから奥村の女の書記に手を引かれ、10キロも離れた安田村へ山を越えて行ったという。安田の人たちは、盲目の旅芸人が道なき道を踏み越えて来たということで、感激ひとしおだったとわれわれに語っている。
国隆の大衆芸は、出身地の奄美で決して評価されることはなかった。放浪芸人国隆の半生は、乞食同然であったという。だが、国隆の芸は哀感とともに常にユーモアがあり、人びとの心をなぐさめた。「無一文で沖縄の隅々まで流したのは、わたしひとりでしょう」と国隆は語っている。国隆こそ南島の昭和史を歩いた漂白の芸人だったのだ。沖縄ジァン・ジァンで燃えつきてすでに15年、南島を遍歴した国隆の芸は何であったのか、いま静かに光が当てられつつある。
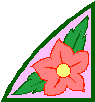
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集