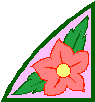○我が家の宝 by 知名定男 (雑誌「うるま」 2002年5月号 “島唄美しゃ”
から)
 沖縄を代表する楽器三線にはいろいろな型がある。古い順に言うと、南風原(フェーバラ)型、久葉の骨(クバヌフニ)、久葉春殿(クバシュンドゥン)、真壁(マカビ)型、知念大工(チニンデークー)、与那(ユナー)型、江戸(イドゥ)与那。それぞれ構造に特徴があって、太くて柔らかな音、細くて高い音など、演奏者が自分の声に合う三線、または好みによって選ぶようである。
沖縄を代表する楽器三線にはいろいろな型がある。古い順に言うと、南風原(フェーバラ)型、久葉の骨(クバヌフニ)、久葉春殿(クバシュンドゥン)、真壁(マカビ)型、知念大工(チニンデークー)、与那(ユナー)型、江戸(イドゥ)与那。それぞれ構造に特徴があって、太くて柔らかな音、細くて高い音など、演奏者が自分の声に合う三線、または好みによって選ぶようである。
我が家にもいくつか名器がある。その中でも際立っているのが、父定繁が長年大事に大事にしていた南風原三線だ。この三線は、長期にわたり琉球古典音楽の名人や三線達人の手を渡り歩いた。戦前、安冨祖流古典音楽の名人、平良雄一氏が所蔵し、なんらかの理由で、民謡の神様チコンキーフクバルこと、普久原朝喜氏の手に渡ったのである。それがまた、なんらかの理由で普久原氏と大阪で兄弟分にあたる父、知名定繁の手に渡ったのである。そして現在は、私が家宝として所蔵している。
この南風原型三線は、たくさんの著名な音楽家達が所蔵したと言われているが、それもそのはず。歴史的古典音楽家、池宮輝喜氏が名器を求めて世界中を廻り、自分の目で鑑定し選び抜いた名器ばかりを紹介した「三味線宝鑑」に、この南風原三線も写真つきで載っているのである。私はたまに三線箱からそれを取り出し、おもむろに弾いたりするが、何か他の三線と違う。ネック(竿)が細いせいか絃を弾く度に振動し、それが心に響くのである。弾くほどに日々の暮らしの疲れを癒してくれる。心の乱れを直してくれる。大人になった気分になる。過去における過ちを反省させてくれる。あたかも自分が名人になった気分にもなる。摩詞不思議な名器南風原である。私には身に余る代物なのかも知れない。
さて、それでは、この名器なる楽器はどの程度の値打ちなのか、お金に換算するとどうなのか。値段がはたしてあるものなのかと言うと、これは難しい問題になってくる。三線屋等で市販されている三線には、協定の値段があるかも知れないが、歴史ある三線、由緒ある名器に値段があるのか。昔の話にこんなのがある。どこそこで鳴り響いた三線と自分の家を交換した話、馬と交換した話。ただ、ここでもはっきりとした値段が出てこない。
十数年前に北谷のある収集家が、我が家を訪ねて来た。「三味線宝鑑」を見て、私が所蔵する三線を見たいと来訪されたのだ。私は怪しむことなくお見せした。すると、しばらく見入っていた彼は、300万円でゆずってほしいと言い出したのである。びっくりした私は思わず、何ですって? と自分の耳を疑った。彼はそれでも平然としていた。当時私は、ある事業の失敗でお金に困っていた。のどから手が出るほどにお金がほしかった。が結局はお断りした。
「この三線には名人の手を渡り歩いた歴史があり、父定繁の形見でもあり、音楽家を志す私自身の誇りなのです。たとえ貴方が一億積まれようと譲るわけにはいかないのです」
と丁重にお断りしたのだ。しかしなぜか自分の発した言葉と、喉から手が出るほど欲しかった物を失ったという複雑な気持ちで、溢れる涙が止まらなかった。
話をもとに戻そう。だとしたら我が家の家宝、南風原三線は一億でも売らないと言ったのだから、それでは一億円以上するのか。そんなはずはないよなあー。
これも聞いた話なのだが、中国は床の間に書物を飾っておくらしい。いかにも学問の国だ。日本は刀剣や鐙兜を飾る。戦の好きな民族だ。我が沖縄は三線を飾る。音楽を愛し、平和を愛する証だ。
私は、この南風原三線を家宝とし、この三線のもつ歴史や誇りを大事にし、末代まで語り継がれるよう心から祈念し、これからの音楽生活に精進していきたい。

○勝手口インタビュー にっぽんの妻たち 〜沖縄民謡歌手知名定男夫人 知名幸子
インタビュアー 根岸康雄 (知名定男芸能生活45周年記念リサイタルのプログラムから)
 長年の努力と精進によって、各分野で第一人者となった男達。
長年の努力と精進によって、各分野で第一人者となった男達。
だが、その陰には妻として片時も離れず男を支えてきた女達がいる。
夫と共に歩んできた熱き人生を、今、夫人自らが深く静かに語る……。
◇入籍時に姉さん女房と初めて知って…
「幸せですよ、うん、後悔なんて何もないです」(幸子夫人)
「(女房は)叩かれても叩かれても、相手を許してしまう。それはいわゆるウチナンチュウ(沖縄の人)の持っている強さ以外の何ものでもないんですよね」(知名定男氏)
アルバム『赤花』、『島うた』、沖縄民謡をベースに唄い人気を得た女性グループ“ネーネーズ”のプロデュースなど、沖縄民謡の歌手として第一人者的存在の知名定男氏(49。―管理人注:年齢からみて1994年頃の文章と思われる)。
沖縄県沖縄市の自宅の縁側で、知名氏の奏でる三線(沖縄の三味線)の音色と、透き通った唄声は、海に向かって吹く風と共に、快く胸にひびく。夫を笑顔で見つめる幸子夫人の童顔もまた、沖縄民謡が似合っていた。
知名幸子、沖縄民謡歌手・知名定男夫人、1939年宮古島生まれ。
「父の仕事の関係で、小学校のときに宮古島から沖縄本島に来て、あちこち転校したの。南大東島に住んだこともありますよ。
中学を卒業して、那覇市内の靴店に2年ほど勤めて。次にコザ(現沖縄市)のアポロって喫茶店で働いて。それからね、クラブに勤めたりスナックにいったり、石川県の金沢のホテルで沖縄の人たちと働いたこともありました。
そして金沢からコザに戻って、クラブに勤めているときに、お父さんと知り合ったんです」
「当時、彼女は『クラブ沖縄』って店でホステスをやっとったんですよ。その店にポクの門弟が出入りしていて、誘われて飲みにいったんです。そのときに知り合って。タイプだったのかなー、けっこう通いつめた」(氏)
「ムッツリとして愛嬌のない人だった。なぜ親しくなったのか、さあ、覚えてないわ。お父さんは覚えているのかも(笑)」
「ポクは姉妹店の民謡クラブのステージに出演していて、そのうち民謡クラブが忙しくなったから彼女も、ホステスとしてポクが出ている店で働いて。店にいる間がデートという感じで。“昭和20年生まれぐらいかい?”と訊いたら“うん”というから。
そうこうするうちに子供ができて、お互いに再婚なもんだから入籍せずに子供は認知しておったんですよ。子供が学校に行くようになって入籍に行ったら、彼女の生年月日が昭和14年て、初めてわかったの。驚いたよ、6歳年上で、びっくりした。
ええ、ポクは再々婚。3度目です。まっ、3人の女性と知り合ったっていうか。若い頃って分別なく盛り上がるっていうか、胸のうちで悪いなーと思っても、自分の妻よりも好きな女性が現れて、かたときもその人と離れたくないんだという。ボクは惚れた女とは、一緒にならないと気がすまないタチだから。
最初の人と1年ぐらい暮らして、子供が1人できて、次の人とは2年ぐらいおって、子供が1人。二人とも女の子で」(氏)
「(前の夫は)バクチ好きでねー。それが嫌だったの。生活費全部、ポーカーとかで賭けちゃう」
「ボクは2人の娘をひきとって、自分の親に預けて。子供に対して、申し訳なかったというのはありますよね。ただ娘たちと、彼女との間にできた息子たちと、仲がいいんでね」(氏)
「(再婚したのは)なんでかなー。うん……、優しかった。あの頃、私、友達とアパートを借りていましたから。私が仕事を休んでも、友達に私の好きなエビの握りを持たせて、私それを食べながら、“うわー、こんなことしてくれるんだぁ…”って。
お父さんの歌を初めて聴いたときは“いいうたさぁーだなぁ”って思った」
「“うたさぁー”は、沖縄の言葉で歌い手という意味ですよ。昭和46年の何月頃だったか。とりたててきっかけなんてないけど、もうこいつといっしょになろうと、判断したんでしょうね。
一緒になって1年ちょっとで、男の子を産んでくれましたからね。沖縄では男の子を産むというのは、大きな仕事を成しとげたことで。沖縄は祖先崇拝というか、宗教的に縦の線を大切にしますから。これで根が切れない、我が家は安泰だと。どんなもんだ!という感じで。
ですから、長男を産んでくれた女性だという気持ちになりまして。すぐに次男も産まれて、それが強い楔になったような。
だからって、仕事に精を出そうとか、なかったけど。沖縄の人はのんびりして、あまり仕事をやらんですから」(氏)
◇唄わない歌手?客に媚びない気持ちは今も…
「最初は名護でお店をやって、お客さんがいつもいっぱいだった。儲かったお金はどこにいっちゃったんだろう(笑)」
「ボクがステージで演奏して、当時は海洋博景気でね」(氏)
「お店は夜でしょ。昼は家のことをせんといかんし。店に行く時に子供を友達に預けて、カウンターの中でつまみを出したりお酒を作ったり、大変でしたよ」
「名護の店で300万円たまって、それを元に具志川に店を出したんですけど、ダメで」(氏)
「落ち込むなんて、ぜんぜん。私は食べるものがなくても気にしないって感じだから。お店は何度も変わったなぁ」
「つぎに人を入れずにボクが独演する民謡酒場を作ったんですが、その頃から性格がだんだん気難しくなってきたというか。客に媚びを売った形で、水商売の延長のように唄いたくないというね。だから、ケンカばかりしとったです。彼女は“唄ってよ!”と」(氏)
「だって、お客さんは唄ってほしいでしょ。“何時頃始まりますか”って。“いつ唄いますか”って訊いても“唄わない!”って。腹立つでしょ。お客さんがかわいそうだしね」
「“おまえも歌い手の気持ちというものをもうちょっと分かれ!”っていったの」(氏)
「わかんないよねー、歌を唄ってくれれば、気持ちよくお客さんだってお金遣ってくれるし」
「“お金払って聴きにきているのに!?”といわれると、“その金返すから帰れ”って、何回も客とケンカした」(氏)
「そうなの。私はお金ほしいしさね(笑)。ハラハラするわけ、店の中で何いいだすかって」
「唄わされるのが嫌いなんです。お金を遣う人の前だから唄うとかいう気持ちは全くない。聴いてくれるお客にだけ、命をかけて唄いたいという。それは今でも変わんないんです」(氏)
◇沖縄民謡の担い手としてこれからも…
「自分が唄いたいとき。お店にお客がだーれもいないのに、ひとりで唄っていたり。もう腹立たないけどね。そういう性格だなーって思っちゃってさ。私は“唄わなくても店にいなさい”って(笑)、お父さんがいるだけで、ビールのお客さんがボトルを注文してくれるんです。
『赤花』ってアルバムを出したときは、沖縄の人たちが怒って、“沖縄民謡でもない変な歌を作って!”って電話で文句をいわれて」
「『赤花』でエレクトリックな楽器を使ったりしたのは、沖縄の歌をね、ポピュラーミュージックというか、そういう形でとらえてほしいなという」(氏)
「着物姿をやめて、パーマ頭にヒゲをはやして、ジーパンのかっこうで唄ったんですよ。それでね、また文句の電話があって、“くさぷっきて!”(あんなかっこで)って」
「ボクは『赤花』以前からジーンズで唄ってましたよ。なぜ着物じゃなきゃいかんのか!?若い子たちはどんどん本土指向になっていて、沖縄文化を忘れがちになっている部分があったから、なんとか若者の目をこっちに向けさせようという」(氏)
「おじいちゃん(管理人注:知名定繁)が、“定男は沖縄民謡にみんなの目を向けさせるために頑張ってるんだから、お父さんを信じて怒らないでよー”って。人から“変な歌作って!”って、電話で怒られても、“あ、そうですか”って。“そうですか、そうですか”としか、私は返事しません。電話がかかってくるということは、あっ、聴いているんだなーと思ったし。
大きな借金も抱えましたからね。9年前ですか、ミュージカルをやったんです。あれ、すっごい借金。まだ、その借金を返している」
「戦時中の沖縄の白ゆり部隊をテーマにした作品に感動して、なんとか沖縄で公演したいと、オレも見境いなくやって。客は2万5千人入ったんですよ。でも、2千5百万円の赤字。やっぱりね、劇団員を20名大阪から連れてきて、約1か月おったから、その間のホテル代とか。あれはまいったよな……」(氏)
「最初から赤字覚悟でやりますでしょ。反対しても、きくような人じゃないことは、わかりますから。“この家なくなるかなー、またアパートに戻るのか……”と思って。落ち込む前に私はあきれかえっちゃって(笑)。この家も売りに出したけど、今もこうしてもってる(笑)」
「あれはやり過ぎですね」(氏)
「お父さんは幸せもんだよ。だって自分のやりたいことを何でもやってきたし」
「今度はライブハウスをオープンするんですよ。民謡の担い手の発着地点として、沖縄音楽のルネサンス的なものになればと」(氏。管理人注:『ライブハウス島唄』のこと。)
「赤字はだしませんよ、ええ」
「彼女は強いって。そうでしょうね。叩かれても叩かれても、許してしまう。それは強さ以外の何ものでもない。抜けてるようで自分の城をちゃんと作ってますから」(氏)
「一緒になって23年――、いろいろありましたけど、素敵な生活だったと思ってますよ(微笑)」

○与那国の歴史 by 立松和平 (雑誌「うるま」 2002年5月号 “島へ島へと”
から)
 その時私は援農隊の正規のメンバーではなく、ただついていっただけだったから、時間はいくらでも自由になった。援農隊の組織者は東京や札幌で説明会をやり、面接を
して、島にいくメンバーを決める。与那国島に援農隊を送り込むまでが、中心の大きな仕事である。砂糖キビ刈りがはじまり、製糖工場が動きだすと、あとの仕事は自動的に進んで
いくということになる。
その時私は援農隊の正規のメンバーではなく、ただついていっただけだったから、時間はいくらでも自由になった。援農隊の組織者は東京や札幌で説明会をやり、面接を
して、島にいくメンバーを決める。与那国島に援農隊を送り込むまでが、中心の大きな仕事である。砂糖キビ刈りがはじまり、製糖工場が動きだすと、あとの仕事は自動的に進んで
いくということになる。
私は翌年援農隊に参加しようと決めていた。そのためにこそ、与那国島について知りたいと思った。実体験の集積が一番よいのではあるが、それには時間がかかる。ガイドブックというのではなく、その島の地誌や歴史などが書いてあるしっかりした本がほしい。しかし、たいていはないものねだりのこ
とが多い。
そんな気持ちであいている時間に島を散歩し、島に唯一ある土産店にふらりとはいった。クバ笠や籠がたくさんある中に、ハードカバーの一冊の本が目にとまった。カバーもない、青い単色の上に金の箔押しがしてある地味な本で、「与那国の歴史」池間栄三著と書いてある。私はその本を手にとり、ぱらぱらとページをめくってみて、完全に私が求めている本だということがわかった。さっそく私は買い求めた。
ここには与那国島のすべてが書かれていた。地誌、伝説、上代の遺風、祭事、民謡、年表と、この一冊を読めば、今日的なことはともかく、与那国島のおおよそすべてのことはわかるのである。これだけのことを独力でやりとげた人がいることに、私は感心した。与那国島に対して強い愛があるのであることは、すぐにわかる。
著者の池間栄三という人は、医者である。自序にはこう書 かれている。
「本誌は、岳父新里和盛氏が与那国町の委嘱をうけて、1939年に起稿したものである。岳父は不便な孤島に在って、実に根気よく、島内外の伝説、記録を渉猟し、根気よくその筆を執ったのであるが、1950年の秋、病魔におそわれ、未だ本誌の完成を見なかったのを残念に、他界したのである。まことに心中察するにあまりあるものがあった。爾来その草稿は塵挨に埋もれ、折角集録した文献は散逸の虞れがあったので、1954年に岳父の後をうけて、不肖筆を執ったのである。」
ここには世代から世代への意思の受け渡しがある。しかし池間栄三氏は医者として多忙な日を送りながら、ついに「与那国島誌」を出版した。その後、なお充実させるためにさら
に史料を集め、改訂版としての「与那国の歴史」の出版の準備をすすめていたところ、池間栄三氏は突然病死したのであった。
そのあとを継いだのが、苗子夫人である。友人の池宮城秀意氏が、「与那国の歴史」に一文を寄せている。
「栄三君亡きあと苗子夫人は彼が執筆をすすめていた遺稿をとりまとめることで心の支えとした。そして一周忌までには改訂版の『与那国の歴史』を仏前に献げるように、すべてをそれに集中したのであった。写真を揃えたり、原稿の清書など苗子夫人は独りすすめてきた。」
池宮城氏の文章が書かれた日付は、「1972・3・3」となっている。1939年に起稿されてから、三人の手になり、33年の歳月がたっている。一冊の本が、このように長い歴史をはらんでいるのだ。
私が手にとった一冊の本「与那国の歴史」は、その後、与那国島に関する私のバイブルとなったのである。その後さら に改訂飯がでて、私は二冊持っている。

○織りなす日々 by 篠原 章 (りんけんバンドのCD「織りなす日々」のライナーノーツから)
 この9月15日(注:2001年)、久々にりんけんバンドのライヴを見た。ホームグラウンド
“カラハーイ”での定例ライヴである。初めてりんけんバンドを見たのが1990年1月のことだから、足かけ12年にわたって彼らの演奏を聴き続けてきたことになる。ライヴに足を運んだ回数も40回近い。その間、色々なことがあったが、彼らのステージの基本的なスタイルは今も昔も変わらない。にもかかわらず、不覚にも涙を流してしまうときがある。9月15日もそう
いうライヴだった。
この9月15日(注:2001年)、久々にりんけんバンドのライヴを見た。ホームグラウンド
“カラハーイ”での定例ライヴである。初めてりんけんバンドを見たのが1990年1月のことだから、足かけ12年にわたって彼らの演奏を聴き続けてきたことになる。ライヴに足を運んだ回数も40回近い。その間、色々なことがあったが、彼らのステージの基本的なスタイルは今も昔も変わらない。にもかかわらず、不覚にも涙を流してしまうときがある。9月15日もそう
いうライヴだった。
上原知子がいいのはあたりまえである。歌はもちろん、その一挙手一投足にいたるまで、もはや“至極の芸”の域に達している。が、この日涙を誘われたのは、上原知子が素晴らしかったからだけではない。フロント3人衆(桑江
良美・稲福克典・大城隼)のパフォーマンスに、人間としての“無限の力”を感じたからである。島太鼓や櫂を操りながら、ステージを縦横無尽に動き回る彼らの姿が、いつにも増して美しく見えたのである。
直前の9月11日、にわかに信じられないようなテロ攻撃が行われた。人間とはなんと残酷で悲しい存在なのかと、ぼくは絶望的な気分を抱えたまま沖縄に飛んだのだが、りんけんバンドのステージは、「人間って、こんなに力強く、楽しく、そして優しい存在なんだよ」と、訴えかけてくるようだった。武力など、この上質のエンターテインメントを前にひれ伏すに違いないと、この日のぼくは、柄にもなく純真無垢な気持ちになった。
そのりんけんバンドが、『織りなす日々』と題する12枚目のオリジナルアルバムを制作した。CDデビュー以来足かけ12年で12枚、1年に1枚ずつアルバムを発表してきたことになる。十ニヵ月・十二支など、「12」
という数字は暮らしのなかでよく使われる数字である。おそらく12という数字は、地球のリズムを表す数字ではないかと思う。その意味で12枚目というのは、地球のリズムを体に合わせながら音楽に取り組んできたりんけんバンドにとって、ひとつの節目を示す作品だ。
このアルバムが以前と大きく異なるのは、まずエンジニアを照屋林賢自身が務めているという点である。そのせいか、陰影が増してキラキラしている。以前の作品より立体感があるのだ。上原知子のボーカルがまたまぶしい。吸い込まれそうな手触り感のあるこのボーカルを際だたせるように、べース・上原顕の柔らかいフレージングやキーボード・山川清仁の小気味よいプレイが艶やかに織り込まれている。
作曲はすべて当代随一のメロディーメーカーである林賢。「織りなす日々」や「夏ぬ風」のような新鮮な作風には感嘆するばかりだ。作詞のほとんどは例によって名嘉睦稔で、小林一茶顔負けの素朴で印象的な言葉が連なる。「涙」あたりを聴くと、二人のコンビはレノン=マッカートニーに匹敵するんじゃないかと思う。今回はまた、「1.2.3.4」で桑江良美が作詞家デビューしている。
沖縄とヤマトといちばん違うのは時間の観念である。沖縄では過去と現在と未来が、人を真ん中に置きながら融け合っている。時間を「経済的資源」としか見ないどこぞの世界とは違って、時間に温もりがあるのだ。『織りなす日々』
というのはそういうことなのだ。過去に対する尊敬と、現在に対する柔軟さと、未来に対する希望とが、心のなかで融けあって共生している状態なのだと思う。
そんなことを考えながら、『織りなす日々』を聴いていたら、ぼくたちの時の流れが紅型のように染め上げられて、天空の星まで届くような錯覚を覚えた。りんけんバンドの次の12年がまた楽しみになった。

○琉球フェスティバル by 知名定男 (雑誌「うるま」2002年7月号 “島唄美しゃ”
から)
 今や夏の風物詩になっている沖縄関連の最大イベント「琉球フェスティバル」。
毎年、東京と大阪で行われていて、今年で8回目の開催となる。この催しを首を長くして待っている人達のことを思うと、1回目からプロデュースに関わってきた私としては感無量の思いがあり、苦労を費やしてきた先駆者達の夢が叶い、まさに奇跡に近いイベントの盛り上がりにしみじみ喜びをかみしめている次第だ。この喜びを誰に向かってありがとうと伝えよう。先駆者か、あるいは主催者なのか、いや首を長くして待っている観客か。
今や夏の風物詩になっている沖縄関連の最大イベント「琉球フェスティバル」。
毎年、東京と大阪で行われていて、今年で8回目の開催となる。この催しを首を長くして待っている人達のことを思うと、1回目からプロデュースに関わってきた私としては感無量の思いがあり、苦労を費やしてきた先駆者達の夢が叶い、まさに奇跡に近いイベントの盛り上がりにしみじみ喜びをかみしめている次第だ。この喜びを誰に向かってありがとうと伝えよう。先駆者か、あるいは主催者なのか、いや首を長くして待っている観客か。
そもそも琉球フェスティバルは、75年頃に当時沖縄に非常に深い関心を持ち、うちなーんちゅにさえなろうとしていた竹中労というルポ・ライターが考案した。膨大なお金をはたいて、東京は日比谷野外音楽堂、京都円山公園、大阪フェスティパルホールの会場を貸し切り開催されることになった。勇気のいる決断だった。
東京こそ大入りになったものの京都、大阪は散々たるものだった。そのため彼は、出演者のギャラを支払うためあちこちから借金までしていた。当時の出演者は、嘉手苅林昌、金城睦松、山里勇吉、登川誠仁、知名定繁、糸数カメ、大城美佐子。若手では嘉手苅林次、大工哲弘、それに私。司会進行はあの上原直彦と照屋林助、さらに八木正男と北島角子という錚々たるメンバーだった。これだけのメンバーを網羅し、果して採算は取れるのかというイベントを彼は強行したのだ。
出演料、宿泊費、移動費、それはもう目もくらむような大金を懸けての大イベントだった。沖縄を想い、そこに暮らす人々を愛し、島唄にのめり込み、彼は琉球フェスティバル開催実現に向けて心を駆り立てていた。激しい思想家であった彼は、身も心も「琉球フェスティバル」実現への活動に捧げ、やがては朽ち果てた。遺言により彼の骨は、沖縄の海にばらまかれた。
やがて彼の遺志は、当時の制作スタッフだった人達の手によって復活するのである。すなわち第2次琉球フェスティバルの開催だ。私はその相談を持ちかけられた時、飛び上がらんばかりに驚き、そして喜んだ。沖縄音楽が日本でも注目されはじめ、ワールドミュージック・ブームに便乗し、新しい沖縄音楽の時代をつくれると思ったからだ。早速、照屋林賢や大工哲弘に話を持ちかけ、琉球フェスティバルの歴史を蘇らせ、亡き竹中労の遺志を継ぎ、新たな沖縄時代を形成したいということを理解してもらい、10年続ける約束をもとに「琉球フェスティバル」ははじまった。
これまでに一番印象に残っているのは、日本武道館に約1万人、大阪ドームに約2万人を動員したステージだった。これまでの沖縄関連イベントでは考えられない観客数である。集まったうちなーんちゅは、全員涙で顔をくしゃくしゃにして何を想い、何を感じたのであろうか。会場は盛り上がり、興奮の坩堝と化した。まさにあれは沖縄パワーだった。戦後の苦境を耐えぬいてきた人達が泣いた。三線を弾くことさえ肩身がせまく、それでも歌を愛してきた人達が泣いた。若い歌い手が改めて沖縄を認識し泣いた。出演者達が感動と喜びに泣いた。舞台と観客が一体となり泣いた。涙と喜びと感動の沖縄の風が吹き、フィナーレのカチャーシーの熱狂と乱舞のなか、私は目を閉じて「労さん、ありがとう」と呟いた。
6回目と7回目にはやむを得ない理由があって私は参加を辞退した。参加しないという関わり方もあると思ったからだ。琉球フェスティバルですべてのものを見て、何かを感じて欲
しいと思う。そのためには不参加も止むを得ない場合がある。それはご理解いただきたい。
やがてフェスティバルの季節がやってくる。今年はどんな内容になるのか、どんな唄者たちが出演するのか楽しみに期待してください。

○本当の沖縄、本当の島の歌―嘉手苅林昌
by 登川誠仁 (「登川誠仁自伝 オキナワをうたう」 から)
 ここで嘉手苅林昌さんのことに触れさせてください。
ここで嘉手苅林昌さんのことに触れさせてください。
嘉手苅林昌さんの前にも、普久原朝喜さんほか、たくさんの尊敬すべき方々がいました。しかし私にとってこの方は特別です。
嘉手苅さんは1920(大正9)年、のちにコザ市となる中頭郡越来村に生まれ、1999年、79歳でこの世に別れを告げました。
嘉手苅さんは、同じ沖縄の「唄者」といっても私とは道が違います。嘉手苅さんは師匠を持たず、昔からの歌を独学で覚えた人でした。
嘉手苅さんはまた、私ほどには「毛遊び」も経験していないだろうと思います。というのも、私の家も貧しかったが、嘉手苅さんの家も負けず劣らずで、若い頃は親から「イリチリー」(奉公)に出されたり、「ヒオーサー」(日雇い)をしていたこともあったそうです。だから夜中に仲間と一緒に遊んでいるような暇はなかったはずです。
嘉手苅さんは、あちこちの仕事をしながら、自分で見たり聞いたりして歌を覚えていった人でした。先生と呼べる人にかからなかったから、そのせいもあって言葉が聞き取りにくくはありましたが、沖縄の歌の第一人者であることに変わりはありませんでした。
嘉手苅さんの歌は、「琉歌」を知っていれば、実はさほど難解ではありません。
琉歌とは、一般に「8・8・8・6(サンパチロク)」の音数で詠ずる沖縄独特の歌の形式をいいます。本島の歌はこのサンパチロクで作られた歌が多く、さらに、かつての優れた琉歌を応用し新作を作ることも珍しくないために、ある程度、琉歌の決め事を知っていれば嘉手苅さんの歌の言葉の一つ二つを手がかりにして、「アレだな」「次はこうくるな」ということが分かります。
 そこまで理解してしまえば、嘉手苅さんの節回し、言葉の使い方がどれほど絶妙であるかが見えてくるというわけです。だがそういうことも知らずに、ラジオなどで嘉手苅さんの歌をちょっと耳にするだけだったら、何を言っているか分からないはずです。
そこまで理解してしまえば、嘉手苅さんの節回し、言葉の使い方がどれほど絶妙であるかが見えてくるというわけです。だがそういうことも知らずに、ラジオなどで嘉手苅さんの歌をちょっと耳にするだけだったら、何を言っているか分からないはずです。
それは仕方がない。仕方がないが、私に言わせれば嘉手苅林昌という「本当の沖縄の歌」に、あなた方は一生出会えなくなってしまうのです。
嘉手苅さんは、今こううたったかと思えば、次はまるで違うようにうたうことのできる人でした。絶対に型どおりにはうたわなかった。好きなようにうたいながら、しかし「ナークニー」ならちゃんと「ナークニー」の味になっている。こういう所が面白かった。私がうたう時も、自分で書いた工工四すら崩してうたいますが、嘉手苅さんほどではありません。当意即妙の化身のような人でした。もう嘉手苅さんのような人は、生まれ出ないでしょう。
嘉手苅さんは、裏声の名人でもありました。しかしそれは普通にあるような女性的で線の細い裏声ではなく、地声とまるで違わない、太くて大きい声でした。
私たちは若い頃、嘉手苅さんが裏声を使っていることが分かりませんでした。嘉手苅さんの大酒飲みも沖縄の歌の世界ではつとに有名でしたが、連日連夜、我々と同じように飲んでうたっているはずなのに、彼だけはいっこうに声が掠れなかった。
いったい、ナゼなのだ? と思っていたら、裏声でうたっていたことが分かったのです。それほどあの方は地声と裏声を境目なくうたうことができました。どこでどのようにしてこんなことを「発明」したのか……。まったく不思議な人でした。
嘉手苅林昌さんの歌は、教えられて出来るものではありません。特別な人です。私は嘉手苅さんのような唯一無二の唄者と一緒に歩いたことで、この方から私にしかできないことをやるようにと、知らず知らずの内に教えられていたようにも思うのです。
(写真:若き日の嘉手苅林昌と登川誠仁。1959年4月。本書から。)

○奄美のしまうたへの案内 by 豊島澄雄 (武下和平のCD「立神」のライナーノーツ から)
 ■しまうたを生んだ圧政の歴史
■しまうたを生んだ圧政の歴史
どの地方のものであっても、民謡というものがその地方の風土、生活、歴史の産物であることは、いうまでもない。が、とりわけ奄美大島の民謡「しまうた」においては、この地方の置かれた地理的環境、気候、歴史、民俗を抜きにしては、しまうたそのものが理解できないほどの深い結びつきが見られる。
奄美大島は、大島本島を中心として、その東北に横たわる喜界島、西南に沖縄にまで連なる徳之島、沖永良部島、与論島の五島から成る。大島本島は鹿児島から約380km、沖縄から約343kmと本土、沖縄間のほぼ中間に位置する。この地理的関係が、奄美大島の歴史に決定的な意味を持った。
気候は海洋性かつ亜熱帯性で、気温は平均21.6度と高く、雪を見ることはない。年間降雨量3,353ミリ、多雨多湿の島でもある。夏から秋口にかけては台風の通過路となる、いわゆる台風銀座で、年6、7回は猛烈な台風の襲撃を受ける宿命にある。
変化に乏しい温暖な気候の反面で、この台風の災禍、そして大島本島、徳之島における毒蛇ハブの存在が、島人に大きな緊張を強いることになる。
旧藩政時代、奄美諸島は「道の島」と呼ばれた。本来ならば、文化を伝播する「海上の道」という豊かなイメージを与えられるべき言葉だが、近世の奄美の歴史の上では、全く逆に悲惨な意味しか持ち得なかった。すなわち薩摩藩にとっては、琉球侵攻と支配のための道の島々でしかなかったからである。そしてそれは、薩摩藩による苛酷極まる圧政の歴史と重なってくる。
奄美諸島は、13世紀半ば頃から沖縄に琉球王朝が成立していく過程で同王朝に朝貢し、やがて完全に服属することになるが、それ以前はさらにのびやかな時代があったことを島の伝承は語っている。
慶長14年(1609年)、薩摩藩は、道之島を経由して一気に琉球に侵攻した。これが奄美の受難の歴史の幕明けだった。やがて、奄美に特産する砂糖に目をつけた薩摩藩は、ひたすらな収奪に乗り出す。封建制下でも認められる最小限の自由さえ奪われ、ただ砂糖製造のための奴隷の島と化したのである。
このような苛政と圧迫の中から、民衆のうめき声として多くのしまうたが生み出された。
■しまうたの意味
奄美における「しま」という言葉は、必ずしもアイランドを意味しない。ふるさと、郷土、出身地などを指していう場合が多い。従って、「しまうた」という時、奄美大島のうたという総称の意味もあるが、より比重が置かれるのは、自分の村(集落)のうたということである。つまり、あらゆる「しまじま」(村々)に、その「しま」独自の歌がある。これらは、その地勢や人情風俗によって徹妙な違いを見せる。
このように、各「しま」ごとに歌われるが、大きく分けると、奄美本島では笠利節と東節という二つの流れになる。笠利を中心とする奄美本島北部地方は、平野が多くのびやかな地勢を成している。それに見合って、笠利節は平明さと荘重さを特徴とする。一方、南大島地方は山岳が多く地勢は険しい。ここで歌われるのは、節回しの変化にも富んだ情緒てんめんたる歌である。
■しまうたと琉歌の違いと共通性
しまうたは、琉歌の影響のもとに発達してきた。したがって、共通するところも非常に多い。
その最も大きな点は、詞型である。琉歌もしまうたも八八八六調の30音となっている。日本本土の民謡が、たいてい七七七五調、26音を取っているのとは大きく違う。三味線(蛇皮線)を用いるという共通性もある。
こうした共通性の半面、大きく違う点も少なくない。まず違うのは、作詞者の問題である。琉歌は、多くの場合、作詞者の名前がはっきりしている。すなわち琉歌では、支配者たる役人が庶民統治のために作った。勿論、その後庶民へ波及してからは、庶民が作詞者の中心になったことは言うまでもない。
それに対して、しまうたは、すベて無名の庶民の作である。このことは、しまうたが、日本上古の歌垣にも通じる「うた遊び」の中などで即興的に作られることが多かったこととも無関係でないだろう。うた遊びでは、その場の雰囲気に合わせて、掛け合いで歌われるが、よく知られた歌のほかに、その場で作られる歌も少なくなかった。
また、同じように三味線を使うといっても、両者にはかなりの違いがある。琉球三味線に比べて、奄美の三味線は糸が細く、皮も簿いという違いがある。このような三味線は、音が高く澄明で、裏声を多用する奄美のしまうたにはよくマッチするのである。
そして最後に、琉歌としまうたの何よりも大きな違いとして挙げなければならないのは音階である。琉歌としまうたは、ちょっと耳にしただけでも、その違いがすぐわかる。これは琉歌が琉球音階を使っているのに対して、しまうたは律音階を用いているからである。律音階は、日本本土各地の民謡と同じものであり、このため、しまうたは日本民謡の南限であるという指摘もある。
■さまざまな種類のしまうた
しまうたとひとくちにいっても、その内容にはさまざまな種類がある。これを大きく分けると、遊びうたと祝典や教訓のうたということになる。
祝いうたは、さまざまな祭り、行事の際に歌われるものである。その代表的なものが正月歌と年日祝いの歌である。
正月歌は、いうまでもなく新年を迎えるめでたさを寿ぐものである。
年日祝いは、13歳から始まって、25、37、49、61、73、85歳に当たった時に祝うのである。ここで歌われるのは、長寿を願い、一家の繁栄を祈りながら、親子の情愛を歌い上げる。
婚礼歌もまた祝いうたのうちに入る。婚礼には、いろいろと式次第があるが、その式次第ごとに歌われるうたが決まっている。ほかに出産祝いの歌といったものもある。
教訓歌は、文字通り、人生上の教訓を歌にしたものである。もともとは、儒教の影響を強く受けて出来た琉歌の中の教訓歌が始まりだという。そのような琉球教訓歌がそのまま歌われたものもあるが、しまうた独自の教訓歌もある。教育などというものの行きわたらない時代に、この教訓歌は、無二の教育手段であった。
遊びうたは、先にも触れた「うた遊び」で歌われるうたの総称である。これは、恋愛歌が非常に多いのが特色である。しかも、実話や伝説に基づいた、固有の人名の登場する物語歌が多い。ほかに、生活苦や世上の噂話をうたにしたものも多い。
総じてしまうたは、身近な出来事、情感の動きを歌うもので、英雄豪傑や戦争の話は出てこない。また、藩政の圧制下で、露骨に直接苛政を怨むうたもなくはない。が、哀調切々たる響きそのものが、言わず語らずのうちに悲惨な生活を訴えている。そこにもしまうたの特徴の一つがある。
■しまうたの技巧〜唱法と三味線
しまうたの唱法で、最も注目されるのは裏声を多用することである。低い音域の声から高い音域へと次第に歌い移って行くと、ある高さのところで裏声となる。これを極めて自然に行うのがしまうたである。このことによって音域は大きく広がり、表現力がそれだけ増すことになる。この裏声の活用は、琉球民謡では見られず、日本本土の民謡でも例が極めて少ないといわれる。
また、唱法の技法として「尺音」という言葉がある。これは、一小節の中では常に一定の拍子を保ちながら歌っていかなければならないという、歌唱法のルールのことである。例えば、低音域から高音域へ移って行く時、苦しくなって途中で息継ぎをしたり、あるいは、こぶし回しを気取るあまり、間に余計な飾り音を付け加えたりして拍子を崩すことは厳しく否定される。そうした歌い万は「尺音がなっていない」と批判されるのである。「尺音」のないうたしゃは、下手なうたしゃとされる。
三味線の技法にも独特なものがある。琉球三味線では、指先にツメをはめてはじく。これに対して、奄美では、竹の皮を細く薄く削ってバチにする。このバチを使うと、音が高く澄んだ音色となり、澄明なしまうたによく合う。弾き方の特徴としては、上から弾きおろすほかに、下から上にはじき返す「返しバチ」の技法がある。これも琉球三味線では見られない。さらに、弦を押さえる指を使う技法がある。一つは、左手の人さし指で三番線を押し、バチで弾いた後すぐ、左手薬指で同弦を軽く抑えてはじく。これをクックヮ(装飾音)という。これによって旋律に微妙な色どりが添えられる。
また、音色をまろやかにする秘技というべき技巧もある。三番線の開放弦は音が鋭すぎる場合がある。そんな時、二番線の5のツボを薬指で押さえながら、さらにその下のツボを小指で押さえ、弾いた瞬間に小指を放すという技法である。この技法を使える人は少ない。
弾き始めと終わりには、人さし指で弦を二回連続して押すことにより、瞬間的に静的空間を創り出す技巧もある。
琉球から三味線が伝わってはじめて、しまうたは大きな発展を見たわけだが、その奏法は琉球を離れて独自に練り上げられたということができよう。
■タイコうた〜八月踊り
しまうたには、三味線うたと並んで「タイコうた」といわれるものがある。タイコを伴奏とするうたで、その代表が八月踊りである。
八月踊りは、もともと稲のみのりを神々に祈る節句の行事に始まる。これも各しまごとの八月踊りがあるが、今でもしまごとの差異は著しい。三味線うたが、次第に各しまごとの違いを小さくしているのに対し、八月踊りはより強く古型を残したものといえる。
■百年に一人のうたしゃ
奄美大島で“百年に一人しか出ないうたしゃ”と名声を集める武下和平は、昭和8年8月、大島郡瀬戸内町諸数の生まれ。父・源栄氏もうたしゃとして知られ、生まれた時から三味線の音に馴染んで育ったという。
小学校6年の時、父の従兄弟に当たる福島幸義氏が帰郷したのを機会に、しまうたと詩吟の手ほどきを受けた。
昭和34年頃、山田米三氏に認められ、その天分が花開くきっかけとなった名瀬の民謡大会に初参加。
昭和36年に文部省主催の芸術祭民俗芸能大会に出演、昭和39年には名古屋で開催された労音主催・日本民謡大会に出演、その美声は全国のしまうたファンを魅了した。
相方をつとめる早田信子は昭和22年、瀬戸内町古仁屋の生まれ。父・武田正氏は古くからのうたしゃとして、またねぃんごうしゃ(歌の数を多く知っているだけでなく、その由来も熟知した人)として知られた。幼少より父の歌や三味線を聴いて育つ。昭和59年4月、奄美民謡武下流関西同好会に入会。以来、武下和平の相方をつとめながら、しまうたと三味線に励んでいる。

○星人にも通じる超人間的オジィ・登川誠仁
by 藤木勇人 (「沖縄オバァ烈伝番外編 オジィの逆襲」から)
 「登川誠仁」――この名前を聞いただけで、映画『ナビィの恋』のオジィ役での名演技を思い出す人も少なくないだろう。
「登川誠仁」――この名前を聞いただけで、映画『ナビィの恋』のオジィ役での名演技を思い出す人も少なくないだろう。
通称「セーグヮー先生」、御年71歳。沖縄民謡界の大御所であり、熱狂的なファンには「沖縄のジミ・ヘンドリックス」の愛称で親しまれ、沖縄ではその名を知らない人はいない存在である。1999年に封切られた『ナビィの恋』でその存在は全国に広く知れ渡り、「沖縄にはまだこんな逸材が隠れていたのか」と思った人も少なくないはず。
セーグヮー先生は、主人公のナビィオバァ(平良とみ)の年下の旦那・恵達役で実に愛嬌のあるオジィを演じ、最後にはナビィオバァが初恋の人と駆け落ちして置いていかれてしまう恵達オジィの哀愁をみごとに演じきっている。本業ではない役者としてもその存在感を発揮したセーグヮー先生であるが、先生自身のスゴさは、実はこんなものではない。沖縄民謡界の巨匠としての先生のスゴさを聞く機会はほかにもあると思うので、ここでは同じく沖縄の芸能の世界に身を置くものとして、日頃垣間見ているセーグヮー先生の人間的スゴさについて、ちょっとお話ししてみようと思う。
私がセーグヮー先生と初めて会ったのは、かれこれ13、4年前になるだろうか。当時、私は相棒とふたりでお笑いコンビを組み、地元沖縄を拠点に活動していた。そんな私たちがある日、宜野湾市民会館で開催された催しに参加することになった。
その日の催しは沖縄民謡を中心とするもので、私たちは目先を変える色物ということで、沖縄民謡界の大御所と一緒に大舞台に立つことになった。舞台の「取り」は、沖縄漫談界の重鎮・照屋林助先生とセーグヮー先生のコラボレーションである。民謡と漫談――専門分野の違いはあれど、気心の知れたご両人のコラボレーションは、以前から大評判を呼んでいた。私たちが緊張しつつリハーサルを終え、楽屋で休んでいるときに、事件は起こった。
「誰かーっ! セーグヮー先生に酒を飲ましたのはー!!」
舞台監督の怒鳴り声が、楽屋中に響き渡った。舞台監督がいうには、セーグヮー先生は昼間から酒を飲んでいて、かなりいい気分になっていたらしい。リハーサルは終えたのだが、本番は夜だから「それまで家で昼寝してくる」といって帰ってしまったというのである。先生の家は会場から決して近くない。舞台監督がなだめながら「本番まで楽屋でゆっくりしていてほしい」といったようだが、知らない間に姿が消えていたという。
実はセーグヮー先生の酒好きは業界でかなり有名である。過去にもいろいろな事件(?)を起こしているらしく、「仕事のときには先生に酒を飲ましてはいけない」というのが業界内では暗然の了解となっていたらしい。
こうなると当然のことながら、舞台監督の怒りの矛先は酒を飲ませた人間に向けられる。楽屋に怒鳴り込んできた舞台監督に、出演者のひとりがこういった。
「そこにあった急須に酒が入っていたのを見つけて、勝手に飲んでいたよ。あの先生が、こんな近くに酒があったら見つけださないはずはないさー」
真っ赤な顔で興奮している舞台監督に向かって、事情通の出演者がさらにひと言。
「もう戻ってこないはずよー」
彼の発言が、舞台監督の怒りにさらに油をそそいだ。
「誰かーっ! 急須に酒を入れたのはー!!」
それを聞いて、私たちは真っ青になった。実はその犯人は、私たちだったのである。といっても確信犯ではない。酔っ払いのコントをするために必要だった泡盛の三合瓶を買ってきたはいいが、中身を水と入れ替えるために、入っていた泡盛を一時的に急須に移しておいただけなのである。まさかそれをセーグヮー先生が見つけだして、本番前に飲むなどとは想像もしていなかった。
犯人として素直に自首はしたものの、舞台監督の怒りは収まらない。
「本番前に先生を連れ戻せなかったら、責任をとってもらうからっ!!」
そういい捨てて、舞台監督は楽屋から出ていった。とはいわれても、こちらも本番前。会場から出て先生を迎えにいくわけにもいかない。とにかくセーグヮー先生の家に電話をかけまくるが、先生の奥さんもこれまたかなり手強かった。何度電話しても、電話口に出た奥さんが返してくる言葉は、「寝てるから、後で電話してねー」だったり、「私にはわからんよー」だったり……。結局、先生と直接話すこともできないまま、舞台開演時間を迎えてしまったのである。
自分たちの出番が終わり、先生が戻ってきてないかと慌てて楽屋を探しても、先生の姿はない。そしてステージは取りの林助先生とセーグヮー先生の時間を迎えた。
「林助先生、ひとりでお願いします……」
うなだれる舞台監督の言葉に、林助先生は表情ひとつ変えず「わかった」とひと言。こんな事態にも平常心を乱されることのない林助先生の貫禄に驚きつつ、私たちは深々と頭を下げて、ゆっくりとその姿が舞台中央を進んでいくのを袖から見送ったのだった。
と、そのときである。私たちの横をなにかがかすめ通った、いや、そんな気がした。そして舞台上に目をやると、林助先生の横にはその巨体とは対照的な小さな体のセーグヮー先生がチョコンと立っていたのである。そして何事もなかったかのように、息の合った掛け合いが始まり、会場を爆笑と感嘆の渦に巻き込んでいったのだった――。
※ ※
この初の舞台共演以後、私はセーグヮー先生とおつきあいをさせていただくようになり、たびたび家にも足を運ばせていただくようになった。
それはちょうど午前中うちに先生の家の近くにいったときのことだった。何気なく家をのぞいてみると、先生は三線を弾きながら唄っていた。
「イレー、チャーグァーヌメー(入ってお茶でも飲んでいけ)」
先生の言葉に甘えて上がり込み、先生の唄にしばらく耳を傾けていた。すると、私はあることに気がついた。
「先生、ソーミナー(メジロ)が一緒に唄ってますよ」
はじめは偶然かと思ったのが、先生が飼っているメジロがあまりにも絶妙なタイミングで唄に合わせるように鳴きだすので、驚きのあまり唄っている先生に声をかけてしまった。
「いー、唄うよー。わしが唄ったらソーミナーも唄うんだ」
セーグヮー先生は表情も変えずにこういうと、さらに話を続けた。
「昔、犬を飼ってたら、やっぱり一緒に唄ってたさぁ。だけど犬はアーウーアーウーして唄が下手でよ。あれは人の稽古を邪魔するから、よそにあげた。ソーミナーよりも唄がうまいのがおるよ。ホラ、アレ、人の声のマネする鳥がおるでしょ……。そう、九官鳥よー。あれは唄がうまいんだわ。声までそっくりだからねー。だけどよー、あれもわしを怒らして、頭にきたもんだから人にあげた」
なんで九官鳥が先生を怒らせたのか、私が不思議そうな顔をしていると、
「あれはよー、なんの用事もないのにわしとそっくりな声で、勝手に人の奥さんを呼ぶんだからよー。だから頭にきて、あれも人にあげた」
表情も変えず、セーグヮー先生はこういった。
いまでこそ沖縄民謡界の重鎮であるセーグヮー先生だが、唄と三線だけの民謡でここまでの地位を築くのは楽な道のりではなかったようだ。戦前は手がつけられないやんちゃ坊主だった先生が、戦後は得意な三線を生かし、基地でハウスキーパーをしながら英語でも唄をうたっていたという。まだみんなが貧しかった時代である。米軍の気を引いては、軍事物資をいただいていた。当時、「戦果」と呼ばれていたそうした物資の多くは缶詰類だったが、もらったものとはいえ軍事物資なので堂々と持ち帰るわけにはいかない。見つからないよう苦心しながら持ちだした缶詰類は、村の老人たちにも配っていたという。
たいへんな時代ではあったが、このとき身につけた英語が役にたった。三線を弾きながら英語で唄う島唄がセーグヮー先生のレパートリーになったのだ。また、日頃の会話にも絶妙なタイミングで英語が飛び出し、このことがセーグヮー先生のカッコよさにひと役買っている。『ナビィの恋』を見た方なら、恵達オジィが三線を弾きながらアメリカ国歌を演奏するシーンを覚えているのではないだろうか。実はあれも、セーグヮー先生のアドリブなのだ。
「ヤマトはキライ」と公言していたセーグヮー先生だったが、映画の影響もあって増えている内地での公演依頼を受けることがある。私も偶然、東京公演の日に居合わせたことがあって、会場に足を運んだ。
超満員の中で演奏は始まった。観客はセーグヮー先生の演奏に聴き入り、観客席は静まり返っていた。そんな観客を見て、先生は舞台の上から観客に向ってこう声をかけた。
「意味もわからないくせに、なにをそんなに静かに人の唄を聴いているか。私はあんたたちがこの唄の意味がわかっていないということを、ちゃんとわかってるんだ」
セーグヮー先生のこの言葉に、一瞬、会場に緊張が走った。そんな反応に構わず、先生がさらにひと言。
「なぜなら、唄ってるわしが意味がわかってないんだのに」
実におちゃめで愛嬌があって、それでいて飄々としたこの沖縄民謡の天才老人。もしかするとこの御仁、「登川誠仁」ではなく「登川星人」という宇宙でも通用する唄者ではないかと、私はひそかに思っているのである。
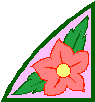

 沖縄を代表する楽器三線にはいろいろな型がある。古い順に言うと、南風原(フェーバラ)型、久葉の骨(クバヌフニ)、久葉春殿(クバシュンドゥン)、真壁(マカビ)型、知念大工(チニンデークー)、与那(ユナー)型、江戸(イドゥ)与那。それぞれ構造に特徴があって、太くて柔らかな音、細くて高い音など、演奏者が自分の声に合う三線、または好みによって選ぶようである。
沖縄を代表する楽器三線にはいろいろな型がある。古い順に言うと、南風原(フェーバラ)型、久葉の骨(クバヌフニ)、久葉春殿(クバシュンドゥン)、真壁(マカビ)型、知念大工(チニンデークー)、与那(ユナー)型、江戸(イドゥ)与那。それぞれ構造に特徴があって、太くて柔らかな音、細くて高い音など、演奏者が自分の声に合う三線、または好みによって選ぶようである。 長年の努力と精進によって、各分野で第一人者となった男達。
長年の努力と精進によって、各分野で第一人者となった男達。 この9月15日(注:2001年)、久々にりんけんバンドのライヴを見た。ホームグラウンド
“カラハーイ”での定例ライヴである。初めてりんけんバンドを見たのが1990年1月のことだから、足かけ12年にわたって彼らの演奏を聴き続けてきたことになる。ライヴに足を運んだ回数も40回近い。その間、色々なことがあったが、彼らのステージの基本的なスタイルは今も昔も変わらない。にもかかわらず、不覚にも涙を流してしまうときがある。9月15日もそう
いうライヴだった。
この9月15日(注:2001年)、久々にりんけんバンドのライヴを見た。ホームグラウンド
“カラハーイ”での定例ライヴである。初めてりんけんバンドを見たのが1990年1月のことだから、足かけ12年にわたって彼らの演奏を聴き続けてきたことになる。ライヴに足を運んだ回数も40回近い。その間、色々なことがあったが、彼らのステージの基本的なスタイルは今も昔も変わらない。にもかかわらず、不覚にも涙を流してしまうときがある。9月15日もそう
いうライヴだった。 今や夏の風物詩になっている沖縄関連の最大イベント「琉球フェスティバル」。
毎年、東京と大阪で行われていて、今年で8回目の開催となる。この催しを首を長くして待っている人達のことを思うと、1回目からプロデュースに関わってきた私としては感無量の思いがあり、苦労を費やしてきた先駆者達の夢が叶い、まさに奇跡に近いイベントの盛り上がりにしみじみ喜びをかみしめている次第だ。この喜びを誰に向かってありがとうと伝えよう。先駆者か、あるいは主催者なのか、いや首を長くして待っている観客か。
今や夏の風物詩になっている沖縄関連の最大イベント「琉球フェスティバル」。
毎年、東京と大阪で行われていて、今年で8回目の開催となる。この催しを首を長くして待っている人達のことを思うと、1回目からプロデュースに関わってきた私としては感無量の思いがあり、苦労を費やしてきた先駆者達の夢が叶い、まさに奇跡に近いイベントの盛り上がりにしみじみ喜びをかみしめている次第だ。この喜びを誰に向かってありがとうと伝えよう。先駆者か、あるいは主催者なのか、いや首を長くして待っている観客か。 ここで嘉手苅林昌さんのことに触れさせてください。
ここで嘉手苅林昌さんのことに触れさせてください。 そこまで理解してしまえば、嘉手苅さんの節回し、言葉の使い方がどれほど絶妙であるかが見えてくるというわけです。だがそういうことも知らずに、ラジオなどで嘉手苅さんの歌をちょっと耳にするだけだったら、何を言っているか分からないはずです。
そこまで理解してしまえば、嘉手苅さんの節回し、言葉の使い方がどれほど絶妙であるかが見えてくるというわけです。だがそういうことも知らずに、ラジオなどで嘉手苅さんの歌をちょっと耳にするだけだったら、何を言っているか分からないはずです。 ■しまうたを生んだ圧政の歴史
■しまうたを生んだ圧政の歴史 「登川誠仁」――この名前を聞いただけで、映画『ナビィの恋』のオジィ役での名演技を思い出す人も少なくないだろう。
「登川誠仁」――この名前を聞いただけで、映画『ナビィの恋』のオジィ役での名演技を思い出す人も少なくないだろう。