
|
読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と |
| 《No.9》 1 変わりようのない歌者―国吉源次 上原直彦 2 「月夜浜」にて 新城和博 3 伝説の宝庫・与論島〜集団移住 籾 芳晴 4 片思い〜沖縄病という病 下川裕治 5 嘉手苅林昌のスパゲッティ 篠原 章 |
6 人間の基本的欲求に、愛で応える場所 林 秀美 |
|
|
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集

読んでよかった、感動した、そのとおりだ、ためになった…と
感じられる名文が、世の中には数多くあります。
そのようなHP管理人の心情を、お立ち寄りいただいた方々に
少しでも理解していただきたいあまり、
このページを設けてみました。
引用文については、出所等を明らかにしつつご迷惑にならない
よう心がけて掲載させていただきますので、
ご理解のほどよろしくお願いします。
《No.9》
1 変わりようのない歌者―国吉源次 上原直彦
2 「月夜浜」にて 新城和博
3 伝説の宝庫・与論島〜集団移住 籾 芳晴
4 片思い〜沖縄病という病 下川裕治
5 嘉手苅林昌のスパゲッティ 篠原 章
6 人間の基本的欲求に、愛で応える場所 林 秀美
7 書籍『カチャーシーどーい』のはしがき
仲宗根幸市
8 生きるための道具 松村 洋
9 綱引き 赤嶺政信
○変わりようのない歌者―国吉源次 by 上原直彦
(国吉源次のCD「伊良部トーガニー」のライナーノーツから)
落語に「長短」という噺がある。江戸っ子持ち前の気が短い男と、江戸っ子ながら、やたら気の長い間のびした男の噺である。
歌者国吉源次と私は「長短」の関係。
平成14年1月29日。午後2時53分。2月1日で42年目に入る琉球放送ラジオ番組「民謡で今日拝なびら」生放送直前のスタジオに国吉源次はのっそり入ってきた。
「あのぉ…うゝん…。電話…あった?」
「何のッ。誰から?」
「んゝん…ビクターから」
「誰にッ」
「あんたに…」
「何でッ」
「んゝん…CDの…」
「誰のッ」
「ワシの…」
「それでッ」
「んゝん…原稿…」
瞬く間に7分が過ぎて3時の時報。オープニングテーマの三絃の音が流れる。国吉源次は
「んゝん…直サンは忙しそうだから うゝん…とにかく…んゝん…よろしく…うゝん…」
と、言い残して姿を消した。
一時間の番組を終えて考えてみた。国吉源次の用件は、こうであろう。
「今度、ビクターからCDを出すことになった。ジャケットに載っける原稿を書いて欲しい。その件について、ビクターの担当者から依頼の電話があったはずだ。よろしく」
30年ばかり付き合っているが、万事がこの調子。今朝食べたメシの話をするのに、夕べ床に入り、そして、見た夢の楽しかったこと。その夢から快く醒めて洗面をし、食卓につくまでを「んゝん…うゝん…」入りで語る。もっとも、歌者仲間はそれを国吉・上原の「阿吽の呼吸」と言っているが…。放送屋稼業40年。時計の秒針に脅迫され続けて身についた<気短>な性格の私には一番こたえる会話シーン。国吉源次とは、そうした男である。
しかし、近頃になって気づいたことがある。
「国吉源次は、この30年余り生き方を変えていない」
このことである。気長な口調も行動も、歌に対する姿勢も熱情も変わっていない。世の中は前後左右に揺れ動き、猛スピードで変化しているが、国吉源次は侵されず毒されず流されず染まらず<生のまま>で生きている。これは驚異だ。
このことを彼流には、こう語るにちがいない。
「うゝん…変わりたい人は…んゝん…変わればいい…ワシは…変わりたくないし…ワシの歌う宮古の歌も変わらない。また…変えたくない。新しくしたい人は…うゝん…新しくすればよい。ワシは、うゝん…変わら…んゝん…ないッ」
この一枚は、そんなCDである。
○「月夜浜」にて 〜アコースティク・パーシャ「月夜浜」発売記念ライブ
by 新城和博 (新城和博著「南風道草通信 道ゆらり」 から)
何度かこのコラムでも紹介した「Acoustic Parsha」アコースティク・パーシャ(関係者は「アコパ」と言うらしいが……業界っぽすぎるよね)のCD「月夜浜」の発売記念ライブが、先日那覇のライブハウスで行われた。心地よい緊張感と心切なくなる陶酔感の波が打ち寄せる、僕にとってはまったくもって最高のライブだった。
「Acoustic Parsha」は、新良幸人の歌・三線に、沖縄No.1ポップス・ロック・デュオ「Acoustic M」(アコM)のギタリスト知名勝、クロスオーバー的に県内の音楽シーンで活躍するジャズ・ベーシスト真境名陽一、そして八重山民謡とぅばらーま大会優勝者で幸人たちとともに「ゆらてぃく組」で活躍した金城弘美がコーラスで参加している。広く知られた八重山民謡のスタンダードを、あくまでも静かにやさしく、それでいて美しく張りつめた緊張感ある演奏で納められたこのアルバムは、ここ数年来新良幸人ファンとして聴いてきた僕としても、最高傑作のアルバムではなかろうかと思う。仕掛け人・プロデューサー上地正昭(バーシャクラブのバンマスです)、してやったりの仕事だ。
三線、アコースティック・ギター、ウッド・ベース。ステージにはテレビ・モニターがおかれ、演奏中ずっと沖縄の島々の上空からの映像が流れる。演奏のコンセプトは、「けして激しく盛り上がらない」。八重山民謡のスローナンバーのみを淡々と演奏していくのだが、最初は大変な緊張感で、ステージ客席ともに息を飲むかのような雰囲気。特に、ギターとベースの二人の緊張はそうとうなもの。幸人も「この二人、楽屋でも酒飲まないで練習しているんだよ、はは」と乾いた笑いを浮かべた。その本人もいつものふりむんな(プチぱからしい)トークもなく、緊張しているかも。でもいい感じだ。
そして徐々にその演奏は地下のライブハウスに馴染んできた。気がつけば「謡(うた)の気配」が充満している。その深く静かな海の底に沈み込む快感。耳で聞くのではなくて身体で味わう旋律の豊かさというのだろうか。僕は久々に「謡に抱かれる」心地よさを思い出した。
同じ唄を聴きながら、涙で目が開けられない人がいる横で、あまりの気持ちよさに目が開けられない人(寝ているんですね。これ、気持ちいいんだよねー)がいて、さらに演奏者の指先を食い入るように見る人がいる。いろんな聴き手がいる中で、ますます演奏のテンションはあがっていく。するとよけいに観客は静かになっていくというのが、このアコパの特徴なのだ。あっ「アコパ」って言ってしまった!
今回のライブには、スペシャル・コーラスとして、あの古謝美佐子さんがステージにたった。「元ネーネーズ」なんて形容詞はいらない、沖縄民謡の枠をグイッと広げ続けている歌い手なのだけど、今回はほんとにコーラス(つまり囃しですね)だけで参加。なんて贅沢。美佐子さんは、CDの八重山民謡のコーラスとはまた違った、まるで沖縄に昔からある弦楽器のような声とフレーズで、新しい「Acoustic Parsha」セッションを作り出した。八重山と沖縄との歌の違いもよく分かって、僕はおもしろかったな。
その日のステージは、CDに納められた全12曲にパーシャ・クラブのオリジナル3曲、そしてアンコールの「月ぬ美しゃ」と、歌と夜が深まる感触が本当に気持ち良かった。アンコール最後の「月夜浜」は10分近く歌ったのではないだろうか。朗々たる歌声がこんなにも切ない……心と体が、泡盛片手にとろけるような、文句なしのエンディングだった。
幸人が歌う八重山民謡には、独特の飛翔感がある。海の底に引き込まれたかと思っていたら、実は島の上空から美しい海と山と村の姿を見つめていたような。
ステージの上でずっと流れていた沖縄の島々の映像を見ていて僕は気づいてしまった。その視点は、僕たち祖先の視線なのだ。島で生まれ、島に生き、島から逝く、その島人が最後に、そして初めて俯瞰できる生まれ島の、その刹那の風景が、歌の響きに隠されている。そんな気がしたのは、泡盛のせいだけじゃないだろう。
……思わず語ってしまったが、実際ライブが終わったあとも、長年幸人を聴き続けているシンカ(仲間うち)で、その感動を話し込んでしまったのだった。そういう年頃なのかねー、僕たちも。
○伝説の宝庫・与論島〜集団移住 by 籾 芳晴
(「奄美島唄ひと紀行」(南海日日新聞社刊) から)
与論島には長い伝統によって生み出された不文律があった。自らも「小さな島」と歌う通り周囲21.9キロの島では生産力に限界があり、一定以上の人口に達したら分村を志して集団移住を図る以外にない。一定の人口とは七千人。
もちろん、現在のように食糧その他の物資の移入が望むだけ手に入り、「飽食の時代」といわれる今日では想像もできないことだが、戦前では農業の生産性も低く、凶作、流行病の追い打ちをかけられると住民は極限状態に追い込まれた。
与論城跡の一角には、二つの集団移住の慰霊碑がひっそりとたたずむ。
最初の長崎県口之津移住は、新天地を求めて人々が“黒いダイヤ”といわれた石炭生産の担い手として酷使された。その惨状は今もって往時を知る人々の語り草となっている。
明治31年、与論は未曽有の台風に見舞われた。名工を呼び、前年に完成したばかりの校舎が倒壊したことからも分かるように、人家、農作物はひとたまりもなかった。沖縄からも救援米を運んだが間に合わず、ソテツの毒による死者が続出した。当時の大島支庁長と与論戸長・上野応介らによって分村計画が進められた。
積極的な反応を示さない島民に対し、三井物産は巧妙な手段で人集めに成功した。当時、与論にはまだヤンチュ(管理人注:家人。薩摩の藩政時代、上納米や砂糖を納めきれない貧しい農家は、その代償として身売りをして豪農などの一種の奴隷となっていた。)たちがいた。
これに目をつけた三井は主家に身代金を支払い、ヤンチュたちは「自由」を求めて移住を決意した。戸長の娘婿・東元良が役場の職を辞してリーダーとなったので、離島苦に悲鳴を上げた人々の参加も多くなった。
故郷を後にした第一陣240人。南島とはいえ、寒気の厳しい明治32年2月のことである。次いで33年に100人、34年に400人が移住した。3回目には上野応介戸長も職を辞し、移住団の先頭に立っている。
希望を持って出発した人々が直面したのは、新天地どころか苦しい長い道程の入り口だった。労働現場は沖仲士。団平船から本船に石炭を積み込む作業。すべて人力によって船腹を満たさなければならない。
24時間労働はザラ。時には3日連続ということもある。与論組はいつも条件の悪い現場を与えられ、食事はおろか賃金さえも現地人と差別された。
最初の約束とは大違いで家もなく、近くの民家の納屋に分宿して激しい労働に従事したが、上野応介、東元良らの抗議で「与論長屋」が造られた。こんな中で、与論の人たちは「誠の島」と歌われるように、「打ち出しょり出しょり……誠打ち出しばぬ恥かきゅんが」と念じながら働いたが、その誠意は裏切られることが多かった。
従順で無知な彼らは会社の思うつぼである。彼らの流した汗は、三井発展の大きなポイントになっている。おまけに、習俗が違うことによる差別。周囲からは「ヨーロン」「ヨーロン」と馬鹿にされる毎日。
こんな中で、帰ろうにも帰れない故郷を思い、唄、三味線に慰めを求めると、それがまた異境人扱いの差別に輪をかける。
口之津移住から10年目に、与論の人たちは三池に移されたが、ここでも同様なばかりか、無理解な新聞社が「三池の与論村・全く鎖国主義の一部落」と題した特集記事を組む始末。
移住集団の不満が爆発したのは大正8年9月だった。余りの差別に怒った人たちが団結して立ち上がった。自分の労働に自信を持った人たちが、ようやく会社という「権威」に立ち向かったのだ。
だが、長い間異郷の地で辛苦をなめつくして、この人たちやその二代目たちは太平洋戦争、三池争議という大きなあらしを経てようやく自分たちの故郷第二の与論村を北九州に築くことができたのだった。
明治初期、全国的に流行したのがラッパ節(演歌)。特に炭鉱労働者、花街などで愛唱された。郷里・与論から北九州を中心とする炭鉱街で苦しい労働に耐えた人々が、我が身を慰めるかのように「ラッパ節」を口ずさむようになった。
さらに、昭和30年代初期、相次いで天災に見舞われた与論の人々は、これらの炭鉱へ出稼ぎに行き、ラッパ系の歌を聞き覚えた。彼らが帰郷して歌う間に島で「与論小唄」として親しまれるようになり、さらに「十九の春」として田端義夫などにレコーディングされるにおよんで二度日の流行期を迎えた。
与論小唄
木の葉みたいな 我が与論 何の楽しみ 無いところ
好きなあなたが あればこそ 小さな与論も 好きとなる
近頃誰かさんの 顔いろは 三月桜の 花のいろ
あれに迷うな 手を出すな あれは誰かさんの 囲い花
十九の春
私があなたにほれたのは ちょうど十九の春でした
今さら離縁と言うならば もとの十九にしておくれ
もとの十九にするならば 庭の枯れ木を見てごらん
括れ木に花が咲いたなら 十九にするのもやすけれど
○片思い〜沖縄病という病 by 下川裕治 (「沖縄ナンクル読本」(講談社文庫)から)
沖縄病を患っている。
病状は相当に重いという自覚もある。
初めて僕がこの病に冒されていることに気がついたのは、4年ほど前のことだった。日曜日の午後、子供たちがなにげなくテレビをつけると三線の音が響いてきたのだ。どうもNHKが、沖縄民謡の番組を放映していたようなのだが、そのあたりははっきりはしない。というのも子供たちは、10秒もしないうちにリモコンを押してバラエティ番組にチャンネルを替えてしまったからだ。だから僕が三線の音を聞いたのは、ほんの数秒ということになる。しかし僕は「反応」してしまった。
正直なところあまりいい感覚ではなかった。風邪のひきはじめに似ていた。なにか背筋に冷たい感触があり、後頭部が少し疼いた。これはまずい、という直感はあったが、特効薬がないこともまた知っていた。
本書にも筆者として加わってもらっている仲村清司氏は、那覇空港に降り立ったとき血が逆流するような感覚に襲われたという。彼は大阪に生まれ育っているが、両親は沖縄から移住したというウチナーンチュ二世である。那覇空港で琴線に触れたのは、おそらく血の問題だったのだろう。
信州に生まれ育った僕のDNAには沖縄はきっと入り込んでいない。だから僕の沖縄病の発症は、仲村氏ほどの激しさはともなわなかった。しかし脳と体に巣くった病魔は、その後も着実に侵攻していったようだった。
次に沖縄病を自覚したのは、それから2、3カ月がすぎた中央線の電車のなかだった。どのあたりを走っていたのかという記憶すらないが、車窓に流れる広告看板のなかに『沖縄』の文字を見つけたのだ。突然、心臓の鼓動が早くなるのがわかった。
「なんの看板だろうか」
と眺めると沖電気のコマーシャルだった。僕は「沖」という文字だけに反応してしまったようだった。
気もそぞろというのは、こういうことをいうのだろうか。その頃も日々、原稿や編集の仕事に追われていた。夢見がちな瞳で、沖縄の空気に憧れるほどの余裕はなかったはずである。しかし心はいつも沖縄の空に飛んでいたのかもしれない。困ったものである。この後は沖を超越して、「お」の文字だけに反応してしまいそうな自分が怖かった。
同じような体験を10年ほど前に味わっていた。その頃の僕は、東南アジアのタイにいれこんでいた。街を歩いていると、「タイプ」とか「タイヤ」という看板にいちいち目が止まってしまった。どれも「タイ」に見えてしまうのである。そのぞくっとする感覚の後にバンコクの街の臭いや音が蘇ってきてしまった。当時こんな人間はタイフリークとかバンコク沈没組と呼ばれていた。結局、僕はその感情を抑えることができず、家族を連れてバンコクに住んでしまうのである。
当時すでに僕は、本を書く仕事のほかに、格安航空券雑誌の編集長も務めていた。そんな立場にいる僕が、
「後はよろしくな」
などという惚けた言葉を残してバンコクに向かってしまったのである。それも1カ月や2カ月という期間ではなく、最低でも半年を予定したバンコク暮らしだった。残された編集部員はあまりの無責任ぶりに、なんと勝手な、と拳に力をこめたのかもしれないが、
「目的はなにもないそうです。ただタイヘの思いを抑えきれなかったようなんです」
と同僚から聞いて、ただ口をあんぐりと開けるだけだったのかもしれない。
惚れっぼい体質というものがあるのだろうか。沖縄を訪ねる人は年間400万人にものぼる。この人たちが皆、沖縄病に罹っていたら、沖縄はとんでもないことになってしまう。やはり感染しやすいタイプというものがある気がしてならない。
僕の周りにも沖縄に行ったことのある人は多い。海外に比べれば気楽に訪ねられるし、航空券もずいぶん安くなってきた。彼らと話をすると、
「沖縄っていいですよね」
とそつのない言葉を選ぶ人がいる。そんなタイプは沖縄病に感染していないといっていい。日本各地や海外の国々と同じレベルでとらえているのだ。とりたてて沖縄は好きとか嫌いといった範疇にはないのだ。
勝手な憶測をいわせてもらえば、沖縄病感染者は無口な人が多い。どこか人づきあいが下手で、初対面の印象はどことなく暗い。東京暮らしの辛さが背中に滲んでいる人もいる。そんな人たちと、東京の沖縄料理屋に入るとする。最初は言葉も少ないのだが、泡盛の酔いも手伝って、しだいに沖縄談義が盛りあがってくると、彼らの瞳に明かりが灯ってくる。そして、やおら口を開いたかとおもうと、
「ポークというのは、厚さが5ミリに切らないとだめだと思うんです。それ以下でも、それ以上でもいけない。最初は強火でちょっと焦げ目がつくぐらいまで火を通し、そのあと火を弱めて……ですね」
といきなり各論に入ってくるのだ。こういうタイプは確実に沖縄病に罹っていると思っていい。訊くと沖縄を訪ねた回数は軽く10回は超え、「移住」という文字が喉に止まった魚の骨のようにひっかかっている。
だいたいポークなどと聞いても、一般の本土の人たちにはまったくわからない。実は豚の屑肉からつくったポークランチョンミートという缶詰だとわかれば、天を仰ぎたくなるはずである。そんなジャンクフードにどうしてそんなに入れ込むの……と。
沖縄料理屋の沖縄談義を、にんまりとした顔つきで聞きながら、一切口を開かないタイプもかなり危うい。相当の重症であることが珍しくない。皆の話をメモをとらんばかりの勢いで、脳細胞に記憶させていることが多いのだ。
そんなひとりと偶然、那覇の居酒屋で遭遇したことがある。以前、東京の料理屋の席で一緒になったらしいのだが、互いに言葉を交わすこともなかった。その場は那覇にある一軒のとんでもなく安い居酒屋の話で盛りあがったのだが、お互いにその店の名前をしっかりと覚えていて、「次に行ったときに……」と心に誓っていたのだった。
本土の暮らしにどこかうそ寒さを覚えてしまった人たちにとって、沖縄という土地は身がとろけてしまいそうなほど優しく映る。ウチナーンチュはお節介といわれてもしかたないほど世話好きである。やることはどこかいい加減で詰めが甘いというのに、そんなことを棚にあげて人の話に聞き入ってくれる。
沖縄では連日のように飲み会がある。しかしそれが決まるのが、当日の夕方であることが珍しくない。一本の携帯電話でのやりとりが発展して、いつのまにか飲み会が決まっていくのだ。僕のところにも7時頃に連絡が入って、指定された居酒屋に向かうと、すでに20人ぐらいが集まっていて、一瞬、そんなにきちんとした会だったのかと恐縮することがよくある。
輪に加わって話を訊いてみると、
「夕方、あいつから電話があったさー」
てな具合で、ここに集まっている人も半数以上が初対面だとわかり、なんだか肩のカがすーっと抜けていく。集合時間も「今日の夜」といういかにも沖縄らしい決め方だ。そんなことを聞いているうちに、また初対面の人が現れて、自己紹介が始まるのである。
東京で20人を超える飲み会をすることは大変なことである。それぞれの都合を調整し、場所を決め、予算を打ち合わせ……と面倒くさいことが短くても一週間は続く。ところが沖縄では、その日の夕方の一本の電話で飲み会が決まってしまうのだ。
「皆が出席する」「定刻に始める」。こんな決めごとをとっ払ってしまえば……と目からウロコが落ちるのである。
何回となくそんな飲み会に顔を出すと、やはりそこは沖縄であって、その先がスコーンと抜けていることがわかってくる。シビアーな人間関係を避けようとするのは、島という狭い共同体の処世術でもある。しかし、沖縄にぞっこんの患者には、あっという間に居酒屋に集まるウチナーンチュに真綿にくるまれたような安堵を見いだすのである。
「こんな世界があったんだ……」
本土の暮らしのなかにぽっかりと開いた灰暗い空洞に、そんな沖縄の風が吹き込んでくる。すると、いてもたってもいられなくなり、突然、受話器をとったかと思うと、沖縄行きの飛行機の予約に走ったりするのである。
それでも金はあまりないから、できるだけ安い便を探してもらう。僕の場合は、直前でも安い日本トランスオーシャンの最終便になることが多い。いや、あの便を僕はかなり気に入っているのだ。いったん予約が入ると、なぜだか急に体が軽くなる。「あさっての夜は沖縄だ」と思うと、嫌なことも忘れられる。
日本トランスオーシャンの那覇行き最終便の出発時刻は夜の8時20分である。夕暮れどきの混み合った電車に揺られて羽田空港に向かう。疲れた面持ちのサラリーマンを眺めながら、「いや、僕はこれから沖縄なの。暖かくて甘い風が流れる島に行っちゃうわけ」などとひとり呟きながら優越感に浸るわけだ。
最終便の搭乗口は、いつも羽田空港の80番か81番である。ここはバス便専用の搭乗口なのだ。すでに売店も閉まり、ロボット式の掃除機が動きまわっている。那覇空港の到着時刻が11時をまわってしまう便を利用する団体観光客など皆無で、待合室に座っているのは、仕事や用事で東京にやってきたウチナーンチュがほとんどである。沖縄方言が飛び交い、そこはもう沖縄なのである。
バスは羽田空港のなかを延々と走る。ボーイング737型という中型機が停まっているのは、なぜかいつも空港の端である。
ふーっと溜め息をつきながら席に座る。今日も一日忙しかった……。
それから約3時間――。
僕は那覇空港前のタクシー乗り場の列に並んでいる。潮風と南の果物の芳香が混ざった甘い匂いが鼻孔をくすぐる。暖かい風が心地よく、東京で着ていたセーターを脱ぐ。
沖縄に来た。
一カ月前にもここにいたというのに、また来てしまった。
たとえ詰めが甘くても、この島の人々は温かい笑みで迎えてくれる。カーテンがゆっくりと揺れる風がある。
沖縄病とは「逃避病」であることはわかっている。しかし逃げ場所を確保しないと、心の均衡を保てない男がここにいる。辛くなってきたら、「沖縄へ行けばいい」とどこかで思っている節がどこかにある。それが沖縄への片思いであることもわかっているのだが、その思いを断ち切ることはできそうもない。
○嘉手苅林昌のスパゲッティ by 篠原 章 (「沖縄ナンクル読本」(講談社文庫)から)
この食堂(コザのデイゴホテルの食堂で)では実にさまざまな人たちに出会った。沖縄で活躍する芸人たち、沖縄民謡や沖縄古典音楽の大物たち、沖縄ポップのミュージシャンたち。コザは沖縄固有の音楽・芸能の中心地でもある。いちばん深い印象が残っているのは、民謡の大御所・嘉手苅林昌だ。
三年ほど前の春、いつものように遅い朝食を取っていると、背筋をしゃんと伸ばした痩身の老人が入ってきた。白いワイシャツのいちばんうえのボタンをはずし、グレーのズボンをはいている。隣り合ったテーブルにおもむろに腰掛け、背筋を伸ばしたまま「スパゲッティ」と一言。しわがれ声が渋い。最初は誰かわからなかったが、老人とスパゲッティという取り合わせが気になったので、じっくりと横顔を見ると、なんと嘉手苅林昌ではないか。登川誠仁や照屋林助などとともに戦後の沖縄民謡を支えてきた男である。即興の歌詞を交えてブルースマンのように歌い、魔術のような三線を弾く沖縄最高の唄者(うたさー)である。ステージは何回か見たことはあったが、こんなに近くで実物を見るのは初めてだった。
林昌はほとんど微動だにせず、遠くを見つめながらスパゲッティを待つ。林昌のスパゲッティ好きは有名である。りんけんバンドの照屋林賢は若い頃、林昌と同じ屋根の下に住んでいたという。林昌は、暇さえあればスパゲッティを作って、ときには林賢にも勧めたらしい。民謡大家の林昌が、フライパンでスパゲッティを手際よく調理している姿を想像すると、なんだか可笑しい。
注文はたんに「スパゲッティ」だったが、運ばれてきたのはケチャップの色も鮮やかなスパゲッティ・ナポリタンだった。デイゴホテルは、林昌の好みを知っている。林昌はナポリタンを見て、一瞬、嬉しそうな笑みを浮かべた。
一本のフォークを上手に操りながら、林昌はひたすら食べることに集中する。フォークにスパゲッティを巻きつけては口に運び、巻きつけては口に運びという作業を間断なく繰り返す。三線を持たせれば第一級の骨張った手の甲の動きが美しい。背節は相変わらずしゃんと伸びたままだ。食べ終わるまで約十分、最後の一口を口に運ぶと、紙ナプキンでさっと唇を拭い、「おねえさん、お勘定」。テーブルで座ったまま長財布を出して代金を支払うと、ぼくのテーブルの脇をすり抜けるように食堂を出ていく。林昌のからだがあたりの空気をかき混ぜて、わずかに潮風が吹いたように感じた。
「放浪の唄者」とか「風流の唄者」と呼ばれていた林昌は、喩えていえば「風」なのだ。その林昌もすでに亡き人となってしまった。
○人間の基本的欲求に、愛で応える場所
by 林 秀美 (「沖縄ナンクル読本」(講談社文庫)から)
沖縄で五百円玉ひとつで遊べるところはどーこだ?
カラオケ、パチスロ、ゲーセン……手っ取り早い遊びは数々あろうが、私は迷わず「大衆食堂!!」と答えたい。遊ぶと言っても、別にミニスカートのおねえさんが食事を運んでくれるわけではないが(……ンなところで遊ばないって)、人間の基本的欲求を実に正しく満たしつつ、この島の文化を学び、さらには人々の愛に触れる場所として沖縄大衆食堂は存在している。なにやらオオゲサな言葉を並べてしまったけれど、ひらたく言うと私は大衆食堂なる場所が大好きなのだ。
沖縄そばからステーキまで、一軒の店でなんでもアリの大衆食堂はとっくに死語かと思っていたが、この島でそれを探すのはそれほどムズカシイことではない。
タクシーの運転手さんが、やや疲れ気味の顔で「ゴーヤーチャンプルー」を頼んでいる隣で肉体労働系のニーニーが大盛りの「沖縄そば」を豪快にすすり、その背後で元気なオバァの三人連れが揚げ物だらけのランチをパクパク食べる場所。もちろんここにはネクタイ姿のオッサンやハラヘッタ中高生だってやってくる。
東京で仕事をしていた頃、日常生活の中にこんな場所はなかった。ラーメンが食べたい人とカレーを食べたい人が一緒にランチとなれば、どちらかが譲らなくてはならないし、サラリーマンとOLが同居する店はあっても、そこにオバァやガキンチョが来ることはなかった。なんでもアリの場所もなくはないけど、それは全国統一規格のツルリとしたファミリーレストランだったりするから、ちょっと悲しくなってしまうのだ。
これを沖縄的チャンプルー文化と言っていいのかどうかは知らないけれど、メニューにも客層にも、統一感というのがまるで感じられない。そこにあるのは『おいしいものを、安く、ニコニコ、モリモリ食べたい。食べさせたい』という客と店の双方にある、きわめて素朴にして正しい感情だけだ。私が沖縄の大衆食堂に通う最大の理由は、そこにあるのだと思う。たぶん。
そして私は五百円玉ひとつを握りしめてテクテク歩く。壁にベタベタ貼られた短冊メニューの方言に頭を悩ませ、まいったかと言わんばかりの大盛りごはんをペろりと平らげたりする。ドンブリメシにフライドチキン(!!)と野菜炒めがのっかった「親子丼」が出てきても、お風呂のアカスリとしか思っていなかったヘチマを食べろと言われても怒らない。ここではそういうモンかとニコニコ食べるだけだ。長崎チャンポンのつもりで頼んだ「チャンポン」が、予想とあまりにかけ離れた姿で出てきたときは、さすがにポカンとしたけれど。皿のごはんに野菜炒めがのったモノをここではチャンポンと呼ぶのかぁ……と納得するしかないワケだ。
そのチャンポンを沖縄でもトップクラスのドカ盛りの食堂に食べに行ったときのこと。「はいよー、おまたせー」とおばちゃんから渡された皿は、手にズッシリと重い。ドッジボールほどの直径の皿から溢れそうになりながら天高くそびえる野菜炒めの山。さすがの大盛り好きの私もちょっとコシが退けた。食べても食べても、ちっとも減らないのだ。
昭和ひとケタ生まれの親の元で育ち「ごはんは残さず食べなさい」と言われ続けてオトナになった私は、食べ残すことに人並み以上の罪悪感を覚えてしまう。だから残すことはできないのだ。せっせと食べる。食べ続ける。でもおばちゃん、ゴメン。もおダメだぁ〜。
残した分を持ち帰り用に詰めてもらいながら、おばちゃんに訊いてみた。
「なんで、こうまで大盛りにするの?」
……口には出さぬが、こんなんで採算はとれるのかという余計な心配もある。
「お金がない人でも、ここに来たらお腹いっぱいになれるさーねー」
実に屈託のない笑顔を浮かべておばちゃんは、ふくふくとこう言った。
確かに量からみるとカンペキに二食分はあるのに、たったの五百円という破格値だ。コロンと五百円玉一個を手渡して、私はまた来ようと思った。沖縄の大衆食堂は、おばちゃんの愛がテンコ盛りで出てくる店だったのだ。
○書籍『カチャーシーどーい』(ボーダーインク)のはしがき by 仲宗根幸市
沖縄・奄美の人たちは、古来自らの思いをことばより歌や踊りで表現するのがうまかった。沖縄の人たちはカチャーシーのリズムを聴くとじっとしておれず、だれはばかることなく飛び出て乱舞する。見知らぬ人同士でも、踊りが始まれば皆きょうだいの気分になり、連帯感が湧くから不思議である。
黒潮の帯にさんざめくカチャーシーは、手をこねりガマク(腰)をこころもち入れ、上体を安定させて波に揺れているように踊る。この波に揺れるリズムに合わせたカチャーシーは、南島の人たちの原初的動作であり、沖縄芸能の原点である。
明るくにぎやかなカチャーシーは、ハレの祭りや日常生活でしょっちゅう出合う沖縄を代表するぞめきの芸能である。カチャーシーはエイサーの雄飛によって、日本本土はもとより海外でも熱い視線が注がれ、わが国で四国徳島の阿波踊りと双璧をなすぞめきの芸能といってよい。
かつて、私は沖縄本島北部のある村で感動的場面に遭遇したことがある。若いころ、他村へ嫁いだ明治生まれの女性が久しぶりにふるさとへ帰った。すると、道路でばったり幼友だちに出合ったのである。くだんの二人の女性は、その瞬間他人の目をはばかることなくサッサッサッサと、およそ30秒ほど踊り出した。二人は完全に陶酔状態にあった。「こういう世界もあったのか」と、私はこの劇的場面を目のあたりにして、圧倒されてしまったのである。二人にとって、カチャーシーは喜びの最高表現であり、挨拶ことばは二の次なのだ。ほとばしる感情の高揚こそ、歌や踊りの原点であることを強く実感した。
カチャーシーは、まれに一対一の場合が見られるが、集団の場合が断然多い。カチャーシーは沖縄の人たちの喜びの最高表現であり、魂の叫びなのである。
この情熱的踊りは、いったい何なのであろうか。私は長年沖縄のぞめきの芸能に関心を寄せてきた。カチャーシーはウチナーンチュ(沖縄の人たち)の生活にあまりに深く浸透しているため、県民にとって当たり前になり、ことさら考えることすらしない状態にある。したがって、沖縄のぞめきの芸能はこれまで体系的に究明されることはまったくといっていいほどなかった。
カチャーシーのテーマは深遠である。非力な私の手に負える世界ではない。だが一つの救いは、徳島県の民謡芸能研究家で、先年他界した桧瑛司氏と私は、二十年前から黒潮文化圏のぞめきの芸能を追究してきた経緯がある。黒潮の流れに花咲くぞめきの芸能を、桧氏は「乱舞の紐」、私は「乱舞の帯」と称してきた。
そんなことから、茫洋としているカチャーシーの生態を芸能の発生から展開、社会的機能含め、その全体像を描きたいと私は考えるに至った。カチャーシーというぞめきの源泉、流れ、ざわめき、芸態の探索を通して、南島の芸能史や精神史のあらたな風景が見えるかも知れないからである。
本書はカチャーシーの流れと乱舞の広がりを、琉球列島だけでなく日本列島までも視野に入れ、系譜の解明を試みることにした。そこで見えてきたのは、カチャーシーに込められている庶民の熱い思いとさんざめく黒潮の神秘な作用であった。さらに万人を虜にする、すさまじいエネルギーのカチャーシー(そのもとになるサーサーモーイ)は、沖縄芸能の原点であることをあらためて確認出来たことである。
それでは、ウチナーンチュの祈りや喜び、夢をふくらます乱舞の華・カチャーシーの扉を開けよう。
○生きるための道具 by 松村 洋 (「唄に聴く沖縄」(白水社)から)
沖縄唄文化の変化を追ってきた本書の最後に、宮本常一が女性の暮らしについて書いた文章の一節を記しておこう。宮本は、自給中心の昔の生活のなかで、とくに女性たちの負担が大きかったことを指摘した後で、こう述べている。
……そうした仕事に追いまくられながらも昔の人たちはどことなくのどかであり、かつ明るさがあったと思います。けっして昔の生活がいまよりゆたかであったというのではありませんが、どこかのどかなものがありました。それは何故だったのでしょうか。それにはその生活のなかに二つの重要な生活を明るくする要素を持っていました。一つは時間にとらわれないこと、いま一つは労作業のなかに歌を持っていたことだと思うのです。
沖縄には「ウチナータイム」という言い方がある。沖縄の時間。約束の時間になっても来るべき人が来ない。ことが始まらない。でも、そんなこと、たいして気にしない。そういうゆったりした時間感覚のことである。こういうのんびりした時間の流れは、沖縄にかぎらず、まだ世界中にある。
だが、時は金なり。時間は資本主義の重要な要素である。資本主義システムは、最大限の利潤を上げるために時間の効率的な利用を求める。「ムダな時間」を追放しようとする。当然、ウチナータイムは、資本主義的観点からは否定されるべきものである。
現代の私たちの感覚は、ぼーっと待たされ続けることに、すでに耐えられなくなっている。だから、コンサートは、だいたい予定された時刻に始まる。ふつうは、遅れても、せいぜい10分か15分である。30分遅れたら、絶対に怒りだす客がいる。私自身は、主としてタイで、午後5時に始まるはずのライブが午後8時に始まったなどという体験を重ねているので、開演が1時間や2時間遅れたところで、べつにどうということもない。だが、日本では、2時間遅れの開演などというのは許されない。さすがに沖縄でも、もうダメだろう。
さらに、宮本は唄に注目している。かつて、日々の暮らしは労作業の連続であった。だが、唄はハードな暮らしを明るくしてくれた。生涯を通じて日本中を歩きまわり、無名の人びとに話をきき、たんねんに記録した宮本は、生活のなかにある唄のカに気づいていた。
現在、私たちは、たくさんの音楽作品をCDなどで手軽に聴くことができる。元気な唄、愉快な唄、心に沁みる唄が収められているアルバムに出会えれば、幸せな気分になれる。また、とくに大都市では、じつにたくさんのコンサート、ライブ演奏が毎日行なわれている。充実したコンサートも、もちろん楽しいものである。だが、宮本が言う「昔の人たち」は、いつでも唄が聴ける便利な装置など持っていなかった。好きなミュージシャンのコンサートに行って楽しむという体験もなかった。それでも生活のなかに唄をもち、そのことが生活を明るくしていた。
暮らしのなかに唄をもつというのは、どういうことなのか。突き詰めて言えば、唄は、人間が日々幸せに生きていくためにあった。唄は、生活に添えられた、たんなる飾りではなく、人間が幸せに生きていくために絶対に必要な道具だった。生きるための道具としての唄は、自由自在に使いこなされた。沖縄にかぎらず、世界中でそうだった。
だが、私たちは現在、唄よりも科学技術が実現した便利な機械やお金で買えるサービスに頼って生きるようになった。日常生活のなかで、唄の役割が小さくなったことは否定できない。それでもやっばり唄が生きるための道具であるとすれば、これから私たちは、暮らしのなかで唄をどのような場所に置き、どのように使っていけるだろうか。唄はどのような役割を果たし、どんなカを発揮するだろうか。
人間は唄という文化を創った。唄を使って生きてきた。唄のカはたいしたものだった。これから唄文化がどう変わっていくにしても、唄のカは、たいしたものであり続けてほしい。それが、唄好きの願いである。
私たちが唄で生きる。そのことによって、唄は、生きる。
○綱引き by 赤嶺政信 (「シマの見る夢―おきなわ民俗学散歩」(ボーダーインク刊)から)
今年もまた綱引きの季節が巡ってきた。明治中期の翁長村(現西原町)の農村生活を活写した比嘉春潮氏の名作「翁長旧事談」の中に、綱引きについての次の一節があって、沖縄の綱引きの民俗を理解するのに参考になる。
『大豆や稲が花を持ち始めてから熟するまで、農村では「鳴物は法度」といって、皷や銅鑼の如きは勿論のこと伐木や石切りの如き激しい物音は「法度」であり、三味線さえ遠慮された。「作物を驚かしてはいけない」というのであった。これを犯すと神の「あらび」(怒り)で実りがわるいとされた。この静寂を最初に破るのは稲干場における夜番の吹く法螺貝であり、引続いてはこの綱引き前の幾晩かの少女たちの皷の音であった。夏の夜に響くこのひさしぶりの「物音」は部落の人々に一種の深い感興を与えるものであった。』
法度はハットゥと読み禁止の意味である。稲が実る季節には「鳴物法度」以外にもいくつものタブーが存したことは、八重山西表島の『慶来慶田城由来記』の中に「3月15日から5月に稲が熟して刈り始め、ほうれ(プーリィ。豊年祭)をする間は、女は月のさわりを持っているので、『持なこつ』『磯下り』『海よくせ』をしてはいけない。若葉が萌え立つ時分はよくよく慎み、自然の法則を恐れること(4月15日頃から豊年祭までは男女とも磯下り禁止)」という記事があることによって窺い知ることができる(『石垣市史叢書1』)。『琉球国由来記』巻一の「山留」の項にも、4月1日から5月1日までは山留(ヤマドゥミ)と称して諸種のタブーがあるが、これは作物に害をもたらす大風が吹くことを恐れての「斎戒」であると記している。
私見によれば、綱引きの魅力のひとつは銅鑼や法螺貝、ケレレンケットー(鉦鼓)の音に代表されるその喧噪さにあるが、その喧噪は、自然の恵みとしての収穫を得るためみずからに強いた抑制を打ち破るものとしてあったわけである。「作物を驚かしてはいけない」ということからすれば、その抑制は、稲に宿るあるいは稲に実りをもたらすモノについての信仰があって、それに対する心配りということになろうか。「自然の法則を恐れる」(原文は「天とう恐入」)とあるが、日々が喧噪の中にある現代のわれわれの生活が、自然(天とう)に対して「恐入」態度から遠く隔たった場所に来てしまっていることを痛感させられる。
さて、じつは僕は、綱引きに関してはインフォーマントとしての資格があって、かつて自分の綱引き体験を次のように記したことがある。
「シマの人たちと大汗にまみれながら力の限り綱を引いていると、このシマで生まれ育った自分のシマンチュとしてのアイデンティティーを確認できる。夜の闇、藁の感触、鳴り響く銅鑼とブラ(法螺貝)の音、テービー(松明)、乱闘、勝利を祝う婦人たちの綱引き歌とチジンの音、それらのものが現実とは違う別の世界ヘシマの人々を誘(いざな)うかのようである。綱を引き終わり消耗しきった体を休めながら口にふくむ泡盛は格別で、綱談義に花を咲かせながらの男たちの夢の宴は延々と続く。たかが綱引き、されど綱引き」(「南風原町喜屋武の綱引き」)。
綱引きの当事者である僕は、先の比嘉春潮氏の綱引きの描写を深い共感をもって読むことができる。もちろん比嘉氏の生きた時代と違い、現代はもはや稲作もなければ鳴物法度も存在しないが、綱引きの喧噪が現代の綱ムシたちを魅了しているのは昔と変わらないはずだ。僕のムラでは、8月十五夜の村アシビは昔から盛んで、部落内の地区対抗の運動会が大いに盛り上がった時期もあるが、同じくシマの人が楽しく集う行事でも、綱引きの興奮は趣を異にして格別なものがあるのである。
宗教学者の中沢新一氏は沖縄の綱引きについて、先の比嘉氏の報告をもとに、同じ豊年祭でも、御嶽における神人たちによる儀礼(言語による祈り)と喧噪(音、リズム、かけ声)を旨とする綱引きの間にある断層について注意を喚起しつつ、「そのような仕掛けを用いて人々がめざしているのは、象徴的秩序を批判することを通して、言語のように媒介によって人々を結びつけるのではなく、膚を触れ合わせたり同じリズムや同じ筋肉の痙攣を分つ者の間に、一つの直接的な『共生空間』を形成することにあるのではないだろうか」と指摘している。詳細は割愛せざるをえないが、中沢氏によれば、夜の眠りの中で個人が夢を見るように、共同体は祭りの中で夢を見るのだという(「夢の作業と共同体の祭り」)。
ヒヤーユイ(綱を担ぎあげる時のかけ声)、ハーイヤ(イチュイ=威勢を示すかけ声)・グァーングァーン(銅鑼の音)・ハーイヤ、ヤッチャイ(若者たちの体ごとのぶつかりあい)、ナドーイ・サーイ(引き始めの合図の発声)、サーイ(引く時のかけ声)・グァーン(銅鑼の音)・サーイ・グァーン、ユインドー(寄るぞー、勝利を確信する叫び)、<東立ち雲や世果報しぬくゆい/遊びしぬくゆる二十歳女童>(女性たちの綱引き歌)。
みずからに「法度」を課すこともなくハーダーリーになりがちなわが身のありさまを反省しつつ、シマの綱引きの熱狂(シマの見る夢)を思い描いてみる。
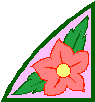
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜大きな環−心に刻んでおきたい名文集