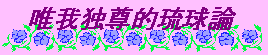 その2 2001.01.31
その2 2001.01.31
激論のさなかに見えたオアシス
|
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜唯我独尊的琉球論
その2 2001.01.31
激論のさなかに見えたオアシス
仕事でまたもや上司と対立してしまった。
新年度に行う事業の企画について、直属の上司とどうもことごとく意見が合わないのである。
たとえば、企画全体のコンセプトについて相談すると、彼はそのうちの手法の一部分について納得がいかないらしく、話題はそのことばかりに向いてしまってなかなか本論に入ることができなかった。
また、人・モノ・カネといった一定の制約の中で最大限の効果を出そうと考えたプランが、ある種の理想論でもってさまざまなオプションが付加されて実現するのが困難なものとなり、そこから先は担当者の熱意や工夫でなんとかするようにとのわけのわからない結論になったりしたこともあった。
このようなことがよくあって職場内でもちょっと名の知れたこの上司の欠点をまとめて言ってしまうと、まず第一に部下の話を聴こうとしないことであり、第二に、上司の性格や考え方について熟達するあまり、行政行為の受け手である「国民、県民、市民」といった立場で考えることができない…ということになろうか。
彼に決裁権があるわけではないので、まあテキトーにあしらっておけばよいようなものなのだが、自分もアホというか、そこで論陣を張ってしまうものだからいつも口論となり、結論のない後味の悪い結果を迎えてしまうということになってしまうのだ。
彼にとっては言うことをきかない部下がいてさぞかし困っていることと思うが、こちらとしても、上層部の意向や自分の立場ばかりを気にし、「判断」を避けて前例踏襲を続けているその姿勢には、そう簡単に従うことはできないのである。
そんな状態で、職場ではいつも悶々としているワタシだが、今回は、まわりの職員が黙り込んで聞き入ってしまう(だろう)ほどの大激論になってしまった。
あまりの理不尽さのために、この人と話していてもラチがあかないと思い、こちらとしては議論を終結させたい…というか、単にやめたくなったのだが、彼がいつまでも内容に乏しい持論だけを早口かつ抑揚のない口調でしゃべり続けるものだから、頭に血が上ってつい大声で反論してしまったのだった。
言わば「切れた」状態になってしまったわけだが、その時…。
自分の中で「あれっ?」という不思議な感覚が生まれた。
このようなことは初めてのことなのだが、なんと、笑うなかれ、すっかりすさんでしまった現実の世界とは裏腹に、心の中には、南国の風景の中で沖縄民謡と波の音に身をたゆたわせている自分がいたのだった。
切れると同時に、仕事とはいえなぜ人間関係を損ねてまで議論をしなければならないのか、ということを考えていたのだと思う。
こと職務という面から考えれば、組織内の上司より納税者のことを考えるべきことはまごうことのない正しい判断だと思うし、上司というものはそのために説得して上手に使っていくものだと常に自分に言い聞かせ、これまでそのようにしてやってきた。
かなりキザな言い方をすれば、まず自分が高い目標や理想を持つことが第一歩であり、それに向かって進もうとする自分にさえウソをつかなければ、前例などなくても、上司の理解などなくても、やりたいようにやっていけばいいのだという自負のようなものがあった。
それが自分の役目なのだと考えていたし、自己実現の方法の一つとしてやりがいをも感じていた。
しかし、このようなケンカ腰の議論も、その先に見えるものが何もない、暖簾に腕押しのような不毛のものなのだと気づいたとき、「いったいオレは何をやっているんだ!?」ということに思い当たったのだろう。
心象として出てきたのは、沖縄本島の西海岸あたりの海だろうか。海面に当たる日差しが照り返してきはじめたくらいの午後の時間帯で、リーフが切れるあたりの沖には白波が立っている。そこで大工テッチー(だいくてつひろ)がTシャツを着て立ったまま三線をかかえて唄っている。どこまでも濃い眉、二枚貝の貝殻を連想させる大きな二重まぶた、宇宙のような広がりを感じさせる鼻の穴。
うーむ…見事。ああ、沖縄だなぁ。彼らはすてきだなあ。国民のために…なんていう大げさで実体のないことなど、そんな発想自体持たないのだろうな…当たり前だよなぁ。
鼻の穴…。おっ、今度は安里勇(あさといさむ)の登場だ!日焼けした顔。黄土色の絣の着流しに裸足がよく似合うぞ、いいぞいいぞ…。毎日の糧としての漁。喰える分だけの魚を自然から恵んでもらう日々。目の前にいる精彩のない顔をした男性はさっきから何をしゃべり続けているのだろう。
安里さんの住む八重山の、そう、この間訪れた鳩間島の人たちなら、「そう気負わないでぇ…。しばらく島でのーんびりしていけばいいさぁ」などと言って、こんな論争などには取り合わないのだろうな。
沖縄には「癒し」の場なり精神性があるというが、こういうことなのかもしれない。
とかく「北」の人間は、一旦はまりこむと盲目的にのめりこんでしまうが、「南」はそうじゃないよ、ということのたとえとして、沖縄の三線のチントゥンテンという弾き方と、津軽三味線のテケテンテケテンテケテケテケテン…という弾き方の好対照が用いられたりする。
言いえて妙だよね。津軽三味線の奏者は苦痛を感じているような顔で真剣そのものだが、南の島の家々から聞こえてくる三線の音色はなんとゆったりとしたものか。
また、「個」よりも、家族や近親者などを大切にする風土もあって、親元を離れてぎすぎすした都会の生活を送っている人々などにはほっとするものがあるよなぁ…。そしてまた、見ず知らずの旅人にもとてもやさしい、人なつっこい人々がそこには住んでいる。まず、「人間」というものを疑っていない。すばらしいことではないか。
もうすっかり議論の内容から離れて、まったく別のことを考えているワタシ。怒りも急速におさまってしまい、目の前で持論を述べている上司が滑稽で、その熱血ぶりがいとおしくさえ感じてしまっている自分に気がつく。
その持論展開が長引くのに合わせ、妄想はまだまだ続く。
もうだいぶ前のことになってしまったが、1999年11月に解散した初代ネーネーズのメンバーたちは今、何をしているのだろうか。
その4人のメンバーはそれぞれ個性があっておもしろかったが、私はそのうち、いつもは向かって左から2番目の位置で歌っていた比屋根幸乃(ひやねゆきの)が特に好きだった。
いちばん背が低くて、ステージ衣裳を着るとかつてNHKの「おかあさんといっしょ」で活躍していたぬいぐるみのピッコロに似てしまうのだけれど(スンマセン…)、ステージでは彼女がMCを担当させられていたようで、少々無理をしながらも元気にその任務を遂行している姿に私は図らずもけなげさを感じてしまったのだった。
彼女は透明感、安定感のある高音が持ち味で、その完成度には定評があった。彼女が「ノーウーマン・ノークライ」の高音部や「平和の琉歌」のソロパートを歌うときなどは実に魅惑的で、感動的であった。
また私はかねがね、あの声、あの語り口、あのパースナリティなら絶対声優に向いていると考えていたのだけれど…。地元のラジオ局などで活躍してはいないだろうか。ぜひ近況が知りたいものである。
(Photo: Yukino Hiyane from CD メモリアル・ネーネーズ「オキナワ」)
自分としてもこれまでに経験したことのない現実からの離脱だったが、比屋根幸乃とピッコロのイメージが重なって思わず笑いが顔に出てしまったところで、目下の置かれている状況に立ち返った。
「何がおかしいのか」とどやされるのではないかと心配だったが、さっきまで怒っていたヤツが急に笑い出したことに驚いたらしく、その上司も一方的にしゃべることをやめ、お互いの戦意も薄れて、議論はやはりうやむやのままに終わったのだった。
自己実現もいいが、長い間役人生活を送っているうちに、いつの間にか、そのためには何を失ったって、犠牲にしたってかまわないんだもんね…という、気負いというか傲慢さのようなものが身に付いてしまっていたのかもしれない。
信念を持ってまっすぐに進むということも重要だけれど、大切なものはもっと別のところにあるのではないか――。
それは、たとえば家族であり、友人であったり、あるいは誠意や真心、相手を思いやる心などの概念的なものであったりするわけだろうが、何よりも大切なのは、「ゆとり」とでも言うのだろうか、そういったことを気づかせてくれるような何かを自分の中に持っている…ということなのではないだろうか。
いい大人になってこんな青臭いことを言うのもいささか恥ずかしいのだが、気づくのが遅かったけれども、幸い私の心の中にはそのようなメカニズムがあった…というか、知らない間にできてきていたのだった。
それがこのたび思いもよらない形で噴出してきたわけで、ははあ、そういうことなワケね…と、沖縄のある南西方向を見やって伸びてきた顎の無精ヒゲなどさすりつつ、一人大きく何度もうなずいているのであった。
沖縄病Tobiの琉球弧探訪 〜唯我独尊的琉球論