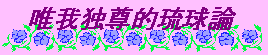 その4 2001.03.18
その4 2001.03.18
琉球民謡の大御所が勢ぞろいだゾーの巻ぃ〜
|
その4 2001.03.18
琉球民謡の大御所が勢ぞろいだゾーの巻ぃ〜
いやあ…。2001年3月16日の金曜日という日は、とってもいい1日でありました。
なにがって、沖縄病のワタシのことですから、洞察力のスルドイ皆さんはもうだいたい察しがおつきでしょうけれど、この日はNHKを席捲したと言っても過言ではないほど、あちこちで沖縄ミュージックが取り上げられていたのでした。…そんなことかって? そんなことなんです。
まず昼。「昼どき日本列島」ではこの1週間、八重山列島からの中継が行われていて、16日は小浜島でのさとうきびの収穫の様子などが放送されていました。快晴で25度(!)。写っている人々はみんなむんじゅる(笠でしょうか)をかぶってにこにこしながらの作業です。
この季節に作業を手伝いに来ている若者はインタビューに答えて「この島が好きだし、おじいちゃんやおばあちゃんの顔が見たくなって毎年やってきてしまう…」なんていうことをきりりとしたいい顔で話していました。くぅーっ! てぃーむじゅむじゅー、ひさむじゅむじゅー!
年度末までにケリをつけなければならない仕事に追われてほうほうの体でなんとかこの日も昼休みにまでたどり着き(昼休みはビジネスという戦場の塹壕か?!)、うまくもないパンなんぞをもそもそと齧っているときに(これはまた戦時食なのかっ!? …大げさだって)こういうシーンを見てしまうと、なにかこう自分がかわいそうというか、オレは何をしているのだろうというか、根本的なところで間違った道に入ってしまっているのではないかというような猜疑心にさいなまれてしまうのですよねー。
でもこの日は、朝に新聞で夜の番組をチェックしていたので多少は我慢できようというもの。だってさ、なんとなんと!
総合テレビ夜8時からの「堀内孝雄と香西かおりの二人のビッグショー」(普段はみたことないケド)にはゲストとしてネーネーズが登場するし、BS2では同じ時間帯に「琉球の魂を唄う」と題した2時間ものの番組があって、琉球民謡会の大御所登川誠仁(のぼりかわせいじん)をはじめ、宮古の国吉源次(くによしげんじ)、八重山の山里勇吉(やまざとゆうきち)、奄美の武下和平(たけしたかずひら)と、琉球弧の島々の第一人者がずらり登場するからなのですよ、アンタ。
ちょっとはしゃぎすぎていますが、このごろは、戦後から数えて(…だってサ)第3の流行などといわれて繁栄を極めてきたオキナワン・ミュージックの波もすっかり退潮気味で、マスメディアに取り上げられる機会がめっきり少なくなっていたものだから、ワタシのような者にとってこのようなことは砂漠のオアシス、渡りに船、天の恵みの世果報雨(ゆがふあみ)、鼓腹撃壌、酒池肉林…と感じられてしまうワケです。
これはぜひみなければなりません。ささ、仕事なんか後回しにして早く帰ろ帰ろ、そそくさ…と、すべてを投げ打って家に帰ったのは言うまでもありません。
しかし、こんなことでシアワセになれる単純そのものの自分は、なんとすばらしいことかと思います。仕事のことで苦悩のあまり首をくくってしまう…などということは実は私の職場でもたまにあったりするのですが、おそらく自分はそういうこととは無縁のままに生きていけそうな気がします。
思うに、このような悲劇が起きないようにするための重要なファクターとは、苦悩の量の多少ということよりも、その苦悩をすっかり忘れてしまうことができる部屋、あるいは抽斗が自分の頭や心の中にあるかどうか、ということなのでしょう。
どうしたら、あなたは無邪気になれますか? 気持ちが溶けていきそうな経験を今もしていますか? 無邪気な子供やお年寄りは、自分から死んでしまおうなどとは露も考えていないはずですよね。
――はっ!…ということは、もしかしてオレ、ボケが始まってきているのだろうか!?
話を元に戻して、ここからは番組に登場した唄者のインプレなどを綴っていきます。
まずは、ネーネーズ。
彼女たちを見るのは、ちょうど1年前、2000年3月に有楽町の東京国際フォーラムで行われた本土初公演を観に行って以来ですが、皆さん少しづつ板についてきました!って感じでしょうか。東京公演のときはみんな緊張してオドオドしていたような印象がありましたが、今回は地元の沖縄市民会館でのステージということもあってかとても落ち着きがあって、大人になったヨナ、少しは先代の貫禄というかゴージャス感も身についてきたヨナと思えました。特に伊計季代花(いけいきよか)、金城正代(きんじょうまさよ)の変貌ぶりは著しく、とてもきれいになっていました〜!
バックには三線の知名定人(ちなさだひと)。ネーネーズのホームグラウンド「ライブハウス島唄」のホームページを見ると、厨房用の厚口ビニール前掛けを着用したままのこの人の写真が載っていたりするのですが、今回は和服を着て、やるときはやるんだかんなという雰囲気。彼はチナサダオ楽団のメンバーで、初代ネーネーズのさよならコンサートでも三線を弾いていました。
曲は、安里屋ユンタ(あさどやゆんた。総合テレビなので共通語バージョンのほう)、次に堀内、香西とともに十九の春(じゅうくのはる)を。「いまさら離縁と言うならば 元の十九にしておくれ―」という歌詞を聴いて、映画「ナビィの恋」を思い出しました。このほか「島唄」や「花」など、ま、お定まりのラインナップでした。
ちょっと脱線しますが、先の3月10日、「ナビィの恋」を観てきました。
去年の7月(わざわざ仙台まで行ったのですよ)以来となりますが、2回目となると、ナビィ(平良とみ)と恵達(登川誠仁)、ナビィとサンラー(平良進)の会話の内に潜むそれぞれの心理がよーくわかって、1回目とは違った面白さがありました。
初めて観たときは、恵達(登川)のほか、東金城(あがりきんじょう)の本家夫婦(嘉手苅林昌と大城美佐子)とその息子(嘉手苅林次。彼は三線ではなくバイオリンを弾いていた)、アブジャマー男(山里勇吉)などの多芸ぶりを感服しながら観ていましたのでね。
戻って…と。
次は、「琉球の魂を唄う」からです。番組の副題は「沖縄民謡のカリスマ登川誠仁の素顔」ってんだからすごいでしょ?!
まずは誠グヮー。
2000年7月の沖縄サミットのオープニングフェスティパルでトリを張ったときの様子から映像はスタートします。カチャーシーの定番ソング「唐船どーい」の替え歌「サミットどーい」で1万人の観客を踊らせてしまっています。
この人、身長150センチほどしかない70歳のおじいちゃんなのですけれど、チッチッ…あなどってはいけません。琉球民謡協会の会長で、自分が主宰する登川流は数ある流派の中でも最大のものなのだそうです。そして、彼の破天荒な性格と天才的な三線の早弾きにより、沖縄のジミヘン、小さな巨人などの異名を持っているんですよー。
この番組、「ナビィの恋」の監督の中江裕司(なかえゆうじ)がナビゲーターを務めているのですが、彼がこの映画をつくる際に、誠グヮーのキャラクターに惚れ込んで、ナビィの連れ合い役として出演してもらうために誠グヮーの自宅まで何度も足を運んでようやく口説き落とした…という裏話が添えられていました。
また、そのときに培ったテクニックなのでしょうか、「登川サンは差し入れと色気に弱いから…」なんて言いながら、山城まんじゅうを買って登川宅に向かうシーンなどもあって、笑ってしましました。
誠グヮーの自宅の居間でインタビュー。タバコは9歳から、酒は11歳から…とか、「戦果」といわれる米軍の倉庫からの略奪物品をうまく回して20歳前までに小さな2階建ての家を建ててしまったこと、博打に入れ込んでその家を賭けてしまい全部持っていかれてしまったことなど、テレビでここまでストレートに言っちゃっていいの?と心配になるほどすさまじい話が続きました。
結局すっからかんになって、師匠に当たる板良敷朝賢(いたらしきちょうけん)という人から当時流行っていた琉球芝居の地謡(じかた)として誘われたのが、この世界の人となったきっかけなのだそうです。うーむ、人生というのは何が幸いするかわからないものですね。
このほかには、「誠グヮーの1日」も紹介していました。沖縄の人にしてはチョー早い朝5時に起きて近所の掃き掃除。人に見られるのがいやなので、誰も起きていないときにやるのだとか。それが終わると庭の水撒きや、飼っているメジロの世話をし、午後になると弟子達がやってきて民謡の稽古、さらには、三線片手に工工四(くんくんしー)を書く…という手法により作曲活動を。就寝は11時ごろで、なぜか毎日米軍払い下げの寝袋に入って寝る…というようなことでした。
肝心の唄については、何かのお祭りの一環として、石川市集会所(とテロップには出ていた)という立派で大きな瓦家(カーラヤー)を会場にして行われた独演会の様子を中心に編集されています。
自作のものだろうと思われる「油断するな」、ついで「口説(くどぅち)」。「口説」は、今回の場合は役人が花街のジュリ(尾類。本土でいう女郎のようなものか)と遊ぶ様子を歌詞にしたもので、方言のわかる観客が時折わっと笑うような内容だったようです(ワタシにはよくわからない)。
誠グヮーの「とぅばらーま」は初めて聴きましたが、八重山の道トゥバルマのような、自然の中で朗々と唄う…という印象のものから少し離れて、「悲しさ」「さびしさ」というような範疇のものが前にでてきているような感じの独特なものでした。
続く「国頭(くんじゃん)ジントヨー」、「ナークニー」は、いわば十八番。さすがに声量は多少落ちたなという感はありますが、なあにまだまだ、誰にも負けんゾというところ。
調子に乗ってきた誠グヮーは、観客にリクエストをするよう求めると、観客も心得たもので、「多幸山(たこうやま)」を要求。ただでさえスピードがあって調子はずれっぽいところのある唄なのですが、彼が自分の節回しで唄うとこれにさらにぐにゃぐにゃ感が加わって、一種独特のものになるのですねー。これがまた、いいんですよねー(人によって結構好き嫌いはあると思うケド…)。
独演会の最後は「嘉手久(かでぃく)」。カチャーシーですね。「テントゥルルン、テン、シトゥリトゥテン…」という三線の音色を模した歌詞が気持ちいい。80過ぎのオバアだって、ここに至ってはガンガン踊っちゃうのですから、沖縄はすごい。
そしてオーラスは、自宅の居間で、中江監督のリクエストにより「ひやみかち節」を。これを聴くにつけ、沖縄は過去も現在もいろいろあって大変だけれど、きっとこれからもずっと力強くしたたかに自分達の文化なりアイデンティティを守っていくのだろうなと感じました。
「琉球の魂を唄う」の2人目は、宮古島を愛する情熱の唄者、国吉源次です。
宮古生まれで、畑仕事をやりながら祖母から教わったという唄の数々を持ち歌にしています。年は誠グヮーと同じ70歳。
まずは「なりやまのあやぐ」からスタート。知名定男が「ミャークにはアーグがある!」と言って評価することしきりの唄。落ち着きがあり、曲調もどこかに御嶽の森の蒼さのような深みが感じられて、ああこれは八重山でもなく、もちろん本島でもないところのものだなとすぐにわかってしまうような宮古独特のもの。
ここで、「伊良部トーガニ」をやる前に、源次さんの口上が入ります。「私の芸道は、この唄に賭けていると言っても過言ではありません。…奥が深いので征服するのは難しいと思いますが、死ぬまでがんばります。」などと妙に甲高い声で一生懸命にしゃべるので、その真面目一徹の姿勢にとても好感が持てます。実は似たような話を彼が1991年の琉球フェスティバルでしているのを、ワタシは知っているのですけれど…。
さすがに本人がそう言うだけあって、もう、天下一品の出来です。三線と笛だけでこのような一大交響楽(のような雄大さが感じられるんです!)が出来上がるのですから、まったくオドロキです。なにせあちらでは、国吉源次といえば伊良部トーガニ、またその逆も真なり…といわれているワケですから。番組では源次さんが海を前にして遠くに伊良部島を眺めながら唄うという設定でしたが、これがまたよく、映像の力というのは凄いと思いました。
彼のいいところはまた、その衣裳にあります。ずっと前から彼の正装は、膝下までの丈で白と紺の縞の絣を藁の腰ひもでまとめ、頭にはむんじゅるをかぶり、その紐を顎の下でしっかりと固定して唄う…というものです。きつい日差しの中で、明るい色の着物が実にまぶしくて、それはカッコいいのですよ。
このほか、生まれた集落で唄われていたという「新城見差親(あらぐすくみさすうや)」「初恋」の2曲、そして最後は「クイチャー」です。
「クイチャー」は、白浜の砂のように米や粟がたくさんできるよというようなことを唄いながら、みんなが輪になって、手を上にかざしてにぎやかに踊るものなので、年貢を納めきったたことに狂喜乱舞するときの唄なのだろうと思っていたのですが、源次さんはこれをきっぱりと否定していました。
苦労して収穫したものをそっくり、首里の役人から人頭税(にんとうぜい)として持っていかれてしまうことへの、憂さ晴らしの唄だ、年寄り達からもそう聞かされたものだ…というのです。そう思いながら聴くと、そういった形でしか憂さを表現できなかったかつての宮古の島民には深い哀惜の情が湧いてきて、考えさせられてしまいます。
3番目の登場は、八重山は石垣島白保(しらほ)生まれの山里勇吉(75)です。
この人の声量のすごさは、一度聴いたら忘れられないほど。映画ナビィの恋ではアンガマのお面をかぶってなにやらおどけた役回りをしていましたが、その中でも「とぅばらーま」や「月の美しゃ(つきぬかいしゃ)」などの八重山民謡とともに、年齢に不相応なほどにメリハリの効いた八重山空手を披露するなどしましたよね。
安里屋ユンタの元唄から始まって、若夏の季節に田草を取りながら唄う労働歌「うりづんジラバ」を。その後は、白保の豊年祭の映像とともに「白保節」「夜雨節(ゆあみぶし)」「弥勒節(みるくぶし)」と続きます。
豊年祭では、「白保節」は神女(ツカサ)が拝所(うがんじゅ)を出るときに豊年を願って唄われるもの、「夜雨節」は神女が拝所から自宅に向かうときに唄われるもの、「弥勒節」はあの世から弥勒様がやってきて作物が豊かに実ることが約束されたときに唄うもの…なのだそうです。ちなみに、山里家は白保の旧家で、豊年祭には神様の料理をつくる役を担っているそうですよ。
最後は、彼の十八番、「とぅばらーま」です。かつては農作業の帰り、暗くなった道を馬などを曳きながら、とぼとぼと歩くスピードで唄った…ということで、これを「道トゥバルマ」というそうな。勇吉さんはこの「道トゥバルマ」を唄わせたらナンバーワンだからということなのか、今回は馬にまたがっての登場で、ちょっと「やらせ」が見え見えの感じ。
勇吉さんが言うには、とぅばらーまを唄うには体の中から湧き出てくるものをうまく表現する必要があり、その意味では若いときには出せなかったものが出せるようになったと…。そこまではいいのですが、声の迫力は4、50代の時とは比べるべくもなく、もはやあのような真似はできないと嘆いておられたのには仰天! はっきり言って、私は30年前の勇吉さんの声を想像するだけで恐ろしくなってしまいます。だって、今だってもの凄いんですよ、声量…。
最後は、奄美100年に一人の唄者と言われる武下和平(67)。
実は私はあまり奄美方面にはなじみがなく、この人の名前を知らなかったのですが、聴けば、ああこの声、聴いたことある!って感じ。今回唄われた曲もほとんど聴いたことがあるものでした。
奄美南部の加計呂麻(かけろま)島諸数(しょかず)の生まれで、今は尼崎市で民謡教室を開いており、全国各地に多くの門下生がいるそうです。
1曲目は「朝ぱな節」。「唄遊び」という、たくさんの人から様々な歌詞が即興で飛び出す奄美独特の歌会の中で披露されました。
2曲目は「嘉徳なべ加那節」。奄美南部の嘉徳(かとく)に生まれたなべ加那というとても気高い神女を称える唄です。
3曲目は「むちゃ加那節」。加計呂麻島の生間(いけんま)に生まれたウラトミとその娘むちゃ加那の悲劇を唄ったものです。ウラトミは美人だったがゆえに薩摩の役人に目をつけられ、それを拒んで喜界島へと逃げるのですが、むちゃ加那もその美貌ゆえに島の女達の反感を買い、崖から突き落とされて死んでしまうという、なんと悲しい内容のもの。
いずれも裏声が入っての哀調たっぷりのもので、同じ琉球弧にあって、同じ三線を使って、どうしてこうも隣りの圏域と違う音楽的風土ができあがるのかと、少し戸惑ってしまいます。ちょっとの地域の差で文化の形成も異なっているわけで、今の日本本土の画一化、平板化してしまった文化的様相を見るにつけても、沖縄と奄美の間には深い人為的な断層が出来ていたのだろうということは想像に難くありません。
奄美の唄は、支配者への恨みを歌詞の裏に読み込んだので、わざと発声をはっきりさせないで唄う伝統があるのだそうです。奄美の唄が悲しげに聴こえるのは、琉球、薩摩、日本、アメリカ、日本と、常にその時々の強者によって支配されつづけたという悲しい歴史がそうさせるのでしょう。
先の宮古の「クイチャー」と表現方法を比較するとなかなか興味深いのですが、いずれも背景に搾取という現実が重くのしかかっていたのだということに、我々は思いを馳せて考察すべきだろうと思います。
4曲目は、油断するなよ魚たち、イカを見たら喰いつけよ…と唄う「一切(ちゃっきり)朝ばな節」、そして最後は奄美のカチャーシーというのでしょうか、「六調」で締めくくりとなります。
この「六調」、八重山の「六調」とルーツは明らかに同じようです。しかし、曲名はもちろん「あなた百まで、わしゃ99まで…」といった歌詞も同様なのですが、曲のスピード(奄美のほうが早い)、調子(奄美はやはりうら悲しく、影の部分を感じる)、囃子(奄美には少ない)…などの面で様相を異にしているのがおもしろいです。
そしてワタシは気づいてしまったのですが、この曲は、わが山形県の代表的民謡である「花笠音頭」とも相通じるものがあるのです! 「若松様よ、枝も栄えて葉も茂る…」といった歌詞は同じだし、めでたい席でよく唄われることや、合いの手の入り方(八重山では「ユイヤナー、ユイヤサマヨー」に対し、山形では「ヤッショー、マカショー」)の感じがよく似ていることなど、いくつかの共通点があるのです。
推測すると、かつて踊り念仏の風習が一世を風靡した時代があり、そのメジャーレパートリーが全国に広がって、土着しながら独自の進化を遂げていったのではないか…と、勝手に思い込んでいるのですが、明確な答をご存知の方はいらっしゃいませんか?
は〜〜。長くなってしまいました。私的なシアワセにお付き合いいただき、ここまで読んでいただいたアナタのやさしさ、我慢強さに感謝します。